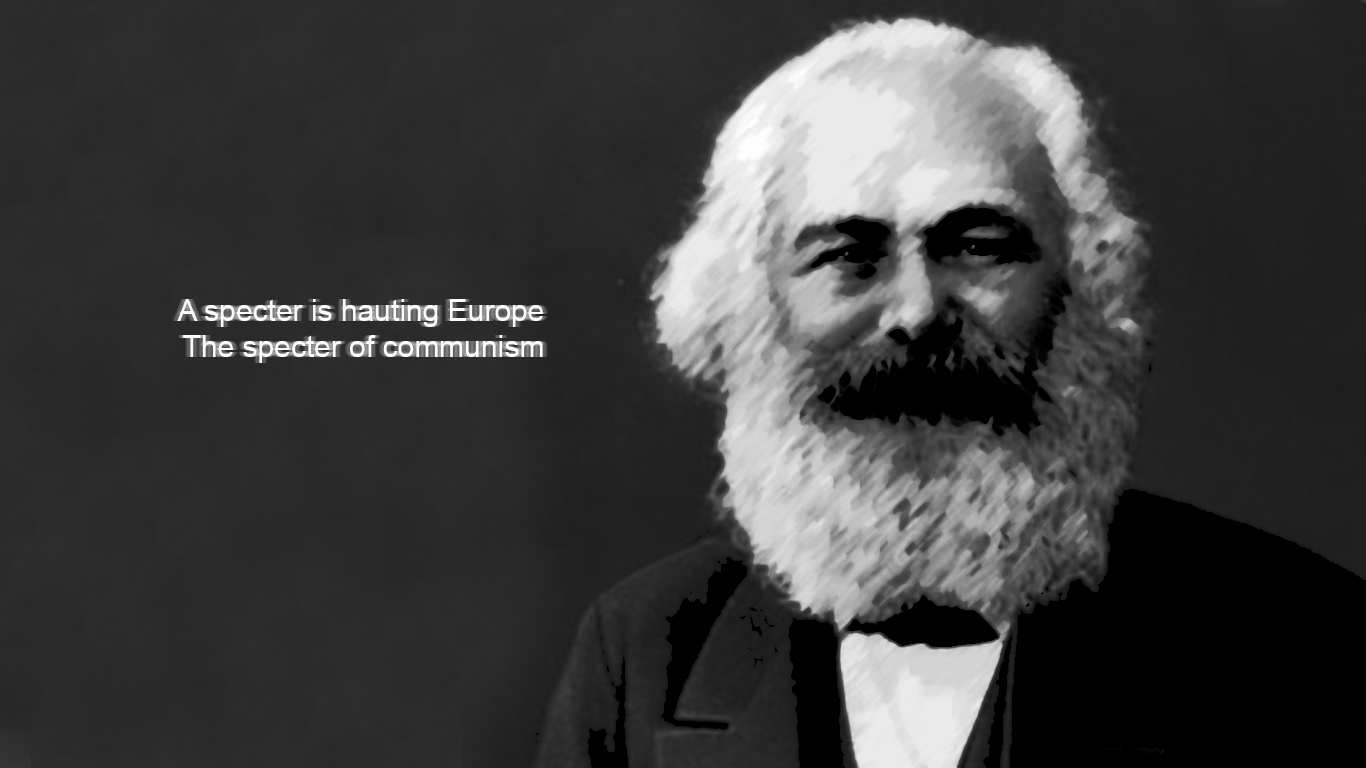町山智浩の映画ムダ話『カリガリ博士』サンプル - YouTube
ドイツのヘッセン州ヴィースバーデン出身のユダヤ人社会学者ヘルムート・プレスナー(Helmuth Plessner, 1892年~1985年)の「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes 1935年)」はイデオロギー懐疑(Ideologieverdacht)が学者の信念だけでなく一般人の信仰をも破壊していくプロセスを冷徹に描く。
【第一段階:信仰の崩壊】イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)はデカルト同様、最初から本物のイデオロギー(独Ideologie, 英ideology、人間の行動を左右する根本的で包括的な観念)を備えた求道者だった。だから、ただひたすら物心二元論の立場からイデオロギー懐疑(Ideologieverdacht)による精度向上に努めたが、それは一般人が実践可能な種類の苦行ではなかったのである。歴史学に同様のイデオロギー懐疑を持ち込んだランケも同じ振る舞いを繰り返した。
*逆をいえば一般人は慣れ親しんだ救済史観から離れたがらないし、イデオロギー懐疑の強要はかえって信仰の世俗化(die religios Verweltlichung)を遅らせるばかり。
- ルネ・デカルト(René Descartes、1596年〜1650年)の機械論的自然観…イエズス会附属学校でスコラ学的教養と「信仰と理性は調和する」をモットーとするカソリック理念を叩き込まれる。「我思う、ゆえに我あり(仏: Je pense, donc je suis、羅: Cogito ergo sum)」なる直感に突き動かされてフランス語で執筆した「方法序説(Discours de la méthode、1637年)」を発表。自然を思惟実体としての精神、およびその延長実体としての物体そのものに峻別する物心二元論から出発し、前者が後者を精密に把握しようとするなら幾何学的体系の組み上げや科学実証主義的観察が不可欠であるとした。
*ちなみにムワッヒド朝(al-Muwahhidūn1130年〜1269年)時代のアンダルス(イベリア半島内イスラム圏)出身のアラビア哲学者アヴェロエス/イブン・ルシュド(Averroes/ibn rusd、1126年~ 1198年)が既に、この様な方法論だとユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学の様な関係にある「同じくらい確からしい複数の別解」が次々と観測される可能性を指摘している。 - ニコラ・ド・マルブランシュ(Nicolas de Malebranche、1638年〜1715年)の神中心主義…デカルト流の心身二元論のから出発しながら「すべての事物を神において見る(voir toutes en Dieu)」とする立場から「人間は神のうちなる観念を通して事物的世界を認識する」「精神と物体の間に実在的区別はあるが、それは二つの世界の分を意味しない。見る私と見られる物体は私の経験世界では区別されるが、神の視界では自然に一つにつながっている」という結論に到達したフランスのオラトリオ会修道士。奇しくもルイ14世と生没年が一緒。
*スンニ派古典思想を完成させたイスラム神秘主義者アルガゼル/ガザーリー(Algazer/Ghazzali、1058年〜1111年)の流出論の影響が見て取れるとも。フランス重農主義とも思わぬ接点が?
- イスラム神秘主義者アルガゼル/ガザーリー(Algazer/Ghazzali、1058年〜1111年)の流出論…イスラム圏が編み出した「神が全てを創造したなら、どうしてこの世に悪が存在するのか」なる疑問への模範解答の一つ。「神の英知そのものは無謬だが、流出の過程で誤謬が累積して矛盾や悪が生じる」という立場に立つ。
*スーフィー(イスラム神秘主義者)としては密教同様「神(CPU)に対する正しいアプローチ(無謬のコーディング)は世界そのもの(接続デバイス)に働きかける」とするコンピューター的世界観に到達した。デカルトやマラブランシュの機械的自然論もそのバリエーションの一つ。 - 「近代歴史哲学の父」ナポリのジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668年〜1744年)が提案した機械論的史学…「数学的知識以外の知識はあり得ない」とするデカルト派の認識論に対し「新しい学(Principi di scienza nuova、1725年)」の中で「幾何学が無から証明済みの定理を積み上げて無謬の体系を構築する様に、歴史学も無から人間の行為事実を積み上げて全体像を構築する」とし近代的歴史学に出発点を与えた。
*歴史家がとりあえず当てにして良いのは「異なる二つの時代が同一の全般的性質を持ち、そのため一つの時代から他の時代を類推して論じることができる」「同じ種類の時代が、同一順序で再起する傾向がある。英雄時代には必ず古典的時代が続き、新たな未開状態への衰微が始まり、というように時代は循環する」「このような循環運動は、単純にもとのところに戻るのではなく、螺旋を描いて進展する(すなわち完全な予測は不可能)」の三大仮説、用心すべきは「古代に対する大言壮語、理想化と誇張」「 国民的自負の投影」「学者が自分の性質を、歴史上の行動者に投影する」「二つの民族が類似の観念や制度を持つときに、一方が他方から学んだに違いない、と考える偏見」「古代人も比較的身近な時代に関しては、現代人より事情に通じていたに違いない、と考える偏見」の五大誤謬とした。もしかしたら中世イスラム世界を代表する歴史哲学者イヴン・ハドゥラーンの循環史観を批判的に継承したのかもしれない。
アフリカ北岸最後の黄金期(14世紀) - 諸概念の迷宮(Things got frantic) - ドイツの歴史家ランケ(Leopold von Ranke、1795年〜1886年)による反救済史観…実証主義の立場から史料批判に始まる科学的歴史学を確立。キリスト教的救済史観(終末論をも含む普遍史(Universal History))、および啓蒙主義から派生した教訓的、実用的歴史学を激しく非難し、歴史学の使命はあくまで「実際の事物がどのようなものであったか」ただ黙々と明らかにする点にあるとした。
*私生活ではあくまで敬虔なプロテスタント。その潔癖性の投影が見られるとも。まぁ「(総てを司る神の視点から見下ろせば)ヨブ記」という事であろう。
- 20世紀初頭のドイツで行われた価値判断論争(Werturteilsstreit)…主に社会政策学会を舞台に社会科学における認識の客観性と倫理=実践的な価値判断の関係を巡って争われた。 G.シュモラー率いる講壇社会主義者達は特定の倫理的理想を歴史的に把握し,この理想によって社会問題に実践的・政策的提言を行うべきであると主張したのに対し、ウェーバーもゾンバルトも没価値性(社会科学的認識において実践的な価値判断を排除すべき)を主張。
*20世紀初頭に入るとマルクス主義を継承した社会学者もこぞってこのアプローチに逃げ込む。逃げなかったのは「敵友理論」のカール・シュミッツに、その友人で魔術的リアリズム運動創始者として名高いエルンスト・ユンガー(Ernst Junger 1895年~1998年)くらい?
確かにこれでは一般人への垣根が高すぎる?
ヘーゲルとヘーゲル左派 ―歴史の弁証法的展開― - まさおさまの 何でも倫理学
カントは人間の有限性を直視したがゆえに、理想と現実の二元論を堅持し続けました。しかし、理想は永遠に理想であってけっして実現されることはない、それにもかかわらずその実現に向けて永遠に努力し続けなければならないという、この過酷な要求に人間は耐えきれるのでしょうか。理想がけっして実現されえないのだとしたら、人間は理想への努力を放棄してしまうのではないでしょうか。
カントが提起した問題は、プロイセンの若き哲学者たちフィヒテ、シェリング、ヘーゲルらに受け継がれていきました。彼らは総称して 「ドイツ観念論 (理想主義)」 と呼ばれています。中でもヘーゲルは、若い頃にはカント哲学に惹かれていた時期もありましたが、やがてカントと訣別して、カント的主客二元論を克服することを自らのライフワークとしました。そしてその果てに壮大な哲学体系が構築されたのです。最後の主著 『法の哲学』 の中でヘーゲルは「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」と述べていますが、これはまさにカント的主客二元論に対する勝利宣言にほかなりません。
ドイツロマン主義とナチズム―遅れてきた国民 (講談社学術文庫) | ヘルムート プレスナー, Helmuth Plessner, 松本 道介 | 本 | Amazon.co.jp
(概要)カントの達成したコペルニクス的展開とは「深淵なら彼岸側でなく此岸側にも広がっている」すなわち「我々がこの世界において何かが存在すると認知するという事は、我々が 何か認識しているという事だ」とか「科学的・数学的アプローチによってカテゴリー(悟性)と形而上学(理性)の裂け目は埋まる」といった信念に基づくイデオロギー懐疑(Ideologieverdacht)に一生の間ずっと不断で従事し続けなければならない宿命の再発見を意味している。
*とはいえ「決して到達しえないゴールに向けて未来永劫努力を続けねばならない」と告げられて却って奮起するのは筋金入りの苦行者だけと相場が決まっている。我々がこの世界において何かが存在すると認知するという事は、我々が 何か認識しているという事だ…理性 (Vernunft) はそれ独自の原理 (Prinzip) に従って事物 (Sache, Ding) を認識するが、理性の側から見ると経験に先立って内在的に(a priori=先験的に)与えられる原理の起源を示す事が出来ないばかりか、その原則を逸脱して自ら能力を行使する事も出来ない。
*困った事にベイズ統計学や機械学習といったFeature Selection(特徴選択)の世界は「初期状態がどうあれ経験の量的蓄積が判断力向上につながっていく」実例に満ちている。元来ならカテゴリー(Category)の定義そのものに至る案件なのだが…
ここでも下部構造(物そのもの)が上部構造(カテゴリー(Category)上の認識)を規定するが、問題は神や魂といった(感性や悟性の対象に選べないが故にカテゴリー化(Categorize)不可能な)純粋に思惟上の仮象としてのみ存在する理性概念をどう扱うかだったりする。
*「人は語れないものについては沈黙しなければならない」とする立場から「いや、むしろ我々の不完全極まりない認識世界の影響から完全脱却した純粋抽象こそ宇宙唯一の真理」とする立場まで千差万別。デカルトは後者、カントは前者寄り。カテゴリー(Category=純粋悟性概念)…感性と共同で経験に基づいて特定の認識世界を構築する概念把握能力。ユークリッド幾何学やニュートン力学の様に「一見完璧に閉じた無謬の体系としか見えないが(非ユークリッド幾何学や量子力学との邂逅によって)アンチノミー(Antinomie=二律背反)が発生すると全体像の放棄か発展的解消を要求される体系」あるいはそれを構成する最小単位の編集のされ方をいう。
*15世紀末から16世紀初頭にかけて人体解剖学の分野が躍進を遂げたボローニャ大学とパドヴァ大学で流行した新アリストテレス主義哲学に起源を有する。天動説に対する地動説、自然法論(英natural law theory、独Naturrechtslehre)に対する法実証主義(英legal positivism, 独Rechtspositivismus)もそうした自由な雰囲気の産物だった。
欧米的合理主義はイタリアから始まった? - 諸概念の迷宮(Things got frantic)形而上学(羅: Metaphysica、英: Metaphysics、仏: métaphysique、独: Metaphysik=純粋理性概念)…世界の真実を感覚や経験を超越した(純粋思惟によってしか到達出来ない)普遍的原理に求める立場。世界の根本的な成り立ちの理由(世界の根本原因)や、物や人間の存在の理由や意味など、見たり確かめたりできないものについて考える。
*古代ギリシャ・ローマ文明起源とされるが、実際欧州に与えた影響はむしろそれへの懐疑から生まれたエピクロス派哲学やストア派哲学の方が大きいとも。ただしストア派哲学も「自然の普遍性」は信じる立場。*ソ連崩壊までは「唯物論の対語だが、マルクスが上部構造が下部構造によって規定される事を明らかにした時点で歴史的役割を終えた」なんて威勢の良い定義をしばしば見掛けたものである。以降は「理性の側からの呼び掛け」が途絶えたせいか概ね沈黙。
「悟性と理性の裂け目はどんなに努力しても埋まらない(それでも埋めるべく努力を一生続けるのが人間)」とするカントの苦行者的スタンスに対し、ヘーゲルは「その隙間は既に神によって埋められている」という立場を選択。後者の方が当時のドイツ人が聞きたかった話に近かったのでたちまち広まった。「何でも相手のレベルに合わせる」ヘーゲルさんの大勝利?
【第二段階:信仰の世俗化】啓蒙思想全盛期から復古王政期にかけての難しい時代を生きたヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel、1770年〜1831年)の足跡を辿るのは難しい。いずれにせよ彼の踏み出した一歩がドイツ全体における信仰の世俗化(die religios Verweltlichung、人間が古い権威から解放されながら、次第に低い代替形式に結び付けられていく過程)を加速させた事実は揺るがない。
*悲しい事に農本主義的伝統の下で生きてきた人間は、それから解放された途端にその権威主義的拘束から自由になれる訳ではない。隣国フランスですら半世紀以上苦しめられている。
実はそれは、かつて英国王の所領だったハノーファー経由でドイツに流入したエドモンド・バークの「(ドイツ観念論の立場からすると)浅薄極まりない」保守主義思想との「対決」の産物だったのかもしれない。
①ヘーゲルはデカルトやカントの様に(超人的アプローチが必要で一般人を置き去りにする)物心二元論は選ばなかった。その代わりにマルブランシュ同様に神中心主義を採用し、(キリスト教からキリスト教的な要素を排除し尽くす)理心崇拝の伝統に従って絶対精神(Der absolute Geist)や世界精神 (Weltgeist)といった「神の代替品」を新造する。
*ヘーゲルの提唱した「正・反・合」の三段階弁証法 (Dialektik)や止揚(aufheben)にはアヴェロスやカントを本気で悩ませた二律背反(独: Antinomie)問題の様な深刻さが感じられない。むしろ「息子は最初こそ父親に反抗するが、やがて全てを理解して自ら黙従の道を選ぶものだ」といった前近代的な家父長主義的保守主義的鷹揚さが表面に出てきた感がある。ちなみにこうした側面はマルクスや「精神分析の父」フロイトも多分に持ち合わせていて、むしろ「息子達(娘達)」に一生反抗を続ける決意をさせる形で歴史的役割を果たす事になる。
我々の目には主観と客観、個別と普遍との対立と見えるものは、実は本当の対立ではない。主観も客観も、同じ一つの物、すなわち絶対精神が自己疎外して個別化したものに過ぎない。だから絶対精神の立場からすれば、どちらも自分自身の一つの契機に過ぎない。それが対立して見えるのは、外化され個別化したものの立場から見るからだ。つまり我々個別の人間は、絶対精神の疎外された形である限り制約を受けた存在であるが、可能態としては、絶対精神そのものの一部として無制約なのである。
個別と普遍との関係についても、同じようなことがいえる。個別の存在としての個人と普遍的な存在としての人間社会とでは、一見対立した関係にあるように見えるが、そうではない。どちらも絶対精神の立場からすれば、自分自身の一契機に過ぎない。絶対精神が自己疎外して個別化したものが個人なのであるし、それがある一定の人間社会にとって倫理的な枠組となったものが、当該の人間社会がその成員たる個人に課す制約となるに過ぎない。
こんなわけで、我々が生きているこの世界は、絶対精神というものが自己疎外して展開したものなのだ。その絶対精神が人間の意識の形をとると、理性になる。その理性の立場からすると、この世界が絶対精神の現れだということは、理性としての自分自身がこの世界全体を成り立たせている根拠だ、ということだ。そこから、「理性とは、物の世界のすべてに行き渡っているという意識の確信」が生まれてくるわけなのである。
要するに、ヘーゲルが理性の章で展開しているのは、絶対的な観念論だということになる。絶対的なというのは、それがこの世界についての唯一の説明原理であるということであり、観念論というのは、この世界を精神という観念的な原理で説明しているからである。
②一方、キリスト教的救済史観(終末論をも含む普遍史(Universal History))については「歴史とは絶対精神が己を具現化していくプロセスである(貴方も同じドイツ人なのだから共感して没入さえすればこの偉大なる事業に参加可能である)」というアプローチで懐柔を試みた。
*もちろん「権力は、何者がそれを行使するにしても、それ自体においては悪である」という立場のスイス人文化史学者のブルクハルトは、これに最大級のレッドアラーム発令。
ブルクハルト『世界史的考察』ヘーゲルの目的論的歴史観に対する批判
「われわれは、永遠の知恵が目指している目的については明かされていないので、それが何であるかを知らない。世界計画のこの大胆きわまる予見は、間違った前提から出発しているので、誤謬に帰着することになる。」
「われわれは一切の体系的なものを断念する。われわれは「世界史的理念」を求めるのではなく、知覚されたもので足れりとするのであり、また、歴史を横切る横断面を示すが、それもできるだけ沢山の方角からそれを示そうとする。」
*フランスにおける普遍神学的啓蒙(網羅)主義から、ドイツの個人単位の認識世界における「世界を知り尽くしたい願望」への鮮やかな飛躍。しかし既にそれは17世紀段階においてライプニッツの単子(モナド)論の中で「モナドには窓がない」という言い回しで予言されていたのではなかったか?
③一時期は百科全書派を見習ってあらゆる学問分野を網羅した体系を構築しようとしたほど啓蒙派だったヘーゲルだが、復古王政時代に入ると急激に保守化して(前近代から続く農本主義的伝統に忠実な)プロイセンの君主制のみが唯一の希望と考える様になる。
*ヘーゲルは市民社会と国王の間に対立関係を認めつつ、そのギャップは官僚の仲介によって埋められると考えた。ある意味それは宰相ビスマルクと(私利私欲を守ることしか考えてないブルジョワに牛耳られた議会を共通の敵と見出した)労働組合運動の父ラッサールのタッグ成立を予感したとも言えなくもない。
20代でフランス革命に熱狂したヘーゲルは共和主義者だったが、ナポレオン戦争で神聖ローマ帝国が崩壊すると、「ドイツはもはや国家ではない」と嘆いて、「ドイツ国制論」という草稿を書き、それを再建するための「国のかたち」を模索する。
ここでヘーゲルは共和制を脱却し、強い君主のもとに領邦を統一する「帝国」の建設が祖国を混乱から救う道だと考える。そのためには、まず宗派対立を収拾し、キリスト教を統一する必要がある。それが『精神現象学』の執筆動機だった。ここでは父と子と聖霊の三位一体という正統派の教義が、さまざまな宗派を超える「弁証法的統一」であることを論証しようとする。だから「正・反・合」のトリアーデには大した意味がないのだが、彼はカトリック・プロテスタントがともに認める三位一体説が分裂した祖国を統一する思想だと考え、これを弁証法と名づける。『精神現象学』はその図式で認識論を書く最初の試みだが、複雑な問題をトリアーデの入れ子構造に押し込んでいるので、必要以上に難解になってしまった。
これがもっとこなれたのが『法哲学綱要』で、ここでは家族・市民社会・国家というトリアーデによって政治と宗教の分離が理論的に基礎づけられ、自由主義的な国家の理論が生まれた。ポパーが「全体主義の元祖」と攻撃したのとは逆に、ヘーゲルは近代の自由主義の元祖なのだ(ロールズもヘーゲルをこう位置づけている)。
ヘーゲルの自由主義は『歴史哲学講義』では明確になり、「世界史は自由の歴史における進歩である」とか「自由とは必然性の認識である」という哲学が展開される。ここで最大限の自由を実現するのがプロイセン帝国だとしたことが「御用学者」と嘲笑されるが、ヘーゲルは宗派対立を終わらせて帝国を実現したプロイセンに期待していた。
ヘーゲル「法の哲学(Grundlinien der Philosophie des Rechts、1821年)」での国家論
ヘーゲルは国家を意思(自由を求める意思)の概念で説明する。
「国家ははっきりと姿を現して、己自身にとって己の真実の姿が見まがうべくもなく明らかになった意志の実体としての倫理的精神である。この意志の実体は、己を思惟し、己を知り、その知るところの物を知る限りにおいて完全に成就する」。
「国家は個々人の自己意識に媒介された形で顕現するが、他方、個々人の自己意識もまたその自由の実体を国家の内に持っている」。
人間一人一人の自己意識=意志が国家の基本になっている。個人の自由実現は国家によって可能になるとヘーゲルは言う。ここで一人一人の「自己意識」を基本においていることに注意したい。「自分とは何か」と「自分たちとは何か」「わが国とは何か」。これらは一連の問いで切り離せないと言うことだ。
また、近代国家とは、あくまでも「国家を作ること」を意識して自覚的につくったものだ。先進国イギリスは、産業革命後の市場拡大のために、国内市場を拡大し安定化するために、イングランド、スコットランド、ウエールズを統一し、対外的には植民地政策を推し進めた。フランスも革命後のナポレオンによる帝政下で中央集権化が進む。
これらの先進国への対抗上、後進国も国家を作るしかなかった。それがドイツ(プロイセン)、イタリア、日本などの「民族国家」だ。日本は植民地化されないために、西欧から国家という諸制度を輸入する形で作り上げた。近代国家は他の諸国家(先進国)に対抗する必要性から後進国が自覚的に作ったものだ。
しかし、後進国の国家が「民族国家」である必然性はなく、他民族国家でもかまわない。「己を思惟し、己を知り、その知るところの物を知る限りにおいて完全に成就する」という意味では、アメリカこそ、旧来の歴史や社会を前提にせず、理想的な憲法の理念から作った純粋な近代国家と言えるだろう。憲法に賛成するすべての者を国民と認めるほどに、それは理念先行国家だ。
市場拡大のために内部の分断、分裂を克服し、統一した中央集権の統合を実現する。さらに外との対抗上も国家を必要とする。後進国では逆に、対外的な必要から国家を必要とする。いずれにしてもそれが近代国家だ。そのナカミは多様だ。それぞれの民族、国民が、自分たちにふさわしい国家を自覚的に作り上げたものだからだ。
君主制について
マルクスなどヘーゲル国家論の批判者は、ヘーゲルが君主制とその官僚制を擁護している点で、ヘーゲルを批判する。この批判、特に君主制擁護への批判は正しい。それは叙述によく現われている。
ヘーゲルの君主国家論は明らかに、当時のプロイセンの君主政権を擁護するのが目的だった。というよりは、彼の国家論は近代国家論だが、その国内体制の箇所はプロイセン国家論になっているのだ。当時のドイツ民族の程度(民度)が、君主制しか可能にしなかったからだ。しかし、露骨にそうは書けなかった。
擁護の姿勢は叙述の不自然さに現れる。ヘーゲルはここでは、いつもの普遍→特殊→個別の順番を壊してしまう。
カントの立法→司法→執行に対して、ヘーゲルは立法→司法→執行を主張していたそうだ。そして、本書ではそれを、立法→執行→君主に変えた。ここにすでにおかしな物があるが、それを問わないとしても、展開の順番は立法→執行→君主になるはずだ。
それが君主→執行→立法と逆転している。その結果、君主論の内部も、個別から普遍への順番になっている。そして、ラストの立法の導出、その内部展開もおかしくなっている。これは、そうまでして、君主権を強調したかったことの現れで、政治的な操作だ。
以上、ヘーゲルの叙述の問題、彼の君主制擁護の姿勢を批判した。しかし、ヘーゲルの真意は「当時のドイツでは、立憲君主制しか可能性がない」ということだったろう。【注釈】には「どの国民も、自分にあった、自分に似通った体制を持つ」とある。民度とその政権、政体は一つなのだ。日本の天皇制もそうだ。エンゲルスはこれを正確に理解している(「フェイエルバッハ論」)。
ドイツロマン主義とナチズム―遅れてきた国民 (講談社学術文庫) | ヘルムート プレスナー, Helmuth Plessner, 松本 道介 | 本 | Amazon.co.jp
(概要)要するに復古王政下のヘーゲルは全てを「理性の選択結果」と肯定する事で一切の批判を諦めてしまった。自然法論に立脚して権威主義体制を張り巡らせてきた家父長制、「無謬たる」プロイセン王の権威によって担保された農本主義的伝統…全部そのまま。彼にとっての最大の不幸は、そうやって「百年前でも百年後でも変わらないドイツ人の理性の拠り所」と見定めた前近代的風景が、産業革命到来によってあっけなく全て歴史の掃き溜め送りになってしまった点にあったのである。
正直「特定の時代への迎合が次の時代への不適合を招いた」なんて展開そのものに特別な新しさはない。問題は弟子筋のマルクス(Karl Heinrich Marx、1818〜1883年)による再利用方法にあった。要するに彼は自らの師匠ヘーゲルを、グノーシス主義の反宇宙的二元論における「狂った偽創造神」に仕立て上げる道を選んだのである。
*グノーシス主義(独: Gnostizismus、英: Gnosticism)の反宇宙的二元論(Anti-cosmic dualism)…様々なバリエーションがあるが、その神話では概ね至福の原初世界がヤルダバオート(Yaldabaoth)あるいはデミウルゴス(Demiuruge)と呼ばれる狂った創造神(自らの出自を忘却しており、自らのほかに神はないと認識)によって破壊され、地上の住人に悲惨な生活を強要する「悪の宇宙」に再構成されたと考える。
【第三段階:攻撃対象の外化】方法論こそ著しく違ったが、カントもヘーゲルも追求したのが「己自身との戦い」だった点は変わらない。ところがマルクスはそれ自体が生温いと感じた。
- 我々が自らを導く理性と信じているそれは、我々を奴隷化する為に権力者が構築した支配システムの一環に他ならない。
- 従っていくら個人の枠内に引きこもって自問自答を繰り返しても何一つ解決しない。団結して蜂起し、実社会を牛耳る悪の大元を断たない限り我々の心に平穏は訪れない。
時流は加速する一方だったのでマルクスの思想そのものはヘーゲルのそれより素早くお役御免になり果ててしまったが、その過程で広まったこうした発想の飛躍は逆に不滅の魂を得た。不愉快な状況に追い込まれた時に真っ先に為すべきは犯人探しと処罰で、躊躇なく率先してこの問題に取り組まない限り自分がスケープゴートにされてしまう。そうした恐怖が革命を否が応でも前へ前へと推し進めていく。
*かくして西欧世界ではサン=シモンの産業者同盟構想やオーギュスト・コントの科学者独裁構想やスペンサーの社会進化論を経てアメリカで科学万能主義(scientism)に至った流れ、あるいはフランスでベルクソンが「エラン・ヴィタール(élan vital=生の飛躍)」哲学に至った流れがドイツでは省かれてしまう。
白瀬小百合「封建体制から産業体制へ -サン=シモンの社会思想-」
オーギュスト・コントと社会学の誕生
1212夜『時間と自由』アンリ・ベルクソン|松岡正剛の千夜千冊
【第四段階:人間性の喪失】「ドイツロマン主義とナチズム、遅れてきた国民(1935年)」の最後に登場する「ドイツ特有の情念の一切を投入して生物学への信仰と民族の根源性への信仰を結び合わせて直接行動に向かわせるイデオロギー」について。今日では一般に「ヒトラーとNSDAPに掛かる」とされるが、実際には(おそらく検閲逃れの為)もう一つの読み方が出来る様になっている。
- ヘーゲルの弟子はマルクスだけではなかった。というより、むしろ「鉄血宰相(Eiserner Kanzler)」ビスマルク(Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen、1815年〜1898年)の方がある意味大きな業績を残したとも。
◎シュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題でデンマーク側の汎スカンジナビア運動に汎ゲルマン運動をぶつけて炎上させる。
◎普墺戦争(1866年)のあった年にナショナリズムを煽りながら北ドイツ連邦を成立させ、次第に南ドイツを併合していく。
◎エムス電報事件を契機に普仏戦争(1870年〜1871年)で大勝利を収める。
◎ドイツ帝国(1871年〜1918年)成立に漕ぎ付ける。
この間ずっと「国民に誰が敵か吹き込み、実際に攻撃させる」孤立無援の戦いをずっと続けてきた。さすがは「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」の人?
- 一方、建国してすぐ大不況 (1873年〜1896年)に巻き込まれ国家単位で精神的余裕を失う。やがて「産業革命導入によって生じた本国の余剰生産力を捌く鍵は植民地」と盲信するに至り、植民地獲得に消極的だったビスマルクが失脚した1890年代から本格的暴走が始まる。さてドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(Wilhelm II.,在位1888年〜1918年)が悪かったのか、それとも側近が悪かったのか…
大不況 (1873年-1896年) - Wikipedia - 当時のドイツ帝国の悪行を数え上げるときりがないが、日本との関係でいうならとりあえず三国干渉(1895年)に続いた膠州湾の占領(1897年)と租借(1898年)だろう。この一連の展開は当時の日本人を本気で怒らせたが、さらに経営不手際が義和団の乱(1900年〜1901年)を招くという後日談までついてくる。
ビスマルクの伝記作家エーリヒ・マルクスによれば、ヘーゲルもビスマルクに強い影響を与えたと主張する。ヘーゲルは「国家のみが人間の普遍的理念を認識し、それ自らの人格的自由を完全に享受できる」「各民族の理想とする国家は人格的自由の実現されうる秩序ある法律組織を持つ文化的国家である」と説き、ドイツ民族国家の中で最も「文化的国家」に近い国はプロイセン王国であると考えていた。そのためビスマルクはヘーゲルからもプロイセンを中心としたドイツ統一を正当化できた。
歴史家ランケからも影響を受けたという。ランケはビスマルクとほぼ同時代の人であり、プロイセン首都ベルリンを活動の本拠にしていたため、ビスマルクと親交があり、彼の死に当たってビスマルクは「私は政治的信念の一致、また1845年以降40年に渡る個人的関係から常にランケとの交友は失わなかった」と書いている。ランケの王政的民族主義、保守的民族国家主義的な思想はビスマルクの目指す物と一致するところであった。
ビスマルクはマキャベリを熱心に研究していた。マキャベリは民族統一主義者であり、そのためには手段を問うべきではないと確信しており「言論による者は敗れ、兵力による者は成功する」「国家の健全は平和ではなく、戦争によって表明される」「政略は道徳である。しかも政治家にとっては最高の道徳である。なぜならそれは国家にとって止むに止まれぬものだからだ。」「君主は約束を守ることによって害を受けるなら、その約束を守らないことが正しい」と説く。ビスマルクの発想そのものである。
「(プレスナーいうところの)ドイツ民族生物学」は、こうしたドイツの歴史を「自然淘汰圧」とか「適者生存の宿命」とか「生存圏確保の為の総力戦(負けた側が滅び去るのは自然の理)」といった生物学用語の援用によって正当化しようとする。ヒトラーが政権を奪取する以前、すなわち1890年代から1910年代にかけても非インテリ階層中心に流行。本当の背景にあるのはむしろ「リベラル派インテリが振り翳す形而上学への拒絶感」なのかもしれない。
そして第三段階から分岐する形で世界システム論が登場する…
さて、私たちはいったいどちらに向けて漂流しているのでしょうか…