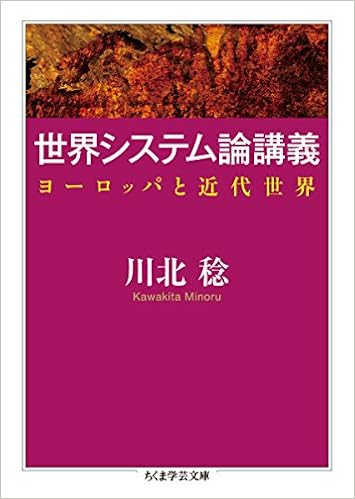
川北稔「世界システム論講義」は、単なるウォーラーステインの世界システム論の要約というより、実例の掘り下げによってオリジナルの学説が抱える還元主義的欠陥を試みた意欲作というべきなのかもしれません。
こうした分析から浮かび上がってくるのは「あえて低開発状態に置かれた周辺に対する中核の搾取」というより、以下。
- 大航海時代幕開けが引き起こした欧州経済中心地の地中海沿岸から大西洋沿岸への推移のインパクトの大きさ。
*穿った見方をすれば何者かの意思が飴と鞭を駆使して欧州東部を再版農奴制に走らせ、西サハラ交易を破壊された西アフリカ諸国を奴隷狩りモノカルチャー国に仕立て上げて大西洋三角貿易を準備した様にも映らないでもない。しかしその何者かとは本当に何者なの? - 欧州領にばかり拘泥する大陸君主達さの傲慢と先見の明の不足。
*ハプスブルグ家がスイスやオランダの独立を認めざるを得ない事態に追い込まれたのも、大英帝国がフランスから海外植民地を奪い放題だったのも、ハノーファー領主でもあったイングランド国王や(ジェントリー階層から嫌われた)スチュワート王朝の伝統的思考様式を継承するスコットランド貴族出身の大臣が米国独立という形でしっぺ返しを受けたのも、オランダ王国がベルギー独立を認めざるを得ない事態に追い込まれたのも全てそのせいとも。 - 大陸型絶対王政をイデオロギー的に支えた(領主が領民と領土を全ん人格的に代表する)農本主義的伝統と自由主義者の相性の悪さ。
*イングランドはジェントルマン資本主義の導入によってなんとか懐柔に成功したが、フランス絶対王政は終始これに振り回されっ放しで「沈んだり潜ったり」を繰り返してきたし、オランダもある意味王政強化が仇となってこの問題に直面する様になり、その繁栄を自ら手放した。
そして産業革命の時代を特徴づけるのも「あえて低開発状態に置かれた周辺に対する中核の搾取」というより、以下。
- 英国やスイスやアメリカといった(領主が領民と領土を全ん人格的に代表する)農本主義的伝統から無縁の国における産業革命の先行
*砂糖に続いて「世界商品」化されたのは主に英国が手掛けた綿織物だけではない。遂に工場で生産される様になったチョコレートやチーズや時計も「販売戦略なしにその厖大な生産量を捌き切れなくなった」という点で重要。それでスイスはチーズ・フォンデュやラクレットといった郷土料理を欧州じゅうに広め、英国のチョコレート会社はバレンタイン・デーなるイベントを考案し、腕時計が鉄道移動者の携帯すべきマストアイテムとして定着するのである。 - 公益の為と称して自ら貧富格差を拡大する自国の商業と工業の拠点を焼き払ったジャコバン派独裁政権のポル・ポト派的蛮行と、その反省が生んだ新たなフランス経済哲学の台頭
*「馬上のサン=シモン」ルイ・ナポレオン大統領/皇帝ナポレオン三世がフランスに産業革命を導入する手段として実践に移し、プロイセン王国/ドイツ帝国やアメリカや大日本帝國から手本とされた。初代と異なり軍隊指揮の才能は皆無でそれが命取りとなったがフランスにブルジョワ二百家による支配の伝統が根付いたのはこれ以降となる。
「馬上のサン=シモン」ナポレオン3世の在野期の思想と著作 - 大不況 (1873年-1896年) を通じて欧州じゅうに広まった「産業革命がもたらす大量供給能力は(庶民の消費者化などの方策がもたらす)大量消費によって支えられねばならない」なる経済理念の一般化。
*イングランドではプリムローズ・リーグ運動によって大衆人気を獲得し(それまで地主の利権の代表種集団に過ぎなかったトーリー党を前身とする)保守党が普通選挙を制した。またドイツでも宰相ビスマルクが労働組合運動を展開するラッサールとその支持者達に接触し国家社会主義の基礎付けを行った。どちらも背景にあったのは(収入制限選挙を武器に)自分の利権のみを代表してきたブルジョワ議員達への憎悪。この感情は1930年代にナチスのイデオローグとして知られる事になったカール・シュミットの敵友理論にまで継承されていく。
プリムローズ・リーグの時代―世紀転換期イギリスの保守主義 単行本 – 2006/12/8 小関 隆
フェルディナント・ラッサール - Wikipedia
そして欧州はベル・エポックなどを謳歌する産業革命成功国と、農奴解放後も再版農奴制の痛手から未だ抜け出せずにいる欧州東部や地方分権化進行によってすっかり零落したオスマン帝国の様な農本主義からの脱却失敗組に二分される事に。そしてこの矛盾こそが(司馬遼太郎が応仁の乱について「革命意識のない一種の生物学的な発熱と脱皮現象」と例えた様に)自然発生的に第一次世界大戦(1914年〜1918年)を引き起こす事になったとも。そう考えると色々しっくりくる感じがします。
現実の歴史の何が厄介かって「農園領主制から出発しながら農本主義から脱却して資本主義社会への適応に成功したユンカー達」とか「最後には遂に自分なりの産業革命導入メソッド考案に成功したフランス」とか「地主の利権のみを代表するトーリーから出発しながら労働者を票田として確保する事に成功した英国保守党」みたいな例外状態に満ちてる辺り。「常に考え続ける人間だけが助かるとは限らないが、少なくとも考えるのを止めた人間はその時点で神の恩寵が全てとなる」みたいな大変シビアな世界観。
ウィルアム・マクニール「世界史講義(The Global Condition: Conquerors, Catastrophes, and Community、1992年)」
相互に行き来する社会によって構成されていたユーラシアの世界システムは1500年以降、正真正銘の世界システムとなった。それに応じて、はるか昔には書記や官吏の記述から漏れる事が多かった文化圏をまたいだ歴史や世界史的展開が一層目立つ様になってくる。世界の密接な関わりに注意を向ける事なく一国の歴史を記す事が不可能となってくる。
内容はともかく「世界システム」という用語とその開始時期は概ねウォーラーステインのそれと重なる点が興味深い。
16世紀は「ローカルシステム集合体」の「世界システム」への移行期
大航海時代到来を背景に欧州経済中心地の地中海沿岸から大西洋沿岸への推移が進行。このサイトは概ねウィルアム・マクニール, 「ヴェネツィア――東西ヨーロッパのかなめ、1081-1797(Venice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1974年)」の言及に従って以下の3地域中心に概観する。
- ポルトガル王国…「アフリカ十字軍」を発端に西回り航路を開拓して1500年代から1530年代にかけて黄金期を築き上げたが、その後衰退してスペインに併合される。後に独立するが、今度は大英帝国経済圏に組み込まれてしまう。
*同時進行で次第に主要植民地ブラジルごとセファルディム系ユダヤ人(1492年にスペインがユダヤ人追放令を出すとポルトガルに亡命し、そのポルトガルも1580年にスペインに併合されるとアムステルダムやハンブルグに本拠地を移す)やオランダ商人にその利権を侵食されていった。
- ヴェネツィア共和国…オスマン帝国の手でレパント交易独占を破られた1480年以降イタリア・ルネサンス運動の継承者となり「文庫本」「オペラ座」「キャンバス画」などを次々と発明。
*しかし次第にドイツ東部や東欧やロシア同様に農場領主制(再版農奴制)地域と同質化していく。
- オランダ(フランドル)…1879年にスペインからの実質的独立を勝ち取って以降、それまでポルトガルがアジアから持ち帰った香辛料やスペインが新大陸から持ち帰った金銀で栄えてきた欧州経済のアントウェルペン/アントワープに代わってアムステルダムがフランドルの経済中心地となる。
*その影響で同じライン川流域に位置する南ドイツでも商業的発展が始まる。
この枠組は補助的に以下も含む。
- スペイン世界王国の一瞬だけの輝き…そのほとんどがフランドル出身のスペイン国王カルロス1世(Carlos I., 在位1516年〜1556年)/神聖ローマ皇帝カール5世(Karl V., 在位1519年〜1556年)とその息子たるスペイン国王フェリペ2世(Felipe II, 在位1556年〜1598年)/イングランド王フィリップ1世(Philip I., 1554年〜1558年)/スペイン国王フィリペ1世(Filipe I., 1580年)の足跡。
*割とこの時期だけハプスブルグ家やスペインの歴史からも浮いている。カール・シュミットではないが「(フランドルやイタリアやポルトガルの助力が得られていた間だけ)単なる陸の国に過ぎない事が忘れられた」という事らしい。
「(自然法に基づく)普遍的支配」の世界 - 諸概念の迷宮(Things got frantic) - ジェノヴァ商人衰退記…第1回十字軍(1096年〜1099年)と1101年の十字軍への協力によってシリアの十字軍国家群や東ローマ帝国との癒着に成功した事で台頭したが、第4回十字軍(1202年〜1204年)による東ローマ帝国一時滅亡以降レパント交易から締め出され、ポルトガルのアフリカ十字軍/西回り航路開拓などで重要な役割を果たしたが、ジェノヴァ略奪(Sacco di Genova、1522年)以降はスペイン王室の御用貸しに変貌。スペインの没落に巻き込まれ欧州経済の中心がアムステルダムや(17世紀以降、神聖ローマ帝国の台所となった)ハンブルグに以降すると取り付く島を失った( 所謂「利子革命」はその最末症状)。最後はとうとう(後にイタリア王国王統となる)サヴォワ家領土に併合されてしまう。
*ちなみに北イタリアではイタリア戦争を集結させたカトー・カンブレジ条約(1559年)によってミラノは神聖ローマ皇帝宗主権下でスペイン王が管理する公国へと変貌を遂げた。中イタリアでもトスカーナ大公国(1569年〜1860年)として再出発したフィレンツェがメディチ家の断絶した1737年以降、神聖ローマ帝国管理下に入った。ウォーラーステインの世界システム論は「欧州の普遍的宗主国の立場を争ったイタリア戦争(1494年〜1559年)の決着はつかなかった」とするが「決着はついたものの欧州経済の中心が地中海沿岸から大西洋沿岸に推移してしまったのでその事が歴史上意味を持たなかった」が正しい。19世紀に入るとナポレオン戦争の後始末でヴェネツィアも神聖ローマ帝国管理下に入るが、それを喜んだのも神聖ローマ帝国だけだった。またスペインに併合された中世地中海の覇者アラゴン王国もそのままひっそりと歴史の表舞台から消えていく。 - 農園領主制(再版農奴制)の甘い罠…大航海時代到来によって衰退必至となったドイツ東部や神聖ローマ帝国や東欧やロシアやヴェネツィアだったが、人口が急増した大西洋沿岸地域の食費高騰に助けられ、農園君主制(再版農奴制)への推移によってその開始時期を遅らせる事に成功した。あくまで一時的な弥縫策に過ぎず、17世紀後半以降次第に効力を失っていったが新たな対策の投入はなく全て小作人に負荷が皺寄せされていった為に(ユダヤ人ゲットー同様)悲惨な光景が現出する。
*ウォーラーステインの世界システム論は農場君主制(再版農奴制)も(新大陸でスペインが履行したエンコミエンダ制やポルトガルが履行したドナトーリオス制同様に中世の延長戦上で履行された因習などではなく)世界システム従属効果の産物とした。オスマン帝国衰退を決定づけた帝国領内分権化と合わせ第一次世界大戦(1914年〜1918年)勃発の遠因の一つとなる。
- ベルベル人王朝衰退記…スペインのレコンキスタ完了(1492年)によってイベリア半島から完全に締め出されたばかりか、西回り航路開拓(海路)によってそれまでマグリブ(チュニジア以西のアフリカ北岸)と西アフリカ諸国を陸路結んできたサハラ交易が崩壊。大国を維持する財源がなくなって両地域とも小勢力に分裂して内紛を繰り返す様になり、その結果西アフリカ一帯は(大西洋三角貿易の一環として)欧州向け奴隷供給国家として再編される羽目に陥った。
*これもウォーラーステインの世界システム論では世界システム従属効果の産物とされた。19世紀前半に奴隷貿易が終焉すると再び大国維持に必要な財源を失い小勢力に分裂して内紛を繰り返す様になり欧米列強のアフリカ分割に際して各個撃破されて壊滅。ちなみに「先込め銃までの供給しか受けられず、最新鋭のライフルや元込銃にあっけなく破れる」悲哀は米墨戦争(1846年〜1848年)によって国土の1/3を喪失したメキシコの方が先に経験した。
- ザクセン選帝侯の暗躍と新教国家スェーデンの台頭…フランク王国カール大帝のザクセン併合(772年〜804年)は北欧を西欧世界と隣接させた。その当時はヴァイキング(北欧諸族による略奪遠征)が発生したが、この時代にはマインツ司教(後に新教に改宗しプロイセン王統/ドイツ帝国皇統となるホーエンツォレルン家の先祖筋)の贖宥状がザクセン選帝侯の領内でも販売された事への抗議を発端とするルターの宗教革命の発信地となる。また八十年戦争(1568年〜1609年、1621年〜1648年)に際しては、これを指導したオランダ総督ナッソー=オラニエ家がザクセン選帝侯と血縁関係にあり軍事的にも同盟関係にあった事からこの地にマウリッツの軍事革命も波及した。
*こうした経緯が重なって三十年戦争(1618年〜1648年)に際しては新教側代表としてスウェーデン軍が参戦しフランス軍と並んで活躍。 - スイスの宗教問題…ドイツ農民戦争(1524年〜1525年)を引き起こしたトマス・ミンツァーと並ぶ新教側急先鋒ツヴィングリ(バーセルやベルンやチューリッヒで神権政治実現を画策)は幸いカソリック勢との内戦で1531年落命した、しかしその後フランスから追放されたユグノー指導者の一人ジャン・カルヴァンが神権政治(1541年〜1564年)を遂行したジュネーブが合流し時限爆弾がリセットされる。
*新教勢とカソリック勢の対立が19世紀に入ってから再燃し二月/三月革命(1848年)の引き金に。
スイス「武装中立」の裏側で - 諸概念の迷宮(Things got frantic) - オランダに「不和の種」が撒かれる…次第に絶対王政を志向するオランダ総督ナッソー・オラニエ家と、共和制継続を志向するレヘント(商業都市を牛耳るブルジョワ貴族)の対立が表面化してくる。
*名誉革命(1688年〜1689年)によって同君連合が成立した事からナッソー・オラニエ家が王統として対外的に公式に認められる様担って対立激化。遂には武力衝突にまで発展し(ルクセンブルグ公国に駐屯する)プロイセン軍の介入まで招いた事がフランス革命勃発の遠因の一つとなった。また復古王政時代にオランダ王国がベルギーを併合した事は(フランス7月革命に便乗した)ベルギー革命(1830年)につながった。
まるで 「行く人来る人」の様な慌ただしさだが、その一方ですべての動きの根底に欧州経済中心地の地中海沿岸から大西洋沿岸への推移を見てとる向きもある。
*ここでいう「大西洋沿岸」はバルト海や北海、さらにスペインやアフリカの西岸をも含むが、そのうち後者は包囲戦(1627年〜1628年)遂行までユグノー経済を支え続けてきたラ・ロシェルや(フランス革命期にジャコバン派独裁政権の手によって在地有力者が粛清され尽くすまで)コルベール重商主義を端緒とするフランス交易の要として栄え続けてきたボルドーに商品売り込み先として周辺化されたとも。またヴェネツィアがオスマン帝国から勝ち取った文書行政用紙の専売権などもカピチュレーション(1536年にフランス使節とオスマン帝国大宰相の間で条約案が合意に達し、1569年までに両国の間で締結された特勅)成立以降はフランスの手に渡り、一時期はヴェネツィアが欧州全体の発行書籍の1/3を占めた出版事業もアムステルだけでなくパリやリヨンがかなり食い込んでいる。
17世紀から18世紀にかけては英仏の「世界システム」参入期
16世紀段階ではまだまだフランスもイングランドも「世界システム」参入を果たしたとは言い難い状況にあった。17世紀以降は遂にそれが達成されるが「どうやって」については様々な議論が存在する。
世界システム論講義-──ヨーロッパと近代世界-ちくま学芸文庫-川北稔
「17世紀の危機」についてのホブズボームの見解
かつて17世紀ヨーロッパの経済が「全般的危機」の状態にあったと論じたのは、英国の歴史家E.J.ホブズボーム(Eric John Ernest Hobsbawm, 1917年〜2012年)であった。マルクス主義 者であったホブズボームの議論は、本質的にマルクスの経済発展に関する 理論を、この時代の歴史にストレートに適用したものであった。すなわち、彼よれば、16世紀のヨーロッパ は、人口増加や物価上昇、セビーリャの文書で確認できるスペインの対アメリカ貿易、デンマークとスウェーデンのあいだのエアーソン海峡関税帳簿によって確認できる東西ヨーロッパ貿易の大発展などにみられる「拡張の時代」つまり「好況期」であった。しかし、この「発展」は、東ヨーロッパ の「再版農奴制」に みるように、あくまで「封建制度」の枠のなかの出来事であった。西ヨーロッパにしても「 絶対王政」という封建的な権力のもとに置かれていたのである。このような 枠( つまり「封建的生産関係」)のなかでの発展(マルクス主義の用語でいう「 生産力 の 成長」)は、おのずと天井に突き当たる。それが1620年代からの「停滞」ないし「危機」である。
こうして、世界的に貿易活動は停滞し、ヨーロッパ各地に反乱や動乱が起こる。イギリスのピューリタン革命とそれにまつわるスコットランドやアイルランドの反乱、名誉革命、フランスのフロンドの乱、カタルーニャなどスペイン各地の反乱などである。スウェーデンにもクーデターがあり、遠くロシアにも、ステンカ・ラージンの一揆がみられ た。
ところで、ホブズボームの見解からすれば「危機」は「封建的生産関係」の危機だっ たのだから、それを脱するには、社会の基盤をなす生産関係を、近代的・資本主義的な ものに一挙に変えることしかない。生産関係の激変は、いうまでもなく革命である。つまり「ブルジョワ(市民)革命」によって社会の体制を一段階すすめることだけが、この「危機」に対する処方箋であり(「発展段階論」)、正しい処方箋を書いたのは、フランスでもスペインでもなく、イギリスであった。17世紀後半以後 イギリスがオランダ、フランスを撃破して、世界の主導権を握り「世界で最初の産業革命」にいたるのは、まさしくイギリスが「世界で最初の市民革命」に成功したためであった。これが、 ホブズボームの議論であっ た。ここでいう、イギリス市民革命とは、17世紀中葉のいわゆるピューリタン革命と1677年の名誉革命を想定するのが一般的であった。
「17世紀の危機」についてのH.R.トレヴァ゠ ローパーの見解
しかし、H.R.トレヴァ゠ ローパー(Hugh Redwald Trevor-Roper, Baron Dacre of Glanton, 1914年〜2003年)など、全ヨーロッパ的な「危機」の存在は確認しながらも「危機」の本質はまったく違うと考える歴史家も少なくなかった。トレヴァ゠ローパー によれ ば「危機」の兆候は、ホブズボームのいうような経済や政治の面ばかりか、 社会 にこそみられ、中世的な魔女裁判やほうき星信仰のような非合理的なものが復活し た、という。繁栄 の16世紀を支えた「 体制」は、絶対王政の宮廷であり、その宮廷は ルネサンス的な奢侈に彩られていた。官僚制度と常備軍という絶対王政の二本柱そのものが、きわめて「 高くつく」道具立てで あった。こうして、王室の「奢侈」を支える ために、財政改革が不可欠となったが、それに成功しなければ、租税強化以外に方法は なかった。結果は、奢侈的な宮廷につながり、甘い汁を吸う「宮廷派」と、重い租税負担にあえぐ「地方派」に、社会を二分することになった。前者がルネサンス的であった とすれば、後者は禁欲と勤勉をモットーとするピューリタン的な思考法に傾いていった のも当然である。「危機」の本質をこのようにみ たトレヴァ゠ローパー は、リシュリューやコルベールなどの財政改革者を登用したフランス王室こそが、この「 危機」に 正しく対応したのであり、だからこそ、その王室は政権を維持し続け、逆に、チャールズ一世のもとで、改革を怠ったイギリス王室は、「革命」を引き起こしてしまったの だ、という。
第三の立場「財政・軍事国家」論
イギリス一国史ないしイギリスとフランスの比較 史といった国別史の次元でいえば、 近年急速に盛んになりつつある「財政・軍事 国家」論 ─ ─17世紀〜18世紀のイギリス 国家が、フランスよりはるかに重い税をとりながら、国民の不満をあまり招くことがなかったという ─ ─ が、両者の議論を総合することに成功するかもしれない。
「ジェントルマン資本主義」と「財政・軍事国家」論
ジェントルマン資本主義論とは対立するイギリス史の見方に「財政・軍事国家」論とでもいうべきものもある。産業革命の存在を強調しようとする歴史家は、むしろ19世紀 イギリス政府の自由貿易政策に、イギリス衰退の原因を求めており、これとの対比で18世紀の政府を称賛するのである。彼らによれ ば18世紀のイギリスは、フランスに比べ てたいへんな重税国家となっていたが、国民の税にたいする反発はそれほど強くはなかった。反税闘争が革命につながったフランスとは、この点でまったく異なっていたというのである。
イギリスの民衆が重税に反発しなかった理由は、イギリス政府が、徴税にあたるべき官僚を、もっとも租税負担の重い中産階級から任命したからであり、貴族に特権を認めなかったからだとも、彼らはいう。そのような徴税システムは、17世紀末に、イングランド銀行の設立を中心とする「財政革命( P. G. M. Dickson)」によって確立された。
しかも、イギリス政府は、このような膨大な資金を、ほとんど軍事費と軍事支出のため に発行した国債の元利の支払いにあてた。その結果、対仏戦争は、資金の豊富なイギリスがつぎつぎと勝利し、大英帝国(第一帝国とも重商主義帝国ともいう)の形成につながっ た、というので ある。かずかずの戦勝は、この重税国家をささえた中産階級─ ─彼らは、重税に耐えるジョン・ブルとしてしばしば戯画化された─ ─を熱狂させ、 彼らの支持はますます強化された。この結果、イギリスは軍事力によって、自由貿易圏 を確保することができ、これを基盤として産業革命に成功した。しかし、19世紀イギリス政府は、自由貿易を前提とし「 軽い政府」に移行したため、結局は、急速に工業化されたドイツとアメリカに敗れ、1873年以降の「 大不況」のなかで、世界システムのヘゲモニーを喪失していくのだという。
とりあえずこのサイトでは「ジェントルマン資本主義」論を中心に以下の様に概観する。まぁ現在なお歴史学の分野で激論が交わされてる状況だから、それほどすっきりとはまとめ切れてない…
- 百年戦争(1337年〜1453年)でフランスとの国境を定め、薔薇戦争(1455年〜1485年/1487年)で中央集権体制に反対する大貴族連合が自滅した後、イングランドのチューダー朝(1485年〜1603年)はジェントリー(地方地主)階層を急増させる事によって体制安定化を図ろうとした。スチュワート朝(スコットランド王統1371年〜1714年、イングランド王統1603年〜1707年、グレートブリテン王国王統1707年〜1714年)開闢後も彼らは大陸式絶対王政導入を断固として拒み続け、それで清教徒革命(1638年〜1660年)や名誉革命(1688年〜1689年)が勃発した。
*その詳細について今日なお激しい議論が続いているが「ヨーマン(中産階層をなす自由自作農)主役説」が既に脱落した一方で、新たに「ピューリタン・ジェントリ」仮説が浮上してきた模様。
ピューリタン・ジェントリ論の射程 - 18世紀に入るとイングランドは南海泡沫事件(1720年)や東インド会社の腐敗といった問題への対処を要求された。穏便派ホイッグが政権を握って中央銀行が設立され有事の際に国債発行で支出を賄うシステムを完成させ「ウォルポールの平和(1721年〜1742年)」を現出させたのがまさにこの時期。それに続いて「平時は国王やスコットランド貴族の後援を受けたトーリー党」「戦時下では植民地拡大に意欲を燃やす海商ホイッグ党」といった役割分担が登場したが北米植民地への対応に失敗しアメリカ独立戦争(1775年〜1783年)を引き起こしてしまう。
* フランスも百年戦争後に公益同盟戦争(1465年〜1477年)とフロンドの乱(1648年〜1658年)を通じて中央集権化に成功したが、スコットランドの実業家ジョン・ローが財務総監として中央銀行成立を目指したミシシッピ計画でバブルが弾け、当人も罷免されて元の木阿弥となってしまった。とはいえ歴史のこの時点でイングランドとフランスの産業インフラに圧倒的格差が開いていた訳ではないとする説も多い。実際には財務総監コルベール死後にナントの勅令(1598年)を破棄したフォンテーヌブロー勅令(1685年)によるユグノー追放がフランス経済に与えたダメージや、英仏間の自由貿易を規定したイーデン条約(1786年)のダメージをどれだけと見積もるかにもかかってくるが、いずれにせよフランス革命期(1789年〜1799年)にジャコバン派独裁政権が(フランス貿易の要)ボルドーの在地実力者を片っ端から粛清し(フランス工業の要)リヨンを住人ごと灰燼に帰してしまい、フランスがその経済的ダメージから半世紀以上立ち直る事が出来なかった事実は揺らがない。 - かくして英国産業革命が始まり、やがて他国にも伝播したが、そのせいで慢性的な供給過多状態が発生た上にアメリカン・ペリル(American peril、輸送網整備と冷蔵技術の進化によって南北アメリカから輸入される様になった安価な農畜産物の欧州大襲来)が重なった為に各国が関税障壁を高め大不況(1873年〜1896年)が発生する。
*ここで興味深いのは「経営学=後発地域がゼロから産業革命を始めるノウハウ」が英国でなくフランスのサン=シモンやオーギュスト・コントなどの社会思想から出発して「馬上のサン=シモン」ルイ・ボナパルト大統領/皇帝ナポレオン三世の時代に一応の体裁が整い、プロイセンやアメリカや日本に伝播していったという事である。(領主が領民と領土を全人格的に代表する)農本主義的伝統の影響下になかった英国やスイスやアメリカでは比較的スムーズに産業革命が始まったが(ベルギーから独立を宣言されたオランダ王国の立ち位置は微妙)これらの国は逆に一様に「教えるのが下手」あるいは「教えたがらない派」だった。
こうして全体像を俯瞰してみると「17世紀の危機」の正体は案外、大不況 (1873年〜1896年)の時と同じ様に(重商主義流行に伴うある種のブロック経済化の進行を背景とする)流通麻痺だったのかもしれない。
*実際、同時代日本でも、全国各地の戦国大名達が楽市楽座などを通じて選別した御用商人と癒着する事で構築された領国ごとのブロック経済が「(西陣商人などの)株仲間(参勤交代の為に整備された交通網を利用した富商と富農の全国規模ネットワーク)」の暗躍によって次々と穴を穿たれ陥落していく。欧州ではその役割をオランダ商人やアムステルダム及びハンブルグに依るセファルディム系ユダヤ人が果たしたとも見て取れるのだが、日本における大名と癒着した御用商人が元禄時代までにほとんど駆逐され尽くしてしまったのに対し、欧州ではドイツ諸侯らの割拠する経済後進地帯を中心に宮廷ユダヤ人(Hofjude(n), Hoffaktor)が19世紀まで残存した。主にフランクフルト出身のアシュケナージ系ユダヤ人で構成された彼らは、実際には確実に(アムステルダムやハンブルグに依る)セファルディム系ユダヤ人と裏で通じ合っていたので「赴任先の経済理解度に応じて見せ方を変えていただけ」とも言われている。
ウォーラーステインの「世界システム論」の内容って思うより全面否定が難しいのです。こうして「あえて低開発状態に置かれた周辺に対する中核の搾取」なるテーゼの部分くらいなら摘出除去も不可能じゃない様に見えますが「それでも搾取は実存する」と信じてる立場の人から「でもこの程度、誤差の範囲内じゃね?」と正面切って決めつけられてしまうと反論は通用しなさそうなんですね。
