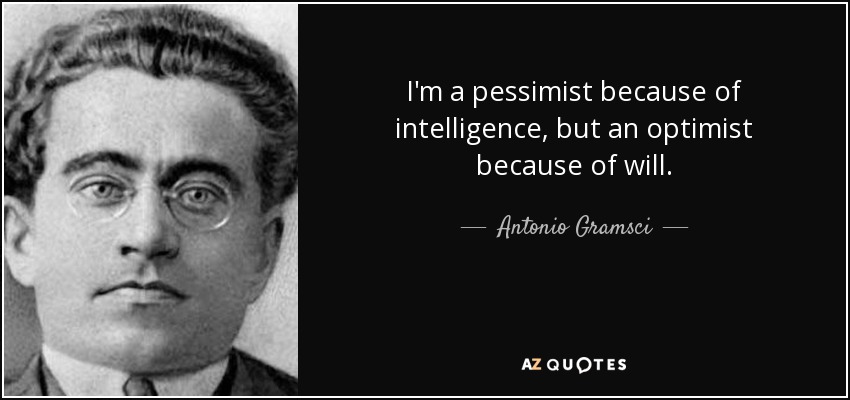最近、駅前で「安倍政権は無実の日本人を次々と逮捕するファシスト政権である!! 一刻も早く打倒しなければ日本人が皆殺しにされてしまう!! その現実を認め様としない精神異常者も全員ファシストであるから我々が殺す!!」 的な事をただひたすら連呼し続ける「平和祈願デモ」に遭遇した。こうしたデモが放置されている現状こそファシズムから最も程遠いとも思えるのだが、彼らに言わせれば、ついそう考えてしまう私の様な人間こそ「日本人の将来の為に真っ先に粛正すべきファシスト!!」という事になるのかもしれない。おそらく「分別のない子供じゃあるまいし、普通の健常者ならそこまで深く考えなくてもどちらが正しいか即断できるよね?」と畳み掛ける内的圧力こそが彼らの最大の武器なのだろう。
そもそもファシズム(Facism)の起源は1961年にやっとリソルジメント(Risorgimento、イタリア統一運動)を達成したばかりのイタリア王国である。当時の政治的情況は現代日本人には想像もつかないくらい過酷なものだった。
第一次世界大戦(1914年〜1918年)後のイタリアの低迷は目を覆わんばかりだった。「時はまさに共産主義躍進の時!!」と信じたサルデーニャ島出身のアントニオ・グラムシ(Antonio Gramsci、1891年〜1937)は、1921年イタリア共産党の結成に加わり中央委員会委員に選出され、イタリア共産党代表兼コミンテルン執行委員としてモスクワに滞在(1922〜1923年)。この地でロシア人のユーリヤ・アポロニエヴナ・シュヒトと結婚する。しかしその間にもイタリアでは予想外の事態が進行していた。1919年に自らの政治理論を実践すべく退役兵からなる政治団体「戦闘者ファッショ(後の「ファシスト党」)」を結成し、1921年に議会選挙に出馬して35議席を獲得し政界入りを果たしたベニート・ムッソリーニ(Benito Amilcare Andrea Mussolini 、1883年〜1945年)がクーデターを決行(ローマ進軍、1922年)。国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世の支持を得て自由党政権を転覆させ、臨時政権を樹立したのである。
ムッソリーニとグラムシの因縁…1913年にイタリア社会党トリノ支部に入党したグラムシは、傴僂だった為に第一次世界大戦で徴兵を免除され社会党機関紙「アヴァンティ !」トリノ支局に入る(1915年、同年大学は中退)。ところでこの頃の「アヴァンティ !」編集長は1911年に伊土戦争への反戦運動で政府に拘束され半年間の懲役刑を受け、1912年以降の党内抗争で改良主義者の粛清に辣腕を揮ったムッソリーニだった。既に1914年時点で国際主義路線を放棄し、民族主義と社会主義を結合をした独自の政治理論(ファシズム)を着想したムッソリーニは第一次世界大戦への参戦を支持し、英国の資金援助を受けて日刊紙「ポポロ・ディタリア」を創刊。反党行為としてイタリア社会党から除名されるも1915年のイタリア参戦に伴い、陸軍に志願入隊。1917年に手榴弾による負傷で後遺症を負って名誉退役を勧告された(最終階級は軍曹)。一方グラムシは1919年、トリアッティ、アンジェロ・タスカらとともに社会主義文化週刊紙「オルディネ=ヌオーヴォ(新しい秩序)」を発刊し、労働者による自主管理を軸とする工場評議会運動を展開。工場占拠闘争をはじめとするトリノの労働運動に積極的に参加している。
レーニン以前のマルクス経済学 - 諸概念の迷宮(Things got frantic)
飛ぶ鳥を落とす勢いに乗ったムッソリーニだが、ただひたすらグラムシの頭脳のみを恐れた。モスクワ滞在時にムッソリーニ政権が逮捕状を出した為、帰国不能となったグラムシはスイスに滞在。このころグリゴリー・ジノヴィエフの後押しでイタリア共産党書記長となる。翌1924年、下院議員に選出されると議員の不逮捕特権を利用してイタリアに帰国。ムッソリーニ政権との対立姿勢を鮮明に打ち出そうとしたがムッソリーニの勢いは止まらなかった。1926年、まさに亡命しかないと決断したタイミングで逮捕され、20年4か月の禁錮刑判決を受ける。だが絶対王政、革命政権、ナポレオン政権の三代に渡って危険視されたマルキ・ド・サド伯爵を文学者として完成させたのが30年以上に渡る刑務所と精神病院への幽閉生活だった様に、1937年まで続く監獄生活こそが「思想家グラムシ」を完成させた。その間書き溜めたノートが33冊。有名な「覇権(hegemony)論」もそこでの重要な論題の一つだった。
なぜなのか?1917年、ロシアでは労働者の革命が実現したのに、他の国々へ波及することはなかった。じつに不思議なのは、20世紀初頭、ヨーロッパ各国の革命運動がすべて敗北したことだ。当時革命情勢にあったドイツやハンガリーでも革命は成功しなかったし、イタリアでも例外ではなかった。1919年から20年にかけ、イタリア北部では「トリーノ工場評議会」の労働者が数か月にわたって工場を占拠したが、革命に結びつかなかった。なぜなのか?
アントニオ・グラムシの有名な『獄中ノート』は、このような問題意識がもとになっている。若きグラムシの革命家としてのデビューは、トリーノでの工場自主管理闘争だった。20世紀を代表する政治学の『ノート』は、革命運動の後退期を経た数年後に書かれたもので、ヨーロッパ革命の失敗や1920~30年代の労働運動の挫折を教訓に、根本的な原因を究明しようとするものであった。そして「来るべきもうひとつの世界」を信じ、そこに行き着く道を模索することをあきらめないすべての人々に、没後75年たった今日でも訴え続けている。
アントニオ・グラムシは20世紀イタリアの国民的思想家であるのみならず、コミンテルンの系譜で生き残った希有な世界的理論家であった。いまやアメリカの大学院生の学位論文で最も多く引用される一人であり、英語圏において20世紀に一番引用・参照されたイタリア人は、ムッソリーニでもクローチェでもなくグラムシであったという(エリック・ホブスボーム)。おそらく日本語でも、ベスト・スリーには入るであろう。
例えばグラムシは、「知識人」概念を有機的・機能的カテゴリーとして拡延し、「すべての人々は知識人である。だがすべての人々が社会において機能的カテゴリーを果たすわけではない」と述べた。それによって「伝統的大知識人」や「大学アカデミズム」内の限定から「知識人」機能を解放し、ジャーナリズムや大衆文学・民間伝承にも「文化」の担い手を拡大した。これが特に重要なのは、ほかならぬ日本のグラムシ研究の重要な部分が、基調講演を行った石堂清倫、代表委員としてシンポジウムを成功させた片桐薫ら非アカデミズムの「在野知識人」により担われてきたからである。また、このシンポジウムを支えた多くのスタッフが、ボランティアの「市民」であり「有機的知識人」であった。そうしたかたちでの普及が、今後も期待できるのである。
特定の人物または集団が長期にわたってほとんど不動とも思われる地位あるいは権力を掌握すること。それによる地域あるいは国家の統治を覇権統治という。それに成功した国や人物は、覇者と呼ばれる。
但し、覇権を得る過程はいわゆる既定路線や全体的同意によるものであってはならず、相対的に有利な立場にある者が武力、権力、財力などの力(power)の行使によってその敵対的立場にある者を制し、勝利あるいは事実上の最優位の立場を獲得することによってでなければそれは覇権とは称されない。
覇権や覇権主義にしても、組織を巨大化する方策として有効な手段であるため一概に悪とは言えない。
第二次大戦下、イタリアのマルクス主義者であるアントニオ・グラムシがこの用語を多用したことから一般に広まったとされる。
覇権は、被支配者の「同意に基く」支配を強調した統治体系という理解が一般的である。
覇権安定論(Hegemonic stability theory)
経済学者のチャールズ・キンドルバーガーによって発表され、ロバート・ギルピンによって確立された理論である。一国の覇権で世界が安定し、かつ経済的に発展するには以下の条件を要する。①一国が圧倒的な政治力及び経済力、すなわち覇権(Hegemony)を有していること。
②覇権国が自由市場を理解しその実現する為に国際体制を構築しようとすること。
③覇権国によって国際体制の中で利益を享受すること。
ある単一の国が圧倒的な覇権を掌握しておくことで国際社会は安定するというものではない。覇権国が諸国に利益を提供することができる国際体制を構築・維持する点が重要である。この体制が諸国にとって有益なものである限り、非覇権国は自ら国際体制を築くことなく円滑な経済活動を行うことができる。
覇権循環論(hegemonic cycle theory)
近現代の国際関係についてポーランド人の政治学者ジョージ・モデルスキー(George Modelski、Jerzy Modelski、1926年〜2014年)が提唱した理論。概ね16世紀以降、世界の政治・経済・軍事他覇権はある特定の大国によりその時代担われ、その地位の循環を繰り返すとする。この世界大国は歴代16世紀のポルトガル、17世紀のオランダ、18世紀と19世紀の大英帝国、20世紀のアメリカ合衆国といった具合に2世紀連続してその地位を務めた大英帝国を例外とし、大体1世紀で交代するものとされその覇権に異議を唱え対抗するのはスペイン、フランス、ドイツ、ソ連といった大陸国で、決まって勝利することは無い。新興大国が既存の世界大国に反旗を翻し世界の不安定性が増した際に決まって世界戦争が起こり、そこで新興大国は敗北し先代の世界大国の側に付き共に戦った国が新しい世界大国の地位を得るとする。世界大国となる条件は以下とする。
①外界に対して開かれた島国もしくは半島国であること。
②内政に競合がありながら政局が安定(例としては大英帝国の保守党と労働党、アメリカの共和党と民主党の二大政党制)していること。
③世界中にその意思を知らしめ影響力を行使する暴力装置(例としては強力な海軍や情報機関)を持っていること。
世界システム論講義-──ヨーロッパと近代世界-ちくま学芸文庫-川北稔
まず大成功を収めたのはオランダであっ た。16世紀に成立し、今日、地球全体を覆っている近代世界システムの歴史上、その中核地域のなかでも、圧倒的 に強力となって他の 諸国を睥睨するようになった国を、「ヘゲモニー国家」と呼ぶ。その 国の生産物が、他の中核諸国においても、十分な競争力をもつほどに なった国家のことである。近代世界システムの全史において、ヘゲモニー国家は三つしか存在しなかっ たと考えられる。第二次世界大戦 後 から ヴェトナム 戦争 までの アメリカ、19世紀中ごろ、ヴィクトリア女王のもとで「イギリスの平和(パクス・ブリタニカ)」を確立 した時期のイギリスのほか、17世紀中ごろのオランダがそれである。時代は、世界システム全体にとっては「危機」の時代であった が、そのなかで、独立直後のオランダが、圧倒的な経済力を確立し たのである。
ヘゲモニー は、まず第一次産業の生産活動から始まる。17世紀のオランダは、もっぱら商業国というイメージが強いが、その実態は農業 の「黄金時代」であり、またヨーロッパ最大の漁業国でもあった。オランダは、たしかに食糧を自給することはなく、東 ヨーロッパ やイギリスからの大量の穀物輸入に頼っていたが、他方では、干拓がすすみ、付加価値の高い近郊型農業─ ─染料をはじめとする工業用原料 や野菜、花卉などの栽培に集中する─ ─を発展させたのである。北海のニシン漁を中心とする漁業は、あまりにも強力で、イギリス漁業 はまったく太刀打ちできなかった。
戦後の日本の歴史学においては、オランダの歴史は、イギリスのそれとの対比で「近代化の失敗例」とみなされ、その失敗の原因を求める 研究が中心であった。中継貿易を中心 にした経済の仕組みがその弱点であった、といわれたものである。しかし、現実のオランダは、世界で最初のヘゲモニー国家として、イギリスにも、フランスにも、スペインにも、とうてい対抗しようのないほどの経済力を誇ったのである。
17世紀中ごろのヨーロッパ では、工業生産でもオランダが圧倒的に 優越していた。その中心は、ライデン周辺の毛織物工業とアムステルダムに近いハーレムなどの造船業、マース河口の 蒸留酒 産業 などで あっ た。
生産 面 での 他国 に対する 優越 は、世界商業の支配権につながっ た。ポルトガル 領のブラジルでも東アジアでも、オランダ人の姿が みられるようになった。政治的な支配がどのようになっていようと、 オランダ人は世界中いたるところにその存在を示すことになっ たのである。こうした世界商業の覇権は、たちまち世界の金融業における 圧倒的優位をオランダにもたらし、アムステルダムは世界の金融市場 となった。オランダの通貨が世界通貨となったのである。のちのイギリスやアメリカの例でもわかるように、世界システムのヘゲモニー は、順次、生産から商業、さらに金融の側面に及び、それが崩壊する ときも、この順に崩壊する。たとえば19世紀末のイギリスでも、生産面ではドイツやアメリカに抜かれ たにもかかわら ず、ロンドンの シティが世界金融の中心としてとどまっていたし、ヘゲモニーを喪失 した現在のアメリカにしても、なお世界の基軸通貨はドルであるのと 同じで ある。
とすれば、オランダのヘゲモニーは、どのようにして成立したのか。一言でいえば、そこにみられるのは、螺旋形の相乗効果である。 たとえば、圧倒的に優秀な造船業を確立したことから、オランダは 漁業と商業で圧倒的に有利になった。ニシン漁に使わ れたハリング・バイスと呼ばれる、船上で塩漬けの加工ができる特殊船はイギリス漁業関係者の垂涎のまとであった。しかし、それ以上に効果があっ たのが、オランダがバルト海貿易用に開発したフライト船である。この型の船は、小人数で大量の積み荷を安価に運ぶことができたため に、バルト海貿易において価格の割に重かったり体積の大きい木材などを扱う「かさばる 貿易」の経済効率を圧倒的に よくした。その結果、エアーソン海峡関税帳簿でみるかぎり、バルト海貿易では、オランダはライヴァルで あるイギリスの10倍もの船舶を動かすことができたのである。オランダの海運運賃は、イギリスの半額程度であっ たといわれている。
しかも、このバルト海貿易こそは、近代世界システムの中核となっ た西ヨーロッパと、その「周辺」つまり従属地域となった東ヨーロッパを結ぶ幹線貿易であったわけで、世界システムそのものの生命線 であった。東ヨーロッパ は、西ヨーロッパに穀物を供給し、また重要な造船資材─ ─マスト材をはじめとする木材、ピッチ、タール、帆布 など─ ─のほとんどを供給した。したがって、オランダは、造船業が発達し、優れた船をつくることができたので、バルト海貿易 で圧勝したのだが、バルト海貿易をにぎったから造船業で優位に立つ こともできたのである。木造家屋が多く、戦争にも、貿易にも木造船 が使われた時代であってみれば、木材を含む造船資材はのちの鉄にも 匹敵する戦略物資であったのだ。この時代にアムステルダムで取引 された商品の四分の三は「 母なる貿易」と呼ばれたバルト海貿易関係のものであったといわれる。
こうした優位は、世界商業にも反映され、16世紀末に成立した多数 の東インド会社を統合して、1602年につくられた連合東インド会社 は、イギリスのライヴァル会社をものともしなかった。資本金もケタ が違っていたが、何よりも、17世紀中ごろまでのイギリス東インド会社は、継続性の薄い、一時的な性格の強い会社でしかなかったからである。
オランダ の、というよりアムステルダムの商業上の優越は、レヘントと呼ばれた有力ブルジョワ、つまり商人貴族の階層を生み出し、金融面での優越につながった。こうして、アムステルダムこそは、世界中の資金が 集まる場所となり、金利のもっとも低い金融市場となっ た。個々の商人はもとより、ヨーロッパ各国の政府がこの市場で資金 を借りようとしたのは当然である。とすれ ば、この金融市場をいつ でも利用できたオランダ人が、造船業や世界的な商業活動でも、植民地の鉱山やプランテーションの開発─ ─ポルトガル領ブラジルでの 砂糖プランテーションのように─ ─においても、資金面で他国の同業者よりはるかに有利な立場に立つことになったことはいうまでも ない。
さらに、こんなこともある。世界商業と金融の中心となったアムステルダムは、必然的に情報センターともなった。安価な資金と十分 な情報からして、海上保険の掛け金率も、アムステルダムで圧倒的に低くなり、外国船でさえ、ここで保険を掛けるようになった。逆 にいえば、金融・保険業などの「みえ ざる 収益」の点でも、オランダは圧倒的な 力をもつようになった のである。
とはいえ、ヘゲモニーの状態は長くは続かない。オランダ、イギリス、アメリカ合衆国の場合は、いずれ も真の意味のヘゲモニーは、半世紀とは続かなかった。ひとつの要因は、ヘゲモニー 国家では生活水準が上昇し、賃金が上がるため、生産面での競争力が低下する ことにあろ う。
オランダにかぎらず、ヘゲモニーを確立した国 は、イデオロギー的 にも、特徴的な傾向を示す。すなわち、圧倒的な経済 力を誇るヘゲモニー国家は、必然的に自由貿易を主張するのである。この時代の オランダでは、有名な国際法学者グロティウスが「 海洋自由」論を 唱えたことは、よく知ら れていよう。圧倒的に強い経済力を誇る国 にとっては、自由貿易こそが、他の諸国を圧倒できるもっとも安上がりな方法なのである。同じことは、19世紀の「ヘゲモニー国家」イギリスにも、20世紀のアメリカについてもいえる。アメリカが自由貿易、より広くは自由主義の使者であったのは、そのヘゲモニーが 確固としているあいだだけであっ たことは、ごく近年のこの国の政策をみれば 明白で ある。
それにしても、自由主義を標榜するヘゲモニー国家の首都(中心都市)は、実際に、世界中でもっともリベラルな場所となる。したがって、そこには、故国を追われた政治的亡命者や芸術家が蝟集すること にもなる。こうしてアムステルダムが、のちのロンドンやニューヨークと同じように、亡命インテリの活動の場となり、画家をはじめ、芸術家の集まる町となっ たのも当然である。
獄中でグラムシは「何故、共産主義はファシズムに敗れたのか?」と自問自答を繰り返し、その結果どうやら「不運に悩まされながら生きる人々は誰もが幸運にすがろうとする。本当に幸運である必要も、本当に人に幸運をもたらす能力を備えている必要さえない。人があやかりたいと思うほど幸運そうに見える人物がその期待を一身に集める」という結論に到達したらしい。ムッソリーニの勝利をそういう形で認めた事が戦後イタリア共産党の出発点となる。こうしてソ連が崩壊しても微動だにしなかった「イタリア構造主義=ユーロコミュニズム」が産声を上げる…
はてさて我々はどこに向かって漂流してるんだろう?