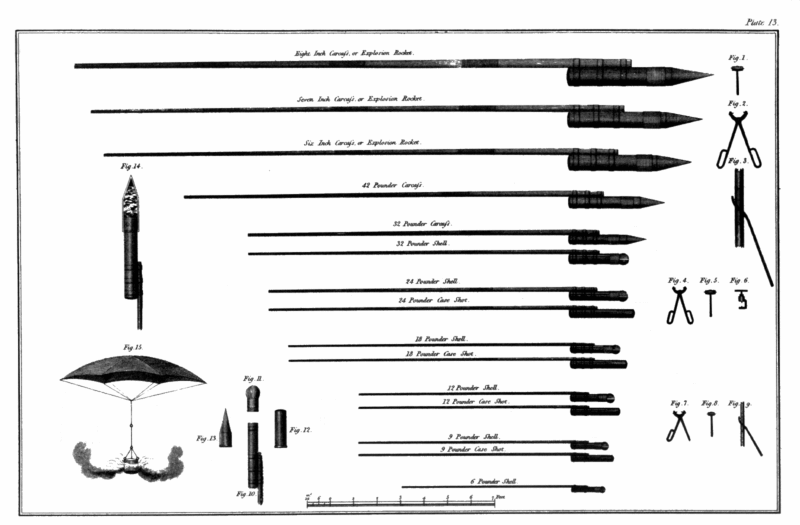以下の投稿では少しばかり大英帝国の事を褒めすぎたかもしれません。
ある意味大英帝国はジェントリー階層の良心によって支えられてきた訳ですが、裏を返せば野蛮な同国人によって絶えず存続の危機に立たされてきたのもまた事実だからです。
イギリスのインド成金。イギリス東インド会社統治下のインドで巨富を築き、本国に帰還した者の中でも、特にインド風生活に染まりきった者を指した。ベンガル地方のムスリム太守の称号であるナワーブ (nawab) に由来する。
- ネイボッブが生まれたのは主として18世紀中葉から19世紀初頭までの期間である。イギリスによるインド支配は東インド会社主導で進められたが、そもそもイギリス本国政府はもとより、東インド会社の理事会すら支配の拡大を望んではいなかった。19世紀に入ると次第にインド統治機関へと重心を移していく東インド会社であるが、18世紀末以前はあくまで商人の会社としてインドへの関わりを強めていったのである。
- それはムガル帝国の皇帝からベンガル地方の統治権を与えられた後も変わらなかった。後のインド高等文官ICSが「文明化の使命」を前面に押し出した「保護者」を標榜していたのとは対称的に、東インド会社の現地職員たちは個人の利益を最優先にしていた。この頃、東インド会社の職員は会社の業務以外にも個人的な交易が許されていたためでもあり、文官(個人商人でもあった)以外も軍人、軍医、司祭に至るまで、少なくとも1760年代までは会社の許可を受けて交易を行い、少なからぬ利益をあげていた。雇用主でもある東インド会社からの給料も支払われていたため、生き延びて勤め上げれさえすれば、それなりに蓄財は難しくなかった(職員の私貿易が禁止されるのは1787年)。
- これらの収入に加え、1769年以降はイギリス人が収税吏に登用されるようになり、現地社会からの直接的な収奪が可能になった。個人による徴税の代行という手段は近代的な国家制度に反するものであり、ネイボッブが白い目で見られた要因の一つには、こういった本国では有り得ない手段によって不当に財を蓄えたと看做されたことがある。またネイボッブとなった者たちは幼少時より東インド会社での業務に従事していたため、ジェントルマンのように十分な教育を受けていることは少なかった。イギリス的価値観やジェントルマン理念を身につけていなかった彼らはインドでの影響を受けやすく、比較的容易に現地の習慣に染まっていった。この点もイギリス帰国後既存社会に適応できず、排斥された理由の一つである。
*それでもカリブ海の砂糖農園主同様、英国議会において強大な権力を握っていたのだから恨まれるのは当然だったとも。
- インド支配が進み、また風土病への対処法が確立されるにつれ、インドは危険な任地ではなくなっていった。こうなると次第に本国で適当な職を得られなかった富裕層の次男・三男などが本格的に参入するようになる。彼らはイギリスで正規の教育を受け、また卑しからざる生まれでもあったため、インドで蓄財して帰ってもネイボッブと呼ばれることはなかった。またネイボッブと呼ばれた当人たちも、本人が上流階級に受け入れられることはなかったにせよ、子、孫の代になるとパブリック・スクールからオックスブリッジという正規のジェントルマン教育を経ることによって上流階級の一員として受け入れられることは可能であった。
1806年に東インド会社理事会によって「よきイギリス人たる」職員養成を目的とした東インド・カレッジ、通称ヘイリーベリー校が設立される。このことによって東インド会社の文官職は正式に富裕層子弟の受け皿となり、ネイボッブのような階級上昇は完全に不可能となった。
*今日ではnabobという単語はむしろ特定のコーヒー・ブランドのみを想起させる事に。
「風と共に去りぬ(1939年)」のスカーレット・オハラ役と「欲望という名の電車(1951年)」のブランチ・デュボワ役でアカデミー主演女優賞を受賞したヴィヴィアン・リー(Vivien Leigh, Lady Olivier、1913年〜1967年)もこういう出自の一人。クラッシック・ファンは「A Midsummer Night’s Dream(1937)」における妖精の女王役から注目しますが、そのエスニックな容貌も、エキセントリックな振る舞いも一般にその出自に負う部分が大きいとされています。
*イギリス領インド帝国ダージリンのセント・ポール・スクールの寄宿舎において父親の英印軍騎兵隊将校アーネスト・ハートリーと母親のガートルード・メアリ・フランセスとの間に生まれた一人娘。母親のガートルードは敬虔なローマ・カトリック教徒で自らの家系はアイルランドとアルメニアを祖とすると信じていたが、旧姓「ロビンソン・ヤーチ(Robinson Yackje)」のYackje(Yackjeeとも表記)から、インド人との混血である可能性が指摘されており、また、それがリーの東洋的美貌の理由であるとも言われている。同時にアイルランド系なのはラフカディオ・ハーンも同じ。要するに英国植民地運動の最前線には常にアイルランド人がいて現地人との恋がある。
あと決して無関係ではないのがジュール・ヴェルヌ「海底二万里(Vingt mille lieues sous les mers、1870年)」「神秘の島(L'Île mystérieuse、1874年)」に登場する潜水艦ノーチラス号艦長ネモ船長(Captaine Nemo)。その正体は「イギリス人の野蛮な側面」に義憤を燃やして蜂起したインドのバンデルカンド大公の息子にしてティッポー・サヒブの甥に当たるダカール王子という設定で、世界中の無政府主義や民族独立運動の後援者の立場にある彼がしばしば見せる粗暴な振る舞いは概ね「(欧米社会への復讐を誓う)野蛮人だから」の一言で片付けられてしまいます。
*ティッポー・サヒブ…攻守双方ともがロケット兵器を大量投入したマイソール戦争(1767年〜1799年)で有名なマイソール藩国の君主ティプー・スルターンがモデル。独自近代化によって東インド会社によるインド支配最大の障壁として立ち塞がり、以降の独立戦争に精神的支柱を与えたとされている。ちなみに英国はこの戦いを通じてマイソール・ロケットを改良したコングリーヴ・ロケット(Congreve rocket)を完成させ、ナポレオン戦争や米英戦争に投入。米英戦争におけるマクエンリー砦の戦いに題材を採ったアメリカ国歌に登場する「rocket」はこれを指している。アメリカ国旗が東インド会社の社旗そっくりなのと併せ突っ込みどころ満載だったりする。
*ヴェルヌの当初の案では、ネモ船長はその頃ロシア帝国に事実上占領されていたポーランドが独立を目指して蜂起した「一月蜂起(1863年〜1865年)」が失敗した際に、鎮圧によって惨殺された家族の復讐の念に燃えるポーランド貴族という設定であった(作品発表は1870年だが、物語の舞台は1866年時点で、ハーマン・メルヴィルの「白鯨(Moby-Dick; or, The Whale、1851年)」への言及もある。「捕鯨業者に復讐する鯨」というアイディアにインスパイされた結果とも)。しかし、当時フランスは普仏戦争(1870年〜1871年)の最中であり、同盟国のロシアを悪く扱うのは危険であるという編集者側からの勧告により破棄された(また、ロシアはヴェルヌの本を扱っていた出版社にとって重要な市場であり、ロシアを悪く扱う本の売れ行きを心配した出版社の事情があった)。その結果「海底二万里」のストーリーは当初と比べ大幅に変わり、ネモ船長は「神秘の島(1874年)」が発表されるまで謎の人物とされることになったのである(1874年になったらどうでも良くなったのは、ビスマルク包囲網が完成してロシアとの関係ばかりか英国との関係も気にしなくて良くなったからとも)。
19世紀後半にドイツ帝国宰相ビスマルクの築いたヨーロッパの外交関係のこと。この体制の間、フランスは孤立することとなった。ビスマルク外交ともいう。
- 普仏戦争後、プロイセン王国は自国主導でドイツ人地域をまとめあげ、プロイセン王家が帝位に就くドイツ帝国を成立させることに成功した。しかし大国フランスに完勝したとはいえ、多数の領邦国家からなる帝国は不安定であり、プロイセン主導の統一国家が出来上がったばかりのドイツは再び近代戦争を戦える状態ではなかった。また、新興国のドイツ相手に屈辱的な敗北を喫したフランスからの復讐を警戒する必要もあり、こうした状況に応じてとられたのがビスマルク体制である。
- この政策の最大の狙いは、ドイツがヨーロッパ諸国と同盟を結んで良好な関係を築き、外交的にフランスを孤立させることにあった。1873年にオーストリア、ロシアと三帝同盟を結び、1878年のベルリン会議で表面化した墺露の対立で三帝同盟が崩壊すると、1881年、あらたに三帝協商を結んだ。さらに1882年にはオーストリア、イタリア(サルデーニャやシチリアの対岸にあたるチュニジアの、フランスによる保護国化に不満をもっていた)と三国同盟を締結した。三帝協商がまたもや墺露対立により崩壊した1887年には、ドイツ帝国(実質的にはプロイセン王国)単独の対ロシア同盟である独露再保障条約を締結して、ドイツの安全をはかる複雑な同盟網をしいている。これはいずれもフランスの復讐を避けるためであり、とくにドイツ帝国と東西で国境を接する露仏の接近により二正面作戦を強いられるリスクへの対処であった。
- それと同時にビスマルクは、その当時盛んに行われたヨーロッパ列強によるヨーロッパ以外の地域での植民地の拡大には極力消極的な態度をとった。これはフランスのナショナリズムおよび軍事力をヨーロッパの外部への領土拡張に振り向けさせることによって対独復讐に向かわせないためであり、そのためにはドイツはなるべく植民地的利害には関心を持たないポーズを取る必要があった(とはいえ、ビスマルク時代の後半においてはややこの方針は修正され、他の欧州列強と衝突しない程度には東アフリカや西太平洋の島嶼部などに植民地を形成する企てが進められた)。さらに、彼はドイツの地位を安定させるためにヨーロッパの勢力均衡が平和なまま現状維持されることを望み、そのため列強間の利害対立を積極的に調停してドイツの国際的地位を高める「正直な仲買人」としての役割を演じた(1878年と1884年の2回の「ベルリン会議」はその現れであった)。
- ビスマルク体制はビスマルクの卓絶した手腕によって維持され、一時的に外交関係が悪化する状況こそあったが、ビスマルクの在任中はその目的を完全に果たした。19世紀最後の四半期はビスマルク体制の成功により、国際連盟や国際連合のような国際平和組織のない時代にありながら、ほとんどと言ってよいほどヨーロッパには戦火が存在しなかった。
1890年、ビスマルクが辞職し、彼を更迭したヴィルヘルム2世の親政が開始された。他の列強との協調関係よりもドイツの帝国主義的利害を重視する、いわゆる「新航路政策」(世界政策)が本格化するとともにこの体制は解体に向かい、ヴィルヘルムの拙劣な外交政策も相まって列強諸国との対立激化を生むこととなる。その間、フランスは露仏同盟を皮切りに徐々に孤立状態を脱し、ついで外相デルカッセが巧みな外交を通じて三国同盟の無効化(独仏開戦の場合のイタリア中立化協定)や英仏協商の締結を果たし、逆にドイツ包囲網が築かれていった。
*同時期には最晩年のプロスペル・メリメ(Prosper Mérimée)がロマン主義文学へのレクイエムともいうべき「ロキス/熊男(Lokis、1869年)」を上梓している。この作品自体は「偶然、狩猟の最中に森の王を仕留めてしまった領主の息子が変貌を始めた息子を現実世界に止める為に結婚式を急ぐが花嫁を食い殺して消息不明となる」という内容だったが、これにインスパイアされたガイ・エンドア(Guy Endor)の「パリの狼男(The Werewolf of Paris, Farrar & Rinehart版1933年、Pocket Books版1941年)」では大量殺戮が相次いだ普仏戦争とパリ・コミューンの時代を背景に「本能を満たす為、月にたった数人を食い殺すだけの狼男」が暗躍する。その大流行は当初「悪人のみを標的とする吸血鬼」としてスタートしたバットマン(Batman、1939年)の設定に影響を与えたとも。ただし読者側のモラルハザードが深刻なタイミングでしかヒットしない設定なのも事実で、実際、バットマンも「バット・ケイブ(蝙蝠の棲家となっている洞窟)の上に建てられた豪邸に暮らしている」という設定以外はほとんど捨て去ってしまった。むしろ当時の設定は「悪党を捕食する悪党」として生きる道を選んだヴィラン側のジョーカーが継承したとも。
最も興味深いのはコナン・ドイル「シャーロック・ホームズ(Sherlock Holmes)シリーズ(1887年〜1927年)」における「植民地人」の扱いだったりします。
- 英国本土でしっかり相応の教育を受けた人物は、たとえ非白人であってもジェントルマンとして描かれる。
- 「植民地の野蛮な悪癖」に染まった人間は、例え白人でも野蛮人として描かれる。ただしそういう白人は英国本土で凶悪犯罪を犯しても、大抵は本国送還されるだけ。
フランス絶対王政期の文学においては(フランスの重要な交易相手となった)オスマン帝国が(野蛮な状態に留まる他のイスラム諸国と異なり)文明国として賞揚されました。当時の英国文学において「英国ジェントルマン文化を受容したインド人やアジア人」が賞揚された事にも、同種の政治的配慮を感じます。その分だけ風当たりが強くなったのが1860年代より形振り構わない形で拡張を続けてきた南アフリカ植民地でした。おそらくホブスン「帝国主義論(Imperialism: A Study、1902年)」が弾劾したのが「南アフリカ植民地の現地有力者と癒着した本国政治家」であったのも決っして偶然ではないのです。
*カリブ海の砂糖農園主、インドのネイボッブ、そして南アフリカの現地有力者。考えてみればその全てが有り余る財力を武器に本国議会に大量議席を獲得して大英帝国を牛耳ろうとしてきた訳であり、その意味で本国のジェントルマン階層や産業資本家階層と対立してきた訳である。
南アフリカ戦争/ボーア戦争/ブール戦争
南アフリカの特殊性、それは植民地政策の都合上同じ白人(現地に植民したオランダ系移民=アフリカーナ)をも「劣等民族」として扱わねばならない点にありました。しかし矛盾もここまで鬱積すると文学に画期を与えたりするので油断なりません。そして産業革命のもたらした大量生産が庶民の大量消費に支えられる時代に入って以降、フィクション世界における流行は、流石に現実世界にまでは直接の影響を与えないものの、時代的雰囲気の変遷には確実に一助を為す様になったからである。
*ここでモード(Mode)とムード(Mood)の違いというややこしい問題が浮上してくる。モードには楽典の如き厳格な形式上の遷移ルールを駆使して時代を主導しようとするが、ムードはあえてその拘束外において勝手に物事を進めようとする。両者の利害は必ずしも不一致とは限らないのだが、そこに数々の齟齬が生まれる。
そもそも「夷狄を待ちながら(Waiting for the Barbarians、1980年)」のJ・M・クッツェー(1940年〜)が「南アフリカを代表する文学者」として2003年ノーベル文学賞を授賞したのは60年代ベトナム反戦運動で検挙され二度と英国本土へのVISAが降りなかったからだった。そして、そこで受賞理由に挙げられた「数々の装いを凝らし、アウトサイダーが巻き込まれていくところを意表を突くかたちで描いた。その小説は、緻密な構成と含みのある対話、すばらしい分析を特徴としている。しかし同時に、周到な懐疑心をもって、西欧文明のもつ残酷な合理性と見せかけの道徳性を容赦なく批判した」といった特徴は、そのまま3歳でオレンジ自由国からバーミンガムへ移住した「英国人作家」J・R・R・トールキン(1892年〜1973年)や18歳でバンクーバーに移住した「カナダ人映画監督」ニール・ブロムカンプ(1979年〜)の作品の世界観にも当てはまる。要するにカミュがアルジェリア人でもフランス人でもなく両者の狭間を生きたアウトサイダー(Out Sider)だった様に「南アフリカ文学」もまた単なる南アフリカ人でも英国人でもない両者の狭間を生きる人々によって紡がれてきたという事になるのだろう。
ならば指輪戦争に登場する「(復活すれば全てを従える)一つの指輪(the One Ring)」とは何なのか。「夷狄を待ちながら(1980年)」に登場する「崩壊していく帝国」とは何なのか。「第9地区(District 9、2009年)」や「チャッピー(Chappie 、2015年)」といったブロムカンプ監督映画でそれに該当するのは何なのか。
ちなみにブロムカンプ監督の時代に至る途上では南アフリカ社会も大いなる変遷を経ている。アパルトヘイト廃絶(1994年4月)によってようやく農本主義的社会構造の解体が始まり、首都ヨハネスブルグが貧富の差の著しい魔都へと変貌。その展開はおそらく南北戦争(1861年〜1865年)後のアメリカが金鍍金時代(Gilded Age)に突入し1890年代に最初の恐慌を経験するまで「摩天楼」ニューヨークが歪な繁栄を続けた状況に対応する。まさしくリヒャルト・ワーグナーが「ニーベルングの指環」4部作序夜「ラインの黄金(Das Rheingold、1854年作曲、1869年初演)」で描いた「黄金(指輪)の力でニーベルング族を従えるアルベリヒの世界」そのもの。実際ワーグナーも1877年にロンドンを訪問した際に「ここはアルベリヒの夢が現実になっている。霧の都(ニーベルハイム、ニーベルング族の居所)、世界支配、労働と勤勉、いたるところ重くたれ込めたスモッグ」と感想をもらしたとされるし、その孫でニーベルハイムを工場に見立てた演出で知られるヴィーラント・ワーグナーも「ヴァルハルの城は、ウォール街だ」と発言している。それまで「視野外の周縁部から迫り来る脅威」を告発してきた南アフリカ文学は、ついにその少なくとも一部を「自分と不可分な内面」として内在化する事を余儀なくされたのだった。
*要するに「産業革命以降の世界にようこそ」という話とも。そういえばイタリア王国(1861年〜1946年)やドイツ帝国(1871年〜1918年)の独立によって「神聖ローマ帝国的領邦国家制(農本主義)最期の残滓」として取り残されたオーストリア=ハンガリー二重帝国の首都ウィーンの発展もまた歪であり、フリッツ・ラング監督はその矛盾を徹底追求する立場から「メトロポリス(Metropolis、1926年〜1927年)を撮影したという。日本でも手塚治虫「メトロポリス(1949年)」が直接そのスタンスの影響を受けたが、荒俣宏が「帝都物語(1985年〜)」で活写した「京都への対抗者として台頭した東京の歴史的特異性」はむしろ「アメリカにおける東海岸文化への対抗者として台頭した西海岸文化」と重なる。フリッツ・ラング監督もアメリカに移住して以降はハードボイルド文化の影響色濃いフィルム・ノワールの作家へと変貌していった。どうやらこの辺りに「南アフリカ文学」と「アメリカ文学」の微妙な境界領域が存在しそうな感じだが、この段階ではまだまだ「汚れ切った街を最期の紳士が征く」高潔感が漂う。英国人漫画原作者アラン・ムーアの手になる「ウオッチメン(Watch Men、原作1986年〜1987年、映画化2009年)」に登場する「私立探偵」ロールシャッハは、どちらかというとハドリー・チェイス流英国ハードボイルドの継承者だが、そこまで崩れてもまだまだある種の精神超人性は留めている。もしかしたら「アメリカ文学」におけるこの要素こそが「南アフリカ文学」における「(既に崩壊し過去の思い出へと変わろうとしているが)復活すれば全てを従える/破壊する力への恐怖」と表裏一体の関係にあるのかもしれない。
ファンタジー好きの人間なら「ホビットの冒険(The Hobbit, or There and Back Again、1937年)」「指輪物語(The Lord of the Rings、執筆1937年〜1949年、初版1954年〜1955年)」で知られるトールキンの名前が登場した時点で戦慄すべきです。源流中の源流を抑えられた様なものですから。
- エルフ(elf, 複数形elfs, elves)…北欧神話などでは「闇の妖精」としてのドワーフ(dwarf、複数形dwarfs, dwarves)と対になる「光の妖精」というニュアンスしか存在しなかったが、トールキンの神話体系によって大幅に拡張。最も優れた集団たる「ハイエルフ」は世界で最も高貴だが、山エルフや川エルフや海エルフといった野蛮で知能も低い下位種族も存在する。自らに絶対忠誠を誓う軍団を必要とした初代冥王モルゴスの手によってエルフが堕落した姿がオーク(Ork)で、ホビット語ではこれをゴブリン(goblin)と呼ぶが、オーガの如き愚鈍な食人鬼的存在はどちら側にも存在し、違いは「主人持ち」かそうでないかだけ。元来の伝承に従ってドワーフを天敵とするが、ドワーフはさらに堕落させられ、「主人持ち」となる事で「闇のドワーフ(Dark dwarf)」に転落する。
- オーガ(英: ogre)あるいはオグル(仏: ogre)、女性はオーグリス(英: ogress)またはオグレス(仏: ogresse)…「騙されやすい間抜けな食人鬼」の事。元来国際的に通用する明確な呼称などなかったが、シャルル・ペロー「寓意のある昔話、またはコント集~がちょうおばさんの話(Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités : Contes de ma mère l'Oye、1697年)」に収録された「長靴をはいた猫」の中で使用されたこの呼称が広まった。スカンジナビア半島の国々ではトロールと関連付けられ、山の中に建てられた城の主人であり莫大な財宝をもっていると考えられる様に。またアルフレッド大王時代のアングロサクソン民話から採択されたとされる「ジャックと豆の木(Jack and the Beanstalk)」にもやられ役として登場する。
- トロール(Troll)…トールキンの神話体系では初代冥王モルゴスの被造物とされる。強力だが、所詮は「木の巨人」エント族を模造した「岩の巨人」に過ぎず、太陽光を浴びると石化してしまう。次代冥王サウロンは、その上位種たるオログ=ハイ(Olog-hai)を生み出した。太陽光に強く、知能も高く鎧を着込んだり大盾を構えたりする。
欧州のファンタジーファンは「指輪物語」に登場する各種族について「人間=アメリカ人」「エント族=フランス人」「エルフ・オーク・ゴブリン=アングロサクソン系およびザクセン系・スコットランドおよびアイルランド系・ウェールズおよびブルターニュ系」みたいな分類をしています。ドワーフはどの国にも該当する概念が存在するのでどうでも良い模様。その一方で「ハイエルフ(ジェントリー階層)に分類されるのは正しく育てられた全体のごく一部。間違って育てられるとオーク=ゴブリンにまで堕ちる」という仕切り方が逆に英国的傲慢さを体現している様に見えたりもする様で。
そもそもトールキンの描く「悪の軍団大襲来」の元イメージは古英文学者として手掛けた英語叙事詩「モールドンの戦い(10世紀末〜11世紀成立)」だったとされています。実際のモールドンの戦い(The battle of Maldon、991年)で「大襲来」したのはヴァイキング(北欧諸族の略奪遠征)ではなく、デンマーク王スヴェン双叉髭王とノルウェー王オーラヴル・トリュグヴァソンの連合軍で、イングランド側守将のエセックス代官(エアドルマン=国王の直轄領を預かる太守)ブリトノートが戦死。「王の直臣」が戦死したのは初めてだったのでイングランド年代記でも大きく扱われ、英語叙事詩「モールドンの戦い」の様な「ブリトノートの犠牲を讃える讃歌」が残される事になった訳ですが、トールキンがその続編として執筆した当代英語叙事詩「ベオルフトヘルムの息子ベオルフトノスの帰還」の中では(当初は彼ら自身も「ブリテン島への侵略者」に過ぎなかった)アングロ=サクソン系諸侯の子弟が「イーリヤス」や「テーバイ攻めの七将」や「ベオウルフ」と言った武勇伝を挙げてその「偉業」を礼賛する一方、同行するイングランド人農夫(かつてアングロ=サクソン系諸侯に屈服し、今やデーン人への鞍替えを考え始めた先住民達を代表する立場)は「戦争など腹が減るばかりだ」とぼやくのみ。ここにおいて既に(ホビット族を主役とする一方で統治機構として官僚制はおろか封建制度すら登場しない)トールキン的世界の基本構造が見て取れるという訳です。こうした既存秩序を根底から疑ってかかる斜に構えたスタンスはクッツェーやブロムカンプにも見て取れる為、南アフリカ出身作家の共通点とも。
またトールキンの場合、さらに自らも従軍した第一次世界大戦において友人知人を大量に亡くした経験をそうした作風の起源に見て取る向きもあります。そういう意味ではこれもまた「総力戦時代」以降にしか登場し得なかった作品と言えるかも。
さて私達はどちらに向けて漂流してるんでしょうか?