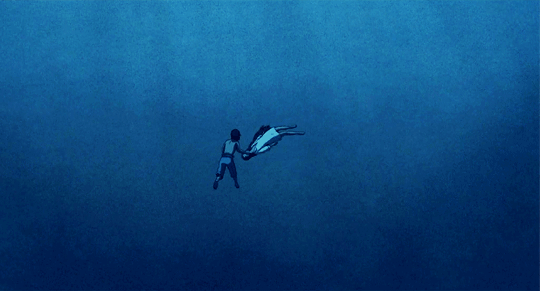「マリアージュ -神の雫・最終章-」に「ローザンヌ国際バレエコンクール」の話が出てきました。その本拠地はフランスと思わせておいてスイス…
ローザンヌ国際バレエコンクール (仏: Prix de Lausanne)
スイスのローザンヌで毎年行われる、15歳から18歳までのバレエダンサーを対象としたコンクール。スイスの非営利法人である舞踊振興財団(Fondation en faveur de l'Art chorégraphique)によって1973年から開催されている。ヴァルナやモスクワなどの旧来のバレエコンクールとは異なり、若手ダンサーにキャリア形成につながる道筋を開くことを目的に掲げている。
- すでにプロとしての活動実績がある者や入団が決まっている者は参加資格がない。
- 結果のみで審査する旧来のコンクールとは異なり、参加者にクラスを受講させ、それ自体も審査対象としている。このクラス審査による評価は準決戦までの各参加者の評価点の半分を占める。決戦も含め、審査では「プロのバレエダンサーとして成功する能力があるか」に重きが置かれている。
- 賞を授与するだけのコンクールとならないように、様々な工夫がなされてきた。現在では参加者全員に対して、選択したヴァリエーションごとに著名ダンサーによる個別の指導が行われている。入賞に至らなかった参加者に対しては、提携バレエ学校およびバレエ団と留学の相談ができる機会が設けられている。
- 世界の著名なバレエ学校33校およびバレエ団32組織と提携しており、主たる賞であるローザンヌ賞でこれらに無償で留学・研修することのできる権利を生活支援金とともに授与している。
こうした内容から歴代の受賞者の多くがプロとして活躍する様になり、若手バレエダンサーの登竜門の一つと考えられる様になった。
- スイスの実業家フィリップ・ブランシュワイグは、妻エルヴィ・クレミスがバレエダンサーだったことからモーリス・ベジャールやロゼラ・ハイタワーと長年親交があり、ベジャールの20世紀バレエ団の公演をラ・ショー=ド=フォンで実現するなど興行師としての実績があった。
- 1969年、ローザンヌにおける舞踊公演の促進を目的とする舞踊振興財団が設立されると、設立に関与したG・クライネルトはブランシュワイグにも参加を求めた。
- 1970年に同財団の理事となったブランシュワイグは、舞踊の世界では個々のダンサーが声楽家など他の領域の芸術家に比べて経済的に不利な立場に立たされている実情を知っていたため、ダンサーを支援する最善の方法を求めて、1972年初頭から知己のベジャールとハイタワーに相談。その結果、若手ダンサーに世界的に知名度のあるバレエ学校で学ぶ権利を賞として授与するコンクールをローザンヌで創設することを決意した。
- レッスン審査を含む予選と、準決戦・決戦の合計3段階で絞り込む選考方法はブランシュワイグ夫妻がハイタワーと相談して決定した。さらに入賞者の留学の受け入れ先として、当時ブリュッセルにあったベジャールのムードラ・バレエ学校、カンヌのハイタワーの学校、さらにロンドンのロイヤル・バレエ学校の3校に協力を求めて賛同を得た。
- 第1回のコンクールは1973年1月19-21日にローザンヌ市立劇場で実施された。当時の参加年齢は15-19歳で、参加者はクラシック・ヴァリエーションと、コンクール用に新たに振付けたフリー・ヴァリエーションを1曲ずつ準備して参加するというものだった。
- 第3回(1975年)からは実施会場がローザンヌのボーリュ劇場となり、提携校も次第に増やされていった。その後コンクールとしての国際的な知名度を高めるため、例外的に1985年にはニューヨーク、1989年は東京、1995年はモスクワで決選が開催された。
日本では1980年から2005年まで、舞踊振興財団の支部にあたる日本事務局が東京に置かれ、山田博子が代表となって参加希望者の問い合わせに応じるなどの支援にあたった。以来日本からは継続的に参加者が出ており、現在までほぼ毎年の受賞者を出している。これまでに吉田都、熊川哲也、上野水香、中村祥子ら70名以上が受賞した。また、日本国籍を保持していながら、多重国籍で他国から出場し優勝、入賞した者として、オニール八菜(ニュージーランド)、ミコ・フォガティ(スイス)などがいる。なお1989年の東京開催では、準決戦と決戦を日本で行うことによる費用として約6,000万円がかかり、富士通や日本児童手当協会、文化庁、NHKなどがこの一部を負担。
この話、以前悩んだ「バンド・デシネ(bande dessinée)はどこまでフランス作品?」という問題と絡んできそうです。
割と簡単な目安が見つかりました。 「その国の高校生がどれくらいフランス語を履修しているか?」。フランスとスイスとベルギーの「近さ」が改めて浮き彫りに。
欧州各国にて高校でフランス語を履修している生徒の割合
— Spica (@Kelangdbn) 2017年2月6日
スペイン人やイタリア人はちょっと勉強すればものにできるんだからもう少しやる気だしなよ pic.twitter.com/bJvPH2DgiH
今やロシアは完全圏外ですが、そういえばプーシキン(Александр Сергеевич Пушкин、1799年〜1837年)や、ドストエフスキー(1821年〜1881年)や、トルストイ(1828年〜1910年)や、ゴーリキー(1868年〜1936年)といった文豪の作品が次々と欧米に紹介され、バレエ・リュス(Ballets Russes、1909年〜1929年)がパリ進出を果たした時期のロシアもまたフランス語漬けの状態にあったのです。スペクタクル史劇の題材に選ばれたのも、この時期の作品が中心。数少ない例外は「ドクトル・ジバゴ(Doctor Zhivago、1957年、映画化1965年)」くらい?
「ドクトル・ジバゴ(Доктор Живаго, 英語: Doctor Zhivago、1957年、映画化1965年)」
ソ連の作家ボリス・パステルナークの小説。ロシア革命の混乱に翻弄される、主人公で医師のユーリー・ジバゴと恋人ララの運命を描いた大河小説。
- ロシア革命を批判する作品であると考えられたために本国ソ連での発表はできず、イタリアで刊行され、世界的に知られることになった。
- 翌年にはノーベル文学賞がパステルナークに授与されることになったが、ソ連共産党が辞退を強制した。受賞すれば亡命を余儀なくされると考えたパステルナークは「母国を去ることは、死に等しい」と言い受賞を辞退。
- ソ連の共産党は「(『ドクトル・ジバゴ』は)革命が人類の進歩と幸福に必ずしも寄与しないことを証明しようとした無謀な試みである」と非難。当時「社会主義革命の輸出」をしていたソ連政府にとっては「ロシア革命は人類史の大きな進歩である」という見解に疑問符をつけることは許しがたいことだったのである。
- ただし、ノーベル委員会はこの辞退を認めず、一方的に賞を贈った。このため、パステルナークは辞退扱いにはなっておらず、公式に受賞者として扱われている。
こういう事情に振り回され、日本語訳の経緯も複雑な事に。
①最初の日本語訳は1959(昭和34)年に原子林二郎訳によって出版された。
- 前年(1958年)のパステルナークのノーベル文学賞受賞辞退の一件で話題の書となったため急遽翻訳が企画された模様である。そのためロシア文学関係者ではないものの時事通信社の業務でロシア語に接していた原子林二郎(時事通信社記者)が翻訳にあたった。
- 原典であるロシア語版の入手が困難なため底本とすることができず、上巻は最初に出版されたイタリア語訳版と英訳版を相互に参照しながらの重訳であった。上巻の翻訳がほぼ完了した時点でミシガン大学出版局から出版されたロシア語版の入手がなり、後からロシア語原典と付き合わせて邦訳文を照合するという慌ただしさだった(原子訳・上巻「あとがき」による)。下巻は、ロシア語原典を底本にして、イタリア語訳版と英訳版を参照しながら邦訳が進められた。但し、ユーリー・ジバゴの詩の邦訳については原子は固辞して専門家に担当して貰っている。
- 原子は重要な文学作品の邦訳を、社命とはいえロシア文学の専門家ではない者が行うことに強い抵抗感を示しており、遠くない将来にロシア文学の専門家の手による邦訳版の出版が望まれる旨を述べている(原子訳・下巻「あとがき」による)。
②21年後の1980(昭和55)江川卓による翻訳が出た。
③2013年工藤正廣による新訳が未知谷から『ドクトル・ジヴァゴ』として刊行された。
そういえば、ウラジーミル・ナボコフの「ロリータ(Лолита - Lolita、1955年)」もまた、最初はフランスで出版されているのですね。
ロシア生まれのアメリカ合衆国の作家、ウラジーミル・ナボコフ(Vladimir Vladimirovich Nabokov、1899年〜1977年)の小説。1955年刊。少女性愛者ハンバート・ハンバートと、彼が心惹かれた少女ドロレス・ヘイズとの関係を描いた長編で、全体はハンバートの手記の形を取っている。
- ナボコフはロシア帝国のサンクトペテルブルクで貴族の家に長男として生まれた。50人の使用人に囲まれ、非常に裕福な環境で育った。ロシア革命後、1919年に西欧に亡命。同年、トリニティ・カレッジ (ケンブリッジ大学)に入学、動物学やフランス語を専攻し、サッカーチームのゴールキーパーも務めた。
- 1922年に大学卒業後、ロシア移民が多く住むベルリンに落ち着いていた家族と合流。同年、父親が暗殺される。文筆や教師などの仕事を始め、1925年に、同じくベルリンに亡命していたユダヤ系ロシア人のヴェラと結婚、1934年には息子ドミトリをもうけた。パリの生活を経て1940年に渡米、1945年にアメリカに帰化した。
- 渡米すると教職のかたわら、この作品を1948年から書き始め、1953年には完成したが、性的に倒錯した主題を扱っているため、アメリカでは5つの出版社から刊行を断られた。
- ナボコフの代理人はさまざまな出版社に足を運び本を読んでもらい、各出版社の編集者は作品のテーマを見抜いてはいたようだが、そのあまりに難解な内容からか、これは読者には「ポルノ」にしかみえないという理由で出版を拒まれる。結果、初版はポルノグラフィの出版社として有名なパリのオランピア・プレスから1955年に出版された。
- しかしグレアム・グリーンらの紹介により読書界の注目の的となる。アメリカでは1958年に出版されベストセラーになった。イギリスでは、作家らが刊行を促す署名運動を起こし、1959年に出版された。
- これまでに何度か発禁処分を受けており、ニコラス・キャロライズなどが編集した「百禁書―聖書からロリータ、ライ麦畑でつかまえてまで」ではロリータに対する批判や発禁処分になった経緯などが書かれている。また、ナボコフ自身による評論「『ロリータ』 について」があり、この作品の本質を見てもらいたいというナボコフの考えや、作品の性的な部分についての自身の考えが書かれている。
- 1962年にスタンリー・キューブリック監督が映画化した際は舞台を制作当時の1960年代に移した。さらにアメリカが舞台としつつ、当時のアメリカの厳格な検閲を避ける為にイギリス人中心のキャスティングが行われ、ほとんどがイギリスで撮影されイギリス映画として配給されている。それでもキューブリックは後に「(未婚の男女が同じ平面上で横たわらない、といったハリウッドの自主規制コードやカトリック団体からの抗議により)主人公たちの関係のエロティックな面を強調できなかった」と述懐している。
*「太陽族映画(1955年〜1956年)」が国際的に衝撃を与えたのは、こうしたルールを一切守らなかったからでもあるらしい。そういえば黒澤明監督映画は割と律儀に「未婚の男女が同じ平面上で横たわらない」コードを守っていたりする?
- ヒロインの愛称である「ロリータ」は今日でも魅惑的な少女の代名詞として使われており、ロリータ・コンプレックス、ロリータ・ファッションなど多くの派生語を生んでいる。
現在ではアメリカ文学の古典として認知されている。アメリカの学校の教材に使われることすらあるが、それはこの作品の後半がロード・ムービー的展開となり、まさにその部分が「アメリカ文学的」と受容された結果とも。
ナボコフの影響はジョン・アップダイク「A&P(1962年)」も若干継承してるらしく作中に「ストークシーはいつか店長になるつもりらしい。たぶん1990年代、A&Pがグレート・アレキサンドルフ・アンド・ペトルーシュキ・ティー・カンパニーとでも呼ばれるようになるころに」なんて気の利いた台詞が出てきます。
新潮文庫の『自選短編集』には、アップダイク自身の手による前書き、「日本の読者に」という作品紹介が掲載されているのだが、そこには「これを書いた当時、この短編は少しJ.D.サリンジャー風すぎる、とわたしの妻が言っていた」とある。
余談だけれど、ナボコフの『ヨーロッパ文学講義』の序文はアップダイクが書いていて、奥さんがコーネル大学でナボコフの講義を受けたことが記してある。ナボコフの薫陶を受けたこの奥さん、さぞかし厳しい読み手だったにちがいない。たぶん同じ奥さんだと思うんだけど。
ナボコフが講義のなかで「アンナ・カレーニン」に出てくるキャシーのドレスや「ボヴァリー夫人」の帽子のデッサンをやったように、女の子たちの水着を、イメージしてみてほしい。ほんとうに筋を追いかけて読むだけではもったいない、ある種、とてもぜいたくな「ことばの悦楽」といったものがアップダイクの小説のなかにはある。
女の子の水着の描写から、日焼けしていないところ、はたまた一風変わった女の子の歩き方、カーラーを巻いたお客の反応から、中年女性の静脈瘤、わたしたちはまるでアップダイクによく見える目を与えてもらったかのように、世界のありとあらゆる「細部」を見ることになる。
そしてそうした細部は、単に精緻に描かれるだけではない。「神は細部に宿る」ということばそのままに、女の子の歩き方をとおして、その子の境遇や性格までもが浮かび上がってくる。アップダイクの切り取る瞬間には、そこに登場人物たちのすべてが凝縮されているのである。そして重ねられていくことばは、視覚的な喚起力に満ちている。
いつの間にかアメリカ文学の話に…この辺りは割とハードボイルド文化の伝統にスムーズに接ぎ穂されてきた感がありますね。
一方、ロシア本土が文化圏から脱落して以降のフランスは…
そもそも国際的に「フランス的デカダン」とイメージされてるものが全然フランス起源じゃないし、今も残ってるかすら怪しいからややこしい…
フランスのル・モンド誌は、同国のコミック市場について、パロディーやラブコメディーは2006~2007年ごろから販売に苦戦し始め、ギャグ漫画も1万部を超えたのは2タイトルだけだったと報じている。近年マンネリ化してきたランキングリストを打ち破ったワンパンマンは、業界をけん引する存在だと期待されている。
現在、日本の漫画を扱うフランスの出版社でトップに君臨するのは「ワンピース」や「ブリーチ」「ドラゴンボール」などを扱うグレナ。2番手が「フェアリーテイル」「進撃の巨人」の版元であるピカ。3番手は「ナルト」の版元、カナ。続いて「聲の形」「有害都市」を出版するキューン。クロカワは5番手だ。
クロカワのライバル社として比較されがちなキューンのディレクター、アハメド・アニェ氏はあるインタビューで「ワンパンマンの売上はスピーディーで、すさまじいもの」としながらも「この勢いは続かないのでは」と危惧(きぐ)し、キューンが出版する「僕のヒーローアカデミア」はワンパンマンのような前評判はなかったものの、さらに勢いのある作品になるかもしれないと語っている。
日本語が流ちょうで、オリジナル版を読みたがる客が多く集まることでも知られるジュンク堂パリ支店。九喜正彦支店長はワンパンマンについて、「オリジナル版と翻訳版の売上はほぼ同等」と話し、原作で読みたがるコアなファンも翻訳版を欲している層も相当数に上ることがうかがえる。
九喜氏は同作について「フランスは文化が違いますから、シンプルで分かりやすいスト―リーが受けます。あまりに日常的なもの、例えば仕事がテーマだとその時点でだめ。働き方の概念がまるで違いますから。主人公がプライベートを犠牲にして仕事をがんばっても共感できない。だからこそ『ワンピース』のような冒険ものは人気があるし、ファンタジーの要素もありシンプルなストーリーであるワンパンマンのようなギャグ漫画も受けたのではないでしょうか」と分析する。
やはり、この観点から見てもオランダ出身で英国を活動拠点とするマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督は(スイスのデザイン学校で学んでその画風の影響を色濃く受けているとはいえ)バンド・デシネ作家とは言い難く「レッドタートル ある島の物語(英題The Red Turtle、仏題La Tortue rouge)」も、フランスにおける興行失敗を最初から宿命づけられていた様に思えてなりません。なにしろ日本の作品すらこういう基準で選ばれるお国柄…
実際、ネット上では同時期「百獣の王(GiedRé - LES ROIS DES ANIMAUX)」の方が受けてたみたいだし。
そういえば永井豪の「デビルマン(1972年〜1973年)」や「UFOロボ グレンダイザー(1975年〜1977年)」が大好きで「戦場のメリークリスマス(Merry Christmas, Mr. Lawrence、1983年)」より「楢山節考(1983年)」を選んだ国でもありました。結構、外連味が命?