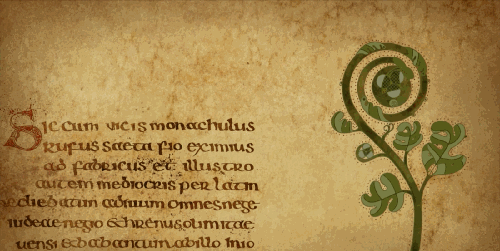こうして「事象の地平線としての絶対他者」について言及するうちに宗教との関係性について言及せざるを得なくなってきました。
まぁ実際「フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France、1790年)を著わしたエドマンド・バークの様に「全ての宗教的感情はこれ(彼の表現では「(美と崇高の概念の源たる)ピクチャレスク(Picturesque)なるもの」)との邂逅を経て芽生える」と断言した人もいて、避けては通れない話題だったりもするのです。
*こうして全体像を俯瞰してみると、こうした大陸哲学の系譜では決して具体的な個人名が挙がらない英国哲学の伝統の源流性がはからずしも浮かび上がってくる。
なるほど「悲劇は登場人物たちが最初からそのような運命を背負っていることを我々が映画の始まる以前から知っている、という点にある」ですか…「アラビアのロレンス(Lawrence of Arabia、1962年)」や「戦場にかける橋(The Bridge on The River Kwai、1957年)」や「太陽の帝国(Empire of the Sun、原作1984年、映画化1987年)」の映画評であってもおかしくないくらい冷徹な俯瞰視点。
これまでの投稿において「(原始仏教における)縁起の世界=(華厳経における)海印三昧の世界」をフェニックス・ガタリいうところの「機械状(Machineque)空間」やオブジェクト指向並列処理言語における「メモリ空間を満たす(同期状況とそれが与える影響も含めた内容の一切がカプセル化によって相互に隠され合った)インスタンス・オブジェクト集合」と等価の内容として扱ってきました。
- ここで対比されているのはスコラ哲学やデカルトやマルブランシュが言い広めてきた「因果論的=機械論的(Mechanique)空間」で、その大源流はイベリア半島経由で欧州に伝わったアラビア哲学にまで遡る。「人間世界における因果関係は全て神を起点に生じる」「神の英知自体は無謬だが、かかる因果律を通じての伝播過程において次第に誤謬が累積し、最後には完全に間違った悪まで生じる」としたペルシャ系法学者/スーフィー(イスラム神秘主義者)のガザーリー( ابو حامد محمد ابن محمد الطوسي الشافعي الغزالي、1058年〜1111年)が提唱した流出論が根底にあるので、コンピュータ工学的には「逐次型プログラミング」に分類される。
*「逐次型プログラミング」…ガザーリーはアリストテレス的世界観を継承し「働きかけるもの(コンピュータ言語=信者の祈り)」が「働きかけられるもの(CPU=唯一神たるアッラー)」を介して「世界そのもの(周辺機器や通信インターフェースの向こう側)」に影響を与えるアーキテクチャーを採用。この辺りは密教(仏教的神秘主義)もスコラ学(キリスト教的神秘主義)もそう大差ない。逆を言えば「メモリを満たすインスタンス・オブジェクト」に該当する「海印三昧の境地」の概念を有するのは「(古代より「梵我一如」理念の研鑽に励んできたウシャニパッド哲学の成果を総動員した側面も有する)華厳経」くらいだし、真言宗始祖の空海から「完成予想図として美しいが、これは動かない」と断言されていたりする。ましてや「オブジェクト指向記法」や「非同期処理」といったコンピューター工学の成果の宗教概念へのフィードバックはまだ行われていない(そもそも科学的マルクス主義ですら「我々のイデオロギーは一切の誤謬を含まないので、末端からの入力によってその振る舞いを変える事など有り得ない」としフィードバック概念の採用を見送っており、そもそも採用の見込み自体が皆無とも)。
*ちなみに「逐次型プログラミング的概念」はカバラー(ユダヤ教的神秘主義、12世紀頃)やゴーレム伝承に先駆ける形でシュメール文学を代表するギルガメッシュ叙事詩(紀元前3000年頃)に登場する。「神の粘土板への記述が生んだ最強の野人」エンキドゥ(Enkidu)。「暴君」ギルガメッシュ打倒の為に遣わされたが、神殿娼婦シャムハトに「人間性」を追記されると同時に「最強の存在ではない」と書き換えられてしまう。以降は(同じく「人間性」を追記されて「名君」に変貌した)ギルガメッシュの冒険に同行する相棒となったが、ギルガメッシュと一緒に神に逆らった折に「死」を追記されてあえなく死亡。思いっきりメタ…ちなみにFateでは「神殿娼婦シャムハトの設定を完全模倣したが、男でも女でもないという基本設定までは変えられなかった」とされ国際的にシリーズ屈指の人気キャラの一人となっている。

- こちらの系譜の思考様式の到達点の一つが理神論(deism)で、一般に創造者としての神は認めるが、神を人格的存在とは認めず啓示を否定する。「神の活動性は宇宙の創造に限られ、それ以後の宇宙は自己発展してきた」とし、奇跡・予言などによる神の介入はあり得ないとして排斥する。オブジェクト志向並列処理言語でいうと「メモリ空間を満たすインスタンス・オブジェクトの呼び出し元を辿っていくと必ずメインループに到達するが、それ自体はプログラムそのものの起動と終了を司るに過ぎない」状態を指す。
*そう、コンピューター自体は西洋の発明品だからその思考様式の延長線上において実現されているのである。逆を言えば「OSの概念」そのものが唯一神信仰的であるとも。
イベントループ (event loop)、メッセージディスパッチャ (message dispatcher)、メッセージループ (message loop)、メッセージポンプ (message pump)、ランループ (run loop) - Wikipedia
*一般に18世紀イギリスで始まり、フランス・ドイツの啓蒙思想家に受け継がれたとされるが、本格化した背景に「リスボン大地震(1755年)の無禍」があり、これを神の所業の一つとして数えられなかった事が挙げられる。
*反動として理性崇拝への傾倒を引き起こしたが、1970年代までに「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマが強く意識される様になって、以降振り出しに戻る。
- ところで華厳経における宇宙神「毘盧遮那仏」はあくまで地球儀の如き「宇宙の真理の全体像の概念化」に過ぎず、何人たりとも働きかけの対象として選べない。それで(龍樹「中論(3世紀)」における「正しい観相に立脚すれば呪術も機能する」なる章句のHackに由来する)密教は「大日如来」なる新インターフェースを開発し、これを宇宙全体に重ねるHackを遂行。日本仏教史上はさらに華厳教学側が「毘盧遮那仏と大日如来の存在は重なり得る(理智不二の法身)」と宣言する歩み寄りを見せるという展開を見せている。
*ガザーリーもスーフィー(イスラム神秘主義者)の立場上「人の手は神に届く」としたが、そのままでは「アッラーの不可視性」を重視するイスラム教学と矛盾してしまうので「まずアッラーとの完全合一ありき」「すなわち人が神に触れているのではなく、神が人の手を借りて自らに触れているに過ぎないのである」とした。まるでヘーゲル哲学の様な解決方法…
-
そして「事象の地平線としての絶対他者」概念との関連が最も取り沙汰されるのが「世俗諦(常人の認識範囲内)と第一義諦(覚醒者(ブッダ)のみが知覚可能な宇宙の真理)を峻別する」龍樹の二諦論や、「物(独Ding、英Thing、人間の認識範囲内)と物自体(独Ding an sich、英Thing-in-itself、人間の認識範囲外に広がる真理の世界)を峻別する」カントのドイツ観念論の世界。
*後者における「物自体」は多くの場合、ギリシア語の「ヌース」(nous, 精神)に由来する「ヌーメノン」(noumenon, 考えられたもの)と同一視され、これが数学的アルゴリズムにのみ寄るとしたデカルトに対して、カントはそれ以外の形而上学も考慮に値するとして、上部座仏教界における説一切有論の主張の集大成たる「倶舎論」や、その大乗仏教への取り込みを目論んだ唯識派(日本ではその論を法相宗が継承)に道を開いたとされる。*またヘーゲルも、これに付け込む形で「人間の幸福とは民族精神(Volksgeist)ないしは、時代精神(Zeitgeist)との合一化を完全に果たし、果たすべき使命を与えられる事である」とする独自哲学を完成させたが、この思考様式はドイツにおいて実践される事はなく、むしろアメリカにおいて開拓者精神、戦前日本において華厳経学と重ねられる展開を迎えている。
*ちなみにカントのそれはリスボン大地震(1755年11月1日)にインスパイアされたエドマンド・バーク「崇高と美の観念の起源(1757)」を出発点としている。人間は大災害に直面する都度「日常の裂け目=事象の地平線としての絶対他者」を改めて意識させられるものらしい。
*また、デカルトの「数学的アルゴリズムのみ」の立場については「近代歴史学の祖」と目される事すらあるナポリ出身のジャンバッティスタ・ヴィーコも風穴を開けていたりする。
874夜『新しい学』ジャンバッティスタ・ヴィーコ|松岡正剛の千夜千冊
インヴェスティガンティ(investiganti)という言葉がある。探求者という意味だ。
17世紀半ば、このインヴェスティガンティとして新しい科学や学問をめざす動きが各地に生まれた。デカルトやガッサンディやライプニッツがそういう一人だった。ナポリにもそういう動きが入りこみ、小さなインヴェスティガンティ学会のようなものができていた。
ジャンバッティスタ・ヴィーコはこの動きの最後の舞台に登場してきた思索者もしくは構想者もしくは教育者である。それまでの動きを覆すような、インヴェスティガンティをめざしたヴィーコのその両手には、「クリティカ」と「トピカ」という二つの方法の剣が握られていた。
そのころナポリ王国には40軒の本屋があったという。ヴィーコはその本屋の一軒に生まれた。すでに王立ナポリ大学は創立されていて、1699年、ヴィーコは31歳でやっと大学に職を得て、修辞学の教授になる。
ここまで就職に時間がかかったのは、ヴィーコが早熟すぎて学校になじめず、長きにわたって自学自習に専念していたからである。そうでもあろう! そうでなくてはヴィーゴは生まれまい。18歳からはドメニカ・ロッカ侯爵にひどく気にいられ、子息の家庭教師としてチレント半島のヴァトッラの居城に過ごしていたせいもあった。これもよくわかる。こうでなくてはヴィーゴではなかったのである。こうして、その9年間こそがヴィーコにインヴェスティガンティとしてのさまざまな構想をもたらした。
これらのことは、その後にヴィーコ自身が書いた風変わりな『自叙伝』にとくとくと語られている。花田圭介がいみじくも“オイディプス型の自伝”と名付けた自叙伝だ。いまは西本晃二の名訳で、みすず書房版に読める。
ナポリは、以前はカルロス2世のスペインの支配下にあったのだが、カルロス2世没後の王位継承にからみ、前の年から新たに皇帝カールに率いられたハプスブルグ家に占められていた。
これでは大学としても皇帝カールに捧げる何かをしなければならないという姿勢を示す必要がある。当時の新学年度の開講は10月18日。その講演がヴィーコに託された。やっとめぐってきたチャンスに、ヴィーコが選んだ講演テーマは「学問方法において、私たちのものと古代人のものは、どちらがより正しく、より良いものであるか」というものである。
このテーマはヴィーコの独創ではなく、そのころ芽生えつつあった「古代人・近代人優劣論争」を踏襲している。すでにピエール・ベールやシャルル・ペローがこの論争に17世紀の後半から乗り出していた。しかしヴィーコは古代人と近代人(近代人とはここでは18世紀人をさす)のどちらかに軍配をあげようというのではなく、古代から近代を貫くべき精神の歴史を構想し、あることを二つ提示したいと決意していた。
そのあることというのが、デカルトを批判することと、自分なりに学問の進歩の歴史を総編集し、そこから新たな「方法」を編み出したいということだった。
こうしてヴィーコは前人未踏の「学の確立」に向かって踏み切った。踏み切り点はまさに1708年の開講日の講演である。この講演の内容はいまは『学問の方法』として岩波文庫で読める。原題は「芸文を学ぶ青年に向けて、われらの時代の学問方法について」となっている。
このなかでヴィーコはすでにデカルトの方法との対決姿勢を切り出している。デカルトの『方法序説』は「理性を正しく導き、諸科学において真理を求めるための方法」を提起した。この方法はただちにポール・ロワイヤルに機関的に継承されたもので(ここにアントワーヌ・アルノーらのデカルト派がこぞって集っていた)、真理と虚偽を最初から分けて学問に望む方法だった。ヴィーコはこれに反抗し、むしろ真理は共通感覚(Sensus Communis、センスス・コンムーニス)から出所するべきものだと考えた。
自然や世界には先験的に真理なるものなどはなく、「真理は作られたものに等しいはずだ」というのがヴィーコの考え方だったのである。ヴィーコはまた、デカルト的でライプニッツ的な代数解析的方法にも疑問をもち、あえて幾何学的な方法によって青年を教育すべきだとも考えた。
これはありていにいえば、デカルトの方法は「普遍の学」(マテーシス・ウニヴェルサリス)に名を借りたフィクションにすぎないとみなしたということなのである。ヴィーコはフランシス・ベーコンのような“学問における森の森”のような構想を実現したかったのだ。学問における森の森、それはまさに「バロックの知」の総合起爆を暗示した。
*最終的にこの系統の拡張は「物事を明晰かつ正確に見つめ、全ての構成要素を別々なものとして見据え、奥の奥まで見通して、そのものの最も根本的な真実を捉えること」へ行き着く。ヴィントゲンシュタインは科学実証主義の精神を「科学者は語れないものについては沈黙しなければならない」と要約したが、これは「語り得ないもの(すなわち「物自体の世界=事象の地平線としての絶対他者」)」についても相応の暫定的認識が存在し、それゆえに「語り得るもの(すなわち「物の世界=その認識範囲に事象の地平線としての絶対他者との邂逅を一切含まないフラットな領域)」との峻別は可能とする立場に立脚する。そして最近欧米で流行しているマインドフルネス瞑想は「語り得るもの」に「事象の地平線としての絶対他者を敬遠する為の必要最低限の言及(ただし「言及」とはいえ言語表現が不可能な領域も含む)」を加えていこうとする動きとも。発想としては(信者獲得の為に様々な要素が追加される以前の)原始仏教の概念に近いとも。
欧米を中心に人気となっているマインドフルネス瞑想だが、ベースにあるのは仏教由来のヴィパッサナー瞑想だ。ヴィパッサナーとはパーリ語の仏教用語で、大ざっぱに言えば「物事をあるがままに見る」こと。スリランカの高僧ヘーネポラ・グナラタナはかつて、ヴィパッサナーとは「物事を明晰かつ正確に見つめ、全ての構成要素を別々なものとして見据え、奥の奥まで見通して、そのものの最も根本的な真実を捉えること」だと述べている。
そして何より、ヴィパッサナー瞑想では脳に、衝動的な反応をやめて「静かにしている」ことを教える。自分は衝動的じゃないと信じている人でも、ハエが飛んできて首に止まれば無意識のうちに手が動いてしまうもの。無意識だから、やめられない。何かよくないこと(同僚に無視されたとか)が起きるたび、何か(たばことか)が欲しくてたまらなくなるたび、私たちは考えもせずに反応してしまう。この反応が癖となり、次にまた似たようなことが起きると、私たちは同じ反応を繰り返してしまう。
ここで瞑想が役に立つ。瞑想を重ねて、衝動に負けず、脳を「静かに」させる習慣を身に付ければ、むやみな反応を抑制できるはずだ。 -
そして1990年代から始まった「(数学的アルゴリズムのみに立脚する)第三世代人工知能の躍進」は、上掲の様な「機械状(Machinique)のコンピューター空間」から「プログラムの起動者にして終了者、インターフェースを介しての操作者」たる人間を「事象の地平線としての絶対他者」の立場に敬遠すると同時に、それ自体が未来に「意識」、すなわち「数学的アルゴリズムを超越した力によって駆動される」可能性を自ら捨て去ってしまったのだった。
*この流れはおそらく「総力戦を最後まで遂行し抜く為、国家が国民を完全統制下に置く必要が生じた」総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)に「人間は主観的誤謬の領域においてしか事象の地平線としての絶対他者との邂逅を果たせない」とする魔術的リアリズムの思想が発生した事と表裏一体の関係にある。
こうして全体像を俯瞰してみると、以下の三種類の定義がごっちゃになっています。そもそも相補的関係にあるからややこしいとも。

- 「科学実証主義=人が認識し言及可能な世界」とその外側…ただし「言語化」や「数値化」自体は不可能でも(数学的アルゴリズムのみに依る)第三世代人工知能技術や、(アナログ処理を可能とする)量子コンピューター技術の導入によって「言及」が可能となる領域も存在する。
*近代以降、社会経営は原則としてまさにこのフラットな次元で運用される様になった筈?
- 「(相互関係が多重のカプセル化によって相互間で隠蔽されている)縁起の世界」と、その構造故に実在の確認が難しい「事象の地平線としての絶対他者の世界」…人間社会は矛盾が鬱積する都度、前者の「多重カプセル化による相互情報隠蔽」の一部を解消し、後者の一部を前者に取り込む形で発展してきた。
*この次元では「職の体系から役の体系を経て自由雇用社会へ」とか「LGBTQA層のカミングアウト問題」といった問題が扱われる。
- 「(「社会的生物として守っている規範」を含めた)人間の認識範囲」とその外側…「主観的誤謬を通じてしか事象の地平線としての絶対他者とは邂逅出来ない」なる立場に立脚する魔術的リアリズム文学が扱う領域。オーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui、1805年〜1881年)の様に「既存社会に対して絶対他者の立場に留まり続ける」決意を固めた「永遠の反逆者」が潜むのもこの領域となる。
*当人が「永遠の反逆者」に留まり続けようとしても、社会的に有用だと2のプロセスを経てどんどん取り込まれてしまうし、悪影響しか与えないと認識されると駆逐対象にされてしまうので生存が極めて難しい。
ここまで分類が精緻になってくると、これまで面倒だから言及を避けてきた様なややこしい問題にも果敢に挑まなければならなくなってきます。例えば「上部座仏教と大乗仏教の分裂とは一体何だったのか」とか…
「縁起の法」こそ仏教の本質
「縁起の法」は、釈迦の悟りの本質で、「すべては種々の因(直接の原因)や縁(間接の原因)によって生じる」と主張されています。つまり、すべての事物は、そのもの自体で独立して存在しているのではなく、原因や条件に依存して、他との関係の中で生起しているのです。世界のすべてのものは、相互依存によって存在し、自分だけで存在しているものはありません。縁起の法は、過去の原因が未来の結果を生むといった時間的な因果関係だけでなく、時間、空間を含むあらゆる現象にかかわるのです。ここまでのことは何か特別なことではなく、至極当然のことです。
部派仏教(Early Buddhist schools) - Wikipedia
釈迦の死後百年から数百年の間に仏教の原始教団から分裂して成立した仏教諸派。釈迦が残した教法を研究・整理して、独自の教義を論(アビダルマ)に編纂して論争を続けたのでアビダルマ仏教ともいう。
紀元前3世紀頃に仏教教団は上座部(テーラワーダ、theravāda、sthaviravāda)と大衆部(だいしゅぶ、マハーサンギカ、mahāsāṃghika)に分裂(根本分裂)。特に大乗仏教側は上座部系の説一切有部に対する敵対的態度を貫いたが、これは「説一切有論(三世実有・法体恒有を主張し、存在としての法が実在するとした立場)」と「空論(全ての存在は空であるとした立場)」の相性の悪さだけでなく、彼らが最も多くの比丘を擁していたので最もオルグの対象とされたせいとも考えられて入る。
*当時の大乗仏教側が党争継続の為に些細な相違を次々と政治問題化していっただけで、実際の上座部系の法蔵部や経量部の教理は大乗仏教の教理と一致することが多く、大乗仏教成立の起源に彼らの教理の影響があった事実もまた揺らがない。
根本分裂後も部派の分裂は止まらず、やがて部派の数は全体で20となった。そして大乗仏教成立後も「釈迦と直弟子時代の初期仏教の継承」を標榜する部派はインドに存続し続け、大きな勢力を有していたと考えられている。
大乗仏教における「空」の概念
大乗仏教では「空(くう)」「無自性(むじしょう)」「仮(け)」が強調されます。縁起の法に基づいて、「すべてのものは、固定した実体がない=空である」、「すべては無自性で、実体を持って存在しているのではなく、仮に設定されたもの、現象したものである」という結論が導き出されます。
日常生活で「現実、現象」と呼んでいるものは縁起の法に基づいています。 私たちの日常世界は、私たちの感覚器官を通して入ってきた情報を脳で処理し、解釈したものにすぎません。 それは五感と脳によって情報処理されたものであって、実際に外界に存在しているもの自体ではありません。
この意味で、生き物が経験している世界は、それをとらえる生き物の側の、さまざまな肉体的・精神的な条件によって、さまざまに作り出される「仮象」に過ぎません。よって、「現実とは、生き物の数だけ存在する」ことになります。 これを言い換えれば、「現実」とは、その「現実」を「観察する側」から独立した実体を有しておらず、「観察する側」が変わるとまったく変わってしまうのです。それは、「観察する主体」と「観察される客体」との相互関係によって現れてくるものにほかなりません。
龍樹は「中論(3世紀)」において上部座仏教の「説一切有論」と大衆部の「説一切空論」の調停を試みた。その産物が「(宇宙の真理など仮象としか感じられない一般信徒の世界観たる)世俗諦」「(宇宙の真理があたかも実在しているかの様に感じられる覚者の世界観たる)第一義諦」の2モードで考える二諦論だったのである。
さらに大乗仏教側は説一切有部の知識の集大成たる「倶舎論」を取り込んで「唯識派」を形成。この系譜がインドに渡った玄奘三蔵が中国に持ち帰って法相宗が形成され、藤原氏の氏寺中心に研究され続けた。
実は「バラモン階層が研鑽してきたウシャニパッド哲学の集大成」ともいわれる華厳経は、唯識派の影響を色濃く受けており「(大乗仏教側からの)上部座仏教の内容と信者の取り込み」に大きく貢献した側面もあったのではと推測されている。
*この時代にマニ教を介して「寺院が僧侶供給階層でもある在宅信徒に経済的にも支えられるシステム」が西方に伝わり、キリスト教における修道院制度の大源流となった。
そう、実は仏教史においては「上座部と大衆部のイデオロギー的対立」というより社会の実像に沿った「(クシャトリア階層に次第に政治的実験を奪われ衰退の一途を辿っていた)バラモン階層」が依った華厳経的世界観(だから「行動」より「達観」を重視する)と「(古代ローマ帝国や中央アジア諸国との交易で力をつけた)新興商業階層」が依った法華経的世界観(「即身成仏」理論など身分制撤廃を示唆する内容が多い)の対峙の方が重要。そして両者を「理論上直交する時空間」に配置したものが、そもそもこのサイトの依る「縁起の世界と絶対他者を対峙させた時空間」概念の出発点になってたりする次第。
*大乗仏教の観点からは「上座部仏教との矛盾」は解消済みだし、その事についての上座部仏教側からの反論が特になかったのが重要。
それではこれだけ重ね合わせて何が残ったかというと…

- 顕密対峙体制…インテリ層が掲げる「(グローバリズムに立脚する)瞑想に立脚する神秘主義」と、大衆側が掲げる「(リージョナリズムに立脚する)ルールの明確化要求」の対峙。
- パラダイムシフトについてのアンヴィバレントな感情の潜在…より具体的には「事象の地平線としての絶対他者」に対する歓迎や排斥といった形で現れ、独特のサイクルを展開する。
- 「宗教次元」との関係性…ここでは、かかる不安定状況がもたらす実存不安に耐え切れず、現実対応能力を犠牲としたミニマルな思考様式に逃げ込む現象のみを指す。概ね党争を激化させ、多数の犠牲者を出す。
思えば遠くにきたもんだ?