作中にまで「今度は違うといいながら、やっぱりお家騒動じゃないですか。確かに兄弟喧嘩じゃなかったけど、姉弟喧嘩じゃないですか」なるメタ言及がありました。地球人目線からすればまさにその一言に尽きます。次々と社員が闇落ちする某企業と並ぶ「MCU(Marvel Cinematic Universe)」のお騒がせ一家…(以下ネタバレ含む)
*「ブラック・パンサー(Black Panther、2018年)」は確かにMCU史上屈指の画期だけど、この観点からすれば、やはり「新たな銀河お騒がせ一家が現れた!!」に過ぎない。

とにかく英語の原題「ラグナロク(Thor: Ragnarok)」と挿入歌「移民の歌(Immigrant Song、1970年)」が読解の鍵となります。
Ah, ah,
We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs flow.
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,
To fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!アアアーアー アアアーアー
われらは 氷と雪の大地からやってきた
熱い泉が湧き出る白夜の大地からやってきた
神々の鉄槌がわれらの船を新たな地へと走らせん
流民の群れと戦うために
歌い叫びながら ヴァルハラよ 今われ馳せ参ず!*Valhalla・・オーディンの宮殿。オーディンとは北欧神話の主神にして戦争と死の神。各地を転々とした逸話があることから、本来は風神、嵐の神としての神格を持っていたといわれる。
On we sweep with threshing oar,
Our only goal will be the western shore.われらはオールをふるい掻き分けてゆく
われらがひたすら目指すは 西の海岸Ah, ah,
We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs blow.
How soft your fields so green, can whisper tales of gore,
Of how we calmed the tides of war. We are your overlords.アアアーアー アアアーアー
われらは 氷と雪の大地からやってきた
湯煙吹き舞う白夜の大地からやってきた
柔らかきお前共の緑あふれる原野は
いかに血塗られた物語を囁かん
われらがいかに戦の潮を鎮めたか
われらこそがお前共の大君主なのだOn we sweep with threshing oar,
Our only goal will be the western shore.われらはオールをふるい掻き分けてゆく
われらがひたすら目指すは 西の海岸So now you'd better stop and rebuild all your ruins,
For peace and trust can win the day despite of all your losing.さあいざ お前共は戦を止め
全ての廃墟を建て直すがよい
平和と信頼が勝利を掴むために
お前共の全てを失った日であるとしても
*the day・・一世 勝利
ラグナロク伝承にも様々なバリエーションが存在しますが、ここで思い浮かべるべきは間違いなくワーグナー「ニーベルングの指環四部作(Der Ring des Nibelungen、1848年〜1874年)」でしょう。
*恐らくアニメ版「海のトリトン(1972年)」における「最終話でのどんでん返し」の元ネタもこれだったのではあるまいか?
「海のトリトン」この最終話のプロットは、富野が脚本を無視して絵コンテ作成時に独断で盛り込んだ。このアイデアは第1クール終了頃に思いついたものの、周りに相談すると確実に却下されると考えて富野は沈黙を貫いた。ただし ## https://t.co/mFZ65AY1gZ
— トナク (@tonaku) 2017年11月22日
「海のトリトン」本作は富野喜幸の初監督作品として、守るべきものに追われる主人公、主人公たちが作る共同体、トリトン族が悪でありポセイドン族が善という善悪逆転の衝撃のラストが後の『無敵超人ザンボット3』に繋がるとし ## https://t.co/mFZ65AY1gZ
— トナク (@tonaku) 2017年11月17日
「海のトリトン」本作は『宇宙戦艦ヤマト』以前に高年齢層に人気を博した作品で、アニメブームの先駆者として重要とされる作品である。日本で初めてファン主体のテレビアニメのファンクラブが作られたとも言われる作品で、とり ## https://t.co/mFZ65AY1gZ
— トナク (@tonaku) 2017年11月17日
「海のトリトン」後に手塚のマネージャー西崎の『宇宙戦艦ヤマト』と富野の『機動戦士ガンダム』が大ヒットしたことで、本作は再評価された。1978年1月25日には、「アニメ愛蔵盤シリーズ」の1作として本作のサウンドト ## https://t.co/mFZ65AY1gZ
— トナク (@tonaku) 2017年11月17日
- 「非道な手段で建設されたが故に、いつか必ず復讐者に滅ぼされる宿命にあったアズガルドの魔都ヴァルハラ」の元ネタは19世紀ロンドン。その影響を色濃く受けたフリッツ・ラング監督映画「メトロポリス(Metropolis、1927年)」はニューヨークに同じ面影を見て取った。
- 原作においては「今や疲れ果て、滅びを受容するオーディン」を裁きヴァルハラを焼き尽くすのは「(夫を殺された復讐に燃える)ヴァルキリーのブリュンヒルデ(古ノルド語Brynhildr、英語Brunhild)とその愛馬グラーネ」及び「(滅ぼされた先住民の怨恨を継承する炎の精)ロキ」。「マイティ・ソー バトルロイヤル」においてはそれぞれの役割が「冥界の女王ヘラ」と「炎の巨人スルト」に分割される事によってニーチェいうところの「神話的解決(すなわち殆ど悲劇としての終焉)」からの脱却が図られている。
*「神話的解決」…それはワグナーが生涯かけて取り組んだ主題とされる。
ワーグナー《さまよえるオランダ人》における幽霊船幻想自体が、新たな領土獲得に躍起になっていた当時のオランダ人たちが、潜在的に抱えていた宗教的不安、後ろめたさから生み出されたものである可能性は指摘されるべきだろう。その場合、この伝承の本質には「神」との関わり、すなわち信仰と瀆神という隠されたテーマが横たわっているわけであって、こうした背景から、ワーグナーの本作を読解する手掛かりを掴むことも可能なのだ。
*司馬遼太郎は「オランダ紀行(1989年)」の中で、そもそも「(南アフリカ起源の)幽霊船幻想」を広めたのは「ユダヤ教徒のドイツ人として生まれフランス人のカソリック教徒として死んだ(すなわちプロテスタントに一生強い偏見を備え続けた)」詩人ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797年〜1856年)だった事、すなわちそこには「欧州の大陸側諸国を置き去りにして経済的発展を遂げ始めたオランダや英国に対する強い憎悪=「神罰が当たって死んでしまえ」なる情緖の投影」があった事を指摘している。またそうした感情が19世紀に入って初めて浮上してきたのは「(産業革命進行による)オランダ経済の英国経済に対する全面敗北」が顕現し(そうしたオランダを見限って独立を果たした)ベルギー中心に(フランスやドイツの)カソリック教圏において「ほらみろ、やはり神罰が当たった」という感情が高まったからとも。しかもこのエピソードにはフランスやドイツに実際の産業革命導入をもたらしたのは(ユダヤ人やプロテスタントといった)非カソリック教徒だったという残酷なオチがつく。
*司馬遼太郎「オランダ紀行(1989年)」…日本においては「オランダやベルギーでは「フランダースの犬」なる作品は完全に忘れ去られている」事を指摘した箇所だけが有名になっているが、こうした「オランダ人とは、ベルギー人とは一体如何なる存在か」の根本に迫る名文が満載された必読書とも。
ワーグナーが尊敬していたフランツ・リストは、ヒロインであるゼンタの「自己犠牲」、そしてワーグナーの作品には男性の苦悩は女性との愛によって遂に解放されるに至るという共通のテーマが存在することに触れている。更にリストは、以下のように鋭く「言葉」と「音楽」という、オペラ芸術そのものに内在する重要なテーマについて興味深い見解を展開している。
ワーグナーには文学的に二重の意味で天賦の才があり、それが彼を叙情的な朗誦へと向かわせ、彼の努力をある一点に集中させたのであった。このことが困難であるということを、既にルソーが次のように言っている。“歌の中で言葉はどんな役割を持っているか、会話の中で音楽はどうだろうか、という問いには、大きな、そして素晴らしい問題がある。劇音楽の全理論はこの問題の正しい解決次第である。”ワーグナーはルソーのようにこの問題を提出するだけで満足していない。彼はその解決に取りかかった。
(アッティラ・チャンパイ編『さまよえるオランダ人 名作オペラブックス』p184)*そういえば「フランス人の伝統的価値観をかき回して賛否両論を得たスイス人」にして「ラブロマンス元祖」ルソーには「むすんでひらいて」の作曲者という顔も備わっていたのだった。
フランスのジャン=ジャック・ルソーが作曲した原曲は、1752年10月18日にルイ15世の前で公演された後、1753年3月1日より一般公開されたオペラ『村の占い師』(fr:Le Devin du village)において、第8場のパントマイム劇で用いられた曲だという。
イギリスの音楽家チャールズ・ジェームズは1766年のロンドン公演のために『村の占い師』を翻訳したイギリス版オペラ"The Cunning Man"を執筆した。一方、1775年にはルソーの曲をもとにした『ルソーの新ロマンス』が作曲されている(作曲者不明)。このどちらが元歌となって、1788年にチャールズ・ジェームズ作曲の「メリッサ」(Melissa)という別れを歌うラブソングになった。
その後、日本の古い資料にも原曲としての記録がある『ルソーの夢』("Rousseau's Dream")に改編された。『ルソーの夢』の最古記録はドイツ系イギリス人音楽家ヨハン・バプティスト・クラーマーが作曲した変奏曲である。この変奏曲の楽譜は1812年にイギリスで発行され、フランス、ドイツでも人気があった。
一方でこのメロディーはイギリスにおいてキリスト教賛美歌として再び改編される。最もよく知られたバージョンは賛美歌『グリーンヴィル』("Greenville")というタイトルである。アメリカ合衆国では同時期に「大事にしていたガチョウが死んだってローディーおばさんに教えなよ」という歌詞で始まるアメリカ民謡 "Go tell Aunt Rhody"(Rody、Rhodieなどとも表記。"Old grey goose is dead"という別名もある)となった。欧米にはこの他にも異なる歌曲が存在する。
日本におけるメロディの初出は、1874年前後にバプテスト教会が発行した『聖書之抄書』に掲載された賛美歌『グリーンヴィル』としてであり、キミノミチビキという日本語の歌詞がつけられた。明治、大正と歌われつづけたが、1931年(昭和6年)以降は賛美歌集に掲載されていない。海老沢敏は著書『むすんでひらいて考』の中で、賛美歌として掲載しようにも唱歌や軍歌として知られすぎてしまったのが要因ではないかと述べている。日本国外では現在も「現役の」賛美歌として歌われている。
賛美歌として紹介された7年後の1881年に、同じメロディーが『見渡せば』という新しい題名と歌詞で、文部省音楽取調掛(後の東京音楽学校、現東京藝術大学)が発行した『小学唱歌集』初編に掲載された。『むすんでひらいて考』に拠れば、『見渡せば』の解説者の原稿にルソーが作曲者である旨が記されている。この歌の歌詞は、国文学者であり音楽取調掛に勤務していた柴田清照と稲垣千頴が、平安時代の古今和歌集にある素性法師の和歌 「みわたせば柳桜をこきまぜて宮こぞ春の錦なりける」を基本にしている。しかし『見渡せば』も賛美歌同様、広まる前に消えてしまった。これは優雅な歌詞が小学生には格調高すぎたことと、日本の軍国色が濃くなり、風流を詠った『見渡せば』よりも軍歌調の『戦闘歌』が持てはやされる時勢になったためである。
『戦闘歌』は東京音楽学校(現東京藝術大学)教授である鳥居忱が作詞し、1895年に軍歌集『大東軍歌』に掲載される。冒頭の「見渡せば」は同じだが、その後はまったく異なる歌詞となっている。この戦闘歌は歌うだけでなく、歌詞に合わせたふりつけがあり、小学校において遊戯曲として用いられていた記録が残っている。この時期吉本光蔵が戦闘歌を編曲した軍隊行進曲、『進撃追撃行進曲』を作っている。また同じメロディーで韓国では唱歌『植松』、中国では軍歌『尚武之精神』が作られており、前者は『見渡せば』後者は『戦闘歌』の影響を受けたものと思われる。
第二次世界大戦の終戦から2年経った1947年、小学一年向けに刊行された最初の音楽の教科書『一ねんせいのおんがく』に、新しい歌詞で登場したのが『むすんでひらいて』であった。以来今日まで『むすんでひらいて』は歌い続けられ、童謡、唱歌として完全に定着している。近年は小学校よりも保育園や幼稚園の手遊び歌(お遊戯)として歌われている。*こうした展開はどうして日本に童謡「ちょうちょう」として伝わった曲がサム・ペキンパー監督の手になるハードボイルド戦争映画「戦争のはらわた(Cross of Iron、1977年)」の主題歌に選ばれたかとも深く関係してくるから恐ろしい。
ドイツの古い童謡「Hänschen klein」(訳:「幼いハンス」)という曲が原曲とされている。これはドイツ東部・ドレスデンの教師だったフランツ・ヴィーデマン(Franz Wiedemann, 1821年 - 1882年)が作詞したもので、その歌詞には子供たちに別離・出発・悲しみからの回復を経験させるという教育上の目的があった。1番で幼い「ハンスちゃん」(Hänschen)が旅に出て母親が見送り、2番で7年の放浪と遍歴の末に「ハンスちゃん」は日焼けした大人の「ハンス」(Hans)へと変わり、3番ですっかり大きくなったハンスが故郷に戻り、あまりの変わり様にだれにもハンスだと分かってもらえないが、再会した母親はすぐにハンスだと分かってくれた、という内容。そのモチーフは、ヨハン・ネポムク・フォーゲル(Johann Nepomuk Vogl, 1802年 - 1866年)の書いた、旅する男がついに母親のもとへと帰ってくるという詩『Das Erkennen』と共通するところがある。
ヴィーデマンはこの詩を、狩りの歌として知られていた『Fahret hin fahret hin』のメロディーにあてはめた。この曲は、ヨハン・グスターフ・ゴットリープ・ビューシンクとフリードリヒ・ハインリヒ・フォン=デア=ハーゲンにより1807年に出版されているが、その起源はより古く、成立は18世紀初頭よりも前と考えられている。
「Hänschen klein」は、米国では「Lightly Row」という表題でドイツの歌詞とは無関係にボートを漕ぐ様子を歌った曲になり、19世紀前半には全米で広く知られる童謡となっていた。1875年(明治8年)から1878年(明治11年)まで米国へ留学した教育学者・伊沢修二(1851年 - 1917年)がブリッジウォーター師範学校でルーサー・メーソン(1818年 - 1896年)よりこの曲を教わり、日本へ紹介したのではないかと推測されている。また「Lightly Row」に対しては、小林愛雄(1881年 - 1945年)が「軽く漕げ」の表題で英語の歌詞を日本語訳した詞が存在する。
そして伊沢が紹介した曲に野村秋足(1819年 - 1902年)が独自に歌詞を付け、1881年に文部省が発行した『小学唱歌集』に「蝶々」の表題で掲載された。ただし、この歌詞と似た詞の童謡や清元は江戸時代から全国各地で知られており、野村も現在の愛知県岡崎市一帯で歌われていた童歌の詞を改作して「Lightly Row」の曲に当てたとされている。また、東京師範学校(東京教育大学、筑波大学の前身)の音楽教師で「蛍の光」(原曲はスコットランド民謡)などで知られる稲垣千頴(生没年不詳)が2番を作詞しており、1896年(明治29年)に発行された『新編 教育唱歌集』では3・4番も追加されているが3番以降については作詞者不明となっている。なお、曲については伊沢が「原曲はスペイン民謡」として紹介したことから長らく伊沢の紹介に疑義が挟まれることは無く、近年まで多くの文献に「作曲:スペイン民謡」と掲載されていた。
現在、広く知られているバージョンは太平洋戦争終結後の1947年(昭和22年)に文部省が発行した『一ねんせいのおんがく』において野村が作詞した原曲を改作すると共に2番以下を廃止したものである。この改作については元歌詞にGHQが教育現場からの排除を主張していた皇室賛美と取られるフレーズが含まれていた事、2番以下の廃止は表題の「ちょうちょう」と無関係な鳥や昆虫に関する描写を排除して曲の主題を明確にした事などが指摘されている。*そう、私達はどう足掻いても総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)にはあらゆる概念が「戦争遂行」の為に政治利用されてきたという現実から逃れられないのである!! あな恐ろしや…
ここでルソーを引用しながら、リストがワーグナーの芸術を、「劇音楽の全理論」を「解決」させる実践的なものとして把捉していることに注目しよう。実は、こうしたオペラにおける「言葉と音楽」という問題については、アッティラ・チャンパイの《魔笛》論でも言及されている点である。チャンパイによれば、モーツァルトのオペラでは、明らかに「言葉」と、それを飾るはずの「音楽」が齟齬を来している。具体的に言えば、たとえテクストが暗澹たるものであっても、モーツァルトはそこに極めて優雅な音楽を与え、言葉と音楽の齟齬による魔術的効果を起こさせることに成功しているのだ。この分裂、不一致こそ、いわばオペラ美学の謎に迫る一つの鍵である。
ルソーの言及からも判るように「歌の中で言葉はどんな役割を持っているか、会話の中で音楽はどうだろうか」という、音楽と言葉の相乗効果による美的特質の問題こそが、劇音楽の本質であると、リストは解釈している。そして、彼はワーグナーに、いわばその歓声された「体現」を見出しているのである。この指摘は、今後ワーグナーの芸術に触れる過程で、一つの指標になるだろう。
やや時代は現代に近付くが、ライプツィヒ・オペラハウスの監督だったヨアヒム・ヘルツによれば、ワーグナーは《さまよえるオランダ人》によって、初めて当時の流行的なオペラから完全に縁を切り、自分自身の「オペラのスタイル」を押し出すことに成功したとされる。ヘルツはまた、船長=オランダ人を「伝説的世界の存在者」として位置付け、ゼンタの父親と恋人のエーリックを、「近代的市民生活」を具現した世俗的存在として位置付けている。その場合、このオペラは「伝説」が平凡な市民生活に「侵入」して来る過程を描いていることになる。ゼンタとは、いわば神話的・伝説的世界と地上的世界を橋渡しするメディウムなのだ。
救いは最早、芸術にしかないのだ。芸術のみが、迷妄に囚われた人間の道に、正しい道を指し示すのである。ごく一部の、選りすぐりの素晴らしい絵画、音楽、バレエ、オペラ……。こうしたものだけ、より端的に言えば、徹頭徹尾、「貴族的な芸術」のみが、我々に本当の幸福を教えてくれるのである。この点で、芸術は宗教以上の圧倒的な力を持っている。宗教は、それも極端に厳格な戒律においては、芸術を遂に敵視するまでに至る。だが、宗教は芸術へと発展するために存在してきたのではないだろうか。今、私が綴っているこの文章は、おそらく極度にエゴイスティックで、見方によれば危険ですらあるだろう。だが、そのように感じた人にこそ、最後までどうか読んでいただきたい。そうした批判に応えるだけの力を、私はこのワーグナーに対する最初の評論において、残しておこうと決意したのだから。
リストが述べたように、ワーグナーのオペラは他のオペラとは違う。少なくとも、これまで私が観てきた一部のオペラ――《魔笛》、《トスカ》、《アイーダ》、《仮面舞踏会》――のどれよりも、直接的に魂に響いてくるのである。私は「オランダ人」役のバリトンであるトーマス・ヨハネス・マイヤーに心から感謝を捧げなければならない。私は彼から、彼の悲劇的な身振り、表情、歌声から、このオペラについてのある種の「解釈」を間接的に教わったと感じている。それは、ワーグナーが本作に宿そうとしたテーマとは無縁のものである。ワーグナーがこのオペラに、「女性による救済」というテーマを据えており、それが後の彼の作品にも受け継がれていくという点は、既に数多くの研究者が指摘してもいるし、ニーチェに及んでは、こうした「女性崇拝」的なワーグナーの信条を批判してすらいる。だが、実質的に、このオペラは、少なくとも私が新国立劇場で観た、マティアス・フォン・シュテークマン演出、飯守泰次郎指揮による《さまよえるオランダ人》においては、「女性による救済」は明らかに、救済とは別の方向において終幕している。すなわち、さまよえるオランダ人を救済するはずの唯一のヒロインであるゼンタは、海に身を投げて絶命し、オランダ人はとうとう、最後まで自分の「呪い」を解放してくれる救世主に出会えずに、悲劇の極北においてオペラは終幕するのである。我々は、むしろこの「救済の実現不可能性」という、このオペラの根深い問題に窮迫しなければならないだろう。
劇場で販売されている公式パンフレットを開いてみると、そこには不思議にもオランダ人が「救済された」と記されている。そう、元々、彼は「死」を待ち望むほどに呪われた存在者だったのだから、ゼンタが命を賭けて「永遠の愛」を捧げたことによって、生の呪縛から解放された彼は、確かに「救われた」と言えるのかもしれない。だが、これは果たして、真に「救い」と言えるのだろうか。そもそも、なぜゼンタは命を捧げまでしなければならないのか。そして、オランダ人はなぜ、「生」ではなく、「死」に救済を見出しているのか。こうした問題設定が、いよいよこのオペラの持つ恐ろしい原理を仄かに垣間見せているのではないだろうか。
異論は数多くあるだろうが、私はあえて主張する。ワーグナーのこのオペラでの真の目的は、むしろ「この地上世界に真の〈救済〉はどこにも存在し得ない」ということを、我々に告知することにあったのだと。そう考えると、このオペラがもっと理解し易くなるのだ。そもそも、ゼンタという女性は、あらかじめ伝説的存在としてのオランダ人を待っていた。彼女は「救う」女である以前に、まず「待つ」女だったのである。その証拠に、ワーグナーは第二幕でゼンタがいかに普通の針子たちとは共有し得ない価値観を持ち、超越的な存在としてのオランダ人に対して「信仰」にも似た愛を寄せているかを披露している。ゼンタからみれば、オランダ人は「来るべき人」である。そして、彼は来たのだ。そう、荒野でメシアを待ち望んでいた洗礼者聖ヨハネが「待つ」預言者であったように、彼女の「待つ」ことに対して、オランダ人は報いたのである。だが、イエスとは異なり、オランダ人は神に「呪われた」存在だった。それでも、ゼンタはオランダ人に惹かれ、運命は彼と共にあり、許嫁的存在であった俗物のエーリックにはないと感じている。
地上で生きながら、伝説的存在と運命を共にするためには、何が必要なのだろうか? いかなる儀式が、いかなる犠牲が? ワーグナーによれば、それは「死」である。つまり、ゼンタは己の命を捧げることによって、オランダ人が自分に「来た」こと、そして自分を「最愛の人にしたい」と望んでくれたことに返礼するのだ。ゼンタの死は、いわば「愛の誓約」であり、同時に「死の誓約」なのである。ここから骨格化してくるのは、このオペラにおいては、「愛と死」が分ち難く結合しており、真の愛のためには死が必要であり、真に死ぬためには愛が必要である、という悲劇的な定式である。そう、私はこのようなことを二十八歳の若さで考えてしまうワーグナーという存在が恐ろしいのだ。というのは、これは三島由紀夫にも通底する、いわゆる「殉死の美学」だからである。
オランダ人は神に、永遠に生きながら呪われ続けた存在であるように定められている身であるので、この生き地獄から解放されることを待望している。彼は「死」を求めている。そして、彼に安らかな眠りを与える唯一の方法は、女性から「永遠の愛」を捧げられるということなのだ。なんという残酷で皮肉な運命だろうか。ようやく女性との愛に満ちた幸せな生活が始まるかと思えば、オランダ人にとってはそれが待ち望んだ「死」の到来になってしまうのだから。
聖書においては、「死」を求める人間は預言者ではない。イエスはあらかじめ自己の死を知っていたが、彼は三日後に「死者のうちから復活すること」を確信していたので、「死」のみを求めていたのではない。だが、オランダ人は「死」を求めているのである。彼を衝き動かしているのは、早く死なせて欲しい、早くこの生きながらの苦しみから解放して欲しいという、深い「死」との馴れ合いなのだ。彼は「復活」など求めていない。そして、究極的に言えば、「愛」はただ、「死」を遂げるために必要な過程として展開するのである。
*要するに本当に死にたがっていたのは「オランダ人」でも「英国人」でもなく「ドイツ人」だったのである。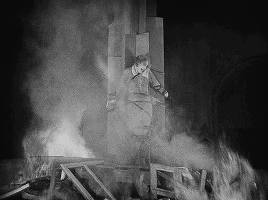
*しかも日本人は伝統的価値観の一致から、その「殉死の美学」を「ええとこどり」しようとした。「さらば宇宙戦艦ヤマト(1978年)」における「裸身で祈る反物質世界の女性」テレサの特攻、高橋しん「最終兵器彼女(2000年〜2001年)」や秋山瑞人「イリヤの空、UFOの夏(2001年〜2003年)」における「無力な男性と代わりに特攻する女性」…
*ところで「指輪四部作」において一般に「ワルキューレの主題」と思われてるテーマ、実は「ブリュンヒルデの愛馬グラーネのテーマ」とする解釈も。
*割とこうした解釈を素直に継承したのが岡本倫「極黒のブリュンヒルデ(Brynhildr in the Darkness、2012年〜2016年)」でしたが2010年代には既に「神話的解決」は時代遅れとなっていた。
*それに対して宮崎駿監督映画「崖の上のポニョ(2008年)」は「指輪物語」や「ラスト・ユニコーン」で「虐げられてきた者達の最後の虚仮の一念」を描き続けてきたランキンバスの執念に対するオマージュによって「神話的解決」を21世紀に顕現させている。*こうした流れを「三菱地所アタック」「無人在来線爆弾」といった形でパロディ化する事によって2010年代後半にまで顕現させたのが「シンゴジラ(2016年)」だったとも。
*最も興味深いのは、こうした歴史的経緯の全てが所謂「アベシネ教」と濃厚にからんでくる事かもしれない。ああ、何たる想像力の貧困化…
- ところで「指輪四部作」は途中からバイエルン国王をパトロンに迎えた関係からニーベルング族ら「民」の要素が次第にフェイドアウトしていく。それに対して「マイティ・ソー バトルロイヤル」は「免れ得ぬ死をどう免れるか」なる積年の課題について「国の根幹は場所でなく民である」なる処方箋を切って見せる。
*興行的に失敗に終わった「ベオウルフ/呪われし勇者(Beowulf、2007年)」のリベンジという側面もあったかも。やはりこの作品にも「民」の要素は欠けており、それが敗因だったとも。
*そもそもディズニーは「さまよえるオランダ人」問題そのものを圧倒的パワーによって捩じ伏せ、強引に解決していたりする。地母神的解決?
*ディズニーの場合、ウォルト・ディズニーのオリジナルからここに至るまでが長かった。そもそもヘラさんのあの髪型って「ディズニーきっての地母神系悪役」マレフィセントを連想させる訳で。そもそもディズニーランドの精神は「時代が変われば正解も変わる。だから我々は(永遠不滅の「シンデレラが見上げて憧憬したシンデレラ城の遠景」を除いて)変化し続ける」ではなかったか?
それにつけても、あの「ラストシーン」。途中の「伏線(Food? Or fighter?)」もあって絶対フェデリコ・フェリーニ監督映画「サテリコン(Fellini Satyricon、1969年)」を意識してるとしか思えない…まさしく「狼は生きろ。豚は死ね」の精神の顕現…
『マイティ・ソー バトルロイヤル』で「ソー3部作」完結へ ― 劇的変化で『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』へ直結 https://t.co/hjoeNCLpof @the_river_jpから えええ、あれで終わりなの……ウウウ………
— はっく* (@hakku_small) 2017年11月16日
トロント・サン誌のインタビューに登場したファイギ社長は、『マイティ・ソー バトルロイヤル』がMCUで果たす大きな役割について語っている。
―『マイティ・ソー/バトルロイヤル』は『マイティ・ソー』3部作の完結編ですか?
「私たちは(MCUの)フェイズ3を完成させ、22本の映画で作り上げている物語を終えようとしています。『アイアンマン』3部作をやり、『キャプテン・アメリカ』3部作をやり、『マイティ・ソー』3部作をやりました。『マイティ・ソー バトルロイヤル』で劇的な変化が起こり、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』に直接繋がるんです」
ここでは明らかに重要なことが2つ語られている。やはり『マイティ・ソー』は3作目『バトルロイヤル』で完結するとみられること、そして『バトルロイヤル』が『インフィニティ・ウォー』のストーリーを直接呼び起こすものであることだ。
これまで『バトルロイヤル』については、“『マイティ・ソー』史上最も笑える作品”として語られることが多かった。また本作に先がけての短編「チーム・ソー」でコメディ路線が強調されたこと、予告編でも従来作品とは明らかに異なるテイストがうかがえたことは、一部ファンの間で賛否両論となっていたのである。もっともタイカ・ワイティティ監督は「作風の変化はわずかなもの」「ずっと笑わせつづけながら、同時にスペクタクルもある、そんな冒険に観客を連れ出したい」と語っていた。『バトルロイヤル』は、『インフィニティ・ウォー』へと物語を導くだけのシリアスさをはらんだ作品になっているのだろう。
しかしファイギ社長がいう「劇的な変化」とは何なのか、『バトルロイヤル』では一体何が起こるのだろうか? いずれにせよ、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)が多くの問題を残したまま『キャプテン・アメリカ』の幕を閉じたように、きっと『バトルロイヤル』も、『マイティ・ソー』完結編とは思えないほどの謎を残して終わることになりそうだ。やっぱりタイトルは“終末”を表す「ラグナロク(原題)」の方が良かった……なんてことがないことを祈りたい。
それにつけても(「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズの様に)ただ笑えるだけでなく「笑いっ放しでないとやってられないRAVE感」も盛り込んだのが「21世紀のモーツァルト」タイカ・ワイティティ監督の恐ろしさ…
マオリ族の血を引いてるせいかまさしく吉田茂同様に「人を食った」御仁の模様?
まぁ彼女ら国際SNS上の関心空間に匿名で滞在する女子アカウントは「モアナと伝説の海(Moana、2016年)」封切り時は「HAKA(マオリ族の出陣舞)」動画とか喜んで回覧してたし、全ての行動の背後にある種のSAMURAI精神が透けて見えるのですね。特に「結婚式HAKA」の支持は絶大。これだけ男臭いHAKAの音頭に女性招待客や(生粋のアーリア系っぽい)花婿まで巻き込まれてく感じが最高なんですね。回覧過程で「これがグローバリズムでないなら、そんなグローバリズムなんて地上に不要」なるパワーワードまで飛び出しました。
*SAMURAI精神…日本人の目にHAKAは「隼人舞」の一種と映る。さらには既に「頑張って頑張って仕事、頑張って頑張って遊び」のCMソングで「ハイホー。ハイホー、仕事が好き」の歌同様に社畜文化に吸収済み。
それにつけても…げに恐ろしきは「DCU(Disney Cinematic Universe)」の全体像?