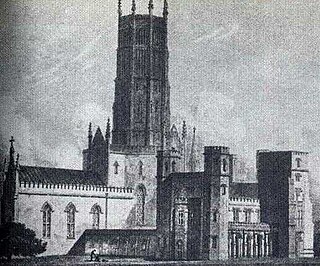欧州人の1/3が死んでゴシック時代(13世紀~16世紀)の中間に強烈な停滞期をもたらした黒死病(現在はほぼ腺ペストであったと推測されている)については「ネズミに寄生したノミが媒介となった」「人に寄生したノミやシラミが媒介となった」「ネズミに寄生して欧州上陸を果たしたノミが、寄生主を人に乗り換えた」といった説が入り混じっています。
黒死病があのような猛烈な破壊力を発揮しうるためには、それに先立って2つの条件が満たされねばならなかった。
— 歴史bot (@history_theory) 2020年6月4日
第1に、腺ペストを人間にうつすことのできるノミを宿している #クマネズミ が、ヨーロッパ全土に分布する必要があった。
第2に、感染しているネズミとノミをあらゆる港に
運ぶことができるように、船舶の航路網が地中海世界をヨーロッパ北部と結びつけなければならなかった。
— 歴史bot (@history_theory) 2020年6月4日
いや、クマネズミのヨーロッパ北部への分布自体、地中海と北方の諸港の間の船による連絡の結果だったらしいのだ。
これは、1291年に恒常化した。
この年、ジェノヴァの一提督が、
これまでジブラルタル海峡の自由な航行を妨げていたモロッコ軍を破り、この海峡が初めてキリスト教徒の船舶に対して開かれたのである。
— 歴史bot (@history_theory) 2020年6月4日
また13世紀には、船舶の構造に種々の改良が加えられたため、年間を通じての航行が可能となり、ヨーロッパの航海者は朔風吹きすさぶ大西洋を、
冬期にも無事渡航できるようになった。
— 歴史bot (@history_theory) 2020年6月4日
なによりも、絶えず就航している船なるものは、ネズミにとって安全な遠距離用の交通機関だった。
こうして、ネズミの生息域は、ユスティニアヌス帝の時代にははっきり存在していた地中海世界という境界線を遥かに越えて広がった。
MWb
ちなみにハツカネズミなら、それ以前のロマネスク時代(10世紀~12世紀)、すなわち(ノルマンディ地方やイングランドやイタリア半島南部を本拠地とした)ノルマン人貴族とアストゥリアス地方の西ゴート王国遺臣達やロンバルティアのランゴバルト貴族達やブルゴーニュのブルグント貴族達の末裔が構築した緩やかな部族連合ネットワークからクリューニュー修道会(10世紀末~)やシトー修道会(11世紀末~)が現れた時代にはもう冒険商人や巡礼者達の積荷経由で欧州中に広まっていたとする研究もあります。
*「冒険商人」…日本中世の悪党の様にどの地域も治安が行き届いおらず自力救済が現則の状況で「海賊」にも「海賊衆」にも「警固衆」にも「商人」にも化ける存在。詳細は不明だし集団や地域ごとの違いもあっただろうが当時の異教徒間接触はただでさえ苛烈を極めたので推して知るべし。例えばこういう分析もある。
ヴァイキング活動は、それを専業とする特定の人びとによって担われたわけではなく、北ヨーロッパのフィヨルドに住む半農半漁民の生業の一つとして行われた。近年、略奪よりも交易が注目されてきたが、その実態はそれほど明らかではない。
『アイルランドのサガ』はノルウェー・ヴァイキングたちの英雄伝説である。そこには、ヴァイキングとなって富も蓄え、最終的には農場主になるという、成功譚に彩られている。その1つである「バンダマンナ・サガ」(菅原邦城他訳『アイルランドのサガ 中編集』、東海大学出版会、2001所収)の主人公オッドは農民の子から、漁民、商人の生活を経て致富し、農民的豪族となる。
- 彼は北アイスランドの農民の息子だった。父と仲が良くなく、12歳のとき、漁網、漁具と12エルの毛織布(アイスランドの家庭で織られるホームスパン、アイスランドの主要輸出品のひとつ、また島内の貨幣商品のひとつ)を持って家出をし、漁場へ出かけ、そこで働く人々の仲間となる。
- 非常に運がよくいつも大漁であった(彼ら交易者、ヴァイキング、あるいは漁民にとって、その運命は幸運に恵まれるかどうかであった)。はじめは信用で借りた資金で漁をしていたのが、3年のあいだに借りをすべて返してなお、立派な商品が残るようになった。
- 北西部に品物の輸送をするようになり、大きな船の一部の権利を買い北部から木材と鯨と魚を運んだが、しばらくして船全体の所有者となる。ついには外国へ行く商船を1人で1隻所有し、積荷の大部分も自分のものとするようになり、外国へ干魚を輸出。
- こうして交易でたいへん豊かになったのち、友人たちのすすめもあって北アイスランドに土地を買い、屋敷を建て、農民となる。豪族になったのちにも1度、外国へ交易旅行に出かけている。
ここにはきわめて平和的な漁業や交易にほぼもっぱら携わることで成功したヴァイキングのライフスタイルが描かれているが、成功譚のモデルであって、それ以上ものではない。熊野聰氏は、ヴァイキングを交易者と評価していながら、彼らはあくまでも個人的土地所有者、農民なのであって「自分の農場で生産されないものは他の農民との交換により、自国で生産されないものは交易により、また必要ならば掠奪によって[手に入れる]。この観点からは、交易もヴァイキング行為も、農民の補充経済の追求なのである」といってやまない。この補充経済とは、農民の出稼ぎという意味のようであるが、「ないものを手に入れる」ことを出稼ぎとはいわない。
要するに、ヴァイキング達は「もの、ひと、とち」の獲得にあたって、相手の合意がえられればともかく、それがえられないとなれば暴力でもって獲得したが、それは買付け交易における見返る商品の不足あるいは欠如に基づいている。取引を望まない相手に交換品を押しつけ欲しいものを手に入れるのも略奪の一形態である。
そして地中海沿岸部で展開した十字軍活動(11世紀末~13世紀末)や、イベリア半島におけるレコンキスタ運動(11世紀~15世紀)や、東欧における大開拓運動(13世紀~15世紀) は人と荷物の往来量をさらに加速度的に増やしていったのです。次々とハンザ(商人組合)が結成され、遍歴商人の定住化が進んで都市が形成され、海路だけでなく河路や陸路も充実…
こういう状況なのでヒトについても「例えばジェノヴァ商人辺りが(奴隷狩りなどを通じ)黒海内陸部から免疫のない強烈な病原体を欧州に持ち帰ってしまった」可能性が完全には否定出来ないのですね。
中世においてはヴァイキングによりスラヴ人(サカーリバ)が、またアッバース朝以降のムスリムによりトルコ人が多く奴隷とされた。それら奴隷とされたトルコ人は生産活動に従事するのではなく、主に奴隷兵士として徴用された者も多かった。また、マムルーク朝、奴隷王朝の名はマムルーク(奴隷兵士)を出自とする軍人と、その子孫に由来する。
中世における世界の奴隷売買の中心地と言えたイスラム世界においては、その奴隷のほとんどがゲルマン人、スラヴ人、中央アジア人およびバルカン人で、黒人は少数であった。奴隷を意味する英語の"Slave"はスラヴ人に由来する。
西欧を例にとればヴェルダン( Verdun, フランス北東部ロレーヌ地方の ムーズ川(仏)/マース川(独)に面した要塞都市、長きに亘ってフランスとドイツとの係争地の対象となってきた)においてアラブ諸国向けの宦官の製造が町の最も活発な産業部門という時代もあった。中世イタリア商人も黒海において奴隷貿易を行ないスラヴ人、トルコ人、ギリシア人、アルメニア人、タタール人の奴隷をアレクサンドリア、ヴェネツィア、ジェノヴァなどへ運んでいる。
ジェノヴァの商人は、カッファ(Cafe, 黒海沿岸に位置するクリミア半島の港湾都市)の後背地で奴隷狩を行なった。1317年教皇ヨハネス22世は、ジェノヴァに対して、異教徒に奴隷を供給して力を強めることがないようにと警告をした。
「奴隷」の代名詞が黒人(いわゆるブラックアフリカ諸民)になったのは大西洋奴隷貿易以降の時代のことであって、それまでの「奴隷」の代名詞は主にゲルマン人とスラヴ人であったのである。
とはいえ(日頃先進的なイスラム文明に触れていた)イタリア商人は黒死病への対策構築も迅速で、その余力がイタリア・ルネサンス(14世紀~16世紀)開始につながっていくのでした。
ところでイスラム世界を代表する14世紀の歴史家イブン・ハルドゥーン(Ibn Khaldūn、1332年〜1406年)が著した「歴史序説(al‐Muqaddima)」や世界史に当たる「イバルの書(Kitāb al‐‘ibar)」はこう分析しています。
- 王朝開闢を可能ならしめる質実剛健で強力な部族的紐帯に結ばれた荒々しい集団が 田舎や砂漠(بدو badw、バトウ)」に現れ、王都を含む都市(حضر ḥaḍar、ハダル)をまとめて服属させ束ねるも、代替わりを重寝るうちに奢侈や富裕生活に耽溺して都市住人と同化し、新たに田舎や砂漠(بدو badw、バトウ)に現れた荒々しい集団に打倒される。
- (当時はまだまだ欧州より先進的文化段階にあった)イスラム文化圏がしばしば政治的混乱期に陥るのはまさにこの循環原理のせいで、部族的紐帯に依存する王朝が強力な支配力を維持可能なのは長くても2世紀前後という。
確かにローマ帝国を滅ぼした異民族達も大半は文明化するにつれ退場を余儀なくされ、フランク王国を築いたフランク族の覇権も、ヴァイキング(北欧諸族の略奪遠征)の落とし子ともいうべきノルマン貴族達の覇権も、それに取って変わった北フランス諸侯の覇権もそれくらいしか続かなかった。彼の生きた14世紀まではまだ、この法則を覆す様な動きはまだ見受けられないのである。
この切ない循環史観は奴隷制灌漑農業に立脚した古代メソポタミア都市国家群から繰り返されてきた。どうして続くかというと、どんなに支配者が入れ替わっても入手した都市を存続させる為に農業暦を握る神殿がどうしても否定出来ないからである。
一方、地の利がある交易拠点なら、住人を皆殺しにしても隊商の往来が途絶える事はなく、すぐに再建されるのだった。
それでは「(各地域をノルマン人貴族を中心とする部族連合が実効支配していた)ロママネスク時代」終焉後の欧州史に目を向けてみましょう。そもそも欧州の場合「各地域を部族連合が実効支配していた」といっても彼らはあくまで教会や神聖ローマ帝国やイングランド王国やフランス王国の権力構造の枠内で現地有力者や領民を束ねていただけであり、彼らが静かにフェイドアウトしていったからといってその全体像自体に大きな変化があった訳でもないのです。
ゴシック時代前期(12世紀~13世紀中旬)
- ノルマン朝(1066年~1154年)断絶を契機にアンジュー家領がイングランド王家の手に渡った結果、英仏を跨ぐ形で巨大なアンジュー帝国(1154年~1259年)が出現。ラ・マルシュ伯ユーグ9世・ド・リュジニャンらフランス諸侯の反発を招いてしまい、その息子ラ・マルシュ伯ユーグ10世・ド・リュジニャンらの策謀にも関わらず一旦はイングランド側がガスコーニュ以外の大陸領全てを放棄する形で問題解決が図られる展開を迎える。いずれにせよ根本的原因たる「イングランド王がフランス国王の家臣でもある」捻れ構造自体は英仏の国境が確定する百年戦争(英Hundred Years' War、仏フランス語: Guerre de Cent Ans, 1337年/1339年~1453年)まで完全解消はしない。
*「ゴシック時代前期最大のお騒がせ屋」リュジニャン家…お母さん(始祖とされるドラゴン人魚メリュジーヌ)も泣いてるぞ!!
-
こうしてフランス王領となったアンジュー家領をフランス国王ルイ9世は弟シャルルに与え、王弟シャルルはアンジュー伯を名乗る様になった(シャルル=ダンジュー)。彼の夢はシャルルマーニュの後継者を自負するフランス王国、ロベルト・イル・グイスカルド以来東ローマ帝国を狙い続けてきたシチリア王国、聖地回復を望むローマ教皇の願望の統合であり、甥のフィリップ3世を神聖ローマ皇帝につけ、コンスタンティノープルを征服して地中海帝国を築き、エルサレムを奪回する計画を練っていた。まず手始めに兄ルイ9世が起こした第7回十字軍(1248年~1254年)に参戦してエジプトに一緒に攻め込むも共に捕虜となる(後に解放)。第8回十字軍(1270年)にも参加し、夢を実現に近付けるべくチュニジア攻めを仕向けるも兄ルイ9世が遠征先で病没するという残念な結果に終わる。かえって敵たるマルムーク朝の侮りを招き、アッコン陥落(1290年)に至る。
*で、もう一人のお騒がせ屋がこの「同じくその登場がほぼ死亡フラグ」のシャルル・ダンジュー… - 第一次バロン戦争(1215年~1217年)で叛旗を翻しフランス王太子ルイ(後のフランス国王ルイ8世)を総大将に担ぎ上げたイングランド諸侯が信じられなくなったイングランド王ヘンリー3世は、母方の親族にあたるリュジニャン一族などのポワチエ人、妻の生国のプロヴァンス人、縁戚のサヴォイア家の一族といったフランス人を側近として重用。これに激怒したイングランド諸侯は(教皇インノケンティウス3世の提唱に従って北フランス諸侯が南フランスを攻めた)アルビジョワ十字軍(1209年~1229年)の英雄シモン・ド・モンフォール (第5代レスター伯爵)の息子シモン・ド・モンフォール (第6代レスター伯爵)を総大将に第2次バロン戦争(1264年~1267年)を起こす。調停を依頼されたフランス国王ルイ9世は反乱者への寛大な処置を望みつつヘンリー3世の肩を持つ。最終的に反乱自体は鎮圧され、シモン・ド・モンフォール (第6代レスター伯爵)も戦死したが、これを契機に英国議会制への道が開ける。
*ここでもリュジニャン家…
-
イタリアに隣接するシュヴァーベンの大公で神聖ローマ帝国皇統のホーエンシュタフェン家は代々イタリア併合を望んできた。初代皇帝フリードリヒ1世は敵対するミラノの破壊にも成功するも(ランゴバルト貴族が影響力を喪失した後、教皇に忠誠を誓う様になった)北イタリア諸都市のロンバルディア同盟にレニャーノの戦い(1176年)で大敗を喫っし、第三回十字軍(1189年~1192年)従軍中、鎧を着たまま河に落ちて溺死。第2代皇帝ハインリヒ6世は(ノルマン系王朝たる)オートヴィル朝シチリア王国(1130年~1194年)は滅ぼして併合する事に成功するも1197年、当時弱体化していた東ローマ帝国への遠征準備中に急死。さらに1208年にはローマ教皇インノケンティウス3世がヴィッテルスバッハ家のバイエルン宮中伯オットー8世と謀って(ヴェルフ家の対立王オットー4世を下し神聖ローマ皇帝として戴冠する直前だった)第4代ローマ王フィリップを暗殺。代わりに帝位を承認したオットー4世も南イタリアに攻め込む気配を見せたので1210年に破門してフィリップの甥のフリードリヒ2世を代わりに帝位に就けた。その後ローマ教皇インノケンティウス4世がシャルル・ダンジューを招聘。やっとホーエンシュタフェン家の断絶に成功し神聖ローマ帝国の大空位時代(1254年~1273年)が始まる。
*いやもう、既に始まってた? -
ところでローマ教皇インノケンティウス3世はフランドル伯やシャンパーニュ伯ら北フランス諸侯をヴェネツィアの船団が運んだ第4回十字軍(1202年~1204年)の提唱者でもある。この十字軍は船賃が全然足らず、エジプトに辿り着くどころか行き掛けの駄賃で(ヴェネツィアと怨恨関係にあった)キリスト教国ザラ市(現在はクロアチアの都市ザダル)を攻略し、さらに(内紛に巻き込まれて)ビザンチン帝国を滅ぼしてラテン帝国(1204年~1261年)を建国しフランドル伯が新皇帝に即位する。しかし翌1205年に侵攻してきたブルガリア軍に大敗し捕虜となって消息を絶った。一方、これを契機にヴェネツィアはビザンチン帝国と近しい関係にあったライバルのジェノヴァに対し、地中海貿易でしばらくの間優位に立つ事になる。
*当然、ビザンチン帝国が復活したら仕返しされる訳である。結局、ビザンチン帝国はパレオロゴス王朝初代皇帝ミカエル8世パレオロゴス(Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος, ローマ字転写:Michaēl VIII Palaiologos, 在位1261年~1282年)の手によって再建されたが、以前の繁栄は望むべくもなくオスマン帝国の手によって首都コンスタンチノープルが陥落する1453年5月29日まで無力な小国に止まり続ける羽目に陥った。その隙を突いてシャルル・ダンジューが魔の手を伸ばしてくる。①まずは1267年に男子後継者の見込みがないアカイア公ギヨーム2世・ド・ヴィルアルドゥアンとヴィテルボ協定を結び、ギヨームを従臣とした上で自分の次男フィリップとギヨームの娘イザベルを結婚させて両者を後継者とし、彼らに男子が産まれない場合にはシャルル自らがアカイア公となる事を決定。②次いでミカエル8世パレオロゴスに国を追われたラテン帝国皇帝ボードゥアン2世ド・クルトネーを保護し、彼の息子フィリップと自分の娘ベアトリス(1275年没)を結婚させて保護者に収まり1273年にラテン皇帝の地位を相続。③1277年にはエルサレム王国の継承権も手に入れエルサレム王を称する様に。④1277年に次男フィリップ、1278年にアカイア公ギヨームが共に男子後継者なく死去し、以降はアカイア公も兼ねる事に。さらに幾つかの領土をアドリア海岸に獲得して東ローマ帝国侵攻の準備を整えたが、ミカエル8世が東西教会統一政策を打ち出したので一時中断を余儀なくされる。1282年に再度侵攻計略に取り組み始めたが、これに脅威を感じたミカエル8世は、アラゴン、ジェノヴァと結び、遠征のために重税を課せられていたシチリア住民の反フランス感情を煽り始める。
同年春に発生したシチリアの晩祷事件自体は偶発的だったが、ある意味工作の結果が実ったとも言える。当初シャルルはこの反乱を軽く見ていたため対応が遅れ、シチリア全土を失った。シチリア住民はローマ教皇に保護を願い出たがシャルルを支持する教皇はかえって住民を破門。このためシチリア住民はホーエンシュタフェン朝王統の娘婿アラゴン王ペドロ3世に援助を求め、これを受けたペドロ3世はシチリアに上陸しシチリア王即位を宣言する。実は彼自身もプッリャ公ロベルト・イル・グイスカルドの娘マファルダの血を引くオートヴィル朝(ノルマン朝)の潜在的王位請求者であった。
*この設定で「それまで「いざ鎌倉」を待って雌伏していたノルマン騎士」が続々と集まってきたりしないのが「部族的紐帯の時代の終焉」なのである。そういえばThe Lord of the Ringsにも「召集」に応じた人数が少な過ぎるのを嘆く場面ならあった。以降、ナポリを拠点とするシャルルとペドロ3世の間の戦争が続いた(シチリア晩祷戦争)。ペドロ3世がピレネー山中から連れてきた傭兵隊アルモガバルス (アラゴン語:Almogabars, カタルーニャ語:Almogàvers, スペイン語:Almogávares, アラビア語:al-Mugavari)はイベリア半島のレコンキスタで鍛え上げられた蛮兵で乗馬突撃してくる重装騎兵をアズコナと呼ばれる重い投槍の投擲で落馬させ、コルテルと呼ばれる肉切り包丁とナイフを合わせた様な鋭利な短剣で(刃の通る関節部を狙って)四肢を切り落とす戦い方で恐れられたという。
シャルルは、ローマ教皇マルティヌス4世にペドロ3世を破門させ甥のフランス王フィリップ3世にアラゴン王位を与えるよう工作。シャルルの意を受けたフィリップ3世がアラゴンを攻めたが、成果は上がらず、逆に敗北した。1284年のナポリとアラゴンの海戦もシャルル側に利は無く、長男シャルル2世が捕虜となり1285年に失意のうちに病死。同年フィリップ3世、ペドロ3世、マルティヌス4世も相次いで死没した。シャルル死後は1288年に捕虜から解放されたシャルル2世が後継者となりシチリア王を称し続けたが通常はナポリ王と称される。後にシャルルの曾孫カルロ・ロベルトはハンガリー王となった。この王朝はハンガリー・アンジュー朝と呼ばれる。
1285年アラゴン十字軍の遠征の帰りに病没した父フィリップ3世の後を継いで即位したフランス新国王フィリップ4世(Philippe IV、在位1285年~1314年)にとって、アラゴンとの争いはナポリ王カルロ2世に対する義理立てに過ぎなかったので1291年に条約を締結し和睦が成立。官僚制度強化に努め、やがて絶対王政へとつながる中央集権化の第一歩を踏み出した彼の関心はむしろ毛織物業で栄え経済的に豊かであったフランドル地方の支配に向けられており、フランドル諸都市の市民と激しく争った。
*戦費捻出の為に次々とえげつないアイディアを実行に移したが、実はドーバー海峡の向こう側のイングランド王エドワード1世(Edward I在位1272年~1307年)にも多かれ少なかれ似た側面が見て取れる。多分何らかの時代精神の体現?1297年にはフランドルの併合を宣言。1300年にイングランド王エドワード1世と結んで対抗するフランドル伯ギー・ド・ダンピエールを捕らえジャック・ド・シャティヨン(Jacques I er de Chatillon)をフランドル総督に任命した。しかしその支配が過酷だった為に1302年5月18日ブルッヘにおいて市民の反乱が起こり、フランス人が虐殺される。再び侵攻して来たフランス軍に対しフランドルの諸都市は同盟を結んでこれに抵抗し、コルトレイクにおける金拍車の戦い(1302年7月11日)にで歩兵中心のフランドル都市連合軍が騎士中心のフランス軍を破った。その後もフランスとの戦争は続き、リール近辺のモン=アン=ペヴェルの戦い(1305年)ではフランス軍が若干優勢という結果に終わっている。和睦と戦闘の繰り返しはフィリップ4世が死没した1314年まで続いた。百年戦争期間中もフランドルは概ねイングランド側に就いており、その後ブルゴーニュ公国領、ハプスブルク家領、スペイン・ハプスブルク家領となりながらフランス革命・ナポレオン戦争期までフランス領になることはなかった。
*日本史にも見受けられる牧歌的な部族連合(Tribal Union)→苛烈な氏族間闘争(Clan War)→生々しい経済戦争(Economic Conflict)の流れ。そして…軍事技術面では、短槍歩兵の密集縦隊が、側面防御を条件に、いかなる騎兵の猛攻にも不敗であることを実証した戦いとなった。特に、それまで圧倒的優勢にあった封建制騎士軍の凋落を象徴する最初期の戦いであった。
封建制軍隊は、直接の家臣でなければ主従関係が成立しないことから、命令系統の一貫性に欠けていた。従軍は臣下の封建的義務であるものの、12世紀以来、主君に従軍するのは年に1回40日程度が慣行だった。そのため、封建軍は大規模な戦闘が不可能であった。また、14世紀当時の騎士は重装備であり、騎士自身だけでなく、馬の動きも鈍重で長距離の駆走も困難だった。
金拍車の戦いは単に市民軍がフランス軍に勝ったという観点だけで捕えるべきではないと思います。多くの歴史的変換点、以後の歴史に多大な影響を与えた戦いなのです。
1.戦法・戦術の変換
当時の最強と言われた戦法は重装騎兵による集団突撃です。大河ドラマの戦場シーンで使われる馬はせいぜい30騎から50騎程度だと言われます。それ以上の数がいてもカメラのフレームで捉えきれないのだそうです。
つまり、30騎や50騎の馬であの迫力ある攻撃シーンが撮れるのですから、実際の戦闘で数百騎の騎馬が押し寄せてきたら戦場に留まる勇気は持てないのかも。実際、重装騎兵の突撃で戦列が大幅に崩れるのは当然のこととされていました。
対して市民軍が採ったのは密集方陣。守る側の恐怖心を取り除くために兵士互いが身を寄せ合い、長槍を付き出し、まるでハリネズミのような陣形が出来るのです。戦史に残る初めての対重装騎兵用戦法です。
*歴史上の最大の皮肉。「トゥール・ポワティエ間の戦い(フランス語: Bataille de Poitiers、アラビア語: معركة بلاط الشهداء, 732年)って何だっけ?
1週間目の正午から全面衝突が始まった。正午、イスラム軍の騎兵隊が突撃を開始した。カールマルテルは日頃から厳格に兵の訓練をおこなっていた。このよく訓練されていた重装歩兵を中心とするフランク軍は、密集隊形を組み、前面に盾の壁をつくって防戦した。これまで数々打ち勝ってきたイスラム重装騎兵による突撃戦術は、フランク軍の盾の壁に跳ね返され、アラブ兵はフランク軍の前に屍を重ねた。モサラベ年代記によると“北の人々は海のように動かすことができず、まるで氷の砦を作るように互いに堅固に立ち、強い打撃でアラブ人の首をたたき落とす”。この日、戦いは勝敗がつかず、日没で止んだ。フランク軍は当然、翌朝から再び激しい戦いが始まると予想していたが、朝靄が明けてみると、イスラム軍は多数の遺体を残したまま姿を消していた。アル・ガーフィキーの遺骸もあった。将軍を失ったイスラム軍は、夜中に南に総退却していたのである。
この勝利で、カール・マルテルの声望は一気に上がった。その後も735-739年にかけてウマイヤ軍は侵攻したがマルテルにより撃退された。また、マルテルは、騎兵に農民付きの土地を与えて忠実な直属騎兵隊を創設しようとした。全土の3分の1を占めていた教会領の没収を強行して、騎士に貸与(恩貸)したのである。このようにして、土地を貸与する(これを封土といった)ことによって臣下に服従(奉仕)させるという主従関係が、フランク王国の新しい支配の制度となっていった。これが封建制度である。
*何てこったい!! カール・マルテルは何故かすっかり自分達が負かした相手の戦術が気に入ってしまったのである。しかも土地を貸与して農地経営も任せ「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威主義」に立脚した自分に忠実な小領主集団を創設するだって? ハスカール制で主人が食客を養うのも恩を売る為だが、原則彼らには「殺し合い」しかさせず、メンタル面をそういう方向に追い込む。日本の旗本も名義上の俸禄(土地)なら与えられるが、土地経営は全て代官に任せて収入を得るのみ。要するに欲しい最強の存在は「軍事サービス提供に専念する職業軍人」であり、農閑期に軍事訓練もする兼業農家なんかじゃないのである。2.軍団構成員の変換
フランスに於ける戦闘員の主力は、配下の領主や小領主達により構成される騎士団です。王や領主達は直属の常設戦闘軍を持っていませんので戦いのたびに呼び集められた騎士や雇われ騎士や傭兵によって軍団が形成されます。イングランドのように農民兵は基本的に存在しなかったようです。しかしながら、云わばプロの軍団が素人の市民軍に敗北したのですから、フィリップ4世の驚きと落胆は大きなものだったでしょう。以後フィリップ4世は近衛兵を初めとする常設軍の創設を果たすことに繋がります。
日本に於いても、かの豊臣秀吉軍が強かったのは秀吉が足軽上がりであり生え抜きの家来がいなかったため、職業武士集団を作った点にあるとされます。農民兵を駆り出すため、種蒔きや稲刈りと言った繁忙時に出兵できなかった他の大名たちとの最大の相違点だと言われています。
フランドルの市民軍は、商人達から財政的な援助を受ける事が出来、最新の武器を入手することが可能であり、ブルッヘの反乱で多数のフランス人を殺していることから、敗戦は死をも意味しますので、戦意が高く、訓練を積み、指揮系統が確立されていたようです。
3.騎士道精神
当時の戦闘では騎士は殺さずに捕虜とし身代金を取る慣行がありました。要は騎士はギブ・アップをすれば命は助かったのです。敵の騎士を捕まえて金にするというのが功名となったわけです。
領主や王から戦争の支度金や遠征費は期待できず、戦に勝っても王や領主から新たに領地を与えられたり、特別の報奨金も期待出来ないのです。
金拍車の戦いにおいては、市民軍に騎士は僅か400騎しかいません。対してフランス軍は騎士2,500騎、功を焦る騎士たちは司令官にせっつき早めの突撃を要請したのです。
ところが、足場は悪く機動力が発揮できず、ようやく敵陣にたどり着いたらハリネズミの陣形に突撃を阻まれ、集団に取り囲まれて個別殲滅。ギブ・アップも通じず叩き殺されてしまいます。この状態に騎士群は集団パニックに陥ったと思われます。
さらに事態を悪化させたのは、撤退が出来ないことです。騎士道は敵に後ろを見せて逃げるというのは卑怯な行為とされていました。フランス軍の司令官も市民軍に対して後ろを見せることは出来ず、最終的な撤退時期を失い甚大な被害をもたらしたのです。
4.市民軍
フランスに於いては、農民の反乱を除いて市民が軍に対抗するなどということはありませんでした。市民決起軍にとってはフランス占領時に反乱を起こしフランス人を虐殺していますので、負けた時の反動が恐ろしい。また、自由都市防衛のために十分な武器を用意できていたのです。当時の最新鋭の武器はボウガンです。弓部分は鋼鉄製ですから弦を引くのに150㎏相当の力(弓力)を要したとされ、歯車が付いた弦を張るための巻き上げ機が付いていました。当然、威力はあるものの連射が利きません。
フランス軍は1,000張のボウガンがありましたが、騎士道精神によれば基本的に飛び道具は卑怯とされ、接近戦での一斉射撃などは行うはずがありません。対して、市民軍はそんな騎士道精神などは一切関係ありませんので、近づいてきた騎士に対してはボウガンをどんどん使ったでしょうし、殺すのは当たり前。戦なのですから。
*騎士道にはアラゴン王カルロ3世がピレネー山中のゲリラ戦から連れ出したアルモガバルスだって敬意を払わなかった筈である。むしろ彼らにとって重要だったのは、手足を切り落とされた味方の負傷兵は生かしておいても運ぶ手間がかかるし、始末しても心理的負担が掛かるし、いずれにせよ多くが壊疽で死んで戦場に戻ってこない事だった。まとめ
このようにいくつかの歴史的特徴を有する金拍車の戦いですが、単に歩兵が重装騎馬に勝ったとする結果論だけ取り上げられることが多いようです。
フランス軍が敗退した戦場には金メッキされた多くの拍車(靴に取り付けられた金具で馬を蹴り、走らせる道具で11世紀に発明され、従前必要であった鞭を持たなくても済むようになり、両手で扱う大きな槍を持つような戦法に変わった。西部劇でカーボーイの靴に付いている金具。中世ヨーロッパでは剣と共に騎士の象徴であり、騎士となる若者には騎士叙任式の際に授けられていた)、一説には500個とも言われる数の拍車が散乱していたので市民は戦勝記念として持ち帰り、コルトレイク聖母教会にいまでも飾理続けています。まさしく歴史の節目…
ちなみに、それまで純粋な要毛の供給地に過ぎなかったイングランドにおいて14世紀から現地での毛織物加工が始まるが、これはマンチェスターなどに移住したフランドル市民が主導した動きだったと考えられている。
どうやら13世紀末からの急激な状況変化、以下の文席に対応してる様です。
1300年代中期のペスト流行期には人口の40〜60%が犠牲になった地域もある。当事者にとっては大惨事のように思えただろう。しかしペスト流行に至るまでのヨーロッパの状況を見ると、既に進行していた多くの問題がパンデミックをきっかけに加速したことがわかるだろう。
1200年代の終わりから続く長期的な景気後退の末に、黒死病の流行が訪れたのだ。それ以前のヨーロッパは「商業革命」による経済の全盛期で、遠距離の貿易が瞬く間に広がり、より多くの貨幣が流通し、経済は成長し続けた。しかしこの経済成長は、人口の増加に支えられたものだった。ヨーロッパ全体を見ると、この時期に人口が倍増したり3倍にまで膨れ上がった地域もあった。
そうして13世紀(1200年代)の終わり頃には、農耕に使用できる土地はほとんど残っていなかった。じめじめして起伏があり農業に適さないような土地ですら耕作に使われる状態だった。ただ賃金が極端に低い人々を農業に使えた。多くの人々は自分の土地を持たず、ギリギリの生活を送っていた。土地を使わせてもらう代わりに領主に対して無償でサービスを提供しなければならないという交換条件が当時盛んだった農奴制度を支えていたのだ。
気候的な要因もある。経済の全盛が長く続いた背景には、穏やかで暖かい天候があったのだ。種まきと収穫の時期さえわかればよい農夫にとって、天気良いかどうかというよりも、先の天気がどうなるか予測することの方が重要だ。しかし1200年代の終わりから1300年代初頭にかけて、天候が非常に悪くなった。天気が予測しにくくなり、雨が多く気温も下がった。さらに1315年〜1322年には西ヨーロッパを「大飢饉」が襲い、数え切れないほど多くの人々が亡くなった。その時点で、何らかのシステム的な誤りの兆候が現れていたと言える。そしてこの状況が黒死病の大流行まで続いたのだ。
まず細部確認。これまでの投稿で述べてきたロマネスク時代(10世紀~12世紀)について述べてきた記述、すなわち「(ノルマンディ地方やイングランドや南イタリアなどを本拠地とする)ノルマン人貴族とアストゥリアス王国の西ゴート王国遺臣達とロンバルティアのランゴバルト貴族とブルゴーニュのブルグント貴族の緩やかな部族的紐帯からクリューニュー修道会(10世紀末~)やシトー修道会(11世紀末~)が現れた」状況の原文がこちら(うろ覚え)。
ウィリアム・マクニール「ヴェネツィア(Venice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1978年)」
732年頃にカロリング家の宮廷で恐るべき戦術が発明された。鎧兜に身を固めた職業戦士による乗馬突撃の一種だが片手に盾、片手に長槍を構えて激突の瞬間身体を前のめりに倒し、重い鐙で衝撃を受け止める事によって構えた槍の穂先に恐ろしいエネルギーを込める様になったのである。戦闘が乗馬突撃の可能な広い場所で行われる限り、こうした重装槍騎兵(Heavy Shock Cavalry)を数十人用意するだけで確実に勝利が勝ち取れた。
- この戦法(重装衝突槍騎兵の密集突撃)は歩兵を蹴散らすのにはもちろん、細長いボートでどんな小さな川も上ってくるバイキングや、丈夫なポニーに乗って疾駆してくるハンガリー騎兵に対してもことのほか有効だった。
- その一方で一説によれば鎧、兜、剣、槍、盾と合計三十キロのフル装備に身を固める騎士一人を養うのには150ヘクタールの土地からの収入が必要となる。その維持費が支払える様になったのはロワーヌ川やライン川の流域で950年前後に社会制度と農作物生産体制の変革があって以降。当時の農業生産力や出生数の増加を単純に「ヨーロッパが寒冷な気候から温暖な気候への変化した結果(中世温暖期理論)」に帰する向きもある。
- いずれにせよそうして(ノルマンディ地方やシャンパーニュ地方を含む)北フランスからフランドルにかけて広がる北西ヨーロッパの肥沃な平原に封建的・荘園的中心地が出現したのである。
いずれにせよノルマンディ地方や北フランスやラインラント(ライン川流域)における専業騎士達の増加は1050年代までに飽和状態に達しノルマン貴族が先頭に立つ形で継承すべき所領を持たない領主の次男坊三男坊や遍歴騎士が新天地を求めてイベリア半島、イングランド、アイルランド、エルベ以東、レパント地方などに進出していった。
- つまり(遺領を分散させない)長子相続の定着がこうした一連の動きの最も重要な引き金になったとも考えられる。そして、それはまだゲルマン部族法の影響色濃いドイツには広まっていなかった。
- 遍歴騎士(Freelancer)とは、その多くが磨き上げる手間いらずの黒い鎧を愛用し、盗賊に転落したり汚れ仕事に手を染める者が多かった事から「黒騎士(Dark Knight)」と呼ばれ蔑まれていた集団である。
ドイツでも10世紀前半より不自由身分から成り上がったミニステリアーレ(Ministeriale、家士)と呼ばれる非貴族騎士(隷農騎士)が現れた。次第に力をつけ、12世紀に入ると封土も与えられて貴族たる自由騎士とほとんど区別がつかなくなるが、その後もフランスやイギリスの家臣と異なり特定の君主への忠誠心は乏しいままだった事で知られる。平気で複数の君主と封臣契約を結び、なかには「皇帝を含めず四十四人の領主と契約していることが 自慢」だったミニステリアーレまでいたという。
中世の詩人フライダンクは「神は三つの身分をつくりたもうた。祈る人、戦う人、耕す人である」と歌った。10世紀末頃にはかなり広まっていた考え方である。「祈る人」である聖職者はともかく「 戦う人」の身分固定化は 戦争の様相が変化し、その結果、かなり兵農分離が進んだことを示している。
- かくして英国ではノルマン・コンクェスト(1066年)が遂行され、南イタリアではロンバルディア(ランゴバルト)人貴族の叛乱に付け入ったロベール・ギスカール率いるノルマン人騎士達が1059年から1071年にかけて所領を確保し、1084年にローマを征服し掠奪した。
- さらには1081年から1085年にかけてはバルカン半島へも新出。イタリア半島に南下してきた神聖ローマ帝国の介入とロベールの熱病による病死のせいで計画自体は挫折したが、東ローマ帝国首都コンスタンティノープルでも同様の振る舞いに及ぼうとした事実は揺るがない。
- ノルマン人騎士達の活躍に鼓舞されたか北フランス諸侯達も第一回十字軍(1097年〜1099年)でアンティオキアやイェルサレムに進出。これにはロベールの息子ボエマンに率いるノルマン騎士団も参加しアンティオキア公国を建設している。
こうした動きを支えたのは乗馬突撃能力に長けた100騎〜200騎の重装槍騎兵で構成された騎士団を編成したら国家建設すら可能となる軍事的ロマンあるいはゲルマン諸族や北方諸族の伝統に基づくハスカール(従士)制に従って「家臣団」を形成した首領が実際に領土と領民を獲得して領主になれた時代性であった。
ハスカール(古ノルド語:Huskarl)/ハウスカール(英語:Housecarl)
11世紀初頭頃から文献記録に登場するゲルマン民族、特に北欧やイングランドで見受けられた軍制の一種。
小規模とはいえ幼少の頃から高度な戦闘訓練を受けて首領や王侯貴族に私兵として仕えてきた職業軍人によって編成された常備軍であり、普段は食客として暮らし、有事の際には報酬として主に金銭や略奪品の分け前などを受け取っていた。
ただしあくまで自発的な戦闘集団であった為に主君に絶対服従を誓うとは限らず、実際首領や王侯貴族が略奪を禁止したり十分な報酬を支払わない場合、彼らを排除したり見捨てたりする事すらあった。
- イングランドへはスヴェン1世双叉髭王(デンマーク王985年〜1014年、ノルウェー王985年〜995年、1000年〜1014年、イングランド王1013年〜1014年)が持ち込んだとされ、この土地でのハスカールは王宮に住み、1人の伯に対して250~300人が仕えていたという。当時のイングランドとしてはほぼ最強の戦士集団であったが消耗補充能力に乏しく、その事がヘイスティングズの戦い(1066年)で不利に働いたとも。なにしろこの戦いではハロルド2世が戦死した後も配下のハスカールが最後の一人に至るまで果敢に戦い、討ち死にしていったとされているのである。そういうハスカールもあった?
- 中世ロシアのキエフ大公国、およびその他の諸公国に存在した親衛隊ないし従士団であるドルジーナ (Druzhina) もまた、元来はロシアに侵攻したヴァイキング(ヴァリャーグ)のハスカールが起源とされる。
- こうしたヴァイキング(ノルマン人)の傭兵部隊は東ローマ帝国ではヴァラング隊 (Varangias) あるいはヴァリャーグ(Varyag)と呼ばれ皇帝の親衛隊として仕え、ノルマン騎士団に対抗出来る唯一の戦力として重宝された。恐らくドゥビナ河とドニエプル川を伝って黒海まで進出し、東ローマ帝国に雇われてノルマン人の好敵手となったスェーデン人冒険商人達あたりではないかと推察されている。
一方、十字軍に招集された封建的騎士(伯とその従者)達は「騎士は攻撃を継続することで勇武を示すことが常に要求される」とする「騎士道の規律(アイテム(Item)=常に前衛(avante garde)であり続ける事を要求される究極の督戦条項条項)」の遵守を誓わされ、自らも部族連合的結集力を背景に先陣争いの功績を競い合い、伝統的乗馬突撃による決戦以外の一切を否定する倫理規定に従って生きたと考えられている。
他方、初期アナール派を代表する一人たるマルク・ブロックの「封建社会(Feudal Society、1939)」には「この最も厄介な分子(騎士達の事)を瀉血するように(十字軍 として)圏外に出すことによって、フェーデ(私闘)で窒息して死滅することから免れたのである」とする。おそらくどちらの側面もあったのであろう。また「空気を読まず乗馬突撃」の気風は時代が下るほど敗北しかもたらさなくなっていく。
そして「見返りが無ければ参戦しない(参加そのものが目的なら、義理だけ果たしたら帰る)」という彼らの現金な態度が「レコンキスタの不人気・東方開拓の人気」なるトレンドを発生させたり、騎士道修道会を誕生させたりしてきたという話。
一方「アストゥリアス貴族(西ゴート王国遺臣)やブルゴーニュ貴族(ブルグント王国遺臣)やロンバルディア貴族(ランゴバルト王国遺臣)の末裔らしい人々」は文献上「聖職者などの従軍者の出自」として登場。またこれらの地域は実際にクリューニュー修道院(10世紀末~)やシトー修道院(11世紀末~)が建てられ始めた場所でもあるんですね。
ブルゴーニュ領ネーデルラント(蘭Bourgondische Nederlanden,1384年~1477年) - Wikipedia
ブルゴーニュ公爵が治めた低地諸国の諸領地の総称であり、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクとフランス北部、ドイツ西部を含んでいた。元々はもともとフランドル伯領で、フランドル伯ルイ2世(Louis de Mâle)が1384年に死亡した際、娘のマルグリット3世の夫であるヴァロワ=ブルゴーニュ家のフィリップ豪胆公が継承。フィリップ豪胆公はブルゴーニュ公も兼ねており、この後約100年間、この地はブルゴーニュ公が治めることになる。
この地方にはいくつもの司教区や独立都市が存在し、それぞれが独自の税制や法律を運用している上に、変更に対してはそれぞれが権利を主張し、統一に対しては大きな障壁となっていた。ブルゴーニュ公による支配権限を拡大する試みは、独立した地元の貴族により所有される個々の町による反乱により失敗した。その一方で、事務員で構成された官僚機構による近代化した中央政府は、ブルゴーニュ公が何世紀もの間芸術的活動に対する支援を行ったり、すばらしい宮廷生活を送ることを可能にした。
*もしかしたらブルゴーニュでもそうだったから容易に対応できたとか?「ノルマン・コンクエスト後の功臣への所領下賜は「領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的権威体制」が構築不可能なほど細分化されていたので土地使用者と土地経営者と小作人が早々に分離した」とか「ボルドーの銘柄はシャトー単位だが、」とかそういう事なのでは?
そして(元来はロマネスク時代にノルマン騎士団が始めた戦争にローマ教皇庁が大義名分を与え、北フランス諸侯なども便乗した)十字軍運動による地中海文化圏への欧州文化圏の接続は、市場貨幣経済の浸透(およびその副作用としての勝ち組と負け組の峻別=貧富格差の拡大)を引き起こし、その結果成立した新興都市ブルジョワ階層(同時代には「商人ハンザから都市ハンザへ」みたいな流れもあった)を発心させ「財産を共有する参事会」を経てドミニコ修道会(1206年~)やフランチェスコ修道会(1208年~)設立に向かわせた。
*そういえばインドにおける法華経の成立過程もこんな感じだった様な。在野信者の逆襲。拭い去れないマサラ・ムービー感。まぁ「大衆」向けだから「ト書き:ここで不信心者100人が踊りながら去る」とか「地面が割れて地涌菩薩が現れて目からビームの大仕掛け」とか全然あり…
すると差し詰め(ドミニコ修道会やフランチェスコ修道会を意識して設立され、旧体制側からのモラル改革を追求した)厳律シトー修道会(O.C.S.O.)あたりは、日本史でいうと(新興鎌倉仏教登場を意識して、旧体制側からのモラル改革を追求した)真言宗や律宗の改革派に該当する?
仏教でいう「戒律=僧の送るべき生活規範」に該当するのが「ベネディクト宗教戒(6世紀~)=修道士の送るべき生活規範」であり、ロマネスク時代(10世紀~12世紀)にはこれが「発心して修道院を立てたり、そこで実際に修道士として生活する人々」ばかりか「発心して十字軍運動やレコンキスタ運動や東欧開拓運動の最前線で戦う人々」や「巡礼者」が共通して尊ぶ宗教的規範となっていた訳です。ゴシック時代(12世紀末~16世紀)にはさらに「使徒行伝」に記述された使徒達の振る舞いを理想視して「在野で托鉢しながら布教活動を行う教化僧」なる概念が追加されます。これは恐らくベネディクト宗教戒の世界観における「祈る」という行為があくまで「(沈黙のうちの)それぞれの個人単位における内なる良心との主観的対話」の範囲内に止まり、異端者との対決に不可欠な「(他の一切の助力に頼らず、対話や演説のみを通じて)第三者に自分が正しいと信じる事を堂々と論じ相手を説得する」スキルについて触れない事への不満に由来しています。
逆を言えばゴシック時代(12世紀末~16世紀)を特徴付けるのは以下となってくるのです。
- 異端派が次々と現れ「何が正しいかについて不特定の誰かに堂々と示し納得させる技術」が必要となってきた…「スコラ学=(12世紀ルネサンスを通じてラテン語に翻訳された)ヘブライ語、ギリシャ語、アラビア語原典の解釈によって補強された正しい教説展開」や「ゴシック建築(魅せる聖書)=文字に依らず視覚的効果だけで鑑賞者に荘厳なる真理を伝える」の登場。
- 「階層や身分が上の人、戦えば強い人、よりお金を儲けてる人はそれだけで正しいのか?」なる懐疑心が生まれた…そういうものに一切依存しない「在野で托鉢しながら布教活動を行う教化僧」が「何が正しいか」について述べ、相手を説得するというファンタジーの登場(そう、あくまでファンタジー。ここ重要。例えば彼らは日本に布教活動に来た時その現実に直面し、妥協を余儀なくされるのである)。
ここではあえてゴシック時代前期(12世紀~13世紀中旬)に話を限って論じている訳ですが、現代に伝わるゴシック概念は、これに続いた「(黒死病流行やその影響を受けた政治や経済の混乱の結果としての)中断期(14世紀)」と「(ダメージからの回復が次第に進んだ)再開期(15世紀~16世紀)」を経た後に形成されて来たものなのですね。
12世紀半ばの北フランスから始まった大聖堂などの宗教建築は、次のような共通の特徴を持っていた。第一には先の尖ったアーチ(尖頭アーチ)で建物の高さを強調し、天にそびえていくような印象を与えようとしていること、第二に建物の壁に大きな窓を開けて堂内に大量の光を取り入れていること、そして第三に、建物を外側から支えるアーチである飛梁などの構造物が外壁からせりだして、建物に異様な外観を与えていることである。
こうした特徴を持った大聖堂などの建築物は北方のヨーロッパが獲得し始めた独自の様式であったが、均整のとれた古典古代世界の文化を崇敬するイタリアの知識人たちは、いびつで不揃いな外見などに高い価値を認めず、侮蔑をこめてイタリア語で「ゴート人の (gotico)」と呼んだ。ゴート人はゲルマン人の古い民族で、実際には大建築とは無関係であったが、野蛮な民族による未完成の様式という意味をこめてそう呼んだのである。ゴシックという言葉はここに由来している(英: gothic / 仏: gothique / 独: Gotik)。
ゴシック様式ファッション(服飾史)
15世紀前半に西ヨーロッパで生まれた奇抜な装飾、誇張された体型、はっきりとした色づかいを特徴とするファッション(現代のゴシック・ファッションとは異なる)。
ゴシックアーマー(プレートアーマー)
15世紀後半のドイツで生まれた鎧。板金に畝をつけ、つま先などをとがらせているのが特徴である。
ゴシック・ロマンス
ゴシック様式の宗教建築は、建物自体の壮大さに加えて、異国や異教の影響を受けた怪物やグロテスクな意匠がさまざまに取り込まれている点にも特徴がある。18世紀後半のイギリスでは、こうしたゴシック風の修道院や邸宅を舞台にした一種のホラー小説が流行し、それはゴシック・ロマンスと呼ばれた。
別荘のストロベリー・ヒル・ハウス(Strawberry Hill House)を自分好みの中世ゴシック風に改築し、敷地内で印刷した「オトラント城奇譚(The Castle of Otranto,1764年)」を発表したホレス・ウォルポール(Horace Walpole, 4th Earl of Orford, 1717年~1797年)。
同性愛スキャンダルによって所領への逼塞を余儀なくされ、そこにシトー派風僧院を建てて千夜一夜物語にインスパイアされた幻想小説「ヴァセック(Vathek,1786年)」をフランス語で発表したウィリアム・トマス・ベックフォード(William Thomas Beckford, 1760年~1844年)。
「ディオダティ荘の怪奇談義(1816年5月)」を契機に「フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス(Frankenstein: or The Modern Prometheus, 1818年3月11日)」を執筆したメアリ・シェリー(Mary Wollstonecraft Godwin Shelley , 1797年~1851年)。
レディング修道院跡やラドクリフ夫人のゴシック小説に刺激されて「ノーサンガー・アビー(Northanger Abbey, 刊行1817年)」を執筆したジェーン・オスティン(Jane Austen, 1775年~1817年)
*これはこれで日本人の間に十分な理解が浸透してない部分。詳細はそのうち稿を改めて。
とある歴史家の分析によれば、この間に実際にはこういう変化があった様です。
古代史を専門とし『暴力と不平等の人類史』を上梓したスタンフォード大学教授のウォルター・シャイデルは、「戦争・革命・崩壊・疫病」という4つの衝撃を中心に古代から現代までを分析している。中世ヨーロッパの労働者の生活は、疫病の感染爆発後、どのように変化したのか。
「世界は一変した」
世界は一変した。感染爆発のさなかとその直後には、人間の活動が低下した。長期的には、ペストとそれがもたらした混乱が、人びとの考えや社会制度に広く爪痕を残した。
つまり、キリスト教の権威が弱まり、快楽主義と禁欲主義が同時に繁栄し、恐怖と跡継ぎがいない者の死亡が原因で、慈善活動が増えたのだ。芸術のスタイルまで影響を受けた。医者は長年守ってきた原則の再考を迫られた。
「経済的バランス感覚」の崩壊。
最も根本的な変化は、経済領域、なかでも労働市場で起きた。黒死病がヨーロッパに達したのは、3世紀にわたって人口が大きく──2倍、時には3倍に──増加していた時だった。西暦1000年ごろから、技術革新、農耕法と収穫高の改善、政情不安の改善があいまって、定住が進み、生産性が向上し、人口が増えた。都市は大規模化し、数も増えた。
ところが13世紀後半には、この長期にわたる繁栄は自然に終息した。中世の気候最適期が終わりを告げると、生産性が低下し、需要が供給を上回りはじめたため、飢えた人びとが増加して食料価格が上がった。耕作に適した土地の拡大は止まり、牧草地が縮小したせいで、タンパク質の供給は減った。
同時に、ますます質素になる食事において基本的な穀物がそれまで以上に主要な食品になった。人口圧力によって、労働の価値が下がり、したがって実質所得が減少した。生活水準も、せいぜいのところ横ばいだった。
14世紀初めには、気候が不安定で収穫が減った結果、壊滅的な飢饉となって、状況はいっそう悪化した。人口水準は14世紀初めの25年間で下がったものの、生活が維持できるかどうかの危機はさらに一世代のあいだ続き、動物間流行病のせいで家畜が激減した。
黒死病によって人口は激減したものの、物理的なインフラは損なわれずに残った。生産性が向上したおかげで、人口の減少ほど生産高は減らなかったため、1人当たりの平均的な産出量と所得は上昇した。
時おり主張されるように、ペストによって、本当に労働年齢にある人びとがそれより若いあるいは老いた人びとよりも多く命を落としたかどうかはわからないが、ともかく労働力に対して土地が余るようになった。
地代と金利は絶対的にも賃金比でも下がった。地主にとっては損だが、労働者は利益を望めそうだった。とはいえ、こうしたプロセスが実際の暮らしにおいてどう展開するかは、中世の労働者に有効な交渉力をもたらす制度と権力構造にかかっていた。
当時の西欧の観察者は、人びとの大量死によって賃上げ要求が高まったことにすぐに気づいた。カルメル会の修道士ジャン・ドゥ・ヴネットは、1360年ごろの年代記でペスト流行後の様子について書いている。
何でもふんだんにあるものの、価格は2倍だった。調度品や食料はもちろん、商品、賃金労働者、農業労働者、使用人などすべてがそうだ。唯一の例外は土地と家屋で、それらは現在でも供給過剰の状態にある。
作家のウィリアム・ディーンが書いたとされるロチェスター小修道院年代記によれば、労働者不足が続いたため、庶民は雇用労働など歯牙にもかけず、3倍の賃金で貴人に仕えるという条件にもなかなか首を縦に振らなかった。
雇い主はただちに、人件費の上昇を抑制するよう当局に圧力をかけた。イングランドが黒死病に襲われてから1年も経たない1349年6月、国王は労働者勅令を発布した。
住民の大部分、特に労働者と使用人(「召使い」)がペストで死亡して以降、多くの人びとが主人の窮状と労働者不足につけこんで、法外な給金をもらわないと働こうとしない……イングランドの領土に住むあらゆる男女は、自由民であれ非自由民であれ、身体が健康な60歳未満で、商売や特殊な技能の行使によって生活しているのではなく、耕す必要のある自分の土地からの不労所得がなく、他人のために働いているのではない限り、自分の地位とつりあう仕事を提供されたらその申し出を受ける義務が生じることを、ここに定める。その料金、仕着せ、支払い、給金は、わが国の統治の20年目[1346年]か、5、6年前の適切な年に、彼らが働いている地域で通常支払われていた金額でなければならない……多く受け取っていることが発覚すれば、牢獄行きとなる。
この勅令の効果は実際にはあまり上がらなかったようだ。それからわずか2年後の1351年、労働者制定法という別の法令で、こんな訴えがなされている。
先の勅令で述べられた雇われ人は、この勅令を無視して自分自身の豊かさや並外れた強欲さを優先している。20年目およびそれ以前に受け取っていた金額の2倍から3倍の仕着せや賃金をもらわない限り、偉人やその他の人びとのために働こうとしない。こうして、彼らは偉人に大変な損害を与え、あらゆる庶民を貧しくしている。
そして、このやっかいな状況を是正すべく、さらに詳細な制約と罰則が科されることになった。ところが、一世代も経ずしてこの施策も頓挫した。1390年代初め、レスターのアウグスティノ修道会の修道士、ヘンリー・ナイトンは年代記にこう書いている。
労働者はひどく思い上がっていて血の気も多いため、王の命令など気にも留めなかった。彼らを雇いたければ、その言いなりになるしかなかった。というのも、刈り取らずに農作物を失うか、労働者の傲慢さと貪欲さに迎合するか、2つにひとつしかなかったからだ。
もう少し中立的な言葉で言い換えると、政府の命令と抑圧によって賃金上昇を抑えようとする試みに対し、市場原理が勝ったということだ。雇用主、特に地主の個人的利益が、労働者に対して共同戦線を張ることによる強制できない集団的利益を上回ったからである。
イングランドばかりかほかの地域でも事情は変わらなかった。1349年、フランスも同様に賃金をペスト前の水準に抑えようとしたが、さらに早く負けを認めるはめになった。1351年には、改正法によって賃金を3分の1上げることがすでに認められつつあった。まもなく、人を雇いたい時は相場どおりの賃金を支払わなければならなくなった。
経済史家のロバート・アレンと共同研究者の尽力により、今では熟練・非熟練の都市労働者の実質賃金を示す長期的な時系列のデータが数多く手に入る。このデータは時に中世にまでさかのぼり、時空を超えて体系的に比較できるよう標準化されている。
賃金が上昇し、肉を多く食べるようになった労働者たち。
ヨーロッパとレヴァント地方の11の都市で記録された非熟練労働者の賃金の長期的傾向から、明確な全体像が読みとれる。ペスト発生前の賃金がわかる少数のケース(ロンドン、アムステルダム、ウィーン、イスタンブール)では、ペストの流行以前は賃金が低く、その後急速に上昇している。
実質所得は15世紀初めから半ばにかけてピークに達している。この時期、ほかの都市でも同様のデータが残されており、やはり賃金上昇の動きが見られる。
14都市の熟練労働者の賃金についてもほぼ同じ構図が浮かび上がる。データが得られた地域では、ペスト発生の直前から15世紀半ばまでに人口の変化と実質所得には際立った相関関係がある。調査対象となった全都市で、人口が最低になった直後に実質所得がピークに達したのだ。人口が回復してくると賃金は減少に転じた。多くの都市で、1600年以降は人口が増え続けて実質所得は下がる一方だった。
地中海東岸でも同様の結果が見られる。黒死病の発生後、期間はヨーロッパより短かったものの、人件費が急騰したのだ。歴史家の アル=マクリーズィーはこう述べている。
職人、賃金労働者、荷物運搬人、使用人、馬丁、織工、作業員といった人びとの賃金は数倍に跳ね上がった。しかし、彼らの多くはもういない。ほとんどが死んでしまったのだ。この種の労働者を見つけるには、必死になって探す必要がある。
ペストの犠牲者からの遺贈や、遺産相続した生存者からの寄贈に支えられ、宗教的、教育的、慈善的寄付が急増した。おかげで、人手不足にもかかわらず建設工事が推進され、職人は非熟練都市労働者とともにわが世の春を謳歌した。
それでは実際のゴシック建設様式自体の変遷はどうなっていたかというと…
ゴシック建築(Gothic Architecture)は、12世紀後半から花開いたフランスを発祥とする建築様式。最も初期の建築はパリ近くのサン=ドニ(聖ドニ)大修道院教会堂(Basilique de Saint-Denis)の一部に現存する。イギリス、イタリアの北部および中部、ドイツのライン川流域、ポーランドのバルト海沿岸およびヴィスワ川などの大河川流域にわたる広範囲に伝播した。
原義
「ゴシック」という呼称は、もともと蔑称である。15世紀~16世紀にアントニオ・フィラレーテやジョルジョ・ヴァザーリらが、ルネサンス前の中世の芸術を粗野で野蛮なものとみなすために「ドイツ風の」あるいは「ゴート風の」と呼んだことに由来する(ゴート族の建築様式というわけではない)。
ルネサンス以降、ゴシック建築は顧みられなくなっていたが(この時期をゴシック・サヴァイヴァルと呼ぶ)、その伝統は生き続け、18世紀になると、主として構造力学的観点から、合理的な構造であるとする再評価が始まった。18世紀~19世紀のゴシック・リヴァイヴァルの際には、ゲーテ、フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアン、フリードリヒ・シュレーゲルらによって、内部空間はヨーロッパの黒い森のイメージに例えられて賞賛され、当時のドイツ、フランス、イギリスでそれぞれが自らの民族的様式とする主張が挙がるなどした。
概説
ゴシック建築は、歴史的区分としては1150年頃から1500年頃までの時代を指し、フランス王国からブリテン島、スカンディナヴィア半島、ネーデルランド、神聖ローマ帝国、イベリア半島、イタリア半島、バルカン半島西部沿岸部、ポーランドおよびポーランド・リトアニア共和国の版図に伝わった建築様式をいう。
しかし、これら歴史的・地理的条件が必ずしも相互に対応しないという点や、建築の形態的・技術的要因、図像などの美術的要因の定義づけが難しいという点で、他の建築様式に比べるとかなり不明瞭な枠組みであると言わざるを得ない。特に後期ゴシックは、地方様式とも絡む複雑な現象で、装飾や空間の構成を包括的に述べることはたいへん難しい。
ゴシック建築は、北フランス一帯において着実に発展していた後期ロマネスク建築のいくつかの要素を受け継ぎ、サン=ドニ修道院付属聖堂において一つの体系の中に組み込まれて誕生した。
12世紀中葉から、サンスやラン、パリ、そしてシャルトル、ランス、アミアンでは、これに倣って大規模かつ壮麗な聖堂が建てられることになった。当然、西ヨーロッパでは、このほかにもたくさんの建築物が建設されていたが、イル=ド=フランス地方をはじめとするフランス王国の中心地においてのみ、初期から盛期にいたるゴシック建築の首尾一貫した発展の状況を見ることができる。
ゴシック建築が伝播した他の諸国の政治的・経済的事情は多様で、発達や伝播の過程は複雑な様相を呈し、後期になるとこれが顕著に現れる。しかし、それでもゴシック建築が一定の建築的構成をふまえつつ流布したのは、国々を跨いで独自の組織網を構築していた修道院の活動が大きかった。
ロマネスク建築と同様に、ゴシック建築においてもベネディクト会やシトー会の影響は大きく、13世紀以降はドミニコ会、フランシスコ会などが、ゴシック建築の伝播に寄与することになった。
ゴシック建築は、尖ったアーチ(尖頭アーチ)、飛び梁(フライング・バットレス)、リブ・ヴォールトなどの工学的要素がよく知られており、これらは19世紀ゴシック・リヴァイヴァルにおいて過大に評価されたため、あたかもそのような建築の技術的特徴のみがゴシック建築を定義づけると考えられがちである。しかし、ゴシック建築の本質は、これらのモティーフを含めた全体の美的効果のほうが重要で、ロマネスク建築が部分と部分の組み合わせで構成され、各部がはっきりと分されているのに対し、ゴシック建築では全体が一定のリズムで秩序づけられている。
リューベック、グダンスク、トルン、クラクフなどの北ドイツやポーランドを中心とするバルト海沿岸およびその大河川の流域ではブリック・コシックと呼ばれる、レンガを用いた独特のゴシック建築が発展した。
ゴシック建築以前
ロマネスク建築からゴシック建築への転換は、11世紀末期から12世紀早初期にかけてイングランドとノルマンディー地方において行われた建築活動によってもたらされた。この地方では、すでに交差リブ・ヴォールトを分厚い構造壁に架ける試みが成されていたが、それ自体はロンバルディアやアルザス、プファルツのロマネスク建築においても同様に行われている。
しかし、ここでは後にゴシック建築に共通する、あるいはそれに発展する要素のいくつか(すなわち、フライング・バットレスに発展する側廊の屋根裏に設けられた梁状の控壁とトリフォリウムに発展する二重シェル式壁(ミュール・エペ)など)が指摘されている。 これらの建築活動は後にイル=ド=フランスに引き継がれ、ゴシック建築を開花することになる。
イル=ド=フランスとその周辺部の初期ゴシック建築
1130年、サン=ドニ修道院シュジェール院長が、修道院付属聖堂(現在は大聖堂)の改築工事を始めた。現在、3つの広間を納めた前廊(西正面)と聖歌隊席を含めた一部が現存している。最初に多数の巡礼者のための大きな入り口が造られたが、これは円柱を束ねた支持柱に支えられた尖頭リブ・ヴォールトが空間を分節しており、これがノルマンディーの後期ロマネスクをゴシック建築に発展させたものになっている。
1140年に着工し1144年に完成した内陣は、後の大改修のためあまり残っていないが放射状の祭室と方形の祭室を有するシュヴェで、前廊と同じく革新的なものだったらしい。
しかし、サン=ドニ修道院付属聖堂はあまりにも早熟した建築であり、12世紀後期になるまで比較的小規模な教会でひっそりと真似られるだけであった。
ところで、サンドニ大聖堂、ゴシック様式と切っても切り離せないのが、シュジェという12世紀前半から半ばにかけてサンドニ修道院の院長であった人物だ。この辺りのところはゴシック建築に関する本などに非常に詳しく書かれており、私の知識の範囲を超えているので割愛させて頂くが、このシュジェなる人物、相当処世術に長けた人物であったらしい。
10歳の時に修道院に入るが、その時、後のフランス王となるルイ6世と知り合い、交友を深めることで、以降様々な形で政治に関与していくことになる。当時は宗教と政治は密接に関係していた(また反目していた)ので、宗教と政治の双方で重要な地位を占めるということは、世を牛耳るということをも意味していた。
国王の権力を後ろ盾にシュジェはサンドニ修道院の地位を高め、確固たるものとしていく一方で、宗教界でも、その処世術を生かし、教皇にも覚えの高い人物となり、押しも押されぬ人物となっていく。
こういった地位を確立した上で、彼は自分の修道院の改築に着手する。ゴシック研究の第一人者オットー・フォン・ジムソンがその著「ゴシックの大聖堂」で、シュジェ及びサンドニ大聖堂に関し、非常に詳細かつ緻密に論述しているが、彼は、コンスタンチノープルのハギア・ソフィア、あるいはソロモンの神殿にインスピレーションを得、ここサンドニにそれを再現しようとした。
1140年に内陣が着工され、その僅か4年後の1144年に献堂されている。この内陣こそが交差ヴォールトを全面に採用、壁面にはステンドグラスが嵌め込まれた周歩廊祭室を持つ、後にゴシック様式と呼ばれるものとなるのである。
その印象は圧倒的で、スケールがそれ程大きくなく、周歩廊祭室の光が人の目線に直に飛び込んでくること、上部には壁が殆どない程ステンドグラスで埋め尽くされていることなどから、シャルトルやパリの大聖堂よりははるかに発展したゴシック様式のように思える。
もっとも内陣上部及び身廊は、シュジェの時代のものではなく13世紀前半の建築家ピエール・ド・モントルイユの手によるものではあるが。とにかくここがゴシック様式発祥の地であり、同様式を確立したシュジェの功績は建築史上、美術史上、大変輝かしいものとなっており、どのような本を読んでも、ここのところは見解が一致している。
サン=ドニと同じ頃(1130年頃から1164年)に建設されたサンス(ブルゴーニュ地方)のサンテティエンヌ大聖堂は、周歩廊があるものの袖廊はなく、立面の強弱というロマネス建築特有の構成を持っている。ただし、六分ヴォールトと3層にわかれた身廊立面はゴシック建築の要素を持っており、これは以後のゴシック建築に影響を及ぼした。
12世紀後半になると、ブルゴーニュとノルマンディーでは活発な建設活動が行われ初期ゴシック建築の発展を促したが、これは個々の独自性やロマネスク建築の伝統を阻害するものではなかった。ノワイヨンのノートルダム大聖堂、サンリスのノートルダム大聖堂(16世紀の改築により当時の造形はあまり残っていない)、トゥルネーのノートルダム大聖堂、サン・ジェルメール・ド・フリなどは、それぞれロマネスク建築特有の構成を持つもの、あるいは逆にその伝統的形態を全く失ったものもある。
イル=ド=フランスとその周辺部の初期ゴシック建築は、シャンパーニュに広がった。シャロン=アン=シャンパーニュのノートルダム=アン=ヴォー聖堂とランスのサン・レミ大聖堂の後陣は、初期ゴシック建築の最終的な完成形態で、両者ともに後陣の立面は4層構造で、大きな開口を取ることによって鳥籠のような線的で軽快な構造となっている。シャンパーニュでは、他にソワッソン大聖堂の袖廊がこれと全く同じ構成を有している。
ブルゴーニュではロマネスク建築が高度に発展していたため、その伝統が生き続けた。ブルゴーニュにゴシック建築が導入されるのは1170年頃であり、これはヴェズレーで建設されたサント・マドレーヌ大聖堂の内陣に見ることができる。全体の構成はソワッソン大聖堂の袖廊に近いが、立面は3層構造で、線的な要素を強く意識したものになっており、これは13世紀以降、この地で盛んになる後期ゴシック建築のデザインに受け継がれた。
プランタジネット・ゴシック
ノルマンディでゴシック建築の雛形が形成されたにもかかわらず、プランタジネット家の勢力下にあった北、西フランスでゴシック建築が導入されるのは遅かった。アンジュー、メーヌ、ポワトゥーなどにゴシック建築が建設されるのは13世紀初頭になってからであるが、プランタジネット家の支配下で形成されたゴシック建築は、イル=ド=フランスとは異なる形態を獲得した。
プランタジネット・ゴシックの代表的な建築物はアンジェのサン・モーリス大聖堂である。極度に湾曲したヴォールトを頂く身廊の立面にはアーケードやクリアストーリなどの分節化が見られない。もともと単廊式で木造天井を持った建築物であったらしく、この形状はポワティエのサンティレール聖堂も同様で、ロマネスク建築の伝統を残す。
アンジェ大聖堂とは異なる形式として名高いのがポワティエの大聖堂で、これは1162年に起工されたが、完成は13世紀末のことである。ほぼ同じ高さ、同じ幅の身廊と側廊で、後にホール式と呼ばれる教会堂の空間に近い。アンジェのサン=セルジュ聖堂はこの形式に則った平面となっているが、細い柱によって分節されたベイと枝リヴによって分節されたヴォールトが、さらに華美な印象を与える。
アンジェ、ポワティエともに、聖堂の形式としてはロマネスク建築において見られるものであり、細部については洗練されているものの、全体としての革新性はイル=ド=フランスのゴシック建築を超えるものではない。プランタジネット朝の建築は後期ロマネスク建築と初期ゴシック建築との間にそれほどの違いがないことを証明している。
カンタベリー大聖堂とリンカン大聖堂
イングランド本土に建設された最初の本格的なゴシック建築は、1174年に起工されたカンタベリー大聖堂である。最初の建設はギョーム・ド・サンスによって設計されたが、不慮の事故によって工事はイギリス人ウィリアムに引き継がれた。後陣が二重シェル式で造られており、全体として彫塑性の強いイングランドのロマネスク建築の伝統を残している。
リンカン大聖堂はカンタベリーの後継であり、パリのノートルダムと対照的なロマネスク建築の厚い壁を思わせるクリアストーリ、屋根裏に開いたトリフォリウムなどの特徴は、イングランドの独自性を物語っている。
フランス王国の盛期ゴシック(クラシカル・ゴシック)
1194年の火災によって焼け落ちたシャルトルのノートルダム大聖堂は、1210年には身廊が再建され、1230年頃にはおおよその完成をみた。盛期ゴシックの最高傑作と呼ばれるこの大聖堂は、ランとパリのノートルダム大聖堂を踏襲した平面(袖廊はラン、二重周歩廊はパリ)をもっているが、内部はかなり独創的な空間になっている。身廊側の柱身はヴォールトの始まる高さまで真っすぐに伸びており、それまでの聖堂の柱が独立した印象を与えていたのに対して、リブとともに垂直性の高い輪郭となっている。身廊の壁面は高いアーケードと低いトリフォリウム、そして採光を得るためにアーケードと同じ高さのクリアストーリを持った3層構造となっており、パリのノートルダム大聖堂と比べると全体のプロポーションが再構成されているのがわかる。ここに嵌め込まれた166もの聖書のモティーフをちりばめたステンドグラスと多数の彫刻で飾られた扉口によって、シャルトル大聖堂はしばしば中世スコラ学世界の結晶とみなされ「凍れる音楽」とも評される。なお「凍れる音楽」という言葉はドイツの哲学者シェリングに由来。
13世紀シャルトル大聖堂は当時流行した形式に沿うような大規模な改修が計画されたが、大聖堂内部の完成度の高さが、それを断念させるほどであった。外観については、本来7つの塔が建てられる予定だったが、こちらは未完成に終わっている。シャルトル大聖堂の影響は大きくソワッソン大聖堂の内陣、ランスとアミアンのノートルダム大聖堂にそれを見ることができる。
ランスのノートルダム大聖堂は、歴代のフランス国王を聖別する司教座であり、政治的な意味でも重要な聖堂である。その平面と立面の構成は、シャルトル大聖堂に準じたもので、装飾を除けば両者の違いはほとんどない。ランスの大聖堂は、シャルトルとは対照的に内部空間にも植物を模した豊かな装飾をもっており、この点はシャンパーニュ地方の特性を示している。外観についても、シャルトルよりも豊かな装飾で飾られており、フライング・バットレスを受けるキュレの修まりはより洗練されている。ただし建設過程は複雑で、4人の主任建築家が入れ替わっており、これによる施工上の混乱が見られる。
アミアンのノートルダム大聖堂は、盛期ゴシックの最も洗練された大聖堂である。1221年ロベール・リュザルシュによって計画されたその大きさは、前述の大聖堂を全て凌駕しており、このため身廊最上部の薔薇窓下に四組窓が追加されている。一つのベイに対して二つの三組アーチの窓が取り付けられ、これらを除いては、ほとんどシャルトルの形態と共通するが、その構成は完全なる均衡を保っている。内陣はすでにクラシカル・ゴシックのものではなくレヨナン式ゴシックの段階に達している。
シャルトルの系譜に連なる最後の大聖堂は、ボーヴェのサン・ピエール大聖堂である。構造的には完全な失敗作で1284年に大規模な崩落をおこしたが、そのまま16世紀まで再建は行われなかった。この大聖堂の建設以後、この種の大聖堂はまったく建設されなくなった。
盛期ゴシック建設の伝播
シャルトルはゴシック建築の一つの頂点であるが、これとは異なった系統に属する聖堂も存在する。盛期ゴシックは、シャルトル大聖堂で確立された系譜のみで語れるものではなくイングランドやノルマンディ、ライン川流域やアルプスでは、全く別系統の様式が採用された。
ブールジュのサン・テティエンヌ大聖堂は、シャルトルとほぼ同時期に建設された。平面は、パリのノートルダムを直接の源泉としているように思われるが、袖廊はなく、主廊立面は、全体的にほっそりとした印象を与える非常に高いアーケードと、背の低いトリフォリウム、小さなクリアストーリから成る。シャルトルに比べると重量の軽い構造で出来ており、このため構成はとても独創的で、他のいかなるゴシック教会堂にもこれに類似するものはなく、またこの構成を真似たものもたいへん少ない。
ブールジュの影響を受けた数少ない建築物の一つに、ル・マン大聖堂がある。この聖堂の建設経緯は複雑なものであったらしく、ブールジュとの共通点は高いアーケードを保有することをおいて他にない。この部分は、従ってブールジュの建築家の手によるものと考えられる。高窓を高くするためにトリフォリウムが排除され、身廊立面はアーケードとトリフォリウムの二層構造であるが、これは後のレヨナン様式の到来を告げるものである。
シャルトルをはじめとする大教会堂が建設されていた頃、イングランドとノルマンディ、ライン川一帯、そしてアルプス山脈周辺部では、これらとは違ったゴシック建築が形成されようとしていた。北方地域では、ゴシック建築特有とされる薄い壁に対する意識は少なく、むしろ構造壁の厚みを利用した意匠が好まれた。
オセールのサン・テティエンヌ聖堂は、1215年に起工されたもので、内部はクリアストーリ、トリフォリウム、アーケードの3層構造から成るが、中間部のトリフォリウムは二重シェル式壁(ミュール・エペ)を意識しており、通路状で背が高く、小円柱によって分節される。
この教会堂と同じ立面を有するものが、1220年頃に起工されたディジョンの教区教会堂であるノートルダム聖堂である。ただし、こちらは下方の窓の部分とトリフォリウムの上部(クリアストーリの下部)に通路が設けられている。両教会堂ともに、その他の意匠は初期ゴシックのもので、クリュニー修道院のノートルダム聖堂やリヨンの大聖堂の身廊部分、シャロン=シュル=ソーヌの大聖堂なども、ほとんど同じ意匠の内部空間を持つ。
カンタベリーでの大聖堂建立によって、イングランドのゴシック建築は1180年頃から定着しはじめる。アーリー・イングリッシュ(early english)と呼ばれる段階における著名な建築物は1225年頃に起工したリンカン大聖堂の身廊である。カンタベリー大聖堂に由来する意匠を持つが、トリフォリウムは身廊に解放された通路状のものではなく、イングランドのロマネスク建築に見られる屋根裏に開いた開口部となっている。壁面はかなり厚く作られており、全体的にずんぐりとした印象で、シャルトル大聖堂のような上方への指向性はない。
ウェストミンスター寺院は、このようなアーリー・イングリッシュの形態に対し、大陸のレヨナン式の意匠を上手く融合させ、新たな空間を創出した。ウェストミンスターの様々な要素、トリフォリウムやクリアストーリは典型的なイングランドの形態であるが、三葉形と多弁飾りの複合トレーサリーといった装飾や、後陣のヴォールト架構は明らかに大陸由来のものである。特に窓のトレーサリーは、以後のイングランドのゴシック建築に大きな影響を与えた。
1250年頃に始まる後期ゴシック建築は、それまでのゴシック建築の様相とは本質的に異なる複雑な現象である。後期の教会堂建築は、どちらかと言うと小型化の様相を示しており、これによって内部空間の立面を上・中・下と区切る分節は解け、装飾に対する嗜好性が全体の空間に対する意識を凌駕するようになった。
フランスの後期ゴシックを特徴づけるのは、全体のダイナミックな躍動感ではなく、細部の技巧的洗練と開口部の拡大である。このような現象の第一歩が1250年から始まるレヨナン式で、これは先行するいくつかの建築物にその萌芽が見られる。
サン=ドニ大聖堂は、シュジェール院長による工事の後、1231年に教会堂はさらに再建工事が行われ、1281年に竣工した。この工事で内陣の上部が建て直され、身廊と袖廊が新規に建築された。身廊はクリアストーリが拡大されたため、トリフォリウムの上が全てランセット窓で構成されており、また、トリフォリウムの外側の壁にも開口が設けられたため、身廊立面の全体が透明な壁と化している。
サン=ドニのように質量感を出さないような意匠は、1235年頃に建設されたサン・ジェルマン・アン・レー城館の礼拝堂にも見ることができる。礼拝堂の窓と西側のバラ窓の浮き彫りはレヨナン式の意匠そのものであるが、一方で、二重シェル式壁に特有の(特にブルゴーニュ特有の)特徴をも備えている。
サン=ドニも含めた1230年~1250年頃の建築物は、レヨナン式ゴシックの前段階にあたるもので、コート・スタイルあるいはステイル・ロワイヤル(宮廷様式)とも呼ばれる。
聖王ルイが東ローマ帝国から購入したキリストの荊冠の保管所として、1242年頃に建設されたサント・シャペル礼拝堂は、控壁と鉄製補強材によって、軽やかな内部空間を形成している。ステンドグラスと彫刻は技巧性が高くレヨナン式ゴシックへの傾向を如実に現している。
パリに残るこの時期の建築物はノートルダム大聖堂の袖廊で、1245年~1250年にかけて建設された。トリフォリウムに類似する横に長いギャラリーと、その上部に設けられた巨大なバラ窓、そしてその間のスパンドレルにも設けられた開口部が、壁の重量を喪失させる。また、袖廊のファサードは、後にフランス国内外で模倣されるほどの影響力を持った。
サン=ドニとパリのノートルダムは、トロワ大聖堂の内陣と1236年頃に起工されたストラスブールのノートルダム大聖堂に影響を与えている。特に後者は、レヨナン式の影響を神聖ローマ帝国の領内に拡大させたと言う意味で重要である。オットー朝時代に建設された基礎の上に建設されたストラスブール大聖堂は、ブルゴーニュ特有の意匠を踏襲しつつ、コート・スタイルの要素を取り入れたものとなっており、ファサードについてはパリのノートルダム大聖堂袖廊の影響を認めることができる。
サン=ドニとサント・シャペルで高度に洗練されたレヨナン式ゴシックは、北フランスと南フランス、そしてイングランドと神聖ローマ帝国にまで広がる。イタリアやスペインでは、これに反抗するような意匠も形成された。
14世紀前半に入ると教義的と呼べるほどに体系化されたので、後期ゴシック建築は教条的で懐古趣味的と批判されることもある。実際1284年に完成したボーヴェのサン・ピエール大聖堂の後陣、1272年に起工されたナルボンヌの大聖堂、1280年頃に起工されたボルドーのサンタンドレ大聖堂、1308年起工のヌヴェール大聖堂などレヨナン式の教会堂を挙げることができるが、これらには特に目立った形態の進展はない。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路というのをご存知でしょうか?
日本では空海ゆかりの四国八十八か所巡りというのがありますが、キリスト教信者には聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラ(スペイン)に続く巡礼路というのが存在します。
エルサレムやローマという聖地は日本人にもよく知られていますが、このサンティアゴ・デ・コンポステーラ関しては、それほど知られていないように思います。
今でも毎年10万人以上の人たちがこの巡礼を行っており(徒歩、自転車、中には馬という人もいるとか)、私もピレネーの方へ行った際には、「巡礼者なのだろうな」と思われる人をたくさん見かけました。
サンティアゴ・デ・コンポステーラに続くフランスからの巡礼路は全部で4本ありますが、そのうち一本が、ボルドーを通っています。その巡礼路上の3つの教会(大聖堂)が、1998年にユネスコの世界遺産に登録されました。ボルドーの街自体は2007年に世界遺産に登録されていますので、3つの教会だけが街より先に登録されたということです。
世界遺産に登録された一つが、こちらのサンタンドレ大聖堂です。
フランボワイアン・ゴシック(Flamboyant)
1340年代以降は、百年戦争の最も熾烈な時期であり、また黒死病の流行にともなってイングランドとフランスの建築活動は完全に停滞した。ヨーロッパのあらゆる活動が再び活発化するのは15世紀になってからであり、この時期まで多くの計画が放棄されたままであった。
- 大教会堂は建設されなかったが、この時期にいくつかの城郭建築と都市自治体の公共建築が建てられている。
- 特に城郭建築は、戦時における火器の使用により砦式から稜堡式に移行したが、その結果として居住性は重要性を失い、城郭と宮殿は全く別系統の建築に乖離していった。
15世紀にゴシック建築が復活するが、中世末期の建築は装飾の技巧性が際立つもので、一般にフランボワイアン(火焔式)と呼ばれる。フランスでは古典ゴシックの影響が強く、トレーサリーは幾何学模様のままだったのだが14世紀末から絡み合った曲線が好まれるようになった。このような趣味は、レヨナン式の空間そのものにはあまり影響を与えてはいないが、このレヨナン式とフランボワイアンの混成が、バロック建築の直接の源泉であるとする見方もある。実際に、構造的意味がまったくない小柱や、ヴォールトとは関わりのないようなリブの構成など、構造的な合理性よりも装飾性を求める考えかたは、バロック建築と共通するものと言えるであろう。フランボワイアンの意匠はフランスで生まれたものではなくイングランドのトレーサリーや神聖ローマ帝国のネット・ヴォールトを取り入れたものである。
1480年に起工されたリューのシャペル=デュ=サンテスプリに見られる辻飾りのついた扁平星形ヴォールトは、ドイツからもたらされた意匠で、このような背の低いヴォールトはシャンパーニュで好まれた。
フランス中心部では、古典ゴシックから伝統的に垂直性への嗜好が強く1489年以後に起工されたパリのサン・セヴラン聖堂、および1494年起工のサン・ジェルヴェ聖堂、ルーアンのサン・マクルー教会、そしてモン・サン=ミシェルの大修道院聖堂の内陣などが、このようなフランボワイアンのすばらしい作例として残っている。
後期において、発展的と呼べるゴシック建築の潮流は、フランス本土ではなくむしろイングランドのゴシック建築であった。 イングランドのゴシック建築は、伝統的に3期に分けられる。アーリー・イングリッシュに続き、1290年以降に華飾式または曲線式(decorated gothic)と呼ばれる建築、そして1330年頃から垂直様式(prependicular gothic)と呼ばれる建築が発達した。
イングランドでは、大陸のフライング・バットレスをあまり採用せず、つねに壁の厚さを想起させる意匠を好み、また、多くの場合、湾曲したアプスではなく平たい東端部を採用した。ほっそりしたプロポーションと薄い壁の意匠を意識した例外的な作例は、ウェストミンスター・アビーのほか数えるほどしかない。華飾式の意匠は、このような傾向のなかで形成されたイングランド独自のゴシック建築であった。
1280年~1290年の間に起工されたエクセターの大聖堂は、アーリー・イングリッシュの典型的な平面を持つが、ヴォールトを支える(ように見える)リブは、アーケード柱頭の持ち送りの上から伸びており、身廊立面は垂直に伸びる線的な要素よりも、面的に見える。イングランドでは大きな窓面が好まれたため、この大聖堂でも湾曲したアプスはなく、大きなステンドグラスを持つ平面的な後陣が採用されている。
1290年に起工されたヨークの大聖堂(York Minster)、リッチフィールドの大聖堂などは、エクセターと全く同じ構成で、ほとんど同じ印象を受ける。
イギリスのゴシック建築、国民的様式とされたのが、いわゆる垂直様式である。イングランド南西部とロンドンでほぼ同時期に見られるため、どちらをその起原とするかについては議論がある。あえて直角的構成を採用するなど、大陸のゴシック建築の規範から隔たった概念のもとに形成されているのだが、特にファン・ヴォールトを用いる場合は、天井を支えるのにヴォールトを必要としなかったという点で、すでにゴシック建築ですらない。
1298年に起工し、1341年に完成したブリストルのセント・オーガスティン大聖堂は、バシリカ型ではなく、広間型の平面を持ち、側廊と身廊の高さが同じためクリアストーリが欠如している。従って、内部空間は両者を鮮明に区分することはない。また、ブリストルの建築家たちは、ゴシック建築特有の構成を驚くほど自由に操作し、束ね柱をヴォールトにまで伸ばして、リブ・放射リブ・枝状リブという三段階のヴォールト架構を用いた。側廊の荷重は、簡素な方杖によって横断アーチに渡されておりこれがトンネルのヴールトを形成している。
荷重を方杖によって簡潔に伝達し、これに美的効果をもたらしている最も印象的な例は、ウェルズの大聖堂である。1338年に、交差廊の上部に光塔の建設が計画されたが、この際、塔の荷重を支えるため、交差廊と身廊との間に巨大な方杖が架けられた。その形の奇妙さと大胆さは、大変強い印象を与える。
一方で、ヴォールトに対する自由な発想はグロスターの大聖堂回廊などにも生かされている。グロスターの回廊はファン・ヴォールト(扇形ヴォールト)を用いており、そこに交差リブヴォールトに覆われたゴシック建築の典型的な構成を見ることは不可能である。垂直様式では、交差リブヴォールトが全く捨てられたわけではなかったが、多くの場合、多数の辻飾りが設けられており、その印象は木々の枝張りに例えられたネット・ヴォールトと変わらないものとなった。垂直様式のリブはヴォールト架構とはもはやなんらの関係性もなく、構造的合理性で説明できるものではない。
垂直様式における最高傑作として名高いのが、ウェストミンスター寺院の東端にあるヘンリー7世チャペルである。壁面を埋め尽くす装飾は、ほとんど櫛の目を見るようであり、また天井からは、鍾乳石を思わせる石飾りが、幾つも垂れ下がっている。ここでは本来、石造建築における力学的な都合から誕生したヴォールトが、ほとんどその力学を無視するかのような装飾へと発展している。
イギリスではゴシック建築が12世紀末から16世紀中頃までと、ヨーロッパで最も長く展開しただけでなく、その伝統が19世紀まで途絶えることなく、18~19世紀のゴシックの復興もそれに起因したといえる。
神聖ローマ帝国では、1230年頃まで特に西方地域でゴシック建築への反抗が根強く見られた。彼らはゴシック建築に無関心というわけではなく、いくつかの教会堂ではゴシック建築から採用されたと思しき装飾も見られるが、あくまで部分的な採用に止まり、構造的・美術的な原理としてゴシック建築を全面的に用いるということがなかった。バーゼルの大聖堂、リンブルク・アン・デア・ラーン大聖堂、ボンの大聖堂など、12世紀~13世紀初頭のこのような傾向を持つ建築物をトランジション・スタイル(移行様式)と呼ぶこともある。
13世紀中期~後期にかけて、帝国内でフランスのゴシック建築が定着することになったが、その伝播はいくつかの芸術の中心地からバラバラに広がる傾向にあったため、ゴシック建築の発展状況は、帝国の政治状況と同じく斑模様である。
いくつかの芸術的中心地を挙げると、まず、ハンザ同盟の市民によって競うように建てられた巨大建築物のひとつ、リューベックのマリーエンキルヘが挙げられる。これは13世紀末~14世紀初頭にかけて、バイエルン、プロイセン、ポーランド、デンマーク、スウェーデン、フィンランドなどで、一般にバックスタイン・ゴーティック(煉瓦造ゴシック、ブリック・ゴシック)と呼ばれる建築を広めるきっかけとなった。構造として煉瓦を用いているため、細かい装飾は省かれ、むしろ構造を率直に表現する意匠となっている。この様式は北部ドイツからポーランド・リトアニア共和国の領域を中心として分布している。
1235年に身廊の建設が着工されたストラスブール大聖堂は、14世紀になっても依然として帝国内で最大の建築工事として続行しており、これは15世紀中期にまで及んだ。サン=ドニ大聖堂とトロワ大聖堂を規範とした身廊を持つ大聖堂の造営工事は、14世紀半ばに技巧的には最盛期を迎え、エスリンゲンのフラウエンキルヒェやウルムの大聖堂など、アルザスやライン川上流部に影響を与えた。1400年代に建設されたストラスブールとウルムの西側両尖塔に見られる独特の形状は、その図像芸術からヴァイヒャー・シュティル(Weicher Stil 、柔軟様式)とも呼ばれる。建築自体の影響力は、地域的には限定されていたものの、建築組合の影響は広がりを持っていたらしく、1459年には、ウィーン、ケルン、ベルン、プラハなどの大聖堂の建築工事が、ストラスブールの建築組合によって管理されることが決定した。ただし、この決定が建築の造営にどの程度影響を与えたのかはあまり明確ではない。
1248年に建設が開始されたケルン大聖堂もストラスブールと比肩しうる大規模工事で、フランスのアミアン大聖堂に依拠し、装飾についてはフランスを凌駕するほど壮麗な部分もある。この大聖堂の影響はラインラントに限られるが、オッペンハイムの大聖堂、バヒャラッハのヴェルナーカペレなどの技巧性の高い教会堂が残る。アーヘン大聖堂内陣もまた、ケルン大聖堂とパリのサント・シャペルの影響を受けたもので、カペッラ・ウィトレア(ガラスの祭室)と呼ばれる。
イタリア半島では、概してゴシック建築への反応は冷淡なものであったが、フランシスコ会とドメニコ会の活動によって、13世紀中期から北、および中央イタリアである程度導入されるようになった。
ゴシック建築の影響を受けたイタリア最初の建築物は、1228年に起工されたアッシジのサン・フランチェスコ聖堂である。ロマネスク建築に見られる単廊式の平面であるが、尖頭リブ・ヴォールトとこれを支える束ね柱、そして内部空間の一貫性は、ゴシック建築を取り入れた独創性の高いものとなっている。ただし、フランスのゴシック建築のように、薄い壁を形成するための構造的な努力はまったく見られず、また、フレスコ画を描くために都合が良いためと思われるが、イングランドのような壁を彫り込むような造形への関心も薄い。従って、サン・フランチェスコは、ゴシック建築というよりも、ゴシック建築の造形を取り入れることによってロマネスク建築の伝統から脱却した教会堂であると言える。
13世紀になっても、イタリアでは典型的なゴシック建築はめずらしい存在であった。
1230年頃に着工されたパドヴァのサンタントニオ大聖堂はロマネスク建築とビザンティン建築の混成様式であるし、1250年頃に起工されたシエーナの大聖堂などは、ファサードを除くとほとんどロマネスク建築のままである。オルヴィエートの大聖堂も、ファサードは美しいゴシック芸術の作品であるが、内部はシエーナと同じロマネスク建築である。
ただし、ゴシック建築の空間が全く無視されていたわけではない。13世紀イタリアでゴシック建築とみなしうる教会堂がフィレンツェに存在する。ドメニコ会が1279年に創建したフィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂は、以後トスカーナ地方で建設されるゴシック建築にきわめて大きな影響力を持った教会堂建築であった。側廊が高いため小さな丸いクリアストーリしかない身廊は、装飾がほとんどなく、柱間が広くとられているので、フランスのゴシック建築に比べてゆったりとして簡素な印象である。
サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂のようなゴシック建築のスタイルは、以後トスカーナのゴシック建築に受け継がれた。これは1300年頃に設計されたフィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂と、1294年に着工されたサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂の身廊を見れば明らかである。サンタ・クローチェ聖堂の造営はフランチェスコ会によるものでサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂には規模的にやや劣るものの、北ヨーロッパの大聖堂に匹敵する大きさである。シトー会の修道院建築から着想されたと思われるデザインで、これを構想したのはサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂と同じくアルノルフォ・ディ・カンビオであると考えられている。両教会堂の簡素で広々とした空間は、しばしばフランスのゴシック建築の美意識と対立するものとみなされ、ルネサンス建築の先駆けとも評される。1322年から開始されたシエーナの大聖堂拡張工事も、完成していれば、おそらくトスカーナのゴシック建築の最良の作品のひとつになったと考えられる。
北イタリアでは14世紀初頭まで宗教建築そのものがあまり重要性を持たなかったが、ビザンティン建築の伝統から脱却しつつあったヴェネツィア共和国では、他の北イタリアに先駆けて、やはり修道会によってゴシック建築が導入される。14世紀初頭に起工されたドミニコ会のサンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ聖堂と、1330年頃に起工されたフランシスコ会のサンタ・マリア・グロリオーサ・ディ・フラーリ聖堂が、その代表的な建築物である。
14世紀後半になると、北イタリアでもようやく大規模な宗教建築が建立され始める。
1387年には、イタリア・ゴシック建築で最も有名なミラノの大聖堂の建設が始まった。この大聖堂は、中世の建築物としては非常に珍しいことだが、設計過程から職人との詳細なやり取りまで、建設に関わる綿密な記録が残っており、イタリアのみならず、フランス、ドイツでのゴシック建築に対する認識を知ることができる。構造と美術的な審議は1401年から始まり、パリから招かれた審議員はフランス伝統の古典ゴシックの形態を、ドイツ人の審議員は突き抜けるような垂直性の高いプロポーションを、イタリアの審議員は幾何学から導かれる幅の広いプロポーションを主張したことが読み取れる。結果的に、この大聖堂はイタリア独自のゴシック建築というよりも、各国のゴシック建築の美意識を取り入れた折衷的性格の強いものとなっている。しかし1858年まで延々と工事を行ってきたにもかかわらず、全体としての完成度はたいへん高く19世紀に追補されたファサード部分もゴシック・リヴァイヴァルの最高傑作として名高い。
ゴシック建築の装飾
ゴシック建築の達成は、中世スコラ哲学の理念、つまり神を中心とした秩序を反映したことにあると言える。中世の人々にとっては事物の全てに象徴的な意味があり、故に、ゴシック教会を彩る様々な装飾は、聖職者たちの世界に対する理解そのものであった。彼らは、美を神の創造と同義であると考え、教会を装飾することを神への奉仕と捉えていた。従って、扉口のマリア像や聖ペテロ像、聖ニコラウス像、ステンドグラスに画かれたキリストの生涯といったものは、決して現代人の意味するところの「装飾」などではなく、石に刻まれた中世精神の表象なのである。
全体像のまとめは稿を改めて。とりあえず、以下のイデオロギーとの連続性次につながる重要ポイントとして浮かび上がって来た気がします。
フィリップ4世にあっては、稀に見る傲慢さと稀に見る敬虔さとが同居している。一見互いに矛盾しているようにみえる2つの性格は、フランスこそがキリスト教圏の中心に位置し、フランス王こそがヨーロッパ諸王のなかで最も敬虔なキリスト者であるという確信によって結びついていた。
このような論理に立脚すれば、フランスに奉仕すること、王に忠勤を尽くすことが、とりもなおさずカトリック教会を守り、キリスト教を守護していくことにほかならない。そのためには、たとえ相手がローマ教皇であろうと戦うことをためらわない。
これはもはや絶対王政の精神? そして「国民感情」もまた黒死病と宗教戦争の洗礼を経て次第に「十分な火力と機動力を備えた常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって養う」主権国家(Civitas Sui Iuris)体制へと推移していく訳ですが、惜しむらくはこの時代にはまだ(イブン=ハドルーンの王朝寿命説の前提となる「乗馬突撃最強世界」を覆す)火力や機動力も、それどころか人々をそれなりに適切な単位で区分けする「国民」の概念自体が存在していなかったのでした(実はこの着稿段階では「国王も黒死病などを契機に主権国家への移行を覚悟した」が結論となる筈だったのだが、あっけなく放棄)。ゴシック時代なる歴史区分について、ここまで明らかに出来た時点で以下続報…