時代の変わり目には、自分を賭ける対象を間違えて抜殻のようになる果ててあっけない死を迎える人々が続出する。だが少なくとも太宰治はその一人ではなかったらしい。

太宰は口ぐせに、死ぬ死ぬ、と云い、作品の中で自殺し、自殺を暗示していても、それだからホントに死なゝければならぬ、という絶体絶命のものは、どこにも在りはせぬ。どうしても死なゝければならぬ、などゝいう絶体絶命の思想はないのである。作品の中で自殺していても、現実に自殺の必要はありはせぬ。
泥酔して、何か怪けしからぬことをやり、翌日目がさめて、ヤヤ、失敗、と赤面、冷汗を流すのは我々いつものことであるが、自殺という奴は、こればかりは、翌日目がさめないから始末がわるい。
昔、フランスでも、ネルヴァルという詩人の先生が、深夜に泥酔してオデン屋(フランスのネ)の戸をたゝいた。かねてネルヴァル先生の長尻を敬遠しているオデンヤのオヤジはねたふりをして起きなかったら、エエ、ママヨと云って、ネルヴァル先生きびすを返す声がしたが、翌日オデンヤの前の街路樹にクビをくゝって死んでいたそうだ。一杯の酒の代りに、クビをくゝられた次第である。
それでは、ここで例示されたネルヴァルについてはどうなのだろうか。
1222夜『オーレリア』ジェラール・ド・ネルヴァル|松岡正剛の千夜千冊
- フランス7月革命前夜に戯曲「エルナニ(Ernani)、1829年)」を発表したヴィクトル・ユーゴーを慕って集まった「小ロマン派」あるいは「青年フランス」を代表する「ダンディ」の一人。
- なまじ復古王政の時代に「国王と教会の権威に対する未来永劫の絶対不服従」を誓った政治的浪漫主義者だったが故に、その大半が二月/三月革命(1948年〜1949年)によって国王と教会の権威が絶対視される時代が終焉すると生きる目標を喪失し自滅に近い最後を遂げる。そうした悲劇を代表する一人。
少なくとも「絶体絶命の思想の体現者」ではない。ただ生き急ぎ過ぎ、その結果として空っぽになって、死の誘惑にあっけなく屈っした風にも見えなくはない。実際「小ロマン派」あるいは「青年フランス」と呼ばれた人達は、大半がそんな具合に死んでいくのである。
ヴィクトル・ユーゴー(Victor, Marie Hugo、1802年〜1885年)の代表作「レ・ミゼラブル(Les Misérables、1862年)」。この作品ではクライマックスにおいてブルボン家からオルレアン家への王統交代に成功したフランス七月革命(1830年)の余波ともいうべき六月暴動(1832年)で蜂起した愛国者集団「ABC友愛会」が玉砕していく。これを「小ロマン派」あるいは「青年フランス」へのレクイエムと見る向きもあるが、実際の可能性としてどうなのだろうか。

- 現実の六月暴動は実質上オルレアン家が有事に備えてイタリアで飼っていた実働部隊「カルボナリ(炭焼党)」の共和主義者(「外人部隊」ながらフランスで出稼ぎ外国人を味方につけ勢力を拡大していた)への粛清に過ぎなかった。
- そういう無益な戦いと承知していたからかどうか、著者が自らを投影するマリユスもこの戦いで殉死する事はない。ジャン・バルジャンに救出されてあっけなく助かり、コゼットと結婚して幸せに暮らす。臨終の席でジャン・バルジャンが残す遺書は「この世知辛い世相において、人間としての尊厳を保つのに必要なのは金である。私がどうやって稼いできたかお前達に伝授する。だから末代まで繁栄し続けろ」というブルジョワ振興期ならではの内容で、しかもかなりの長文。確かに読者の中には「どうやって教会の燭台まで盗むほど落ちぶれてた脱獄囚が、工場を経営する市長にまで成り上がったのか? どうしてその後もお金に困らなかったのか?」気になってた人もいたかもしれないけど、むしろ余韻を台無しにされたと思った人が大半と思われ。
- 加えて著者自身の政治活動が複雑怪奇。オルレアン家に認められて貴族になったり、ルイ・ナポレオン大統領/皇帝ナポレオン三世政権下での政争に敗れてベルギーへの亡命を余儀なくされたり。そのせいで著者が元来、六月暴動や「小ロマン派」あるいは「青年フランス」についてどう考えていたかさえ判らない。
これでは真相はあくまで歴史の闇としか言い様がない。
「レ・ミゼラブル」は後に英国においてミュージカル化され、オーストラリア人監督とオーストラリア俳優を中心にミュージカル映画化された。主題歌「Do You Hear The People Sing」も世界中で大流行。だが米国のOccupy Wall Street運動(2011年)もトルコのタクシム広場占拠運動(2013年)も香港の龍和道占拠運動(2014年)もこの曲を合唱しながら警官隊に粉砕されていく。そのせいで最近のデモではこの曲が「玉砕を呼ぶ死の歌」として忌避される様になったとも聞く。当時ですら難易度が高かったくらいだから、現代人が「絶体絶命の思想の体現者」を目指すのはさらに難しい。そもそも政府側が「うっかり殉死者を出して反政府運動を逆に盛り上げてしまう愚」をすっかり悟ってしまったので、そう簡単には殺してくれないし。
*最近ではむしろ国際的には権力に自らの良心の全てを売り渡し、最後は抜殻の様になり果てて死んでいく(ジャン・バルジャンと対極の存在としての)ジャヴェール警部の悲劇への同情が高まってるらしい。そもそもジャン・バルジャンとジャヴェール警部はどちらも常習的犯罪者からパリ警察署長を経て世界初の探偵事務所を開設したフランソワ・ヴィドック(Eugène François Vidocq,1775年~1857年)がモデル。それぞれこの人物の異なる側面を抽出したキャラクターだったりする。こうした流れを受けて「まんがで読破」シリーズの「レ・ミゼラブル」は六月暴動鎮圧完了間近、マリユスと一緒にジャン・バルジャンの手によって救出されたジャヴェール警部が二人の前で自殺する場面で幕を閉じる。これはこれで絶望感が半端ない。
とにかくネルヴァルという人物を理解するには、まず彼が生きた時代を理解しなければならない。そもそもフランス革命を勃発させた「18世紀的危機」とはどんなもので、歴史にどんな足跡を残してきたのだろうか?
- フランスにおいては馬鈴薯普及史も砂糖国産史も明らかに革命時代(1789年〜1799年)やナポレオン戦争(1803年〜1815年)に先行している。革命政府が「アンシャン・レジーム」の呼称で糾弾した貧富の差の急速拡大。その主要因はむしろ外交革命(1756年)や7年戦争(1756年〜1763年)後のプロイセン沈静化によって平和な時代が訪れた結果としての人口爆発だったかもしれない(気象変化による不作の連続を指摘する向きもある)。実際、上掲の試みは全て並列で進行しているのである。
*「外交革命(独: Umkehrung der Allianzen、英: Diplomatic Revolution、1756年)」…神聖ローマ帝国皇統ハプスブルグ家とフランス王統ブルボン家の歴史的和解。その証としてオーストリア女帝マリー・テレジアの娘マリー・アントワネットがブルボン家に輿入れした。それまで新たな台風の目として暴れ回ってきたプロイセン王国も「バイエルン継承戦争(Bayerischer Erbfolgekrieg、1778年〜1779年)」が当面最後の戦争となったし、この戦争自体「じゃがいも戦争」の別称があるほど戦闘自体は行われなかったのである。
ベルギーワッフルは何故あの形? - 諸概念の迷宮(Things got frantic) - しかしジャコバン独裁政権は自らの信念を貫いた。貧富の差が急速拡大した主要因はあくまで産業の発展の結果とし、フランス国際交易の中心地であるボルドーとフランス工業の中心地であるリヨンを徹底破壊し尽くしたのである。その結果、フランスにおける産業革命開始は半世紀以上遅れたとも言われている。
*アナール派の最近の研究成果の一つで、それに立脚するウォーラーステインの世界システム論にもそれなりの形で織り込まれている。その一方でフランス革命を理想視する立場(というよりスターリン主義や文化大革命の支持者末裔?)からは「ジャコバン派は悪くない。正義を実践する為には全権を握る必要があり、その為には政敵全てを殲滅し尽くす必要があっただけである」と擁護する。何せこの話を事実と認めたら「英国で産業革命が進行した様にフランスでは市民革命が進行した」とする所謂二重革命仮説が崩壊してしまうのである。
ルネ・セディヨ 『フランス革命の代償』書評 - 人口爆発問題についても、フランス絶対王政期からずっと監獄と精神病院に幽閉されてきたマルキ・ド・サド(Marquis de Sade、サド侯爵、1740年〜1814年)が興味深い指摘をしている。「フランス革命政権もナポレオンも全くもって正しい。フランスの人口問題を解決するには水源から毒を流すか、ペストを流行させるか、飢饉で共食いさせるか、国民を次々と戦場に送り込んで殺すか、最初からその四択しかなかったのだ」と。
*彼の著作のうち、代々の権力者から最も危険視されてきた「ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え(l'Histoire de Juliette ou les Prospérités du vice、1797年〜1801年)に登場する重要な主題の一つ。実は執筆過程でマルサス「人口論(An Essay on the Principle of Population、匿名で出版された初版が1978年発表、著者名を明らかにした第二版1803年発表)」の影響を受けてフランスの有識者達が秘密裏にしてた議論を素早く取り入れただけとも。物語中ではこんな風に触れられる。「やがて近いうちに、王国には革命が起こるに違いない。革命の萌芽は多すぎる人口のうちに胚胎するものだ。人民は伸びれば伸びるほど危険になり、知識の光に浴せば浴すほど、あなどるべからざるものとなる。奴隷のように屈従するのは無知の輩だけだ。だから、わしらはまず無料の学校を廃止しようと思う…人民どもが才能を持つ必要が、いったいどこにあろう? むしろ彼らの数を減らすに如くはない。フランスの人口は強引な瀉血を施す必要がある…いずれわしらは戦争をはじめるつもりだよ。飢饉については、わしらが穀物をすっかり買い占めてしまえば、まずわしら自身が大儲けをし、やがて人民どもも共食いをはじめることになろうから、この意見は一考の余地がある」。ドストエフスキー「悪霊(1871年〜1873年)」で語られるビジョンを超えたディストピア。「人口論」を最初匿名で出版したマルサスも、おそらく自分の主張がこうした議論を呼ぶであろう事は十分予測していた。、そして帝国主義時代には、この考え方がさらにエスカレートして「白人世界が生き残る為には、黒人や黄色人の人口調整に着手する英断を下さねばならない」といった議論に発展していく。
「帝国主義イデオロギー」とは何だったのか? - 諸概念の迷宮(Things got frantic) - いずれにせよフランスは「18世紀的危機」をこうした「英断」の繰り返しによって乗り切り、ウィーン会議(1814年〜1815年)以降、比較的穏やかな王政復古期に着地する。隣国オランダも共和主義を標榜する愛国派の一掃に成功。王政国家「オランダ王国」として再スタートを切る。
*かくしてこれ以降、それまで世界を席巻してきたオランダの都市ブルジョワ貴族の活躍も精彩を欠く様になる。ナポレオン戦争中に海外植民地の多くを英国に奪われてしまったせいでもあり、そのゴタゴタからおもむろにシンガポールという新たな東南アジアの経済的中心地が浮上してくる。
シンガポールの歴史 - Wikipedia
無論、すべての欧州国家がこんな身勝手な展開を黙って受容した筈がない。フランス革命はスイスへの「輸出」には完全に失敗し、ナポレオンが撤収を宣言している。また、どさくさに紛れてオランダに併合されたベルギーでは憤慨が頂点に達っし(特にフランス語圏のワロン人の怒りが深かった)これがフランス7月革命に便乗したベルギー革命(1830年)を引き起こす。
ウジェーヌ・ドラクロワの代表作「民衆を導く自由の女神(La Liberté guidant le peuple、1830年)」だって実はフランス革命でなく、フランス7月革命(1830年)を礼賛する為に描かれた作品だった。しかも残念ながらそれは単なる王統交代に終わり、共和国実現を待望した過激分子も粛清され尽くし、この絵も危険視されて一旦は民主の目の届かない地下倉庫へと退蔵されてしまう。
*そもそもフランス革命そのものが「民衆の蜂起」によって始まったとは言い難い。無能なブルボン家との王統交代を狙うオルレアン家が私邸パレ・ロワイヤルに反政府主義者を匿い、彼らに襲撃隊を組織させて「バスティーユ牢獄襲撃(1789年7月)」と「ヴェルサイユ行進(1789年10月)」を敢行したからこそ、混乱が限度を超えて始まってしまったのである。この時の暴走に対する反省を踏まえ、二度目の挑戦となるフランス7月革命ではオルレアン家は実に巧みに振る舞った。どのタイミングで共和主義者を粛正すべきかも心得ており、それが敢行されたのが六月暴動(1872年)だった。ドラクロワの絵が地下に移されたのもそれ以降。おそらくマルクスはこのタイミングでこそ「歴史は繰り返す。最初は悲劇として、二番目は茶番劇として」と主張すべきだったのである。
①とどのつまりフランス革命というのは、それそのものが尊かったというより、その破壊に対する反省から生まれたものこそが尊かったのかもしれない訳である。
- 「50人の物理学者・科学者・技師・勤労者・船主・商人・職工の不慮の死は取り返しがつかないが、50人の王子・廷臣・大臣・高位の僧侶の空位は容易に満たすことができる」と公言して1819年に告訴されたサン=シモン(Claude Henri de Rouvroy、Comte de Saint-Simon、1760年〜1825年)の「産業者(Industriels)同盟」構想
- 「リヨン霞弾乱殺」によって家族の大半と全財産を失ったフーリエ(Francois Marie Charles Fourier、1772年〜1837年)の考案した「アソシアシオン(association)/ソシアビリテ(sociabilite)論」構想。
ここからまさに「ポータブル化された産業革命移植ノウハウ(要するに経営学の先祖筋)」が芽生え、他国への産業革命拡散に役立っていく。フランス自身がその恩恵に預かるのは二月/三月革命(1848年〜1849年)以降、というよりルイ・ナポレオン大統領(転じて皇帝ナポレオン三世)が君臨した第二帝政(1852年〜1870年)以降だった。七月革命を主導したサン=シモン主義のイデオロギーが、この段階になって初めて実践可能となったからである。
国際産業史の立場は概ねそう考える。経営管理論は、中世的伝統の拘束から比較的自由で、産業革命の実践においても先行していた英国やスイスやフランドル(それも前世紀の覇者だったオランダでなくベルギー)から始まったのではない。後発組たるフランスのファヨール(Jule Henri Fayol、1841年〜1925年)が掲げた「PDC理論の祖型」POCCC理論(Prévoir, Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler、計画化(フランス語)、「組織編成、命令系統整備、統制遂行(英語)」、調整(フランス語))から始まるのである。どうしてそういう展開になったのか。後発組だからこそ向き合わねばならなかった自らの後進性の克服過程に重要な意味があったからか。そうとでも考えないと全く筋が通らないからである。
*ドイツにはシュタイン博士(Lorenz von Stein、1815年〜1890年)の「今日のフランスにおける社会主義と共産主義(Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich、1847年)」を通じてまとめて伝えられた。シュタイン博士は大日本帝国憲法起草に当たって欧米留学した伊藤博文の師匠だったし、マルクスも「今日のフランスにおける社会主義と共産主義」を精読し、その内容をベースに自説の基盤の多くを組み上げている。
②こうした誰もが途方に明け暮れるしかない難しい時期に「小ロマン派」もしくは「青年フランス」として集った「ダンディ」もしくは政治的浪漫主義者達は全てを強引に計画通りに進めようとする人たちを翻弄し、かつ自らも翻弄され続けた訳である。とにかくあくまで「国王と教会の権威に対する未来永劫の絶対不服従」を誓う立場からフランス七月革命(1830年)が単なる王統交代に終わってしまった事は弾劾し続ける。その不屈の努力が二月/三月革命(1848年〜1849年)を惹起したとする好意的意見もあるにはある。しかしカフカは逆に彼らの間に政治的イデオロギーの一貫性など一切見られない点に着目した。そして「修行僧の如き真摯な姿勢で徹底的エゴイストとして生き様とした彼らの心には、神に向けられたダンディズムは存在しても、同じ人間に向けられるダンディズムなど存在する余地もなかった」と結論付けた。つまり「民衆の歌」が彼らの心に届く可能性なんて最初から存在していなかったという事。そもそも共和主義に同情する気持ちが少しでも備わっていたら、六月暴動に際して巻き添えで粛正されていた筈であろう。それでは彼らは一体何だったのか? この問い掛けこそが現代社会における彼らの再評価へと繋がっていったとも。
*「修行僧の如き真摯な姿勢で徹底的エゴイストとして生き様とした彼らの心には、神に向けられたダンディズムは存在しても、同じ人間に向けられるダンディズムなど存在する余地もなかった」…この指摘によってカフカはアンガージュマン(Engagement、社会変革を引き起こす知識人や芸術家の政治運動参加)の可能性を盲信するサルトルを完全に敵に回してしまう。現代社会でもこの結論を受容出来ない人は案外多いかもしれない。要するに彼らは訳が分からなかったから放置されただけだったのかもしれないのである。突如として「我々が穢れたゲルマン民族状態から脱皮して本来の先祖たるギリシャ人状態に回帰するにはどうしたらいいですか?」なる奇怪な設問に真摯に悩み始めたドイツのロマン主義者達の様に。
③幸いにも彼らは二月/三月革命(1848年〜1849年)によって「国王と教会の権威を絶対視するイデオロギー」が過去ののものになると巻き添えで自滅していく。そして次世代のイデオロギーを準備したのは皮肉にも「自分を内側から突き動かす純真な力に導かれた生き様だけが尊い」と豪語する彼らのロマン主義的価値観についていけなかった人々だった。
- 「人間の自由意志など社会的同調圧の産物に過ぎない」とし「上部構造/下部構造」仮説に到達したマルクス(Karl Heinrich Marx、1818年〜1883年)。
- 自分の置かれた立場からそれぞれ人の心を動かす言葉を追求したエドガー・アラン・ポーとサド侯爵の文学を研究して「文学とは人の心を動かす言語と文法の体系である」という結論に到達して象徴主義芸術(Symbolisme)に至る道を切り開いたボードレール(Charles-Pierre Baudelaire、1821年〜1867年)。
「国王と教会の権威の絶対視が不可能となった時代」が最初に生み出したのは、それを相対視する思想だったという事。スイスの文化史学者ブルクハルトは「イタリア・ルネサンスの文化(Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Versuch、1860年)」の中で啓蒙主義の産物たる理神論(deisms/ディスムス)について「キリスト教からキリスト教的なるものの一切を取り除こうとする試み」と要約した。ある意味そうした試みへの解答にはなっている。確かに既に「神そのもの」は完全に視野外へと追いやられいるからである。しかし「人間の心を動かす絶対的な力なら存在する」という信念は揺るぎもしなかった。その事が新たな問題を引き起こす。かくして人類は新たな段階、つまり疫病や不況の到来といった不可視の脅威に絶えず怯え続ける神経症的状態へと突入した訳である。いわゆる「不安の時代」。不可視の脅威を次々と竹を割った様に明快な可視的陰謀論に変換してくれるカリスマ的存在に人々が群がる時代…それは突然襲来する疫病や飢饉の恐怖に怯える古代の人々が護符にすがり、魔除けの呪文を唱えた心理状態への回帰に他ならなかったのではあるまいか?
*「キリスト教からキリスト教的なるものの一切を取り除こうとする試み」…「決して美しくはないので既に私の興味の対象外だが」という前置きを除いて、不思議なまでに揶揄する調子が見られない。当人にとってはもしかしたら(フランス人が到達可能な)セカンドベストといった認識だったのかもしれない。
「陸と海と」と「世界最終戦論」 - 諸概念の迷宮(Things got frantic)
④ところが19世紀末までにマルクス主義は(そのパトロンでもあった)ラッサールの国家福祉論などへの傾倒を強め修正主義的結論に到着してしまう。その一方で象徴主義はフロイトの精神分析理論の影響も受けつつオカルト色をさらに増していった。これでは一般人が「不安の解決」を託せない。だから大不況(1873年〜1896年)時代に次第に政治的主導力を握って行ったのはそのどちらでもなかった。
- 18世紀を風靡した啓蒙主義やサン=シモンと袂を分かち…
- (実証哲学(Philosophie positive)によって統合された有識者集団の未来予測に基づいて社会全体を経営する)科学者独裁構想に到達し…
- ハーバード・スペンサー(Herbert Spencer、1820年〜1903年)の社会進化論(Social Darwinism)や米国においてコングロマリット(軍産共同体)を支えるイデオロギーとなった科学万能主義(Scientism)に多大な影響を与えた…
そんなオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)の超絶的態度こそが神聖視され、所謂「帝国主義イデオロギー」に祖型を与える事になったのは、ある種の歴史上の必然でさえあったかもしれないという事である。
*「帝国主義イデオロギーの勝利」…おそらくこの系統だけが「英米VS欧州」とか「白人VS黒人&黄色人」といった「人の心を動かす新たな闘争構造」を想像し続ける力を備えていた事が大きかったのではないか。
レーニン以前のマルクス経済学 - 諸概念の迷宮(Things got frantic)
⑤ここからの流れは早い。
- 第一次世界大戦(1914年〜1918年)は参加国全てに総力戦を強要し、終戦までにロシア帝国や、オーストリア=ハンガリー二重帝国や、オスマン帝国といった全時代的政体をまとめて解体に追い込んだ。
- その過程で広まった総力戦思想から(民主集中制を理想視する立場から議会制民主主義を否定して共産党一党独裁を目指す思想としての)マルクス=レーニン主義やスターリン主義やファシズムやナチズムといった全体主義を産み落とした。
- 色々あって、色々考えた末に最終的に「人間を不当な社会的同調圧力から解放するには個人個人の情報リテラシーを引き上げるしかない」という結論に到達。
こうしてやっと「自分を内側から突き動かす純真な力に導かれた生き様だけが尊い」と豪語したロマン主義者達の生き様が再評価される時代が訪れる。
*そもそも日本人の多くは澁澤龍彦「悪魔のいる文学史―神秘家と狂詩人(1972年)」 を通じて初めて「小ロマン派」あるいは「青年フランス」と呼ばれる人々の存在を知ったのだった。そして「レ・ミゼラブル」のミュージカル化プロジェクトが始まったのが1980年代(1980年パリ公演、1982年映画版公開、1985年ロンドン公演)。ここに新たな時代の変わり目が見出せるとも。
澁澤龍彦「悪魔のいる文学史―神秘家と狂詩人」
*ただロマン・ロランの「新ロマン主義」や、エルンスト・ユンガーの「魔術的リアリズム」に復活の片鱗を見る向きもある。
これでやっと「吸血鬼の先祖筋」としてしか思い出されなくなっていたバイロン卿(George Gordon Byron, 6th Baron Byron, 1788年〜1824年)にも再評価の光明が?
まぁ、この人の場合は生前から「バイロン卿が来たぞ、娘も息子も隠せ!!(バイロン卿は両刀使い)」と叫ばれていた訳だけど。さて、そんな時代をネルヴァルはいかに生きたのか?
ジェラール・ド・ネルヴァル(Gérard de Nerval, 1808年〜1855年)
19世紀に活躍したフランスのロマン主義詩人。その詩作品には、象徴派・シュルレアリスムの要素が認められ、20世紀後半より見直された。ゲーテの『ファウスト』を紹介・訳し、『ドイツ詩選』を著し、新しいドイツ文学の紹介者としても活躍した。1855年、首を吊って自殺した。主な作品に『火の娘』、『オーレリア、あるいは夢と人生』、『ローレライ』、『幻想詩集』などがある。不信心を咎められた時に「俺に信心がないって?信心なら17個も持っているぜ!」と叫んだ。また自分の肖像写真の下に「私は他人だ」と書いたという。
1808年5月22日(日曜日)にパリのサン・マルタン通り168番地で生まれた。2年後にはナポレオンの大陸軍の軍医であった父と共に赴いたシレジアで母が亡くなる。母方の大叔父アントワーヌ・ブーシェによりモルトフォンテーヌのヴァロア地方にあった別荘で養育される。1814年に父が帰還するとパリに移るが、しばしば後の小説で回想されるこの土地を定期的に訪れていた。
1822年にシャルルマーニュCharlemagne(コレージュ)に入学し、テオフィル・ゴーティエと知り合う。在学中の1829年20歳の時に『ファウスト』、その他のゲーテの諸作品、ホフマンの翻訳で脚光を浴びた。これらの翻訳は長きに亘り望み得る最良のものという評判を保ち続けた。1827年10月に刊行された『ファウスト』の初版はこの大傑作の第1部のみ(当時は第1部の存在しか知られていなかった)で、「ジェラール」とだけ署名されていた。ゲーテはこの翻訳を非常に高く評価し、もし自身がフランス語でファウストを書かねばならぬとしたらこう書いたであろうとまで言った。作曲家のエクトル・ベルリオーズはこの翻訳からオペラ『ファウストの劫罰(légende dramatique "La damnation de Faust" 。1946年初演)』の着想を得た。テオフィル・ゴーティエ、ヴィクトル・ユーゴー、アレクサンドル・デュマと親交があり「狼男」ペトリュス・ボレルと共に「青年フランス」の最初のメンバーとなった。1830年2月25日に初公演のさなかで巻き起こった「エルナーニ合戦」ではユゴーを積極的に支持。 1835年には、ロマン派グループがみな集まるドワイエンヌ通りのカミーユ・ルージエの家に居を定めた。1846年にはモンマルトルの「霧の城」に住む。1852年に出版された現代演劇に関する著作の中でこの時代のことを語っている。
1836年には女優ジェニー・コロンに夢中になったが彼女はそれに応えなかった。彼女の死後も変わらぬ偶像崇拝を捧げ続ける。それは亡き母の面影にマリア、イシス、シバの女王といった理想の女性を重ねる独特のサンクレティスム(異教習合)として数々の作品や日頃の言動に足跡を残す事になる。
1841年以降、度重なる精神錯乱の発作に見舞われてブランシュ医師の精神病院にかかるようになる。この施設での逗留と、ドイツと中東への旅とを交互にした。『東方旅行記』は1851年に発表。1853年10月22日付のブランシュ医師への手紙で、シリアを旅行中にドゥルーズ派の密儀を授けられ、その教団で最も高い位階の一つである「ルフィ」にまで達するであろうと断言した。ネルヴァルの全作品は神秘主義、象徴主義、とりわけ錬金術的なものに強く染まっている。
1844年から1847年にかけてベルギー、オランダ、ロンドンを旅し、探訪記や印象記を書いた。時を同じくして、短篇小説家、オペラの台本作家、友人ハインリヒ・ハイネの詩(選集は1848年に出版)の翻訳者としても活動した。これ以降の期間、物質・精神の両面で苦境の中で主な傑作を残す。ブランシュ医師の勧めで自らの情念を浄化すべく「火の娘(1950年〜1854年)」や「オーレリア、あるいは夢と人生(1853年〜1854年)」を執筆。
1855年1月26日、ヴィエイユ=ランテルヌ(古いランタン)通り――ボードレールに言わせると見出し得る最も汚い一角――の下水道の鉄格子で首を吊った姿で発見された。友人たちは、この悪名高い場所でいつもの散歩をしているところを浮浪者たちに殺害されたのではないかという仮説を述べた。普通なら絞首の際の体の動きで落ちたであろう帽子が頭に乗った状態で発見されたからである。
その後、冬を越すのに充分な額である(とネルヴァルが言う)300フランを求める手紙が発見された。葬儀はパリのノートルダム大聖堂で執り行われた。自殺ではあったが、精神状態のためであったと見なされカトリックの葬儀が許された。テオフィル・ゴーティエとアルセーヌ・ウセがネルヴァルのためにペール・ラシェーズ墓地の永代使用料を支払った。マクシム・デュ・カン『文学的回想』(戸田吉信による抄訳 冨山房百科文庫 1980年)に詳しい肖像がある。
1884年にラフカディオ・ハーンが、『東方紀行』について「狂える浪漫主義者」と題する評論を発表している。
ラフカディオ・ハーン「狂える浪漫主義者(ヂェラール・ド・ネルヴァル)」
夢の意味へのネルヴァルの執着はアンドレ・ブルトンが強調しシュルレアリスム運動に影響を与えた。『シュルレアリスム宣言』では、『火の娘』のアレクサンドル・デュマに宛てた献辞で、ネルヴァルが『シメール』のソネを書いている時に彼を訪れた「『超自然的』夢想状態」に言及していることを取り上げている。
マルセル・プルーストとルネ・ドーマルもまたこの重要な作品に大きな影響を受けた。
アントナン・アルトーはネルヴァルに、彼の言うところの「自身の意識に対抗するために神秘的な仕方で同盟を結んだ」社会的な自殺(社会がさせた自殺)を見出した。
日本においては、中村真一郎が大学の卒業論文に選んだ(当時はほとんど知られていない詩人だったので、パリの古書店に注文をだすと、ほとんどの著作が容易に入手できたと中村は回想している)こともあって、中村による訳書、『暁の女王と精霊の王の物語』(白水社、のち角川文庫)『火の娘』(青木書店、のち新潮文庫)『ボヘミヤの小さな城』(創元社、のち旧河出文庫)が戦中、戦後まもなく出版された。
もしかした「 火の娘(Les Filles du Feu)」の作者が「西洋おでん(pot-au-feu)」屋に断られたのって、笑う所だったのだろうか?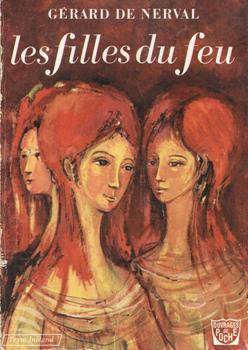
来日以前に小泉八雲が執筆した論評も「狂人が不思議な絵を描いて、それが狂人の仕業であることが最初は余程の鑑識眼のある人でないと分らなかった。彼はそうした言葉の絵師だったのである。明らかに気が狂っており、時々は正気に立ち返っても、どれくらい続いたか疑問とされている」「非常に面白い話をしているかと思うと、時々変な合の手を入れたり、飛んでもない外のことを云い出したりする。まあ、非常に立派な学者であり談話家である人が、酔っ払ってしゃべっているものと思えばいい」とこれまた辛辣極まりない。
*米国に渡ったラフカディオ=ハーンは、ハワイ原住民や黒人のブードゥー文化に興味を寄せつつフランス幻想文学の翻訳者として現地に名前を残した。アメリカの研究者曰く「ラフカディオ=ハーンなくしてラブクラフトなし!!(ラブクラフト自身がそう発言している!!)」だそうである。そんな彼がどうしてその後日本に精神的安住を見出し、帰化までしたのか考えるのは日本人の責務となっている。
そして確かに(カフカが指摘している様に)ネルヴアルには共和主義への同情など片鱗も見られない。そもそも彼のロマン主義の由来が「我々が穢れたゲルマン民族状態から脱皮して本来の先祖たるギリシャ人状態に回帰するにはどうしたらいいですか?」なる奇怪な設問に真摯に応え様としたドイツの古典主義やロマン主義とあってはフランス起源とすらいえない。そもそも「小ロマン派」あるいは「青年フランス」は一人一人がこんな具合に個性的で政治的イデオロギーの共有そのものが見られない。ならば彼らは一体何者だったのか? ただひたすら「国王と教会の権威を絶対視するイデオロギー」への反感のみを共有し続けた光に対する影の様な存在に過ぎなかったのか?
ここでおもむろに「むしろそれこそが「フランス人そのもの」といえよう」なる逆説が浮上してくる。何しろフランス人といったら日本の浮世絵(それもクシャクシャに丸められた磁器の包装紙の表面に印刷されてた広告)にインスパイアされて印象派絵画を描き始めた様な人々。最初から日本人の想像力などはるかに超越した存在なのは当たり前なのである。ましてや、さらに途方もないドイツの古典主義やロマン主義が伝来してどうなったかは想像に余りあるではないか。
こうした観点から改めて「フランダースの犬」に目を向けてみよう。
「フランダースの犬」は厨二病代表格? - 諸概念の迷宮(Things got frantic)
ルーベンスがいなければ、アントワープの町は何だったというのでしょうか? 波止場で商売をする商人を除いて誰も見たいとは思わないような、薄汚くて陰気な、騒々しい市場町に過ぎません。ルーベンスによって、アントワープの町は、世界中にとって、神聖な名前となり、神聖な土地となり、芸術の神様がこの世に生まれたベツレヘム (イエス・キリストが生まれた地名)となり、芸術の神様が亡くなったゴルゴダ(イエス・キリストが亡くなった地名)となったのです。世の人々よ!あなたがたは国に生まれた偉人を大事にしなければなりません。というのは、未来の人は、偉人によってのみ国を知るからです。この時代のフランダースの人たちは賢明でした。ルーベンスが生きている間、アントワープの町は、アントワープが生んだ最も偉大な息子に名誉を与えました。そして、ルーベンスの死後は、アントワープの町はその名前を賛美します。けれども、実を言うと、フランダースの人たちがこのように賢明だったことは、めったにありませんでした。
ただの現実的な英国人ならこんな言葉、口が縦に裂けたって、横に裂けたって、いやそれどころか十文字に裂けたって口にする筈がない。 その一方で「我々が穢れたゲルマン民族状態から脱皮して本来の先祖たるギリシャ人状態に回帰するにはどうしたらいいですか?」なる奇怪な設問に真摯に応え様としたドイツの古典主義やロマン主義もまた自分の問題に手一杯で、他民族も同様の厨二病を患う可能性を認める精神的余裕など存在する筈がない。これぞまさに彼女が血の半分を引くフランスの伝統。しかも著者は餓死する覚悟で何故かフランスではなくイタリアに向かい(とはいえサド侯爵も「フランスにいられなくなったフランス人がまず向かうのはイタリア」と断言し、実際彼の作品に登場する不道徳な人物も大半がその言葉を実践する)、30匹の愛犬に看取られながら亡くなっていく。原作版「フランダースの犬」におけるネロの悲壮な最後など遥かに超越した潔いまでの厨二病的最後。こうした途方に暮れるしかない状況に直面した時、日本人が国際的に発して認められるのは、村上春樹が世界に広めたあの言葉しかあり得ない。
「やれやれ」である…







