最近ネット上で流行しているユング「フロイト先生は, なんでも卑猥にしてしまうんだよなあ」論について、ふと思った事。

フロイトの手に掛かるとなんでも卑猥になる
— 南波純 (@nanbazyun) 2018年1月22日
フロイトさんは大体「女性が何かに追いかけられてる夢を見たらそれは男性に求められたいって意味だし、男性が何か食べたりする夢みたらそれは女性をそういう意味で頂きたいってことだよ!!」的なこと言っちゃうからすーーーぐ卑猥な方向に持ってく心理学の人ってイメージしか持ってない。
— しおまる (@hanamaru_pip) 2018年1月22日
フロイト先生が現存していたら「なんでも卑猥思考」な腐女子の我らと仲良く共存できたかもしれないRT
— かなめ@ニート満喫中 (@S_S_adviser) 2018年1月23日
これ実は「様々な意味で行き詰まっていた19世紀末のハプスブルグ帝国において、その近代化を妨げていた伝統的諸概念、特にインテリ=ブルジョワ階層の偽善にメスを入れたら「ち○こ、ま○こ、う○ち、お○っこ」みたいなそれまで無意識化に抑圧されてきた卑猥な諸概念が一斉に天井を真っ赤に染める勢いで吹き上がった」 が正解。そもそもこの現象自体を発見したのは、フロイトのフランス留学中の師匠だった解剖病理学者シャルコー (Jean-Martin Charcot、1825年〜1893年)で、フロイド先生自身じゃない?
ジャン=マルタン・シャルコー (Jean-Martin Charcot、1825年〜1893年) - Wikipedia

シヤルコー自身は「我慢は不健康の元」なるフランスの伝統的健康観から「卑猥な考えを意識上からひたすら抑圧し続けた結果、無意識下に「ち○こ、ま○こ、う○ち、お○っこの化物」が育ってしまった一時的現象」と解釈し公言を憚っていました。前近代的抑圧の鬱積が産んだ「膿」の排出が一通り終わった現代社会においては、むしろこちらの立場の方が理解を得やすい?
*「我慢は不健康の元」なるフランスの伝統的健康観…まぁこれ「太陽王ルイ14世の王座は(下痢気味の国王の為に)便座を兼ねていた(謁見中ですら好きな時に好きなだけ排泄可能)」なるエピソードにもつながってくる話なので、迂闊に賞賛すると別方面に向いた別種の地獄が口を開く。例えばフランスにおいては不倫は文化。「妻を寝取られた間抜け男」をたった一語で表す侮蔑語「コキュ(Cocu)」が存在する世界。まさしく「あえて神の用意した救済計画に背を向け、悲壮な最後を迎える可能性すら辞さず、自らの内心の声のみに従って善悪の彼岸を超越しようとする」フランス流ロマン主義の世界の大源流…



まぁもちろん「催眠術がこれを解放する恐るべき場面」に幾度も直面した体験があまりにも壮絶過ぎたので「人間の本質はこれだ!!」とか舞い上がっちゃったフロイト先生自身にも非がない訳じゃありません。
*彼は同時に人格心理学の父、すなわちインフルエンサー・マーケティング理論の祖でもある事がさらに話をややこしくしている。
フロイト先生、第一次世界大戦(1914年〜1918年)に敗れてハプスブルグ帝国自体が解体されてしまうと少しは我に返って「タナトス(Thanatos、死を志向する人間の本能)も意外と大事」などと少しは新しい事も言い出しますが…いずれにせよ「特定の強烈な体験から導き出された特定の思考様式で全てを説明せずにはいられなくなる(しかも、そうした発想の出発点となる「特定の強烈な体験」に限って特定の時代や地域固有の現象で普遍性に欠けてる場合が多い)」こうした現象、今日においては科学主義(Scientism)なる呼称を与えられ、まとめて蔑まれていたりします。
「科学を当てはめるべきではないような文脈において科学的な権威を用いずにいられなくなる現象」や「自然科学の手法、自然科学で認められたカテゴリーや概念が、哲学など他の探求分野でも唯一の適切な要素であるという思い込み」を指す。
- ところで「科学主義に対する弾劾」に真っ先に着手したフリードリッヒ・ハイエク(Friedrich August von Hayek、1899年〜1992年)やカール・ポパー(Sir Karl Raimund Popper、1902年〜1994年)もオーストリア人。要するに「(ハプスブルグ帝国の行き詰まりを背景とする鬱積感を背景とする)あらぬ方向への吹き上がり」が最も壮絶な形で観測されたのも、それに舞い上がって科学主義に走った人を輩出したのも、それで我に返って冷静な論議を始めた人を輩出したのもオーストリア(特にウィーン)だったという展開。
*確かにフランス(特にパリ)や英国(特にロンドン)にも啓蒙主義的博物学由来の「自然主義的一元論」なら存在してきたが、同時に解毒薬として確信過剰(cocksureness)を嫌ったバートランド・ラッセルの「科学は,経験的・試行的・非独断的なものであり、確乎不動の教義はすべて非科学的である」なる定言にも見られる様な懐疑主義もまた伝えられてきたのである。その起源はイタリア・ルネサンス期にパドヴァ大学やボローニャ大学の解剖学部で流行した新アリストテレス主義、すなわち「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」なる楽観的信念にまで遡る。
碧海純一「科学的な物の見方と科学万能主義」 - バートランド・ラッセルのページ
バートランド・ラッセル(Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, OM, FRS、1872年〜1970年) - Wikipedia- さらなる背景には「(ハプスブルグ帝国の行き詰まり、第一次世界大戦敗戦に伴うその解体、およびナチス台頭に伴うユダヤ系知識人の大量亡命といった)オーストリア人材の大量流出」なる問題が存在。これによってハプスブルグ帝国内固有の問題が世界中に拡散した側面が確実に存在した。
*特にアメリカは19世紀後半に(安価な農畜産物の大量輸出によってハプスブルグ帝国や東欧諸国やロシア帝国の貧農の暮らしの根幹を破壊し移民を余儀無くさせる)米禍(The American Peril)の仕掛け人でもあったので「インテリ=ブルジョワ階層と貧民が互いに階級的憎悪を抱き合う」ハプスブルグ帝国の人種構造がそのまま大規模な形で持ち込まれる展開を迎えた。
概ね「科学はまだまだ全然未完成だから、現時点においてはそれによって説明出来ない現象が幾らだってある(だから「これで全部説明可能と明らかとなった!!」なんて迂闊に叫んじゃう奴は、その時点でもう科学者じゃない)」と鷹揚に構えるのがルネサンス起源の伝統的科学主義批判、なまじハプスブルグ帝国の敗北体験から出発してるが故にヒステリックに「科学の敗北は人類の敗北!!」と叫んで過激な主張に走る(背景として移民が先住民に向かって「我々は役に立ちます!!」とアピールする悲壮な姿勢も垣間見られる)のがオーストリア系の科学主義批判の特徴とも。
ところで突然ですがそもそもこのサイト、私にとっては以下の様な形で自らの立脚する諸概念のセルフデバッグ手段(Self-debug Method)となっている側面があったりします。そしてそうした次元においては、上掲の様な「ハスプブルグ帝国市民が(自らの抱える)潜在的な論理上の行き詰まりを顕在化させ、それに対処していこうとする姿勢」が実に役立っていたりするのでした。

①「わざと自由連想的に論を展開させて至らない箇所や堂々巡りになってる箇所を炙り出す」…これまでのサイト展開においても幾度か「二点間の最短距離が直線とならない箇所には時空間的歪みが想定される」なる表現で自己言及している。
-
実はオーストリアの精神分析科医ジークムント・フロイト(Sigmund Freud、1856年〜1939年)が1890年代より最初に開発に着手した「自由連想技法(Free Association Technique)」における最も重要な基本技法の一つ。
- 発想的にはヴィトゲンシュタイン(Ludwig Josef Johann Wittgenstein、1889年〜1951年)が「論理哲学論考(独Logisch-Philosophische Abhandlung、英Tractatus Logico-philosophicus、執筆1918年、初版1921年)」の中で述べた「事象の総体としての世界は(一切の矛盾を原則論的に全て外部に追いやる事に成功した)言語空間として存立している」なる思考様式と表裏一体の関係にある。ヴィトゲンシュタインは同時に「語りえないことについては、沈黙するほかない。(Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.)」とも述べているが、フロイトの自由連想技法はまさに「その世界観において何が語り得なくなっているか」明らかにする為に開発され研鑽されてきた分析技法なのだった。
*「事象の総体としての世界」…カント哲学において「人間が直感でしか到達し得ない」とされた「物自体(独Ding an sich、英Thing-in-itself)の世界」に対峙させられた「人間が経験主義的方法論によって到達し得る限界」としての「物(独Ding、英Thing)の世界」に該当。
*「人間が経験主義的方法論によって到達し得る限界」…「デカルト象限(N次元)」の概念が発見され始めた17世紀以降、議論が急速に細密化。「人間が直感を通してしか(あるいはそれを通してすら)到達不可能な超越者(絶対他者)の領域」に向ける強迫観念が「数理や論理哲学によってのみ到達な合理的空間」と「個人が五感と知性と精神を駆使して到達する認識可能領域の限界」の狭間に「合理的空間構築の為に切り捨てられたアウトサイダー的諸概念が跋扈する薄明の領域」を見て取るプロセスを浮かび上がらせた。まさにこの領域こそ「売価ゼロを目指して(人件費や設備投資を含む)原価をひたすらゼロに近づけていく事だけが人類全体の目的に適っている」みたいなタイプの科学主義の故郷?
「人間が経験主義的方法論によって到達し得る限界」を乗り越える試みについて、これまでの投稿ではこんな具合にまとめてきた。
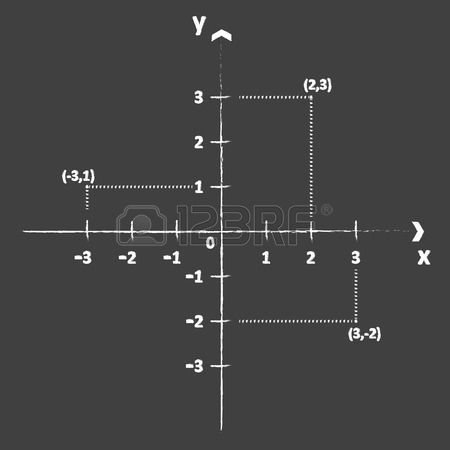
- 最初にデカルト象限が提言された時点では、その対象はこの空間における互換性が保証された幾何学と記号代数学くらいと考えられていた。
- 人文分野からこれに風穴を開けたのがナポリ出身の「近代歴史哲学の創始者」ジャンバッティスタ・ヴィーコの主著「新しい学 Principi di scienza nuova(1725年)」。「数学が無から仮説を積み上げた結果である様に、歴史は無から人間の行為事業を積み上げたものである」という観点が年表のデカルト象限へのマッピングを可能としたのだった。
*最近、中国古典の記述から地名と年代のセットを抽出し、これをソートする事で湖南地方に起こった中華文明が周代(紀元前1046年頃〜紀元前256年)、春秋時代(紀元前770年〜紀元前403年)、戦国時代(紀元前403年〜紀元前221年)を経て「秦の始皇帝による中華統一(紀元前221年)」に至るまでどの様にその活動の中心地を遷移させてきたかを明らかにしようとするプロジェクトがあった。様するにこういうのが「実証的人文科学」の原風景。
- そして以降は「(史料批判やアンケート技法といった)観測結果をどうプロッティングするかに関する技術」や「(標準分布と比較や評価次元検出などといった)こうした観測結果の集合体から有意味情報を引き出す(統計)技術」について研鑽が進行。次第に実証主義的人文科学の体裁が整っていく。
*「白衣の天使」にして「ミス軍務省」のナイチンゲールなどの活躍によってそれが国家経営に不可分な技術という認識が確立したのも大きいとも。
- これはある意味、詩集「草の葉(Leaves of Grass、1855年〜1892年)」で有名な米国詩人ホイットマン、および「堕落論」によって敗戦後の日本を風靡したフランス文学者坂口安吾などが奉じたある種の行動主義、すなわち「肉体に思考させよ。肉体にとっては行動が言葉。それだけが新たな知性と倫理を紡ぎ出す」なるイデオロギーの顕現。ジョン・スチュアート・ミルが「自由論(On Liberty、1859年)」の中で主張した「(進化は時間と死の積み上げによってのみ達成される。すなわち)文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならず、権力がこれを妨げる事が正当化されるのは他人に実害を与える場合だけに限定される」式の思考様式の実践面といえる。
*ところでここで述べている様な(欧州の貴族的功利主義を起源とする)行動主義は、その性質上欧州博物学の伝統に沿って独特の科学主義の源泉となる事がある。英国の進化生物学者ドーキンス(Clinton Richard Dawkins, 1941年〜)の利己的遺伝子の様な形で…
-
ただしジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668年〜1744年)が切り拓いた実証科学的人文科学には「(歴史に実際の足跡を残してきた)人間の具体的足跡そのもの」ではなく「(「厳格な史料批判を経た歴史史料」といった形での)言語化あるいは数理化された当人もしくは第三者による観測結果」しかプロッティング出来ないという本質的問題点が存在した。
*ヴィトゲンシュタインが「事象の総体としての世界は(一切の矛盾を原則論的に全て外部に追いやる事に成功した)言語空間として存立している」なる前提に立脚する論理哲学の分野を構想したのも、この矛盾に対する処方箋の一環。この世界には(その相互関係が必要にして十分なだけ記述可能である限り)「ユークリッド幾何学」と「非ユークリッド幾何学」が共存しても別に構わないという立場。
*その一方で実証主義人文科学は「各個人の様々な評価のN次元上へのプロッティングする」多変量解析なる新たな統計分野も開拓してきた。こうした意味空間方面での数理の発展があったからこそ数多くの心理検査が発明され「(人間の判断を模した)人間の様に振る舞う(第二世代までの)人工知能」が実現したのである。
*しかしながら1990年代以降のいわゆる「第三世代人工知能」は別にこうした歴史の延長線上に現れた訳ではなく、ここにある種のコペルニクス的展開がある。要するに「人間を模すのではなく、目的を達成する為の純粋な形での数理を追求する方が遥かに成果を出しやすい」という事実が周知される様になったのである。とはいえ人類はまだまだこうした新たな展開に全然追いついているといえない。
第二世代人工知能の亡霊がもたらす”AIの冬” - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)
ところでデカルト象限(N次元)概念の完成者ガウス(Carolus Fridericus Gauss、1777年〜1855年)も「数学は科学の王女であり、数論は数学の王女である」と述べている。上掲の様な「デカルト象限(N次元)に何をどうプロッッングするのが正しいか」なる疑問の数学版が整数論なのかもしれない?
- 最初にデカルト象限が提言された時点では、その対象はこの空間における互換性が保証された幾何学と記号代数学くらいと考えられていた。
- 遂に最後まで自力では近代化を阻害する伝統的諸概念から脱し得ず「第一次世界大戦の戦争責任を押し付けられての強制解体」なる理不尽な形での終焉を余儀無くされたハプスブルグ帝国やオスマン帝国。ウィーン世紀末文学などを分析すると、当時ハプスブルグ帝国を追い詰めていったのが「(資本主義的発展に不可欠な新興産業階層台頭を阻止する)領主が領民と領土を全人格的に代表する農本主義的権威主義」の残存と「語りえぬものについては沈黙しなければならない」論理哲学的思考様式の悲壮な共犯関係であった事実が浮かび上がってくる。
*だからこの系譜の科学主義批判者は「科学主義が世界を滅ぼす!!」と批判する訳だが、なぜかその叫びは科学的実証主義そのものを否定する反科学主義者の耳にも心地よく届いてしまうのだった…
こうして全体像を俯瞰すると「欧州における科学主義とそれに対する批判の歴史的地域的二重性」なる問題が浮上してくる一方、20世紀前半のドイツ語圏ではカール・マルクス(Karl Heinrich Marx、1818年〜1883年)が「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」の中で述べた「上部構造論」すなわち「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない」が、上掲で述べてきた様な世紀末ウィーン文化に端を発する「フロイトの自然主義的一元論」と結びついて「(ゾンバルトやマックス・ウェーバーばかりかヘルムート・プレスナーまで取り込んだ)マルクス=フロイト主義」なる新たな普遍的概念が形成され、少なくとも20世紀末までは猛威を古い続けてきた現実と否が応でも直面せざるを得なくなってくるのです。同時に「21世紀に入ると本格的忘却が始まった」のもまた事実…
*マルクスの「上部構造論」…一般にマルクスといえば「生産手段がこれを管轄する政治的手段の詳細を決定する」とした「下部構造論」が有名。しかし実際にはこれ(レーニンが「マルクスの人間解放論」に必然的に含まれる無政府主義的思考を嫌って米国フォード社の理念などに見受けられるテイラー主義に差し替えたといわれる)「タコの入ってないタコ焼き」科学的マルクス主義の主張なので全くの別物。国際的なスターリン主義の流行に反旗を翻して「マルクスの人間解放論」への回帰を叫んだマルクス経済学者アルチュセール(Louis Pierre Althusser、1918年〜1990年10月22日)が一世を風靡した1960年代以降、急速に衰退の一途をたどる。
*こうした展開を背景に「人間が直感的にしか到達し得ない超越的世界の真理は、この現実の世界においては主観的誤謬と区別し得ない領域でしか顕現し得ない」なる諦観から出発した魔術的リアリズム文学が成立する流れもあった。以降、哲学の世界は文学展開の世界からすら置き去りに?
有沢翔治の読書日記 : 寺尾隆吉『魔術的リアリズム』(水声社)
結果として21世紀まで残ったのがユング「フロイト先生は, なんでも卑猥にしてしまうんだよなあ」論だけだという辺り、アーネスト・ヘミングウェイの短編「キリマンジャロの雪(The Snows of Kilimanjaro、原作1936年、映画化1952年)」における「神の家(ンガジェガ)とも呼ばれるアフリカ・エチオピア高原のキリマンジャロ山の頂近くには、不毛の頂上を目指し登り、力尽きて死んだ豹の亡骸があるという。豹が何を求めて頂上を目指したのか、知る者はない」なる一説に通じる趣を感じます。少なくとも私達は現段階においてかろうじて「(人間の心を迷走状態に追い込む)停滞」だけは免れている?