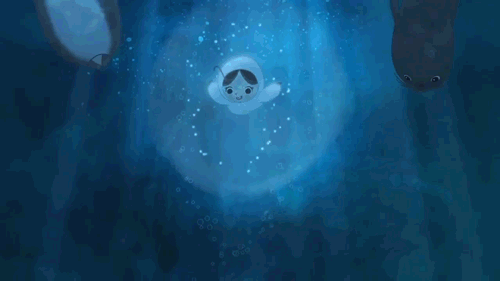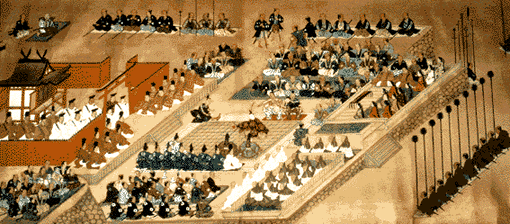トム・ムーア監督は(各時代の政治的意図を濃厚に受けてきた)既存文献に可能な限り頼らない形でのアイルランド神話再建を試みている人。
何故か、その結果再構成された世界観は日本の能と重なる部分が大きかったりします。要するに登場するヒロインに「前シテ」段階と「後シテ」段階が存在するのですね。
しかもアイルランド人はとっくの昔に日本的価値観とアイルランド的価値観の親近性に気づいてました。例えば出雲国造家に入り婿した小泉八雲。
そして「ケルティック能」なる新分野を開拓したウィリアム・B・イェイツ。
奈良時代(710年〜794年)の散楽
奈良時代、大陸から渡ってきた舞楽や伎楽など様々な芸能の中に散楽(さんがく)があったと考えられている(それ以前に伝わっていた可能性もある)。
- 現在の大道芸のような、雑芸(物真似、軽業・曲芸、奇術、幻術、人形廻し、歌や踊り、演劇など種々雑多な芸)を主とするもので、これが日本古来の滑稽な演技「 俳優(わざおぎ)」と習合して、猿楽(のちの能)へと発展していく母胎となる。
- 「散楽」が音便で「さるがく」「さるごう」などと訛り、滑稽な要素も手伝って「猿楽」という字を当てるようになったのである。
起源は西域の諸芸能とされる。
- 何世紀にも亘って、中央アジア、西アジア、アレクサンドリアや古代ギリシア、古代ローマなどの芸能が、シルクロード経由で徐々に中国に持ち込まれていった。それら諸芸の総称として、また、宮廷の芸能である雅楽に対するものとして「一定の決まりのない不正規な音楽」の意で中国の隋代に「散楽」と名付けられたという。
- 実際にはもっと古く、周や漢の時代には既に散楽と呼ばれる民間の俗楽(古散楽)が行われていたとも言われている。後漢以降の時代には、火を吐く、刀を飲む、水に潜り魚の真似をするなどの奇抜な曲芸から、隋や唐では百戯とも称された。
- 日本における散楽の歴史を紐解く上で資料となるのは、それが宮中で行われていた時代の史書『続日本紀』や『日本三代実録』などである。『続日本紀』には、天平7年(735年)に聖武天皇が、唐人による唐・新羅の音楽の演奏と弄槍の軽業芸を見たという記述がある。これが、散楽についての最初の記録とされる。
天平年間のいずれかに、雅楽寮に散楽戸がおかれ、朝廷によって保護される芸能となった。天平勝宝4年(752年)の東大寺大仏開眼供養法会には、他の芸能と共に散楽が奉納された。しかしその庶民性の強さや猥雑さからか、桓武天皇の時代、延暦元年(782年)に散楽戸制度は廃止された。
平安時代(794年〜1185年/1192年)の猿楽
平安時代、猿楽は秀句(ダジャレなど)・物まね・寸劇などの滑稽な演技を主とする芸能となった。これが、現在の狂言へとつながっていく。
- 散楽戸制度が廃止されたとはいえ、散楽は宮中で全く演じられなくなったわけではない。平安時代になると、宴席で余興的に行われるようになった。
- 例えば『日本三代実録』によると、承和3年(837年)に仁明天皇が、弄玉、弄刀(今で言うジャグリングのような曲芸)の散楽を演じさせたとの記録がある。
- 他にも『日本三代実録』には、御霊会などの余興として散楽が演じられたとする記述があって注目されるが、中でも元慶4年(880年)に相撲節会の余興として演じられた散楽は、演者がほとんど馬鹿者のようで、人々を大いに笑わせたとある。当時の散楽師が曲芸だけでなく、今の狂言に通じる滑稽物真似的な芸もしていたことが窺える貴重な記録である。
- 散楽戸の廃止で朝廷の保護を外れたことにより、散楽は寺社や街頭などで以前より自由に演じられ、庶民の目に触れるようになっていった。そして都で散楽を見た地方出身者らによって、日本各地に広まっていった。やがて各地を巡り散楽を披露する集団も現れ始めた。こういった集団は後に、猿楽や田楽の座に、あるいは漂泊の民である傀儡師たちに、吸収、あるいは変質していった。
応和3年(963年)、村上天皇により、宮中では散楽の実演は全く行われなくなった。以降、散楽という言葉に集約される雑芸群は、民間に広まった様々な職業芸能に引き継がれていく。鎌倉時代に入ると、散楽という言葉もほとんど使われなくなった。
鎌倉時代(1185年/1192年〜1333年)の猿楽・田楽
和歌は不得手だったが今様を愛好し『梁塵秘抄』を撰した後白河天皇(在位1155年〜1158年9月5日)の時代は田楽や猿楽といった庶民の雑芸が上流貴族の生活にも入り込み、催馬楽・朗詠に比べて自由な表現が盛んとなっていく時代でもあったとされる。
そういう時代の空気を受けて猿楽は滑稽な演技だけでなく、ストーリー性のある演劇的な演目をも上演するようになる。これが、現在の能へとつながっていく。
- これと並行して大寺院の法会のさいの魔除けや招福の芸能をも担うようになり、それが〈翁〉のもととなる。この芸は、神聖な演技として非常に重視されていた。
- その一方でこの頃、もとは田植えや稲刈りなど農事に関連した芸能から発達した 田楽も演劇を上演するようになる。
こうして鎌倉時代には「猿楽の能」「田楽の能」が併存する事になったのである。
室町時代(1338年〜1573年)の能
室町時代、さまざまな寺社をパトロンとして、多くの座(劇団)が成立するようになる。なかでも、興福寺を基盤とする大和猿楽の中からは観阿弥・世阿弥の親子が登場。将軍足利義満の後援を得て京都にも進出。
- 観阿弥は先行芸能である 曲舞(くせまい)を能に摂取し、それまでの 小歌(こうた)ではできなかった長文の作詞を可能にし、対話の面白さを見せる作品を作った。ただその演目には仏教説話の域を抜け切れていない側面も?
*はじめ興福寺、春日神社などの神事能に奉仕する大和猿楽四座の結崎座の一員として、大和および、近隣の各地で活躍していたが、1370年代ごろから自らの一座を率い醍醐寺での演能など、京都周辺へも進出していった。当時都では猿楽より田楽のほうが評価が高く、足利尊氏などの権力者も田楽を後援していたが、1375年(永和元年 1374年説もあり)に京都今熊野で観阿弥が息子の世阿弥とともに演じた猿楽能を足利義満が見物、以降、将軍はじめ有力武家、公家らの愛顧を得、観阿弥が率いる観世一座は幕府のお抱え的存在とみなされるようになる後半生は京都を中心に各地で活躍、大和でも興福寺の薪猿楽をつとめるなどしていたが、1384年、駿河静岡浅間神社での演能ののち同地で死去。その人気の秘訣は大和猿楽が得意とした物真似芸に、田楽の優美な舞や、南北朝に流行した曲舞(くせまい)の音曲を取り入れた新演出が、当時の観客の心に強い感興をおよばしたことだとされる。- 世阿弥は、能の内容や芸術理論を深化させ、こんにちに伝わる能の基礎をつくりあげた。「幽玄」を重視する能の作風、霊が登場して自らを語る複式夢幻能の形式などは、世阿弥によって整えられたもの。
*「幽玄」…本来中国の典籍に見出される語で,原義は老荘思想や仏教の教義などが深遠でうかがい知ることができないことを意味した。『古今和歌集』真名序や『本朝続文粋』など日本の文学作品でも,神秘的で深い意味があるらしいが明確にはとらえられないという意に用いている例がある。- 彼らは、田楽や、比叡山を基盤とする近江猿楽などのライバル達と鎬を削り合うが、次第に大和猿楽が優勢となっていく。
*「近江猿楽」…中世、近江の日吉(ひえ)神社・多賀神社に属した猿楽団体。みまじ・山階・日吉などの諸座があったが、室町末期には大和四座に押され衰退。元来大和猿楽は物真似の芸能であり、雅な天女舞を中心とした幽玄美を売り物としていたのはライバル関係にあった近江申楽の方だった。世阿弥はむしろその幽玄美を大胆に取り入れる事によってライバルに勝利したとも。
- こうして世阿弥により整えられた能の様式をふまえ、息子達の世代はさらに発展させた能を作っていく。世阿弥の息子の 観世元雅。娘婿の金春禅竹。
*能が庶民のものから貴族や上流武士の深い鑑賞にうつっていく時代を反映して韜晦性や神秘性や空想的異国趣味を強めていく。- また、作品こそ遺していないものの、世阿弥の甥の音阿弥はすぐれた役者として将軍家の寵愛を受け、大和猿楽の地位を確かなものにしていく。
大和猿楽…大和国(現在の奈良県)を中心として活躍した猿楽の座。大和猿楽四座は現在の能楽協会の直接の母体である。
- 古くから興福寺や春日大社などの神事に奉仕することを職務とし、外山(とび)座、坂戸座、円満井(えんまんい)座、結崎(ゆうざき)座の4座が特に知られて、大和四座と称された。
- 室町時代に入って結崎座の観阿弥・世阿弥父子が将軍家に重んじられて猿楽を現在の能楽とほぼ同等の芸能に発展させている。
以後、豊臣氏・徳川氏にも重んじられ、外山座は宝生座、坂戸座は金剛座、円満井座は金春座、結崎座は観世座となり、元和年間に金剛座から分かれた喜多流を加えた四座一流の系譜(原則として世襲)を継ぐ能楽師によって、現在の能楽協会が構成されている。
早春の生田の里。この地を通りかかった僧の一行(ワキ・ワキツレ)の前に菜摘みの女たち(シテ・ツレ)が現れる。僧たちは生田川伝説にいう「求塚」はどこかと尋ねるが、女たちはまともに答えようとはせず、歌を歌いながら古歌にも詠まれる菜摘み続ける。
そのうち肌寒くなってきたので帰ろうとするが、その中の一人だけ帰らず留まっており、僧たちを近くにある求塚へ案内しようと言う。女は、この塚の由来を語る。それは、二人の男に思いを掛けられた菟名日処女(うないおとめ)という女性の、悲劇の物語であった。
昔、この地に菟名日処女(うないおとめ)という女と、彼女に想いを寄せる二人の男がいた。処女は「あの生田川にいる鴛鴦(おしどり)を射た方と契ろう」と言うが、その鴛鴦さえ、二人の放った矢が同時に命中する始末。その時私は「あの鳥の夫婦の仲をさえ引き裂いてしまった。これも全ては私の業ゆえ」と思い、罪の意識から生田川に身を投げた。二人の男は後を追って刺し違え、その三人を埋葬したのが、この塚なのだという。
女は、自分こそその処女の霊だと仄めかし、塚の中へ消えて行く。僧たちが彼女を弔っていると、地獄の責めによって憔悴しきった姿の処女の亡霊(後シテ)が現れ、自分ゆえに二人の男を悩まし、罪も無い鴛鴦の命さえ奪ってしまったのだと明かし、その前世の業によって地獄で苦しみを受けているのだと言う。亡霊は、地獄の責めの様を見せると、消えていくのであった。
高野山の僧の一行が、都へ上る途上、摂津国阿倍野(山城国鳥羽とも)付近に差し掛かった。そこで僧は、乞食の老婆が、朽木の卒都婆に腰掛けているのに気づく。
※卒都婆(卒塔婆)…サンスクリット語でストゥーパ。もとは釈迦の遺骨を納めた聖なる塚のこと。仏教の広まった各地で、これをかたどった塔(同じく卒都婆と呼称)が作られるようになり、仏の体を表すものとして、礼拝の対象となる。後に墓標、死者を供養する塔としても用いられるようになる。また高野山など、聖地への道しるべとしても建てられ、この曲の卒都婆はこちらを指すとみられる。この老婆は、実は、かつて絶世の美女で、数多くの浮名を流した有名な歌人、小野小町その人だった。僧は、老婆が仏を粗末に扱っていると断じ、その振る舞いを正して卒都婆から立ち退かせようと、説教を始める。すると老婆は、非常に含蓄のある言葉を返し、言い負かしてしまう。老婆をただ者ではない、と感じ取った僧は、老婆に対して深々と礼を尽くす。
老婆は、自信満々に歌を詠み、さらに僧を感心させる。僧が老婆に名を尋ねると、老婆は「小野小町のなれの果てだ」と明かす。小町は、美貌を誇った往時を懐かしみ、翻って老いを深めた今の境遇を嘆く様子を見せた後、狂乱状態となってしまう。このとき、小町には、かつて自分を恋慕した深草少将の怨霊が憑りついていた。
その昔、深草少将(四位の少将)は、小町に恋心を打ち明けたのだが、小町は百夜私のもとに通ってきたら、あなたの恋を受け入れましょうと言い、毎日通わせた。深草少将は九十九夜まで通ったが、最後の一夜を通う前に死んでしまう。恋を成就できなかった深草少将の怨念が残り、老境の小町を苦しめていたのである。
小町は、狂乱の内に深草少将の百夜通いの様子を再現するが、やがて狂いから醒め、後世の成仏を願うことが本来の人の道であると語り、悟りの道に入ろうと志す。
雲居寺境内、自然居士(半俗の少年僧、シテ)の七日説法の結願(最終日)。貧しい幼い者が現れ、衣を差し出し両親の供養を願う。自然居士も見物人も幼い者の心がけに涙する。
ところが人買い(ワキ)が説教の場に乱入。買い上げた幼い者を連れ去ろうとする。自然居士はかの衣は幼い者が人買いに自らを売って得たものと見抜き、これまでの六日間が無駄になるのを承知で、善悪を弁えることが更に重要であると説教をやめ、幼い者に縄をかけ舟に乗って去って行く人買いを追い諭そうとする。
琵琶湖畔は大津で人買いに追い付いた自然居士は衣を叩き付けるが、人買いにも一旦買った者は返さないという掟があると譲らない。自然居士もまた人助けに失敗したら二度と庵室に戻らないという掟があると言いはる。人買いは「言う事をきかないと痛い目に合うぞ」と脅すが「それも捨身の行」と譲らない。「殺すぞ」と脅しても「殺されても舟から下りない」としぶとい。
人買いも困り果て、自然居士に舞を舞わせ、それで幼い者を返してやることにする。自然居士は舟を題材にした中ノ舞、羯鼓の舞を見せ、めでたく幼い者を京都に連れ帰ることに成功する。
帰らぬ夫を待ち続ける女の霊を描く。寂しさと喪失感に耐えながらなおも夫を待ち続ける美しい愛情が主題。
伊勢物語の23段「筒井筒」を元に構成されており、前段で伊勢物語で描かれた夫との恋が懐かしく回想される。後段では寂しさの高じた女が夫の形見の衣装を身にまとい、夫への思いを募らせながら舞を舞う。
これは(多くの場合)男性が女装して演ずる主人公が、更に男装する事を意味し、この男女一体の舞が本作の特徴である。なお、題名の「井筒」とは井戸の周りの枠のことで、主人公の女にとっては子供の頃に夫と遊んだ思い出の井戸である。
伊勢物語の各段の主人公は在原業平と同一視される事が多いが、本作でもこれを踏襲し、主人公夫婦を業平とその妻(紀有常女)と同一視している。
九州阿蘇宮の神官(ワキ)が播磨の国、高砂の浦にやってきた。春風駘蕩とする浦には松が美しい。遠く鐘の音も聞こえる。
そこに老夫婦(シテとツレ)が来て、木陰を掃き清める。老人は古今和歌集の仮名序を引用して、高砂の松と住吉の松とは相生の松、離れていても夫婦であるとの伝説を説き、松の永遠、夫婦相老(相生にかけている)の仲睦まじさを述べる。命あるものは全て、いや自然の全ては和歌の道に心を寄せるという。
ここで老夫婦は自分達は高砂・住吉の松の精である事を打ち明け、小舟に乗り追風をはらんで消えて行く。
神官もまた満潮に乗って舟を出し(ここで『高砂や…』となる)、松の精を追って住吉に辿り着く。
「われ見ても 久しくなりぬ住吉の、岸の姫松いく代経ぬらん(伊勢物語)」の歌に返して、なんと住吉明神の御本体が影向(ようごう)され、美しい月光の下、颯爽と神舞を舞う。
平家一門が都落ちした後、都でひっそり暮らしていた平清経の妻のもとへ、九州から、家臣の淡津三郎(あわづのさぶろう)が訪ねて来る。三郎は、清経が、豊前国柳が浦〔北九州市門司区の海岸、山口県彦島の対岸〕の沖合で入水したという悲報をもってやって来たのだった。形見の品に、清経の遺髪を手渡された妻は、再会の約束を果たさなかった夫を恨み、悲嘆にくれる。そして、悲しみが増すからと遺髪を宇佐八幡宮〔現大分県北部の宇佐市〕に返納してしまう。
しかし、夫への想いは募り、せめて夢で会えたらと願う妻の夢枕に、清経の霊が鎧姿で現れる。もはや今生では逢うことができないふたり。再会を喜ぶものの、妻は再会の約束を果たさなかった夫を責め、夫は遺髪を返納してしまった妻の薄情を恨み、互いを恨んでは涙する。
やがて、清経の霊は、死に至るまでの様子を語りながら見せ、はかなく、苦しみの続く現世よりは極楽往生を願おうと入水したことを示し、さらに死後の修羅道の惨状を現す。そして最後に念仏によって救われる。
都へと上ってきた旅の僧(ワキ)がある夜、六条河原院の邸宅跡を訪れる。そこに桶を携えた潮汲み(製塩のため、海水を汲むこと)の老人(前ジテ)が姿を見せる。
海辺でもないのになぜ潮汲みを、といぶかる僧に老人は、ここが亡き融大臣の邸宅・河原院の跡であると伝え、生前の融が奥州塩竈の光景を再現しようと、難波の浦からわざわざ海水を運ばせ、庭で潮汲み・製塩を行わせていた故事を語る。しかし融の死後は跡を継ぐ人もなく、邸宅も荒れ果ててしまったといい、老人は昔を偲んで涙を流す。
*源融(822年〜895年)は嵯峨天皇の十二男。臣籍降下して従一位左大臣にまで登った実在の人物。六条に築いた邸宅・河原院に塩竈の光景を写して風流三昧に耽った、との逸話は、古く「古今和歌集」所載の紀貫之の歌(君まさで煙絶えにし塩釜のうらさびしくも見えわたるかな)や、「伊勢物語」81段などに伝えられている。
老人はさらに、邸宅から見える京の山々について僧に案内するが、ふと我に返ったように桶を取り直して潮汲みを始める。やがて立ちこめる潮曇りの中、老人はいつの間にか姿を消してしまう。
そこにやってきた近所の男(アイ)は、老人の正体は融本人の霊ではないかと僧に教える。男が言うとおりに僧がその場で待っていると、生前の姿の融(後ジテ)が現われる。月の光に照らされながら、融は舞に興じる。やがて明け方が近づくころ、融はまるで「月の都」に向かうように、月光の中に消失する。
タイトルの「砧」とは木槌で衣の生地を打って柔らかくしたり艶出ししたりする道具のこと。この作品では、女主人公が砧を打つことが情念の表現になっている。
都にいる芦屋何某(ワキ)が、侍女夕霧(ツレ)をよんで「訴訟のため都にいるが、こちらにきてすでに三年もたってしまった。ずいぶん長い間故郷を留守にしている。この年末には筑前芦屋(現在の福岡県遠賀郡芦屋町一帯の地域)に帰るから、さきにかえって妻にそのことを伝えてきなさい。」と命じる。夕霧はその命をうけて九州へ旅立つ。筑前の国芦屋の里につき、何某の邸で案内を請うと、橋懸(はしがかり)から、何某の妻(前シテ)が登場する。妻は、夕霧なら人をとおして案内を請う必要はない。こちらへきなさいと招き入れる。そして長年音信のなかった恨みをうったえる。夕霧は帰ってきたかったのだが、宮仕えでひまがなくて心外にも三年間都に滞在したと述べる。妻は、人目も草も枯れ果てた田舎暮らしのつらさを訴え、地謡(コーラス)がその妻の心を「思い出だけが残り、昔のことはあとかたもなく変わってしまったのだ。人の世に偽りというものがなければ、言葉というのは嬉しいものだが、すぐ帰るという夫の言葉を頼りに待つ私の心はおろかな心だ。」と謡う。
そこに、砧を打つ音がきこえてくる(舞台では鼓での演奏)。妻が「なんの音でしょう」と問うと、夕霧は「里人が砧を打つ音です。」と答える。妻は「昔、中国の蘇武という人が、異民族の国におきざりにされたとき、古里の妻子は夫のいるところの夜の寒さを案じて、高楼にのぼって砧を打ったといいます。万里をはなれてその音が蘇武の耳にとどいたそうです。それは妻子の志がしっかりしていたからです。わたしも、さみしい気持ちを砧に託して心をおちつかせましょう。」と言う。夕霧は「砧などというものは身分の低いものが打つものですが、お心がなぐさむのでしたら、私が用意しましょう。」と、後見がもちだしてきた砧の作り物の前に座り、両人「思ひを述ぶる便りとぞ、恨みの砧、打つとかや」と謡いつつ、砧を打つ。
砧を打つにしたがって、妻の感情がたかまっていき、地謡も参加して詩情深い詞章とともに、妻が舞いはじめる。
「西より来る秋の風の吹き送れと間遠の衣打たうよ(いまは秋、飽きられた女のところから、遠い都に、西風をおくれとばかり、砧をうとう)」
「わが心かよひて人に見ゆるならば、その夢を破るな破れてのちはこの衣、たれかきても問ふべき (私の心が夫のもとに通じて、夫が夢をみるなら、夢よやぶれないでくれ、破れたならこののちは、この衣をだれが着るだろう)」
「夜嵐 悲しみの声、蟲の音、まじりておつる露涙、ほろほろはらはらはらと いづれ砧の音やらん (夜の嵐、悲しみの声、蟲のなく声、それらがまじりあって落ちる涙 ほろほろはらはら どれが涙の音か、砧の音か…)」
舞いながら悲しみが最高潮に達したとき、侍女夕霧が立ち上がり、伝言をきいてきた体(てい)で、「なんといえばよいでしょう。いま都からこの年の暮れにもお帰りにならないと知らせがまいりました。」と伝える。シテは「ああせめて年の暮れにはと、自分の苦しい心をいつわってまっていたのに、あの方はもうほんとうに心変わりしてしまわれた。」といい、病の床にふせって、やがて息たえてしまう。
間狂言で芦屋何某の家来(アイ)が登場。口上を述べる。「芦屋の何某殿は、訴訟で都にのぼられ三年になる。故郷のことが心配でも帰ることがおできにならない。そこで夕霧という侍女をつかわし、この年末には必ず帰ると伝えさせたので、奥様もおよろこびになった。待ちかねておられる心を少しでもなぐさめようと、里の女たちが打つ砧を夕霧とふたりで打っておいでであった。そうして元気づけていたのだが、都からこの暮にも帰れなくなったというお知らせがとどき、女心のはかなさ、さては夫は心変わりしたかと、まともでないようなこともおおせられ、ついになくなってしまわれた。それを聞かれて都の殿は、さっそくお帰りになり、お嘆きは大きかったが、返らぬことなので、奥様がいまわの際までうっていた砧をたむけられ、お弔いなさる。みなみなご弔問に参れ。」そういいひろめて、退場する。
芦屋の何某(ワキ)が太刀持(ワキツレ)とともに登場「ああかわいそうなことだった。三年すぎてしまったことをうらんで、ついに永遠のわかれとなってしまったではないか。梓弓を鳴らして死んだ人の言葉をきこう。」と合掌すると、橋懸から妻の亡霊が登場する。このとき亡霊(後シテ)は、泥眼という面をかけ、白い装束をまとい、杖をもった憔悴した姿である。「三途の川にしずんでしまったはかない身」と謡いだし「邪淫の業がふかいのか、安んじて待つことをしなかった罪で、うてやうてやと報いの砧 と地獄でむちうたれております。ああ、生前の妄執がうらめしい。」と訴える。地謡は「責められて叫んでも声はでず、砧の音もきこえず、呵責の声のみがきこえる。」と因果の妄執のおそろしさを謡う。
妻の亡霊は呵責の声に耳をふさぎ、「恨みは葛の葉の」と舞いはじめる。「執心のさまをおみせするのもはずかしい。愛するあなたと二世をちぎってもなおたりず、千代先までもと願ったのに、それを無になさったそらごと、それが人の心でしょうか。」と夫につめよる。「烏(カラス)などという大うそをつく鳥もこれほどのうそはつかないはず。草木、鳥獣でも心はあるでしょう。蘇武という人は雁に手紙をつけて万里をへだてた古里に送ったそうです。愛する心が深かったからでしょう。あなたはどうでしょう。夜寒の砧をうったのに、うつつにも夢にも、思い出してくれたでしょうか。恨めしいこと。」とさめざめと泣く。夫が合掌すると、妄執がはれ、シテは晴れやかに舞う。地謡によって「法華読誦の力にて、幽霊まさに成仏の道明らかになり(中略)打ちし砧の声のうち、開くる法の華心、菩提の種となりにけり (法華経の力で成仏の道が明らかになった。砧をうつ声のなかで法華経の華が開いたのだ。それが菩提の種となったのだ)」と謡われ、シテが成仏したところで能は終わる。
一般に狂女物は再会→ハッピーエンドとなる。ところがこの曲は春の物狂いの形をとりながら、一粒種である梅若丸を人買いにさらわれ、京都から武蔵国の隅田川まで流浪し、愛児の死を知った母親の悲嘆を描く。
渡し守(ワキ)が、これで最終便だ今日は大念仏があるから人が沢山集まるといいながら登場。京都から来た旅の男(ワキヅレ)の道行きがあり、渡し守と「都から来たやけに面白い狂女を見たからそれを待とう」と話しあう。
次いで一声があり、狂女(シテ)が子を失った事を嘆きながら現れ、カケリを舞う。道行きの後、渡し守と問答するが哀れにも『面白う狂うて見せよ、狂うて見せずばこの船には乗せまいぞとよ』と虐められる。
狂女は業平の『名にし負はば…』の歌を思い出し、歌の中の恋人をわが子で置き換え、都鳥(実は鴎)を指して嘆く事しきりである。渡し守も心打たれ『かかる優しき狂女こそ候はね、急いで乗られ候へ。この渡りは大事の渡りにて候、かまひて静かに召され候へ』と親身になって舟に乗せる。
対岸の柳の根元で人が集まっているが何だと狂女が問うと、渡し守はあれは大念仏であると説明し、哀れな子供の話を聞かせる。京都から人買いにさらわれてきた子供がおり、病気になってこの地に捨てられ死んだ。死の間際に名前を聞いたら、「京都は北白河の吉田某の一人息子である。父母と歩いていたら、父が先に行ってしまい、母親一人になったところを攫われた。自分はもう駄目だから、京都の人も歩くだろうこの道の脇に塚を作って埋めて欲しい。そこに柳を植えてくれ」という。里人は余りにも哀れな物語に、塚を作り、柳を植え、一年目の今日、一周忌の念仏を唱えることにした。
それこそわが子の塚であると狂女は気付く。渡し守は狂女を塚に案内し弔わせる。狂女はこの土を掘ってもわが子を見せてくれと嘆くが、渡し守にそれは甲斐のないことであると諭される。やがて念仏が始まり、狂女の鉦の音と地謡の南無阿弥陀仏が寂しく響く。そこに聞こえたのは愛児が「南無阿弥陀仏」を唱える声である。尚も念仏を唱えると、梅若丸の霊(子方)が一瞬姿を見せる。だが東雲来る時母親の前にあったのは塚に茂る草に過ぎなかった。
河内国(大阪府)高安の里の左衛門尉通俊(ワキ)は、さる人の讒言を信じ、その子俊徳丸を追放する。しかし、すぐにそれが偽りであることがわかって、不憫に思い、彼の二世安楽を祈って天王寺で施行を行う。
一方、俊徳丸(シテ)は悲しみのあまり盲目となり、今は弱法師と呼ばれる乞食となっている。彼は杖を頼りに天王寺にやって来て、施行を受ける。折りしも今日は、春の彼岸の中日にあたり、弱法師の袖に梅の花が散りかかる。彼は、仏の慈悲をたたえ、仏法最初の天王寺建立の縁起を物語る。その姿を見ると、まさしく我が子だが、通俊は人目をはばかって、夜になって名乗ることにする。そして日想観を拝むようにと勧める。天王寺の西門は、極楽の東門に向かっていると述べる。
弱法師は入り日を拝み、かつては見慣れていた難波の美しい風景を心に思い浮かべ、心眼に映える光景に恍惚となり、興奮のあまり狂うが往来の人に行き当たり、狂いから覚める。物を見るのは心で見るのだから不自由はないと達観しても、やはり現実の生活はみじめなもの。やがて夜も更け、人影もとだえたので、父は名乗り出る。親と知った俊徳丸は我が身を恥じて逃げようとするが、父はその手を取り、連れ立って高安の里に帰る。
平治の乱の直後。かつて源朝長の養育係をつとめ、今は清涼寺の僧となっていた男(ワキ)は、従僧(ワキツレ)を連れ、朝長の菩提を弔うため、彼の終焉の地である美濃国 の青墓宿(現在の岐阜県大垣市青墓)を訪れる。
朝長の墓前で手を合わせていると、この地の遊女宿の長者(シテ)が侍女(ツレ)・従者(トモ)を連れて現れる。実は彼女こそ、朝長が自害した晩に宿を貸していた女であった。朝長の縁者だと明かした僧に、長者は朝長自害の様子を語り、彼の追善供養を行うために自らの宿所を提供する。
夜、僧が観音懺法で供養を行っていると朝長の幽霊(後シテ)が現れ、供養に感謝し、また長者の懇意に感謝の言葉を述べ、修羅の苦患のさまを見せるのであった。
唐土楚国の湘水というところで山居の僧(ワキ)が毎夜読経をしていると、ひとりの女(シテ)がそっと聴きに来る様子なので、ある夜、僧は女にその素性を尋ねる。
すると、女は「私はこの辺りの者で仏縁を結びたいと思って来るのですから、どうか内へ入れて御法を聴聞させてください」と言う。その志に感じて僧は庵の中に入れて、薬草喩品を読んで聞かせる。
それに対して、女は草木さえも成仏できる法華経の功力をたたえ、その後、自分が芭蕉の精であることをほのめかして消え失せた。
その後もなお僧は夜もすがら読経をしていると、芭蕉の精が再び女の姿で現れる(後シテ)。そして非情の草木も無相真如の體であることや、芭蕉葉が人生のはかなさを示していることなどを語り、舞を舞った。秋風が吹きすさむとその姿は消えて、庭の芭蕉の葉だけが破れて残っていた。
晩秋の9月7日、旅僧がひとり、嵯峨野を訪れ、伊勢斎宮の精進屋とされた野の宮の旧跡に足を踏み入れる。昔そのままの黒木(皮のついたままの木)の鳥居や小柴垣を眺めつつ参拝していると、榊を持った上品な里女が現れる。
女は僧に向かい、毎年必ず長月七日に野の宮にて昔を思い出し、神事を行う、ついては邪魔をしないで立ち去るようにと話す。僧が、昔を思い出すとはどういうことかと尋ねると、かつて光源氏が、野の宮に籠もっていた六条御息所を訪ねてきたのがこの日だと告げ、懐かしそうに御息所の物語を語る。そして自分こそが、その御息所だと明かし、姿を消す。
別に現れた里人から、改めて光源氏と六条御息所の話を聞いた僧は、御息所の供養を始める。すると、牛車に乗った御息所の亡霊が現れる。御息所は、賀茂の祭りで、源氏の正妻葵上の一行から、車争いの屈辱を受けたことを語り、妄執に囚われている自分を救うため、回向して欲しいと僧に頼む。野の宮での源氏との別れの記憶にひたりながら、御息所は、しっとりと舞い、過去への思いを深く残す様子で再び車に乗り、姿を消す。
北国の僧が都に上り千本の辺りまで来ると時雨が降り始めたので近くにあった亭(ちん:高台など眺望の良い所に建てられたあずまや)で雨宿りをしていると一人の女が現れ亭が藤原定家が時雨の和歌を詠んだ場所と教え、その後式子内親王の御墓に僧を案内する。
そこで僧が見たものは葛に覆い隠された御墓。これが定家と密かに契りを結んでいた内親王が亡くなった後定家の執心が葛となって取り憑いている姿と女は語り、我こそ式子内親王と言い姿を消す。
僧が弔っていると法華経の功力で成仏できると喜び報恩の舞を舞う。しかし再び葛が這い纏いその姿は御墓の中に消え失せる。
戦国時代 (1493年〜1587年)の能
戦国時代にはいると、それまで能を庇護していた寺社や大名や公家達に余裕がなくなり、能は新たな観客層を開拓せざるを得なくなる。そういった社会構造の変化や、時代の風潮の変化によって、新しい作風の能が必要となった。
- この時代、 観世信光や 金春禅鳳らが現れ、スペクタクルな能や、見た目に華やかでショー的な能(当時で言う「風流能」)を書いている。
*観世信光は「紅葉狩」「鐘巻(『道成寺』の原型)」の作者でもある。能の鬼は多くの場合女の妄念から生ずるが(例えば鐡輪、葵上、道成寺)、「紅葉狩」では鬼が本体であって、仮に美女の姿をとっている(黒塚もそのように解釈することが可能である)。この点、戸隠、鬼無里の鬼女伝説と内容的に関連しており、後者が能の影響を受けている可能性もある。後に本作をもとに近松門左衛門によって歌舞伎の時代物「色狩剣本地(もみじがり つるぎの ほんち、正徳4年)」、九代目市川團十郎による舞踊劇「紅葉狩(明治20年)」が作られている。- また、この時代、装束が次第に豪華になり、また囃子の体系が確立されるなど、現在みられる様式がほぼ確立されていく。
- 戦国時代末に天下を統一した豊臣秀吉は能を愛し、最奥の秘曲〈関寺小町〉を含む多くの能を自ら舞うなど、たいへん能を保護した。
また 戦国時代後期ころから、新作能はあまり書かれなくなり、能は古典劇としての色彩を強めていく。
源義経が平氏を討伐したのち、頼朝に疑われて西国に落ちるところからこの能ははじまる。前段は義経の愛人静御前と義経の哀切な別れ、後段では平知盛の霊が海上で義経主従を悩ます劇的な場面で構成されている。シテ方は静御前と知盛の霊というまったく異なったキャラクターを一つの能の前半、後半で演じ分けなければならない。なお義経役は子方(子供の能役者)が演じる。また土地の漁師役の狂言方(間狂言)が、終始重要な役柄を演じることも特徴。この形式は「アシライ間(アイ)」といわれている。
義経(子方)とともに登場した弁慶(ワキ)が、義経が頼朝にうとまれたため西国に下るときめたことを語る。まずは淀川をくだり摂津国尼崎大物浦から船出するという計画である。京の南郊、岩清水をとおって、大物浦までの道行が謡われたあと、目的地の大物に到着、この地に住む漁師に宿と船の用意をたのむ。その宿で、弁慶は静御前を都にかえすよう義経に進言、義経が承知するので、弁慶は静のいる別の旅宿にむかう。静(前シテ)は「おもいもよらぬおおせ」と断り、義経に会いにいくという。弁慶はしかたなく静を伴って義経の宿に帰ってくる。
義経は、ここまでけなげについてきた静をほめ、都に帰って時節を待てと命じる。静は弁慶の独断かと疑っていたことをわび、弁慶も義経と静の別れにもらい泣きをする。静は次にお会いできるまで命を惜しむと涙を流す。義経は弁慶に命じ静に酌をさせ、別れの酒盛りとなる。静は烏帽子をつけ白拍子の姿で舞をまう。会稽山の故事を謡いつつ、頼朝の疑いが晴れることを願う舞である。義経、弁慶主従をのせるために用意された船はともづなを解き、主従の乗るのを待っている。静はその場から泣きつつ立ち去る。
間狂言では大物浦で船の用意をしていた漁師(アイ)が登場、義経と静の別れの様子をみて落涙したと語る。弁慶(ワキ)も涙を流したと応じる。ところで内密に船は用意したかと弁慶が問うと、船足の速い船を用意したと漁師は答える。弁慶は、では出発しようという。そこへ義経の従者(ワキツレ)がきて、義経が風が強いので出発を延期しようといっていると報告する。義経は静との名残をおしんでもうしばらく逗留するつもりだと推量した弁慶は、以前は大風でも戦場で船をだしていた義経が、そのように気弱いことをいっていてはいけない、すぐにでも船を出す、用意せよと漁師に命じる。船のかたちのつくりものをもって出てきた漁師は、皆さん船にのってくださいという。一同船に乗ると漁師は船をこぎだし、海上をわたる。彼はこぎながら、いずれ義経が都に復帰したおりには、この海の支配をわたしにまかせてくださいと頼む。弁慶が承知すると、忘れないでくれと念をおす。そのようなやりとりをしているうち海が荒れ模様になってくる。
武庫山(いまの六甲山)から風が吹き降り、船がだんだん沖合いに流されていくので、従者(ワキツレ)がこの船にはあやかしがついているのではないかと心配する。そんな不吉なことはいってはならんという漁師(アイ)との問答のあいだも、波はますます高くなる。弁慶(ワキ)が「あら不思議や海上を見れば、西国に滅びし平家の一門」と声をあげると、義経(子方)はいまさらおどろくことではないではないか、悪逆の限りをつくして海に沈んだ平家一門のことだ、たたりをするのはあたりまえだろうと平然といいはなつ。
そこへ長刀をかたげた知盛の霊(後シテ)が橋懸(はしがかり)からあらわれる。義経を海に沈めんとしてあらわれたのだといい、激しい舞を舞う。その時義経少しもさわがず(謡曲原文ママ)刀をぬいて亡霊と切り結ぶ。弁慶は刀ではかなわないでしょうといい、数珠を繰って経文を唱える。祈りの力で悪霊は遠のくものの、またつめよってくる。双方きびしくせめぎあうが弁慶の祈りが功を奏し知盛の霊は引き潮に引かれて遠ざかっていく。
場面は信濃国戸隠。紅葉見物の上臈(前シテ)一行の道行きで幕を開ける。若い美女が数人連れ立って紅葉見物にやってきた。絶景の中、地謡前に幕を巡らし宴会となる。次いで馬に乗り供の者を従えた平維茂(ワキ)が登場する。鹿狩りにやってきた平維茂の一行である。橋懸りでの道行きの後、楽しげな宴会が開かれているのを発見した維茂は、供の者に様子を見てこさせる。 美女一行の供者(アイ)との問答があるが、美女一行は素性を明かさない。そこで維茂は馬を降り通り過ぎようとするが上臈が現れ、どうかお出でになって、一緒に紅葉と酒を楽しみましょうと誘惑する。
無下に断ることもできず宴に参加した維茂であったが、美女の舞と酒のために不覚にも前後を忘れてしまう。上臈の舞う美しい中ノ舞は突如激し急ノ舞となり、美女の本性を覗かせるが、維茂は眠ったままである。女達は目を覚ますなよと言い捨てて消える。
ここで場面は夜となる。八幡宮の神(アイ)が現れ維茂の夢中に、美女に化けた鬼を討ち果たすべしと告げ、神剣を授ける。覚醒した維茂は鬼を退治すべく身構え、嵐と共に炎を吐きつつ現れた後シテ(面は顰または般若)と丁々発止、激しい攻防の末ついに鬼を切り伏せることに成功する。
一遍上人の教えを全国に広めようとしている諸国遊行の僧が、上総国(千葉県)から奥州へと旅する。白河の関を越えて、新道を行こうとすると老人(前シテ)が現れ、声をかけてくる。老人は、先代の遊行上人が通ったのは、その新道ではなく、古道と呼んでいる昔の道だといい、またそこには朽木の柳という名木があると教え、僧をそちらへ案内する。もう今はあまり人が通わなくなり、草の生い茂った古道をついて行くと、古塚の上に柳の老木がある。僧がこの柳のいわれを尋ねると、老人は昔、西行がこの地へ旅し「道のべに 清水流るる 柳かげ しばしとてこそ 立ちどまりつれ」という歌を詠んだことを教える。そして僧に求めて十遍の念仏を授かると古塚に姿を消してしまう。
僧は通りかかった土地の者からも朽木の柳のいわれを聞き、先程の老人の話をする。土地の者は驚いて、再度、奇特を見るように勧める。その夜、古塚のそばで、僧が念仏を唱え、仮寝をしていると、柳の精(後シテ)が白髪の老翁姿で現れる。そして、夕刻、ここに案内した者だと明かし、草木の霊まで成仏することのできる念仏の功徳をたたえる。さらに柳にちなむ和漢の故事をひき、楊柳観音や蹴鞠のこと、さらに「源氏物語」の柏木の恋の話へと次々と話題を広げてゆき、十遍の念仏への報謝の舞を心静かに舞って見せる。僧が夜明けの風に目覚めると、そこには朽木の柳が立っているだけだった。
時の帝に仕える臣下が、大和国吉野から、都の西方の嵐山に移植した桜の様子を見てくるようにという勅命を受ける。勅使として嵐山に着いた臣下は、美しく咲き誇る桜を目の当たりにする。
勅使は、そこで花守の老人夫婦に出会う。木の下を清め、花に向かって礼拝する姿を不審に思い、勅使はなぜかと問いただす。すると老人夫婦は、神木である吉野の桜を移植したのだから、嵐山の桜も神木である、だから礼拝している、と答える。さらに、吉野の木守(こもり)の神、勝手(かつて)の神が時折訪れる、その神の力により、嵐山というものものしい名を持つこの地でも、風で花が散らされることなく、美しく咲くのだと語る。そして夫婦は自分たちこそが、その二神であると明かし、夜を待てと勅使に告げ、雲に乗って西の山から南のほうへと飛んで行く。
夜になると木守の神、勝手の神が勅使の眼前に現れ、舞を舞う。勅使が感動して見入っていると、南方から芳しい風が吹き、めでたいかたちの雲がたなびき、金色の輝きに満たされて、蔵王権現が力強い姿を現す。
*蔵王権現:吉野山中の金峰山寺の本尊。日本独自の仏。
蔵王権現は、衆生とともに交わりつつ、その苦しみを助け、悪魔を退けて、国土を守る誓いを立てていることを表す。そして木守の神、勝手の神は蔵王権現と一体であり、呼び名が違うだけであることを示した後、嵐山によじのぼって、花に戯れ、梢を駆けて、光り輝く春の盛りを寿ぐ。
中入り狂言として「猿聟(さるむこ)」なる小書(特殊演出)がつく場合がある。これは、猿の格好をした大勢の狂言方の役者が登場し、吉野の猿が嵐山の猿のところに聟入りし、めでたい酒宴を繰り広げるという趣向。一部を除いて、会話は全て「キャキャキャキャ」「キャッキャッ」「キャアキャア」などの猿語で行われる。
場所は天竺波羅奈国(インド中部)。鹿の胎内より生まれ、一本の角を持つ仙人は、一角仙人と呼ばれた(シテ)。勢力を争いの末、龍神たちを岩屋へ封じ込めてしまった。それにより天竺波羅奈国では雨が降らなくなったため、困った帝は策を練り、仙人の神通力を奪おうと、美しい旋陀夫人(前ツレ)を仙人の元へやった。
道に迷った旅人として仙人の元へやってきた官人(ワキ)と旋陀夫人は、まんまと仙人に酒を飲ませ、酔いつぶして神通力を奪う。すると岩屋が鳴動し、封じ込められていた龍神(後ツレ)が飛び出す。驚いて目を覚ました一角仙人は、龍神を制しようとするが、叶わず倒れ伏す。龍神は嵐を起こし、その中を飛び去って行く。
黒谷(俗に黒谷さんと呼ばれ親しまれている金戒光明寺。浄土宗の大本山)の法然上人が賀茂の明神に参詣の時、下り松で男の捨子を拾いあげて連れ帰り育てる。その子が十歳になった時、父母のないことを不憫に思い、説教の後聴衆に向かってその事を物語る。すると若い女性が我が子であると名乗り出、子供の父は一ノ谷で討たれた平敦盛であると言う。
*ちなみに金戒光明寺の境内には熊谷直実と平敦盛の供養塔2基が建てられている。
幼児はそれを聞き、夢で父に会うことを願って加茂の明神へ祈誓をかける。すると御霊夢の中で、父に会いたく思うのならば生田へ行けとのお告げがあったので従者に伴われて生田の森へ赴く。日が暮れてある草庵に立ち寄ると、中に若武者が一人いて、我こそが敦盛であると名乗る。親子の対面を喜びあった後、敦盛は昔の軍物語をするが、ふいに修羅道の責め苦にさいなまれて苦しむ様子を見せる。しかし夜明けと共に我に返り我が子に早く帰ってあとを弔ってくれと言い残して消え去る。
小野の小町はその衰えた老躯を、江州関寺の山陰に小さな庵を結んで侘びしく暮らしていた。その住僧が七月七日の七夕祭の日にあたりの稚児たちを連れて小町を訪ね、歌道の物語を聞かせてほしいとお願いする。
*関寺は現在の大津市逢坂にある長安寺を含む大きな寺であったという。現在長安寺の境内には小野小町供養塔があり、近くの関蝉丸神社の裏山には小町の墓という小町塚がある。またこれも長安寺から近い月心寺の百歳堂には小町百歳の像があるという。関寺の創建は古いが、恵心僧都源信が再建したという。その時一頭の牛が現われ、大いに工事の手助けをしたが、実はこの牛は迦葉仏の化身であり、この霊牛を供養するために大石塔が建てられた。これが今に残る牛塚で、石造宝塔としては最古最大であるといわれている。
小町は今は既に埋もれ木となって、そのようなことは思いもよらぬと断るのであるが、強いての僧の頼みをききいれ、歌道についての古いことなどをねんごろに語って聞かせた。
そうこうしているところに、一人の住僧が小町を迎えにきた。小町は今の身を恥じて一度は断ったのであるが、遂に住僧どもに招じられて寺に赴いた。寺では今宵は織女の祭というので、糸竹管弦を催し、童舞などを舞って興を添えていたが、小町もその面白さに、いつか心も昔にかえって立ち上がり、舞の手も、返す袂もとかく忘れがちで、その上足腰もよろめくのであったが、それでも舞を舞いつつ昔を偲び、あこがれる風情であるが、初秋の短か夜なればあさまにもならば恥ずかしいとて、杖にすがり自分の庵へとたよたよと帰り行くのであった。
途中で允恭天皇とその后衣通姫の名が出てくる。
- 允恭天皇7年12月、新居落成の祝いが行われ、天皇自ら琴を奏で皇后が舞を舞った。当時の慣習として、舞の終わりに舞手は帝に対し「娘子(おみな)を奉りましょう。」と言うのが常であったが、皇后はこれを言いたくなかった。天皇に促され渋々奏上したところ、天皇はすかさず、「そは、誰そ」と問い、慌てた皇后はつい、「私の妹、弟姫です」と答えてしまう。
- 当時弟姫は、容姿端麗でまばゆいばかりの肌の細やかさから、衣通姫(そとおりひめ)と呼ばれていた。皇后は天皇が妹に心奪われることがわかっていたので実は隠していたのである。案の定天皇は、姉の心中を推し量って入宮するのをためらう衣通郎女の元へ、再三使者を送りとうとう妃になることを了承する。
- 天皇はしかし、皇后の嫉妬をおそれて宮中に迎える事はせず、藤原部を定めて新しく茅渟宮を造営しそこへ足繁く通うのである。
- 皇后の怒りは増大し、皇后の出産が迫っても天皇は衣通姫の元への行幸を止めなかったので、さすがの皇后も死を決意する。 これには天皇も慌てて、平身低頭謝ったという。この時皇后が出産したのが、後の雄略天皇である。
江戸時代(1603年3月24日〜1868年)の能
江戸時代になると能は、これまでの展開を踏まえ「 式楽(勅使饗応など、フォーマルな儀式の場で上演される、政府の公式な音楽)」と定められ、格式が重視されて保守的傾向が強まった。
- 芸の統制や演目の固定化が進み創造性は失われてしまったが、それによって工夫は演目の内側へと向かい、細部まで洗練された高度な芸へと発達して、こんにちの能の姿がほぼ完成する。
- 基本的に新作能はつくられず、演目は固定的だったが、埋もれていた作品の復曲はしばしば行われ、たとえば徳川綱吉・家宣の時代に復活された能のなかには〈砧〉〈大原御幸〉など、現在まで伝わる人気曲も含まれている。
- 能が式楽となったことで、庶民の目に触れる機会は稀になってしまったが、その一方で 謡(うたい)は教養や稽古事として人気を博し、たとえば結婚式で〈高砂〉の一節「高砂やこの浦舟に帆をあげて…」を謡うことが慣例化するなど、能のことばは人々にとって身近なものとなった。
- 江戸時代後期の観世宗家であった 観世元章は、演出の工夫に力を入れ、〈采女〉の「美奈保之伝」など多くの小書(特殊演出)を作った。固定化された演目の中でいかに創造性を発揮するか、元章らの工夫によって、現在見られる多彩な演出ができあがったのである。
大衆芸能としての機能は人形浄瑠璃と歌舞伎に継承された。特に「格下」と見られた歌舞伎界は江戸時代一杯、身分上昇運動を試み続けた。
源平の戦いに決着がつき、平家一門が滅びた後のこと。平清盛の娘で安徳天皇の母、建礼門院(女院)は、檀ノ浦の戦いに敗れた時、海に身投げしたのだが、源氏の侍に引き上げられて命を長らえ、出家遁世して都の東北にある大原の寂光院に住み、一門の人々を弔い、仏に仕える日々を送っていた。
春がそろそろ終わり、夏を迎えようかという頃、建礼門院の夫、高倉天皇の父親である後白河法皇が、輿に乗って女院を訪ねる。その頃、女院はともに住む大納言の局(つぼね)(女院の弟、重衡の妻)と一緒に、仏前にお供えする樒(しきみ)の木や花、薪、蕨(わらび)などを取りに山に入っていた。
寂光院に着いた法皇の一行は、こちらも女院と共に住む阿波の内侍(後白河法皇の乳母の子)と会い、女院が出かけていることを知り、待っていた。そこへ女院と局が帰ってくる。こうして女院は、法皇と久々の対面を果たした。女院が、法皇の思いがけない訪問に有難い気持ちを述べると、法皇は、女院が六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六つの世界)を見たと言われているが、どういうわけか、と問いかける。
女院は、数奇な運命を辿ってきた自分の身の上を語り、平家一門の最期と安徳天皇の入水を涙ながらに語る。その後、名残り惜しくも別れの時が来て、法皇は輿に乗って都へ帰り、それを見送った女院は、庵室へ静かに入っていく。
旅の僧の一行(ワキ・ワキツレ)が春日大社に参詣すると、一人の女(シテ)が現れ、春日の森に木を植える。訝る僧たちに、女は春日社創建の故事を語り、木を植えることが神への手向けとなることを説く。次いで女は僧たちを猿沢池に案内し、帝の寵愛が薄れたことを嘆いてこの池に入水した采女の故事を語り、自分こそその采女の霊だと明かして消え失せる。
僧たちが弔っていると采女の幽霊(後シテ)が現れ、采女は和歌や舞によって宮廷に仕えていることを説き、帝の寵愛が薄れる前、曲水の宴の席で御代の永遠を願う歌を詠んだことを明かし、御代の長久を言祝ぐ。
春日社の部分は省略され、最初から猿沢池が舞台となる。小書の名である「美奈保」が「水穂(みなほ)」の宛字であることからも、采女の入水に焦点を当てた演出となっている。
僧侶の一行(ワキ・ワキツレ)が奈良に着いたところで里の女(前シテ)が彼らに声をかけながら登場し、弔って欲しい人がいると言って猿沢池に案内する。そして池に身を投げて亡くなった采女の故事を語り、自分こそその采女の幽霊だと言って姿を消す。
やがて僧の弔いによって現れた采女の幽霊(後シテ)は、帝の寵愛を受けていたかつての日々を思い出しつつ舞を舞い、再び波の底へと消えて行く。演出面でも後シテ登場時に池中から姿を現した事を視覚的に強調する為に熨斗目(のしめ)という装束を被(かず)いて登場するほか、水に濡れた体裁で舞を舞うため様々な箇所で型が変わる。
近現代の能
江戸時代に式楽として庇護を受けていた能は、明治維新によって庇護者を失うと、他の多くの伝統芸能同様、苦境に立たされる。廃業する能楽師や断絶した流派も多く現れた。
- そのような中で、実力で生き延びていかなければならないという時代的背景のもと、厳しい稽古を積んで高い芸位に達した「明治の三名人(梅若実・宝生九郎・櫻間伴馬)」と呼ばれる能楽師たちが登場し、能の芸質という意味ではむしろ高まった。
- その次の世代の「昭和の名人」の時代を含め、幅広い観客層や素人弟子の愛好者の増加など、ある意味では能の黄金期であったとも言える。
二十世紀初頭になると、能はヨーロッパにも紹介され、西欧の演劇人たちの関心をひくようになる。
- アイルランドの詩人・劇作家のW.B.イェイツは能に影響を受け、舞踊詩劇「鷹の井戸」を作った。また、これをもとに作られた新作能が〈鷹姫〉(横道萬里雄作、観世寿夫作曲・作舞)で、昭和42年に銕仙会定期公演にて初演、その後、銕仙会を中心に度々上演されていくことになる。
- クラッシック音楽界でも、イギリスのベンジャミン・ブリテンは能の「隅田川」に触発されオペラ「カーリュー・リバー」を作曲した。
- 近年(平成13年5月)「能楽」は、ユネスコの第1回「人類の口承及び無形遺産の傑作に関する宣言」として宣言された。
- 戦後になると、進歩的な思潮の中で、観世銕之丞家の嫡子であった 観世寿夫がフランスの演劇理論も学び、横道萬里雄・表章ら研究者達の研究成果を元に世阿弥の演劇論に立った能の再解釈・演劇的な見直しをおこない、能はシテだけで舞うのではなく地謡や三役も含めた役者全員による総合芸術であるとの見地から地謡にも力を入れ、確固たる伝統の技に裏打ちされた説得力のある舞台を見せた。
こうしてひとつのドラマとして能の演目をとらえる潮流が生まれ、現在の能楽界につながっていく。
ウィリアム・B・イエイツ「鷹の井戸(At the Hawk's Well 1917年)」
ケルトの若き英雄クーフリンが永遠の生命を求めて井戸にたどりつき、そこで水を求めたところ、井戸のかたわらにいた老人がこの水は涸れていて、これまでもたった三度しか水は湧いたことがないと言う。
二人が問答をしていると、井戸を守るとみえていた女がはげしい鷹の声をあげ、打ち震えはじめる。老人はこれは水が湧く前兆だと言っているとまもなく、女は黒い衣裳を払って立ち上がり、鷹となって移り舞を始める。
クーフリンはその鷹を追い、老人は眠りこむ。舞のテンポがはやくなり、それもやがて歌い収められると、あたりはまったく元のままで、いったいクーフリンはそこに来たのかどうか、女は鷹になったのかどうか、何もわからない。すべてはひょっとして老人が見た一場の夢だったかもしれないという物語である。
絶海の孤島、榛の木立に囲まれた泉に湧くという不思議な水、飲めば永遠の命を得るという。その泉の周りには物言う岩が転がっており、泉の上の榛の木には美しい鷹姫がとまっている。
くる日もくる日も泉の水を求めて、水が湧くのを待ち続ける老人。泉はいつもは枯れていて、不思議な「魔の時間」にだけ湧きいずる。ところが「魔の時間」に立ち合っても意識を失ってしまって、気が付いた時には再び枯れてしまっているという有様。それでも老人は何とか生き長らえつつ、泉の水を待ち続けていた。
そこに現れた若者クーフリン。彼は海の彼方の王国の第三王子。夜の宴に泉の噂を聞いて、帆船を出して遥々やってきた。
クーフリンは老人に、泉はどこだと迫る。才気溢れる若者に、老人は諦めろと言う。老人が待ち続けた果てしない年月、それでも得られなかった水である。その折しも鷹姫が羽ばたき何事かの予兆が起こる。見つめ合う鷹姫とクーフリン、魅入られるな、魅入られると二度と島を出られないと老人は忠告する。若者への嫉妬の言葉を残して老人は死んでゆく。老人もかつてクーフリンのようにこの島にやってきた若者だった。岩達は彼らを哀れみつつ冷ややかに見ているのみ。
鷹姫は舞い、クーフリンは意識を失う。その間に水は湧き、鷹姫が水をすべてを汲み、飲み尽くすとクーフリンは目を覚ます。クーフリンは鷹姫を追うがかなわず、枯れた泉のみが残された。死んだ老人は幽鬼となって彷徨い、泉の水を求めても得られない人間の苦悩を嘆き謡いやがて岩の一つとなる。
最近では「シン・ゴジラ」でゴジラのモーション・アクターを狂言師の野村萬斎が演じて話題となりました。まぁ能の演目に「猩猩」もあるし?
全体的に見てこういう歴史観が浮上してきます。
- 「解脱者を除き死者の魂は輪廻転生する」とする仏教は元来葬式とは無関係。実は「死とは魂魄の分離であり、魂は天に、魄は大地に飛散する」とする儒教もそうなのだが、それを素直に認めてしまうと祖霊を祀る伝統的儀礼が営めなくなってしまうので「祭事に際しては名をもって魂魄を一時的に呼び集められる」とした。これが位牌の起源となる。
第五講 仏教と儒教-3
第五講 仏教と儒教-4
位牌 - Wikipedia
- 鎌倉時代に入ると律宗や新仏教が民衆の中に入り込む為に葬式を営む様になる。神仏習合に立脚する既存寺社も信徒懐柔策としてこのトレンドを受容せざるを得なくなっていくが、あくまで「仏教」の側面で受ける事とし、儒教の礼儀作法を参考に葬礼が整えられていく。
- 藤原氏と縁深い「神仏習合に立脚する既存寺社」の代表格たる春日神社/興福寺の大和猿楽が室町時代、その幽冥性の強い演目によって(比叡山延暦寺に後援された)近江猿楽を圧倒していったのは、こうした時代精神を背景としている。戦国時代に入るとそれは神仏習合や鎌倉新仏教をも視野に入れた風流能へと進化を遂げる。おそらく政治勢力としての仏教教団の衰退と無関係ではない。
- こうした動きはおそらく、仏教からの神道の独立を画策する神本仏迹派によって許し難い展開だった。まずは本居宣長の弟子だった服部中庸(1757年〜1824年)が古事記の天地開闢を独自解釈し「太陽神たる天照大御神が司る天(あめ)・天津族末裔たる天皇の司る地(つち)・月神たる月読命が司る泉(よみ)」の三界に分裂する過程を十図に分けて図示した「三大考」を執筆。これが寛政8年(1796年)「古事記伝」巻十七に附載されると国学者の間で大論争となった。文化9年(1812年)に平田篤胤が発表した「霊能真柱」はそこでの論考をさらに発展させ「黄泉を治める須佐之男命と月読命は同神である」「生者の魂は全て地上の支配者たる天皇に服属し、死者の魂の大半は(地上にぴったりと重なって存在する)幽冥界の支配者たる大国主に服属する。そして大国主に追放されたごく少数の荒魂だけが黄泉の国へと向かう」「死者の魂の拠り所は墓であり、祭礼を欠かすと子孫に仇なす荒魂に変貌してしまう」とし、大衆人気を獲得した。
平田篤胤「霊能真柱」における霊魂観
*以降は幽冥界の実証に関心が推移。文政3年(1820年)秋の末で、平田篤胤45歳の頃、江戸で天狗小僧寅吉の出現が話題となる。この噂の発端は江戸の豪商で随筆家でもある山崎美成のもとに寅吉が寄食した事にある。寅吉は神仙界を訪れ、そこの住人たちから呪術の修行を受けて、帰ってきたという。篤胤はかねてから異界・幽冥の世界に傾倒していたため、山崎の家を訪問し、この天狗少年を篤胤は養子として迎え入れ、文政12年まで足掛け9年間世話をしている。篤胤は、この「天狗小僧」から聞き出した異界・幽冥の世界の有様をまとめ文政5年(1822年)に『仙境異聞』を出版。少年を利用して自分の都合のいいように証言させているに違いないと批判されたが篤胤本人はあくまで真剣で、寅吉が神仙界に戻ると言ったときには、神仙界の者に宛てて教えを乞う書簡を持たせたりもしている。続いて「勝五郎再生記聞」「幽郷眞語」「古今妖魅考」「稲生物怪録」など一連の奇譚について考察。49歳から54歳までの数年間、支那や印度の古記文献や、異国に於ける仙人や神の存在について研究したが、この時期には道蔵などの道教経典を精読し「葛仙翁伝」「扶桑国考」「黄帝傳記」「赤縣太古傳」「三神山餘考」「天柱五嶽餘論」といった道学的文献に傾倒している。彼にとって学問の本質はあくまで「死後の不安を除去する事」だったのであり、その立場に殉じたともいえよう。
*平田篤胤の説いた幽冥観(死後の魂の行方)には、祖霊や産土の神をめぐる伝統的な共同体における宗教的観念への接近という側面があり、それが大衆人気獲得の主要因となった。またそれは明治維新後に柳田国男らによって説かれる民俗学上の祖先観に先行するものでもあった。
そして最終的に戦後、日本の出雲神道はこういう境地に到達します。
日本の古い葬儀の様式は神話の世界に登場し、古事記の中の天若日子の葬儀のくだりに見られます。神葬祭の源流がここにあると言えるでしょう。
そして、仏教伝来以降、急速に仏式での葬儀が普及しました。さらに江戸時代になると、キリシタン対策のための寺請制度(てらうけせいど=人々は必ずどこかの寺に所属しなければならないという制度)により仏式の葬儀が強制されました。しかし、江戸時代の中後期になると、国学の興隆によって国学者たちが日本古来の精神・文化に立ち返ろうと訴える中で、神葬祭の研究も行なわれるようになり、日本古来の信仰に基づいた葬儀を求める運動(神葬祭運動)がおこりました。その結果、幕府は限定的に神葬祭を行なうことを許可しました。
*幕府は天明五年(1785年)吉田家から許可状のある神道者とその嗣子のみに神葬祭を行うことを許可。
明治時代になると、政府の神祇政策の一環として神葬祭が奨励され、例えば、神葬祭専用墓地として青山霊園が設立されました。地域によっては神仏分離や廃仏毀釈に伴い、地域ごと神葬祭に変更したところもあります。葬儀は宗教行為とされる一方、公務員に相当する神主は宗教活動である神葬祭を行なうことを禁止され、神葬祭の普及は停滞しました。
*明治政府の対応はかなり錯綜している。1873年7月18日には火葬が仏教の習俗であるとして禁止されたが、1875年5月23日には解禁。明治22年(1889年)2月11日に公布された大日本帝国憲法では制限付ながら信教の自由が保障された反面、神社神道は宗教ではないとされ、公務員に相当する神職は宗教活動に該当する神葬祭を行うことを禁止された(例外的に府県社以下神社の神職や、宗教活動を認められた教派神道はこれを許された)。戦後、神道は神社本庁として宗教法人としての立場を取り戻し、葬儀に関わることが出来る様になる。
この時代に生きた出雲大社大宮司、第八十代出雲国造(いずもこくそう)千家尊福公(せんげたかとみ)は、記紀などに記された、天孫降臨に先立つ国譲りの時に結ばれた「幽顕分任の神勅」(ゆうけんぶんにんのしんちょく)によって「顕世の“この世”は天照大御神の皇孫がお治めなされること、幽世の“あの世”は大国主大神が主宰なさること」この幽顕二道を明らかに建てることが、世の人々を救いに導く安心立命の道だとして、大宮司を辞任し、教導職として神葬祭の普及に務められ、明治天皇の内親王殿下のご葬儀を執り行うなど、そのご事績は出雲大社の教えの基礎でもあります。
*神道においては「人はみな神の子であり、神のはからいによって母の胎内に宿り、この世に生まれ、この世での役割を終えると神々の住まう世界へ帰り、子孫たちを見守る」ものと考える。よって、神葬祭は故人に家の守護神となっていただくための儀式である。また、神道において死とは穢れであるため、神の鎮まる聖域である神社で葬祭を行うことはほとんど無く、故人の自宅か、または別の斎場にて行う。
これ自体は小泉八雲が世界中に広めた「Exotic Japan」の概念とかなり重なるのですが、その分だけ「幽玄能」とのギャップはかえって増したとも。
というか、そもそも死霊の成仏を前提に描く「幽玄能」と、神と仏と霊と人間の共存を日常的風景として描く「風流能」の間にもギャップが存在すると考えるべきなのでしょう。そしてそれについて語るなら、この人についても触れざるを得なくなります。
浄土宗大本山増上寺36世法主で、江戸時代を代表する呪術師。字は愚心。号は明蓮社顕誉。密教僧でなかったにもかかわらず、強力な怨霊に襲われていた者達を救済、その怨霊までも念仏の力で成仏させたという。
- 陸奥国(後の磐城国)磐城郡新妻村に生まれ、12歳で増上寺の檀通上人に弟子入りしたが、暗愚のため経文が覚えられず破門され、それを恥じて成田山新勝寺に参篭。不動尊から剣を喉に刺し込まれる夢を見て智慧を授かり、以後力量を発揮。
- 5代将軍徳川綱吉、その生母桂昌院、徳川家宣の帰依を受け、幕命により下総国大巌寺・同国弘経寺・江戸伝通院の住持を歴任し、正徳元年(1711年)増上寺36世法主となり、大僧正に任じられた。晩年は江戸目黒の地に草庵(現在の祐天寺)を結んで隠居し、その地で没した。
- 享保3年(1718年)82歳で入寂するまで、多くの霊験を残した。特に奇端で名高いのは、下総国飯沼の弘経寺に居た時、羽生村(現在の茨城県常総市水海道羽生町)の累という女の怨霊を成仏させた累ヶ淵の説話である。この説話をもとに多くの作品が創作されており、曲亭馬琴の読本『新累解脱物語』や、三遊亭円朝の怪談『真景累ヶ淵』などが有名である。
その間、明応7年(1498年)の大地震によって堂宇が損壊し、それ以来、露坐となり荒廃が進んだ鎌倉大仏を、浅草の商人野島新左衛門(泰祐)の喜捨を得て、養国とともに復興を図る。そして鎌倉大仏の鋳掛修復に着手し「清浄泉寺高徳院」と称する念仏専修の寺院の再興に成功し、当時、浄土宗関東十八檀林の筆頭であった光明寺(鎌倉市)の「奥之院」に位置づけた。
そして新たにこういう図式が浮かび上がってくる訳です。
- 実は足利義満や豊臣秀吉の様な絶対君主が能を好んだのは「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマを、その頂点に位置する者として経験する羽目に陥ったからともいわれている。太陽王ルイ14世や藤原道長の様に「完全なる自由を謳歌する(あるいはそう見せ掛ける事に成功する)」タイプは思うより少ない。残りはむしろ「全ての背後に自力ではどうしようもない因果律を見て取る」のを好んだ。その典型例の一人がスターリンで、やはり同様に能を好み、セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の「イワン雷帝(Иван Грозный、1944年〜1946年)」において「人形振り」演出を施されたイヴァン雷帝と自分を重ねていたという。
- その一方で江戸時代の庶民は「(祐天上人の事跡に基づく)累物」や(平安時代の陰陽師)阿倍晴明の活躍を、源義経物や楠木正成物同様に好んだ(それまで脈絡のない断片的冒険譚しか存在しなかったが、次第に全生涯を通して描く長編が編纂されていった)。そしてさらに少女向けミュージカルや白波物の様なアンチヒーローも登場し、娯楽内容は多様化の一途を辿る。
*そういう状況下「体制側から優遇される格上の能楽界」「庶民から支持されながら能楽界への憧憬心を捨て切れない格下の歌舞伎界」という二重構造が江戸時代末期まで続く事に。
出島を訪れたオランダ人が「日本は絶対君主でなく、法による専制国家である」と書き残したのはこういう時代の事。細部はともかく、それが日本の前近代的身分制の到達点だった事実もまた揺るがないのです。
それではこうした文化史の何処がアイルランド文化史と重なるのか?