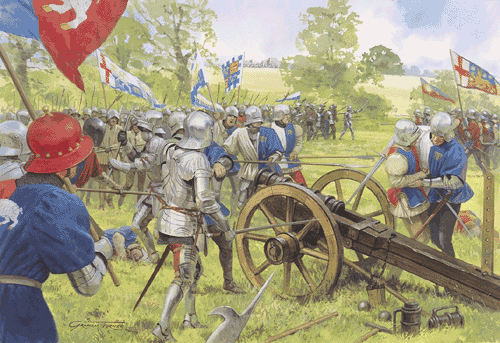近代国家出現は概ね百年戦争(1337年/1339年〜1453年)をフランス側が「リッシモン大元帥のブルターニュ軍編成」によって制したのが起源とされています。
*その百年戦争は概ね「十字軍/大開拓時代(11世紀〜13世紀)の終焉、すなわち「欧州のフロンティア消滅宣言」が必然的にもたらした英仏双方における国境制定要求の高まり」に起因すると考えられている。

- 「いやそうではない。ジャンヌ・ダルクこそフランス・ナショナリズムの起源だったのでは?」という問い掛けから始まる歴史の闇が実在する。
-
また「それを始めたのが(アンジュー帝国時代以降、ブリテン島とフランス本土で共有されてきたケルト文化を継承する)ブルターニュ公だった」事実も同様の闇を窺わせる。「フランス・ナショナリズムの中核にあったのは、本当にその起源とされるパリ辺境伯(西フランク王国の王統を併合したフランス王室の再源流)や、ノルマンディー公国や北フランス諸侯だったのか?」という質問を誘発するからである。
アルテュール3世 (ブルターニュ公) - Wikipedia - 「17世紀後半にフランス宮廷料理樹立を主導した料理人達の多くが(ブルグント王国故地たる)ブルゴーニュ出身だった事実」もまた、こういう意味で歴史の闇に属する。フランスにおける絶対王政樹立過程とは、実は「王権の超越性が証明されていく歴史」どころか「国王が北フランスの貴族大連合に対抗すべく「秘密裏に」さらに外部の勢力を味方につけていった歴史」だったのではあるまいか?
とりあえず根底にあるのは「(大量の火器を保有する)常備軍の維持」が戦争勝利の鍵を握る様になり、それを養う国庫を維持する為に官僚組織が発達し、貴族が軍事力供給階層から将校と官僚の供給階層に変貌して近世が到来したという考え方。実際の中央集権化は英国においては薔薇戦争(1455年〜1485年/1487年)、フランスにおいては公益同盟戦争(1465年~1483年)を通じて果たされたとするのが通説。
そして、まさにここにおいて「かくして必然的に絶対王政の時代が到来し、太陽王ルイ14世が主権者とて降誕。フランス革命によってその座を国民に譲渡した」とするフランス式歴史観と「ジェントリー階層の「王室の藩屏」としての躍進が議会制民主主義成立につながった」とする英国式歴史観の分裂が見られるのです。
フランス国王ルイ14世(在位1643年〜 1715年)
初代英国首相ロバート・ウォルポール(在位1721年〜1742年)
果たして正しいのはどっちなのでしょうか?
この戦いの鍵を握るのが握るのが一人の英国人法律家だったりします。
ジョン・フォーテスキュー(Sir John Fortescue、1394年〜1480年)
イギリスの法学者、政治家。古き国制の思想を背景に、自然法についての思索を深め、イギリスの立憲政体の基礎となるコモン・ロー、法の支配の発展に大きく寄与したとされている。「一人の人間を誤って死罪にするよりも、20人の犯罪人が死罪を免れるほうがましである」との言葉が有名。
フォーテスキューの代表作『自然法論』『イングランド法の礼賛について』『イングランドの統治』の3冊は,いずれもイングランドが内戦に陥ってから書かれたもの。
- 66歳ないし76歳というかなりの高齢になってから書かれたもので、最高の地位を得ていた法律家が抱いた,内戦によって引き起こされた法的秩序の崩壊に対する危機感の表れとされる。
- 3冊のうち最初に執筆された『自然法論』は,ランカスタ朝の王位継承が正統であることを示すために書かれたものである。とはいえ,それを具体的に論じたのは第二部であり,第一部はそれの基礎となる一般的な法的・哲学的理論を,多くの哲学者や法学者を援用しつつ論じている。秩序の瓦解を前にして「政治的権威の正統性と固有の機能にとって試金石になる正義への関心によって支配されていた」ので,まずはその概念がもつ根源的な意味と理念的な構造を確定する必要があったためだろう。
- フォーテスキューの政治理論の核心である,有名な「王的・政治的支配(dominium regale et politicum)」という概念が定式化されたのも,そこにおいてである。その理論は,イングランドの法や統治形態を論じた『イングランド法の礼賛について』と『イングランドの統治』にも継承され,それらの土台をなしている。
Wikipediaに詳細解説はありませんが、その生涯についてもかなりの部分まで明らかになっていたりします。
JAIRO | 国民国家の始原 : ジョン・フォーテスキューの政治理論についての一考察
S・B・クライムズは,彼が校訂・編集・翻訳して1942年に刊行したフォーテスキュー著『イングランド法の礼賛について』のなかで,それまでの研究成果や新しい資料を踏まえて,その作品の詳細な来歴や歴史的意義についての考察とともに,フォーテスキューの経歴をこう論じている。
- フォーテスキューが生きた時代は,中世末期のランカスタ王朝の時期とおおよそ符号する。フランスとの百年戦争が続くなか,1399年にヘンリ4世が興したランカスタ王朝は,1423年に即位したヘンリ5世の時代に,内乱の危機を抑え込み,対仏戦争で勝利してトロワの条約を結ぶことで,発展を遂げた。この時代は,フォーテスキューが青年期から壮年期にかけて法律家として活躍した時期にあたる。
- クライムズによればフォーテスキューの誕生年は1385年ないし1395年であり,正確なことは不明である。リンカンズ・インに学び,1430年以前に4回それの幹事になっている。1418年から17の州や市で35回治安判事として仕事をし,70回以上の巡回裁判を行っている。1421年から8回議会代表になり,それ以外に議会への助言や嘆願を何度か行い,評議会にも出席している。1430年に上級法廷弁護士,1441年に勅選上級法廷弁護士,1442年に王座裁判所主席裁判官になり,その翌年,騎士に叙任された。
- ヘンリ5世の成功した統治が9年で終わった後,1422年に王位を継いだのは1歳にも満たない幼王ヘンリ6世であった。1437年に親政を始めたが,能力を欠いた彼の治世は無秩序を醸成する。対仏戦争の敗戦とフランスにおける領土の喪失,巨額の負債,王の愛顧を受けたサフォーク伯の不正などにより,1450年までに広範な政治的危機が生じ,中央では評議会が分裂し,地方でも暴力と腐敗が蔓延するようになった。1450年5月に起こったジャック・ケイドの蜂起はこうした状況を反映したものであり,彼が3万人を率いて批判した矛先は,主に王を取り巻いて私産を増やす宮廷派に向けられていた。
- 1453年にイングランドはカレーを残してフランスから撤退し百年戦争は終結。その翌年,バラ戦争が始まり,ランカスタ王家側とヨーク公側の間で内乱状態になった。1460年に捕えられた王に代わって軍の指揮をとっていたマーガレット王妃は,王の奪回に成功するが,ロンドンに入ることはできなかった。1461年に王妃軍はタウトンの戦いでヨーク派の軍に敗れた。フォーテスキューはこの戦いで王妃軍に参加し,その後,王・王妃・王子とともにスコットランドへと逃れる。
- ロンドンに入城したヨーク派の辺境伯エドワードが1461年に戴冠し,エドワード4世になると,ヘンリ6世とその周りの人々には私権剥奪法が適用され,フォーテスキューもその対象になって王座裁判所主席裁判官の地位を失った。スコットランドにいる間,フォーテスキューはランカスタ派の王位継承の正当性を説く諸論文を執筆した。『自然法論』はこの時期に執筆されたと推測されている。
- 1463年にフォーテスキューは王妃とともにフランスに渡り,貧困のなかで7年間の逃亡生活を送った。『イングランド法の礼賛について』はこの期間に書かれたものと言われている。そしてヘンリ6世の復位のために,ルイ11世にイングランドへの進軍を促す『ルイ11世のための覚書』を書いている。
- ヘンリ6世妃マーガレットは,ルイ11世の仲介により,長年ヨーク派の中心人物であり,1469年に王と袂を分かったウォリック伯と1470年に和解した。そしてウォリック伯軍はプリマスに上陸し,捕らわれていたヘンリ6世を再び王位に就かせた。
- しかし,大陸に逃れていたエドワードが半年後の1471年に戦力を整えて巻き返し,ロンドンに戻って復位する。ヘンリ6世は逮捕され,バーネットの戦いに敗れたウォリック伯は殺された。この頃ウェーマスに上陸したマーガレットも5月にテュークスベリの戦いに敗れ,王子は殺され,ヘンリ6世も処刑された。マーガレットが上陸したとき,フォーテスキューも同行しており,彼は戦いの後に捕えられている。
- その後,『スコットランドから送られたいくつかの著作に関する宣言書』を書き,それまでに行ったランカスタ派の継承を正当化する主張を取り下げている。そしてエドワード4世の評議会構成員になり,テュークスベリの戦いの後に執筆したと思わる『イングランドの統治──別名,絶対君主政と制限君主政の差異』をエドワード4世に捧げた。フォーテスキューが亡くなったのは1479年である。
イングランドの政治体を「王的・政治的支配」と特徴づけ,フランスの「王的支配」と明確に区別したフォーテスキューの政治理論は,彼の生きた時代にはほとんど影響力をもたなかったものの,過去500年以上に渡り広く引用され続けてきた。
- テューダー絶対王政期の政治思想を形成し,16世紀から国王と議会の間で権力の分割が進んで潜在的な対立関係が形成されるようになると,それは国王側と議会側の双方の側で,自らの主張を正当化するために引用されるようになった。
- 市民革命期に入ると,「議会主権」というイングランド憲法の本性を開示した立憲思想の権威としての評価が定着し,17世紀と18世紀においてホイッグ・アカデミーの立脚点としての地位を保持。
- 第二次世界大戦前におけるイギリス政治思想史研究の泰斗チャールズ・ホワード・マクルウェインは「17世紀の偉大なる闘争において,ブラクトンの次に引用された中世の思想家はフォーテスキューであり……君主大権の支持者も反対者も彼を立憲的教義のチャンピオンとみなしていた」と述べている。
- また自由概念の起源を探求したエリス・サンドズは,「アングロ-アメリカの自由と憲法は本質的に,15世紀にフォーテスキューによって提案されたランカスタ憲法との連続性に依拠している」として,フォーテスキューが立憲思想の発展において果たした役割を至上のものと評価している。その地位は少なくとも1832年の議会改革によって民主的な近代議会が定着するまで保持されたと思われる。
その後,フォーテスキューは理論家というよりは15世紀の「出来事と制度の直接的な記録者で注釈者」とみなされるようになり,その時代の法と政治についての詳細が明らかになるにつれ,単なる誤った記録者とされて彼への言及も減っていった。
今日なお、なかなか英国人自身がそれを認める記述に出会いないのでいるのですが、様々な偶然が重なって「テュークスベリの戦い(1471年5月)」が「ヨーク派のランカスター派に対する大砲殲滅戦」となってしまった事が英国史に与えた衝撃の大きさを感じます。
テュークスベリーの戦い(Battle of Tewkesbury、1471年5月4日) - Wikipedia
グロスターシャーのテュークスベリーで行なわれた戦い。
- この戦いで、薔薇戦争は大きな節目を迎える。ランカスター派の「イングランドの王位奪還」という悲願に一時的な終末をもたらしたからである。
- そして次のヘンリー・テューダーの王朝誕生という政治クーデターの形でヨーク家・ランカスター家の紛争に決着がつくまで、14年間の平和が訪れる。
この戦闘の時点で、精神的に不安定なランカスター家の王ヘンリー6世は、彼のライバルで戦闘では無敗を誇るヨーク家のエドワード4世によって、2回目の退位をさせられたところであった。
- 即位・退位を繰り返すこの状況の変化は「キングメーカー」と称されるウォリック伯の干渉によるものだった。彼はまずエドワード4世を支援し、後にヘンリー6世を支援した。だが、そのウォリック伯も既に亡く(この3週間前のバーネットの戦いで殺されている)、残ったランカスター派の軍隊は、ヘンリー6世の王妃マーガレットとその息子で17歳になる王太子エドワードによって指揮されていた。
- もしマーガレットがウォリック伯の敗戦の時にイングランドに戻って来ていて、彼女と同盟を結んでいたベッドフォード公ジャスパー・テューダー(ヘンリー・テューダーの叔父)と組んでバーネットの戦いに参陣していたら、エドワード4世のヨーク派軍に対抗できる可能性も残っていただろう。
- 彼女の唯一の希望はグロスターでセヴァーン川を渡ることであったが、これはグロスターの町と城を治めるヨーク派のリチャード・ボーシャン卿(Sir Richard Beauchamp)に拒否されて失敗してしまう。
- マーガレットは残っている指揮官の中でも経験豊かなサマセット公に大きく依存したが、彼の能力は王朝を支えられるほどのものではなかった。ヨーク派は大砲で優勢だったのだが、サマセット公はそこを読み違え、王弟グロスター公リチャード(後の国王リチャード3世)がサマセット公の側面を充分攻撃できる位置に布陣してしまったのである。
かくて英国は、近世到来を告げる残酷な軍事局面の経験国の一つとなる。
- チェコ人傭兵ヤン・ジシュカが考案した手砲(Hand Cannon)と装甲馬車(Tabor、Wagenburg)を組み合わせた戦によって騎士の突撃戦術が完膚なきまでに打ち破られたフス戦争(1419年〜1439年)。
- イタリア内戦に関連してスペイン軍のランツクネヒト鉄砲隊がフランス騎兵隊とスイス槍歩兵の密集突撃を粉砕した「チェリニョーラの戦い(Battle of Cerignola、1503年)」
- オスマン帝国のイェニチェリ大砲隊がサファヴィー朝イランのクズルバシュ(サファヴィー教団に深く帰依するトルコ系部族長に指揮される騎馬軍団)を消滅させた「チャルディラーンの戦い(Battle of Chaldiran、Chaldoran あるいはÇaldıran、1514年)」
- ムガル朝始祖バーブルが鉄砲や大砲の連続射撃によって北インドの覇者ローディー朝の大軍の大半を殺戮した「第一次パーニーパットの戦い(The First Battle of Panipat、1526年)」
- 織田信長の搔き集めた鉄砲隊が武田軍を包囲殲滅した「長篠の戦い(1575年)」
たまたまヨーク朝側砲兵隊を指揮していたのが王弟グロスター公リチャード(後の国王リチャード3世)だったのも暗示的であった。
- 後退するランカスター派の中でパニックが起こり、サマセット公は事態を収拾するために、戦闘の主導権を握れなかった罰を理由に、彼の部将であるウェンロック卿(Sir John Wenlock)を処刑したと言われている。しかし一部には、ウェンロック卿はこの日生き残って逃げ延びたという説もある。ウォリック伯がランカスター派につくまで、ウェンロック卿はずっとヨーク派だったからというのがその根拠である。
- 「血まみれの牧草地("Bloody Meadow")」として知られている野原で、恐らくサマセット公の軍隊の半分ぐらいが虐殺された。一部が近くのテュークスベリー修道院に逃げ込んだが、そこにも敵の追っ手が差し向けられたと言われる。死傷者の1人はエドワード王太子だった(戦闘中の死亡であるか戦闘後の死亡であるかは明らかではない)。エドワードは今日に至るまで、イングランド史上「戦死した唯一の王太子」であり続けている。
- マーガレット王妃と義理の娘アン・ネヴィルは「最も高貴な捕虜」とされ、残ったサマセット公を含む全ての戦闘指揮官はその後間もなく手短に処刑された。
ヘンリー6世は既にロンドン塔に収監されており、数日後にそこで殺されている。
この戦いによってランカスター派中枢が蒸発してしまったからこそ、傍系のチューダー家に大躍進の目が回ってきた訳です。かくしてテューダー朝(Tudor dynasty、1485年〜1603年)開闢となる次第。
その後も「ヨーク派」と「ランカスター派」の戦いは現代まで続きます。
それでは、ここに挙げたフォーテスキューなる人物、英国史にどんな足跡を残したんでしょうか?
JAIRO | 国民国家の始原 : ジョン・フォーテスキューの政治理論についての一考察
フォーテスキューの支配論においては、王的支配の中心にあるのは武人の暴力に起源をもつ王的権力であり,その機能的な核となっているのが秩序構成権力であるとされる。
その一方でこれに対抗する政治的支配の中心にあるのが人民という集合体に起源をもつ政治的権力であり,その機能的な核となっているのが正義構成権力であるとする。
王的支配には正義構成権力も含まれ、さらには王的支配と王的・政治的支配は権力でも機能でも対等であるが,あえて王的支配よりも王的・政治的支配を推奨したのであった。
王的権力と政治的権力という権力論の見地からそれを考察する場合,それは確かに抑制均衡論になっている。王が欲望にまかせて暴君になる可能性を肯定しつつ,それを抑える政治的権力の役割を明示した点は確かに後世の制限君主政論や立憲君主政論の先例となったのである。しかしここでいう2つの権力が別個のものであることは,秩序構成権力と正義構成権力という機能的な権力観にまで遡ってはじめて理解可能となる。
フォーテスキューはそのことを明確に自覚していた。それは,王がもつ秩序構成権力は神や善とは無関係に,むしろそこからすれば悪である暴力に起源をもち,人間が社会を形成する限りつねに存在し続けるのに対し,人民という集合体に起源をもつ正義構成権力は,そうした秩序構成権力を統制し抑止する作用をするが,それができずに秩序構成権力をもつ王の自由意志に委ねられる場合があると論じたことに,もっとも明白に表れている。
カール・シュミットの用語を使えば,国内で反乱や内戦が起こったとき,外国の侵略を受けたときといった,いわば「例外状態」においては,政治的権力によって法を制定する時間的余裕がないうえに,軍事的事態という性格から言っても,支配者に決定を任せ「決断」を待つしかない。そのような場合である。「政治的に支配している王は,彼の王国の主たる成員の同意なしに彼の法を変えることはできないが,しかし法が欠落している場合は法の代わりをすることができる」というフォーテスキューの言は,まさにそうした2つの権力の関係を示している。
このような秩序構成権力と正義構成権力の2つの権力観から見れば,王的権力と政治的権力の2項対立はイングランド法学を超え出て,ソクラテスとソフィストの論争に始まる西洋政治思想の伝統に根差すものと理解することができる。古代ギリシア以来の多くの哲学者を立論の論拠としてあげていることからすれば,フォーテスキュー自身がそれを強く意識していたと思われる。この視点に立って西洋政治思想史を概観するならば,正義構成権力観はソクラテスの後,プラトン,アリストテレス,ストア学派,キケロなどに受け継がれ,一方,ソフィストが唱えた秩序構成権力観は,古代末期のキリスト教思想家アウグスティヌスのなかで再生し,中世の教会法学のなかで命脈を保ったと言える。その双方の思考の基盤となっていたのが自然法的な思想であった。
12世紀ルネサンスの後,2つの権力観があることを示したのがトマス・アクィナスであった。しかし,彼はそこにとどまり,2つを対峙させたり,合成したりすることはなかった。それをしたのがフォーテスキューであった。この合成が王的・政治的支配という理論である。この理論の歴史的意義は,イングランドのその後の歴史的展開のなかで明らかになる。
イングランドでは,このような秩序構成権力としての王的権力は,フォーテスキューの死後10年も経たずに戴冠したヘンリ7世に始まる絶対王政のもとで強化されることになるが,具体的には王の下での行政組織の拡大と支配の一元化となって現れた。行政組織の拡大は重商主義経済とともにすでに15世紀から始まっていたが,16世紀はそれが飛躍的に進んだ世紀であった。それを促進したのは国内外の戦争と資本主義経済の発展であった。
こうした事情は大陸でも同じである。都市間の戦争が激しかったイタリアのフィレンチェで外交官も務めた思想家マキアヴェリは,1510年代に執筆された『君主論』のなかで,独自の起源をもつ権力に依拠した政治という営みを明らかにするなかで,そのような支配者の権力装置を「国家 stato」と呼び,その後,権力機構と認識される行政組織は「国家」と呼ばれることになる。1532年に『君主論』が刊行されてから半世紀近く経った1576年,ユグノー戦争の真只中でフランスの政治的統一を求めるジャン・ボダンは『国家論』を刊行し,国家の「絶対的かつ恒久的な権力」である主権を説いた。主権という概念の意義は,王的権力において王という人格と結びついていた秩序構成権力を王から切り離し,国家という権力機構に帰属させたことにある。20世紀になってフリードリッヒ・マイネッケが説いた「国家理性」も,このような権力論的国家観の延長にある。
一方,正義構成権力である政治的権力についてはどうか。イングランドでは16世紀の絶対王政期においても,それの起源となった人民という集合体は議会を通じて一定の権力を行使し続けた。その頃のイングランドは国家機構を整備しつつ,内乱の危機を何度も乗り越えながら国家統合を推し進めていた。そしてそれと表裏の関係で,国内の人民のなかに共同体意識が芽生えるようになっていた。
その背景にあったのは,バラ戦争によって多くの貴族の家系が途絶えたこと,資本主義の発展により力をつけたジェントリ階級が,社会の流動化を進めるとともに政治に参加するようになったこと,そして何より宗教改革が招いたローマ教会やカトリック諸国との敵対により,内部の結束をはかる必要があったことである。
このような状況のなか,16世紀後半に「国民 nation」という言葉が今日的な意味で用いられるようになる。それは「人権」や「人民主権」といった近代民主主義の基礎となる言葉が政治的用語として登場する市民革命の前であった。それの早期の例がエリザベス女王の議会演説であったことから分かるように,国民とは権力機構としての国家に対応する権力主体としての集合体であり,政治的権力の起源となる「人民」の発展型である。
以上より,国民国家とは,秩序構成権力が国家という統治機構に集約され,正義構成権力が国民という集合体に担われる政治形態を意味するとすれば,国家と国民が結合した国民国家の原型は16世紀のイングランドに出現し,そしてそれの理論的原型は,フォーテスキューの王的・政治的支配という概念のなかに見い出すことができると言えよう。
しかし,国民国家(nation state)という言葉はイングランドではあまり使われなかった。フランスのように国家と国民を分節化し,国家主権や国民主権といった言葉で政治を論じるのはかなり後のことである。
イングランドでは,15世紀からラテン語res publica の訳語であるコモンウェルス(common-wealth)という語が広まるようになっていた。res publica は古代ギリシアの politeia に由来する語であり,politeia はポリス(polis)の運営を意味した。アリストテレスにおいて,ポリスは単なる都市国家や統治形態という制度的意味を超えて,共通善を実現する政治的共同体の意味をもっており,res publica やコモンウェルスもそのような意味合いを受け継いでいた。この国家と国民を含み込む政治体を示すコモンウェルスという語が使われ続けたことが,国民国家という語が使われなかった理由の一つである。
さらに「議会における国王」という政治理念が16世紀あたりから浸透するようになっていたことも理由の一つである。それはウォルター・バジョットが「諸権力の融合(fusion of powers)」と呼ぶような,執行権と立法権が混ざり合う統治形態のことであり,王の統治権を議会によって一定程度拘束する長い歴史の結果として生じた,イングランドに独特な政治様式である。17世紀に国王と議会が対立するまで,それは文字通り「諸権力の融合」として機能し,フォーテスキューもまたそこに対立関係を見い出す視点をもっていなかった。
多くの論者がそこにフォーテスキューの中世的思考の限界があると指摘するのは,もっともなことである。ただし「議会における国王」という原則はそれ自体に民主的な原理を含み持つので,市民革命の後もその原理を保ちつつ,民主主義を漸次的に実現する基盤になった。
フォーテスキューの理論に基づいて言えば,こうした民主化の進展は,秩序構成権力が国王から国家という統治機構に移行するのに合わせて,正義構成権力が国王から国民へと移っていくプロセスを意味したのだった。
19世紀のスウェーデン国王は、次第に議会に政治的判断権限を奪い取られていきます。
これを先行して経験したのが英国王だったという位置付けで、まぁそれが両国における 「国民主権」概念の樹立過程になったという次第。
もちろん実際にはフォーテスキュー当人が「テュークスベリの戦いという大砲殲滅戦」からいかなる影響を受けたかはあくまで不明。具体的言及など皆無な上、(テューダー朝史観に阿った)シェークスピア史劇の世界に至っては、その圧倒的破壊力はあくまで(英国王権の正統性を脅かす)「フランスの瀆神的な魔女ジャンヌ・ダルク(およびフランス系王妃マーガレット)」や「(瀆神的な存在の代表格たる)リチャード三世」に結びつけてのみ語られる有様なのです。
シェイクスピアが劇作家として成功するきっかけとなったと言われる『ヘンリー六世』三部作および『リチャード三世』(第一・四部作)の中、唯一全作品に登場するのがこの「虎の心」を持った女性、アンジューのマーガレットなのである。ヘンリー六世の后となるいきさつから始まり、その統治の期間、王位継承権をめぐる内乱、いわゆるバラ戦争の勃発からヘンリー六世側の敗北に至るまで、王妃という立場にある彼女の存在が劇中大きな位置を占めるのは当然であろう。
しかし、史実ではヘンリー六世が王権争いに敗れ1471年に殺害された後、1476年に故郷フランスに帰国し1482年に死亡するまで、彼女が再びイングランドの地を踏むことはなかったのだ。ところが、プロットの展開上の必要性がないにもかかわらず、シェイクスピアはこの史実を枉げて第一・四部作を締めくくる『リチャード三世』の中でマーガレットを再登場させる。
『リチャード三世』において、彼女は劇のアクションに全く関わらない部外者である。『ヘンリー六世・第三部』の終わりに追放され、フランスへ送り返されたはずのマーガレットは、いつの間にかイングランドに舞い戻ってきて宮殿に闖入し、王とその世継ぎをはじめとして、その場に居合わせた人物に対して次々と呪いの言葉を投げつける。さらに、劇の終盤近くに再び登場し、悲しみに打ちひしがれる王妃エリザベスとヨーク公爵夫人を前に自分の呪いが半ば成就したことを満足げに語り、フランスへと去っていく。
『リチャード三世』の中でマーガレットはある種の神性を与えられており、『ヘンリー六世』三部作とこの劇を四部作として繋ぐ役割をしている。2 )なぜマーガレットだけがそういった特別な役割を担わされることになったのだろうか。彼女が『ヘンリー六世』三部作全てに登場する唯一の人物であったことは大きな要因であろうが、それだけでは『リチャード三世』における彼女の圧倒的な影響力は説明できない。
「大砲の魔女」ジャンヌ・ダルクと「フランス系英国王妃」マーガレットの同一視
アンジューのマーガレットが最初に登場するのは『ヘンリー六世・第一部』の五幕三場である。彼女の登場に先立ち、この場面ではまず英仏百年戦争でフランス側の救世主として軍を率いてきた乙女ジャンヌ(Joan de Pucelle)の正体が暴かれる。一般に聖女として描かれることの多いジャンヌ・ダルクであるが、シェイクスピアは終始彼女を魔女として描いた。この作品の中では実際に悪霊たちを舞台上に呼び出させ、助けを求めさせている。その直後、フランス軍はヨーク公率いるイングランド軍に敗北し、ジャンヌはヨーク公に捕らえられて退場する。彼らと入れ替わりにサフォーク伯ウィリアム・ド・ラ・ポールに捕らえられたマーガレットが登場する。しばしば指摘されるように、この場面では、『ヘンリー六世・第一部』で圧倒的な存在感を示している乙女ジャンヌの役割をもう一人のフランス女性、アンジューのマーガレットが引き継ぐことが舞台上で視覚的に示唆されていると考えられる。
乙女ジャンヌとマーガレットには、共通する性質が見てとれる。まず、イングランドに敵対するフランスの女性であり、どちらも戦場で自ら軍隊を指揮し敵と戦うことである。フィリス・ラッキンが指摘するように、シェイクスピアはフランス軍を指揮しているのが女性であることを繰り返し強調し、イングランドとフランスの争いを男性的な価値観と女性的な価値観の葛藤として定義している。イングランドの英雄トールボットを姦計により捕らえようとしたオーヴェルニュ伯爵夫人とともに、乙女ジャンヌとマーガレットの三人のフランス女性は、『ヘンリー六世・第一部』においてイングランドのリーダーたちにとっての脅威となる存在である。
さらに、ジャンヌもマーガレットも貞節の美徳からは逸脱した女性である。乙女ジャンヌは、登場するや否や性的なあてこすりの対象となる。皇太子シャルルが熱心にジャンヌに耳を傾ける様子をアランソンは「間違いなく下着の中まであの女の懺悔を聞いているんだろう、そうでなければこんなに話が長引くはずがない」(“Doubtless he shrives this woman to her smock; / Else ne’er could he so long protract his speech.”1Henry 6, 1. 2. 119-120)と揶揄する。その後もシャルルとの性的関係を仄めかす台詞が語られる(1Henry 6, 2. 1. 22-24; 49, etc.)。火刑を宣告されたジャンヌは、自分が妊娠していることを口実に処刑を逃れようとし、シャルル、アランソン、レニエと相手の名前を次々と挙げる。「聖なる乙女」の正体が容赦なく舞台上で曝け出されるのである。
その一方で、マーガレットとサフォークの愛人関係が『ヘンリー六世・第二部』の中心として描かれる。父権制社会を維持するためには、女性の性を管理することが不可欠であり、女性の性的逸脱は制度そのものへの脅威となることは言うまでもない。
こうして、劇中で乙女ジャンヌが行使する力が終息するのと同時にアンジューのマーガレットが登場することで、イングランドの男性的価値観への脅威としての役割が二人の女性の間で象徴的に引き継がれるのだとすると、終幕近くになって現れるマーガレットが体現する脅威というものは、そもそも『ヘンリー六世・第一部』の第一幕ジャンヌの登場から劇中に存在していたと言えるのではないか。
マーガレットを捕虜にしたサフォーク伯は一目で彼女の美しさに心を奪われる。妻帯者である彼は、何とか彼女を自分の傍に置く方法はないものかと考え、ヘンリー王の后にすることを思いつく。うまくいけば自分の恋心も満足させられるかもしれない(“Yet so my fancy may be satisfied”,1Henry 6, 5. 3. 91)、という期待を抱きながら急ぎ帰国をし、すでにアルマニャック伯の息女と婚約をしていたヘンリー王を説き伏せてマーガレットとの結婚に同意させるのである。
こうしてサフォークはうまく事を運び、旅立つのだ
かつて若きパリスがギリシャへと旅立ったように。
あのトロイの王子と同じく恋でも良い結果を得、
しかも、彼よりもっと大きな成功を収めるために。
マーガレットは今に王妃になり、王を支配するだろう
だが俺はあの女も、王も、それに王国も支配してやろう。
(1Henry 6, 5. 5. 103-108)サフォークはここで自分をトロイの王子パリスに擬える。パリスがスパルタの王メネレーアスの妻ヘレンを略奪したことがトロイ戦争の引き金になったことは周知の通りである。サフォークはすでにイングランド王の妻マーガレットとの不義の関係を思い描き、そればかりか彼女を通じて王と王国を自分の支配下に置くという大胆不敵な野心を語っている。しかし、自分とマーガレットをパリスとヘレンに喩えた瞬間に、彼らの未来にはトロイ戦争の陰惨さが影を落とすことになるのである。
*テューダー王朝期(1485年 - 1603年)は宗教革命を背景に貴族の基礎教養がキリスト教神学から古代ギリシャ・ローマ古典に切り替えられた時期に該当。ガリカニスム (Gallicanisme)期のフランス貴族の間でも同様の動きがあってヘレニズム時代のストア派哲学やそれを継承した古代ローマ時代の哲人政治家セネカが理想視される様になり、ベンサムの功利主義やジョン・スチュワート・ミルの古典的十主義哲学につながっていく。*そういえばシェークスピアは「タイタス・アンドロニカス(Titus Andronicus、1590年前後)」「ジュリアス・シーザー(The Tragedy of Julius Caesar、1599年)」「アントニーとクレオパトラ(Antony and Cleopatra、1606年〜1607年頃)」といったローマ史劇も手掛けている。「キリスト教史劇」と併せ20世紀後半のハリウッド史劇の大源流となる。
「女戦士」としてのマーガレット
『ヘンリー六世・第三部』において、マーガレットが最も激しい敵意を向けるのはヨーク公であり、その死後はヨークの息子たちである。これは、ヨークがヘンリー王と皇太子エドワードの地位を脅かす暴挙に出たからであるが、同時に夫ヘンリーの王としての不適格性を彼が露呈させたからでもあるのではないだろうか。
- イングランド王と王妃、その称号だけではなく実体を手に入れることをマーガレットは望み、サフォークはさらに実体となった王妃を通して国を支配する実権を握りたいと思う。彼はすでにグロスターの妻に罠を仕掛けてあることを明かす。「こうして一本ずつ雑草を残らず抜き取ってしまいましょう、そうすれば、あなた自身が幸福な王国の舵を取ることになりましょう。」(“So one by one we’ll weed them all at last, / And you yourself shall steer the happy helm.”2Henry 6, 1. 3. 99-100)――グロスター夫妻は、引き抜くべき最初の雑草である、とサフォークは考える。雑草を根絶やしにすれば、国の舵を取るのは王妃であるマーガレットであり、実質的には自分であるという自信が、“shall”という助動詞からは見え隠れする。王としてのヘンリーの存在は、彼らの思考からは除外されているのである。
- 彼の計画通り、エリナーは館で怪しげな交霊術の会を催しているところを取り押さえられ、裁判の末、三日間公然に晒された上でマン島に追放される。この機に乗じて、グロスターを快く思わない王妃と貴族たちが結託し、グロスターは摂政の職を解かれ、程なく大逆罪の廉で逮捕される。さらに王妃と枢機卿ボーフォート、ヨークらの同意の下、サフォークはグロスター暗殺の計画を実行に移す。
- ここまでは、サフォークは国家の実権を掌握するため計画通り事を進めているようであるが、思いもかけず計画は水泡に帰してしまうことになる。グロスターを慕う平民たちがその死の真相を求めて暴徒化し、ウォリックとソールズベリーが彼らの代弁をする形で舞台に現れるのである。
おそれながら陛下、平民たちはこう伝えてくれと申しています
サフォーク卿を今すぐ死刑にするか
美しいイングランドの領土から追放するかしない限り
彼らは力ずくでも彼を城から引きずり出し
散々苦しめた挙句嬲り殺しにしてやると。
彼らは言っています、
あの男が善良なハンフリー公爵を殺したのだと、
またこうも言っています、
あの男が陛下の死を狙っているのではないかと。
ただ陛下への愛と忠誠の心から…
彼の追放を願って、こうして差し出た真似をしているのです。
(2Henry 6, 3. 2. 243-253)- アナベル・パターソンはグロスター公ハンフリーを「民衆の代弁者」(“the people’s spokesman”)と見做し、ソールズベリーはここで一時的にグロスターの代理を務めているのだという。この抗議の声は道義的に信頼すべきものであり、また、この劇において人々があげる抗議の声にシェイクスピア自身が条件付き――つまり正しい動機から出ており、基本的には王に忠実であり、正しい代弁者に基づいたものであるという条件――で賛同していることを伝えている、と論じる。
- ヘンリー六世はこの民衆の声を聞くと、極めて意外なことに、突如として国王の大権を発動する――「彼に三日間以上この国の空気を穢させはしない、背けば死刑にする」(“He shall not breathe infection in this air / But three days longer, on the pain of death.”2Henry 6, 3. 2. 287-288)。これまでヘンリーは何事につけても側近に判断を任せ、自ら決断をするということを避けていた。そのヘンリーが国王大権を行使するとは、予期せぬことである。最も手強い敵、グロスターさえ片づければ後は思いのままだと考えていたマーガレットとサフォークにとっては、まさに晴天の霹靂である。后の嘆願に耳を貸そうとせず、宣告を繰り返してその場を去るヘンリーに、マーガレットの呪いの言葉が向けられる――「災いと悲しみがつきまとうがいい!満たされない心と辛い苦悩が親しく付き合う友となるがいい!」(“Mischance and sorrow go along with you! / Heart’s discontent and sour affliction / Be playfellows to keep you company!”2Henry 6, 3. 2. 300-302)。これは『リチャード三世』で呪いの女として登場するマーガレットが第一・四部作の中で初めて吐く呪いの台詞である。観客は、劇のクライマックスであるこのシーンで、舞台上でキスと抱擁を交わし百行以上に渡って別れを惜しむこの恋人同士の台詞を耳にする。
- 王妃マーガレットとサフォークの関係は、公然の秘密となっている。身分を隠してイングランドから出国しようとしたサフォークは、出帆直後に巻き込まれた海賊との海戦で捕虜となり、ケント州の海岸に連れ戻される。身代金を取って全ての捕虜を解放するよう支持していた海賊船の指揮官は、サフォークが身分を明かした途端態度を変え、次のように言う。「王妃にキスをしたその唇には地面を舐めさせてやろう」(“Thy lips that kiss’d the Queen shall sweep the ground”, 2Henry 6, 4. 1. 75)このように、シェイクスピアは王妃と彼の愛人関係を一般に広く知れ渡った事実として描き、サフォークを人々の敵意の対象として作り上げているのである。
- サフォークは殺害され、その遺体は自由になった捕虜の手で王妃の元へ届けられる。次に観客が目にするマーガレットは、サフォークの生首を胸に抱いて嘆く衝撃的な姿である。ケント州で蜂起したジャック・ケードの反乱の対応に追われるヘンリー王とバッキンガム公、セイ卿と対照的に、マーガレットの発する言葉はほとんどが傍白であり、観客以外の誰からも注目されることはない。夫であるヘンリーから一度だけ声をかけられるが、それも極めて冷淡な皮肉に満ちた言葉である(“if that I had been dead, / Thou wouldst not have mourn’d so much for me.”2Henry 6, 4. 4. 23-24)。国の緊急時にあって、明らかに彼女は部外者であり、サフォークを失った今となっては全くの孤立無援である。
- 悲嘆にくれるマーガレットが心を向けるのは、「復讐」である。
悲しみは心を弱くし、
恐怖に怯えさせ判断力を鈍らせると言うわ、
だから復讐することだけを考えて
泣くのはやめよう。
(2Henry 6, 4. 4. 1-3 )
だが、マーガレットが考える「復讐」とは何だろうか。サフォークを追放したヘンリーに対してなのか。それとも二人が目指していた権力の座を遠ざけるもの全てに対してなのか。彼女の復讐心がどこに向けられているのか、彼女自身が明確に語ることはない。というのも、サフォークを失った後のマーガレットは、それ以前の雄弁さをしばらく失うからである…(中略)…もしかすると、彼女自身、自分の復讐心をどこにぶつけてよいのかわからないのかもしれない。彼女が再び自分の立場を雄弁に主張するようになるのは『ヘンリー六世・第三部』においてである。ロンドンの議事堂を占拠したヨークは、自分がヘンリー四世によって王位簒奪されたリチャード二世の正式な王位継承者の末裔であると主張する。ヨークの主張が正当なものであることは、ヘンリー六世も認めざるを得ない(“I know not what to say, my title’s weak”, 3Henry 6, 1. 1. 134)。王側に付くエクセター公までもが自分の立場を忘れてその主張の正しさを認めてしまう(“My conscience tells me he[York]is lawful king”, 3Henry 6,1. 1. 150)。兵力にものを言わせてでもヨークを王位に就かせようとするウ
ォリック伯に対し、ヘンリーは姑息とも言える取引を申し出る。王ヘンリー ウォリック卿、ひと言だけ聞いてくれ、
私の存命中は王でいさせてほしいのだ。
ヨーク 私と私の後継者に王位を譲ると確約すれば
生きている間は王として平和に治められるようにしよう。
王ヘンリー それで結構だ。リチャード・プランタジネットよ
私の死後、この王国は君のものだ。
(3Henry 6, 1. 1. 170-175)ヨーク側にとっては王座に就くことが先延ばしにされただけであり、王位継承権の正当性が認められたことになる。しかし、ヘンリーは自分が退位させられる不名誉を回避するために、自分の後継者である皇太子エドワードを廃嫡したことになる。
つまり、父から息子へと受け継がれるはずの既得の継承権を自分勝手に他人に与えたのであり、彼の行為は父権制度そのものへの侵害を意味する。ジーン・E・ハワードとラッキンが論じるように、この行為はヘンリーの家長としての地位にとっても、一国の王としての地位にとっても致命的なものとなり、この劇の随所に見られる裏切り行為のパラダイムともなるのである。当然のことながら、ヘンリーはこの不当な取り決めによって、彼に付いていた有力な貴族たちや王妃の信頼を失い孤立することになる。クリフォード卿、ノーサンバランド伯、ウェストモアランド伯は、捨て台詞を残して王妃のもとへ向う。
続いて現れた王妃マーガレットは烈火のごとくヘンリーを責め立てるが、わけても彼女に我慢ならなかったのは、国の頂点に君臨し大権を行使する立場のヘンリー王が、臣下であるはずのヨークとウォリックに「無理強いされた」(“enforc’d”, 3Henry 6, 1. 1. 229)という言葉である。正式な結婚で生まれた後継者である息子の権利を守る義務があるにもかかわらず、無理強いされたからといって戦うこともせず安易に譲り渡してしまったという事実は、国王として、家長として、彼が不適格者であることを如実に示している。このことが、息子を廃嫡した法案が取り消されるまではヘンリーと食事もベッドも共にしない(“I here divorce myself / Both from thy table, Henry, and thy bed”, 3Henry 6, 1. 1. 247-248)とマーガレットに誓わせる。つまり、ヘンリーの家長としての地位を認めない、ということである。そして、自ら軍を率いてヨーク軍と戦うことを宣言する。
あなたの軍旗を見捨てた北方の貴族たちも
私の軍旗が翻るのを見れば、それに従ってくれるでしょう。
必ず翻らせてみせる、あなたの不名誉となり
ヨーク家の破滅となるように。
(3Henry 6, 1. 1. 251-254)ここでマーガレットは、夫ヘンリーの戦場における無能ぶりを印象付け、彼よりも自分の方が男としての役割をうまく果たせると主張している。自分が夫の地位にとって代わると言っているのである。
マーガレットの主張は、明らかに彼女が当時の父権制度の社会規範から逸脱した女性であることを示している。しかし、同時に彼女が要求しているのが父権制度の保証する父から息子への権利の継承であるという点で彼女の立場は逆説的である。
マーガレットは、自分と息子エドワードとの絆が父親であるヘンリーと彼のそれよりも強いことを強調する(3Henry 6, 1. 1. 220-225)。近代初期の社会において、子供は父親のものであり、父親からその気質を受け継ぐと信じられていた。また、母親の身体は子供を世に送り出すために通過する器官に過ぎないと考えられていた。そのため、正式の結婚により生まれた嫡子に「父親の子」という属性が与えられるのに対して、庶子は母親と結びつけて語られることが多い。従って、ことさら母親と息子の絆を強調することは、それ自体危険をはらんでいると言えるだろう。
皇太子エドワードの気質は明らかに母親譲りである。マーガレットとサフォークの愛人関係は既知の事実であり、皇太子の嫡出性に疑問が投げかけられても不思議ではない。劇の中でこの問題が正面切って浮上することはないが、リチャードが皇太子エドワードに向けた「お前の父親が誰であれ 、そこに立っているのが母親であることには違いない。母親と同じような口をきくからな」(“Whoever got thee, there thy mother stands, / For well I wot, thou hast thy mother’s tongue.”3Henry 6, 2. 2. 133-134 ; 傍点筆者)といった台詞や、ヨークの長男エドワードがヘンリー王をメネレーアスに喩えた台詞(3Henry 6, 2. 2. 146-149)は、皇太子の正当性の問題に一瞬であれ観客の目を向けさせるのだ。
マーガレットがヨークに見せる残忍さは、彼が自分と息子の権力の基盤であるべき王の実体を露呈させ、将来の権利までも侵害したことへの怒りの大きさを示している。モグラ塚の上に立ち、紙の王冠を戴いた王の姿にヨークを戯画化することは、ヘンリー王の不適格性を暴いたヨークを貶め、彼もまた王座には不釣合いなちっぽけな存在にすぎないことを見せつけるための手段にちがいない。さらにマーガレットは、ヨークの幼い息子ラットランドの血で染まったハンカチを差し出し、涙を拭いてみろと迫る。抵抗する術を持たない幼児の殺害を舞台上で演じることが、観客に強い衝撃を与え、激しい感情を引き出すのは言うまでもない。クリフォードによる幼児ラットランドの殺害は、それ自体衝撃的であり復讐の野蛮さを印象付けるのに十分であるが、シェイクスピアは、その血で染まったハンカチをマーガレットに出させることで、ラットランド殺害の衝撃を蘇らせ、彼女の残忍さを観客の脳裡に焼きつける。この仕打ちはマーガレットの味方であるノーサンバランドにとってすら酷すぎるものに感じられ、同情の涙を誘い出すことになる。
ヘンリーの王位と皇太子の王位継承権を守るための戦いは、ヨークの死後、彼の三人の息子たちを相手に続けられることになる。ランカスター軍の指揮をとるのは、やはり王妃マーガレットである。ヘンリーの王権を守ることが大儀であるにもかかわらず、彼はヨーク軍との戦闘においては足手まといでしかない。戦闘が始まると、王妃もクリフォードも声をそろえて王に戦場を離れるように勧める。本来ならば、自分の権利を主張して先頭に立って戦うべき王は、戦場から爪弾きにされ、ひとりモグラ塚の上で思索にふける(3Henry 6, 2. 5)。ヨーク殺害の場面で、モグラ塚が彼の手に入れようとした王座の戯画であったように、ここでもモグラ塚に腰掛けるヘンリーは、王の称号を持っていながら何の権威も持たない空ろな王が玉座についている姿の戯画である。
その目の前で繰り広げられるのは、無名の二組の親子の悲劇である。二組とも父と息子がヨーク側とランカスター側に別々に徴集され、一方は知らずに父親を殺してしまった息子が、もう一方では知らずに息子を殺してしまった父親が、それぞれの肉親の死体を前にして自分たちの運命を嘆くのである。その嘆きに形骸化した王ヘンリーが加わり、自分が悲劇を引き起こした原因であることを嘆く(3Henry 6, 2. 5. 103-112)。様式化された台詞はまるで戦争の悲惨さを歌う三重唱のような響きを持ち、観客の心に訴える。
ランカスター側が敗走し、エドワードが王として即位してからは、貴族たちの裏切りの連続となる。エドワードとフランス王の妹ボーナ姫との結婚話を進める使命を持ってフランスに渡ったウォリックの元には、エドワードがグレイ卿の未亡人エリザベスと結婚したとの知らせが届く。ウォリックはこの王の裏切りを知ると、フランス王の助力を頼みにフランスに渡っていた王妃マーガレットと和解し、ランカスター側に寝返る。エドワードの弟クラレンス公ジョージも、一旦エドワード側に寝返ったサマセットと共にランカスター側に付く。16)ウォリックの兄にあたるモンタギューは四幕一場ではエドワードに忠誠を誓いながら、次に登場する四幕六場ではランカスター側として登場する。エドワードのもう一人の弟グロスター公リチャード(後のリチャード三世)は、表面上兄王に従いながら、長い独白の中で王座への野心を抱いていることを明かす(3Henry 6, 3. 2. 124-195)。ヘンリー王がかつて国家の利益よりも自分の欲望を優先し、マーガレットと結婚したのと同じことをエドワードは繰り返し、同じように混乱を招くことになるのだ。エドワードの宮廷では、王妃となったエリザベスの近親の者たちが王によって優遇され、貴族たちの反感を買っている。こうして、エドワードもまた為政者としての資質を欠いた人物として描かれているのである。
「国王製造人」との異名を持つウォリックの働きにより、ヘンリーは一度は王位に返り咲くが、ウォリックの死後、再びマーガレットの指揮の下、テュークスベリーでヨーク側と対決することになる。戦いに先立ち、マーガレットは修辞疑問を繰り返す巧みなレトリックを駆使して、有力な戦士を失って意気消沈する味方の貴族や兵士たちの勇気を鼓舞する。「[舵手パイロットが]舵とりをやめて、恐怖に怯えた少年よろしく (“like a fearful lad”)溢れる涙で海水を増やすようなまねをするのが立派な行いでしょうか」(3Henry 6, 5. 4. 6-8)や、「さぁ、勇気を出しなさい!避けられないものを嘆いたり恐れたりするのはか弱い子供のすること(“childish weakness”)です」(3Henry 6, 5. 4. 37-38 ; 傍点筆者)という台詞から明らかなように、彼女が訴えかけるのは、ランカスター軍の男たちが誇りにすべき「男らしさ」である。さらに「少年」、「子供」といった言葉で常にその若さを強調される皇太子は、「臆病者」(“a coward”)でもマーガレットのように「勇敢な心を持つ女性」(“a woman of this valiant spirit”)の言葉を聞けば不屈の精神を吹き込まれることだろう、と言う(3Henry 6, 5. 4. 39-41)。マーガレットと皇太子は、本来は弱く無力なものとされる女と子供についての規範を自ら逸脱して見せることで男たちのプライドに働きかける。
次の場面で、捕虜となったマーガレットはすでに死の覚悟を決めており、もはや彼女が全てを賭けて戦ってきたランカスター家の王位継承権について語ることはない。この点で、最後まで王位継承者として語ることをやめなかった息子エドワードとは対照的である。今や意気消沈した無力な女性にすぎないマーガレットの目の前で、息子エドワードは刺し殺される。17)「ああ、ネッド、かわいいネッド、お母さんに話しかけておくれ、坊や」――マーガレットの叫びは、王妃でも女戦士でもなく、一人の母親の悲痛な叫びである。
彼[シーザー]は大人だった、でもこの子はまだほんの子供。
子供相手に狂暴な怒りをぶつける大人はいないはず。
…お前たちには子供がいないのだろう、屠殺人。もしいたら、
その子のことを考えて憐れみの情をかき立てられただろうに。
(3Henry 6, 5. 5. 56-57, 63-64)大人であるシーザーの暗殺は、今行われた非道な子供殺しに比べれば非難に値しない、また人の親であればこれほど酷いことはできない、とマーガレットは言う。この台詞に含まれるアイロニーは明らかである。観客はすでに復讐心に駆られたクリフォードが幼いラットランドを容赦なく刺し殺すのを目撃している。一幕でラットランドの血で染まったハンカチを父親ヨークに突きつけたマーガレットの残酷さが、五幕での母親の目の前で若い息子が刺し殺されるという残酷な場面と対応するよう意図されているのは明らかであろう。観客は因果応報(ネメシス)の厳しい原理を目の前に見せつけられるのである。
サフォークの死に際して復讐を誓った時のように、またヨークの王位簒奪の企みに対して自ら復讐を果たした時のように、マーガレットが息子の死に対して新たな復讐心を燃やすことはない。彼女が切望するのは、ネメシスのサイクルから身を引いて死ぬことだけであるが、その望みが叶えられることはない。絶望したマーガレットが最後に残すのは、息子を殺害した者とその子供達に息子と同じ運命が降りかかることを願う呪いの言葉(3Henry 6, 5. 5. 82)のみである。こうして、父権制度の約束する権利を守ろうとしてその規範を逸脱し、本来男性の役割である戦士というペルソナを身につけたマーガレットは、王妃という地位だけでなく妻、母親という立場をも奪われて生きることを余儀なくされる。『リチャード三世』の中で、年老いたマーガレットは王妃エリザベスに対して「お前が死ぬずっと前にお前の幸せな日々は死に絶え、悲しみの時間がずるずると引き伸ばされた後で、母でもなく妻でもなくイングランドの王妃でもないものとして死ぬがいい!」(Richard III, 1. 3. 206-208)という呪いの言葉を吐くが、その言葉はそのままマーガレットの人生を要約しているように思われる。
*シェークスピア史劇の「正統性創出」機能に感動したアレクサンドル・デュマは「ダルタニアン物語(1844年〜1850年)」において「(フランスの絶対王政化を推進した)イタリア人宰相」リシュリューやマザランを悪役視する一方で、当時「スペイン人王妃」として一緒くたに憎まれたルイ14世と初代オルレアン公の生母アンヌ・ドートリッシュ(Anne d'Autriche)救済の為に「悪女ミレディ」を創設して「7月王朝(オルレアン朝)史観」とでも呼ぶべき大衆向けの歴史観を完成させた。ベネディクト・アンダーソンは「フランスの公定ナショナリズムは18世紀からの新聞や小説の盛り上がりに端を発する」と述べているが、ヴィクトル・ユーゴー「レ・ミゼラブル(Les Misérables、1862年)」同様にその延長戦上に位置付けられる。
1220夜『モンテ・クリスト伯』アレクサンドル・デュマ|松岡正剛の千夜千冊*こうした流れのオリジナルとなったシェークスピア史劇の主題は「百年戦争でのフランスへの敗戦」や「テュークスベリの戦いにおけるランカスター朝側の大敗北」といった英国王権の瑕疵を如何に説明するかであり、それは「ジャンヌ・ダルク(大砲の魔女)」や「フランス人王妃マーガレット(大砲にやられた魔女)」や「ヨーク朝最後の英国王リチャード三世(大砲で魔女をやっつけた呪い返しにやられた奇形)」の悪役連載によって達成されたという訳である。
それにしても、「大砲は悪魔の発明品」なんて観念があったのねぇ。先日、キリスト教国が誇る焼夷兵器「ギリシャ火薬」が魔女の薬みたいな製法で作られてるような記述も見かけたが、案外この手の兵器にも幻想がまとわりついてるものねぇ。
— 日下春生(zsphere) (@faketaoist) 2017年1月26日
ベネディクト・アンダーソンのナショナリズム論との接点
『ヘンリー六世』三部作において、マーガレットは娘から妻、愛人、母親、そして夫も子供も失った未亡人、と女としての人生の様々な相を経験する。その大半が、歴史における重大なテーマである王権をめぐる闘争に関わるものであった。
その闘争に敗れ、全てを失った女として『リチャード三世』の劇世界に舞い戻ってきたマーガレットは、ひたすら自らが王権と関わってきた過去を語る。語ることによって登場人物一人一人を過去と結びつけ、さらに呪いという形で彼らの未来に起こることを予言する。彼女の人生そのものが「長い歴史のアクション」を体現しているかのようである。『ヘンリー六世』三部作でマーガレットの辿った軌跡と『リチャード三世』で彼女が語る内容を考えると、彼女が時代の生き証人として過去を語り、未来を予言することで『リチャード三世』の世界に過去から未来――観客にとっては、同時に過去の長い時間の経過――を通観する歴史の視点が導入されるのである。
マーガレットは、その娘時代を除いて――ジャンヌ・ダルクがその時代の彼女の役割を肩代わりしているのかもしれないが――近代初期の父権制度の規範からは逸脱した女であった。サフォークとの愛人関係は、結婚制度が支える父権社会そのものを覆す危険性をはらんでいた。また、父権制度が保証する父から息子への権利の継承を守るためであったとはいえ、自ら軍隊を指揮し男性の位置に取って代わるマーガレットは、当時の社会規範で理想とされる寡黙で目立たない女性とは対極に位置する。そういった女性が男性優位の社会において、常に男性にとっての脅威となることは言うまでもない。マーガレットの役割を特徴づける呪いとは、抵抗の手段を全て奪われ、全く無力な状態で吐かれるものであり、彼女の呪いは、その実質的力の欠如の裏返しともいえる。それでもマーガレットの呪いの言葉が聞く者の精神を揺るがす力を持つのは、その言葉が男性優位の社会に対する彼女の脅威に裏打ちされたものであるからに他ならない。シェイクス
ピアは、あらかじめ成就されることがわかっている呪いをマーガレットに語らせることで、彼女に単なる登場人物としての役割を超えた神性を与えているのである。
*ベネディクト・アンダーソンは「想像の共同体(Imagined Communities。想像の1983)」の中でナショナリズム発祥を「キリスト教的普遍史観(「メシア的時間」)からの脱却過程=均質で空虚な時間(過去と現在と未来をひとつの均質な時間で貫こうとする態度)」と結びつけて語っているが、まさにそれ。
821夜『想像の共同体』ベネディクト・アンダーソン|松岡正剛の千夜千冊*フランス絶対王政下のそれ同様、英国の公定ナショナリズムは「家父長制」的側面が強く、女子供や庶民や植民地人をその外側に追いやって「(自らは理性を有さない)組み敷かれるべき存在」として一まとめにしてしまう。まさしくシェイクスピア喜劇「じゃじゃ馬ならし(The Taming of the Shrew、1594年)」の世界。ここで興味深いのが、この作品中に「組み敷かれるべき存在」として登場する「パドヴァの商人バプティスタ・ミノーラの長女カタリーナ・ミノーラ」がイタリア・ルネサンスと結びつけられ、かつ作中において「(現在はもう通じない)昔話」と総括されてるあたり。エリザベス女王統治下において物語は単純に「男性の女性に対する優位=勧善懲悪」なる体裁を取る事は許されなかったのである。じゃじゃ馬ならし - Wikipedia
*割とこういう錯綜した歴史観を踏まえておかないと、欧米人が「未来を花束にして(Suffragette、2015年)」をどう観たか理解出来なかったりする。日本史について相応の基礎教養がないと「尊皇攘夷志士」がただのテロシストにしか思えないのと同じ。
そういえば、そもそもシェークスピア史劇の世界においては「百年戦争の掉尾を飾ったカスティヨンの戦いこそが、ヨーロッパ史において大砲が戦争の決着をつけた主要な要因となった初めての戦いだった。」という認識もまた存在しないのですね。
カスティヨンの戦い(仏Bataille de Castillon, 英Battle of Castillon、1453年7月17日)
百年戦争においてフランス王国・ブルターニュ公国とイングランド王国の間で行われた最後の戦い。
- ブルゴーニュとイングランドの同盟解消に成功したフランスは、徐々にイル=ド=フランスとシャンパーニュを制圧。アキテーヌに対してもその周囲から圧力をかけ始める。
- 1439年、オルレアンで召集された三部会において、フランス王国は軍の編成と課税の決定を行い、翌1440年に決定に反発した貴族の反乱(プラグリーの乱)を平定、1444年に行われたロレーヌ遠征の傭兵隊を再編成して、1445年には常設軍である「勅令隊」が設立された。貴族は予備軍として登録され、平民からは各教会区について一定の徴兵が行われ、訓練・軍役と引き換えに租税が免除されたため、自由(franc)という名前の付いた「自由射手隊(francs archers)」が組織されている。
- これら一連の軍備編成を行うと、シャルル7世はノルマンディーを支配するイングランド軍討伐の軍隊を派遣。1449年、東部方面隊・中部方面隊・西部方面隊に別れたフランス軍は3方からノルマンディーを攻撃し、11月4日にはルーアンを陥落させた。
- これに対し、シェルブールに上陸したイングランド軍は1450年4月15日、アルテュール・ド・リッシュモン大元帥が指揮を執るフランス軍と激突、このフォルミニーの戦いにおいてイングランド軍は大敗を喫し、8月には完全にノルマンディー地方を制圧されてしまう。シャルル7世はイングランド軍の立て直しを計る時間を与えまいとすぐさまアキテーヌ占領に着手。9月にギュイエンヌへ南下しベルジュラックを奪い、翌1451年5月にデュノワ伯ジャン・ド・デュノワとジャン・ビューローが率いるフランス軍がギュイエンヌの中心都市ボルドーを包囲、交渉の末に6月に占領すると、8月20日に南のバイヨンヌも占拠して百年戦争も終結を迎えたように思われた。
- しかしイングランド王家によって300年も統治されてきたボルドーの市民たちは、自分たちのことをイングランド人だと思っており、イングランド国王ヘンリー6世にこの地方を再び取り返すことを要望する使節を送る。
- 1452年10月17日、シュルーズベリー伯ジョン・タルボットは、ボルドー付近に3000人の武装兵および射手と共に上陸。フランスの守備隊はボルドーの市民たちによって追い出され、彼らは大喜びでイングランド人たちのために市の門を開けた。アキテーヌ南部のガスコーニュ地方の多くの町が、ボルドーの例に倣って、イングランド人たちを受け入れた。ノルマンディーとブルターニュにもイングランド艦隊が迫り、ノルマンディーを占領統治していたアルテュール・ド・リッシュモン大元帥と甥のブルターニュ公ピエール2世が迎撃して上陸を防いだが、これらは陽動で時間稼ぎをしている間にボルドーのイングランド軍は増援を得て強化されている。
- 冬の間、フランス国王シャルル7世は自分の兵隊を集め、作戦行動を取るべき季節に備えた。1453年の春がやってくると、シャルル7世はボルドーに向けて、3つの軍隊にそれぞれ別の経路を取らせて送り出した。ロエアック元帥ことアンドレ・ド・ラヴァルとジャン・ビューローが率いる一軍はボルドー周辺地域を落とす作戦に出てボルドーから50kmほど東に離れたカスティヨンを包囲した。
- シュルーズベリー伯はこの新たな問題に対応するために、新たに3000人の兵隊を本国から受け入れたが、その数はガスコーニュの境界まで何千人ものフランスの軍隊を押し返すには全く足りないものであった。フランス軍がカスティヨンを包囲下に置くと、シュルーズベリーは町の守備隊長の要求を受け入れた当初の作戦(野戦で国境まで押し返す)を放棄し、この町の解放に取り掛かる。
- ラヴァル・ビューローらはシュルーズベリーを恐れ、自分の配下の7000人から10000人の兵士に陣地を塹壕と矢来で囲うように命令し、300台の大砲を矢来の隙間に並べた。数の上での優位を享受しているはずのフランス側にしては、恐ろしく防御的な編成であった。彼らはカスティヨンを囲む一切の努力を放棄したのである。
- 7月17日、シュルーズベリーはフランス側の陣地に近づいたが、それは1300人の騎乗兵からなる前衛部隊を伴った主力軍の到着以前だった。彼はフランスの野営地の前の森において同程度の規模のフランス側の自由射手(francs archers(フランザルシェ)、弓の訓練をする代わりに租税を免除(franc)された自由民、民兵)からなる部隊を撃破しており、自兵の士気を大いに向上させていたのである。
- 最初の小競り合いから数時間後、カスティヨンの町からの伝令がシュルーズベリーの休憩中の軍隊(彼らは夜を徹して行軍してきていた)に、フランス軍は総退却し数百もの騎兵が要塞を捨てて逃げ出したと報告してきた。町の城壁の辺りから、粉塵がもうもうと巻き上がって遠ざかっているのが見えた。しかし逃げ出したのは来たるべき戦闘の前に陣地を去るように命じられた非戦闘員従軍者(商人・洗濯婦・売春婦)でしかなかったのであった。
- シュルーズベリーはすぐさま配下の兵士たちを再編成すると、フランス軍の陣地に向けて進撃。その結果完全武装した数千の弓兵と数百の砲門によって防御されている堡塁を目の当たりにした。驚きはしたもののシュルーズベリーは怯まず、フランス軍に対して突撃を合図。
*実はシュルーズベリーは直前の戦いで捕虜になっており、捕虜宣誓(釈放後も一定期間戦線に立たぬことを誓って解放される)をしての仮釈放状態にあったので武器をとってフランス人と戦うことができなかった。- イングランドの軍隊はフランスの陣地に突撃したが、塹壕を越えても雨霰と降って来る矢や太矢(石弓の矢)、猛烈な臼砲や大砲や小火器の攻撃を喰らった。集中砲火が行えた理由はかつての小河川の河床を有効活用した塹壕線であった。
- 一旦戦闘が始まると、シュルーズベリーは主だった召使からなる何人かの兵隊の増援を受け取ったが、1時間後、ブルターニュ公ピエール2世により派遣されたブルターニュ軍の騎兵が到着し、イングランド軍の右側面を衝く。イングランド軍は敗走しすぐにフランス軍の主力によって追撃され、シュルーズベリーは息子のリール子爵ジョン・タルボットと共に戦死した。
- この大潰走の最中、シュルーズベリーの馬は大砲の砲弾によって殺され、その馬の下敷きになった。ある自由射手が、彼がシュルーズベリーであることに気づき、手斧で彼を殺すまでその状態であった。
フランス軍は勢いに乗りボルドーを10月19日に落とし、ギュイエンヌ平定を果たしたことで百年戦争はフランスの勝利に終わった。一方、イングランドでは敗戦後にヘンリー6世が精神錯乱を起こしたのを契機に側近のサマセット公エドムンド・ボーフォートと王族のヨーク公リチャード・プランタジネットが内紛状態に突入。2年後の1455年に薔薇戦争が勃発して諸侯は疲弊し没落したが、王権は著しく強化されテューダー朝による絶対君主制への道が開かれる。フランスでも宗教戦争が起こって内乱が発生したが、祖国が統一されたことで王権が伸張し、ブルボン朝の絶対君主制へと進んでいく。
こうした思考様式は「機関銃の歴史」にも垣間見られます。「騎士道精神の全面崩壊」を恐れるあまり欧州人は、この殺傷力の高い兵器を同じ欧州人に向けるのを精神的に拒絶し続けてきました。この壁を平然と乗り越えたのが「騎士道精神って何? 美味しいの?」のアメリカ人と日本人、ボーア戦争(1880年〜1902年)で「植民地人は同じ白人でも欧州人の範疇に入らん」なる方便を駆使した英国人、「戦いは勝ってこそ」が伝統的信条の「チュートン騎士団国の末裔」ドイツ軍人という辺りにも独特の民族障壁を感じずにはいられません。そしていずれにせよ第一次世界大戦(1914年〜1918年)以降は誰もこうした倫理史には注意を払わなくなっていきます。
*そもそも欧州にはローマ教会が農民が騎士を打倒するのを恐れ「キリスト教徒同士が相手に弩を向ける事」を禁じ、そのタブーが英仏百年戦争以降黙殺される様になり、さらにはイングランド側が「ウェールズ流長弓術」投入で一時的優位を確保し、鉄砲や大砲の登場期にはもはや禁令の発令すらなかった歴史が存在する。
14世紀以降、銃の速射性の向上のため様々な人物により試行錯誤が重ねられてきた。レオナルド・ダ・ヴィンチも機関銃のアイディアを書き残している。
16世紀に技師、博学者でペルシア生まれのインド人であるファトフッラー・シラジが、砲身が17本ある黒色火薬を詰めたハンドキャノン(手銃)を発明している。イギリスではパルマーという人物が王立協会あての論文で、弾丸の発射の反動と漏れるガス圧を利用しての自動射撃の可能性について述べている。
詳しい資料が残っている最初のものは、ロンドンの法律家ジェームズ・パックルが発明したパックルガンで、1718年5月15日「ディフェンス」という名前で特許を取得。時代を先取りした口径25.4mmのフリントロック式リヴォルヴァーカノンで、薬室の構造など具体的な説明がされている。1722年に行われた公開実射試験では7分間に63発を発射している。しかしながら、キリスト教徒には丸い弾丸、トルコ人異教徒には四角い弾丸を使用するなど現実性に乏しい部分も見られ、実際に製造されることはなかった。
19世紀中頃までに数多くの連発火器や、半自動火器が登場する。ボレーガン(ミトラィユーズなど)やダブルバレルの拳銃は、銃の部品を何重にもすることに頼っていた。ペッパーボックスピストルは撃鉄を1つにしたが、銃身は複数必要であった。リボルバーはあらかじめ弾倉に弾を込めさえすれば1つの銃身で連発が可能であるが、パックルガンと同じく依然として半自動であった。
1834年、デンマークの発明家N・J・レイプニッツが空気圧機関銃を発明する。1分間に80発の連射が可能であったが、2mのはずみ車を2つ必要とするなど、非常に大掛かりな装置であったため、実用化されることはなかった。
1854年、イギリスのヘンリー・ベッセマー卿が蒸気を利用した自動後装銃の特許を取得。完全な自動装填装置を備えていたが、後に画期的な製鋼法(転炉)を発明したことにより、そちらに関心を向けるようになってしまった。
この頃までは、欧州社会を中心に機関銃が開発されていたが、騎士道精神がまだ残っていた西洋社会の中で白人同士の戦争にそれらの使用が忌避され、主に植民地の住民に対して使用された。白人同士で最初に大々的に使用されたのは、こういった倫理的制約の薄かった新興国であるアメリカ合衆国の南北戦争からであった。機関銃の持つ軍事合理性が騎士道精神より優先されたのである。
- 1861年の南北戦争の最中、セールスマンのJ・D・ミルズが、リンカーン大統領の前でユニオン・リピーティング・ガンと呼ぶ銃の実演を行った。この銃は、単一の銃身で自動連射が可能な手回し式機関銃で、1分間に最高で120発の連射が可能であった。リンカーンはコーヒーミルガンと呼び、ミルズの熱心な説得もあって、周囲の反対を押して1丁1,300ドルという高値でミルズの持っていた10丁すべてを買い取った。機関銃が販売された初めての記録である。この機関銃の開発者、起源ははっきりしたことは分かっていない。
- 1860年-1861年にウィルソン・エージャーによって製造されたものであるとされるが、1855年には原型が製造されていた可能性がある。エージャーと共にウィリアムズ・パーマー、エドワード・ヌージェントの名前があり、銃の特許権をめぐって裁判沙汰になっていて、アメリカではこの銃の特許の記録は残っていない。イギリスではエージャーが特許を取っており、エージャーガンとして知られていた。この銃はアメリカ軍の将校により少数購入され、橋などの防衛用として投入された。初めて機関銃が戦争で使われた記録であるが、信頼性、安全性に欠けていたため評判はすこぶる悪く、1865年までにはすべて軍から払い下げられた。
- 1862年11月-1863年5月の間、アメリカでの機関銃に関連する特許は80件以上に上っているが、実際に陸軍、海軍で試験されたものは7件だけであった。
- この時代最も、そして、初めて成功したものはガトリング砲で、1862年にリチャード・ジョーダン・ガトリングが発明した。束ねた銃身と薬室を手動で回転させる事により次弾を装填し連射を可能にする仕組みであり、他の機関銃と比べて最も信頼性が高かった。それでも、加工精度の低い弾薬が原因ですぐに弾詰まりを起こし、軍の評価は低かった。1865年に発表されたモデル1865は大幅に信頼性が向上しており、軍は評価を改め、1866年にはアメリカ陸軍で制式採用された。海外でもイギリスが採用した他、日本、ロシア、フランスなど各国が購入するなど広まった。アメリカでは自衛団などにも配備され、鉱山会社などでは労働者のストライキや暴動対策にも使用された。
- ガトリング砲やそれに類似する物は南北戦争やインディアン戦争、普仏戦争に投入されたが、機動性が悪く、少数しか投入されなかったため、有用性は認められたものの、課題も多く戦果も限定的であった。日本国内で使用された最初の機関銃はこのガトリング砲で、1868年に戊辰戦争の一局面である北越戦争で長岡藩の家老を務めていた河井継之助が初めて実戦投入した。
アメリカでは1871年にはガス圧を利用するフランスのオチキス機関銃が登場した。
1884年(特許取得は1883年)には、アメリカ人のハイラム・マキシムがイギリスで、水冷反動式のマキシム機関銃を発明し、1891年にはイギリス軍に採用された。マキシム機関銃はヴィッカース社により大量生産され、多くの国で類似品が生産された。1905年にはコルト社が空冷ガス圧式のブローニング機関銃を生産した。これらにより、機構が複雑で、重量がかさむガトリング砲は急速に廃れていった。
日露戦争では、日本軍はオチキスを「保(ホチキス)式機関砲」として採用、一方のロシア軍はマキシムPM1905重機関銃を使用した。旅順攻囲戦でロシア軍の機関銃が攻撃側の日本軍に対し圧倒的な破壊力を示した。その一方、日本側も騎兵に機関銃を携帯させ、効果的な用法を展開した。この当時は攻撃時における機関銃の運用法が確立していなかった。また、初期の機関銃は大きくて重く、三脚などの銃架に載せ3人以上で運用するもので、陣地や要塞などの防御兵器には向いていたが攻撃には不向きであった。その後、攻撃時に歩兵とともに前進し1-2人で運用できる軽機関銃が開発された。
第一次世界大戦においても機関銃は大いに威力を発揮し、突撃する歩兵が鉄条網で足止めされたところを守備側が機関銃によって撃ち倒し、攻撃側は多数の犠牲者を出した。そのため、双方とも塹壕に篭り陣地を構築して戦線が膠着し、これが、戦車を誕生させる要因になった。また、航空機の武装としても取り入れられ、当初は地上用の改良型だったが、高い発射速度とともにより軽量で加速度のかかった状態でも確実に作動するものが求められ、同調装置が発明されるなど航空機専用のものが開発された。
第二次世界大戦でドイツ軍が使用したMG34は、通常は軽機関銃として、三脚をつければ重機関銃として使用できる多目的機関銃として開発された。GPMG(汎用機関銃)の先駆けである。
軽機関銃の中でも、分隊ごとに装備されたより軽量なタイプは、「SAW(分隊支援火器)」とも呼ばれる。 通常、射手一人のみで運用される。小銃から発展した簡易機関銃といったものも多い。
広義には短機関銃もこの部類に含まれる。特にビラール・ペロサM1915は、拳銃弾を使用する軽量連装型機関銃として配備されている。
航空機がジェット化されると、単銃身の機関銃、機関砲では発射速度が足りず、高速の航空機を相手にすることが難しくなってきた。そのため、銃身を複数本束ね、より連射が効く機関銃として「バルカン砲」などのガトリング砲がモーター給弾式の形で復活した。
いかなるイメージ形成が行われたにせよ、欧州ではこの時期を境に「自然法とキリスト教的普遍史観が肯定する中世的分権状態」を超越した「(権力集中が生み出す)絶対的暴力の実在を前提とする権力論」にまつわる議論が始まった事実は動きません。「国民国家」樹立に至る歴史を巡る議論の最初の出発点は、あくまで歴史上のこの時点たるべきなのです。
こうした観点に立つと、その経済的繁栄と市民社会における自由な空気の横溢にも関わらず「オランダは国民国家になりそこなった国」なんてパースペクティブが浮上してきてしまいます。
- ウェストフェリア条約(1648年)締結によって公式に独立を勝ち取りながら、以降も延々と「総督派」と「都市門閥派」の対峙が続き、中央集権化が一向に進まなかった。
- 実際、イングランド王を兼ねたウィレム3世の総督時代(1672年〜1702年)を挟んで1650年から1747年の間、2度にわたって主要な州で総督を置かなかった時代がある(無総督時代)。1747年、オーストリア継承戦争(1740年〜1748年)に巻き込まれてフランス軍の侵攻を受けた連邦共和国は、イギリスの後押しもあって、ウィレム4世(在任1747年〜1751年)を7州全ての総督に指名し、その地位の世襲を宣言した。
- オラニエ公ウィレム5世(Willem V van Oranje-Nassau、在位1751年〜1795年)の時代にはさらに共和派の愛国派(パトリオッテン派)が出現して1785年に蜂起。国外追放されたオランダ総督一族(オラニエ=ナッソウ家)は彼らを鎮圧する為にプロイセン王国の軍事力に頼るしかなかった。
- オランダ王国(1815年)の成立はナポレオン戦争後のウィーン体制下、すなわち復古王政時代(1815年〜148年)にまで遡る。しかしながら国民統合が遅々として進まず、ベルギー革命(1830年)を食い止める事も出来なかった。
こうした歴史は、概ね17世紀後半以降のオランダの経済的没落とセットで語られます。
同時期にはオスマン帝国の既得権益が「軍事力を掌握するイェニチェリ軍団」「商業分野を独占するギリシャ人」「軍人と官僚の供給民族として台頭したアルメニア人」「徴税権を購って半独立状態を勝ち取った在地有力者達」に分割される一方、国外に追放されたユダヤ人の流入によって欧州経済が活気付いています。一方、フランスにおいては絶対王政化によってギルド(職人組合)や農作物市場といった伝統的社団の温存が図られる一方で農村共同体の崩壊が進行。サン=キュロット階層(浮浪小作人階層)と呼ばれる革命戦争やナポレオン戦争の兵士供給階層が急拡大しています。
ある意味「国民国家」とは、それ自体がこういう時代にあるべき軍事力の形態を追求した産物だったかもしれません。ナポレオンは「戦争は戦争を持って養うべし」としましたが、これは石原莞爾ら大日本帝国の昭和軍人にも好んで引用されています。
流石に15世紀〜16世紀段階の欧州において、そこまで覚悟を決めた人間はいなかった?
さて、私達は一体どちらに向けて漂流してるのでしょうか…