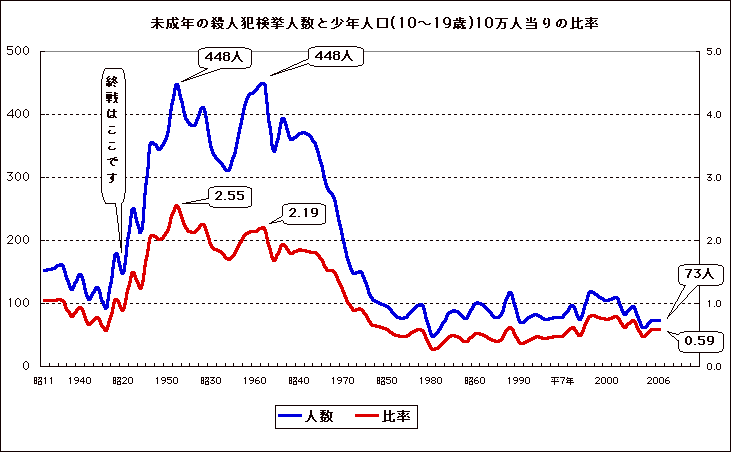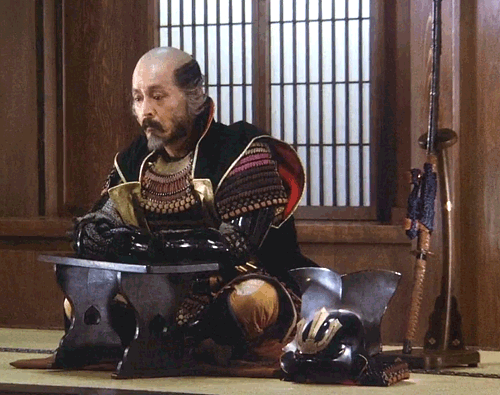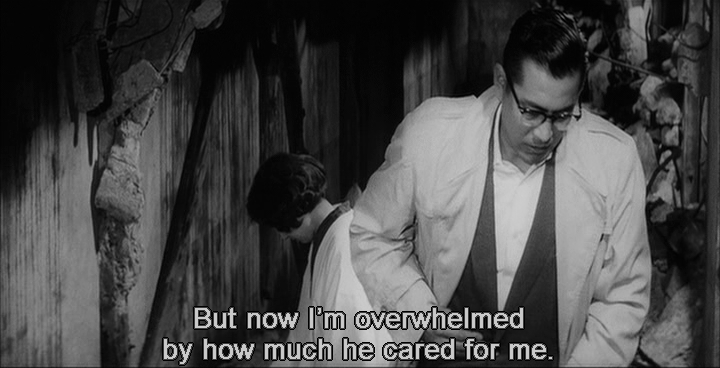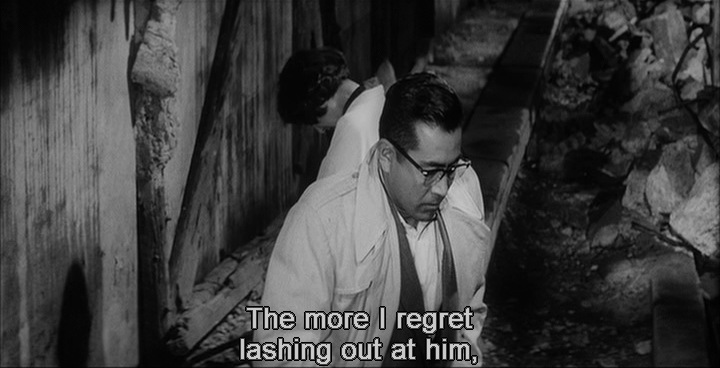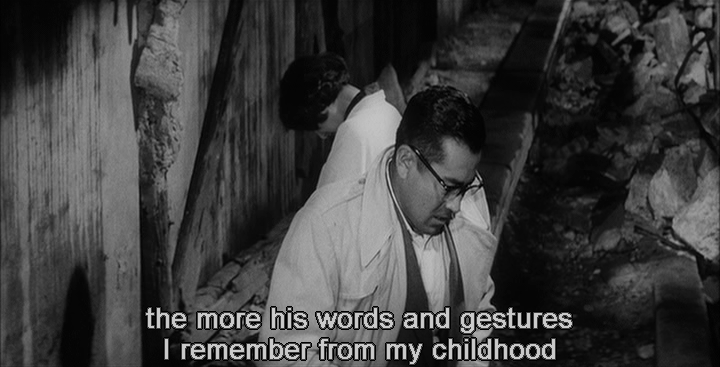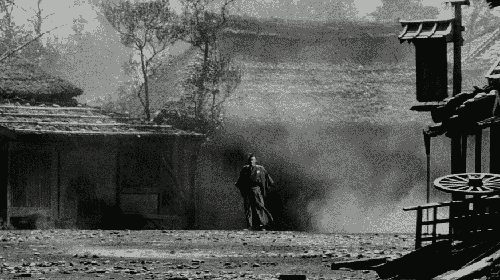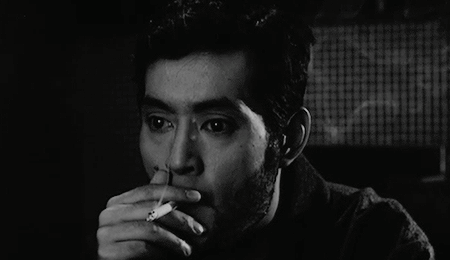黒澤明監督映画における1950年代までと1960年代以降の繋ぎ目。
黒澤明監督映画「悪い奴ほどよく眠る(The Bad Sleep Well、1960年)」
黒澤が東宝より独立して創始した黒澤プロの初作品。東宝との共同制作だが、次回作『用心棒』以降は菊島隆三が黒澤プロ側のプロデューサー(東宝側は一貫して田中友幸が担当)として固定されるので、本作は黒澤の数少ない製作・監督兼任作品(他には『どですかでん』『影武者』、途中から製作を兼ねた『隠し砦の三悪人』がある)となった。
- 脚本自体は「いきものの記録(1955年)」惨敗後、今井浜の舞子園で「どん底(1957年)」「蜘蛛巣城(1957年)」「隠し砦の三悪人(1958年)」と一緒に執筆された。
*すなわち良い意味でも悪い意味でも松本清張ブームの影響で執筆された社会派ミステリーではない。
- 興業上の成功だけを狙った安易な作品ではなく、あえて難題を扱うという意志から、公団とゼネコンの汚職という題材を選んだと黒澤は語っている。
*「羅生門」「生きる」「七人の侍」「いきものの記録」および上掲4脚本を手掛けた橋本忍。以降黒澤組から離れ、松本清張原作・野村芳太郎監督映画「張り込み(1958年)」「砂の器(1974年)」や異色時代劇「切腹(1962年)」脚本などを手掛ける。こういう分野では彼の影響力が大きかったとも。
- 次回作以降、黒澤は二人(以上)カメラマン分担体制を確立するので、単独カメラマンがクレジットされる映画はこれが最後である。岡本喜八作品などで知られ、これが唯一の黒澤作品となる逢沢譲が担当している。
- 冒頭、状況説明を登場人物の語りで行うのは(本作では結婚式の場に取材に来たベテラン新聞記者が他の記者たちに語る)、ギリシア悲劇のコーラス隊のコーラスを踏襲したもので、黒澤映画の常套手法であるが、それを結婚披露宴で行うのは、後に映画『ゴッドファーザー』でも採用されている。
*大元は「虎の尾を踏む男達(1944年〜1945年、公開1952年)」すなわち能楽冒頭の語りだったとも。また「ゴッドファーザー」はただ単に「結婚披露宴の場面から始まる」だけでなく「その時結婚した夫が以降妻に冷たく当たる様になって家庭問題に発展」「最後にはとうとう夫が裏切者として始末されてしまい、妻が半狂乱となる場面で終わる」といった部分まで「悪い奴ほどよく眠る」と重なっている。
- 本作で西幸一(三船敏郎)の妻岩淵佳子を演じた香川京子は終盤、兄の岩淵辰夫(三橋達也)の車から降りるシーンで、シートベルトをしていなかったので誤って車がブレーキをかけて止まった反動で、フロントガラスに頭から突っ込んでしまい、顔を何針も縫うほどの大怪我を負ってしまった。傷も大きかったので「もう女優の仕事はダメかもしれない」と引退を本気で覚悟したという。このとき香川が運ばれた病院にマスコミが集まってくるが、三船敏郎が香川の病室のドアの前に立ち、すべての取材を断っていたという。また三船は、ロケバスに衣装係が積み込むのを手伝うなど、そのように、三船は一生懸命に人のためにしてくれる人だと、香川は語っている。
- 本作で「巨悪の目に見える頂点」岩淵(日本未利用土地開発公団副総裁)を演じた森雅之は当時49歳と、息子役の三橋達也と一回りしか変わらないが、実年齢を上回る初老の役を演じて新境地を開いた。
タイトルは、本当に悪い奴は表に自分が浮かび上がるようなことはしない。人の目の届かぬ所で、のうのうと枕を高くして寝ているとの意味であり、冒頭のみならず、ラストシーンでもタイトルが大きく出る。
公開当時には「父を殺した現代社会の悪の機構に対する復讐譚」「強大な悪を暴く社会派映画」と認識された様ですが、正直その観点から眺める限り実に薄っぺらな作品です。しかしまさにその「薄っぺらさ」こそが、この作品を「時代に置き去りにされ、途方にくれながらも生き急ぐのを止められなかった男達の挽歌」たらしめるという悲しい展開。
まずは、この作品における「薄っぺらさ」あるいは全然背骨が通っていない感じの正体を突き止めるところから始めないといけません。
- 復讐鬼する側の動機が、揺らぎまくる…ある時は「親を殺された仇」、またある時は「国民を苦しめる税金泥棒の退治」、しかも舌の根も乾かぬうちに今度は「税金泥棒の片棒を担いだのは俺の親父も同じだ。わずかな餌で飼い慣らされ、上司の身代わりに殺されたって恨む事も知らない。牛や豚だってもっと親切に殺されていくよ」などと(人間をそういう鋳型に嵌めてしまう)官僚機構そのものの悪口を言い出す。挙げ句の果てに元来、巨悪の懐に飛び込む手段に過ぎなかった筈の結婚相手(香川京子)に本気で惚れてしまい、イジイジと苦悩。ちっとも憎悪が凝縮して復讐に向かう構図が成立しない。
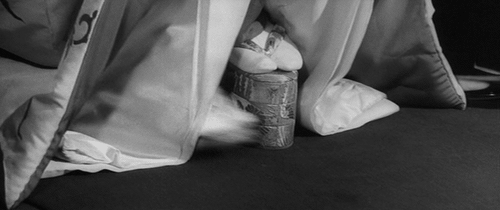



- 復讐する側のモチベーションが常に枯渇寸前…ともすれば枯渇しがちなやる気を、強引な自己鼓舞だけで保たせ様とする場面が目立つ。曰く「悪を憎むのは難しいよ。憎しみを掻き立て続け、俺自身悪になりきらないと出来ないよ」。曰く「こいつを許す権利なんて誰にもないよ。こういう事でもないと、今頃は幸せなツラしてすやすや眠ってる奴らなんだ。それを思うだけで次々と憎悪が湧いてくる筈なんだ」。まさしく音楽用語でいうRAVE状態。
- 何故かこの作品においてのみ乱発される「国民の為に」なるスローガン…このせいで、他の登場人物達を動かしてる動機も実に薄っぺらく見える。検事は「公団の方はまず国民の利益を求めなければならない立場です」「その120億円は国民が血の出る思いで出だした税金ですよ」、マスコミは「貴方は国民に対して全て正直に話す義務があります」、復讐鬼側も「好きな様に喰い物にされ、しかも恨む事も憎む事も出来ずにいる国民に代わってあの悪党をどもを裁いてやる」。他の黒澤映画の多くに見られる「伝説の人々(Legends)と庶民の邂逅が生み出す濃厚な駆け引きの世界」とは比較にならない薄っぺらさ。
さらには「敵」としてクローズアップされる組織すら、恐ろしいまでに抽象的で薄っぺらな存在ときています。
黒澤明監督作品「悪い奴ほどよく眠る(The Bad Sleep Well、1960年)」より
復讐鬼側に「自らを口封じする為の自殺」を止められ、彼らと行動を共にする様になった和田(公団契約課課長補佐、藤原釜足)の発言。
和田「私は恐ろしいんです。こんな事していて末はどうなるんです? 相手は引いても押してもどうにもならない恐ろしい勢力なんですよ。私は25年役人をして、それを肝に銘じて知っているんです」
西幸一(三船敏郎)「そう、みんなそう思って諦めている。だから彼奴らはのうのうとのさばっている」
和田「これ以上幾ら責めたって部長は口を割りませんよ。貴方達は役人の気持ちを知らないんだ。役人は上司に類を及ぼす様な事は決っして言わない。例えわが身がどうなろうとも」
板倉(加藤武)「美しい話ですな。だから汚職が後を絶たない。大物は安心して税金を盗める。めでたしめでたしという奴ですよ」
和田「私だって苦しいんですよ。時々一体自分が何なのか分からなくなる。自分は一体誰なのか。生きてるのか、死んでるのか。あんた達には目的があるからいい。しかし私には…」
板倉「それじゃあ、何も?」
和田「それが、それがわからない」
ただこれは「生きる(1952年)」においては主に善良面に注目した「官僚の世界」の暗黒面に目を向けただけとも。
- 役人の「時々、自分が生きてるか死んでるか分からなくなる」という嘆きや間接的にしか語られない主人公の死などに「生きる」へのセルフ・オマージュを見て取る向きもある。
- 「国民なる便利使いばかりされている抽象概念」の前身を「生きる」における「本来市役所の奉仕対象である筈の市民」に見て取る向きもある(ただし「生きる」の主人公だけは「汚水溜まり近隣の主婦」という公僕として本当に奉仕すべき相手に邂逅した)。
*この辺りはトルストイ「イワン・イリイチの死(Смерть Ивана Ильича、1886年)」における「時流に押し流され、皇帝の臣下から国民なる新設抽象概念に対する奉仕者への変貌を強要される官僚の悲哀(しかも当人は全く自覚してない)」の影響を受けている可能性がある。 - 「生きる」の主人公はとりあえず「汚水溜まりを埋め立てて公園を建設する」目的は果たしてから亡くなったが、市役所の雰囲気の停滞した雰囲気の刷新にまでは成功しなかった(本人も別にそれを望んでいた訳ではなかったが)。「悪い奴ほどよく眠る」の役人は、まるで「侍の1日」で切腹する「家禄百五十石の使い番」の様に上役に生死与奪の権利まで握られているが、忠誠心から逆らえない。
*ここまで態度が変貌するなら、やはり「侍の1日」シナリオは没にして正解だったという事になる? - 状況的に「生きる」の主人公は(息子夫婦を含めた)周囲から「老いらくの恋」に走ったと誤解されていた(一方、誤解された相手の娘は葬式の席にも現れない)。「悪い奴ほどよく眠る」では最終的に官僚社会の尻尾切りで自殺に追いやられる主人公の父が(現在の生活の虚しさから)結婚前の私生児(政略結婚の為に捨てた女の子供)たる主人公との関係修復を試み、それを跳ね除けた主人公に精神的トラウマを残す(しかしながら主人公は「政略結婚によって女性を不幸にした父親の罪」を繰り返してしまう)。
*ここに「いきものの記録(1955年)」における「猪突猛進型の家父長」中島喜一(三船敏郎)と死んだ妾の息子の関係を見てとる向きもある。
ところで海外ではこの作品をシェークスピア戯曲「ハムレット(he Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark、1600年〜1602年)」翻案と見る向きが多い様です。
- 先王ハムレットの亡霊(King Hamlet, the Ghost)…先代のデンマーク王。ハムレットの父。クローディアスの兄。「悪い奴ほどよく眠る」では官僚社会の尻尾切りで自殺に追いやられた西幸一(三船敏郎)の父に該当。映画内に直接登場はしないが、詰め腹を切らされ西幸一の父同様に自殺しかけた所を助けられた和田(公団契約課課長補佐、藤原釜足)が、ある程度までその立場の代弁者となる。
- ハムレット(Hamlet)…父の亡霊に悩まされ、最終的には復讐を果たして死んでいくデンマーク王国の王子。「悪い奴ほどよく眠る」では同様に官僚社会の尻尾切りで自殺に追いやられた父の無念を晴らす為に復讐を思い立つも、政略結婚した敵の娘に本気で惚れてしまい道半ばで倒れる西幸一(三船敏郎)に該当。
- ホレイショー(Horatio)…ハムレットの親友。最後に瀕死の彼から全てを聞かされ、後世に語り継ぐ役を託される。「悪い奴ほどよく眠る」では西幸一(三船敏郎)の復讐の手助けをする板倉(加藤武)に該当。
- クローディアス(Claudius)…ハムレットの叔父。ハムレットの父の急死後にデンマーク王位を継ぐが(父の亡霊から彼に毒殺されたと囁かれ復讐を思い立った)ハムレットに殺される。「悪い奴ほどよく眠る」では基本的に「三悪の一人」にして「目に見える巨悪の頂点」岩淵(日本未利用土地開発公団副総裁、森雅之)に該当するが「オフィーリアとレアティーズの父」としてのポローニアスの側面も継承。その一方で「本当の巨悪」も切り離された。
- ポローニアス(Polonius)…デンマーク王国の侍従長。王の右腕だがハムレットと王妃の会話を盗み聞きしているところを「鼠の様に」殺される。「悪い奴ほどよく眠る」では基本的に「三悪の一人」守山(公団管理部長、志村喬)に該当するが、多くの属性を「三悪」の残り二人に持って行かれてしまう。白井(公団契約課長、西村晃)は「鼠の様に殺される」側面だけ継承したキャラとも。
- オフィーリア(Ophelia)…ハムレットの恋人。ポローニアスの娘。父親をハムレットに殺されたショックで発狂する。「悪い奴ほどよく眠る」では、父の岩淵に騙されて夫たる西幸一の死に加担しててしまったショックで発狂する岩淵佳子(香川京子)に該当する。
- ガートルード(Gertrude)…ハムレットの母。クローディアスと再婚し王妃となる。ポローニアスがハムレット暗殺の為に用意した毒杯を誤って飲み死亡。「悪い奴ほどよく眠る」では「本当の巨悪」が岩淵に送ってよこした(口封じの為の毒薬かもしれない)睡眠薬を代わりに飲まされる岩淵佳子(香川京子)に該当する(それは実際には毒薬ではなかったのかもしれないし、あるいは彼女の発狂の間接的原因になったのかもしれない)。
- レアティーズ(Laertes)…ポローニアスの息子。オフィーリアの兄。「悪い奴ほどよく眠る」では(彼女を不具にしてしまった罪悪感から)妹の佳子を溺愛し、その発狂を契機として父の岩淵と決別する岩淵辰夫(三橋達也)に該当する。
おや、瀕死のハムレットからデンマーク王位を譲り渡されるノルウェー王子フォーティンブラス(Fortinbras)が余ってしまいました。
- おそらく彼は基本的には妹の夫たる西幸一(三船敏郎)の「事故死」、そして妹の岩淵佳子(香川京子)の「発狂」によって父たる岩淵(日本未利用土地開発公団副総裁、森雅之)の後継者となる地位を得た岩淵辰夫(三橋達也)に該当する。
- ただし「ハムレット」では常に「何者かになろう」という意志でガムシャラにあがき続けるフォーティンブラス王子と、恵まれた立場にありながら「何者になるべきかわからない」とウジウジし続けるハムレット王子が終始表裏一体の対比的存在にとして描かれ抜くのに対し、「悪い奴ほどよく眠る」においては西幸一と岩淵辰夫の双方がそれぞれの立場なりに「何者かになろう」とガムシャラにあがき続ける存在にして、恵まれた立場ながら「何者になるべきかわからない」と悩む存在として描かれる。
- そうした展開故に最終的に「岩渕家の継承者」として残った辰夫はその道を選ばず、発狂した妹を連れて出奔する。そしてもし「本当の巨悪」が岩淵に送ってよこしたのが「発狂薬」だったとしたら、既に「尻尾切り」は始まっているのであり(西幸一を死に追いやった)岩渕を外遊先で待つのは「事故死」。辰夫は西幸一同様に「父との和解の機会を逃した息子」の立場に立たされる事になるのである。それは(「ホレイショー=板倉(加藤武)」と手を組んでの)新たな復讐劇の始まりとなるのかもしれない。
もしこの見立てが正しいとすれば「悪い奴ほどよく眠る」に対する「ハムレット」の影響は、その初期設定まで遡らねばならなくなるかもしれません。
「ハムレット」の初期設定はこういうものだった。
- 「デンマークの王位継承権者は、最後の生き残りの王女ガートルードである。彼女と結婚する資格を争って決闘したのが、先王ハムレットと、隣国ノルウェーの王フォーティンブラス(先代)である。
- ハムレット王が勝ってデンマーク王になったものの、ハムレット王子はこの決闘の当日に生まれた、つまり婚前交渉によってできた子供なので、私生児とみなされる。本来、王位継承権がないハムレット王子は、ヴィッテンブルグの神学校に留学させられ、聖職者になるはずだった。
*そして「ハムレット」に登場するフォーティンブラス(二代目)もまた、継ぐべき領土を持たないという意味でハムレット同様「私生児」の立場にあった。- ところが、先王が新たな子をなさぬうちに急死したため、隣国のフォーティンブラス(二代目)が「繰り上がり継承権」を主張して戦争準備を始める。そこで新王クローディアスは、まずハムレット王子を呼び戻して、彼が庶子ではなく王位継承権者であることを宣言、デンマークが空位となる事態を防ぐ。いっぽうフォーティンブラスには、デンマーク王位への野心を捨てさせるかわりに、彼のポーランド侵攻を支援するという形で「外交的決着」をはかり、戦争を回避することに成功する。
- しかし、こうした新王の和平政策を「妥協、屈辱」と考えるタカ派青年将校たちは、ハムレット王子を「反クローディアス王」の旗頭として担ごうと画策する・・・。
だからハムレットは死に際に一見デンンマーク王家とは縁もゆかりもなさそうな隣国の王子「フォーティンブラス」を次のデンマーク王に指名し、それに誰も文句を言わず従うのである。
*つまりハムレットには自分と同じ「私生児」の立場にあるフォーティンブラスへの同情があり、それは家臣団とも共有されていたという事。
こうした「文学上における復讐者の神経症的心理」については、精神科医シグムント・フロイトが第一次世界大戦(1914年〜1918年)後、綿密な解析を試みています。
シグムント・フロイト「精神分析の作業で確認された二、三の性格類型(1916年)」
シェイクスピアの『リチャード三世』の冒頭のモノローグモノローグで、後に王となるグロースターは、こう呟いている。
だがこのおれは、このようなやさごとには生れつき向いていないし、
自惚鏡に向って骨を折るようにできていない。
おれは下手くそな刻印を押された出来損いの貨幣だから、
流し目ですまして歩く女の前に出かけてゆくほどの心臓がない。
そんな均整というものを切り取られているこのおれは、
あの「自然」の女神に、ついだまされて、
かたわで、未完成で、月たらずのままで、
ほとんど半分もでき上らぬうちにこの世に送り出されたのだ。
こんなに不恰好で、およそ浮世離れの姿をしているので、おれが
跛(ちんば)をひいてそばを通ると、犬のやつめはおれに吠えかかる。
……[中略]
こんな巧言令色の軟弱な時代を、楽しく暮らすような色男には、
おれは絶対になれっこはないのだから、
おれは決心した。いっそのこと、悪党になってやる、
そしてこのごろのあのつまらぬ楽しみを呪ってやる一読しただけでは、この台詞がわたしたちのテーマとどう関係があるのか、分かりにくいかもしれない。リチャードが言おうとしているのは、たんに次のようなことだと思えるかもしれない。「この軟弱な時代にはうんざりした。少し楽しんでやろう。だが醜い姿のために色男になることはできないから、悪人の役を演じてやろう。陰謀を企て、殺人を犯し、そのほか、好きなことをやってやろう」。
しかしこのような浅薄な動機づけでは、その背後に真面目なものを隠していないかぎり、観客のうちには共感のかけらも生みだすことはできないだろう。そして観客に共感を生みだすことができなければ、この作品は心理学的には不可能なものになってしまう。もしも観客に内的な反感を感じさせずに、主人公の大胆さと巧みさに賛嘆の念を抱かせようとするならば、作者は観客の心のうちに、主人公にたいする同情の気持ちを作りだす秘密の仕掛けを作っておく方法を心得ておかなければならない。そしてこの同情の気持ちは、もしかしたら自分も主人公と同じ気持ちをもっているのではないかという感情と理解を土台とするしかないのである。
だからリチャードの独白は、すべてを語っているわけではない。彼はたんにほのめかしているだけであって、ほのめかされたものを解釈して仕上げるのは、観客にまかされている。そして実際に、ほのめかされたものを解釈解釈してみると、浅薄な動機という外見は姿を消して、リチャードが自分の醜さを描きだしているときの苦々しさと詳細さが正当なものとしてあらわになってくる。そしてわたしたちとの共通性がはっきりとしてきて、この悪人に同情せざるをえなくなるのである。
彼がほのめかしているのは次のようなことだ。「自然はおれに、人から愛されるような好ましい姿を与えてくれなかったが、これはひどく不公正なことだ。人生はおれに損害賠償をする義務がある。おれは賠償を取り立てる。おれは自分が〈例外者〉であることを要求する権利がある。ふつうのやつらが遠慮するようなことでも、実行する権利があるのだ。おれは不正をすることができる。おれに不正が行われたからだ」。するとわたしたちは、自分もリチャードの立場に立たされれば、そう考えるかもしれない、ある程度は自分もリチャードと違いはないのだと感じるのだ。リチャードは、わたしたちが自分のうちに感じる一面を、法外なまでに拡大した姿にほかならない。
*つまり「復讐者」となる事は「例外者」となる事。神経症的人格を特徴付ける「自己中心性」や「復讐願望」が表面化する展開。
シグムント・フロイト「精神分析の作業で確認された二、三の性格類型(1916年)」
現実において、リビドーが欲求を満足させることのできる対象が失われるのが、外的な欲求不満である。外的な欲求不満は、それに内的な欲求不満が重ならないかぎりは発病の原因とはならず、病的なものではない。
内的な欲求不満は自我に由来するもので、リビドーが支配しようとしているほかの対象を、リビドーと争うために発生する。そのときに葛藤が発生し、神経症が発病する可能性が生まれる。すなわち、抑圧された無意識という迂回路をたどって、欲求が代償充足される可能性が生まれるのである。
内的な欲求不満はすべての場合で問題になるが、現実の外的な欲求不満によって、内的な欲求不満が働けるような状況が準備されるまでは、いかなる効果も発揮しないのである。
人間が成功の頂点にあって発病するという例外的な事例では、内的な欲求不満がそれ自体で独立して働いたのであって、外的な欲求不満の代わりに願望の充足が訪れた後になって、初めて現れるのである。ここには一見したところ奇妙なところがあるように思えるが、よく考えてみれば、自我がある願望を無害なものとして容認していることは異例なことではない。ただしそれはその願望が空想にすぎず、実現することはありえないと思われている場合にかぎられるのであり、その願望の実現が近づき、それが現実になろうとすると、自我はそれに激しく抵抗するのである。
これが神経症の発病の周知の状況と異なるのは、普通の神経症では内的なリビドーの備給が強まって、それまではまでは取るに足らぬものとして容認されていた空想が、恐ろしい敵に変身するのである。これにたいして、成功の頂点で発病する神経症の場合には、葛藤が発生するためのシグナルが[リビドーの備給の内的な強まりではなく]現実の外的な変化によって出されるという違いがあるにすぎない。
精神分析の仕事がわたしたちにわかりやすく教えてくれたのは、現実が好都合な形で変化したときに、そこから長く待望してきた利益を享受することを禁じるのは、その人の良心の力だということである。この良心というものは、まったく思いもかけなかったところで働いて、わたしたちを驚かせる。良心にそなわっている裁いて罰する傾向がどのようなものであり、それがどこから生まれたかを探るのは、困難な課題である。
*「例外者」の中には「復讐の達成」に手が届かない間だけ心の安寧が得られるタイプが存在し、達成の瞬間が近づくとむしろ抵抗する。神経症的人格を特徴付ける「自己拘束による無能力状態」が表面化する展開。
シグムント・フロイト「ドストエフスキーと父親殺し(1928年)」
古今をつうじた文学の三大傑作が、どれも父親殺しというという同じテーマを扱っているのは偶然ではない──ソフォクレスの『オイディプス王』、シェイクスピアの『ハムレット』、そしてドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』である。これら三つの作品ではどれも、父親殺しの動機が、一人の女性をめぐる性的なライヴァル関係にあることも明かされている。そのことをもっともはっきりと語っているのが、ギリシアの伝説に基づいた悲劇『オイディプス王』の筋立てだろう。この悲劇では主人公がみずから父親を殺害しているのである。しかしある程度は表現を緩和し、包み隠さずには、詩的な作品として作りあげることはできない。精神分析では、主人公が父親を殺害するという意図をもっていることを明確にしようとするのだが、それがあからさまに主人公の口から語られたのでは、精神分析的な準備のない読者には、耐えがたいことだろう。
ギリシア悲劇[の『オイディプス王』]では、事実を曲げずに、巨匠の手腕によって、主人公の意図が緩和されているのであるが(意図を緩和するのは、どうしても必要なことなのである)、そのために主人公の無意識的な動機が、主人公にとっては認識できない運命の強制によって実現されるのである。主人公は意図せずに、そして一見すると女性からの影響をうけずに、父親を殺害することになっている。それでも女性をめぐるライヴァル関係は筋の中に組み込まれている。主人公は[それと知らずに父親を殺害した後に]、父親を象徴する怪物[スフィンクス]を退治した後でなければ、すなわち第二の父親殺し殺しを実行した後でなければ、実の母親である王妃を手に入れることはできないのである。オイディプスは自分の罪が暴かれてそれを意識した後になっても、その行為が運命の強制であったという作者の筋書きの助けを借りて責任逃れをすることはない。自分の罪を認め、意識したうえで犯した完全な罪であるかのように、みずからを罰するのである。これは熟慮してみれば不当なことにみえるかもしれないが、心理学的にはまったく正しいことなのである。
これにたいしてイギリスの悲劇[『ハムレット』]の場合には、描写はもっと間接的であり、主人公が父親殺しを実際に行うのではなく、別人が犯罪を実行する。実行者にとってはこの犯罪は、父親殺しではないのである。だからといって、一人の女性をめぐる性的なライヴァル関係という不愉快な動機のほうは隠蔽されていない。[殺害者である]叔父による父親の殺害が、主人公のハムレットにどのような影響を及ぼしているかを調べることで、主人公のエディプス・コンプレックスがどのような間接的な働きをしているかを理解できるのである。主人公は叔父に復讐しなければならないと思うが、不思議なことに復讐を実行できないことに気づくのである。
わたしたちは、ハムレットを行動できなくしているものが、彼の罪悪感であることを知っている。この罪悪感は、[ほんらいは自分で父親を殺害したいという欲望をもっていたことにたいする罪悪感であるが、それが]復讐という課題を遂行できないという感覚から生まれた罪悪感罪悪感に姿を変えているのである。これは神経症ではごくふつうにみられるプロセスである。主人公はこの罪を、超個人的なものと感じているように描かれている。彼は自分だけではなく、他人も軽蔑しているからである。「人をその人相当に待遇したら、むちをまぬかれる者はだれもいないじゃないか?」というわけである。
ロシアの小説[『カラマーゾフの兄弟』]はこの方向をさらに一歩進める。この小説でも父親を殺害したのは[息子ではなく]他人であり、女性をめぐるライヴァル関係にあって[父親殺害の]動機をしばしば明かしていた主人公のドミートリーではない。しかしその他人というというのも、殺害された父親にとってはドミートリーと同じように息子の関係にあるのであり、ドミートリーの兄弟でもある。
また法廷での弁論では、心理学への有名な嘲笑が展開される。心理学というものは、まるで両刃の剣のようなものだと嘲笑されるのである。この弁論を裏返せば、ドストエフスキーの考え方のもっとも深い意味を理解することができる。これは手の込んだ隠蔽作業なのである。ドストエフスキーが嘲笑しているのはほんとうは心理学ではなく、裁判の捜査手続きである。その犯罪に実際に手を下したのが誰であるかは、どうでもよい問題なのである。心理学にとって重要なのは、この犯罪を心のうちで望んでいたものは誰なのか、そして犯罪が実行された際に、これを喝采したのは誰かということである。だからカラマーゾフ家の兄弟のうちで、他の兄弟と対照的な人物として描かれているアリョーシャに至るまですべての兄弟たちは[心理学的には]有罪なのである。衝動的に欲望の享受を望むドミートリーも、シニックな懐疑主義者のイワンも、実際に犯罪を実行した癲癇患者のスメルジャコフも、みんな同罪なのである。
*神経症的人格の特徴の一つ「非現実性」が表面化し「自己拘束による無能力状態」を誘発する展開。
フロイトの理論は全てが正しかった訳でもありませんでしたが、その神経症的病理の解析技法自体はカレン・ホルナイ(Karen Horney、1885〜1952)に継承されています。
神経症的要求4つの特徴|心ブログ 心理学をきっかけに一歩踏み出してみよう
カレン・ホルナイの定義する神経症的要求の特徴①「非現実的」
「~すべきだ」という思想を相手がどんな状況であろうと強要する。具体的にはこんな感じ。
- 「自分だけは病気になるはずがない、年を取るはずがない、自分から人が離れていくはずがない、自分は成功者になるべきだ」と考える。
- クラスに20人の友達がいたら、20人全員から好かなければならない。
第三者から見たら高慢に見えるが、本人は当たり前と思っている。
カレン・ホルナイの定義する神経症的要求の特徴②「自己中心的」
ジョージ・ウェンバーグ曰く。自分が自己中心的な理由で悩んでいるにも関わらず、
「誰も俺のことを分かってくれない」と言い出すのは神経症的だが、これは世界で最も使われるフレーズでもある。神経症者はさらに一歩踏み込んで「悩んでいるのは、世界で自分だけ」と考え「自分がこんなに悩んでるのに裏切られた」事こそを1st priority(最優先事項)と考える。具体的にはこんな感じ。
- 自分がパーティーを企画して欠席者が出たのが許せない。自分が入院したらみんなお見舞いに来るべきと要求する。向こうにも事情があるだろうとは考えない。
- 自分が上司に親しみを感じても、上司は自分について同じ様に感じるとは限らないのだが、それが分からない。上司との距離が5なら、自分との距離も5と考える。彼女との距離が5なら、自分との距離も5と考える。この心の状態が「自分が好きになった女性にフラれて刺してしまった」事件を誘発したりする。
- 夜分遅くに電話を掛ける。自分がメールしたらすぐに返信すべきだと要求する。それが迷惑行為でも、自分にだけは特別にその行為が許されると思っている。
- 小鳥に寒そうだといってお湯を飲ませて、結果殺してしまう。
- 「自分の知っていることが他者も知るべき唯一のこと」なので「お前はこんなことも知らないのか」という言い方が口癖となり、何でもかんでも褒めてもらえないと満足できなくなる。
要するに「自分の現実が唯一の現実」なので他者の現実が想像出来ず、自分の物差しでしか物事を計れない。「自分が何かして相手は感謝するのが当たり前」と考える。
カレン・ホルナイの定義する神経症的要求の特徴③「それにふさわしい努力をしない」
ギニスの「Friend and Factor」という本に「友達がいないと嘆く孤独な人に限って、それを作ろうと努力しない」という言葉がある。良いポジションや給料を望むが、その為の努力はしない。痩せたいと絶えず呟いてるのに何もしない。神経症者の場合はさらに踏み込んで魔法の杖を求めたり、何もしないまま幸運を待ったりするばかりで、自分の人生を自分の力で生きていこうという心の姿勢自体が存在しない。具体的にはこんな感じ。
- 夫からのDVに苦しむ妻に「別れたらどうですか?」と提案しても別れたくないと言う。だが夫への愚痴はこぼし続ける。これではまるで「自分の人生は駄目だった」と嘆き続ける人生に執着しているかの様である。
- 「直ちに」神経症を克服する方法を聞いてくる。そんな方法ないと説明すると激怒する。
そして「他人はなにもしない」と嘆く。
カレン・ホルナイの定義する神経症的要求の特徴④「復讐的」
ホルナイは「正義の強調は復讐心のカムフラージュ」と述べている。具体的にはこんな感じ。
- 矢口真理が不倫した時に、矢口真理のブログや2ch掲示板に非難の投稿が相次いだという。心の底に憎しみを抑圧している人だろう。だから正義を振りかざして相手をものすごく非難する。
- 自分の不安を他人に優越することで解消しようとしている未婚の女性は、友達が素敵な人と結婚していくことを不快に思い、心の底から「おめでとう」といえない。
絶えず相手を見返して、責めてやると憤慨している。根底に復讐心のエネルギーがあって、そこから相手への欲求が出てくる。これまでの全てをひっくるめ「世界はすべて私に奉仕すべきだ」と考えているとしか思えない。
*この感情こそが全ての症状の出発点。(シェイクスピア史劇「リチャード三世」でグロースター公が冒頭に放つ)「例外者」宣言であり、それ自体は誰の心にも潜んでいるといってよい。
黒澤明監督映画に登場する「神経症的キャラクター」すなわち「生きものの記録(1955年)」における「狂える家父長(三船敏郎)」や「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」における「復讐鬼(三船敏郎)」と重ねると、奇妙な不一致が浮かび上がります。彼らはその振る舞いに神経症的兆候を覗かせつつも「それにふさわしい努力をしない」という点だけは合致せず、しかも社交的で処世術に長け相応の行動力すら備えているのです。あたかも神経症患者の夢想の中にのみ存在する「自分が英雄として無双する世界」をそのまま取り出したかの様に。両作品が抱える「根本的浅薄さ」には、これに由来する部分が少なくないとも。
*一方、逆に演技面から見ればこの二作品は珠玉の奇跡。なにしろこうした脚本上の弱点を「(神経症的非活動性とは全く無縁にしか見えない)三船敏郎の肉体と演技」が見事に吹き飛ばしてしまうのだから。そう、あたかも荒唐無稽なアクション映画「コマンドー(Commando、1985年)」がアーノルド・シュワルツェネッガーの肉体の躍動によって破綻を免れている様に。
*「生きものの記録(1955年)」における「狂える家父長」の役は最初、志村喬が演じるはずだったが「内から込み上げるパワーが足りない」という判断から三船敏郎にバトンタッチされたという。おそらくそれが正解。志村喬ではこのキャラクターの神経症的重責に押し潰されて身動きが取れなくなっていた可能性が高い。そういえば同種の重責が掛かる「ゴッド・ファーザー(The Godfather、1972年)」のビトー・コルレオーネを演じたのも「肉体派」のマーロン・ブランドだった。役者の肉体恐るべし。
また、こういう分析もあります。
シグムント・フロイト「精神分析の作業で確認された二、三の性格類型(1916年)」
若者についての報告書、とくに思春期の前期の年代の若者たちの報告書には、後にはきわめて立派な人物になった人々が、思春期の前期に盗み、詐欺、ときには放火など、赦しがたい行為を咎められていたことが記載されていることが多い。これまでわたしは、人生のこの時期には道徳的な抑制力が弱いためだと考えて、こうした報告を重視してこなかった。そしてこれらの事実のあいだに、意味深長な関連があるのではないかと考察を試みようとはしなかったのである。
しかしわたしが分析した患者たちのうちで、こうした若年期をとっくに過ぎているのに、治療しているあいだにも、このような犯罪行為を犯すという明確で、興味深い興味深い事例が確認された。そこでこうした出来事について、ついに根本的に研究せざるをえなくなったのである。
そして分析作業によって、驚くべき結果が判明したのだった。というのは、こうした犯罪行為が行われたのは、それが禁じられているからであり、犯罪行為を行うことで、犯罪者の精神的な負担が軽減されるからだったのである。患者は、どこから生まれたのか理解しがたい圧迫するような罪の意識に苦しめられていて、罪を犯した後は、この圧迫が軽くなったのである。何らかの方法で、少なくとも罪の意識がいわば〈格納された〉のである。
逆説的に響くかもしれないが、犯罪行為が実行される前から、罪の意識が存在していたのであり、罪を犯したがために罪の意識が生まれたのではなく、罪の意識が存在したがために罪が犯されたと主張したいのである。こうした人物を、罪の意識のために犯罪者となる者であると呼ぶのは妥当なことだろう。もちろん罪責感が犯罪行為よりも前から存在していたことは、この犯罪行為という結果とは別の一連の言動によって証明されている。
しかし科学的な仕事の目的は、例外的に興味深い事例を確認することにあるわけではなく、次の二つの問いに答える必要がある。犯罪行為の前から存在していた暗い罪責感はどこから生まれたのか、そしてこのような罪責感は、人間の犯罪行為において重要な原因となっている可能性があるのではないかという問いである。
- 第一の問いを探求することによって、人間の罪責感一般の源泉についての洞察がえられるはずである。
*ここでフロイトはエディプス・コンプレックスについて得意げに語り「父親を殺し母親と性的に交わりたいという衝動の克服こそ人類にとっての良心の源泉」と結論付けるが、この考え方自体は後世に継承される事はなかったのである。
①昭和20年代(1945年〜1955年)の日本映画、深作欣二監督映画「仁義なき戦いシリーズ8本(1973年〜1976年)」、そして「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」におけ復讐鬼側(詳細は後述)は(原爆投下を含む)敗戦の痛手にこれを求めた。
②石原慎太郎原作「太陽族映画(1955年〜1956年)」は(敗戦を契機とする戦前インテリ=ブルジョワ層の権威失墜が引き起こした)退屈にその原因を求めた。
③「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」における岩淵辰夫(三橋達也)の粗暴な振る舞いの原因は、父岩淵の「世慣れた」部分に起因する。
④フランシス・コッポラ監督映画「ゴッド・ファーザー(The he Godfather、1972年)」のカルロ・リッツィ(ジャンニ・ルッソ)の粗暴な振る舞いと裏切りは、マリオ・プーゾの原作(1969年)では栄えあるコルレオーネ一族の女婿となりながら(チンピラ根性が抜けず)捨て扶持を充てがわれ飼い殺しにされる鬱屈が原因とされる。「悪い奴ほどよく眠る」見立ての映画飯では西幸一(三船敏郎)の立場に該当。ちなみに続編(1974年)では、第一作において(長兄ソニーの粗暴さと対となる)「純真無垢さの象徴」だった次兄フレド・コルレオーネ(ジョン・カザール)が同様に飼い殺し状況への反感から裏切る。
- 第二の問いに答えることは、精神分析の仕事の枠組みを超えるものである。子供たちでよく観察されることだが、子供たちは「悪い子」になって、おしおきをみずから招いておいて、罰せられると心が穏やかになって満足することがある。こうした子供たちが成人してから精神分析で研究してみると、罰をみずから招いた罪責感の痕跡をみいだすことが多い。
*土居健郎著『「甘え」の構造(1971年)』っぽいエピソードだが、上掲のグループにそうした要素は不思議なまでに一切見られない。どうやら1960年代後半から1970年代前半にかけての「若者の台頭」と密接な関係にある様である。その一方で戦後統計はアプレゲール( après-guerre=戦後派)犯罪を超える勢いで1940年代後半から1960年代末にかけて「超えてはならない一線を超えた」少年犯罪の増加があった事を記録に留めている。
- 成人の犯罪者について[罪責感が犯罪の原因となっているかどうかを]考察する際には、罪責感なしに犯罪を犯す人物は考慮から除外する必要がある。こうした人物は、道徳的な抑制力をもたずに成長してきた人物であるか、あるいは自分たちの犯罪は社会との闘いであると正当化するような人々であるか、そのどちらかである。
後になってある友人から、ニーチェもまた「罪責感から罪を犯す者」について検討していたことを教えられた。たしかに『ツァラトゥストラ』の「蒼ざめた犯罪者」の節を読むと、罪責感が犯罪以前に存在することや、罪責感を合理化するために犯罪を犯すことについて読み取れないことはない。犯罪者のうちのどの程度の者が、こうした「蒼ざめた」犯罪者に分類できるかは、将来の研究に待たねばならない。
それでは実際の脚本執筆過程はどういうものだったのでしょうか。
私の参加は我儘で不遜で一方的だった。仕事に当てるスケジュールは二週間、その代わりノーギャラ、脚本料なしの極端に責任の軽い身勝手である。
黒澤組が二次キャンプと称し、舞子園から河津浜の旅館に移動した時点で、私は東京を出て合流したが、小國旦那や菊島さんに混じり、久板栄二郎さんがいた。久板さんとは顔見知りだが、一緒に仕事をするのは初めてで、総勢五人である。一つの机に四人なら各辺に一人だが、五人だとどこかの辺が二人になり窮屈だ。それに私は黒澤さんの左隣が定位置だが、そこには久板さんがいるので、黒澤さんの右隣で菊島さんと並んだが、なんだか原稿を書く手勝手や要領がよくない。仕事は途中参加だから、話の流れに乗り切れず、マゴマゴしているうちに約束の二週間が過ぎたので、東京へ帰って来た。
暫くして完成した脚本が送られてきたが、なんだか読む気になれず、出来上がった映画も見ていない。名前を並べる脚本家の一人としては無責任、かつ不見識の極みだが、この作品には脚本を手に取らせたり、試写会の会場や映画館まで足を運ばせるものがない。
話は社会風潮をバックに、公団の汚職を取り上げ当世風だが、もう一つ生彩がなく『生きものの記録』以後はどうも冴えない作品ばかりが続く。
この映画(「悪い奴ほどよく眠る」)、小津(安二郎)さんに冷やかされた。監督協会のパーティで「あれは久板と黒澤がカッカして書いて、君と橋本君は寝てたんだろう」。事情を知らない小津さんがズバリ指摘したんです。 菊島隆三(脚本)
— 黒澤組スタッフの言葉 (@kurosawa_staff) 2017年1月28日
とにかく混乱した状況ではあった様です。そこから憶測するに、例えばこういう展開も考えられるのではないでしょうか?
- GHQ占領下(1945年〜1952年)、「虎の尾を踏む男達(1944年〜1945年、放映1952年)」を封印された黒澤明監督には「静かなる決闘(1949年)」において「性病」と「堕胎」、「羅生門(1950年)」において「自殺」、没シナリオ「侍の1日(1952年)」において「切腹」を扱う様な反骨精神が見受けられる。そういえば「いきものの記録(1955年)」や「蜘蛛巣城(1957年)」に濃厚な家父長制の軛(くびき)、「隠し砦の三悪人(1958年)」における「忠誠心ゆえの躊躇なき殉死」もGHQ占領下では禁止条項だったのであった。
*ただし「忠誠心ゆえの躊躇なき殉死」については黒澤明監督も必ずしもポジティブ要素とは捉えていなかったし(ヒロインの雪姫も激怒している)、黒澤明監督映画の影響を色濃く受けたジョージ・ルーカス監督に至っては、そうした要素の完全排除を狙っている(代わりに「ならばジェダイ騎士団とは何なのか?」という問題を抱え込む展開に)。
*ちなみに「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(Rogue One: A Star Wars Story、2016年)」に登場するドロイドK-2SOが、しばしば「ボスが言うので…(The Captain says…)」という言い回しをするのは「忠義」、その必要がある時にはジンもキャシアン平気で殴る辺りは「勧進帳」の影響と目されている。とどのつまり武蔵坊弁慶。もちろん最後は「立ち往生」。
- こうした振る舞いから黒澤明が同様にGHQが禁じた「仇討ち」について何も考えていなかった筈がない。しかしその一方では「たとえ完全には振り切れないにせよ、悪は悪として決然と切り捨てられねば、正義の存続は不可能となる」なる倫理的使命感から、これを全面的に肯定して美化して描く事も考えていなかったとも推定される。
*1940年代に芽生えた「焼け跡センチメンタリズム」の一バリエーションとも見て取れる。「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(Rogue One: A Star Wars Story、2016年)」における反乱同盟の「汚れ役専門部隊」に、久し振りにその純粋に近い形を見た。「上の奴らなら、帝国軍に降伏したって失うものなんて何もありゃしねぇ。だが俺たちはどうなる? 何の為にこの手を血で汚してきた事になるんだ?」これである。まさしく黒澤明監督映画「野良犬(1948年)」の世界。
*この魂を「和風ハードボイルドの祖」大坪砂男の孫、虚淵玄が継承しているのが興味深い。祖父の著作から引用して「ハードボイルドとは泥の大海の中に蓮の花を探すセンチメンタリズム」とか述懐。「PsychoPass-サイコパス(2012年〜2015年)」第1期最終回(2013年)
狡噛慎也執行官「悪人を裁けず、人を守れない法律を、何でそうまでして守り通そうとするんだ?」
常守朱監視官「法が人を守るんじゃない。人が法を守るんです! これまで、悪を憎んで正しい生き方を探し求めてきた人々の思いが…その積み重ねが法なんです!!」
- こうした条件を勘案しても「悪い奴ほどよく眠る」は最初から「復讐を主題としつつ、その成功を描かない」作品として構想された可能性が高いという結論に行き着く。そしておそらく(最初から本編の展開へと密接に絡んでくる事から)かなり早い段階から「(官僚社会を比較的肯定的に描いた)生きる(1955年)」の逆バージョンを目指す方向性も定まっていた様にも見て取れる。
*黒澤明監督は、その倫理的使命感から「酔いどれ天使(1948年)」の脚本執筆に際して若い結核持ちのヤクザ松永(三船敏郎)の最後についても「美化やロマンチックな要素を一切排除し、少しでも惨たらしく殺せ」と指示している。「七人の侍(1954年)」でも野武士側に同情的な描写は一切なし。「用心棒(1961年)」でも無頼は情け容赦なく皆殺し。ちなみにGHQ検閲の源流に当たるHays Codeにも「観客をギャングやその情婦への憧憬に導く描写を禁じる」という条項が存在する。これと黒澤明監督の信念の関係は明らかにされてない。
- しかしながら、やはり「復讐」展開には独特の快感とカタルシスがある(そして「酔いどれ天使(1948年)」の時代から「三船敏郎の飼い慣らされてない野獣の様な肉体」は物語の暴走を要求する)。脚本がその方向に引き摺られた結果「挫折に至る結末への着地方法」が見出せなくなっり、それで「ハムレット見立て」が導入されたと考えれば「気持ちよく復讐が進む場面」と「ハムレット見立ての場面」がちぐはぐに混ざり合う理由が上手く説明出来るのではあるまいか。
*後付けだからこそ、前半「ホレイショー(Horatio)=板倉(加藤武)」の存在が妙に浮いてたり、岩淵佳子(香川京子)がオフィーリア(Ophelia)役とガートルード(Gertrude)役を兼ね「クローディアス(Claudius)=岩淵(日本未利用土地開発公団副総裁、森雅之)」の代わりに「毒杯」を仰いだ後で(その時は無事)別の場所で発狂する不思議展開になったとも見て取れる。脚本の共同執筆に加わった橋本忍が述べる「(執筆者が多く、統制者がいないが故の)現場の混乱」がこういう部分に現れていると見る向きも。
黒澤明の「たとえ完全には振り切れないにせよ、悪は悪として決然と切り捨てられねば、正義の存続は不可能となる」なる倫理的使命感は、必ずしも作品に対してポジティブに働くとは限りません。それが最初に顕著に現れたのがこの作品だったとも。そして「影武者(1980年)」では全盛期の持ち味だった「伝説の人々(Legends)と庶民の短いながら濃厚な邂逅を描く」部分にまで齟齬が見られる様になるのです。
「仲代達矢の語る日本映画黄金時代」
黒澤明監督映画「影武者(1980年)」に主演して
この話は信玄より泥棒のほうが面白いんですよ。信玄は威風堂々というか静か、泥棒は非常に喜劇的要素を持っていて動き回ることができる。ただ、これを喜劇的要素でやっては困るというのが黒澤さんの注文でした。勝さんはやっぱりあの泥棒の役をね、あの人は喜劇うまいですからね、きっと喜劇的な芝居をやったんだと思います。それが黒澤さんには気に入らなかった。
黒澤さんからすると、「これはあくまでも信玄が主役だ」と。泥棒が目立ってはいけないんです。「あの泥棒までが信玄の人徳によって死んでいく、家臣もみんなも死んでいく話だ」と。だから、泥棒が信玄を食っちゃいけないわけです。それで私も抑え目に泥棒の芝居をしました。
でも、見てる人は、私の泥棒の芝居を観ながら「勝さんのほうが面白かったろうな」って言ってんですよ。でも、「勝さんの『影武者』見てないだろう、あなたたち」って言いたいです。想像だけで存在しないものと比べられてもね。『影武者』を実際に演じたのは、私しかいないんです。
こうした憶測がどれくらい当たってるかどうかはともかく「ハムレット」は復讐者たるべき主人公が「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ(To be, or not to be : that is the question.)」なんて逡巡する芝居であり、それを思わせるパートと「サクサク復讐が進行するパート」が混在してれば全体がちぐはぐに見えるのは致し方ない事かと。
*ちなみにアメリカ人は「To be, or not to be : that is the question.」より、クリストファー・ノーラン監督作品「ダークナイト(The Dark Knight、2008年)」の台詞「英雄として死ぬか、悪に染まって生き延びるかさ(You either die for hero, or live long enough to see yourself become the villain.)」の方が気に入ってる模様。確かにこっちの方が より行動主義的?
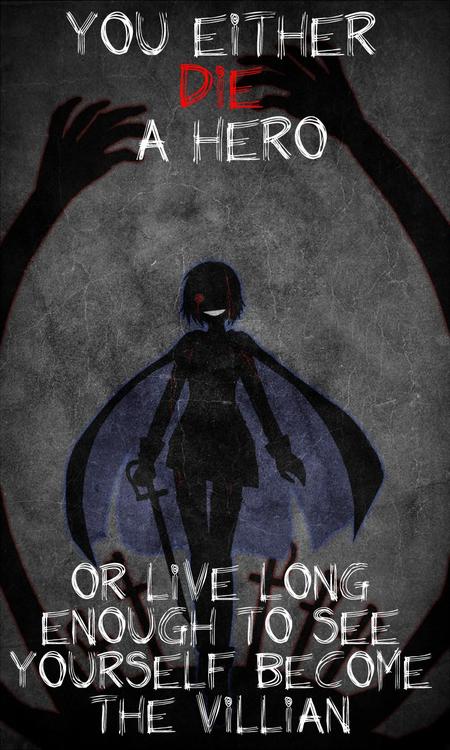
実はこうした実存不安が茫漠と渦巻く最中、「何者かになろう」とガムシャラにあがく人や「(なまじ環境に恵まれてるせいで)何者になるべきかわからない」とウジウジする人が現れる状況というのは、むしろ現代人にとってこそ馴染み深かったりします。
*「野良犬(1949年)」が扱ったアプレゲール(après‐guerre=戦後派)との関係は微妙だが、「太陽の季節(1955年、映画化1956年)」「処刑の部屋(1956年)」「狂った果実(1956年)」といった日活太陽族映画の爆発的流行にその前兆を見る向きもある。青少年による強姦や暴行や不純異性行為満載だったにもかかわらず(映画業界が自主的に設立した)旧映倫はこれを無審査で通し、この事への世論の不満爆発が(第三者を加えた)現在の映画倫理委員会(映倫)が作られるきっかけとなった。ちなみに舞台が「外人に憧れの地」湘南なので「狂った果実」には国外固定ファンが付いている。またこれらの作品における手持ちカメラの滅茶苦茶な使い方がジャン=リュック・ゴダール監督映画「勝手にしやがれ(À bout de souffle/Breathless、1959年)」「気狂いピエロ(Pierrot Le Fou、1965年)」などに影響を与える事になった。
- 科学的マルクス主義イデオロギーやソ連の崩壊を契機として、反戦運動や反原発運動や環境運動に「より確固なもの」を求める様になった左翼陣営
- 米国オルタナ右翼(Alt-Right)の供給源と目される「絶えず冗談を言い続ける事で自分を無理矢理ハイな状態に保っているが、実際には何も信じてないニヒリストの若者達」の台頭。
この分野に対する黒澤明監督の挑戦は敗戦直後のGHQ占領時代まで遡ります。
- 「静かなる決闘(1949年)」…GHQ改定によって超人的な聖人君子に仕立て上げられる以前のシナリオでは、誤って梅毒に感染した藤崎恭二(三船敏郎)が理性の限界を迎えて発狂する結末だったという。その世界観においては元来、自らの耳目で確認し得るものと(その一環としての)快楽しか信じぜず、平然と周囲に性病を撒き散らし続け、自らも自滅に追い込まれる「唯物論的エゴイスト」中田進(植村謙二郎)の恐怖。
- 「いきものの記録(1955年)」…際限を知らぬ「猪突猛進型の家父長」中島喜一(三船敏郎)が原水爆の恐怖に取り憑かれ自滅していく物語。禁治産認定を受けて以降は気の張りを失って急速に老け込み、最後は発狂に追いやられる。
ただし当時の日本人はどうやら(上掲の二人同様)現代人より遥かに「イメージが難しい抽象的恐怖」に危機感を抱く感情が乏しかった様です。
なにしろ焼け跡から生まれたドヤ街において「敵」は、それこそ「ポカポカっとやったら案外簡単に和解に至る相手」から「どちらか一方しか生き残れない生存競争の相手」まで概ね手の届く範囲に居ました。そして、この容易に可視化可能な枠内で「(貴種流離譚を背景とする)伝説の人々(Ledgends)と庶民の一瞬の邂逅」や「掃き溜めに鶴の恋愛沙汰」を一緒くたに描くのが、それまでの黒澤明監督映画の基本的方法論だったのです。
- しかし性病感染に対する恐怖は?
- 原水爆に対する恐怖は?
とりあえず上掲2作では「赤死病の仮面」の如く手の届く範囲内にいる特定の人物に集約される形で描かれました。もしかしたら「映画で映像として提示可能なのはそこまで」なんて諦観ゆえの決断だったかもしれません。
じっと座ってメモばかり取っていても前進しない「机上の学問,机上の空論と言うだろう.映画は,全てが映像として映るんだから,具体的じゃないと困る.統計的にとか,仕組みとしてはこうなりますよと言われてもね,ヨーイスタートって言った時どうなんだってことなんだよ」 #kuroken
— 黒澤明「生きる」言葉 (@AkiraK_Bot) 2017年1月28日
『生きものの記録』の興行の失敗は想像を絶するひどさで、こんな不入りは自分の過去の作品にも例がなく、私にはその現象が信じられなかった。『七人の侍』では日本映画開闢以来の大当たり、それに続く黒澤作品であり、ポスターも黒澤さん自身が斬新でユニークな絵を描き、宣伝も行き届いていた。にもかかわらず、封切りには頭から客が全く来ない。観客はある程度詰め掛けたが、作品が面白くないとか、中身が難し過ぎるとかで減ったのなら分かる。だが頭から客の姿は劇場にはなく、全くの閑古鳥なのだ。まるで底無し沼に滅入り込むような空恐ろしい不入りである。と同時に、映画の観客の本能的な叡智の鋭さに、私は慄然として身震いした。
原爆に被爆した人は気の毒で、こんなにも悲しいという映画なら、作り方次第で当たる可能性もなくはない。だが原爆の恐怖に取り憑かれた男の生涯──人類が保有する最も不条理なもの、その原爆にはいかに対処し、いかに考え、いかに解決をすべきかなどの哲学が、映画を作るお前らにあるはずがないと、観客は頭から作品の正体を見抜き、徹底した白眼視の拒絶反応で一瞥すらしないのだ。
もし誰かライターが先行し第一稿を上げていれば、黒澤さんは一読でこの作品の製作の無意味と徒労を直感したと思う。
原爆の恐怖──それを被爆の惨状なしに描こうとすれば、肝心の恐ろしさを伝える映像がないのだから、台詞とか行動で恐怖を説明するしかなく、展開するドラマはすべて説明でしかあり得ない。
しかし、説明しなきゃ分からないものは、映画で説明しても分からないとするのが黒澤さんの映画信条であり、このままでは理解できないことを一方的に観客へ押しつけることにしかならないのだから、脚本作りの段階で黒澤さんは何の躊いもなく『生きものの記録』を打ち切ったはずである。
当時の日本人は水爆が生んだ怪獣が暴れる「ゴジラ(1954年)」なら面白がり、水爆実験で被爆した鮪が水揚げされると一斉に買い控えています。しかしながら、この種の神経症的恐怖に共感を覚える事はなかった様なのです。
しかしながらGHQ検閲によって内容を滅茶苦茶にされてしまった「静かなる決闘(1949年)」や、主人公の原水爆に対する神経症的恐怖が全く共感を呼ばなかった「いきものの記録(1955年)」と異なり、「悪い奴ほどよく眠る」の場合は、それまでバラバラだった要素が、とある回想シーンを契機に突如として一つに結びつくのでした。
黒澤明監督作品「悪い奴ほどよく眠る(The Bad Sleep Well、1960年)」より
軍需工場の廃墟。西幸一(三船敏郎)と板倉(加藤武)と和田(公団契約課課長補佐、藤原釜足)が防空壕跡から這い出してくる。
板倉「おい、絨毯爆撃が終わって二人でこの壕から這い出してきた時は驚いたな。まったく土地の形相が変わってて一面火の海だ。俺は今でもあの地獄みたいに壮大で胸糞悪い景色を夢に見るぜ」
西幸一「俺もだ」
板倉「しかし早いものだな。高等学校から勤労動員でここに駆り出されたのは、ありゃもう15年んも前の事だ。見ろ、あの煙突、確かお前と果し合いをやったのはあの煙突の下でだぜ。お前は何だか生意気で嫌な野郎だったよ」
西幸一「お前もさ」
板倉「しかし殴り合ってみると」
西幸一「そうでもなかったか?」
板倉「それから、あのリアカー。覚えているか、タイヤのない…」
西幸一「敗戦後なんとか食いつなげたのは、あのリアカーのお陰だったな。」
板倉「はは、和田さん。二人でね、工場で潤滑油に使ってた菜種油をリヤカーに乗せて湘南の別荘地に持って行った途端に売り切れちゃってね。」
西幸一「それを元手に随分と稼いだな。食料品のブローカー、繊維品のブローカー、鉄のブローカー…」
板倉「俺の肉親は室蘭の艦砲射撃で全滅。こいつは私生児。いいコンビだった。もっとも大学に入る入らないじゃ意見が対立したがね。」
西幸一「しかしお前が大学を出ていてくれて助かったよ。お前の戸籍とその履歴のせいで俺は岩渕の娘婿になれたんだからな」
太平洋戦争末期のにアメリカ海軍艦艇が北海道室蘭市一帯に行った艦砲射撃で、485人(うち市民439人)の死傷者を出した。
- 室蘭市は周囲に鉄鉱石の鉱山や炭鉱が存在したほか、良好な港湾を得られたことから第二次世界大戦以前から日本製鐵輪西製鉄所、日本製鋼所室蘭製作所(当時は高射砲等の兵器を製造)の工場が建ち並ぶ重工業の町であった。戦略上重要な都市であり、戦争末期には攻撃目標となった。
- 1945年(昭和20年)7月中旬以降、アメリカ海軍の機動部隊は日本本土に対する大規模な攻撃作戦を行った。7月14日に北海道空襲があり、室蘭も攻撃目標となった。室蘭沖では第65号海防艦と第74号海防艦、貨物船の第1雲洋丸が撃沈され、貨物船4隻が損傷した。
- 翌7月15日には、アメリカ艦隊は第34任務部隊から第34.8.2任務隊(司令官:オスカー・C・バジャー(Oscar C. Badger)少将)を分遣し、室蘭に対して艦砲射撃を加えた(「アメリカ海軍第二次世界大戦公式年表」より)。アイオワ、ミズーリなど戦艦3隻のほか軽巡洋艦2隻、駆逐艦8隻、計13隻の主砲による艦砲射撃が行われ、1,000発以上の砲弾が各工場や住宅地に着弾した。その結果、市内が壊滅状態となる甚大な被害が生じることとなった。日本製鋼の砲身工場は完全に破壊され、その他の工場も3日~10日間に渡って操業停止に追い込まれた。
- 当時の室蘭市には日本陸軍の室蘭防衛隊が置かれて室蘭臨時要塞を建設中であったが、艦砲射撃を防止することはできなかった。室蘭防衛隊隷下の第8独立警備隊は15cmカノン砲などの重砲も有しており、港湾に接近する艦艇への抑止力として期待されていたが艦隊は港口とは向きが異なる南東(登別方面沖)方向からの遠距離射撃を行っており無力であった。
*「第8独立警備隊」…陸軍第31警備隊の第32警備大隊主力と、津軽要塞重砲兵連隊の第3中隊より編成された。指揮官は大山柏少佐。現在、室蘭八幡宮など市内数カ所には慰霊碑が建立されており、艦砲射撃が行われた日には多くの関係者が慰霊に訪れている。
短時間で八百数十発の砲弾が室蘭の空から雨の様に降った。敵の姿が一切見えない、海の向こう側から断崖を超えての砲撃だった。市民は見えない爆撃の音に防空壕の中で恐怖に震えるしかなかった。
砲弾は3発一緒に飛んでくる。砲弾が爆発すると外側の鉄が炸裂し、それ自体が凶器として飛んでくる。つまり道路などが被弾すると直径10数メートル、深さ5メートルほどの擂り鉢状の穴が開いてしまう。そこに人間がいたりすると炸裂した鉄で人間の体がスライスされた状態になる。艦砲射撃後、電線にヒラヒラとリボンの様に見えるのは、人間の皮膚であったり、肉であったり、腸であったりした。
起伏の激しい土地柄、室蘭の防空壕は裏穴に横穴を掘って設置するケースが多かった。しかし艦砲射撃では爆風により岩肌が崩れてしまい、入り口が塞がれ生き埋めにされた人が沢山いた。生き埋めにされて死んだ人の顔はみんな白くしぼんだ感じになり、まるで別人の様で見分けがつかなかった。
そして火災があちこちに広がったのである。
さらに続いて西幸一(三船敏郎)が妻の岩淵佳子(香川京子)に内心を打ち明けます。
- 実は(政略結婚の為に自分の母を捨てた)生前の父とは疎遠で憎悪しか抱いていなかった。
- その父が官僚の尻尾切りで自殺に追い込まれたと知り、何もせずにはいられなくなったが、いまだに何を為すべきかについて思い悩んでいる。
おそらく隠し通した第三の理由があります。それは「焼け跡から始めたビジネスが、焼け跡消失によって面白くなくなった」事。つまり背景にあるのは当時の様な日々の緊張感が失われる一方、商売の場にどんどん大企業が進出してきて将来が真っ暗になってしまった焦燥感。
要するに彼らはある意味「腹が減って山から下りてきた野生の熊」だったのです。「親の仇」とか「国民に代わって巨悪を討つ」といった大義名分はあくまで後付けで思いついたものに過ぎず、だからこそ口先ばかりで薄っぺらく、しかも揺らぎまくる。でも当人にとってはそれで十分。何しろ実際に望んでいるのは「世間をアッと言わせた後、刑務所に収監されて高みの見物と洒落込む」事だけだった訳ですから。
「センチメンタルな弱虫だから、強そうな顔をして意地を張っているだけだ。弱みを見せたり、人に負けるのが嫌だから、無茶なほど頑張るだけだ」・・・父のような人間が実は泣き虫なのを似た者父娘の私はよく分かる。 #kuroken
— 黒澤明「生きる」言葉 (@AkiraK_Bot) 2015年6月18日
*こうした「具体的で自分の手に負える範囲への視野狭窄」、実は過去作品にも共通して見受けられる。
- 「目に見えない」梅毒の脅威を最後まで信じず、全てを終始青年医師(三船敏郎)の作り話として弾劾し抜く(原作の芝居ではそれで逆に青年医師側を発狂に追いやる)「静かなる決闘(1949年)」の「闇屋の親分(植村謙二郎)」。
- 「癌で死ぬ前に汚水溜まりを埋め立てて公園を立てる」計画の実現に固執した「生きる(1952年)」の「市民課課長(志村喬)」。
- 原水爆に殺される前にブラジルに移住する」計画の実現に固執した「いきものの記録(1955年)」の「猪突猛進型の家父長(三船敏郎)」。
ある意味戦後復興を支え、高度成長を準備したのはこうした「具体的で自分の手に負える範囲への視野狭窄」に支えられた人々であり、それまで怪しげなブローカーとして暗躍してきた「悪い奴ほどよく眠る」の西幸一や板倉も同じグループに属するが、次第に経済の中心は大企業が寡占する建設業界や重工業へと推移していく。彼らは単なる「腹が減って山から下りてきた野生のクマ熊」ではなく「手負いの熊」だったのである。ただし「市民課課長(志村喬)」や「猪突猛進型の家父長」同様、自らはそれを自覚していない。それゆえに「従来通りの方法論で押し通せば全て上手くいく」という信念を一切揺らがせず、明るく楽観的なままそれぞれ、それなりの形で破綻を迎えるという次第。
- 「生きる(1952年)」における市民課課長(志村喬)…しつこく付きまとい過ぎて、元部下の小田切とよ(小田切みき)に嫌われる。彼女は葬式の席にも現れない。
- 「いきものの記録(1955年)」における「猪突猛進型の家父長(三船敏郎)」…家族の起こした裁判で禁治産者認定を受けて以降急速に衰退し、最後は発狂に至る。
- 「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」における「義賊二人組(三船敏郎と加藤武)」…復讐を思い立った側(三船敏郎)が「焼け跡時代の様な非情性」を震えなくなっており、それが躓きとなって自らの命も失う。
こうまで類型として揃うと、没シナリオ「侍の1日」で描こうとした「徳川時代初期の武士」もまた、「武功次第で立身出世が思いのままの(それゆえに切腹の作法も見事な)野獣めいた戦国時代の強面武者」と「官僚化によって家畜に変貌した(切腹の作法もなってない)江戸時代中期以降の算盤武士」の狭間にのみ現れた同類型のロマン主義的英雄が必然的に迎える悲劇だったのかもしれない。

*同時期の横溝正史に目を向けてみよう。終戦直後から続けてきた「"民主主義の使者"金田一耕助が田舎の因習を解消する」路線で執筆された「悪魔の手毬唄(「宝石」連載1957年〜1959年)」の当時の評判は空前の不評。「悪い奴ほどよく眠る」封切り当時には、この頃日本全国に急速に新築されつつあった団地の住民関係を主題に選んだ「白と黒(「日刊スポーツ」連載1960年〜1961年、1974年)」を手掛けていた。内容は日本初のクレージー・サイコ・レズ物。しかし何もかもが真新しい(それが故に人間関係も従来の伝統とは一線を架した独特のものとなる)団地という舞台と、既存作品通りのアナクロな姿で歩き回る金田一耕助のミスマッチは誰の目にも明らかで、ほどなく横溝正史は断筆に追いやられる。江戸川乱歩に至ってはもっと潔く「影男(1955年)」で大人向け作品を打ち止めとし、以降は断筆となる1960年末まで「少年探偵団」シリーズに専念。
*そういえば、その「悪魔の手毬唄」における最重要人物は「トーキー映画の日本上陸によって職を失い都落ちを余儀なくされたサイレント映画の弁士」なのである。まさしく「伝説の人々(Ledgends)」の一員。まさに貴種流離譚の典型例で、この男が本能の赴くまま果てしなく子種を撒き散らし続けた結果が、後世における陰惨な連続殺人事件の伏線となっていく。作者の横溝正史自身、この「時代に切り捨てられた男」に自分を重ねていたとしても不思議ではない。ちなみに当時ブレークスルーとなったトーキー映画は「Morocco(1930年)」らしく、同時代において既に坂口安吾が「日本における美男子のマスターピースがゲーリー・クーパーになってしまった」と嘆いているし、「悪魔の手毬唄」でも「本当の意味での事件の真犯人は(サイレント映画の弁士を都落ちに追い込んだ)モロッコ」という説が開陳されている。しかしそれは高度成長期に差し掛かり、前に進む事しか考えなくなった当時の日本の読者が読みたい作品ではなかったという次第。きちんとした形でこうした取り組みが再評価されるのは1970年代におけるリヴァイヴァル・ブーム以降となる。
冒頭でこの作品における「物語展開の薄っぺらさ」について述べました。それが同時にこの作品を「時代に置き去りにされ、途方にくれながらも生き急ぐのを止められなかった男達の挽歌」たらしめているとは、つまりこういう事だったのです。
- それにしてもこの作品における西幸一(三船敏郎)は既存作品にも増して格好良い。ロイド眼鏡のせいでまるでスーパーマンに変身する前の新聞記者クラーク・ケントの様で、やる事なす事全て自信に満ち、不可能な事などない様に見える。
- サイドキック(Sidekick、親友兼相棒)の板倉(加藤武)も抜け目なく、二人は自分達の計画が失敗に終わる可能性など露程ほども考えていない。そう、まさに「いきものの記録(1955年)」において南米行きを計画する「猪突猛進型の家父長」中島喜一(三船敏郎)が禁治産者認定を受けるまでそうだった様に。
- その後「いきものの記録(1955年)」の中島喜一は、偶然再会した家庭裁判所の調停員に向かって「あんたらがワシを寄ってたかって殺したんじゃ。恐怖に実際の行動で対応する手段を奪う事によってな」と言い放つ。相棒を失った板倉(加藤武)も「これでいいのか!!」と叫ぶが、「たとえ完全には振り切れないにせよ、悪は悪として決然と切り捨てられねば、正義の存続は不可能となる」と信じる黒澤明監督は、その倫理的使命感から「天国と地獄(1963年)」のラストシーンの如く冷徹に両者の間にシャッターを落とし、後の判断は観客に委ねたのだった。
アメリカ映画では「最後の賞金稼ぎ」トム・ホーンの最後を描いたスティーブ・マックイーン製作総指揮・主演映画「トム・ホーン(Tom Horn、1980年)」あたりを連想すると良いでしょう。
- 撮影中に悪性の中皮腫と診断されたマックイーンの生涯最後の西部劇。西部開拓時代も終焉に差し掛かると、トム・ホーンの様な「賞金稼ぎ=単なる牛泥棒でも一切の躊躇なく脊髄反射的に射殺する殺人マシーン」はむしろ社会秩序維持の邪魔となり、とうとう冤罪で逮捕されて処刑されてしまう。
- 牢獄の中でトム・ホーンはこう叫ぶ。「銃を返せ!! 馬を返せ!! あれがないと俺じゃない…いや、あれこそが俺だったんだ」。またこうも叫ぶ。「俺をこんなふうにしちまったのも、西部だろ!?」。
- その「荒くれ男代表」が映画冒頭では(鉄道網の整備と冷蔵技術の発展が西部にもたらした)蟹に舌鼓を打ち「美味ぇ、この地上にはこんなにも美味ぇ代物があったのか。ずっとこいつを食べて暮らしてぇ」と絶賛するのである(台詞の内容はウロ覚え)。それこそがまさに自らの身上の破滅の序曲とも知らずに…
とどのつまりアメリカにおいてすら、産業革命本格導入期(いわゆる「金鍍金時代(Gilded Age、1865年〜1893年)」)における「時代に切り捨てられてきた男達の悲劇」に再評価の光が当たったのは1970年代以降、1960年代後半に始まるニューシネマ(New Hollywood)運動の影響を受けて問題提起型西部劇がやたら増えて以降だったのです。
黒人西部劇
日本の場合は1960年代末から1980年代にかけて長期的な「怪奇/オカルト/超能力/UFO/超古代史/サイキック・ブーム」があり、その過程で江戸川乱歩、夢野久作、横溝正史らノスタルジーを誘う異色作家が再評価されました。
*かくして「天国と地獄(1963年)」の竹内銀次郎(山崎努)が「八つ墓村 (1977年)」の多治見要蔵(山崎努)となってパワーアップして蘇る…
しかし黒澤明監督映画のこうした「復興期におけるロマン主義的英雄達への挽歌」的側面はむしろ積極的に忘れ去られていったのです。どうしてそんな展開に?
*「ロマン主義的英雄達への挽歌」…一見それっぽくない「生きる(1952年)」の市民課課長(志村喬)だがミイラに例えられたり「僕は君の若さを取り込みたい」とか吸血鬼めいた台詞を吐く。以外とユニバーサル・モンスター系?
メアリ・シェリー作品におけるロマン主義文学の廃墟的光景:男性英雄像の破壊、及び英雄に代わる女性像
- 「生きものの記録(1955年)」の記録的な興行失敗の後、黒澤明監督は脚本家を集め「蜘蛛巣城(1957年)」「どん底(1957年)」「隠し砦の三悪人(1958年)」「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」の脚本をまとめて執筆。「羅生門(1950年)」「生きる(1952年)」「七人の侍(1954年)」「生きものの記録(1955年)」の共同脚本を手掛けてきた橋本忍は、これに参加した後に一旦黒澤組から離れる(「どどすかでん(1970年)」で一時復帰)。
*要するに「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」は世間でそう言われ、黒澤明監督自身もしばしばそう認めた様な「松本清張ブームの便乗作品」ではなかったのである。逆を言えば、あえて「社会派ミステリー・ブーム」なるパラダイムシフト以前の(一歩間違えば時代遅れの)古い脚本で新作を撮り続けたという事でもある。
- 1957年、松本清張ブーム開始。橋本忍は黒澤明監督映画「醜聞 -スキャンダル-(1950年)」「白痴(1951年)」で助監督を務め、黒澤から「日本一の助監督」と評価された野村芳太郎と組んでの「張込み(1958年)」「ゼロの焦点(1961年)」「砂の器(1974年)」、山田洋次監督と組んでの「霧の旗(1965年)」といった松本清張原作映画を次々と成功に導く。
*当時における脚本家としての橋本忍のスタンスを鑑みると「悪い奴ほどよく眠る」への評価が辛いのは仕方がない。自ら社会派ミステリー・ブームの渦中に飛び込み、(当人的には没シナリオ「侍の1日(1952年)」の延長線上にあった)小林正樹監督映画「切腹(1962年)」を皮切りに今井正監督の「仇討(1964年)」、岡本喜八監督の「侍(1965年)」「大菩薩峠(1966年)」、小林正樹監督の「上意討ち 拝領妻始末(1967年)」といった異色時代劇の脚本を手掛ける過程で黒澤明監督とは全く異なるリアリズム哲学に到達した人物だったのだから。そして1969年には東宝の目玉映画「風林火山(稲垣浩監督)」と大映の目玉映画「人斬り(五社英雄監督)」双方の脚本を手掛ける快挙すら成し遂げている。
- 1960年、安保闘争。この頃「"変装名人の元義賊"多羅尾伴内シリーズ(1946年〜1960年)」や「"民主主義の使者"金田一耕助シリーズ(1947年〜1956年)」の顔だった片岡千恵蔵の主役からの引退、PTAからの圧力などが重なって「2丁拳銃ヒーロー」が映画からもTV番組からも少年向け月刊誌からも駆逐される。手塚治虫「鉄腕アトム(1951年〜1968年)」もこの年までは「多羅尾伴内あるいは少年探偵団フォーマット」中心だったが、安保デモに直面すると「僕自身が1950年代に言い広めてきた様な明るく屈託のない未来世界は、このままだと訪れない」と考える様になり、以降様々な物語スタイルを試行錯誤する様になっていく。
*多羅尾伴内あるいは少年探偵団フォーマット…ヒゲおやじ探偵が単身で事件の真相を突き止めるまでが全体の9割。アトムはクライマックスにのみ召喚され、数コマ無双しただけで飛び去ってしまう。ウルトラマンの大源流?
- そして1960年代に入ると(スパイ謀略物やピカレスク小説も含むハードボイルド系小説に牽引される形で)未曾有の翻訳出版ブームが巻き起こる。
それでは、こうした「(致死性の)焼け跡的センチメンタリズム」から決別した黒澤明監督は以降、どちらに向かったのでしょうか?
- あくまで憶測だが「生きものの記録(1955年)」の後でまとめて執筆した「蜘蛛巣城(1957年)」「どん底(1957年)」「隠し砦の三悪人(1958年)」「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」の四脚本のうち、黒澤明監督的に最も手応えが大きかったのは「隠し砦の三悪人(1958年)」だったのではなかろうか。
*この時点で既に「焼け跡的センチメンタリズム」の残滓が見受けられるシナリオは「悪い奴ほどよく眠る」一本のみ。もしかしたら、それさえも最初から本質的に含まれていた訳ではなく「復讐アクション部」と「ハムレット見立て部」の間の不整合を埋めるべく最後に追加された添え物だったかも。
- これが突破口なら、アーネスト・サトウが日本に伝授した英国外交官の極意「噛まないなら吠えるな。 噛みちぎれないなら噛むな」に徹っするのみ。そうすれば作品の構造も自然と必要最小限にまとまる訳である。実際「用心棒(1961年)」「椿三十郎(1962年)」「天国と地獄(1963年)」「赤ひげ(1965年)」といった1960年代作品ではこのフォーマットが遵守されている。
*アーネスト・サトウ(Sir Ernest Mason Satow、1843年〜1929年)…幕末期から明治期にかけて活躍した英国人外交官。
当時の制作状況については、こんな証言もあります。
『用心棒』がスタートした時、東宝の製作の総帥である、森岩雄氏が脚本を読み、既に撮影が始まっているのに中止を命じた。
「この脚本はよくない、黒澤君の撮るべきものものじゃない。今、やめると会社の損失は大きい。しかし、黒澤君の名誉には代えられない。即刻中止すべきである」
そしてその森さんの意図を受け使者に立ったのが、プロデューサーの田中友幸氏だった。友幸さんがそれを黒澤さんに伝えると、黒澤さんは顔を真っ赤にして激怒し、いかなることがあっても撮影はやめないと、断固として撮影を強行し、映画を仕上げ、その『用心棒』が思いがけない大当たりを取ったのである。
「用心棒(1961年)」試写会
私は観客席に座り込んだまま手を叩き続けた。
脚本を書いた菊島さんと、黒澤さん、そして絞りの強い絵の、溢れる力感で作品を押し切った監督の黒澤さんのために──自分では不可能視し、見切りをつけていた「いきなり決定稿」が、意外や意外、まるで私をアザ笑うように、ものの見事に華麗な大輪の花を咲かせ大成功をしたのである。すべては、黒澤さんと、菊島さん、二人のお手柄だが──私には今井浜での、『隠し砦の三悪人』のある一日が鮮烈な記憶で蘇ってくる。
舞子園の八畳では机を部屋の中央に据え、私は床の間に対して座り、右に黒澤さん、正面には床柱を背に菊島さん、左が小國旦那の並びで、原稿は常に右回り、私の書いたものは黒澤さん、菊島さん、小國旦那に回って、私に戻り、他の人の書いたものは、左の小國旦那から私の手に渡り、同一シーン競作の中身の確認が行われる。
ある日、自分の原稿が黒澤さんから菊島さんに回った時、菊島さんは次の小國旦那には回さず、首を傾げていたが、顔を上げ、私にいう。
「橋本君、こんなふうに突っ込んでしまうから、動かなくなる。この手前でこうすれば捌ける」
といって小國旦那には回さず、自分で私の原稿を直し始めたが、直し終わると、正面から直接私に渡した。私は受け取って見て自分の目を疑い驚嘆した。何と言う見事な捌き方なのだろう。菊島さんの芝居の捌きには定評があるが、まさに絶妙である。私がその原稿に魅入られたようになっていると、隣の黒澤さんが手を伸ばし、自分にも見せろという。黒澤さんは私から菊島さんの直した原稿を手に取って見ると、途端に顔が引き攣り息を詰めてしまう。
黒澤さんと私の脚本は先行直進型、菊島さんと小國旦那は追い込み型、私の欠点や長所は黒澤さんの欠点であり長所でもあるのだ。自分が見過ごした原稿──いや、必ずしもそれがうまくいっているとは思わないが、自分にはどう直すのか、直感での直す力、捌く技術がない。だが菊島さんはスラスラとそれをやってのける。その菊島さんの前捌きの妙には、黒澤さんも感嘆のあまり声も出ない。
かつては『野良犬(1949年)』などの先行例もあり、黒澤さんも菊島さんの腕は知っている。だが黒澤組を離れ……有為転変のこの世界で数多い辛酸をなめてきた菊島隆三は、もうかつての菊島隆三ではないのだ。
前捌きの上手さとは? なにがどのように上手いのか、専門用語過ぎるので、こういう形で表現すれば分かりやすいとも思う。
例えば東映映画の仁俠物で、兄弟分を殺られた高倉健が、死を賭けた最後の殴り込みで、敵地に乗り込んで行く。だがそれを途中で、藤(現・富司)純子が「待って!」と町並みから飛び出し取りすがる。
「お願い!……行かないで!」
私や黒澤さんはここで立ち往生だ。高倉健の動きがつかない。ここで棒立ちのままじゃどうにもならないし、さりとて、藤純子を突き飛ばし駆け出す訳にもいかず、ニッチもサッチもいかなくなりドラマが止まってしまう。
ところが東映の作品を書くライターは手慣れたものである。藤純子は高倉健に縋りつき離さず、泣き続けるが、暫くして「でもどんなに止めても、あなたは行くのだわ」といって涙を拭って離れ、「じゃ、行ってよ……行って!」
「すまねぇ!」
実に見事に捌けるのだ。
捌きとはこうした芝居に類するもので、私や黒澤さんは相撲でいえば四つ相撲、相手力士を力で土俵際まで持って行くが、相手に粘られるとそこで動けなくなる。
だが菊島さんはこれ以上押せない時には、押すと見せて押さず、逆に引いて相手の形を崩し、自分の得意技に引き込み仕留めてしまう。 前捌きとはこうした引き技が多く、いずれにしても効果的だが、多用するとあざとく、わざとらしさが目立つ。また引き技には変わり身が付いてまわるから、多用すれば相撲ではケレン相撲……芝居でいえば、ゴマカシとかはったり芝居、いわゆる俗受け芝居になる。
話に真実性を追求するとか、人間の真実に迫るものの場合は、こうした手法は一発で作品を御破算にしてしまう。だが話の出だしから、これは作り話、全くの虚構であることを観客に承知させておけば、意外なまでにこれが手練手管として使えるのではなかろうか。
黒澤さんのこれまでの映画は、オリジナルであれ、原作のあるもの、または翻訳物であれ、それらは作り話であっても、根底では真実を追い、リアルを感じさせるものが圧倒的だっただけに、こうした手法が一切使えなかったのだ。 だがリアル感を全く必要としない素材、ド頭から客には面白い作り話の虚構であることを十分に心得させたもの、徹底した娯楽物にすれば、こうした手法が自由自在に使えるのだ。
綿密な打ち合わせはしなくても、テーマとかストーリーを突き詰めなくても、人物の彫りや、話の構成にそれほど気を使わず──いきなり取っ掛かっても、こうした脚本なら、「いきなり決定稿」で作れるのだ。菊島さんの前捌きの鮮やかさと変わり身の早さから、作り方次第では、新しい手練手管の娯楽物の脚本が出来るのではなかろうか。あとは自分の演出力で、今までにはなかった面白い娯楽作品が作れるかどうか。(いや、黒澤さんとしても、そう簡単に踏み切ったのではない)『生きものの記録』以来、他の者には一切漏らさないが、焦燥と懊悩の孤独の日々が続いたのではなかろうか。
『生きものの記録』の失敗は、ストーリーが未知数で不確定なオリジナルものだったので、次ははっきりした明確な形のある原作物をと、ゴーリキの『どん底』や、シェイクスピアの『マクベス』を取り上げたが、これらも形だけは整うものの、作品から発酵する豊潤な映画独自の面白さがない。
仕方がないので、次は題材を一変し、昔書いた活劇物『敵中横断三百里』に似た時代活劇篇、『隠し砦の三悪人』である。しかし、これも活劇の要素はアクション、絵の流れのスピードでもあるが、重荷となる黄金運搬を主題としたため、スピード感覚に欠け活劇の快感にはほど遠い。
最後はライター五人まで総動員する『悪い奴ほどよく眠る』で勝負手に出たが、これも時流には乗り切れず中途半端に終わってしまった。
もう手がない。後がないのだ。作品は上昇気流には乗らず、どれもが下降線を辿り続けており、次の作品にもし失敗すれば、栄光も名声もすべてを失いかねない。
剣ヶ峰に立った以上は、のるか反るかだ。引き技も変わり身も恐れず、思い切って、今までにはない娯楽物をやってみるしか……よしッ、やる、やってみる! それが成功、大成功をしたのである。
ここで橋本忍の「社会学的リアルを依代(登場人物や物語)に宿らせる」作劇方法と、シナリオライターに「構図」の提供を求める黒澤明の作劇方法の優劣を争っても仕方ありません。
とにかく映画文法的には展開のクライマックスにおいてカタルシスさえ生み出せれば良く、そこから逆算して「銃が火薬で銃弾を撃ち出すのに必要な密閉状態」や「アクセルを踏み込めば加速し、ブレーキを踏めば減速して止まり、ハンドルを左右に回せばその通り曲がる操縦系統」といった物理構造が、それが必要とされるタイミングまでに用意されていればそれでよいのです。
- まるで交響曲の様に、終始「強力な構図」に従って全体が進行していくタイプのシナリオの成功例が「羅生門(1950年)」「生きる(1952年)」「七人の侍(1954年)」「蜘蛛巣城(1957年)」「隠し砦の三悪人(1958年)」。
- ただし交響曲方式は、最初に決定した「構図」に観客をしっかり「正しい(製作者側が意図する)方向に」楽しく迷わせず導く力が備わってないと脱落者を出してしまう。「生きものの記録(1955年)」や「悪い奴ほどよく眠る(1960年)」についての(特に公開当時の)不評はこれに由来する。
*もし制作されていたら没シナリオ「侍の1日(1952年)」もまた後者に分類されていた可能性が高い。というのも以降の時代劇では「(井原西鶴や近松門左衛門もそう描いている様に)武家社会は最初から矛盾だらけで、仇討ちや切腹はこれを糊塗する為に貧乏籤を引いた人間に人身御供的に強制された悲劇」なる見解が広まり定着していったからだった。とどのつまりそもそも「二食か三食か」問題以前に「(井原西鶴や近松門左衛門らの証言が残る)元禄時代以前には本来あるべき美しい武家社会が存在していた」なる前提が崩壊してしまう訳で、それを勘案するとこのシナリオは没となって本当に良かったとしか言い様がない。
- その一方、全体がほぼリアクションの連鎖のみで構成されているのが「野良犬(1949年)」「用心棒(1961年)」「椿三十郎(1962年)」「天国と地獄(1963年)」となる。おそらく「菊島さんの前捌きの妙」だけが理由ではない。そもそもダシール・ハメットが開拓したハードボイルド文学の基本構造そのものがこうなのである。
*そして観客からすれば、正しい方向に楽しく迷わせず導く「構図」さえしっかりしてたら、それがいかなる理論で成立していようが割とどうでもいい。
ところで国際SNS上の関心空間における時代劇ファンは、こうした話にあまり関心を持たない一方で「黒澤明映画の三船敏郎はエロいが、仲代達矢はエロくない」「エロい仲代達矢が見たければ「大菩薩峠( The Sword of Doom、1966年、監督岡本喜八・脚本橋本忍)」を見るべし」 みたいな情報交換に熱心。
そこへ乱入してくる安部公房原作・脚本映画「他人の顔(1966年)」の仲代達矢が一番エロい派。畜生、なんて眼をしてやがる…
むしろどうしてこういう結果になるかが気になります。
- それぞれの作劇法の違いと何か関係が?
- 焼け跡的センチメンタリズムや、それと表裏一体の関係にある倫理的使命感の有無も何か関係してくる?
どうやらそういう研究の方が注目を集められそう?