昨年年初に「今の自分には数理の掌握が決定的に欠落している」という認識に到達してから早や一年と2か月。とりあえず到達したのが以下の認識となります。
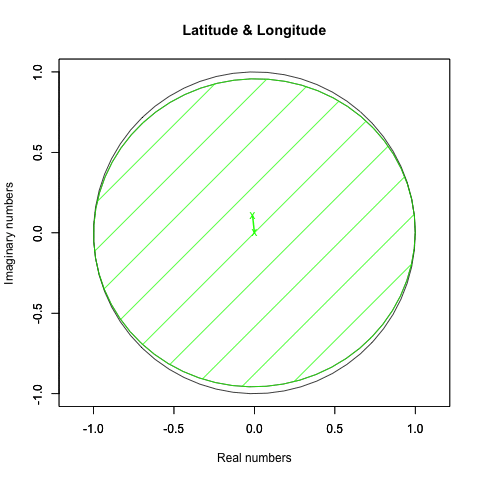
- 事実とは何か。近世数学の出発点はまさにそれであった。不幸にも我々はそれを誤差だらけの観測値を、それぞれが相応の基準値で正確な目盛りが振られ、かつ相応の基準値で相互の相関関係も確かめられた評価軸を積み重ねた認識空間に配置し続ける不完全な形においてしか「世界そのもの」の全体像を俯瞰し得ない。
- そしてかかる悲観的認識こそが、この様な人間社会の無様な有様に相対する「我々に認識可能な範囲外を跋扈する絶対他者」のみが「あらゆる完璧な事実の源泉たる世界そのもの」を掌握しているとする形而上学(希Μεταφυσική、羅Metaphysica、英Metaphysics、仏métaphysique、独Metaphysik))的認識の出発点となっできた。「(実証主義科学がどれだけ否定しようとも)万人が従うべき普遍的真理は実在する(そしてお前等と違って私にだけはかかる良心の声がちゃんと届いており、それに従って行動しているからお前らと違って絶対に間違いを犯さない)」と主張する社会自由主義者(social liberalist)の最後の砦…
-
それではこの人間社会が甘んじている不完全な認識状態内からは、この限界を超越しようとする動きなど全く起こせないのであろうか? 意外にもそれが必ずしもそうでなく、まさにその様な歴史的展開こそが人間社会の面白さだったりする訳である。
ユージン・ウィグナー『自然科学における数学の理不尽なまでの有効性(1959年)』
例えば以下の様に(相関係数の計算に似た振る舞いを見せる)オイラーの公式cos(θ)+sin(θ)iの一般型Cos(θ)+Cos(θ-π/NoC)iと分かると、数理によって掌握可能な範囲が大幅に広がったりする。そしてその図示に際しては、もっぱら大数学者ガウス(Johann Carl Friedrich Gauß/Carolus Fridericus Gauss, 1777年~1855年)の発見した1の冪根の巡回性に頼る。第一の点は、〈数学の概念は、まったく予想外のさまざまな文脈のなかに登場してくる〉ということ。
The first point is that mathematical concepts turn up in entirely unexpected connections.しかも、予想もしなかった文脈に、予想もしなかったほどぴったりと当てはまって、正確に現象を記述してくれることが多いのだ。
Moreover, they often permit an unexpectedly close and accurate description of the phenomena in these connections.第二の点は、予想外の文脈に現れるということと、そしてまた、数学がこれほど役立つ理由を私たちが理解していないことのせいで〈数学の概念を駆使して、なにか一つの理論が定式化できたとしても、それが唯一の適切な理論なのかどうかがわからない〉ということ。
Secondly, just because of this circumstance, and because we do not understand the reasons of their usefulness, we cannot know whether a theory formulated in terms of mathematical concepts is uniquely appropriate.〔この二つの論点をさらに言い直すと〕第一の点は〈数学は自然科学のなかで、ほとんど神秘的なまでに、途方もなく役立っているのに、そのことには何の合理的説明もない〉ということ。
The first point is that the enormous usefulness of mathematics in the natural sciences is something bordering on the mysterious and that there is no rational explanation for it.第二の点は〈数学の概念の、まさにこの奇怪な有用性のせいで、物理学の理論の一意性が疑わしく思えてしまう〉ということ。
Second, it is just this uncanny usefulness of mathematical concepts that raises the question of the uniqueness of our physical theories.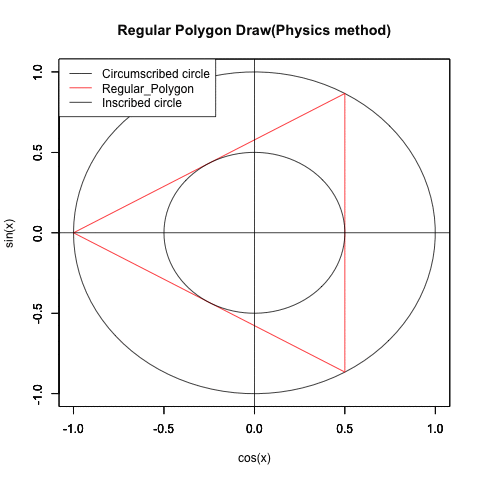

- そして現代社会においては、こうして「数理との境界線」がきっちり引けてからが哲学(Philosophy)の本来の出番となる筈なのである。
私の考える「現代社会において哲学(Philosophy)が担うべき主要責務」は、例えば以下の様なタイプの暴走の抑え込みである。同一個人内に重なって現れる事もあるし、また大なり小なり誰でも備える特性とした関係上、対処範囲の適切な設定が重要となる。
- 「(どんな厳密な検証を経てもアルゴリズムの誤謬や視野外のパラメーターのせいで計算が間違ってる可能性がもたらす実存不安から逃れ得ない)科学実証主義」について「だから信用ならない」と貶める不可知論者。概ね自分なりの「代案」を備えているか、あるいは変化か現状維持を嫌っている。どんなに数が増えてサイレント・マジョリティ化けるしても、蜂起にまで至るシステムは備えない事が多い。
党争を生き延びて勝利を収める事しか念頭にない政治的人間(フランス革命の展開を詳細に吟味したシュテファン・ツヴァイクによる規定)。究極的には不可知論者と同様の論法に加え、超越的権力を動員したり集団蜂起して政治的圧力を掛け事態を恣意的に自分にとって都合の良い形で進め様とする可能性を内包。党争に勝利する為なら何でも犠牲にするタイプだけでなく、自らの保身や立身出世のみを一心不乱に追及するタイプも含む。
「暴力論(Réflexions sur la violence, 1908年)」のソレルが規定した宗教的人間。見掛け上の特性こそ政治的人間とほぼ同じながら「(たとえ方便でも)絶対に他人に譲歩しない超越的な内的価値観」を備えており(スンニ派政権にとってのシーア派、帝政ロシアにとっての分離派、フランス革命政府にとっての王党派の様に、政治的人間側が迂闊に内ゲバの延長線上で刺激して)反旗を翻す機会を与えたら厄介な抵抗者に変貌する。一応究極的には「自分と同一と認識可能な他者しか認めない」形で絶対他者の完全視野外化を狙ってくる可能性を備えるが、そういう規模に達するまでの難易度が高い。
それぞれ究極的には何らかの形で事象の地平線(我々が認識によって到達可能な範囲外)を跋扈する絶対他者を完全視野外に追い出そうとする態度やダブルスタンダードなどを含む可能性を内包するが、これを顕現化させるのが精神的老化や未成熟、逆にそれを抑制するのが精神的成熟といえる。
先例を求めるとしたら、とりあえずギリシャ哲学における「中庸の精神」、ヘレニズム時代のエピキュリズム(快楽主義)やスコラ派といった「修身哲学」や仏教哲学における「二河白道の境地」辺りだろうか。
アリストテレスは「ニコマコス倫理学」のなかで、知識を「Σοφια ソフィア(智)」と「φρόνησις フロネシス(実践倫理)」の2種類とし両者を明確に区別し、人間の行為や感情における超過と不足を調整するメソテース(ギリシア語: μεσοτης、 Mesotes、中間状態を保つ徳)をその代表格とした。英語ではGolden Mean(又はHappy Mean)といい、日本語訳に際しては中庸という儒教用語が当てられた。
- とどのつまりアリストテレスのそれは勇敢(蛮勇と臆病)、節制(快楽と苦痛)、貴富(放埒と論色)といった両極端の状態を避けて初めて顕現する美質を引き出す実践知という事になる。
*逆をいえば決して天然の形で自然に存在する事がない。だからこの思考様式は決っして自然主義の形態を選べない。欧州貴族主義の根底にあり続けてきた功利主義。ジョン・スチュワート・ミルはこれから出発して古典的自由主義に到達。- 一方、儒教における伝統的中心概念の一つたる「中庸」も「過不足なく偏りのない状態を保つ」徳を「中庸の徳たるや、それ至れるかな」と称揚されている点では似通ってる。ただしこちらの方は「民に少なくなって久しい(聖人による善導が不可欠)」「修得者が少ない高度な概念(選民主義や神秘主義への逃避)」「聖人でも難しい半面、学問をしなくても発揮出来る」「非凡でなければ実践不可能だが、現れる結果は平凡でなければならぬ」といった禅問答が延々と続くばかり。朱子に到っては「中庸章句」の中で「(どうせ実践は不可能なのだから、実践可能な)誠の方が重要」と開き直っている。
*要するに(礼儀作法の正しさや、宮仕えを効率よく乗り切るノウハウの共有が主目的で普遍倫理や実践知の追求に無関心の)伝統的儒教や(大学「格物致知」から導出した「居敬窮理」の理念を掲げる主知主義的な)朱子学との相性が最悪なのである。仏教だと最初期の入門編の「四門出遊」説話当たりでもう「死も、病も、老衰も、怖がっても、怖がらなな過ぎても負け」みたいな話になるが、それを真っ先に「迷妄」と否定したから如何なるゴールにも辿り着けなくなってしまったとも。ここを履き違えると必ずといってよいほどグノーシス主義的思考様式、すなわち「この世界は全て似非真実に立脚する仮象の世界」「真実に到達した人間だけがその矛盾から脱却出来る」と考える選民主義に到達し「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマに向けての暴走が始まってしまう。一切の実利を捨てまで党争における勝利のみが追求される氏族戦争(Clan War)の世界の再来…
*カール・マルクスが到達した人間解放論、すなわち「我々が自由意思や個性と信じ込んでいるものは、実際には社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない(本物の自由意思や個性が獲得したければ認識範囲内の全てに抗え)」の危うさはまさにここにある。
ヘレニズム時代(紀元前334年~紀元前30年)にはプトレマイオス朝エジプトのアレクサンドリアにあった研究機関ムセイオンを中心とする自然科学の発展(エラトステネス・アリスタルコス・アルキメデス・エウクレイデス(ユークリッド)などを輩出)、ストア派やエピクロス派の様な自制心を重んじる修身哲学、ガンダーラ仏像や華厳経の様な東西融合文化が生まれた。
ちなみに今日ではギリシャ芸術代表と目されているミロのヴィーナス、ラオコーン、サモトラケのニケといった写実的でありながら人間美や精神性を持った大理石彫刻が生み出されたのもこの時代。それは(様々な形での文化衝突を引き起こしながらオリエント全域に伝わった)ギリシャ人の「神の照覧を妨げない為に全裸で運動する習慣」と不可分に語れない。とどのつまり、様するに自然も人間も(特定の宗教観やイデオロギーのフィルターを通してではなく)直接ありのままを観察対象とする事が重視された時代だったといえよう。
17世紀前半のフランスは帯剣貴族だけでなく(最終的に文壇をほぼ独占するに至る)法服貴族等の新興階層まで理性と意志の高揚と力を強調し, 困難に立ち向かう英雄を理想視する英雄的ストイシスム (Stocisme heroque) が横溢していた。これはセネカ (Lucius Annaeus Seneca, 紀元前1年頃~紀元後65年) の思想に代表されるような本来のストイシスムが形を変えて復興したものであり、国家の困難に対して無関心であることを諌め, 危機に対しても勇敢に立ち向かうことを促す栄光と高邁な精神に溢れたものだった。
ただしフロンドの乱(Fronde, 1648年~1653年)の失敗と国王へのさらなる権力集中が進行した同世紀後半には「如何なる英雄的行動も、その動機まで踏み込んで検証すれば情念や欲望に操られる惨めな存在が浮かび上がってくるのみ」「人間の誇る理性だって想像力や情念・欲望・自己愛にに引きずられ, その判断を無意識の内に歪められている」と考えるジャンセニスム的ペシミズムや、その逆に洗練された快楽追求を至上の目的とするエピキュリスム的風潮が勢いを増していく。
こうした「リベルタン(Libertin、善悪の彼岸を超えて刹那的快楽に生き様とする放蕩貴族)的苦悩(ただしあくまでロココ時代的軽薄さと表裏一体)」からアベ・プレヴォー「マノン・レスコー(Manon Lescaut、1731年)」や様々なロマン主義作品が派生する事に。
フランス語で初めて執筆された哲学書ルネ・ デカルト(1595年〜1650年)「方法序説(Le Discours de la Methode、1637年)」
第三の原則は、常に運命をねじふせようとするより自分自身を抑えるようにして、世界の秩序を変えるより自分の欲望を変えるようにしよう、そして一般論として、われわれの持つ力の中には、自分の思考力以外には絶対的なものはなにもないのだ、という説得に自分を慣らそうということだった。つまりはなにか自分の外のことに対して人事をつくしても、それが失敗するかは絶対にわからないのだ。そしてこの一つの原理によって、将来、自分の手に入らないものを望むようなことを防ぐのに十分に思えた。こうしれば、不満を抱かずにいられる。
というのも、われわれの意志は当然のこととして、理解力にもとづき、何らかの形で入手可能だと思えるものだけを望むから、もし自分の外のものがすべて自分の力の及ばないものだと考えるなら、生まれながらに持っていてしかるべきだと思えるそういう外部のものが、こちらの落ち度ではない原因で奪われたときにも、残念がったりしないのは明らかだろう。それは、シナやメキシコ王国を所有していないからといってわれわれが残念がったりしないのと同じことだ。あるいは、ダイヤのように衰えない身体を望んだり、あるいは空飛ぶ鳥の翼を望んだりしないように、病気のときにも健康を望んだり、幽閉時にも自由を望んだりしないのも、あたりまえのことだろう。
でも、この方法であらゆる対象を見るように精神を慣らすには、非常に長期の規律と、頻繁な瞑想の繰り返しが必要だったことは告白しておこう。そして、かつての哲学者たちが、運命の影響を逃れて、困窮と貧困の中でも神々すらうらやむような幸福を楽しめた秘密は、主にここにあるのだろうと思う。つまり自然によって自分の力に与えられた限界のことばかりをしつこく考えることで、かれらは自由になるのが、自分の思考だけであることを完全に納得しきったのだ。だからこの結論だけで、他の物体への欲望をまるでもてあそばずにすむようになったのだろう。そして思考するうちに、それが絶対的な影響を獲得したので、他のどんな人よりも自分がもっと裕福で、強力で、自由で幸福だと自負するだけの根拠を得るにいたったのだろう。他の人々は、天与や運命がどんなに微笑もうと、この哲学を持たなければ、自分たちの欲望すべてを実現するなんてとうてい不可能だからだ。
浄土教における極楽往生を願う信心の比喩。ニ河喩(にがひ)とも。善導が浄土教の信心を喩えたとされる。主に掛け軸に絵を描いて説法を行った。
絵では上段に阿弥陀仏と観音菩薩・勢至菩薩のニ菩薩が描かれ、中段から下には真っ直ぐの細く白い線が引かれている。 白い線の右側には水の河が逆巻き、左側には火の河が燃え盛っている様子が描かれている。 下段にはこちらの岸に立つ人物とそれを追いかける盗賊、獣の群れが描かれている。
下段の岸は現世、上段の岸は浄土のこと。 右の河は貪りや執着の心(欲に流されると表すことから水の河)を表し、左の河は怒りや憎しみ(憎しみは燃え上がると表すことから火の河)をそれぞれ表す。 盗賊や獣の群れも同じく欲を表す。
東岸からは釈迦の「逝け」という声がし、西岸からは阿弥陀仏の「来たれ」という声がする。 この喚び声に応じて人物は白い道をとおり西岸に辿りつき、悟りの世界である極楽へ往生を果たすというもの。
この図式に立脚して初めて仏教がどうしてずっと終始「自らの置かれた状況の絶対客観視」を重視してきたかが理解可能となる。*とはいえ日本仏教もその歴史上かかる原義を忘れ「(氏族戦争の延長線上に芽生えた)党争史上主義」に振り回されてきた経緯が存在する。
当然それぞれの時代に設定された倫理尺度の中には、既に寿命が切れているものも混ざっています。とはいえ、そういう部分自体は最新の統計技法や機械学習を用いて尺度再抽出でも行って再調整すれば良いだけの話。現代哲学者の為すべき責務は他にあります。例えばバイアス問題、すなわち「機械学習だけでは人間やその社会の悪い部分まで複製されるのみ」問題をどう克服するか? そこには上掲の問題を解決する重要なヒントが含まれているのでは?
考えてみれば、まず私自身がここでいう「それまでの認識可能範囲が脱却可能であるj事」のエビデンスになろうとしてるとも。さて今年末にはかかる現場の延長線上において、どんな私が何を語っているのでしょうか?
