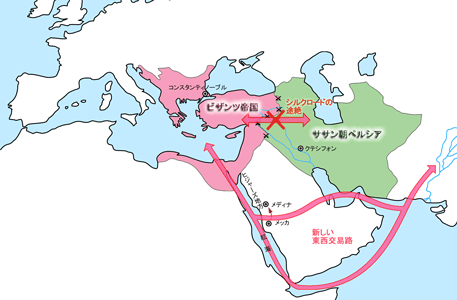「近代的ナショナリズム(Nationarism)」は、概ね現在では特定の国家や民族に紐付けされた政治的感情として理解されています。ところが前近代においては、そもそも「国家(Nation)」や「民族(Ethnos)」といった概念自体が存在していませんでした。
①そうした「近代ナショナリズム(Modern Nationalism)」以前の時代における「原ナショナリズム(Pre-modern Nationarism)」は文化(Culture)の一種としてのみ存在していた。その起源自体はかなり古く、またその一部が帝国や王国や絶対王政を粉飾する「装飾」として利用される事もないではなかったのである。
*ベネディクト・アンダーソンいうところの「公定ナショナリズム」や「言語ナショナリズム」の大源流。おそらく最源流まで遡ると「ヘブライ教徒の神殿宗教からの脱却と啓典の民への移行」「ヘブライ教徒のユダヤ教徒(ヘブライ語話者)とキリスト教徒(ギリシャ語話者)への分裂」なんて話にまで行き当たる。
*もう一つの大源流が「氏族戦争(Clan War)時代における、古くから伝わる伝承を援用しての名家やその領地支配の正当化」であった。ただし「公定ナショナリズム」の源流という意味では以下に述べる様な「イスラム圏におけるスルタンの統治正当化理論」の方が本命に該当するかもしれない。
- 「アケメネス朝ペルシャ(紀元前550年〜紀元前330年)の再来」を称したサーサーン朝ペルシャ(226年〜651年)。一方、ビザンチン(東ローマ)帝国において冷遇されていたユダヤ人や、退去を命じられたアカデミアを快く迎え入れて経済的・文化的に繁栄。逆にビザンチン(東ローマ)帝国はギリシャ化しつつギリシャ文明に対してアンビバレントな態度をとり続ける。
- 「ペルシャ文明とヘレニズム文化の継承者」を称し「知恵の館(Beyt al-Hikuma)」を建設したアッバース朝(750年〜1517年)。ここからムタズィラ神学が生じ(歴代スルタンからイスラム法学者への対抗馬として重んじられた)アラビア哲学へと発展。

*このアラビア哲学がイベリア半島経由で欧州中世に伝わりスコラ学の大源流となる。ただし当時の欧州人はそれをあらなる大源流たる新プラトン主義やアリストテレス哲学の継承と考えていたらしい。 - イベリア半島のレコンキスタ運動の途上、1085年に奪還したトレドでアラビア語文献翻訳派(Toledo School of Translators、11世紀〜12世紀)が栄えたカスティーリャ王国(1035年〜1715年)。
- ピレネー山脈からアイルランドに至る広大な領土を所有し、最盛期にはフランス王国の半分、イングランド王国全土、アイルランド全土(名目上)を支配下に置いたプランタジネット家(アンジュー家)のアンジュー帝国(英Angevin Empire、仏Empire Plantagenêt、12世紀〜13世紀)。イングランドとフランスの王室の度重なる政略結婚の産物で、トルバドゥール(Troubadour:男性型)/トロバイリッツ(Trobairitz:男性型)と呼ばれたイスラム文化圏起源の南仏吟遊詩人がウェールズやブルターニュに伝わるアーサー王伝説を支配地域全体に広める。
*フランス国王フィリップ2世(在位1180年〜1223年)の時代にアンジュー、ノルマンディーといったヨーロッパ大陸領の大半を喪失。この敗北によってプランタジネット家が大陸に保有する領土がガスコーニュのみとなった事が百年戦争(1337年/1339年〜1453年)勃発の遠因の一つとなる。
- ヴァロワ家4代(14世紀後半〜15世紀中旬)の時期に宮廷で華やかな騎士文化が栄えたブルゴーニュ公国(843年〜1477年)。詳細はヨハン・ホイジンガ「中世の秋(1919年)」などに詳しい。
*フランスの歴史家いわく「マホメットなくしてシャルルマーニュ大帝なし」。イスラム教団の侵攻に対抗すべく「鎧で踏ん張る重騎士の密集突撃」という戦術が開発され、ノルマン人と北フランス諸侯が中東方面に進出。一方ポーランド諸侯に招聘されたチュートン騎士団や神聖ローマ帝国諸侯は東欧への進出を目指す。かくして「十字軍時代もしくは大開拓時代(11世紀〜13世紀)」と呼ばれる騎士達が主導する時代が現出する事に。
②こうした「原ナショナリズム(Pre-modern Nationalism)」が「近代ナショナリズム(Modern Nationalism)」に発展する契機となった出来事。それはルネサンス期におけるカトリックの普遍性喪失や出版資本主義(Print Capitalism)の発達だった。
*出版資本主義(Print Capitalism)…有名なレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロの時代のイタリア・ルネサンスにおいては、まだまだ芸術家や著述家がローマ教会や僭主(Signore)やイタリア傭兵隊長(Condottiere)パトロネェージュに全面依存するしかなかった。発想の飛躍が起こるのは(オスマン帝国よりレパント交易から締め出され、新たな財源開拓が必要となった)ヴェネツィアが「携帯可能な小型本」「観光客向けの豪勢なオペラ」「キャンバスに描かれ土産として売られる絵画」といった商品を次々と開発していく1480年以降。やがてこのシステムはオランダ経由でフランスのパリやリヨンなどにも伝わる。
③そして17世紀後半に入ると(オスマン帝国やオランダの没落開始を尻目に)フランス絶対王政が台頭。「原ナショナリズム(Pre-modern Nationalism)」の「近代ナショナリズム(Modern Nationalism)」への適用が本格的に始まる。
*大航海時代(15世紀中旬〜17世紀中旬)到来によって欧州経済の中心が(オスマン帝国やイタリア諸国と縁深い)地中海沿岸から(スペイン、ポルトガル、オランダ、フランス、英国、北欧諸国などがひしめく)大西洋沿岸に推移した影響も大きいとも。
- ラテン語の普遍性を継承する形で「言語ナショナリズム」が、イタリア・ルネサンス料理への対抗心から「宮廷料理ナショナリズム」が、ローマ教会への対抗心から「ガリカニスム( Gallicanisme、フランス教会中心主義)が芽生え、絶対王政を装飾する文化として発展。
- この時期にはシャルル・ペローの「ルイ大王の世紀(Le siècle de Louis le Grand(1687)」発表を契機とする古今論争、世界初の散文童話週「寓意のある昔話、またはコント集~がちょうおばさんの話(Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités : Contes de ma mère l'Oye、1697年)」刊行なども行なわれている。
④同時期英国ではジェントリー階層の形成が進行。まだまだ貴族中心だったとはいえ、フランスやイギリスでは臣民意識の形成が始まったといえる。
- なまじ「原ナショナリズム(Pre-Modern Nationalism)」に共通項が多い分だけ、イギリスにおける「近代ナショナリズム(Modern Nationalism)」はフランスのそれと対照的な展開を辿る形となった。
ウィリアム征服王やジョージⅠは英語を話せなかったにもかかわらず歴代の王のあいだに陳列されている。イギリスの王はことごとく外国人である。
*そもそもアンジュー帝国時代のプランタジネット朝の首都は事実上ノルマンディーに置かれていたし「(国政に関心のない)外国人王」の支配下にあった事が英国で議会政治が発達した主要因なのだった。まさしく「亭主元気で留守がいい」の世界。ブリテン島とアルモリカ半島の間のブリトン人の絆は、9世紀以降の聖人伝で見られるように、意識としては継続されたが、領主レベルでは、政治的駆け引きのなかで敵対的となることもあった。
ギヨーム公のヘイスティングズの戦いでは、レンヌ伯に敵対的な北東部の領主たちが数多く参戦し、その褒賞としてイングランド各地に領地を与えられた。征服の100年後でも、イングランド王国全体の約5000の騎士領の5%(250の領地)がブルターニュ出身の騎士たちのものだった。ちなみに、ギヨーム一族はブリテン島の半分の領地を、そのほかのノルマン出身貴族が1/4を取得し、以前の支配者であるサクソン人はわずか5%を保持するに過ぎなかったという。このことは、島嶼系のアーサー王伝説が、フランスその他大陸ヨーロッパに流布する背景として重要である。
ノルマンディー公ギヨームに敵対して敗走したレンヌ伯コナン二世に続くブルターニュ公は、ケルネ(コルヌアイユ)伯のアラン四世である。ブレイス語地域の伯とはいえ、フランス語宮廷文化の浸透の速度は速く、彼がブレイス語を操ることができた最後の領主といわれている。彼はギヨーム征服王の娘と結婚し、王との接近を図るが、かえって従属的立場が強まる。その孫、コナン四世の時代になると、さらに政治的緊張度が深まる。英仏両国にまたがる、いわゆるアンジュー帝国が形成されるためである。アーサー王伝説の形成と流布については、この帝国がいわばその基地をなしていたと考えられるので、この帝国の成立経緯についても触れておこう。
ギヨーム征服王の息子、イングランド王ヘンリ1世(アンリ)の娘マティルダ(マティルデ)と、アンジュー伯ジョフロワ4世の子が、ヘンリー1世として、1154年、プランタジネット朝を興す。ヘンリー二世は、父からはアンジュー伯領を、母からはイングランドとノルマンディー公領を継承し、さらに1152年にはアキテーヌ公国女性相続人アリエノールと結婚して、フランス南西部アキテーヌ公領をも手中に収めた。現在の英仏両国の相当部分を領地とする、広大なアンジュー帝国はこうして誕生したのである。
もちろんこれで実効的な支配は期待できない。王は有力諸侯のひしめく大陸の領土を巡回するため、フランスに滞在することが多く、ノルマンディーのルーアンが実質的な首都だったようだ。これはノルマン・コンクウェスト以来、ノルマン朝歴代イングランド王に共通することであり、したがって英語を操る能力はなく、もっぱらノルマン・フランス語を用いていたことになる。
ヘンリー2世はまた、1165年、ワリア(ウェールズ)の支配を復活させ、1171年、ヒベルニア(アイルランド)を攻略する。ブルターニュも例外ではなく、1166年、コナン四世の公位を譲位させ、1169年、ブルターニュの自身の支配権をフランス王ルイ7世に認めさせた。
ヘンリー2世の子リチャード1世(リシャール)は、1189年から1192年の第三回十字軍など、生涯の大半を戦いのなかで過ごし、その勇猛さから獅子心王と称され、中世騎士道精神を体現する王と後代絶賛された。幼少時代はフランス南西部アキテーヌ地方で育ち、王位についてからのイングランド滞在は通算してもわずか6ヵ月で、彼もまた英語がほとんど話せなかった。
プランタジネット家によるブルターニュの支配権は、ヘンリー2世の孫、アーサー1世(アルチュール)まで続く。アーサー1世はイングランド王リチャード1世の事実上の世継ぎだったが、その地位はヘンリー2世の末子ジョン(欠地王)に奪われ、さらにはわずか16歳でジョン支持派に暗殺される。この短命のブルターニュ公アーサーは象徴的である。中世騎士道精神を体現する叔父リチャード1世から嘱望され、その名もアーサーである。そしてまさにこの時代が、アーサー王伝説の全ヨーロッパ的に流布される時代なのである。
- 百年戦争(1337年/1339年〜1453年)から薔薇戦争(1455年〜1485年/1487年)にかけての時代を扱ったシェークスピア史劇はテューダー朝(1485年〜1603年)に媚を売った改竄の嵐だった。
*むしろアレキサンドル・デュマはこれに感動して「模倣」を決意。7月王政(1830年〜1848年)のオルレアン王統を擁護する歴史観に支えられた「ダルタニアン物語(1844年〜1855年)」を発表。
-
所謂「妖精伝承」一つとっても英仏のそれは複雑に入り混ざっている。
-
ここでさらにややこしさを深めるのが(ヘレニズム時代のストア派哲学や、ローマ時代の哲人貴族セネカを源流とする)英仏貴族の(存続を最優先課題として掲げる)功利主義を経てフランスの啓蒙学者コンドルセや英国の自由主義哲学者ジョン・スチュワート・ミルの「数理のみを絶対忠誠対象として奉じる臣民意識(古典的自由主義)」が成立する流れ。
*カール・マンハイムはこうした発想が「政治的平等と経済的平等のみを追求する進歩主義的思考様式」の源流となった事を認めつつ(さらなる平等概念の全人格化を要求する)市民意識に一線を架す。
こうした歴史展開を踏まえ、改めてベネディクト・アンダーソンの「近代的ナショナリズム(Modern Nationalism)発展史」に目を向けてみましょう。
ナショナリズムの発生と歴史的変化は「宗教共同体」と「王国」という二つの共同体と、それを構成する「聖なる言語」や「メシヤ的時間」という観念を掘り崩し「国民共同体」へと変貌させていく過程として描かれます。
- 時間の了解形式における「メシヤ的時間」から「均質で空虚な時間」への変化…これが「私有財産的言語」と結合して国民という観念が生まれ、ブルジョワジーと知識人を苗床として広まっていく。
- 「聖なる言語」の特権性が「出版語」によって相対化・領土化されていく変化…人文主義者の古典発掘と欧州の全地球的規模への拡大を背景として出版資本主義(Print Capitalism)と俗語ナショナリズムが政治利用される様になっていく。
フランス革命によって意識的に達成すべき「モデル」が形成されると、欧州各地で興隆した民衆ナショナリズムに対抗すべく「共同体が国民的に想像されるにしたがって、その周辺においやられるか、そこから排除されるかの脅威に直面した支配集団が、予防措置として採用する戦略」として公定ナショナリズムが登場。
具体的な政策としては、国家統制化の初等義務教育、国家の組織する宣伝活動、国史の編纂などですが、それらを通じて「王朝と国民が一体であること」が際限なく肯定されました。要するに強制的な「国民化」政策が行われたのです。
これまで見てきた様に、この理論を構成する各要素が現実の歴史展開から採択されたものである事実は動きません。しかし本当にこの順番通り展開したのでしょうか?
*実は近代的ナショナリズム(Modern Nationalism)の登場を二月/三月革命(1848年〜1849年)以降と見積もる向きも多い。というのも欧州中心部におけるオルレアン王政の打倒(フランス)や「出版の自由」「自由主義内閣」「陪審裁判制等」を要求として掲げる自由主義者と封建的賦課の廃棄を迫る農民の蜂起(ドイツ)に連動する形で東欧やイタリアなどではハプスブルグ君主国を相手取った民族紛争が展開したからである。そうした動揺はさらに隣接するオスマン帝国にまで伝わった。
意味不明だった1848年のウィーン革命
- 軍国時代の大日本帝国に「(明治時代への回帰を願う)公定ナショナリズム」らしきものを見出すのは比較的容易である。ただし「(その登場を喚起した筈の反体制的な)民衆ナショナリズム」は見出せず、かつどこまで「公定」と見做すかが実に難しい。
*ちなみに「大日本帝国は紛れもなく(帝政ロシアと同様)終始公定ナショナリズム国家だった」という立場に立つ人は1930年代後半に始まる「皇民化運動」を引き合いに出す事が多い様である。また在日外国人に対する同化政策の一切に「ファシズム再来」のレッテルを貼ろうとする傾向が見て取れる。
皇民化教育 - Wikipedia
日本統治期台湾における国語=日本語の位置付け*確かにまぁ「日鮮同祖説」や「日ユ同祖説」は「公定ナショナリズム」そのもの。
日鮮同祖論 - Wikipedia
日ユ同祖論 - Wikipedia - アンダーソンは「フランス革命の実態がどういうものだったにせよ、それをモデルに意識的に達成すべきビジョンが形成された点が重要」とする。ところが実は現在では「そのビジョンが共和主義を達成した」イメージそのものもまた空想の産物に過ぎなかったと考えられる様になった。
*とはいえ、アンダーソンはあくまで「実際に何があったかなど関係ない。後世の人々に何があったと想像されるかだけなのだ」というスタンスなので「だから何?」という話にしかならない。
*実際に第二帝政を廃止に追い込んだのは普仏戦争(1870年〜1871年)に勝利して皇帝ナポレオン三世を捕虜としたドイツ帝国だった。その結果成立したのも「共和制」とは名ばかりの「権力に到達したブルジョワジー(bougeoisie au pouvoir)」ないしは「二百家」と呼ばれる政治的エリート階層による寡占支配体制だった。彼らはフランス国軍によるパリ・コミューン殲滅も、ドイツ帝国軍のパリ入場も大歓迎だったという。さらにはナチス・ドイツ軍のパリ到着も喜んで迎えたとされる。フランスの歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッドがしばしば口にする「親独派」には、間違いなく彼らに対する含みがある。
*最大の皮肉はエドマンド・バーク「フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France、1790年)」に描かれたフランス革命も同時代証言としてはありえないほど戯画化された内容だった事。現実直視より情熱と行動主義を重視するロマン主義全盛期だったせいか革命側陣営側も反革命側陣営側も「事実をそのまま後世に伝える事」に何の魅力も感じなかったらしいのである。
*ちなみに辛亥革命(1911年)を中国で経験したフランス軍将校は、現地中国人から「フランスには1人のナポレオンしか現れなかったが、中国はより偉大なので同時に10人のナポレオンが現れる」と誇らしげに自慢されたという。実際その予言は実現し中国は群雄割拠時代に突入していく。またアンダーソンは「ブラジルにおけるクレオール・ナショナリズムの不在」を説くが、皮肉にも南米諸国のうち最も安定した発展を遂げたのは(ポルトガル王室の臣民として出発した)そのブラジルだったりする。
- 19世紀前半のドイツにおける(普遍史観や王権神授説の代替物としての)ヘーゲル哲学の発展は(個人的研究成果の発表に過ぎなかったにも関わらず)極めて「公定ナショナリズム」的だった。とはいえ民衆はあくまで「(軍人や官僚に絶対服従を誓う一方で個人的享楽を追求する)ビーダーマイヤー的庶民」レベルに留まったし、プロイセン王国を筆頭に多くの諸国が(ナショナリズム台頭を含む)あらゆる自由主義的運動を厳しく取り締まり続けたのである。何故なら領邦国家の乱立する当時の地方分権状態への反逆に他ならなかったからであった。
*同様のジレンマはハプスブルグ君主国全体に及んでおり、次第に各領邦国家の国境線を超えた言語ナショナリズムへと発展していく。
*ちなみにアンダーソン自身はこう述べている。
ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism、1983年)』「民族=国民」というヨーロッパ的国民国家概念はどうやってつくられたか……人文主義者による古典古代の発掘と、地理上の拡大は、人間の多様性を知らしめたのだった。インカ、アステカ、インド、中国、日本などの文明はエデンからはじまる(均質な)時間には収まらなかった。
ヨーロッパ体制を批判するのに、古典古代を持ち出すまでもなく、異文化の地を援用すればよかったのだ。「神に選ばれた文明」という世界観は崩壊した。18世紀後半から本格的な比較言語学がはじまる。古代は複数あり、ギリシアより古い文明はいくらでもあるのだ。ホブズボーム曰く「進化をその中核とする最初の科学」が成立した。
いかなる言語も平等なのだから、いまやその言語を賛美するのは所有者だけとなった。一言語一国民、辞書の大増殖、文法学者や言語学者、文学者の黄金時代。書物の集積である大学、学校は、ナショナリズム戦士の養成所となった。
古代ギリシアとは既に別の民族であるギリシア人は、普及していたギリシア古典に触れ、トルコからの独立を果たそうと決意した。近代ギリシアはトルコのくびきから解放されねばならない。
ルーマニア語の文法、辞書出版により、キリル文字からローマ字へと移行し、ルーマニアは正教会圏から分離した。ロシア口語は正教会スラヴ語に勝利した。チェコ語もかつてはボヘミア地方の農民の言語にすぎなかった。要するに全ヨーロッパが言語によって分裂した。
オーストリア=ハンガリーのヨーゼフ二世はドイツ語を国家語に選んだが、これはドイツ語話者と他言語、とくにハンガリー語話者とのあいだに軋轢を生んだ。同じことがオスマン朝のトルコ語でおこった。
国籍のなかったハノーヴァー家やロマノフ家やホーエンツォレルン家は自分たちの国民的帰属を発見していく。科学と資本と懐疑の時代に、王権神授説はもう使えなかったのだ。だが、国民を代表するということは責任がかかることでもあった。
ロシアは全土のロシア化を行ったが、これは公定ナショナリズムと呼ばれる。だが、これは非スラヴ住民の抵抗をひきおこした。ロシア革命のもっとも激烈な支持者はグルジアなどの非ロシア地域の住民だった。
*「(モンゴル帝国から継承した)アジアの専制君主」的側面も備えるロシア・ナショナリズムにはまた独特の側面が備わっている。聖イシュトヴァーンは外国人を尊重し、こう言った「言語と習慣において統一された国はもろくて弱い……」、彼はのちハンガリー初代の王としてまつりあげられる。
ハンガリー・ナショナリズムは作家によって始められた。そしてドイツ語の公用語制定に反発して広まった。マジャール貴族のナショナリズムとは別に、民衆的ハンガリー・ナショナリズムもまた成長した。1848年、コシュートの革命において、ハンガリー人即マジャール語の原則が決められ、農奴制、免税特権が廃止された。ユダヤ人や、非マジャールキリスト教徒などもハンガリー人として容認された。ところが翌年ツァーの軍隊によって鎮圧され、今度はウィーンの指導のもとに社会政策が実施され、革命家は追放された。
幸運にも、1866年普墺戦争でのプロシアにたいする敗北により、オーストリアはハンガリーとの二重帝国を設立せざるを得なくなった。その後のハンガリーの政策は、ロシアのロシア化、プロイセンのデーン人、ポーランド人にたいする政策、封建イングランドのアイルランドにたいする政策に酷似するものだった。
*「欧州暗黒時代におけるマジャール人の侵攻(ザクセン辺境候によるその撃退が神聖ローマ帝国の起源となる)」に端を発するハンガリー・ナショナリズムもまた結構ややこしい。
現代ハンガリー。ナショナリズム試論*いずれにせよ現在では多くの研究者が「ドイツ・ナショナリズムもロシア・ナショナリズムもフランス・ナショナリズムに刺激される形で生まれた」と考える様になった。有名なトルストイ「戦争と平和」において貴族達が宮廷で交わす言葉は全てフランス語である。確かにフランス語は、かつてラテン語が果たした「国際公用語」としての役割を全うしたのだった。
*多民族国家たるオーストリア=ハンガリー二重帝国における言語政策はもっと複雑な内容だったが、アンダーソンの言説にそれに対する配慮は見られない。ある意味「多民族国家はナショナリズムが発生した単位で分割されるのが正しい」とスタンスに立脚しているせいであろう。ちなみにハプスブルグ家の皇帝を19世紀一番悩ませたのはイタリア人、オスマン帝国のスルタンを悩ませたのはギリシャ人やアルメニア人であったとされる。そして最近では逆に「ハプスブルグ君主国やオスマン帝国からの解放が全ての諸民族に明るい未来を与えた訳ではない(むしろ不幸になった国の方が多い)」現実も頻繁に指摘される様になっている。
*その一方では「イギリスがハプスブルグ君主国化していく」という指摘も。
*そもそも実際にドイツ帝国を成立に向かわせたのは(プロイセン宰相ビスマルクが扇動した)シュレースヴィヒ=ホルシュタイン紛争(1848年〜1864年、対デンマーク)、普墺戦争(1866年、対オーストリア)、エムス電報事件(1870年、対フランス)といった「(公定ナショナリズムとは次元の異なる)近代的ナショナリズム(Modern Nationalism)」高揚であった。とはいえ実はその後の文化闘争(Kulturkampf、1871年〜1878年)においては、これに便乗する形で「ポーランド故地へのドイツ同化政策」が履行されている。国内のデーン人に対しても同様の動きがあった様であり(ナチス時代における「北欧諸族・アーリア民族同祖説」の源流とも)それ自体は明らかに公定ナショナリズムの一種。「領民の臣民化」を急ぐドイツに「多民族国家として栄える」選択肢など存在しなかったのであった。
第一次大戦後のドイツ喪失領
プロシア参謀本部~モルトケの功罪 - 普墺戦争/「身内」の戦争
ここで改めてベネディクト・アンダーソンが「想像の共同体(1983年)」冒頭に掲げた「ナショナリズムを巡る3個の謎」に目を向けてみましょう。
- 「平均的な歴史家から見れば、国民の存在というものは近代国家が生み出した当然の現象の帰結と見えるのに、ナショナリストの目には国民がひどく古いものと見えるらしい。」…これはおそらく「近代ナショナリズム(Modern Nationarism)」が、あたかも「原ナショナリズム(Pre-modern Nationalism)」の当然の帰結の様に振る舞う戦略を選ぶ傾向が強い事に起因する。
「臣民/市民意識」の特徴をあえて列記するなら下記となる。
*この時には(存続を最優先課題とする)貴族の功利主義同様、先例主義に従おうという姿勢、可能な限り「自分もまた伝統主義に導かれているだけに過ぎない」と見せかけようとする欺瞞工作が見受けられるのが普通なので、その事へも留意が必要。- 個人単位では「臣民意識(Liberty=奉仕の代表に特権開放を求める心)」と「市民意識(Freedom=放置を求める心)」が表裏一体を為す構成となっている。
*例えばビーダーマイヤー期(Biedermeier、1815年〜1848年)期のドイツ庶民の心には「軍人や官僚の指図には盲従する臣民意識」と「可能な限り個人的享楽を追求しようとする市民意識」が共存していた。ゲッベルスは両者が意識の奥で「個人的享楽の追求を目溢ししてもらえるのが奉仕の対価」といった関係を形成してるのを的確に見抜いていた。
- そのうち「臣民意識」の欲求は(フランス人アイデンティティがイタリアやイギリスやドイツのそれとの対比に由来する様に)相対化から出発する事が多く、しかもそれ自体はとりわけ個性的でない事が多い。また権利には義務も付帯するので「ノブレス・オブリージュ(noblesse oblige)」的な規範も生じる。
*例えば「胡椒は貴族の香辛料l、生姜や辛子は庶民の香辛料」「レモンティは貴族の飲み物、ミルクティは庶民の飲み物」「ざる蕎麦は目上の食べ物、盛り蕎麦は目下の食べ物」みたいな垂直系の峻別(この感情からマイカーやマイホームを渇望してる人も結構いる?)。それから「関東風対関西風 」みたいな水平系の峻別。
- 一方「市民意識」はその純粋性を保つ為に「例外」を排除しようとするが、行き過ぎると「究極の自由は先生の徹底によってのみ達成される」ジレンマに陥る。
*そこで追求されているのはもはや「足る事を知るFreedom欲求」ではなく「限度を失ったLiberty」なのである。「欲望の追求の放置」自体は自由の証だが、「欲望充足そのものの目的化」は「欲望の奴隷」に他ならず、自ら自由を放棄するに等しい。
*実際「純化」を追求するあまり「フランス絶対王政下の臣民意識」はユグノー教徒を、「ジャコバン独裁体制下の市民意識」はヴァンデやリヨンやトゥーロンといった王党派本拠地を「異物」として完全排斥せずにはいられなかった。こういう局面では判断に冗長性を持たせる工夫が不可欠。
「計算癖(独Rechenhaftigkeit、英Calculating Spiritの)が全人格化した世界」だけが唯一の選択肢として残った世界においては人類全体が「採用したアルゴリズムが間違ってるリスク」と「重要なパラメーターを見逃してるリスク」を背負う。そしてリスク分散の為、あえて多様性を許容。こういう世界で暮らしていくには、おそらく以下の様な(多様性容認を補助してくれる)哲学のどれかの習得が必須となってくる。
- 「龍樹の二諦説(大乗仏教)」…カント的なタイプ(認識可能領域とその外側)と遠藤周作「沈黙」的なタイプ(各人の打算によって成立する実社会と内面的良心の世界)の2モード。後者はしばしば日本人の独創とされるけど(マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(1904年〜1905年)」でジャンセニスムと並べて叩いてた)ルター神学っぽくもあり、「沈黙」を映画化したマーティン・スコセッシ監督も完全に理解してた。思うより国際的に理解が得られやすい思考様式?
- 「ガザーリーの流出論(スンニ派古典思想)」…中身は実質上「新プラトン主義も加味したアリストテレス哲学」なので、その内容が欧州にも相応に広まる。ちなみにシーア派思想の方がより深く古代ギリシャ思想と融合してるらしい。
イスラームにおける理性(‘aql)と伝承(naql)―スンニー派とシーア派 | 同志社大学 一神教学際研究センター CISMOR
東京大学東洋文化研究所
- 「プラグマティズム哲学」…認識可能領域とその外側で構成されるカント哲学を「神は必ず問題解決に必要な事は全て認識可能領域内に置いておいてくださる」という強い信念で補強した内容。その一方で「問題解決の為なら神でも使う」と宣言。
- 「新アリストテレス主義」…「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」という考え方。科学実証主義の直接の起源。イタリア・ルネサンス期にパドヴァ大学やボローニャ大学の解剖学部で生じたが、大元は(デカルトの合理主義哲学と同様に)スコラ学で、そのさらなる大元はイベリア半島在住のアラビア哲学者アヴェロエス(イブン・ルシュド、1126年〜1198年)。
- 「功利主義」…元来、欧米貴族の間で継承されてきたそれは「最大効用を追求する」攻撃的な内容というより「(一族の後世まで視野に入れた)生存を最優先課題と考える」保守的な内容らしい。ストア派の禁欲主義とエピクロス派の快楽主義は表裏一体の関係にあって、欧州貴族に規範として崇められたローマ貴族のセネカ自身はストア派哲学者だった。そしてその延長線上に(コンドルセの啓蒙主義を継承した)ジョン・スチュアート・ミルの古典的自由主義が成立。
*まさしく「計算癖が全人格化した世界」の理念そのものだから、ある種のトートロジー?
遠回りな様だが、こうして「欧米の個人主義」は樹立されてきたのである。
- 「龍樹の二諦説(大乗仏教)」…カント的なタイプ(認識可能領域とその外側)と遠藤周作「沈黙」的なタイプ(各人の打算によって成立する実社会と内面的良心の世界)の2モード。後者はしばしば日本人の独創とされるけど(マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(1904年〜1905年)」でジャンセニスムと並べて叩いてた)ルター神学っぽくもあり、「沈黙」を映画化したマーティン・スコセッシ監督も完全に理解してた。思うより国際的に理解が得られやすい思考様式?
最も根底にあるのが(割と純粋な形での)生存本能である事を決して忘れてはならない。
- 個人単位では「臣民意識(Liberty=奉仕の代表に特権開放を求める心)」と「市民意識(Freedom=放置を求める心)」が表裏一体を為す構成となっている。
- 「近代国家ではどこかの国民に帰属すること、すなわちナショナリティをもつことはごくごく当たり前のことであるのに、どの国民も自分たちは他の国民とは異なる国民性(民族性)や文化性をもつというふうに確信する。」…これはむしろ「差別化」を重視する「臣民(Subject)意識」に起因する。「党派性の確立こそ最重要課題」と考えるカール・シュミット流の政治哲学の大源流。
*ある種の生存本能を背景にしているという点で上掲の「原ナショナリズム(Pre-modern Nationalism)の当然の帰結の様に振る舞う戦略」とも無関係ではない。
- 「それほどの国民にとっては当然ナショナリズムは大きな意味をもっていそうなのに、ナショナリズムをめぐる理論や研究はどの国でも、ひどく貧困で支離滅裂である。」…そもそも「原ナショナリズム(Pre-modern Nationalism)」は近代以降の政治哲学の基軸に据えるには複雑な歴史を辿り過ぎており、かつまた全ての記録が後世に体系立てて伝わった訳でもない。そこから現代人の感覚で「ええとこどり」を目指したら当然「熱狂的信者以外の目には支離滅裂にしか映らない」展開となる。ある意味、神秘主義信仰が抱える本質的ジレンマとも。
*「ある意味、神秘主義信仰が抱える本質的ジレンマ」…ここで急遽「顕密思想」問題が表面化してくる。「インテリ=ブルジョワ階層独裁主義」の限度が問われる事になる。
そして、こうした観点を含み置いた上で欧州保守主義思想の大源流にある「ケルト民族にまつわる共有幻想」にアプローチすると、ベネディクト・アンダーソンが到達したビジョンの背景にあった景色が鮮烈に浮かび上がってくるのです。
欧州における「言語ナショナリズム」の源流。
ケルト語圏で修道院文化の生み出したものの中で、美術面に劣らず重要なのは俗語(ヴァーナキュラー)による文学の誕生だろう。
たとえばフランス語の最初の文学は一一世紀末の武勲詩『ローランの歌』(1098年頃)であり、ドイツ語の『ニーベルンゲンの歌』は13世紀になる。英語についてはやや早く、古英語(アングロサクソン語)の英雄伝『ベオウルフ』は八世紀初めに成立したとされる。
ヒベルニア(アイルランド)のエール(ゲール)語についてみると、現存する最古の文書こそ『ナ・ヌイドレ(ドゥンコウ)書』(1106年頃)、『ラグネッヘ(レンスター)書』(1160年頃)など12世紀となるが、その起源をたどると6世紀まで行き着く。もっとも有名なのは6世紀のダラーン・フォルギルによる「コルムキル(聖コルンバ)頌歌」である。ワリアのカムリー語の場合も、現存する文書は13世紀以降のものだが、『アネイリンの書』『タリエシンの書』などのカムリー語詩歌の創作年代が、その歴史状況からみて6世紀にまでさかのぼることは、研究者間のほぼ一致した見解である。
西欧の主要言語における文学の成立が11世紀~12世紀以降になり、もっとも早い英語でもせいぜい8世紀なのに、ゲール語ややカムリー語などどうひいき目にみてもメジャーとはいえない言語において、6世紀という早い段階で書きことばによる文学がなぜ誕生したか。
この答えはまさにその文化的周縁性にあるといっていいだろう。フランスの社会言語学者バッジオーニの提唱していることだが、ローマ帝国の周縁部(リメース)とその隣接地帯、すなわちブリタニア諸島、ドイツ北東部、スカンジナビア、ボヘミアなどでは、ラテン語は教養人にとっても外国語でしかなく、その使われ方も古風なままであった。権威ある言語が自由に日常的に用いられないというなかで、地元のことばをそれに代用するという考え方が生まれ、ラテン語に似せた書きことばでの使用がはじまったというわけである。
したがってヨーロッパでは、ローマ帝国の周縁部、その内外で最初に、日常的に用いられる俗語による書きことばが誕生した。こうした俗語が現代の国語・民族語の形成につながるのである。ブリタニア諸島での言語についてみれば、ローマ帝国のはっきりとした外部であるヒベルニアでは、6世紀には詩歌ばかりでなく、年代記や法的文書までゲール語で書かれるようになった。カムリー語の法的文書は10世紀、聖人伝はラテン語からの翻訳で11世紀末になって登場するので、ゲール語と比べるとその使用頻度は低い。ワリアが一部はローマ帝国領内だったということも関係しているだろう。
スカンジナビアでは、ローマ帝国がまだ活力を保っていた後二世紀にルーン(ルーネ)文字が誕生し、北ドイツでは四世紀にウルフィラなる僧侶によって、ゴート文字を用いるゴート語新約聖書の翻訳が試みられた。文字の作成は文学の誕生以前の独自の書記文化創出であり、まさにローマ帝国周縁部での言語的権威創出の試みということができる。この点ではケルト語のオガム文字もそうした試みの一つだといえるが、三世紀末から八世紀の墓碑銘などの碑文に用いられたにすぎなかった。その意味ではこちらは失敗事例といったほうがいい。
これに対して、ラテン語が教養人のことばとしてふつうに用いられた地中海地域では、いつまでもラテン語の書きことばとしての権威が失われず、地元の言語の文字使用が結果として遅れた。さらにいえば、ローマ帝国期の俗ラテン語の時期を経て、古典ラテン語の権威が9世紀には確立し、16世紀という近代はじめにまで持続したフランスでは、国家を超えるその権威をフランス語が引き継ごうとした。そこでフランス語のヨーロッパ全域にわたる普遍性が、まさにラテン語の生まれ変わりとしてとして主張されることになる。
*アンダーソンは「想像の共同体」のクレオール共同体に興味を寄せている。それは英語ないしはスペイン語という共通言語がありながら、ヨーロッパのどの地域よりも早くに「国民」という観念を成り立たせていたからだった(クレオール・ナショナリズム)。これは上掲の様な「周縁性」の産物と考えるべきだろう。そういえば欧州の中世前期、特にロマネズク文化を牽引したのは「周縁部」の数珠繋ぎに成功したノルマン人ではなかったか。
クレオール - Wikipedia
イングランドにおける古英語の残存
七世紀には、「七王国」のマーシア、エセックス、ウェセックスなどでも、エイダンの弟子筋によってヒベルニア系キリスト教の布教が進み、ヒベルニア、アルバ、ワリアばかりでなく、イングランドでも優勢になる。ただしキリスト教は絶対的権威を獲得しておらず、首領レベルでもこの当時は異教の残存がみられた。それは七世紀のアングロサクソン人における文字の導入についても影響を及ぼした。 大陸に分立建国したゲルマン諸族もこの頃法的文書が誕生していたが、それはラテン語によっていた。ところが、七王国のアングロサクソン人においては古英語だったのである。口伝の慣習法はすべてアングロサクソン語であり、この成文化という側面はあったが、ラテン語が絶対的権威を保持していなかったので、こうしたことが可能になったことは、大陸との比較において明白である。この場合も、周縁的文化地域での、俗語という新たな形での書きことばの誕生ということができる。
スペインのケルト人
ガリシアという地名は、ローマ時代イベリア半島のカライキイ族に由来する。ケルト系ともいわれる。五六九年、ガリシア中北部のルーゴで開かれた宗教会議には「ブリトン人の教区(セデース・ブリトノールム)」が記された。五七二年のブラーガでの宗教会議では、マイロックという人物が、「ブリトン人の教会の司教(ブリトネンシス・エクレシアエ・エピスコプス)」として署名した。こうした記述は、移住してきたブリトン人が集団で居住し、そこに教会なり修道院があったことを想像させる。ブリトン人の司教の名は、六三三年のトレドの宗教会議から六七五年のブラーガの第三回宗教会議まで見られる。以降まったく見られなくなるが、ブリトン語は次の世紀まで使われ続け、九世紀のノルマン人の襲来によって壊滅してしまったというのが研究者の見解である。第二次世界大戦後、ブルターニュ中南部アン・ノリアン(ロリアン)の町で開催され続けている「インターケルティック・フェスティヴァル(ケルト文化交流祭)」には、伝統的なケルト文化圏六地域(ブルターニュ、コーンウォール、ウェールズ、スコットランド、マン島、アイルランド)のほかに、ガリシアとアストゥリアスが参加しているが、この歴史的経緯がもとになって、加わっているのである。ただし現代のガリシア語はれっきとしたロマンス系言語で、そこにケルトの痕跡はほとんどない。
古典古代の再発見とカトリックの普遍性喪失
15世紀は大きくいえば、古典古代の再発見の時代であり、時代の思潮であるユマニスム(人文主義)が歴史の概念を一新し、聖書の大洪水とトロイア起源一辺倒の歴史観再考がはじまった時代である。タキトゥスの『ゲルマニア』がドイツの修道院の倉庫で「ある。タキトゥスの『ゲルマニア』がドイツの修道院の倉庫で「発見」されたのは一四五五年だった。ドイツでは16世紀はじめにはフランク族のトロイア起源は捨て去られ、ゲルマンの独自性が強調されるようになる。
フランスでは、16世紀以降、ヴィテルボのアンニウスの『古代史(1498年)』と、ルメール・ド・ベルジュの『ガリアの顕揚とトロイアの偉傑(1511年〜1512年)』などによって、ガリアがトロイアの先に来る、つまりギリシア・ローマに先んじるのがガリアであり、これこそフランスの起源だという思想が築きあげられていくことになる。
16世紀は、絶対主義国家が基礎を固める時代であり、民族的独自性が重視された。国家的アイデンティティの象徴として、国語と独自の歴史がはじめて主張されたのである。1539年の「ヴィレール・コトレ法」は、フランス語を王国の文書で独占的に使用しようとするものであり、フランスの国家的自立性、民族的一体性を宣言する。
活版印刷術の発明の影響力も大きい。ユマニスムや古代史、国語や次に述べる宗教文書類も、このお陰をこうむって急速な展開が可能になったのである。16世紀のもう一つ重要な点は、カトリックが欧州規模での普遍性を喪失することであるが、これについては既述のとおりである。
フランスの起源としてのケルト
16世紀後半、民族起源論争の一環として、言語起源論争が起きる。ここで古代に使われていたケルトという概念が復活する。ケルトが題名で用いられる最初の重要な書は、ピカール・ド・トゥートゥリの『古代ケルト学について(1556年)』であり、ガリア語がギリシア語のもとになっていることを論じた書である。つまりここではガリアの別名としてケルトが用いられた。フランスではガリアに主要な関心があり、その同義語として登場したのである。
ガリア人論は、16世紀半ばのギヨーム・ポステルでは、ガリア人こそ世界の最初の民族であり、したがってフランスは人類の起源につながるのだといい、極限までいたる。自分の言語が人類最初の言語だという主張は、実はこの時代、オランダでもドイツでも同じように展開された。次にみるケルトマニアも、自分たちのケルト語こそ人類の起源につながるという考え方であり、この引き写しなのである。
古代ガリアの実像について議論されるようになると、ドルイドについても言及されるようになる。国王顧問官クロード・ド・セセールの『フランスの王国(1519年)』に、ドルイドがキリスト教伝来以前の聖職者的位置にあったと言明される。議論の力点は、ギリシアを凌ぐガリア文化の優秀性であり、キリスト教に受け継がれる宗教的継続性である。ジャン・ルフェーブルジャン・ルフェーブルの『ガリアの花と古代、ドルイドという古代ガリアの哲学者考(1532年)』が、近代における最初の本格的ドルイド論である。
ノエル・タイユピエは、ガリアからフランクへ、断絶することなく政治が継承されたとする。重要なのは、ドルイドの生け贄思想が、決してキリスト教に反するものではないと主張されたことである。「決してキリスト教に反するものではないと主張されたことである。「人を犠牲に捧げるという考え方は、ユダヤ人や預言者たちの思想を受け継ぐものであり、……イエス・キリストはみずからの死と受難によって、父なる神に身を捧げることになるのである」(『国家史とドルイドの共和国(1585年)』。こうしてドルイドは、キリスト教に接続される。「シャルトルの大聖堂は、聖母マリアのためにドルイドらによって建てられたのである(同書)」とまでいわれる。異教的な野蛮な習俗という見方ではなかったのである。
「ブルターニュ派」の動き
1400年頃書かれたとされる、作者不詳の『聖ブリオク年代記』がブルターニュ公に献じられた、ブルターニュの過去の栄光を讃える最初の書である。15世紀のピエール・ルボー、16世紀のアラン・ブシャール、ベルトラン・ダルジャントレなども、宮廷つきの重要な歴史家である。こうした初期の宮廷つき歴史家では、全欧的起源であるトロイアと、ブリテン島の起源をなすブルートゥス伝説が重視され、続いてブリテン島からの移住起源としてのコナン伝説が取り上げられる。ただダルジャントレだけは、フランスにおけるガリア優越論を受け入れて、ブリテン島からの移住ではなく、ガリアのブリトン人がブルターニュの起源だと主張した。ブリテン島のケルト系言語はもともとガリア語であり、ブレイス語がその直系で、ブリテン島のほうはガリア人のコロニーだと考えるのである。
ガリアはたしかにフランスの起源かもしれないが、言語的にはブルターニュこそそれを継承しているのであり、これが、ガリア語=始原語=ケルト語=ブレイス語という、次のケルトマニアの思想に直結していく。
17世紀~18世紀ブルターニュを代表する歴史家は、ベネディクト会士ロビノーと、モリスである。ロビノーはダルジャントレと同様、ガリア=ケルトがブルターニュの起源だという議論を展開するが、建国者として重視するのはもっと後代、9世紀のノミノエであり、彼の論点が、19世紀以降のブルターニュ民族主義のなかで語られる英雄伝説の出発点になったと考えられる。一方モリスは、ダルジャントレやロビノーでは無視されたコナン伝説を再び取り上げ、ブリトン人の移住をブルターニュの起源として重視した。この考え方も一部では19世紀まで続いた。
ケルトマニア
17世紀西欧の民族起源論で盛んに取り上げられたのは、スキタイ人起源論である。ケルトとスキタイとの重なりは、すでにすでに古代ギリシアのヘロドトスや古代ローマ時代のストラボンが論じていたのだが、ケルト人とゲルマン人を同一民族とする考え方につながっている。オランダ人のボクスホルニウスと、数学者として有名なライプニッツが代表的主唱者であり、特にゲルマン語圏では支持する知識人が多かった。一八世紀のブルターニュで、ケルト語こそ人類始原の言語であり、それを引き継ぐのがブレイス語であると主張する人々が現れる。その考え方があまりに偏執的なので、19世紀になって、軽蔑のニュアンスをこめてケルトマニアと呼ばれた人々である。
その最初の人物とされるのがポール・ペズロンである。彼の議論の出発点は当時の思潮であるスキタイ起源論である。ただしスキタイ人とケルト人の関係が逆転されて、ケルト語が先に来る。彼の新主張は、ガリアを引き継ぐのがもはやフランス王国ではなく、ブルターニュとウェールズだという点にある。聖書の「大洪水(創世記)」の後に登場する、ヤフェトの子ゴメルの言語が、ヘブライ語を直接引き継ぐケルト語であり、この原民族の生き残り、その純粋な子孫がブレイス語であり、カムリー語なのだった。ブリトン人こそヨーロッパの起源であり、聖書に説かれているように、それは人類全体の起源でもある。こうした強引さがケルトマニアたるゆえんである。
こうしてブリトン人は、アーサー王伝説にもまさる栄光の歴史を手に入れることになった。シモン・ペルーティエでは、アイルランド人も起源的にはブリトン人であり、ケルト人、ガリア人であるとされ、その原民族はケルト語全域に拡大された。ブルターニュ出身のジャック・ルブリガンでは、最初の人間アダムとイヴの言語がすでにブレイス語だったと、究極まで行き着く。ブレイス語だったと、究極まで行き着く。
だが19世紀になって、比較言語学、考古学が学問として独り立ちするようになると、こうした議論はたちまち信用を失い、消え去ってしまうことになった。ただ生き残った単語が二つだけあり、それが「メンヒル」と「ドルメン」である。これは、ケルトマニアの一人、ブルターニュ出身のラトゥール・ドーヴェルニュが提唱し、革命期の歴史家ルグラン・ドシーが採用することで、考古学用語として用いられるようになった経緯がある。
ブリトン人の新たな栄光は一世紀ともたなかったのだが、学問としてのケルト語学はドイツ人のツォイスを起点に、19世紀後半から基礎が築かれることになる。
ネオ・ドルイディズム
イギリスでは、16世紀半ばにはジョン・ベイルによって大陸のアンニウスなどの思想、すなわちヤペトの息子サモテスがケルト人、ブリトン人の先祖だとする説が紹介され、それを引き継ぐ形で、1568年、ケンブリッジ大学のジョン・カイウスが、ブリテン島の先住民はケルト人だと言明した。スコットランドのジョージ・ブキャナンは言語分類論の先駆者だが、『スコッティア事物史(1582年)』のなかで、欧州の言語をラテン語、ゲルマン語、ガリア語に区分し、ガリア語のなかにベルガエ語、ブリタニア語、ケルト語を位置づけた。
17世紀には、ライプニッツのケルト・スキタイ起源論も輸入され、18世紀はじめには、カムリー語、ブレイス語の起源をなすケルト語が、「大洪水」時代の「祖語」だとするペズロンの議論も紹介された。ウェールズ出身でオックスフォードの図書館の司書になったエドワード・ルイドは、島嶼ケルト語を、ゴイデル語とブリトン語に二分した最初の人物であり、ケルト言語学の祖とみなされる。こうしたケルト論の興隆を背景として、古代のドルイドを復興しようとする精神運動がはじまる。現代の研究者はこの運動を「ネオ・ドルイディズム」と命名しているが、現代にまで継続する流派を形成している。
16世紀のケルト・ガリアの発見のなかでは、古代ケルトのドルイドがキリスト教を準備した、聖職者の祖型として評価される面があった。この運動は、それとはまったく逆に、キリスト教への対抗精神として、フリーメーソンとパラレルに展開された神秘主義運動であり、時代思潮である合理主義や啓蒙思想への反発をも内包するものだった。フリーメーソンとは、石工(メーソン)の組合が団結のために編み出した加入儀礼を参考にしつつ、ジェントルマンの交友団体として結成されたものである。その後の西欧知識人の間で隠然たる勢力を誇ったといわれるが、その揺籃期では、ネオ・ドルイディズムとまったく重なっていた。
生みの親は、両方ともジョン・トウランドという、北アイルランド出身の知識人である。オックスフォードで、ドルイド研究者ジョン・オーブリーに出会い、古代ケルトに心酔する。宗教的にはカトリックだったが、プロテスタント自由主義派、英国国教会派、さらにはおそらくこうしたキリスト教内部の対立に嫌気がさして、汎神論、自然宗教派を経て、フリーメーソンとドルイドという、一種の神秘主義にたどり着いたのだった。
フリーメーソンは、当時のブルジョワ教養階層にあっては、宗教宗教的喧騒をこえる人的結合体、知的交流団体として機能したのである。ヘンリー・ローランヅは、ドルイドの人身御供、またその玉座を巨石文化誕生に結びつけ、ネオ・ドルイディズムの理論的支柱となった。1717年6月、ロンドンのパブで、フリーメーソン・イングランド支部大ロッジ(グループ)が設立された。これが、現在の国際的秘密結社フリーメーソンにつながる団体の記念すべき第一号なのである。同年9月、このパブとはそれほど遠くないパブで、「古代ドルイド団」が、やはりトウランドを中心として結成される。ネオ・ドルイディズムの開始である。これには、イングランド、アイルランド、ブルターニュの代表が参加したとされるので、その交流範囲はブリテンとケルト語文化圏に重なることになる。
復興されたドルイド団は、ブルジョワ的紳士の社交クラブであり、古代のそれとはもちろんまったく別物である。1781年結成の「ドルイド古代団」は、むしろ互助会的、現代でいえば保険機関的役割を担った。1792年に、ウェールズのモルガヌグ(エドワード・ウィリアムズ)の設立した「ブリテン島バルド・ゴルセズ」は哲学的文学的団体であり、19世紀に続々と誕生する各種学術団体の先駆ともいえるものである。
ゴルセズはカムリー語で「玉座」を意味し、そこからドルイドの儀式、さらには団体の別名となった。ウェールズでは、バルド(吟唱者)の祭礼が「アイステズヴォッド」と呼ばれ、中世末期、1450年頃一度復活した経緯があるが、1789年に再興された。これが19世紀の間に、詩吟・歌謡のナショナル・フェスティバルに成長していく。このなかでゴルセズの果たした役割は大きかった。
1819年以降、この集団によって詩歌の優勝者たちが聖別されるという儀式を経ることで、祭りのいわば権威づけが行われるようになった。ゴルセズの位階は、「ドルイド」(賢者、白衣)を頂点に、「バルド」(詩歌に秀でる者、青衣)、「オヴァット」(智者、薬草などの知識に秀でる者、緑衣)に整備され、宗教色が薄められた。そして1861年にウェールズ全域から代表を集めたコンクール「全カムリー・アイステズヴォッド」がはじまる。現代では、ウェールズでもっとも文化的活力を持つ最大の祭りになっており、なおかつすべてがカムリー語で執り行われ、言語文化的な結束点ともなっている。
ブルターニュでは、1900年、ウェールズの支部という形で「ブルターニュ・バルド団ゴルセズ」が設立された。これには1898年結成の「ブルターニュ地域主義連合」もからみ、ウェールズとは異なり、最初から政治がらみで展開された。第一次世界大戦後のブルターニュの自治主義運動にかかわった人物の多くが、このドルイド団体のメンバーだった。彼らの儀式にはキリスト教以前の異教性を感じさせるエキゾチズムがあり、彼らの参加する地域主義連合の大会はフォークロア的な祭りの観も呈していた。だが、カトリック教会は、彼らの異教的性格に非寛容で、結局、ウェールズにおけるようなポピュラリティを獲得するにはいたらなかった。現代でもドルイドを標榜する神秘主義的結社が多数存在するが、どれもホビークラブの域を出るものとはいえない。
ケルト・アカデミー
フランス革命によって、ブルターニュは地域としての特権はいっさい奪われた。五県に分割され、地域としての一体性は政治的にはまったくなくなってしまった。ブルターニュの独自性は、言語文化的な背景として、過去の記憶として、知識人の間での学術文化活動のなかで主張され、19世紀後半からは、それが民族主義的な政治運動の展開につながることになる。
19世紀初頭、ナポレオン帝政期に設立されたケルト・アカデミーにおいて、ケルトは再び注目を浴びる。アカデミーは、1805年3月にパリで設立されたが、その活動は革命派の文化財調査保存運動の延長線上にあった。1807年にケルト・アカデミー年報第一巻が発行され、そこで習俗・習慣・迷信・儀礼・伝統行事などについて、五一項目にのぼる民俗学的調査表が発表された。この会は民俗学的な研究がその中心にあったのである。
ブルターニュ出身者はここでも大いに活躍した。地方会員の三分の一はブルターニュだったと言われるが、なかでも画家のペランによる『アルモリカのブリトン人の習俗・慣習。衣装描写集(1808年)』は、20世紀フランスの代表的民俗学者ヴァン・ジェネップによって、民俗学的な「最上の描写」と讃えられた。だがアカデミー自体は、ナポレオンと盛衰をともにし、1814年には活動がほとんど行われなくなった。
民衆歌謡の採集とロマン主義
民謡採集とロマン主義ヨーロッパの民俗学は、民衆歌謡の採集からはじまった。このなかでケルト語圏の採集家たちが模範的な役割を担ったのであり、その先陣をきったのがスコットランドのマクファーソンだった。1760年に出版された『古詩断章、スコットランド高地で収集、ガーリック(ゲール)すなわちエルセ語から翻訳』である。内容は、三世紀のスコットランドであり、フィンガル王とその息子オシアンの武勲詩である。序文では、「いにしえのスコットランドの詩歌の純粋な残存物」だと主張され、なおかつ「キリスト教ないしはその信仰に対する言及が全くみられない」とし、キリスト教受容以前にさかのぼる伝承の古さを強調する。これこそ19世紀民族主義の源泉となるロマン主義の思想であり、民俗学の学問的要請である。
ほぼ同時期、北欧やドイツでもキリスト教以前にさかのぼる詩歌の掘り起こしが行われており、こうした独自性の追求が全欧州規模ではじまっていた。たとえばポールアンリ・マレの『ケルト人、とりわけ昔のスカンジナビア人の神話と詩歌の記念碑(1758年の)』である。マレは、ゲルマン人とケルト人が同一民族で、スカンジナビア人がケルト人の末裔だとする、すでに紹介した立場をとった。
ここで注目すべきなのは、チュルゴーやディドロなど百科全書派が『古詩断章』のフランス語訳を手がけていることである。つまり実学の集大成であり、なおかつ啓蒙的な百科全書と、キリスト18世紀末の状況では結びついていたのである。民俗学は庶民の実学の探究であり、そこから民族的本質を見出そうとする指向性があるが、それはすでに誕生時点で内包されていたといえる。
マクファーソンはその後さらに精力的に調査を行い1773年には集大成版の『オシアン詩集』を出版する。これはフランスばかりでなく、イタリア、ドイツなどでも翻訳が相次ぎ、ゲーテやナポレオンもこの詩歌の崇拝者となった。このなかでドイツのヘルダーは重要である。1764年、彼は弱冠20歳で『古詩断章』の翻訳を行っている。1777年には、「文明化していない民族はみな歌い踊る。……彼らの歌は、民族の記録庫であり、学問・信仰・神統記・始原論の宝庫である」(『中世の英語・ドイツ語詩歌の類似性について』)と書いた。文明化とはここではキリスト教化である。歌こそキリスト教化していない「民族の記録庫」として重要だというのである。1778年~1779年には、自ら率先して諸民族の詩歌を集め『民謡集(フォルクス・リーダー)』を出版する。すでに民俗学的要請を心得ていたのである。
歴史教育と古代のイメージ
フランスでは大革命以降、普通教育が開始されるが、実際の学制改革は19世紀の三期にわたる。
- 第一期は1830年代で、地方の町村に小学校ができはじめる。
- 第二期は第二帝政期の1850年代であり、カトリックの活動が大幅に緩和されて、彼らの手になる小中学校が全国的に広がる。この時代はまた、産業革命が進展し、全国的に鉄道網がいきわたるようになり、パリと地方の距離が一挙に縮まる。
- 第三期は、第三共和政期の1880年代であり、ジュール・フェリーによる教育改革として知られ、義務教育がはじまる。
1830年代の教育改革の必要性から、一般向けのフランス史が書かれるようになる。代表的なのがミシュレの『フランス史(第一巻は1833年)』であり、ここから「われらが祖先ガリア人」という表現が普及していく。フランス人の意識としては、貴族はフランク人、民衆はガリア人の系統だという意識が今でもあるが、これは18世紀前半にブーランヴィリエ伯爵が打ち出したものである。ミシュレらの「われらが祖先ガリア人」という表現には、民衆的フランスこそ真のフランスだという意識がある。
*いわゆる「サン=シモン主義」の出発点もまさにこれ。この一方で、一九世紀前半でブルターニュ出身の最大の作家シャトーブリアンが『殉教者(Les Martyrs、1809年)』で描く古代ガリアの女ドルイド「ヴェレダ(Velléda)」は、理性的フランスへの同化を拒否する神秘的野性的知性を象徴し、ブルターニュの反フランス・ナショナリズムの原点となった。歴史家アメデ・ティエリの『ガリア史(1828年)』、アンリ・マルタンの『フランス史(第一巻1833年)』は、ドルメンの上で人身御供を行うドルイドのイメージを民衆に広めた。
*ここで「保守主義者」シャトーブリアンの名前が登場。
ブルターニュの民謡採集
民謡の採集も盛んになり、歌から過去の事実を説明するという民俗学的手法もすでに用いられた。1823年に報告された「ケルラスの跡取り娘」では、1575年頃、実際にあった結婚の悲劇を歌ったものだということが明らかにされた(ブロワ著『一六世紀ブルターニュのロマンス、ケルラスの跡取り娘』)。
固有名詞の入る語り歌をブレイス語で「グウェルス」という。こうした語り歌こそ歴史的文書にも匹敵する、収集すべき歌とされ、競って集められた。たとえば1837年に発表された歌「グウェンガンの包囲戦(フレマンヴィル)」は、1489年のアンナ女公のフランスとの戦い、ないしは1591年の宗教戦争の際の、グウェンガン町の包囲戦を題材にしたものと推定された。
1839年、ブルターニュの民謡収集の決定版『バルザス・ブレイス(ブルターニュ詩歌集)』がラヴィルマルケによって刊行される。フランスのロマン主義作家ジョルジュ・サンドが、ホメロスのイーリアスをも凌ぐと絶賛した作品である。ドイツ語訳、英語訳などが出され、ヨーロッパ中で評判になるといっていいのだが、英訳者は次のように言う。
「(イギリスの)カンブリア、デヴォン、コーンウォールでは、近隣の民族との融合によって、地名とわずかな普通名詞を除いて、ケルトの民族的特徴がほとんど消えてしまった。ウェールズでは何世紀も前から同化がはじまっているが、ブルターニュでは大革命でやっとそれが開始された。……ウェールズではプロテスタントのメソジスト教会が、アイルランドでは宗教的民族的戦争が、ケルト的詩歌への結実を妨げてきたが、ブルターニュではこれが自由に解き放たれ、詩歌となってほとばしり出たのである。10世紀、12世紀、14世紀に歌われた語り歌や讃歌讃歌が、口伝によって、農民、物乞い、さらには昔のバルドに代わる放浪の大道芸人のなかで、父から息子へ、母から子どもたちへと歌い継がれてきたのである」
ここではケルト的民族性が意識され、言い方に誇張はあるが、ほかのケルト語圏ではすでに消滅している伝承が、ブルターニュでのみ残っているという考え方が示される。19世紀ブレイス・イーゼルの農村の状況についてみれば、この見方は当たっているかもしれない。
ラヴィルマルケの考え方で重要なのは、ドルイド信仰などケルト的な文化が、キリスト教化によって破壊されたのではなく、文化的伝統として引き継がれたということにある。すでに見たようにこの思想は16世紀から存在したが、ケルト文化の背景を持つキリスト教を自らのアイデンティティと考える、ブルターニュの民族派キリスト教徒の欠くことのできない論拠ということができる。
彼の『バルザス・ブレイス』の解説部には次のような箇所がある。
「こうした(ドルイドの)儀礼が、守護聖人の祭礼に習合し、結局は聖人信仰だけが生き残った。たとえば、聖ロナンの隠遁修業所は、山の中腹にあるネヴェットの森に位置するが、ここにはドルイドの遺跡があり、六年ごとに練り歩きが行われるのである」。
これはもともと異教的・民間信仰的な行事がキリスト教化されたといわれているロコルンのトロメニー祭礼の事であり、19世紀中頃からすでに、ブルターニュのキリスト教は、異教的なものを取り込む独特なものだった、と認識されていたことになる。
19世紀前半のティエリ、マルタンらからはじまるフランス・ナショナリズムと結びついたガリア論は20世紀でも活発で、その最大の貢献者はカミーユ・ジュリアンであり、彼の『ガリア史(全八巻、1907年~1926年)』である。これまでの研究の集大成であり、ギリシアとの関係など内容的には今日でも有用な情報が数多く含まれている。
比較言語学者は祖語という単一起源を設定はするが、これを文化や人種の起源と結びつけることはしなかった。ところが一部のケルト学者はこの一線を踏み越えて、人種主義的傾向を持った。ドイツのケルト学は20世紀初頭、ベルリンほか5大学でケルト学の講座を持つなど、研究を先導する位置にあったが、ベルリン大学ケルト学講座教授ミュールハウゼンらがこうした立場を取り、ケルト人はゲルマン人と並んで、真性のアーリア人とみなされることになった。彼はナチス親衛隊の研究教育振興会である「祖先の遺産(アーネン・エルベ)」のメンバーにも加わった。こうしたナチス・イデオロギーとの結合により、1897年創刊の権威あるベルリン大学の『ケルト言語研究誌』は第二次世界大戦後10年あまり休刊を余儀なくされる。
原聖「ケルト概念再考」
ああ、これは誰にも纏め切れなくて当然?
これまで随分と「アイルランド系」の投稿をしてきましたが、何か地雷原を手探りで歩いてる感じでした。これで少しは先行きが明るくなった?
さて、私達は一体どちらに向けて漂流してるのでしょうか…