世界史は歴史のある時点まで「(強力な部族的紐帯を武器とする辺境民族が新たな王朝の支配者となり続ける)循環史観」の支配下にあったと目されています。
*その最後にして最大規模の動きがモンゴル世界帝国(1206年〜1634年)の興亡だったとも。


こうした制約を打ち破ろうという動きが「(「暴力的手段を国家が十分に独占している状態」を法源とする法実証主義に基づいて)火器を大量装備した常備軍を中央集権的官僚制が徴税によって賄う」主権国家の登場でした。その発想自体は(トルコのオスマン帝国やインドのムガル帝国など)欧州以外にも現れたが「経済学や経営学に基づく国家統制」なる概念に到達して後世までそれが存在したのは欧州においてだけだったのです。しかも、その欧州においてすら(かかる理念が中途半端な形でしか実践出来なかった)フランス絶対王政やハプスブルグ帝国は現代まで生き残る事は出来なかったのだから現実は中々に手厳しかったといえましょう。
*まぁ江戸幕藩体制ですら、存続を諦めて「自ら死を選んだ」のである。しかもそれだけでハッピーエンドに至った訳でもない。
- この意味合いにおいては、イングランド共和国護国卿(Lord Protector、1653年〜1658年)オリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell、1599年〜1658年)やルイ14世の財務総監コルベール(Jean-Baptiste Colbert, 1619年〜1683年)や東インド会社総裁ジョサイア・チャイルド(Josiah Child、1630年~1699年)が展開した重金主義(bullionism)や重商主義(mercantilism)こそが欧州史の極めて重要な展開点だった事になる。
17 世紀は国家が台頭した時代だったから、国家が必要とする二種類の階級の出現がその特徴だ。国を運営する官僚と、そのお金を出す商人だ。重商主義は、こうした実務家たちの小冊子や研究や協定がたくさんあわさることで発達した。イギリスとオランダでは、経済著作の大部分は台頭するブルジョワコミュニティ出身の商人 (merchants) たちが書いた――だから重商主義 (Mercantilism)ということばがでてきた。フランスとドイツではブルジョワ階級が小さかったので、経済議論はもっぱら国の役人が書いた――だからフランスの重商主義はむしろ「コルベール主義 (Colbertisme)」 (フランスの財務相ジャン・バプティスト・コルベールにちなんだ名前)で知られ、ドイツの重商主義は「官房学派 (Cameralism)」(王立chamber を指すドイツ語にちなむ)として知られる。
イギリス・オランダとフランス・ドイツの重商主義の背景はこんな風にちがっているけれど、その経済ドクトリンはどれも大差ない。どっちも商人たちの富と国の力との親密で共生的な関係を認識していた。商売が繁盛すれば歳入が増え、国の力も増す。国の力が増せば、利益の高い交易ルートを確保できて、商人たちの望む独占を与えられる。
*近代日本における「産業報国運動」を連想させる。そしてかかる総力戦的体制は戦後高度成長期の間も維持されたのである。*クロムウェルの時代にイングランドはその経済基盤を(砂糖産業の本拠地たる)西インド諸島や(キャラコ生産の本拠地たる)インドへと移し始めた。そして以降、次第に欧州大陸諸国間の勢力争いから距離を置き「日没を知らない」大英帝国への変貌を果たしていく。
- こうした「主権国家間の競争が全てとなった」状態を背景に、最初に形成されたのは「国家を生産や消費の主体(計測され、予測と計画を建て、それに従って運用される対象)とする経済学」だった。特に最終的には「税収の大きさを縦軸に、国民の公共サービスに対する満足度を取る」形式へと辿り着くイタリア効用主義経済学の伝統が果たした役割が大きいとも。
17世紀後半以降、ハプスブルグ家支配下において「法律家市民層(ceto civile(togato))」が官僚層として台頭。これ経由でアルプス以北(英・仏・蘭)の新思想(デカルト、ニュートン、ロック等)がナポリに伝わり、アントニオ・ジェノベージ(Antonio Genovesi 1713年~1769年)を始祖とするナポリ啓蒙運動が流行する。スコットランド啓蒙主義同様に「富と徳の関係」に関して激論が交わされる。
そして修道院長にして役人だったフェルディナンド・ガリアーニ (Ferdinando Galiani 1728年~1787年)が1759年から1769年までフランスのナポリ大使館に詰めており、同時代のフランス経済学者達の多くと知り合いだった。やがて(フランス革命が始まると守旧派に粛清されて消滅する)スコットランド啓蒙主義にも(フランス飢饉の時も「自然状態」がどうといった観念論に興じる事しか出来なかった役立たずの集まりに過ぎない)フランス重農主義にもNoを突きつけ、1751年の論文において効用と希少性の両方に基づく新しい価値理論を導入し「限界革命の始祖」となり、1770年の論文において国際収支に関するかなり現代的な分析を提供して(経済主体としての政府に関する真剣な分析と、自然価値に関する効用ベースの理論を特徴とする)イタリア効用主義の伝統の創始者の一人となる。立場的にはフランスの新コルベール主義やドイツの新官房学派に近く、実際ガリアーニは自著で国を「善意の独裁者」と呼んでいる。*ある意味国家間の競争が全てとなる「総力戦体制時代(1910年代後半〜1970年代)」を先取りした展開。競争に参加した各国は自国の最終的勝利を目指す集-立(Gestell)システムとして自利を追求しただけだが、どの国も最終勝者とならなかったので「競争終了による停滞状態」に見舞われる事なく(国家プロジェクトとしての)様々なテクノロジーの研鑽ばかりがむやみやたらと進む事になった点は冷戦当時の世界情勢に近いとも。
*かかる時代には「輸入を最小限、輸出を最大限とする」貿易差額主義や(奴隷制農場や再版農奴制を含む)人件費を最小限に抑える政策が流行した。ある意味今日のデフレ経済信仰の先駆けとも。
*ここで興味深いのが「国王の戦争や浪費を支える為の重税」には国際競争力を損なうインフレの進行を食い止める効果もあると目されていたという辺り。ちなみに第二次世界大戦下のアメリカにおいては戦時国債購入を勧める大キャンペーンが展開したが、これも宣布調達の為というより戦争特需による景気の加熱の冷却が主目的だったという。当時確立した国家経済学のノウハウの少なくとも一部は後世もしっかり現役であり続けてきたのである。
ところが19世紀後半に入ると「産業革命のもたらした大量生産・大量消費スタイルの普及に伴い(主に西ヨーロッパで)消費の主体が王侯貴族や聖職者といった伝統的インテリ=ブルジョワ=政治的エリート階層から生産の担い手でもある産業階層に推移した経済的変遷」が起こってしまうのです。
*恋愛ロマンス小説分野においては既に(18世紀啓蒙主義的=百科全書派的衒学趣味の産物として生まれた)フランスのルソー「ジュリまたは新エロイーズ( Julie ou la Nouvelle Héloïse、1761年)」から(あくまで知識と認識の範囲が限られた個人が、それなりに完成度の高い世界観に到達してそれに従って生き様とする)ドイツのゲーテ「若きウェルテルの悩み(Die Leiden des jungen Werthers、1774年)」への飛躍過程で視覚化されていた問題。1970年代に改めて可視化された「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」政治上のジレンマが、1980年代においては「究極の個人主義は他者一切の支配によって成立する」個人レベルのジレンマに落とし込まれていったプロセスの先取りとも。
歴史のこの時点でハプスブルグ君主国、オスマン帝国、帝政ロシアといった主権国家化が十分でなかった国の脱落が明白に。後の第一次世界大戦(1914年〜1918年)やロシア革命(1917年)を契機とする共産主義勢力台頭の遠因となってしまいます。
*旧共産主義圏には「当時の後進国は資本主義受容の準備として共産主義化を必要とした」とする「共産主義瘡蓋(かさぶた)論」が存在する。これらの地域では大衆が「計測され、予測と計画を建て、それに従って運用される対象」として管理され(競争を生み出す)自由な生産や消費を禁じられたが、それはこうした展開が引き起こす(インフレやデフレの進行、貧富格差の拡大といった)経済変化に対応する能力が著しく欠けていたせいでもあったのである。
- 産業革命導入に当たって最後の足を引っ張ったのは、封建的権威を担保に取った融資しかしない守旧派銀行家達の存在。かくしてフランス第二帝政においては海外の産業投資家の大量誘致による「宮廷銀行家」フランス・ロスチャイルド家の独占状態の破壊が、大日本帝国においては「廃藩置県(1871年)」「廃債処分(1872年)」「秩禄処分(1876年)」による「大名貸し=江戸幕藩体制を支えた札差」の撲滅が遂行されている。
またドイツ帝国ではライン川流域の鉄鋼業、鉱業、機械工業、電気産業を中心に「ヘル・イム・ハウゼ体制(事業家による家父長的な経営規範)」を標榜する工業領主が次々と台頭。ちなみにイタリア王国は1939年までソ連並みに国営企業の数と経済規模が大きく、実質的に共産主義国家と大差ない状態だった。
*オランダやスイスや英国やアメリカにおいては自然発生的に始まった産業革命だったが、フランスやドイツ語圏や日本といったむしろ前近代時代に高度な身分制社会が構築された国々では一旦それを破壊しなければその段階に進む事が出来なかったのである。そのノウハウは主に「馬上のサン=シモン」皇帝ナポレオン三世の手によって編纂され、ドイツ帝国や大日本帝国やイタリア王国に模倣される形で拡散。またさらに「社会民主主義の父」ラッサールの弟子達とプロイセン宰相ビスマルクの協業から生まれた「国家福祉主義」も次第に様々な国へと影響を与えていく。また自らの民族的起源を仮想し国民教育によって普遍化していく動きも同時進行で広まっていく。
*個人的には「資本主義的成功」を納めた中華人民共和国やベトナム社会主義共和国も、ここでいう「サン=シモン流産業政策」によって成功を納めたのではないかと考えている。
- また同時期には統計学の導入によって「国家を計測し、予測と計画を建て、それに従って運用する技術」が飛躍的に発展。特に絶えず移民の実態把握を続けなければならないアメリカでは、その作業の機械化が急務となっていく。
*かくして「コンピューターの祖」としてのタピュレーティング・マシン(Tabulating machine、パンチカード・システム)の実用化が始まったのである。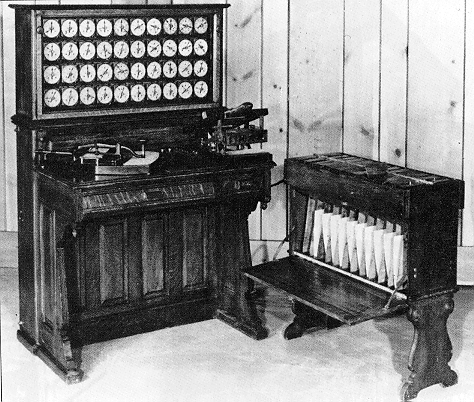
1880年の米国の国勢調査では、集めた調査票の集計に7年以上かかったとされています(集計期間は文献により違いがあります)。当時の米国の人口は7000万人以下であり、仮に一人の国勢調査票のデータが100文字分100バイトだったとして、全データ容量は7ギガバイト。今考えると少ないデータ量といえますが、当時は手に余るデータ量であり、まさにビッグデータだったのでしょう。
実は米国の国勢調査はビッグデータだけでなく、ITの誕生においても大きな意味を持ちます。当時の米国は移民が増えており、1890年の国勢調査では、人口増から集計に10年以上かかることが予測されました。つまり次の国勢調査までに集計が終わらないことになります。
そこで米国政府は集計を速くする方法を公募し、そこで採用されたのがハーマン・ホレリス氏が発明したパンチカードによる集計機(タビュレーティングマシン、日本ではパンチカードマシンと呼ばれることも多い)でした。そのタビュレーティングマシンを使うことにより、集計作業は18ヵ月ほどで終わったとされます。
こうして石ノ森章太郎「仮面ライダー(1971年〜1973年)」において悪の組織ショッカーが最終目標に掲げた「コンピューター(電子頭脳)による国民の背番号管理システムを乗っ取り、テレビを洗脳装置として全国民を奴隷化するビジョン」などが可視化される展開を迎えます。
そして皮肉にも、かかる実存不安の高まりは「パソコンの普及」によって克服される展開を迎えたのでした。

