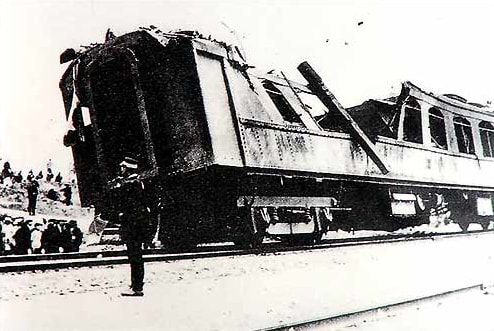欧米的合理主義はイタリアから始まった。
しかし19世紀スイスの文化史学者ブルクハルトは「イタリア・ルネサンスの文化(Die Kultur der Renaissance in Italien, ein Versuch、1860年)」の結語で、こうした考え方の登場は、当初むしろ当時の信仰深い人々を「理神論(deisms/ディスムス)」や「人格神論(theisms/ティスムス)」に走らせたとする。
- 「理神論(deisms/ディスムス)」…キリスト教から「キリスト教的なるもの」を捨て去った残りで、しかも感情的になってその補償を求めない立場。当時の教会の腐敗を嫌悪し、一切の関係を立ちたがった心境が背景にあるという。ブルクハルトは本書中でこれをフランス革命と結びつけ「世界史的諸考察(Weltgeschichtliche Betrachtungen、1905年)」では、さらに「歴史における危機(ローマ帝国の滅亡、宗教改革、フランス革命)」を乗り越えた原動力の一つと位置付けている。
*だが理神と自然の崇拝はフランス重農主義をも生み出す事に。
- 「人格神論(theisms/ティスムス)」…神的存在に対し(中世には知られていなかったレベルまで)絶対的に高められた信仰。その一方で子供らしい素朴さや異教的余韻に包まれており、キリスト教なしで存在し得る一方でキリスト教と矛盾せず、罪や救済や魂の不滅といったいかにもキリスト教的な教説とも容易に結びつく。神を「全能の力をもって人間の願望を叶えてくれる存在」と認識する辺りは現生利益的でもある。ブルクハルトが別の箇所で当時のイタリア人について「人間にしか感動しない」「イメージ能力が過多」と述べており、かつまた当時が森羅万象を擬人化してイメージする古代心理の復興期だった事を指摘している事と関係が深そうである。
「イタリア・ルネサンスの文化」結語近くより…「中世の人間はこの世界を反キリスト出現まで教皇や皇帝が守りぬかねばならない"涙の谷"と考えた。ルネサンス期の宿命論者は、精力的活動と虚ろな諦念と迷信の間を激しく行き来した。だがこの選ばれし精神の集まりは、目に見える世界は神が愛から創造したもので、それは神の中にあらかじめ存在する原型の写しであり、神は永遠にそれを動かし、創造し続ける存在であるという信念に到達した。個々の人間の魂は、まず神を認識する事によって神を自分の狭隘な限界の内側に引き寄せる事も出来るが、その一方では神への愛によって自分を無限に拡大していく事も出来る。この世界観においては中世的神秘論と、プラトンの教説と、近代固有の精神の境界線が衝突することなく触れ合うのである」
「涙の谷」…特定の地名ではなく、荒廃と嘆きのある場所を指す。「雀さえも、住みかを見つけました。つばめも、ひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主。私の王、私の神よ。 なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。 彼らは、いつも、あなたをほめたたえています。 なんと幸いなことでしょう。その力が、あなた(神)にあり、その心の中にシオンへの大路のある人は。彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉のわく所とします。初めの雨もまたそこを祝福でおおいます。 彼らは、力から力へと進み、シオンにおいて、神の御前に現われます。 」(詩篇84:3~7)。
ちなみに英国人歴史学者トインビーは「ヘレニズム 一つの文明の歴史(1961年)」の中でむしろヘレニズム文化を(王と神を同一視するオリエント信仰と「人間にしか感動しない」ラテン気質の混合から生まれた)英雄崇拝の一種とし、そこにファシズムやナチズムの起源の一つを見てとっている。
ブルクハルト 「世界史的諸考察(Weltgeschichtliche Betrachtungen、1905年)」
「ローマ帝国の危機は断ち切ることができなかった。それはこの危機が、人口の少なくなった南方の国々を占有したいという、繁殖力旺盛な若い諸国民にきざした衝動から起こっていたからである。これは一種の生理学上の均衡化であり、この均衡化は部分的には見境なく行なわれたのであった。」 *しかし宗教改革の場合、それは防げたはずだとブルクハルトは主張する。
「宗教改革の場合には、これを阻むために、聖職者階級の改革と、教会財産の適度の削減、それもあくまでも完全に支配階級の意のままにできた程度の削減で十分であったであろう。」 *またフランス革命も、ある程度緩和はできたはずだと主張する。
「結局のところ、人間の内部には大きな周期的変化を求める抑えがたい衝動がひそんでいる。」*ここで突如の論理的飛躍。
「危機を起こさせる外見上本質的に見える前提条件は、きわめて発達した交通機関の存在と、異なった事柄を誰もがほとんど同じように思考するということが広範囲にわたって拡まっていることである。」
「時が到り、かつ危機を起こさせる真の材料が出そろうと、そのことは伝染病さながらに、電流の伝わる速度で何百マイルもの距離を越えて伝わり、通常はたがいにほとんど識ることのないじつにさまざまな住民にまで及んでゆく。この報らせは宙を伝わってゆき、そして、重要な一点において住民たちはすべて、たとえ漠然とではあったとしても、突然たがいに了解しあう、「変わらねばならないのだ」と。」
「権力はかえってこのような時代にこそ中断ということをいちばん我慢しない。ある一人の人もしくはある党派が疲れてくずおれるか、もしくは破滅すると、ただちに別な人が立ち現れる。」
こうしたブルクハルトの「歴史における危機」論とカール・シュミットの主張をあえて連続的に語ろうとする立場がある。
「陸の国」スペインから「海の国」イギリスへと覇権が移っ たことを、ドイツの法哲学者カール・シュミットは「 空間 革命」と呼びました。
当時、スペイン帝国は中世の「 中心で、無敵艦隊を擁していましたが、実質的には「陸の国」でした。地中海は波が穏やかであり、無敵艦隊といっても陸軍兵士を輸送することが主な役割だったからです。その 無敵艦隊が一五八八年にイギリス艦隊に敗れたことで、スペイン帝国の凋落が決定づけられ、イギリスの時代が始まりました。
海を制したイギリスは、海洋支配をもとに全世界を網にかけていきます。一六〇〇年に東インド会社を設立して、半ば略奪的な行為を重ねながら、資本を蓄積していきまし た。略奪的な貿易は、 相手方が主として「 新大陸」だったので海を通じておこなわれることになり、海を支配すること で全世界の利益を吸収することができたのです。
いわばイギリスは海という「 空間」を創造し、それまでの領土にもとづいた陸のシステムとはまったく異なる新しい貿易のルールを築いたわけです。
ところでカール・シュミットとはいかなる人物か?
池田信夫 カール・シュミットと「決められない政治」(2013年04月16日)
自由主義や民主主義の前提とするのは、合理的個人である。ケルゼンの実定法主義(法実証主義)では、法の正統性は数学のように、その論理整合性のみで決まると考えられている。しかし法律を数学になぞらえるとすれば、ユークリッド幾何学も非ユークリッド幾何学もともに成り立ち、どちらが正しいかを決めることはできない。このような非決定性が実定法主義の欠陥であり、それは「ナチスの制定した法律も無矛盾であるかぎり正しい」という結論を導く。
「ナチスの制定した法律も無矛盾であるかぎり正しい」…これは「デカルトの演繹法(機械的宇宙論)」そのものが抱える欠陥で、その延長線上で科学と認定された歴史学も孕んでいるもんだいである(所謂「歴史観」問題)。
これに対してシュミットは「主権者とは、例外状態にかんして決定をくだす者をいう」という『政治神学』の冒頭の有名な言葉で、法を超える主権者が法秩序の本質だとする。法の正統性は論理ではなく暴力によって決まり「敵か味方か」という政治力学が法の衣をまとっているだけだ。
「法実証主義( legal positivism)」…トマス・ホッブスが清教徒革命期(1638年〜1660年)、王政復古期(1660年 〜1688年)、名誉革命期(1688年〜1689年)と権力者が交代する都度、法体系が刷新されるのを目の当たりにして「軍事力的裏付けなしに法が正当性を獲得する事はない」と考えたのを発端とする。その意味では「法の正統性は論理ではなく暴力によって決まる」という表現には相応の誤謬が含まれている。
このような主権者を欠いたワイマール憲法は、シュミットの警告した通り、何も決まらないという欠陥を露呈し、「決定できる」ナチスに乗っ取られてしまう。何も決まらない状態は民主主義の失敗ではなく本質的な欠陥であり、決定する主権の存在こそ真の問題だというシュミットの指摘は、現代日本にとっても重要だ。
「主権者を欠いたワイマール憲法は、決定できるナチスに乗っ取られた」…多くの人間が指摘している様に「何も決められない状態」を克服する為に(独裁色の強い)大統領内閣(Präsidialkabinett)へと移行したのはワイマール政権自体で、カール・シュミットが絶賛したのもこれ。それゆえにヒトラーも選挙で勝っただけでは権力が掌握出来ず、国防軍の何倍もの規模を誇る突撃隊(S.A.)を後ろ盾にヒンデンブルク大統領に権限譲渡を迫る必要があった。その段階ではもう議会制民主主義そのものが機能を停止していたのである。
【Wikipedia】カール・シュミットにおける「例外状態(Ausnahmezustand、ドイツ語の「Ausnahme」が例外、「Zustand」が状態)」
一般に国家における非常事態を意味するが、カール・シュミットはこの用語を議会制民主主義批判と関連付けて用いている。議会制民主主義における諸政党は、社会的・経済的な利権集団に過ぎず、国家に対して責任を欠いている。彼らは自らの利益のために立法を重ねるため、そうした体制下での「議会制民主主義の発展」とは、政治的倫理・理念を欠いた妥協のための技術が磨かれたにすぎないのである。
だから彼は(特定集団の経済的利害に左右されない)真正の政治が秩序をもたらし、その秩序のもとで法が形成されるのが望ましいと考える。しかし、議会制民主主義下の日常はこれとは異なっており、「民主的に」(=様々な利権団体に翻弄され妥協を重ねながら)議会で法が定められるのが、議会制民主主義下の日常であると捉えている。
著書『政治神学』において「主権者とは、例外状態に関して決断を下す者である」と示されているように、彼にとって真正の政治が復権する状況の一つが「例外状態」であった。ヴァイマル憲法第48条(大統領緊急令など)は、非常事態(例外状態、Ausnahmezustand)において大統領が強力な執政権を行使することを認めており、たびたび国家的危機において緊急令が出されていた。とりわけ、世界恐慌後はヒンデンブルク大統領のもとで緊急令が濫発された。このヴァイマル共和国末期における権威主義的体制こそが、彼の支持するところであった。
【Wikipedia】カール・シュミットにおける「友敵の究極的区別(連合と分離の強度)」
カール・シュミット「政治的なものの概念(Der Begriff des Politischen、1932年)」は、まず人間性について自由主義が論じるような善性を政治理論から排除する。そして事実はともかく「人間は悪しきものである」と見なすことで、政治権力や国家秩序の理論を構築することが可能になるとする。これが有名な「友敵理論」の出発点となる。
道徳における善悪、美学における美醜、経済における利害に該当する政治特有の範疇は「友と敵の区別」である。
ここでいう「敵」とはあくまで実存的な他者・異質者であり、単なる競争や討論の相手ではない。自己を根本から否定する存在であり、逆に自らを肯定して敵と一緒に争うのが「友」である。そして「敵」との敵対性や「友」との同質性の極限までの追求が「政治化」という事になる。
あらゆる宗教、経済、人種などの対立が「政治化」し得る一方で、それは必ずしも他者の殺害や破壊などを含む闘争を意味しない。それ事態も多様な敵対関係の一形態に過ぎない。
政治がこうして「友」と「敵」を峻別する営みである以上、政治に参加する国民にとって重要なのは誰が友で誰が敵なのかについての判断という事になる。国民がその判断を放棄する時には、新たな保護者の庇護下で「敵」と「友」が定められる(例外状態)。
民主主義2.0とカール・シュミットの「民主主義」(Hatena Diary 2009-12-26)
1923年に出された『現代議会主義の精神史的地位』において、シュミットはルソーの「一般意志」について次のように述べている。「人民は元来決して具体的な内容に協賛を与えるのではなく、抽象的に、投票の結果現れる一般意志に、協賛を与えるのである…この結果が個々人の投票の内容と誤っているならば、評決に敗れた者は、彼が一般意志の内容について誤った見方をしていたということになる。」「ルソーの考えた一般意志は、本当のところは、同質性である。これこそ真に徹底した民主主義である」。シュミットが注目するのは、「一般意志」という概念が持つフォルム(形式)である。「民主主義」においては、個々の国民は自らの意志とは異なる法律に賛同をすることもあるが、それは法律が「一般意志」の結果だからである。「一般意志」とは単なる多数意見ではなく、国民の意志そのものに他ならない。「一般意志」は投票の内容においてではなく、フォルムにおいて国民の意志を「代表(Repräsentation)」する。国民は、そのつど表決にかけられる個々の法律それ自体に同意しているのではなく、「一般意志」という「上からの」フォルムそのものに同意するのだ。
投票はシュミットにおいて技術的な問題にすぎない。彼にとっては、いかにして国民意志が「代表」されるかというそのフォルムこそが問題であって、その方法は投票でなくてもよい。それは「拍手と喝采」による独裁でも構わないのである。
まさしく「自由のあるところには秩序はない」と「究極の自由主義は専制の徹底によってのみ達成される」の狭間の際どい綱渡りの実例。当時「下部構造が上部構造を決定する」とするマルクスの用語/概念があまりに流行してた為、それを否定するニュアンスもあったとも。実はロシア革命以降広まった民主集中制はむしろシュミットの立場に近い。
しかし「政治的対立の図式それ自体は現実と無関係に成立し進行する」とは、裏を返せば政治と実際の歴史の無関係性をも示しているのである。バロック様式の勇壮さがロココ様式の華美と表裏一体の関係にあった様に、新古典派様式の質実剛健さはウジェニー皇后が第二次帝政期にリバイバルしたルイ16世の治世を席巻したマリー・アントワネット王妃の優美な生活様式と表裏一体の関係にあった。そしてこれらの様式はその表面的な政治的対立図式と無関係に芸術様式としてしっかり連続性を保っている。そもそも手掛けた芸術家層まで二分されていた訳ではないのだから当然の話とも言える。
その一方で(未読などであくまで憶測だが)カール・シュミットがこういう人物である以上、その彼が第二次世界大戦下に著した「陸と海と(Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung、1942年)」は「我々の敵たる"海の国"、つまりイギリスとアメリカは我々と友たる”陸の国”欧州諸国(都合によりスペインもこちら側)によって殲滅されつつある(ポルトガルやイタリアについて触れるとややこしくなるので無視)」と読むのが正しいのでは? そもそも友敵理論でも持ち出さない限り「陸の国」と「海の国」を厳密に区分けする事なんて出来ないし、区分けする意味もない。
政治学者カール・シュミットが書いた 『陸と海と』 は日本の運命を考える上でも必読書だ!(2012年1月4日)
要約してしまえば、人間の生存条件ではそのそも「陸」にあったため、どうしても「陸」の視点からものを見がちだが、「陸」から「海」へと行動範囲が拡大し、旧約聖書の『ヨブ記』の象徴的な表現を使えば、ビヒモス(=クマなどの陸の怪物)から「リヴァイアサン」(=クジラなどの海の怪物)へと中心がシフトしたのが、近現代史の特色である。
陸の国の海の国に対する戦い、海の国の陸の国に対する戦いが世界史である、というのがシュミットの基本的立場である。副題の「世界史的一考察」とは、ブルクハルトを意識したものだろうか。
しかも「陸」と「海」につづく第3のエレメントとしての「空」が人間の行動範囲のなかにはいってくる。いいかえれば制海権から制空権へのシフトである。二次元の平面から三次元の立体への視野の拡大である。
こうした紹介文を読んでも、現代人には同時代に発表された石原莞爾「世界最終戦論(1940年)」の仲間としか思えない。それが普通の感覚なんじゃないの?
五味川純平「戦争と人間(1965年〜1982年)運命の序曲2」
張作霖爆殺事件(1928年6月4日)と石原莞爾の満州赴任(当時中佐)
「……君は、旅順にいる参謀の石原中佐を知ってるか?」
「名前だけはね。まだ会ったことはない」
「そのうちに紹介するよ」
伍代喬介は、それきりものを云わなくなった。彼は、このとき、世人がずっと後年になって、石原莞爾の着想と信ずるようになった満洲占領計画を考えていたのである。
喬介としては、青年連盟の面々が気焔をあげて在満邦人を煽ってくれることは、都合がよかった。石原参謀の軍事計画を実現に近づける上に好材料を提供してくれるからである。その意味では、青年連盟の活動も無価値ではない。
石原莞爾が張作霖事件の四ヵ月後に関東軍参謀として旅順に赴任してから、間もなく、喬介は石原構想のなかに喬介自身の長年の野心の鮮明な青写真を読み取ることができた。石原の世界最終戦の構想に共鳴したのである。
石原莞爾 - Wikipedia
石原莞爾について石原は大の日蓮の信者で、そのことは早くから軍部外にも知られていたとみえる。彼が少佐のときにドイツ駐在を終えてシベリア経由で帰国の途中、ハルビンに降りると、日蓮信者の邦人数十名が南無妙法蓮華経の幟を立てて駅頭に出迎えたほどである。軍学の大家で日蓮信者であるということが、日蓮宗徒には救世主の如く見えたのであろうか。
八紘一宇 - Wikipedia
田中智學 - Wikipedia
立憲養正會 - Wikipedia石原は、本来、徹底的に科学的でなけれならぬはずの戦争論に日蓮の「前代未聞の大闘諍、云々」という〝御託宣〟を持ちこんで、それを天皇崇拝に結びつけ、必勝の信念を強調した。彼は自分を天才と過信していたのかもしれない。
国家を戦争によって隆盛へ導くつもりで、彼自身が設けた陥穽に落ちこみ、国を誤る重大な一つの契機を醸成しつつあったが、伍代喬介は石原参謀の日蓮坊主臭さなどは、どうでもよかった。喬介は石原の戦争をもって戦争を養うというナポレオン流の考え方が気に入ったのである。石原の戦略論が、満蒙を領有して日本が世界の覇者となるための最終戦の拠点としていることが、喬介の日ごろの野心と完全に一致したのだ。
石原は、日本が満蒙を領有して住民を「救済」すれば、列国の干渉がはじまり、遂にはアメリカと戦うことになると予言しているが、これが彼の云う最終戦となるもので、その時期の決定に三つの要素を措定している。その一は、日本が東洋文明の中心に位置すること。その二は、アメリカが西洋文明の中心に位置すること。その三は、飛行機が無着陸で世界を一周し得ること、である。一は、軍閥抗争に明け暮れている中国を見ては、日本人の大半が日本が東洋文明の中心を占めるのは当然と考えていたことである。二は、世界大戦(第一次)によってヨーロッパのほとんどの国がアメリカの債務国となったのを見ては、だれしも予想したことである。三は、一九二七年(昭和二年)五月にリンドバーグが大西洋無着陸横断飛行を敢行してからは、決して夢想ではなくなったのだ。したがって、以上の三つの要素を措定するには、必ずしも天才の閃きを必要とはしないのである。石原構想が非凡に見えたのは、たぶん、彼のはったりとケレン味のせいであったろう。
日露戦争でかろうじて面目をほどこしたものの、苦い経験を積み、欧州大戦が長期持久の甚だしい消耗戦となったのを見た軍の一部では、従来の即戦即決主義を超えて、持久のための国家総動員計画を考える必要に迫られた。日本が満蒙進出の方針を捨てないかぎり、常に戦争の危険はあるからである。
石原莞爾がはったりをきかせて神がかった戦略論を振りかざしはじめる前から、国内政治諸力の虚実を測りながら、国家総動員計画を培養していた軍人がいる。永田鉄山である。
石原などは、永田が時間をかけて育成していた国家総動員計画の一端を担ったにすぎないと思われるが、永田・石原を結ぶ線は、満洲事変前ほぼ一年間を除いては、奇妙に史実の裏面に埋伏している。それだけ、永田の計画は深く静かに潜行していたと考えるほかはないようである。
エーリヒ・フリードリヒ・ヴィルヘルム・ルーデンドルフ(Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, 1865年〜1937年)
ドイツの軍人、政治家。第一次世界大戦初期のタンネンベルクの戦いにおいて第8軍司令官パウル・フォン・ヒンデンブルクを補佐してドイツ軍を勝利に導いた。
大戦中期から後期には参謀本部総長となったヒンデンブルクの下で参謀本部次長を務め「ルーデンドルフ独裁」とも呼ばれる巨大な実権を握った。最終階級は歩兵大将。
戦後はアドルフ・ヒトラーと結び、ミュンヘン一揆を起こした。『総力戦(1935年)』の著者としても知られる。この著作においてルーデンドルフは戦争と政治の関係が変化した結果として政治そのものが変化したとして、総力政治の概念を導入して総力戦の必然性を論じた。
- クラウゼヴィッツの『戦争論』(1832年)で展開された理論が時代の変化に対応できずに陳腐化しており、またこれを研究することは混乱を招くものとした。そもそもクラウゼヴィッツが生きた時代での戦争は国民とは別に政府と軍隊だけによって行われるものであり、これは過去のものとなった。
- 戦争の性質を変えたのはフランス革命であったが、19世紀には本質的な暴力性は表面化していなかった。しかし第一次世界大戦で戦争の様相は変化したのであり、国民も戦争に貢献することが求められるようになったのである。こうして戦争の本質が変化したことであり、したがって戦争と政治の関係、特に政治の本質が変化したのである。
- クラウゼヴィッツは政治の価値を戦争の価値より重視しており、戦争指導を政治・外交に従属させていた。しかし政治の任務はより拡大したのであることを考えれば、総力的な戦争、総力戦と同様に総力的な政治、総力政治を実施しなければならない。戦争が国民の生死を決める最も重大な緊張であるために、総力政治は平時から国民に闘争の準備を進める。そのために政治は戦争に寄与しなければならない。
- さらに総力戦では従来の軍事力の要素であった兵員や兵器だけでなく、非軍事的要素も含まれるようになる。海上封鎖や経済制裁によって物資の補給を阻止する経済的な攻撃や、国民の士気を削ぐためにビラやラジオ放送による心理的な攻撃を与えるため、政治は戦争の要求を満たさなければならない。したがって総力政治は国民士気を維持して共同体の維持を促進する。
- 総力戦は政治権力の中枢から指導される必要があるために軍部指導部、特に最高司令官の元で一元的に指導されなければならない。最高司令官は総力政治のために軍事的な戦争準備だけでなく、財政、商業、生産、教育を指導する。
この著作の刊行後にその理念の一部は第二次エチオピア戦争やスペイン内戦で現実のものとなったが、ヒトラーは第二次世界大戦の開戦においてこの理論を排除している。つまり軍人が国家を指導するのではなく、政治家ヒトラーによって軍人を統制することが徹底されていた。日本では永田鉄山や石原莞爾がルーデンドルフを深く研究するなど、ドイツに留学・駐在を経験した武官を中心に、昭和期の日本陸軍の思考に大きな影響を与えた。

床次竹二郎一派の楊宇霆詣りというのは、前年の晩秋のことである。民政党を割って新党倶楽部を作った床次は、中国視察旅行に出て、奉天をも訪れた。床次の新党倶楽部は院内勢力としては、彼の皮算用ほどに大きくはならなかったが、床次自身は権力の帰趨に敏感な政界の惑星である。彼の民政党脱党は、民政党の「軟弱」と非難される対支政策に対する反対の表明であって、対支強硬政策を一枚看板とする田中・政友会に同調するためと一般に信じられていたから、張学良としても床次の来訪を重要視せざるをえなかった。
その床次が、張学良邸での晩餐会では、会談を儀礼的なものにとどめたのに反して、その帰途、楊宇霆の屋敷に立ち寄り、ここでは余人を遠ざけて、密談長時間に及んだ。これを知った張学良が疑惑を抱いたのは当然である。学良は日本が楊宇霆を満洲の主権者として擁立するものと猜疑したにちがいない。それでなくても、長年にわたって亡父・作霖の右腕であった楊宇霆に対して、若年の張学良はいつもひけめを感じていたのである。
床次訪問は、楊宇霆暗殺の確かに動機の一つとはなっただろう。けれども、もっと作為的に張学良の心理を楊宇霆抹殺へ傾斜させた者がいる。その作為者が張学良側近のなかにいたとしても不思議はないが、ここでいうのは、それではなくて、日本人のことである。
張学良が楊宇霆の存在を気にして、猜疑心を次第に深くしていたところへ、ある日、一冊の書が贈られた。日本外史である。豊臣家滅亡のくだりには赤丸を印してあって、その寓意は、東三省の実力者楊宇霆を徳川家康になぞらえ、若年の張学良を豊臣秀頼の立場に置き、秀頼が家康から滅ぼされたのと同じように、学良も楊宇霆から滅ぼされる運命にあることを暗示しているようであった。張学良の秘書陶尚銘が後日語ったところによれば、張学良はこの日本外史の示唆によって楊宇霆の即時暗殺を決意したというし、日本外史の贈り主は大川周明博士であったという。
張学良が楊宇霆を暗殺したのは、そのこと自体は外国の権力関係の出来事と見えるが、日本との利害の複合作用によることは明らかである。
鉄道問題交渉のために奉天へ派遣されたかつての張作霖顧問・町野武馬は、張学良から交渉を回避されたので、やむなく楊宇霆と交渉し、吉会・長大両線の敷設契約実行の声明を出す約束を取りつけた。楊宇霆はその夜殺されたのである。
張学良の側では、権力関係と外交問題が一つの決着点に到達しつつあったし、日本の側でも、満蒙権益の一部が画餅に帰するか否かの瞬間に近づきつつあった。
楊宇霆を殺した学良は、翌日、部下の王家楨を日本総領事館へやって、殺害の事実と、それが対日関係には何の変化をも及ぼさないことを伝えさせたが、鉄道問題に関するかぎり、これは、事実上、白紙還元を意味するにひとしかったのだ。
大川周明は、楊宇霆抹殺が日本の利益となると考えたか、張学良の対日硬化を予想して逆にそれを奇貨とすべしと考えたか、あるいは張学良の懐柔を考えたか?
おそらく、そのいずれでもないだろう。彼は、大正から昭和年代へかけての右翼国家主義の指導者の巨頭と目されている。この巨頭は、いかなる種類の建設にも従事せず、常に破壊の背景にあった。それでいて、牧野伸顕(内大臣)との関係などを見れば、上流社会の急所へ取入ることは巧妙だったらしい。
彼が政党政治破壊の歴史劇に登場する時期は近づいているが、少し先走って云えば、彼は「日本精神」とか「日本的」とかいうきわめて不得要領な概念がそのまま肉体を持ったような人物である。学者でありながら、神がかった性癖の持主で、これも彼の処世術の演出であるのかもしれない。
陰謀を指導するほどの緻密な計画性も実行力もないくせに、昭和六年の三月事件、十月事件、昭和七年の五・一五事件に関係している。
三月事件(昭和6年(1931年)3月20日決行予定のクーデター未遂事件)
十月事件(昭和6年(1931年)10月決行予定のクーデター未遂事件)
五・一五事件(昭和7年(1932年)5月15日勃発した反乱事件)敗戦の東京裁判ではA級戦犯二十八被告の一人となりながら、法廷で東条英機の禿頭を叩いたりして、発狂を理由に審理を免れ、松沢病院に入れられた。入院中に「精神異常者」であるはずの彼は、難解の書コーランを全訳するという「奇蹟」を現わした。退院後、張作霖事件で有名な河本大作の告別式(昭和三十一年一月三十一日)には、その案内状に名文を起草した。とにかく、彼は、非合理が合理以上に幅をきかす国では有名になる資格を充分に持った奇怪な人物であった。
その大川周明が、張学良に、豊臣秀頼の運命を暗示するために、日本外史を贈ったのである。もっとも、陶尚銘の後日談以外に、大川周明が贈ったという証拠はない。証拠がなければ殺人犯人も無罪であるという論法からすれば、彼も楊宇霆暗殺の教唆者であることを免れるかもしれない。けれども、彼が関係した事件は悉く暗殺の既遂・未遂事件であり、五・一五事件の訊問調書では、陶尚銘の談話を裏書きするかのように、語るに落ちている。
国家主義運動の巨頭と仰がれた人物の、張学良・楊宇霆にかかわる部分の陳述は、こうである。
『(前略)……昭和三年五月張作霖の爆死事件が突発した。我々は此の事件が日本の満洲政策に一転換期を与へる事を切望したのでありましたが(中略)……
張作霖の後を嗣いだ張学良氏は其の時二十八歳の青年であり 其の人物を見抜いた日本人は殆どなく 概ね無為の御曹子と評価して居り 之に対して作霖時代から勢力を揮って居った楊宇霆が居る
そこで作霖死後日本の当局者間に起った問題は今後誰を中心に対満交渉を続けて行くかと云ふ事です 即ち形式的には学良氏の満洲政権継承を承認するが実際の談判相手として学良楊宇霆の熟れを択ぶかと云ふ事であります(中略)
私は数度の会見に依って当時日本人間に行はれて居た学良氏の評償が甚だしく実際と相違せる事を知った 例へば彼が阿片中毒で人と対談中でも席を外して三十分毎に注射しなければならぬと云ふ噂が殆ど真実として通って居た
然るに実際は私と四時間以上も対座し其間始終端然として頭脳は最後迄極めて明晰毫も評判の如き中毒を認めなかったのみならず 相当の所迄打明けて色々の話をしたが 私は彼が容易ならぬ人物である事を認め 其の大胆と俊敏と狡猾とを知り 此の人を坊っちゃん扱ひにする事の甚しく誤れる事を覚り 吉会鉄道問題を初め満蒙諸懸案の談判相手は楊宇霆ではなく学良氏にしなければならぬと考へました(中略)
然るに多年楊宇霆を相手に商取引を行って来た大倉組は学良中心を喜ばず極力之に反対して楊中心の運動を猛烈に行った 私は資本家の力が日本の政局に如何に大なる影響を与へ得るか此の時に切実に目撃した 大倉組の努力は実に参謀本部を動かし政府当路を動かして 学良は無視せられ 交渉は実際に於て楊中心に行はれるに至ったのであります
此の間学良は自ら韜晦して日本に馬鹿にされて知らぬ顔をして居たが 翌昭和四年正月十日突如楊宇霆及び其の腹心常陰槐を殺し楊派の勢力を勦絶して了った 私は此の正月から四月迄奉天、北京、上海の間を往復して居たのでありますが 学良が楊を殺した翌々日の朝に彼を訪問しました(中略)
常陰槐の逮捕・処刑行って見ると神色自若として居る 自分と楊とが両立出来ないのは豊臣秀頼と徳川家康とが両立出来ないと同じで 今度の事は張家の為止むを得なかったのだと平気で話した(後略)』
大川周明は資本家の利権による国策の壟断を憎み、したがって、それに加担したかに見える楊宇霆を、学良を用い用いて誅戮し、資本家の企業を挫折させたかったにちがいない。豊臣秀頼と徳川家康の話を学良がしたと大川が調書で述べているのと、学良の秘書の陶尚銘が日本外史の贈り主は大川であったというのとは、単に偶然の符合とは考えられない。一冊の史書の効用によって、国の内と外に計略をめぐらすのは、陰謀好きな学者の考え出す手段としては妙手というに値しよう。
「五族協和」と「日本人優越主義」
「落ちついとるな、君は」
喬介は厭味をまる出しにした。
「先月、本渓湖の邦人経営の石灰山が、支那官憲によって作業場を破壊されてだ、強制閉鎖されたが、これも大したことではないな?」
「あれは付属地外ですから、経営者が支那人と個人的に契約していたのを、懲治盗売国土暫行条令にひっかけられたものです」
「その条令は、いつ出た?」
「まだ成文化されてはいません。管内各地方官に密令の形で伝達されている模様です」
「そんなものを承認するのかね」
「付属地外ですから、簡単には片づきますまい。柔軟な、弾力のある交渉をしなければならないと思いますが……」
「君らの云う柔軟は、われわれの云う軟弱と同義語だろう。君は新顔だが、詳しいらしい。教えてもらおう」
喬介がニタリとした。
「〝日鮮人土地租借禁止〟に関する訓令、というのがあるな?」
「あります」
「あります」
「朝鮮人土地耕作取締に関する訓令、というのもある」
「そうです」
「みんな奉天省だ」
「そうです」
「あります」
「朝鮮人を締め出し、ひいては、日本人を締め出そうとする法令だ、みんな」
篠崎は喬介の烈しい視線をじっと受けとめていた。
「外交官諸君は、東三省政権の法令によってがんじがらめになっても、没法子だというのかね?」
「朝鮮人は気の毒です」
篠崎の眸が暗くなった。
「東北政権から見ると、満洲に入る朝鮮人は、日本の満洲侵入の先鋒だという見方が一つと、共産主義を満洲に持ちこんで来るバチルスだという見方が一つあります。どっちにしても、無視することはできないんです。ですから、朝鮮人は共産主義者であっても、なくても、東北政権の迫害を受けることになります」
「それを坐視するのかときいているんだ」
喬介は大声を出して、急に思い直したらしく、調子を変えた。
「君にどなっても、しようがないな」
「伍代さんは融和の方法をお持ちですか?」
「なくもない。あるだろう」
「教えていただけますか?」
「民族各々その程度、その適性にしたがって、共有の天地に適所を占める……」
「幻想的ですね」
篠崎が眼を細めて笑った。
「伍代さんはリアリストだと思っていましたが」
「構想雄大となるとな、片々たる文書の字句をほじくるような近視眼者流の糞リアリストには、実現不可能としか見えんさ」
「うかがいましょうか、その雄大な構想を」
「満洲は、元来、満洲族のものであって、漢民族のものではない。それを、漢民族が移入して来て、満洲旗人より多くなったから漢民族のものだと主張する。これを混同するから、問題がややこしくなる。いまや、満洲はだれのものでもない。日、朝、満、蒙が共に生活している。みんなが栄えれば、文句はない……」
「森恪さんや、石原さん流の考え方ですね」
「森恪や石原莞爾が考え出したことではないよ、君。満蒙の現実が、それを示しているんだ。教えているんだ。現実の教えに従わないのは、霞ヵ関の貴公らだけだよ」
「先をうかがいましょう」
「諸民族のうち、現在の段階で最も進歩しておるのは日本人だから、日本人が指導する。これは理の当然だ」
「つまり、満蒙の支配ですか」
「指導だ。政治指導、経済指導だ。それに、北にソ連をひかえておる。防衛ももっぱら担当せねばならん」
「日本の支配、いや、指導でも結構ですが、これを、日本人よりはるかに数の多い漢・満民族が拒否したら、どうなりますかね?」
「机上の空論を現実にあてはめないで、現実を見てみたまえ。全満を歩いてみることだ。君もウィットフォーゲルぐらい読んどるだろう。民衆は惨苦の茅屋に呻吟しておる。同族の軍閥・政権の支配下でだ。日本はこれに一大変革を加えようというんだ。理想の大道に障碍があれば、排除することは当然だろう」
「……つまりは、武力行使ですね」
篠崎がひとりごとのように呟いた。
「御説はよくわかりました。本省でも、追々、そういう考え方が出て来るのではないかと思います」
「結構だ」
伍代喬介の傲った耳には、このときの篠崎のことばは、うわべしか聞こえなかったようである。
カール・アウグスト・ウィットフォーゲル(Karl August Wittfogel、1896年〜1988年)
ドイツで生まれアメリカに帰化した社会学者、歴史学者。ドイツ語では「ヴィットフォーゲル」とも表記される。フランクフルト学派の一員であったほか、東洋史、とりわけ中国研究において活躍し、「中心」「周辺」「亜周辺」といった文明における三重構造の概念を提示した。
- ニーダーザクセン州ヴォルタードルフで生まれた。フランクフルト大学で学ぶ。早くから社会主義運動に加わり、ドイツ独立社会民主党員をへてドイツ共産党員となった。
- 青年期より中国に関心を抱き、中国の社会経済について研究を進め、官僚制の起源とされる四大文明が河川の流域に位置し水利事業と大規模灌漑農業に基づいた共通点から水力社会と名づけた。また、周辺民族が中国に同化されるという従来までの理解を改め、遼・金・元・清を「征服王朝」という概念を通じて考えた。
- 1933年にナチスが政権を掌握すると一時投獄されるが、その後アメリカに亡命してアメリカ国籍を獲得。このころ中国にも訪れている。第二次世界大戦後はパトリック・マッカランの委員会に加わるなど反共主義に転向し、ワシントン大学などで中国史を教えた。
- なぜ西洋や日本のようなウィットフォーゲルが文明の「亜周辺」と呼ぶ最も資本主義が発達した地域から離れた北アジア、中央アジアを抱えるソ連やモンゴル人民共和国から社会主義革命が起き「亜周辺」の対極にある中華人民共和国、エジプト、イラク、インド、パキスタンなどは五カ年計画によって計画経済が敷かれ、非同盟を掲げつも中東戦争や印パ戦争ではソ連や中国と軍事協力するなどかなり似た体制をとってたかという問題について、アジア的生産様式の概念を利用して「アジア的専制政治」として説明した。
「亜周辺」というのは、ウィットフォーゲルの理論をもとにした分析フレームワークである。「中心(core)-周辺(margin)-亜周辺(submargin) という三層」で文明を論じたもので、日本は「亜周辺」に位置づけられる。著者自身の表現を引用しておこう。
- 「<亜周辺>とは文明史において、その文明を成立させた地域の外側で、その文明の強制を受けることなく、その文明の諸要素を自由に受け入れた地域、具体的にはユーラシア大陸の西端の西ヨーロッパと東端の日本を指すものである(ウィットフォーゲル)。
- そこでは、中心の文明に教条的に制約されることなく、先行する社会を下敷きにして、独自な文化を展開させることができた。この前近代の歴史において観察される文明のメカニズムから近代文明の未来を考える上でのヒントとして利用できるものがある(出典:「亜周辺と知識人-『「東洋的専制主義」論の今日性』を書き終えて-」(2008年4月1日 「本と社会」 新評論社のニューズレターより 太字ゴチックは引用者=さとう)。」
中国社会の研究者であるウィットフォーゲルは「日本は東洋的世界ではない」としているのである。
さらに湯浅氏は、「封建制」と「武人社会」がもたらした多元的社会は、専制国家である中国・コリアとは根本的にことなることを強調している。封建制が「亜周辺」である西ヨーロッパと日本においてのみ出現したことの意味を考えるヒントがこのフレームワークにあるのだ。海洋国家日本とユーラシア大陸の根本的な違いと言い換えてもいいだろう。
ウィットフォーゲルのこの仮説はその理論通りにスターリンや毛沢東が自然改造計画や大躍進政策と称して運河やダムの建設や灌漑農業の集団化に邁進していた当時では反響が大きく、同じく中国を研究するジョゼフ・ニーダムからは反論を招いている。
20世紀を強迫概念的に席巻した「最終戦争不可避史観」は既に過去のものになった。それに納得できない人達が今日なお戦い続けている…