実際の大学の博士課程にある人は、歴史についてこういう悩み方をしてるのですね。
やはり博論ではデュルケーム入れなければ駄目か。
— هريرة (@_hurayra) May 28, 2018
問題はデュルケムの社会的連帯論が集合意識−社会と展開していくのに対して、ハルドゥーンは「文明」という枠組みの中で、連帯意識論から王朝(ダウラ)論へと展開していく点。
— هريرة (@_hurayra) May 28, 2018
「社会」に相当する概念がなぁ…。
さらに問題なのはハルドゥーンにおける諸概念の定義。本人が厳密に定義してないので、研究者毎の用法が多様すぎ、解釈の余地がありすぎである。
— هريرة (@_hurayra) May 28, 2018
ハルドゥーン、「社会」(に相当するもの)の統合力は…概念化して…ないかなぁ…。
— هريرة (@_hurayra) May 28, 2018
イブン・ハルドゥーン大学からイブン・ハルドゥーン関係の論集が刊行されたよという情報をもらう。
— هريرة (@_hurayra) May 30, 2018
イブン・ハルドゥーン大学がどういう関心・論調でハルドゥーン学に取り組んでいるか知るのにいいのだが、トルコ語…。
— هريرة (@_hurayra) May 30, 2018

イブン・ハルドゥーン(Ibn Khaldūn、1332年〜1406年)はイスラム世界を代表する14世紀の歴史家。チュニス(現チュニジア共和国、歴史上有数の世界都市の一つ)生れ。祖先は南アラブ系(ハドラマウト)でセビリャの支配貴族であったが、イベリア半島におけるレコンキスタ運動の進行もあって13世紀半ばにチュニスに亡命した。
*ハドラマウトといえば東ローマ帝国とササン朝ペルシャの戦争が泥沼化してアラビア半島沿岸部が代替交易路として栄えた6世紀以降台頭し、アフリカ大陸やイベリア半島や東南アジアに進出した国際的商業民族。ユーラシア大陸を闊歩した(インド南岸が本拠地で東南アジアを超え中国や朝鮮半島や日本列島といった東アジアまで中声貿易網に絡め取った)タミル人や(中央アジアのオアシス交易を支えた)タジーク人と並ぶ存在だが、地中海や黒海の沿岸を制したフェニキア商人の時代(紀元前10世紀〜紀元前後)において既にインド南岸の「黒い女神」の意匠が地中海沿岸に伝わっている事から、当時より既にユーラシア大陸全域を結ぶ国際的中駅貿易網にアラビア半島沿岸部も相応の形では組み込まれていたと考えられている。幼くして諸学を修めた後,北アフリカ,イベリア半島の諸スルタンに仕え,波乱万丈の政治生活を送ったが,その悲哀を感じて隠退するとともに,膨大な《歴史序説al‐Muqaddima》と世界史に当たる《イバルの書Kitāb al‐‘ibar》を著した。
1399夜『歴史序説』イブン=ハルドゥーン|松岡正剛の千夜千冊
イブン・ハルドゥーンが書き上げた『歴史序説』は、初めて「文明」というものを思想の裡に抱握した画期的な大著作だった。この男にとっては「文明」とはそのまま「人間社会」のことだったから(そのように見たのはイブン・ハルドゥーンが最初だ)、これはまさしく「人間社会についての初めての学」が成立したということだった。
はたして西洋の歴史家たちはこのことに気がつくとギョッとして、さすがにその後はイブン・ハルドゥーンを畏怖をもって読んできた。「歴史は社会変化によって変質していく」ということを世界史上初めて説明しえたのが北アフリカの一人のムスリムだったことを、悔しくとも認めざるをえなかった。
ヨーロッパはイブン・ハルドゥーンによって、初めて歴史社会学の構想と可能性を教えられたのである。
それでも、アーノルド・トインビー(705夜)がイブン・ハルドゥーンを「トゥキデュデスやマキャベリの著作に匹敵する大著作をものしたアラブの天才」と絶賛してから、ずいぶんの月日がたつ。ヨーロッパの多くの識者たちが「アラビアのモンテスキュー」と称賛してからもだいぶんがすぎた。まさしく彼は「アラビアのモンテスキュー」であり、「イスラームのヘーゲル」だった。いや、それ以上の「何者」かであったのである。
1382年,マムルーク朝下のカイロに移住し,学院の教授になったり,マーリク派の大カーディーとして裁判行政に尽くしたりしたが,その間,ティムールの西アジア遠征に対する防衛軍に加わり,ダマスクス郊外でティムールと会見したことがある。
ティムール(Tīmūr/Taymūr,、1336年〜1405年)
ティムールはサマルカンドのグリ・アミール廟(アミールの墓)に眠っている。その棺の裏には「私がこの墓から出た時、大きな災いが起こる」と刻印されていた。
1941年、ソ連の調査団が開封し、ティムールの脚の障害などを確認した。その3日後、バルバロッサ作戦(第二次世界大戦のドイツのソ連侵攻)が実行された。これに恐怖を感じたソ連は棺を鉛で溶接した。これ以後この棺は開封されていない。多くのイスラム教徒は,預言者ムハンマドの範例・慣行(スンナ)をその伝承(ハディース)の研究を通じて知ろうと試み続け、それこそが(信仰上も重要な意味を有する)歴史研究と信じてきた。
*この辺りが(その多くが多様で多態的な形で歴史的事象由来と設定される)戒律の世界と関係してくるから難しい。だからギリシア語の史書がアラビア語に翻訳された事例はないが,明らかにギリシア的精神を継承する時間と空間との両軸において未知の広い世界を探ろうとする試み自体はイスラム教圏にも細々と存在し続ける。「アラブのヘロドトス」として知られる地理学者マスウーディー(896年〜956年、十二イマーム派のシーア派)も歴史についての抽象的な考察を行っているが,一歩進めて歴史発展の法則性を探ろうとしたのがイブン・ハルドゥーンで,大著《歴史序説》を残した彼は前近代における世界で最も独創的な歴史家といわれる。
マスウーディー(896年〜956年) - Wikipedia
14世紀のアラブの歴史哲学者イブン・ハルドゥーンは彼を「歴史家のイマーム」と表現している。
その旅行先はアルメニア、アゼルバイジャン地方、カスピ海ほとりの各地を含むペルシアのほとんどの州。さらにはアラビア、シリア、エジプトも。インダス川流域だけでなくさらにその先のインド亜大陸の西海岸まで足を延ばしている。東アフリカへは一回のみならず何度も往復した。航海した海もインド洋のみならず、紅海、地中海、カスピ海も。研究者によっては、スリランカと中国にも行ったとする。マスウーディーの著作を英語に翻訳したLunde & Stone(1989年)は、その翻訳書の序文でこう書いている。「マスウーディーはペルシア湾岸で出会ったアブー・ザイド・アル=シーラーフィー(Abu Zaid al-Sirafi)という人物に、中国についていろいろと教えてもらった。また、シリアでは、かつてビザンツ帝国の提督であってイスラームに改宗したトリポリのレオという人物に会い、ビザンツ帝国のことについても多くの情報を得た。亡くなるまでの数年間はシリアとエジプトで暮らし、エジプトでは、アンダルシアの司祭が記録したというクローヴィスからルイ4世までのフランク王国の王の名前の一覧を手に入れた」。ところでイブン・ハルドゥーンも,学問の研鑽の最高の方法は,各地の偉大な学者から教えを乞うために旅をすることだと述べている。多くのウラマーにとって,学問を求める旅は特別のことではなく,普通の生活の一部となっていたのであった。
*この辺りはアジアにおける仏僧の国際的交流や「書斎ごと欧州中を転居して回った」ルネサンス期の人文学者の生き様にも見て取れる。こうした旅に重きをおく知識の在り方は(アレキサンダー大王の東征(紀元前334年〜紀元前323年)からプトレオマイオス朝エジプト(紀元前305年〜紀元前30年)滅亡の間にオリエント全域を席巻した)ヘレニズム時代やマニ教の国際的流行(全盛期3世紀〜9世紀)を契機にユーラシア大陸じゅうに広まったコスモポリタン意識と密接な関係があるとも。ならばそのさらなる大源流は古代中国や古代ギリシャの様に比較的均質な人種集団が無数の都市国家に分割統治され、何か政変がある都度、敗北側が他国に亡命してきた伝統的慣習まで遡れるのかもしれない。
この偉大な歴史家の名前が日本では吃驚するほど知名度がない事と、日本の歴史学が世界に通用しないのは表裏一体の問題と考えられそうです。
*元来「中央集権の正当性を特定の個人が体現する」絶対王政なる政体は、そのシステム自体への言及自体を一切許さない。「国主供給国がコロコロ変わる」ナポリがその抜け穴となった事には歴史的必然生すら存在したといえる。


- 「時間と空間との両軸において未知の広い世界を探ろうとする」科学実証主義的態度自体は、とりあえず「(デカルト(René Descartes、1596年〜1650年)が「理性を正しく導き、諸科学において真理を求めるための方法」として代数と幾何学の統合を試みる過程で発案した)直行する評価軸の集合体」なる概念に立脚する「N次元空間」成立まで遡り得るが、実際の科学実証主義的歴史学の起源はこれをさらに批判的に発展させて「(それぞれが成立に至るまでのエピソードとセットで記録され、さまざまな次元からの多様で多態的な反証性を保持する)歴史的事象の集合体」へと還元した「年表空間」を提案したジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668年〜1744年)の「学問の方法(De Nostri Temporis Studiorum Ratione、1708年)」や「新しい学(Principi di scienza nuova、1725年)」の世界観を大源流とする。
【中公文庫5月の新刊】『新しい学(上下)』ジャンバッティスタ・ヴィーコ 著 上村忠男 訳
— 中公文庫(中央公論新社) (@chuko_bunko) May 22, 2018
デカルトの科学主義に立ち向かい、人間の歴史の価値に光をあてるヴィーコ。古文献・風習・言語・芸術・貨幣などを読むことで、〈真なるもの〉に迫る。https://t.co/TN4XqCTJmj pic.twitter.com/QANsiEivYk874夜『新しい学』ジャンバッティスタ・ヴィーコ|松岡正剛の千夜千冊
インヴェスティガンティ(investiganti)という言葉がある。探求者という意味だ。
17世紀半ば、このインヴェスティガンティとして新しい科学や学問をめざす動きが各地に生まれた。デカルトやガッサンディやライプニッツがそういう一人だった。ナポリにもそういう動きが入りこみ、小さなインヴェスティガンティ学会のようなものができていた。
ジャンバッティスタ・ヴィーコはこの動きの最後の舞台に登場してきた思索者もしくは構想者もしくは教育者である。それまでの動きを覆すような、インヴェスティガンティをめざしたヴィーコのその両手には、「クリティカ(反証性の保証)」と「トピカ(どんな事物や現象についての知識もそれをトポス(分母の場)から切り離さず、それどころか後から発見しやすい仕組みをあらかじめ組み込んでおく発想)」という二つの方法の剣が握られていたのであった。*「批判的検証」…真理(どこまで詳しく検証しても矛盾が露呈しないというて点で正しい仮説。後期ハイデガーいうところのアレーティア(Aletheia=脱 - 秘匿性)にも対応)と虚偽(詳しく検証すると矛盾が露呈して存続不可能となるという意味合いにおいて誤った仮説)を最初から時空間的展開から切り離して厳密に峻別する「普遍の学(マテーシス・ウニヴェルサリス)=デカルト的でライプニッツ的な代数解析的方法論」に対抗すべく「真理は作られたものに等しいはずだ」と主張した。すなわち自然や世界には先験的に真理なるものなどはなく「(それ自体が時間経過の過程で変遷していく各時代や各地域の歴史感覚の影響を受けて変遷していく)共通感覚(センスス・コンムーニス)から出所するものとしたのである。こうした志向様式の導入によってジャンバッティスタ・ヴィーコはある意味「(元来、それまでの伝統的認識においても「神の領域」においてのみで実在可能で、現世の人間には到達不可能と解釈されてきた)真理(Idea)の世界そのもの」を仮想化(Virtualization)する事に成功し「社会が知識を蓄積し、これから導出される世界観の変化に基づいて自らの振る舞いを変化させていく」という新たな歴史観を創出する事に成功したのだった。
-
こうした考え方が台頭したのは「戦争遂行の為に臣民や国内資産を最後まで全て動員可能な官僚制によって常備軍が維持される」主権国家の国際的台頭期だった。とはいえ大英帝国やフランス絶対王政の様な成功例ばかりでもない。
*オリエント世界におけるアケメネス朝ペルシャの最終的勝利、古代ギリシャ世界におけるマケドニア王国の最終的勝利、エルトリア人やフェニキア人やギリシャ人に対するローマ人の最終的勝利、そして古代中国における秦の最終的勝利…当時の世界においては広域を支配する強国が台頭する様な大事件は常に片田舎で始まった。欧州の場合は神聖ローマ帝国皇帝とローマ教皇が「欧州の覇権」を争っていた時代、こっそり「裏舞台」で繰り広げられてきたイベリア半島におけるレコンキスタ運動(718年〜1492年)、ヴァイキング(及びヴァリアリーグ)とその末裔達の暗躍(9世紀〜12世紀)、そして英仏百年戦争(英Hundred Years' War、仏Guerre de Cent Ans、1337年 / 1339年〜1453年)などがこれに該当する。*そして英国においては薔薇戦争(Wars of the Roses、1455年〜1485年 / 1487年)と清教徒革命(Puritan Revolution または Wars of the Three Kingdoms、狭義1641年〜1649年、広義1638年〜1660年)、フランスにおいては公益同盟戦争(1465年〜1477年)とフロンドの乱(Fronde、1648年〜1653年)によって絶対王政化を志向する王権と伝統的均衡状態を保ってきた大貴族連合が自滅し「戦争遂行の為に臣民や国内資産を最後まで全て動員可能な官僚制によって常備軍が維持される」主権国家への本格的変遷が始まったのだった。
*実際、同様に絶対王政化を志向したオランダ総督オラニエ=ナッサウ一族は都市貴族との対立に苦しめられたし、北欧諸王朝の絶対王政化も完全なる失敗に終わっている。帝政ロシアやフランス絶対王政においても改革は遅々として進まず遂には革命まで勃発してしまった。ただしナポレオン戦争には総力戦思想を欧州全体に、ロシア革命には共産主義思想を世界中に広める効果もあった事実も決して見逃してはならない。
*神聖ローマ帝国やオスマン帝国やムガール帝国に至っては事実上中世的分封状態に逆戻りしてしまい、大英帝国傘下の東インド会社に実質上の植民地とされてしまったり(ムガール帝国)、第一次世界大戦(1914年〜1918年)を契機とする最終的解体を待つしかなかった(神聖ローマ帝国やオスマン帝国)のである。
-
ところでウォーラーステインの世界システム論(World-System Theory)は「資本主義とは中心部の周縁部からの収奪によって成立するシステムの事であり、歴史の進行によって(世界帝国が成立し)周縁部が消失すると必然的に崩壊してきた」とし、さらには「世界経済」の成立が「世界帝国」成立に発展しない新たな枠組みが15世紀〜16世紀頃の欧州の欧州から始まったとした。実際それ以外の循環はメソポタミア文明や古代エジプト王朝が成立した古代からモンゴル世界帝国やティムール世界帝国が開闢された近世直前まで繰り返されてきたのであり、そのメカニズム解明を成し遂げた偉人こそが「前近代最大の歴史哲学者」イブン・ハルドゥーンだったという位置付けとなる。
*むしろ欧州には歴史の最初の時点から「集-立(Ge-Stell)システムの追求過程は歴史を循環させる」なる意識自体が存在しなかった。何しろゲルマン民族大移動によって帝政ローマを滅ぼした部族連合段階の蛮族達は、ローマ帝国の後継者となるどころか単一の部族連合を形成する事すら実現出来ず「(祖先伝承や国王や教会の権威を背景に)領主が領土と領民を全人格的に代表する権威主義的農本体制」に基づく割拠状態に突入。この状態を克服するのに「戦争遂行の為に臣民や国内資産を最後まで全て動員可能な官僚制によって常備軍が維持される」主権国家樹立が不可避となったという歴史的経緯だったのである。欧州において(イブン・ハルドゥーンが全体像を俯瞰してまとめた様な)循環史観が芽生えなかったのは、むしろ必然といってよい。4世紀から6世紀に及ぶ約200に及ぶゲルマン人の大移動は、一般に375年の西ゴート人のドナウ川越境から、568年の北イタリアでのランゴバルド王国の建国までとされ、これを第1次ゲルマン人大移動という。次いで8世紀に始まり、11世紀まで続いたゲルマン人の一派ノルマン人の移動を第2次ゲルマン人大移動という。
「(イブン・ハルドゥーンが全体像を俯瞰してまとめた様な)循環史観」が欧州人の目から完全視野外となったのは、何よりもまず「(それ自体は循環史観の枠組内に留まる)ノルマン人諸侯のロマネスク文化」の盛衰が、英国王朝や北フランス諸侯にバトンタッチされた過程があまりに自然に遂行され、かつ生存バイアスによって速やかに忘れ去られてしまったからだった。そしてフランスにおいてはさらに公益同盟戦争(1465年〜1477年)とフロンドの乱(Fronde、1648年〜1653年)における大貴族連合の自滅を契機に(彼らの栄光の歴史も同様に生存バイアスによって速やかに忘れ去られた後に)中央集権への抵抗形態が中世的な「大貴族連合との勢力均衡状態の理想視」から「啓蒙主義の体現者」百科全書派が掲げた様な「技術と学問のあらゆる領域にわたって参照されうるような、そしてただ自分自身のためにのみ自学する人々を啓蒙すると同時に他人の教育のために働く勇気を感じている人々を手引きするのにも役立つような知識」に依って有識者一人一人が理性的に対峙する方式へと遷移する。その背景にはさらに「(欧州には古代ギリシャ時代のイデア論と認識された)スンニ派古典思想」すなわち「神の叡智そのものは無謬だが、現世への流出過程で誤謬が累積し、遂には妥協の余地のない対立や悪まで誕生させてしまう」なる理念の浸透が存在した。
*教皇至上主義への対抗上、英仏の貴族階層が古代ローマ時代の哲人政治家セネカ(Lucius Annaeus Seneca、紀元前1年頃〜65年)の著作を通じてヘレニズム時代のコスモポリタン思想の精髄ともいうべき(エピキュリズムと表裏一体の関係にある禁欲主義を体現した)ストア派哲学に望んで染まり、そこから近代にまで通用する功利主義の概念を導出したのも大きい。「国主の藩屏」なる存在、モンゴル貴族も、清朝の八旗制も、江戸幕藩体制下における旗本も天下泰平の時代に腐敗してそれぞれの国の近代化に一切関係しなかったが、彼らだけは違ったのである。ちなみに明治政府が「(公家と大名の残党を寄せ集めた)華族」制度を設立した背景にはこうした文化の摂取が目的としてあったらしく、明治天皇の「これよりラストチャンスを与える。お前達は(大英帝国のジェントリー階層の様に)様々な形で国家の発展に寄与する近代貴族に成長出来なければ(フランス革命で滅ぼされたフランスの王侯貴族の様に)国民から見捨てられるだろう」なる激烈な訓令まで残っている。
17世紀前半のフランスは帯剣貴族だけでなく(最終的に文壇をほぼ独占するに至る)法服貴族等の新興階層まで理性と意志の高揚と力を強調し, 困難に立ち向かう英雄を理想視する英雄的ストイシスム (Stocisme heroque) が横溢していた。これはセネカ (Lucius Annaeus Seneca, 紀元前1年頃~紀元後65年) の思想に代表されるような本来のストイシスムが形を変えて復興したものであり、国家の困難に対して無関心であることを諌め, 危機に対しても勇敢に立ち向かうことを促す栄光と高邁な精神に溢れたものだった。
ただしフロンドの乱の失敗と国王へのさらなる権力集中が進行した同世紀の後半には「如何なる英雄的行動も、その動機まで踏み込んで検証すれば情念や欲望に操られる惨めな存在が浮かび上がってくるのみ」「人間の誇る理性だって想像力や情念・欲望・自己愛にに引きずられ, その判断を無意識の内に歪められている」と考えるジャンセニスム的ペシミズムや、その逆に洗練された快楽追求を至上の目的とするエピキュリスム的風潮が勢いを増していく。
こうした「リベルタン(Libertin、善悪の彼岸を超えて刹那的快楽に生き様とする放蕩貴族)的苦悩(ただしあくまでロココ時代的軽薄さと表裏一体)」からアベ・プレヴォー「マノン・レスコー(Manon Lescaut、1731年)」やサド侯爵の暗黒小説の様な様々なロマン主義作品の祖型が派生する展開を迎えたのだった。ジェントルマンの美徳として教養を重視する立場は16世紀まで遡ることができるが、これは15世紀末にイタリアから輸入された人文主義の影響もあり、ジェントリが武芸に秀で伝統的権威を持っていた貴族に対抗する上で教養が必要になったためである。
トマス・エリオットは『為政者の書』を著し、ギリシア・ローマ的な西洋古典教養を備え、地方行政を担うことのできる人物を理想のジェントルマンとして描いている。その後、中央集権化が進むにつれ、ジェントルマンは地方行政のみならず、中央の宮廷においても重視されるようになるが、そのような情勢の変化に合わせて、求められるジェントルマン像も変化した。1561年に翻訳されたバルダッサーレ・カスティリオーネの『宮廷人』は、古典教養に加え、音楽、詩、舞踏、作法、礼節などさらに広い領域における知識と素養を求めている。
このような「必須科目」は家庭教師から教わるのみならず、オックスブリッジでも習得された。両大学は中世では聖職者の人材育成の場としての性格をもっていたが、ヘンリー8世やエリザベス1世によって、教会の勢力を削いで宮廷に人材を供給するべく古代ギリシャ・ローマ時代の古典研究の重視に方針転換された。
養成機関としての役割自体は残るが、オックスブリッジから宮廷へ、というルートが確立されたことによって、聖俗両方の上部構造が両大学出身者によって占められることとなり、社会の上層に広がるジェントルマンの共同体が形成された。大学教育によるジェントルマンの選別という方法は新参者を共同体から排除する働きをした一方で、新参者本人はジェントルマンと認められなくとも、子や孫の代でのジェントルマン化に途を拓くものであった。
特に、イギリス帝国の拡大に伴い、新規に中流階級出身のジェントルマンが増えた19世紀には、土地の取得に代わるジェントルマン化の方法として活用された。*歴史上の最大の皮肉の一つは「産業革命がもたらした大量生産・大量消費に立脚する生活スタイルの浸透が、消費の主体を王侯貴族や聖職者といった伝統的インテリ階層から(現実の産業至上主義を支える)庶民にシフトさせていった時代」において、両者の連続性を担保したのが(経済的理由から庶民への合流を余儀なくされた)没落貴族層だった事という辺りかもしれない。これもまた(おおむね文弱化した旧支配階層が、概ね文明に劣等感を有する新支配階層に併呑される形で消滅する)循環史観においては観測され得ない展開だったりする。皮肉にもその一方では同時期以降(産業的発展に欠かせない)石油やレアメタルを筆頭とする地下資源の価値が高騰し、その採掘事業が後進国においては「(メソポタミア文明や古代エジプト王朝における大規模灌漑事業の様に)循環史観を支える「集-立(gestell )システム」になってしまった観も。
*神聖ローマ帝国やスペイン王国や帝政ロシアやオスマン帝国の旧領の多くが果てしなく続く民族紛争の舞台に成り果ててしまったのは、こうした意味合いにおける「前近代的な循環史観からの脱却」が十分ではなかったからとも考えられる。「イスラム文明がほとんどペルシャ人やトルコ系諸民族によって主導されてきた現実」に対する反感から芽生えたアラブ・ナショナリズムの世界に至っては当時への回帰だけが人類救済の道と信じられている有様。こうした際どい綱渡りをかろうじて摺り抜けた非ヨーロッパ系諸国としてはブラジルや南アフリカなどの例が著名だが、最近ではその成果が本物だったかどうかが試されている。
*「ダイアモンドは永遠に(Diamonds Are Forever)」なるスローガンがメディアミックス方式で洗脳的に流布され、その優美さと現実の採掘・流通携帯の過酷さのギャップをネタとする同題名のイアン・フレミング「ジェームズ・ボンド」シリーズ第4作(原作1956年、映画化1971年)も発表された。しかし実はダイアモンドの価値が国際的に高騰したのは1919年にダイヤモンドの反射・屈折率といった光学的特性を数学的に考慮したブリリアント・カットが登場して以降。多くの人間がこの人類の忘れっぽさを象徴する歴史的皮肉に気づかない。
*そもそも「(しばしば民族浄化運動の引き金を引く)宗教立国」なる理念自体、(ギリシャに依った)東ローマ帝国(395年〜1453年)や(マグリブに依った)ムラービト朝(1040年〜1147年)およびムワッヒド朝(1130年〜1269年)の自滅、さらには同様の試みが衰退を招いたスペイン王国やフランス絶対王政の存在がその不可能生を証明した様なものだが、困った事にその都度生存バイアスによって失敗例は瞬く間に忘れ去られ、性懲りも無く繰り返されてきたのだった。
その一方でこうしたイデオロギーと無縁な大英帝国や(オランダやベルギーを輩出した)フランドル地方やスイスやアメリカはあくまでこうした論争を外側から傍観し続けてきたのでした。
翻って日本もまた、伝統的にこうしたイデオロギー論争は苦手としてきたのです。
歴史は人の行動によつて形づくられるが、人は具体的には個人である。
歴史は人の行動によって形作られる。外に現われた行動は言うまでなく、心の動きも、人の心の動きなのでそれを広義の行動に含ませることができよう。ところが人は具体的には個人である。民族・社会の動きと言っても現実に行動し思惟し意欲するのは、どこまでも個人である。或る民族の生活様式、風俗、習慣、道徳、宗教的信仰、一般的な気風、その他その民族に於て共通のことは色々あるが、現実に喜怒哀楽するのは個人である。社会組織や政治上の制度、経済機構とかあって、それが個人と色々の関係を持つが、現実に行動するのは個人の外に無い。様々の集団的な活動がされ、いつのまにか行われてゆく社会の動きや世情変化とかがあっても、現実には個人の行動があるのみだ。
あらゆる歴史的現象は人の行動であり、現実には個人の行動である。社会として集団としての働きとか、民族の一般的な気風とか、または風俗習慣とか、そういうものは、人の行動についていう限りにおいては、抽象的概念に過ぎない。
集団は単なる個人の集りではなく集団としての働きをするので、社会の動きもまた個人の行動の集まりではなく、それと性質の違う、社会としての様々な働きによると考えられる。がその働きは、多くの個人の間に相互にまた錯雑した関係に於て、断えず行われる色々の事柄についての、また形での作用と反作用との入り混じった働きにおいて現われる。要するに、多くの個人の心の動き、行動によって生ずるのである。風俗とか習慣の形作られるのも、また同様である。制度や組織も、それにより個人が制約されるが、形作り成立させるものはやはり個人間の働きである。あらゆる歴史的現象は「人の行動で、現実には個人の行動だ」ということは、これだけ考えても明かであろう。
「現実には」と言ったが、これは「具体的には」と言ったのと同じ意義である。社会や集団としての働き、民族の一般的気風、風俗習慣とかそういうものは、人の行動について言う限りは、抽象的概念である。
人は行動することにおいて生活する。それでは人の生活とはどういうものか。
ところが人が行動する、何ごとかをすることは人の生活の働きである。「人は行動することにおいて生活する」。そこで、人の生活とはどういうものか、を考えてみる。
①人の生活は時間的に進行する過程をもつ。
第一に知られるのは、生活は時間的に進行する、つまり「過程を持つもの」である。人のすることは、どんな小さなことにも過程がある。短時間のことでも、一言一行時間的進行の過程の無いものは無い。むしろ「人は言行すること生活することによって時間というものを覚知する」と言ってよい。
②人が何事かをするのは、現在の状態を変えることだ。
第二に「人が何事かをするのは、現在の状態を変えることだ」ということ。一言一行でも、それを言わぬ前しない前と、言った後した後とでは、それを聞いた人、仕掛けられた人またはそれにあづかる事物に、何程かの変化を与える、それにより自身に変化が生ずる。外に現われた言行でなく心の動きだけでも、その前後では自己の生活に変化がある。「自己の言ったことしたこと思ったことなどが自己自身に制約を加へ自己を束縛するが、それは自己を変化させることなのだ。がまたそれと共に、自己は自己として持続されている。今日の自己は昨日の自己ではない、が、それと共に昨日の自己である。だからこそ変化がある。
③生活の動きは断えることなく連続している。
第三に「生活は断えず動いていて一刻も静止していない」。人は常に何事かを言い何事かをし、何程か心を働かせていて、そのため断えず生活が変化している。その動きかたは色々で、大きく強いこともあり、小さく弱いこともあり、突如激しい動きの起るように見えることもあれば、徐々に動くともなく動いていることもあり、その徐々な小さい動きも、動くことの力によって、或は他からの刺戟により、大きな動きとなることもある。いかなる動きかたをするにしても、その動きは順次に前を承け、後を起してゆくから、「生活の動きは断えることなく連続している」。生活は一つの生活として一貫している。この意味では今日の自己が昨日の自己であり、遥か前からの自己であり、遥か後までの自己である。
④どんな一言一行でも生活の変化によつて、あるいはその他の道筋によって、そのはたらきをかならず後の生活に及ぼす。
そこで第四にこう考えられる。どんな一言一行も、生活の変化によって、或はその他の道筋によって、その働きを必ず後の生活に及ぼす。その働きが時を隔てた後現われることもあり、明かに知られずに行われることもあるがそれの無いことは無い。その働きに大小強弱の違いはあつても、一度したことは消滅してしまうものではない。
⑤絶えず動いている生活は一刻ごとにそれそれの特異な姿をもち特異なはたらきをするので、二度と同じ状態にあることが無い。
第五には、断えず動いている生活は一刻毎に夫々の特異な姿を持ち特異な働きをするので、二度と同じ状態にあることが無い。一言いうにも、その時の気分・生理心理的状態、ふと思ひ出したこと、相手の人物態度、対談の行掛り、周囲の状況、その他の様々の条件が働き合って、言う事・言い方が決まるが、これらの条件が夫々様々の条件上その働き合いにより出来ているから、多くの条件が同様にあり同様に働き合うのが二度ある筈はなく、従って「同じことは二度と言われない」のである。
⑥生活を動かしてゆくものは心のはたらきであるが、必しも常に調和しているのではなく、その間に齟齬のあることがあり、時には衝突も生ずる。
第六は、言うまでもないが「生活を動かしてゆくものは心の働きだ」ということ。この言い方は心の働くことが生活の動きとなるが、一応こう言っておく。さてここに心の働きというのは、理智のみではなく、意欲、情感、生活気分と言われるようなもの、を含めてのことである。事実、人の生活を直接に動かすのは主として後の方の力である。もっと適切には、理智とか意欲情感とかいうものが別々に有り別々に働くのではなく、それらは一つの心の働きの色々の側面で、それらは互に滲透し合い変化させ合い、一つの働きの中に他の働きが含まれていて、それによって人の生活を動かしてゆく、かゝる名をつけられない肉体の働きもそれに参加するのだが、便宜上しばらくはこう言う。心の色々の働きは必しも調和していなくて、その間に齟齬のあることがあり、時には衝突も生ずる。理智によって成りたつ思想も、多くの異質のもの、互に一致しない考え方から構成されたもの、を併せ持つことがある。従って、心の働きが生活を動かしてゆく動かし方も単純でない。生活と心の働きを分けて言ったのは、これを言おうとしたからである。
⑦人の生活には多方面があり、それらが互にはたらきあって一つの生活を形づくる。それ故にこそ時に生活の破綻も生ずる。
第七は「人の生活は一つの生活だが、それには多方面がある」。衣食住、職業・職務に関すること、娯楽に関すること、家庭人として、社会人として、その他の関係に於ての人として、の夫々の仕事色々あるが、人の生活にはこれらの多方面があり、それらが互に働き合い一つの生活を形作る。しかしそこには、性質の異なるもの、由来の同じでないもの、互に調和し難いものもあり、その間に衝突の起る場合が少なくない。そのために生活の破綻が生ずることもある。人はこういう生活をしている。いわば多方面の生活が一つの生活なので、それ故に生活の破綻も生ずる。
⑧その一方で社会の働きを受けながら社会に働きかけるのが人の生活である。
さて第八には「人は孤立して生活するのではなく、一言一行も他人との、また集団としての社会との、交渉を持つ」もので、「生活は社会的のもの」だ、ということ。他人との交渉が相互的である事は言うまでもなく、社会との関係に於も、「社会の働きを受けながら社会に働きかけるのが人の生活である」ことを忘れてはならない。上述の如く、もともと社会は多くの人の働き合いによって形作られているものである。
⑨人の生活は歴史的のものであり、人は民族または国民としての長い歴史のうちに生活している。
第九には「人の生活は歴史的のもので、人は民族または国民としての長い歴史の中に生活しているものだ」ということ。「人の思想が多くの異質のものを含むのも、生活の多方面に調和し難いもののあるのも、民族史国民史の色々の段階に於いて生じたものが共存しているところに原因がある」。
⑩人は環境に対して受動的な地位にあるのみではなくして、能動的なはたらきをする。けれども環境の力は強い。自ら環境を作りつつ、その環境から強いはたらきをうける。そこに生活の主体たる人の力があり、生活そのものの意味がある。
最後に第十、生活するについての人の態度を一言しておく。「生活は自己の生活だ。しかしそれは物質的精神的社会的自然的な色々の力、色々の事が働き合って生ずる環境の中において営まれる。人は環境の働きを受けつゝ、それに対応し、それを自己の生活に適応するようにしていこうとする」。この意味で「人は断えず環境を作って行く。そこに生活の主体たる人の力があり、生活そのものの意味がある。人は環境に対し受動的な地位にあるのみでなく、能動的な働きをする。けれども環境の力は強い。自ら環境を作りつゝ、その環境から強い働きを受ける」。言行思慮が自己を制約すると言ったが、それは自己の言行などがそのまゝ環境を形作ることなのである。この環境は、それを形作るものの間に調和の無い場合が多く、またそれにも常に変化がある。従って人の生活の環境から受ける働きにも混乱が有り勝ちで、人はともすれば環境に圧倒され、或はそれによって生活を乱される。「ただ剛毅な精神と確乎たる生活理念とを持つものが、よく環境に対し能動的な働きをなし、環境を生活に適応するよう断えず改めてゆき、主体者としての力を発揮し、生活を真の生活たらしめる」。かかる人に於て、生活が人の生活で自己の生活である。
それでは歴史とは何か。それは生活の過程のある地点からそれまで経過して来た過程を振り返り見る時に現れてくる知識である。
ここで、問題を歴史に立ち返らせる。歴史は生活の姿だが、通常、それは個人生活ではなく集団生活、特に民族生活または国民生活を指して言う。すなわち生活は断えず生活する自己を変化させ時間的に進行して行く、その進行過程がそのまま歴史であるが、ただそれが歴史として人の知識に入って来るのは、その過程の中のある地点に立ち、それまで経過して来た過程を振り返り見る時である。生活は断えず進行して行くから、進行するある現在の瞬間にこの地点を定める時、過去からの生活の過程が歴史として現われて来る。これが普通の意義での歴史であるが、歴史が生活の過程ならば、現在の瞬間からさらに先の方に進行してゆく過程、即ち未来の生活もまた歴史を形作るものだから、歴史の語の意義を一転させ、人は常に歴史を作って行く、という言い方をすることもできる。あるいは未来の生活の進行におけるその時の現在の地点に立ち、その時までの過程を振り返って見れば、今から見ると未来の生活が過去の生活として眺められ、普通の意義での歴史がそこに見られる、といえる。この地点は刻々に先に移ってゆくから、歴史の過程は次第に先の方に伸びてゆく。しかし、未来に作られてゆく歴史の如何なるものであるかは、現在から知ることができない。うしろを向けば作られて来た歴史が知られるが、前を向けば知らない歴史を刻々に作つてゆくことだけがわかる。この知られない歴史を刻々作ってゆき、知らない歴史を刻々知られる歴史に転化させてゆくのが、生活である。
津田左右吉(1873年〜1961年) - Wikipedia
『日本書紀』『古事記』を史料批判の観点から研究したことで知られる20世紀前半の歴史学者。岐阜県美濃加茂市下米田町出身。
1891年(明治24年)、東京専門学校(後の早稲田大学)邦語政治科卒業[2]。卒業後、白鳥庫吉の指導を受けた。1901年、28歳で『新撰東洋史』を刊行。1908年まで千葉中学等で中学校教員を務めた。
1908年より満鉄東京支社嘱託・満鮮地理歴史調査室研究員になる。研究長は白鳥庫吉であった。満鉄調査部の満州朝鮮歴史地理調査部門には、他に松井等、稲葉岩吉、池内宏らがいた[3]。津田はこの調査部で「渤海考」「勿吉考」等東洋史研究調査を行った。同機関は、1914年に東京帝国大学文科大学に移管されるが、それまで勤務した。1913年(大正2年)には、岩波書店より『神代史の新しい研究』を刊行。
1917年に『文学に現われたる我が国民思想の研究』を刊行し1921年まで続刊。この体系的な著作において、津田は、日本の思想形成における中国思想の影響については否定的もしくは消極的な立場をとり、日本文化の独自性を主張した。
1918年(大正7年)に早稲田大学講師に就任、東洋史、東洋哲学を教えた。翌1919年、『古事記及び日本書紀の新研究』を発表。
1920年(大正9年)に早稲田大学文学部教授。
1924年(大正13年)、51歳で『神代史の研究』を発表。前著とともに、神武天皇以前の神代史を研究の対象にし、史料批判を行ったものである。
*『古事記』や『日本書紀』、特に神話関係の部分について後世の潤色が著しいとして文献批判を行った。その方法は津田の創始ではなく、明治以降の近代実証主義を日本古代史に当てはめ、記紀の成立過程についてひとつの相当程度合理的な説明を行った側面が大きい。明治以後の近代史学では、歴史の再構成は古文書、日記等の同時代史料によるべきであって、たとえば『平家物語』や『太平記』を史料批判なくして同時代史料に優先して歴史の再構成に使用してはならないという原則が、広く受け入れられていた。ただし同様の原則を古代史に適用することは、直接皇室の歴史を疑うことにつながるゆえに、禁忌とされてきたのである。それを初めて破って、著書の中で近代的な史料批判を全面的に記紀に適用したのが津田だった。それゆえ津田が従前の歴史学から離れた立場にあったわけではないが、津田の業績を基本的に承認・利用しつつ、その核心部分を肯定する文章を自ら書き下ろすことは避けようとする態度が他の学者にはあった。然し、このような「津田史観」すなわち津田は記紀を「否定」したともされる見方について、津田自身はそれを「誤解」であるとしており、実際津田自身は天皇制を「否定」したことはなかった。
1927年、『道家の思想と其の開展』を発表。1930年には『日本上代史研究』、1933年には『上代日本の社会及び思想』、1935年には『左伝の思想史的研究』、1937年には『支那思想と日本』岩波新書、1938年には『儒教の実践道徳』『蕃山・益軒』と刊行し、旺盛に執筆活動を続けた。
*中国思想等についての実証研究においては「儒教は人間性を無視している」として、中国思想は「特殊な否定的なもの」であるとして、中国の思想には批判的であった。その一方では近代西洋文化に対しては肯定的な近代主義者でもあったので「明治人に特有な脱亜論的ナショナリズム」を体現していたとも評価される。
1939年、東京帝国大学法学部講師(東洋政治思想史)を兼任。
1939年(昭和14年)に津田が『日本書紀』に於ける聖徳太子関連記述についてその実在性を含めて批判的に考察したことについて、蓑田胸喜・三井甲之らが津田に「日本精神東洋文化抹殺論に帰着する悪魔的虚無主義の無比凶悪思想家」として不敬罪にあたるとして攻撃した(津田事件また津田左右吉事件)。
*政府は、1940年(昭和15年)2月10日に『古事記及び日本書紀の研究』『神代史の研究』『日本上代史研究』『上代日本の社会及思想』の4冊を発売禁止の処分とする。同年1月に文部省の要求で早稲田大学教授も辞職させられた。さらに津田と出版元の岩波茂雄は同年3月に「皇室の尊厳を冒涜した」として出版法(第26条)違反で起訴され、1942年(昭和17年)5月に禁錮3ヶ月、岩波は2ヶ月、ともに執行猶予2年の判決を受けた。津田は控訴したが、1944年(昭和19年)に時効により免訴となった。ともいう。しかしこの裁判については、津田自身は「弾圧ではない」と後に述べており、事件の実態について研究がすすめられている。
戦後戦後、津田自身の戦前における「弾圧」の経験とあいまって学界に迎えられ、皇国史観を否定する“津田史観”は第二次世界大戦後の日本史学界の政治的主流となり、敗戦による価値観の転換を体現するものとなった。
*一方、反共産主義者でもあり、戦後の共産主義の流行には批判的であった。
1946年(昭和21年)、雑誌『世界』第4号に発表した論文「建国の事情と万世一系の思想」では、「天皇制は時勢の変化に応じて変化しており、民主主義と天皇制は矛盾しない」と天皇制維持を論じる。天皇制廃止論者達からは「津田は戦前の思想から変節した」と批判されたが、津田の「天皇制を立憲君主制に発展させるべき」との考え方は戦前から一貫したもので、戦後になって変化したわけではない。
津田左右吉 建国の事情と万世一系の思想皇室は皇室として長く続いて来たのであるが、これだけ続いて来ると、その続いて来た事実が皇室の本質として見られ、皇室は本来長く続くべきものであると考えられるようになる。皇室が遠い過去からの存在であって、その起源などの知られなくなっていたことが、その存在を自然のことのように、あるいは皇室は自然的の存在であるように、思わせたのでもある。(王室がしばしば更迭した事実があると、王室は更迭すべきものであるという考が生ずる。)従ってまたそこから、皇室を未来にも長く続けさせようという欲求が生ずる。この欲求が強められると、長く続けさせねばならぬ、長く続くようにしなければならぬ、ということが道徳的義務として感ぜられることになる。もし何らかの事態が生じて(例えば直系の皇統が断えたというようなことでもあると)、それに刺戟せられてこの欲求は一層強められ、この義務の感が一層固められる。六世紀のはじめのころは、皇室の重臣やその他の朝廷に地位をもっている権力者の間に、こういう欲求の強められて来た時期であったらしく、今日記紀によって伝えられている神代の物語は、そのために作られたものがもとになっている。
政治の形態は時によって違い、あるいは朝廷の内における摂政関白などの地位にいて朝廷の機関を用い、あるいは朝廷の外に幕府を建てて独自の機関を設け、そこから政令を出したのであり、政権を握っていたものの身分もまた同じでなく、あるいは文官でありあるいは武人であったが、天皇の親政でない点はみな同じであった。そうしてこういう権家の勢威は永続せず、次から次へと変っていったが、それは一つの権家がある時期になるとその勢威を維持することのできないような失政をしたからであって、いわば国政の責任がおのずからそういう権家に帰したことを、示すものである。この意味において、天皇は政治上の責任のない地位にいられたのであるが、実際の政治が天皇によって行われなかったから、これは当然のことである。天皇はおのずから「悪をなさざる」地位にいられたことになる。皇室が皇室として永続した一つの理由はここにある。
このような古来の情勢の下に、政治的君主の実権を握るものが、その家系とその政治の形態とは変りながらも、皇室の下に存在し、そうしてそれが遠い昔から長く続いて来たにもかかわらず、皇室の存在に少しの動揺もなく、一種の二重政体組織が存立していたという、世界に類のない国家形態がわが国には形づくられていたのである。もし普通の国家において、フジワラ氏もしくはトクガワ氏のような事実上の政治的君主ともいうべきものが、あれだけ長くその地位と権力とをもっていたならば、そういうものは必ず完全に君主の地位をとることになり、それによって王朝の更迭が行われたであろうに、日本では皇室をどこまでも皇室として戴いていたのである。こういう事実上の君主ともいうべき権力者に対しては、皇室は弱者の地位にあられたので、時勢に順応し時の政治形態に順応せられたのも、そのためであったとは考えられるが、それほどの弱者を皇室として尊重して来たことに、重大の意味があるといわねばならず、そこに皇室の精神的権威が示されていたのである。
ところが、十九世紀の中期における世界の情勢は、日本に二重政体の存続することを許さなくなった。日本が列国の一つとして世界に立つには、政府は朝廷か幕府かどれかの一つでなくてはならぬことが明かにせられた。メイジ(明治)維新はそこで行われたのである。この維新は思想革命でもなく社会改革でもなく、実際に君主のことを行って来た幕府の主宰者たる将軍からその権を奪って、それを天皇に属させようとしたこと、いわば天皇親政の制を定めようとしたことを意味するのであって、どこまでも政治上の制度の改革なのである。この意味においては、タイカ改新及びそれを完成させた令の制度への復帰というべきである。ただその勢のおもむくところ、封建制度を廃しまたそれにつれて武士制度を廃するようになったことにおいて、社会改革の意義が新にそれに伴うようになっては来たが、それとても実は政治上の必要からのことであった。ヨウロッパの文物や思想をとり入れたのは、幕府の施設とその方針とをうけついだものであるから、これはメイジ維新の新しいしごとではなかった。維新にまで局面をおし進めた力のうちには、むしろ頑冥がんめいな守旧思想があったのである。
さて幕府が消滅し、封建諸侯と武士とがその特殊の身分を失って、すべての士民は同じ一つの国民として融合したのであるから、この時から後は、皇室は直接にこの一般国民に対せられることになり、国民は始めて現実の政治において皇室の存在を知ることになった。また宮廷においても新にヨウロッパの文物を採用せられたから、同じ状態にあった国民の生活とは、文化の面においてもさしたる隔たりがなくなった。これはおのずから皇室と国民とが親しく接触するようになるよい機会であったので、メイジの初めには、そういう方向に進んで来た形跡も見られるし、天皇親政の制が肯定せられながら輿論政治・公議政治の要求の強く現われたのも、またこの意味を含んでいたものと解することができる。ヨウロッパに発達した制度にならおうとしたものながら、民選議院の設立の議には、立憲政体は政治を国民みずからの政治とすることによって国民がその責に任ずると共に、天皇を政治上の責任のない安泰の地位に置き、それによって皇位の永久性を確実にし、いわゆる万世一系の皇統を完からしめるものである、という考があったのである。
しかし実際において政治を左右する力をもっていたいわゆる藩閥は、こういう思想の傾向には反対の態度をとり、宮廷その他の諸方面に存在する固陋ころうなる守旧思想もまたそれと結びついて、皇室を国民とは隔離した高い地位に置くことによってその尊厳を示そうとし、それと共に、シナ思想にも一つの由来はありながら、当時においてはやはりヨウロッパからとり入れられたものとすべき、帝王と民衆とを対立するものとする思想を根拠として、国民に対する天皇の権力を強くし政治上における国民のはたらきをできるだけ抑制することが、皇室の地位を鞏固きょうこにする道であると考えた。憲法はこのような情勢の下に制定せられたのである。そうしてそれと共に、同じくヨウロッパの一国から学ばれた官僚制度が設けられ、行政の実権が漸次その官僚に移ってゆくようになった。なおメイジ維新によって幕府と封建諸侯とからとりあげられた軍事の権が一般政務の間に優越な地位を占めていた。これらのいろいろの事情によって、皇室は煩雑にして冷厳なる儀礼的雰囲気のうちにとざされることによって、国民とはある距離を隔てて相対する地位におかれ、国民は皇室に対して親愛の情を抱くよりはその権力と威厳とに服従するようにしむけられた。皇室の仁慈ということは、断えず説き示されたのであるが、儒教思想に由来のあるこの考は、上に述べた如く現代の国家と国民生活との精神とは一致しないものである。そうしてこのことと並行して、学校教育における重要なる教科として万世一系の皇室を戴く国体の尊厳ということが教えられた。一般民衆はともかくもそれによって皇室の一系であられることを知り、皇位の永久性を信ずるようになったが、しかしその教育は主として神代の物語を歴史的事実の如く説くことによってなされたのであるから、それは現代人の知性には適合しないところの多いものであった。皇室と国民との関係に、封建時代に形づくられ儒教道徳の用語を以て表現せられた君臣間の道徳思想をあてはめようとしたのも、またこういう為政者のしわざであり、また別の方面においては、宗教的色彩を帯びた一種の天皇崇拝に似た儀礼さえ学校において行わせることにもなったが、これらの何れも、現代人の国家の精神また現代人の思想と相容れぬものであった。
さて、このような為政者の態度は、実際政治の上においても、憲法によって定められた輔弼ほひつの道をあやまり、皇室に責任を帰することによって、しばしば累をそれに及ぼした。それにもかかわらず、天皇は国民に対していつも親和のこころを抱いていられたので、何らかの場合にそれが具体的の形であらわれ、また国民、特にその教養あり知識あるものは、率直に皇室に対して親愛の情を披瀝ひれきする機会の得られることを望み、それを得た場合にそれを実現することを忘れなかった。「われらの摂政殿下」というような語の用いられた場合のあるのは、その一例である。そうして遠い昔からの長い歳月を経て歴史的に養われまた固められた伝統的思想を保持すると共に、世界の情勢に適応する用意と現代の国家の精神に調和する考えかたによって、皇室の永久性を一層明かにし一層固くすることに努力して来たのである。
ところが、最近に至って、いわゆる天皇制に関する論議が起ったので、それは皇室のこの永久性に対する疑惑が国民の一部に生じたことを示すもののように見える。これは、軍部及びそれに附随した官僚が、国民の皇室に対する敬愛の情と憲法上の規定とを利用し、また国史の曲解によってそれをうらづけ、そうすることによって、政治は天皇の親政であるべきことを主張し、もしくは現にそうであることを宣伝するのみならず、天皇は専制君主としての権威をもたれねばならぬとし、あるいは現にもっていられる如くいいなし、それによって、軍部のほしいままなしわざを天皇の命によったもののように見せかけようとしたところに、主なる由来がある。アメリカ及びイギリスに対する戦争を起そうとしてから後は、軍部のこの態度はますます甚しくなり、戦争及びそれに関するあらゆることはみな天皇の御意志から出たものであり、国民がその生命をも財産をもすてるのはすべて天皇のおんためである、ということを、ことばをかえ方法をかえて断えまなく宣伝した。そうしてこの宣伝には、天皇を神としてそれを神秘化すると共に、そこに国体の本質があるように考える頑冥固陋にして現代人の知性に適合しない思想が伴っていた。しかるに戦争の結果は、現に国民が遭遇したようなありさまとなったので、軍部の宣伝が宣伝であって事実ではなく、その宣伝はかれらの私意を蔽おおうためであったことを、明かに見やぶることのできない人々の間に、この敗戦もそれに伴うさまざまの恥辱も国家が窮境に陥ったことも社会の混乱も、また国民が多くその生命を失ったことも一般の生活の困苦も、すべてが天皇の故である、という考がそこから生れて来たのである。むかしからの歴史的事実として天皇の親政ということが殆どなかったこと、皇室の永久性の観念の発達がこの事実と深い関係のあったことを考えると、軍部の上にいったような宣伝が戦争の責任を天皇に嫁することになるのは、自然のなりゆきともいわれよう。こういう情勢の下において、特殊の思想的傾向をもっている一部の人々は、その思想の一つの展開として、いわゆる天皇制を論じ、その廃止を主張するものがその間に生ずるようにもなったのであるが、これには、神秘的な国体論に対する知性の反抗もてつだっているようである。またこれから後の日本の政治の方向として一般に承認せられ、国民がその実現のために努力している民主主義の主張も、それを助け、またはそれと混合せられてもいるので、天皇の存在は民主主義の政治と相容れぬものであるということが、こういう方面で論ぜられてもいる。このような天皇制廃止論の主張には、その根拠にも、その立論のみちすじにも、幾多の肯べがたきところがあるが、それに反対して天皇制の維持を主張するものの言議にも、また何故に皇室の永久性の観念が生じまた発達したかの真の理由を理解せず、なおその根拠として説かれていることが歴史的事実に背いている点もある上に、天皇制維持の名の下に民主主義の政治の実現を阻止しようとする思想的傾向の隠されているがごとき感じを人に与えることさえもないではない。もしそうならば、その根柢にはやはり民主主義の政治と天皇の存在とは一致しないという考えかたが存在する。が、これは実は民主主義をも天皇の本質をも理解せざるものである。1947年(昭和22年)に帝国学士院(同年中に日本学士院と改称)会員に選ばれた。
1949年(昭和24年)に文化勲章受章。1960年(昭和35年)に美濃加茂市名誉市民第1号に選ばれた。
1961年(昭和36年)、武蔵境の自宅で死去。
津田の個々具体的な主張には、かなり印象論的なものも多く、批判もあった。日本史の坂本太郎や井上光貞は、津田らの研究が「主観的合理主義」に過ぎないという主旨の批判を行っている。ただし、坂本や井上をはじめ戦後の文献史学者の多くは、津田の文献批判の基本的な構図を受け入れており、一般に継体天皇以前の記紀の記述については単独では証拠力に乏しいと見ている。歴史学界の外部からは、津田が歴史史料以外を信用せず、考古学的・民俗学的な知見を無視したことに批判がある。
ここで語られているのはまさしく「現実は互いに不可分な相互関係によって結ばれた諸概念によって成立している」とした仏教の縁起論そのもの。
- こうした概念を固めたとされるインド僧の龍樹(2世紀)の思想自体はこの段階で分析を諦めてしまった状態を「世俗諦(俗人の悟り)」として退け、さらにその背後に透けて見える全体構造を観想しようとする態度を「真諦(真の覚醒者の悟り)」を設定しているという点で形而上学的であり、この求道者的態度こそが密教(仏教的神秘主義)やスーフィズム(イスラム神秘主義)といった「観想を通じて世界そのものに働きかけるプロセスの厳密化を志向するタイプの神秘主義」を経てコンピューター工学の基礎概念を準備する展開を迎えるのだが、確かに世俗諦から出発するとこういう運動には結びつきにくく「人類は今すぐでも一切のコンピューター使用を停止して、人間らしさを取り戻すべき」といった反近代主義に流れてしまう。ここまでくるとむしろ「国外思想の日本的受容」というより「穢れを忌避する日本の伝統への回避」としかいえない展開を迎える。
*「人類は今すぐでも一切のコンピューター使用を停止して、人間らしさを取り戻すべき」…そもそもコンピューターなるハードが本質的にはただ単に物理化学や統計学を構成するアルゴリズムを体現する存在に過ぎない事が分かってない。だから「算盤で十分じゃないですか」どころか「電卓で十分じゃないですか」とか平気で口にする。
*さらに世俗諦は「現世で起こることは全て前世の因果で決定済である」と考える時間的因果論や「現世でどれだけそれに反した生活を送ろうが、真の信仰心は守れる」とする日本的二諦論を派生させたりもする。 - こういう話になると一部日本人が必ず「人間性を放棄したキリスト教の悪しき伝統」とか言い出すが、そこで想定されているのは概ね「この世界は神が最初の動作を行って駆動を開始した」とするスコラ学の機械的宇宙論である。要するに江戸時代に日本へと伝わり、儒学者の総攻撃を受けたマテオ・リッチ「天主実義(1595年)」の時代からあまりアップデートされてない。皮肉にもこのいかにも欧州中世的なタイプのイデオロギーは信仰の主体を個人でなく伝統的共同体と考え、これを布教の対象とする事で「個人こそ信仰の主体」と考える宗派より日本で傳教の実績を挙げてきた。戦国時代西日本における「イエズス会の布教活動」や文明開化期における東北での「聖ニコライのロシア正教布教」がこれに該当するが、むしろこの系譜はその「後進性」ゆえにむしろ本国で存続の危機に立たされる事になる。
*いずれにせよ、フェニキア商人の男主人(バール) / 女主人(バーラト)二重信仰やマニ教の様な(最終的には宗教的独自性を失って自滅した)折中主義と、(かえって信仰としての本質を明らかにした側面すらある)イエズス会や聖ニコライの日本での布教に際しての適応主義の峻別は「神の叡智自体は無謬だが、流出の過程で矛盾が累積し、遂には妥協点の見えない対立や悪まで顕現してしまう」とする(実質的にスンニ派古典思想の果実そのものだが、欧州では古代ギリシャ哲学の直伝と認識されている)イデア流出論でも持ち出して来ない限り図れない。皮肉にもこういう柔軟な対応は伝統的に「世俗諦に屈した」日本神仏習合信仰の方が得意で、むしろそれを全面的に拒絶するタイプの原理主義的儒学者の方が苦手としてきたのである。
- 確かに(イスラム教圏におけるアラビア哲学の展開からの連続性と断絶性に十分自覚的とはいえないという点で不完全な)西洋思想には様々な問題もあるが、少なくとも「神の叡智自体は無謬だが、流出の過程で矛盾が累積し、遂には妥協点の見えない対立や悪まで顕現してしまう」とする(実質的にスンニ派古典思想の果実そのものだが、欧州では古代ギリシャ哲学の直伝と認識されている)イデア流出論からボローニャ大学やパドヴァ大学の解剖医や天文学者中心に流行した新アリストテレス哲学(実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。逆を言えば実践知識の累積が引き起こすパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく、とする循環史観)や、ジャンバッティスタ・ヴィーコのクリティカ&トピカ論(あらゆる歴史的事象の解釈が時代変遷に伴って揺らぐ事を想定し、発見や解釈の履歴も同時に蓄積していく心構え)が派生する流れくらいは押さえてないと、そもそも実証科学的人文科学として成立しないのである。
実証科学的人文科学の観点から見て、上掲の津田左右吉「歴史とは何か」にも垣間見られる「世俗諦に屈した縁起論」の抱える問題点は以下となりそうです。

- 例えば伝統的地域共同体史は、概ね国を問わず「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制」との関係の変化として描き得るが、この際「領主が領民に及ぼす縁の力」と「領民が領主に及ぼす縁の力」は一瞬たりとも等質の関係を構築しない。欧米においてはこの事への解釈として「領主の領民に対する拘束は、それがいかなる物理的・精神的・法的な形式を満たしているかに関わらずその一切が人間の生得的権利に対する侵犯である」なる立場の無政府主義的(無神論的)リバタリアン、「改善の努力は農奴制からの解放や選挙権の付与といった可視化可能な部分に対してのみ行い、それ以外の諸要素については沈黙を守る」(マクルーハン言う所の)原義としての進歩主義者、「背負ってるものの違いが王侯貴族と庶民の格差の自然な源泉」とする貴族主義者、そして「人間の幸福は、民族精神(Volksgeist)ないしは時代精神(Zeitgeist)とも呼ばれる絶対精神(absoluter Geist)と完全なる合一を果たし、自らの役割を与えられる事によってのみ達せされる」とするヘーゲル哲学らがそれぞれ多様で多態な意見を開陳してきたが、現状を全面肯定する「世俗諦に屈した縁起論」に立脚する限り、本質的には「何事も状況によって色々である」以上、踏み込んだ発言が出来なくなってしまう。
*日本の歴史学者は概ね「史料の声を全て拾う(恣意的解釈による取捨選択を行わない)」科学実証主義的過程においてこの欠陥が克服される(逆をいえば「史料に立脚しない主張」は百害あって一利なし)と考える。その考え方自体は別に間違っていないのだが、「神の叡智自体は無謬だが、流出の過程で矛盾が累積し、遂には妥協点の見えない対立や悪まで顕現してしまう」とするイデア流出論によって拡張された実証科学的人文学は元来「真実は一つ」なる立場に立たず、真実について異なる信念を共有する集団同士が(それぞれ相応の検証は通過した)歴史事象を共有しつつそれぞれ独自の道を歩む展開を想定している(これは「非ユークリッド幾何学」や量子論が登場して以降の数学や物理学の展開も同様)。この「あと一歩」が足りないせいで主張が海外に通用しない側面も確実に存在する様に見受けられるのである。
-
そもそも日本語が「理想主義者(idealist)」と「アイディア屋(Idea man)」を同じ概念の別側面として表現出来ない欠陥を抱えるのも、この「世俗諦に屈した縁起論」に由来する本質的な「真諦の世界への侮蔑」が原因だと思われる。いうなれば、最小限の会話を成立させる為にも不可欠なコンセンサスも備えていないに等しい。
*MCU(Marvel Cinematic Universe=マーベル・シネマティック・ユニバース)作品の興行成績が日本と海外でリンクしないのも、これが原因とも。そういえば「(上掲の意味合いにおける)イデア論に基づいた倫理設計が的確に行き渡っているから、どんなに派手なアクションが展開しても破綻せず安心して鑑賞可能」という条件は荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険(1987年〜)」も満たしている。*おそらくウンベルト・エーコ「薔薇の名前(Il Nome della Rosa、原作1980年、映画化1986年)」の影響を色濃く受けた京極夏彦の推理小説「鉄鼠の檻(1996年)」も、この種の反知性主義の恐ろしさを巧みに盛り込んでいた。
*「この種の反知性主義の恐ろしさ」…五味川純平「戦争と人間(原作1965年〜1982年、映画化1970年〜1973年)」においては淡々と統計データを提示して開戦の無謀を説く「当時の日本における唯一の良心」共産主義者と「やってみなければ分からないじゃないか!! お前の様な座って考えてるだけの人間が日本を滅ぼすのだ!!」と嘲笑う帝国軍人が対比的に描かれた。当時の共産主義者がそんな清らかな存在だったかはともかく(とはいえ1970年代前半、つまり反差別主義に染まる以前のマルクス・レーニン主義者が、その時代に差し掛かってなお科学実証主義的立場を理想ししていたという点で興味深い物証ではある)、そうした極端化された行動主義が当時の日本や学生運動全盛期に横溢しており「旧左翼」陣営から軽蔑の視線を注がれていた事実そのものは揺るがない。そういえば学生運動の最中には、学生運動かが研究室に押し入って設備を破壊して回りながら、研究者達に「我々の様に行動しない貴様らに存在価値はない!!」と豪語したという。これで両者の重ね合わせが行われなかったと考える方がおかしい。そして、こうしたルサンチマンが映画「戦争と人間第3部(1973年)」に描かれた「大陸では民間人への略奪・輪姦・虐殺を働くばかりで、実際の戦闘では旧式ライフルしか装備していないせいで(アメリカ軍から最新式の自動小銃や機関銃の供与を受けた)八路軍や(ドイツ戦車軍団と対等に渡り合った未来の戦車を大量装備した)ソ連戦車隊に一方的に大量虐殺される皇軍」に結実。そして同時進行で「山岳ベース事件(1971年〜1972年)」や「あさま山荘事件(1972年)」が進行し、新左翼陣営は本格的に国民からの支持を失っていく。
*こうした状況を背景に1970年代後半までに「反差別」を共通目標に設定した「旧左翼と新左翼の野合」が達成される。この時点ではもはや「科学実証主義の一環としてのマルクス・レーニン主義」の支持者は既に壊滅していたとも。
-
こうした戦前日本からの「イデア論の不在」に対する問題意識は、日本人を「方法論的個人主義に立脚する社会学の大家」マックス・ウェーバーに飛びつかせたが、彼の「社会と人間は外骨格生物における外殻と中身の関係にあり、中身の成長に脱皮による殻の拡張が間に合わなくなったら死ぬ」なるイデア論的主張もやはり広まる過程で歪曲され「外殻(既存社会)に幽閉されている限り人類は真の意味で自由になれない。一刻も早く全国民がこれから脱皮せよ‼︎」なる、ある意味「世俗諦に屈した縁起論」に現実社会全てを還元させようとする政治的イデオロギーへと変貌してしまう。この状況を揶揄したと思われるのが「エヴァンゲリオンの赤い海」…
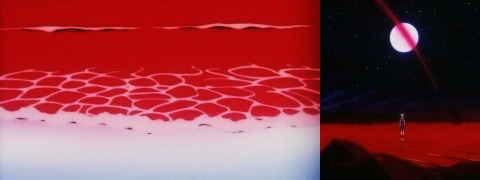
*同時進行でアナール派や経済人類学の導入が進行したが、これもその「反権力的雰囲気」が気に入られたせいだったと考えられている。
こうして全体像を俯瞰して浮かび上がってくるのは以下の様な景色。
1399夜『歴史序説』イブン=ハルドゥーン|松岡正剛の千夜千冊
日本にはセム系一神教に特有な「神に対する恐怖」がきわめて薄い。イスラームにおけるアッラーに対する畏怖は「タクワー」とも言われ、『クルアーン』(コーラン)では「神を恐れよ」という投げかけが頻繁に告げられる。これは心理学的には身が縮みあがるような絶対的な“対神恐怖”というものなのだが、これが日本人にはさっぱりわからない。あるいは、そんなふうには神を絶対視しない。とくにイスラームの「タウヒード」(神の唯一性)が実感できないままなのだ。
*上掲の「(実質上スンニ派古典思想と合致する)イデア論」は、この恐ろしさを合理的に薄める事で近世への歴史的展開を準備したといえる。最初に「恐怖」がなければ、その有り難みもまた分からない?
言ってみれば、日本人には神や仏はなんとなく感じさえすればいいわけだ。それが初詣と仏式葬儀とクリスマスとが、なんなく共存できている理由なのである。
要するに日本人は社会の法と仏教の法とをつなげられなかったのである。
「世俗諦に屈した縁起論」なる現象の背景には、さらに「伝統的エリート階層が真諦を独占する顕密体制に対する階級的憎悪」から「全てを(一切が不可分な)縁起の世界に還元しようとする破壊衝動」がドロドロと渦巻いていたのが日本特有の伝統的情景だったといえそうです。そう考えると第一次世界大戦特需を背景に1910年代に花開いた自由主義が右翼(軍国主義者)側からも、左翼(社会主義者)側からも挟撃されたのは歴史的必然というべきだったかもしれません。
*とはいえ、よく考えてみるとこれはこれで「世俗諦に屈した縁起論」的世界観から完全に離れ切っていない気がしてきた…
僕は精神が好きだ。しかしその精神が理論化されると大がいは厭いやになる。理論化という行程の間に、多くは社会的現実との調和、事大的妥協があるからだ。まやかしがあるからだ。
精神そのままの思想はまれだ。精神そのままの行為はなおさらまれだ。生れたままの精神そのものすらまれだ。
この意味から僕は文壇諸君のぼんやりした民本主義や人道主義が好きだ。少なくとも可愛い。しかし法律学者や政治学者の民本呼ばわりや人道呼ばわりは大嫌いだ。聞いただけでも虫ずが走る。
社会主義も大嫌いだ。無政府主義もどうかすると少々厭になる。
僕の一番好きなのは人間の盲目的行為だ。精神そのままの爆発だ。しかしこの精神さえ持たないものがある。
思想に自由あれ。しかしまた行為にも自由あれ。そして更にはまた動機にも自由あれ。
巴里のグラン・ブルヴァルのオペラ前、もしくはエトワアルの広場の午後の雑沓初めて突きだされた田舎者は、その群衆、馬車、自動車、荷馬車の錯綜し激動する光景に対して、足の入れ場のないのに驚き、一歩の後に馬車か自動車に轢ひき殺されることの危険を思って、身も心もすくむのを感じるでしょう。
しかしこれに慣れた巴里人は老若男女とも悠揚として慌てず、騒がず、その雑沓の中を縫って衝突する所もなく、自分の志す方角に向って歩いて行くのです。
雑沓に統一があるのかと見ると、そうでなく、雑沓を分けていく個人個人に尖鋭な感覚と沈着な意志とがあって、その雑沓の危険と否とに一々注意しながら、自主自律的に自分の方向を自由に転換して進んで行くのです。その雑沓を個人の力で巧たくみに制御しているのです。
私はかつてその光景を見て自由思想的な歩き方だと思いました。そうして、私もその中へ足を入れて、一、二度は右往左往する見苦しい姿を巴里人に見せましたが、その後は、危険でないと自分で見極めた方角へ思い切って大胆に足を運ぶと、かえって雑沓の方が自分を避けるようにして、自分の道の開けて行くものであるという事を確めました。この事は戦後の思想界と実際生活との混乱激動に処する私たちの覚悟に適切な暗示を与えてくれる気がします。
『先駆』五月号所載「四月三日の夜」(友成与三吉)というのがちょっと気になった。
それは、四月三日の夜、神田の青年会館に文化学会主催の言論圧迫問責演説会というのがあって、そこへ僕らが例の弥次やじりに行った事を書いた記事だ。友成与三吉君というのは、どんな人か知らないが、よほど眼や耳のいい人らしい。僕がしもしない、またいいもしない事を見たり聞いたりしている。たとえば、その記事によると、賀川豊彦君の演説中に、僕がたびたび演壇に飛びあがって何かいっている。
しかし、そんな事はまあどうでもいいとして、ただ一つ見遁みのがす事の出来ない事がある。賀川君と僕との控室での対話の中に、僕が「僕はコンバーセーションの歴史を調べて見た。聴衆と弁士とは会話が出来るはずだ」というと、賀川君が「それは一体どういう訳だ」と乗り出す。それに対して僕がフランスの議会でどうのこうのと好いい加減な事をいう、というこの最後の一句だ。何が好い加減か。この男は自分の知らない事はすべてみんな好い加減な事に聞えるものらしい。
僕らの弥次に対して最も反感を抱いているのは警察官だ。
警察官は大抵仕方のない馬鹿だが、それでもその職務の性質上、事のいわゆる善悪を嗅かぎわけるかなり鋭敏な直覚を持っている。警察官の判断は、多くの場合に盲目的にでも信用して間違いがない。警察官が善いと感ずることは大がい悪い事だ。悪いと感ずることは大がい善い事だ。この理屈は、いわゆる識者どもには、ちょっと分りにくいかも知れんが、労働者にはすぐ分る。少なくとも労働運動に多少の経験のある労働者は、人に教わらんでもちゃんと心得ている。そしてそれを、往々、自分の判断の目安にしている。いわばまあ労働者の常識だ。
僕らの弥次に反感を持つものは、労働者のこの常識から推せば、警察官と同じ職務、同じ心理を持っている人間だ。僕らは、そんな人間どもとは、喧嘩をするほかに用はない。元来世間には、警察官と同じ職務、同じ心理を持っている人間が、実に多い。
たとえば演説会で、ヒヤヒヤの連呼や拍手喝采のしつづけは喜んで聞いているが、少しでもノオノオとか簡単とかいえば、すぐ警察官と一緒になって、つまみ出せとか殴れとかほざき出す。何でも音頭取りの音頭につれて、みんなが踊ってさえいれば、それで満足なんだ。そして自分は、何々委員とかいう名を貰って、赤い布片でも腕にまきつければ、それでいっぱしの犬にでもなった気で得意でいるんだ。奴らのいう正義とは何だ。自由とは何だ。これはただ、音頭取りとその犬とを変えるだけの事だ。
僕らは今の音頭取りだけが嫌いなのじゃない。今のその犬だけが厭なのじゃない。音頭取りそのもの、犬そのものが厭なんだ。そして一切そんなものはなしに、みんなが勝手に踊って行きたいんだ。そしてみんなのその勝手が、ひとりでに、うまく調和するようになりたいんだ。
それにはやはり、何よりもまず、いつでもまた何処どこにでも、みんなが勝手に踊る稽古けいこをしなくちゃならない。むつかしくいえば、自由発意と自由合意との稽古だ。
この発意と合意との自由のない所に何の自由がある。何の正義がある。
僕らは、新しい音頭取りの音頭につれて踊るために、演説会に集まるのじゃない。発意と合意との稽古のために集まるんだ。それ以外の目的があるにしても、多勢集まった機会を利用して新しい生活の稽古をするんだ。稽古だけじゃない。そうして到る処に自由発意と自由合意とを発揮して、それで始めて現実の上に新しい生活が一歩一歩築かれて行くんだ。
新しい生活は、遠いあるいは近い将来の新しい社会制度の中に、始めてその第一歩を踏み出すのではない。新しい生活の一歩一歩の中に、将来の新しい社会制度が芽生えて行くんだ。
僕らのいわゆる弥次は、決して単なる打ち毀しのためでもなければ、また単なる伝道のためでもない。いつでも、またどこにでも、新しい生活、新しい秩序の一歩一歩を築き上げて行くための実際運動なのだ。
弁士と聴衆との対話は、ごく小人数の会でなければ出来ないとか、十分にその素養がなければ出来ないとかいう反対論は、まったく事実の上で打ち毀されてしまった。怒鳴る奴は怒鳴れ、吠える奴は吠えろ。音頭取りめらよ。犬めらよ。
こうして全体像を俯瞰してみると、リバタリズムって本当に存命時「ヨーロッパで一番危険な男」と称された「永遠の革命家」オーギュスト・ブランキ(Louis Auguste Blanqui、1805年〜1881年)の一揆主義と表裏一体の関係にあるのですね。「真の革命家に勝利の日など訪れない。何故なら体制転覆に成功したその日から、新たなる反体制派への弾圧が始まるだけなのだから」。何たる諦観…
(おそらくビスマルク宰相によるドイツ帝国建国過程に学んだと思われる)カール・シュミットの政治哲学は「政治とは適切な敵を設定し、味方を一致団結させ同化を進める技術である(敵友理論)」「政治は選挙で選ばれた各利権の代表者を寄せ集めただけでは始まらない。そうした個々の利害関係を超越した判断を行える政治的エリート集団の形成を必要とする(例外状態)」と主張しましたが、こういう「醒め切った個人主義者」は完全船頭対象外となります。だから余計に憎悪を買ってしまったという次第。総力戦体制期(1910年代後半〜1970年代)には、有り勝ちだった悲劇…
そして結果として科学実証主義は「語り得ることを語り尽くすことで語り得ぬことの輪郭を浮彫りにする」立場へと到達する訳ですが、欧米社会と異なり大して葛藤する事なく主権国家への移行を完了してしまいます。ある意味「最初から近世への準備が整っていた国」にカウントし得る存在だった訳で、だから古代循環史観とは無縁だった欧州思想史においてその観点がスッポリと抜け落ちた様に「歴史とは何か」とか「社会とは何か」といった課題について鋭い思考が養われる事がなかったとも。
- そもそも日本という国は最初期の「古墳国家段階」や「護国仏教段階」において律令制導入などを経て部族連合段階から完全脱却を果たしている。
- 前近代まで経済的発展を牽引してきたのは「有徳人」や「株仲間」と呼ばれる正体不明の人々の詳細不明のネットワークだった。
*ある意味「世俗諦に屈した縁起論」のイメージの大源流の一つだったとも。
- 都中心主義からも室町時代末期における「京都焼き討ち」を契機に克服。
*そして全国に「小京都」が出現し都会と田舎の文化格差が急激に縮まる。 - 宗教問題も「神仏習合」によって有耶無耶に。
*これも「世俗諦に屈した縁起論」のイメージの大源流の一つ?
それではおもむろに冒頭の設問、すなわち「イブン・ハルドゥーンとデュルケームはどういう関係にあるのか?」に戻って見たいと思います。
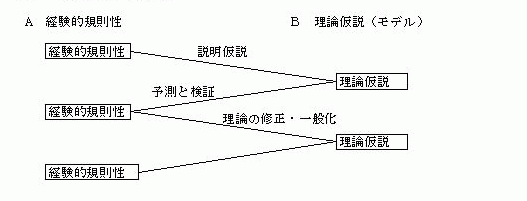
- (ティムール帝国の興亡まで見届けた)14世紀の歴史学者イブン・ハルドゥーンの視野には「文明=国家=社会」は、部族的紐帯を武器に田舎から攻め上がってきた蛮族が繁栄によってすっかり文弱化した旧支配階層を滅ぼして政権交代を達成した後、自らも文弱化して部族的紐帯を失っていく循環プロセスを繰り返しているとしか映らなかった。
*ただしメソポタミア文明時代から繰り返されてきたこの種の政治的営みは「戦争遂行の為に臣民や国内資産を最後まで全て動員可能な官僚制によって常備軍が維持される」主権国家の登場によって継続不可能となる。
- 主権国家においては産業革命の展開も加速し、伝統的地域共同体の崩壊が相次ぐ。「社会学の父」デュルケームはこうした歴史展開を危惧し、社会安定の為に新たな共同体の形成が不可避と考えて方法論的集団主義に基づく研究に邁進したのだった。
*「戦前最大のマルクス主義理論家」戸坂潤は「我々が自由意志や個性と信じているものは、社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない」と述べたマルクスの主張は「社会実在論」においてフランスの社会学者デュルケームが(個人心理学的アプローチから)模倣犯罪学なる分野を立ち上げたタルドを論破した事によって実証主義的人文科学への足掛かりを得たと考えた。
*一方ドイツにおいては「我々が自由意志や個性と信じているものは、無意識からの命令に過ぎない」とするフロイトの無意識論と結びつき「個々人の無意識に当人も意識しない形で共通性を強制挿入するある種の権力」としての社会が方法論的個人主義的に探求された。有名なマックス・ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年~1905年)」もこの立場から執筆されている。
確かに結果としてイブン・ハルドゥーンの研究は王朝論となり、デュルケームの研究は共同体論となりましたが、どちらもその時代なりに「社会を存続させるのは何か?」について真摯に取り組んだ点ではぴったりと重なってきます。ここで興味深いのが戦前日本を代表するマルクス主義理論家だった戸坂潤がその著作の中でドイツ社会学の方法論的個人主義とタルドの模倣犯罪学には反感を表明し、デュルケームの方法論的集団主義には喝采を送っている辺り。

- 考えてみればフランスが革命を通じて郡県制へと移行出来たのも、明治政府が「版籍奉還(1869年)」「廃藩置県(1871年)」「廃債処分(1872年)」「廃債処分(1872年)」「秩禄処分(1876年)」を矢継ぎ早に遂行して徳川幕藩体制を解体して都道府県制に移行出来たのも、伝統的地域共同体にそうした急激な変化を受容するだけの柔軟性が備わっていたからであった。

- イエズス会や聖ニコライが伝教対象に選んで大成功を収めたのもやはり伝統的地域共同体だったし、立憲政友会も在地有力者や現地リーダーを標的とした「我田引鉄」作戦によって度重なる選挙権拡大を乗り切っている。
こうした観点から見ても戸坂潤は間違いなく「日本の共産主義運動の成否は全国各地の伝統的共同体をどれだけ取り込めるかに掛かっている」と考えていたし、その考え方を実践したのが所謂「労農派」だったとも。
その点、イブン・ハルドゥーンの観点が所謂「テュルク=タジーク制」において既得権益安堵の代償に官僚供給層として機能するテュルク(オアシスなどに定住する在地有力者。中央アジアでは主にペルシャ系)にまで及んでいたかどうかが気になります。王朝論しか展開出来なかったのは都市しか知らず、田舎には足もむけた事がなかったからかも知れず、かかる都市と田舎の分断こそがイスラム諸王朝の伝統的課題となってきた訳ですから…

