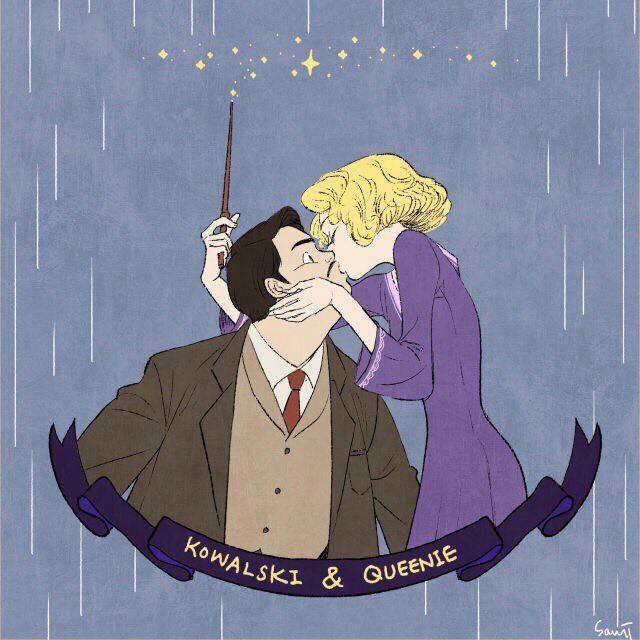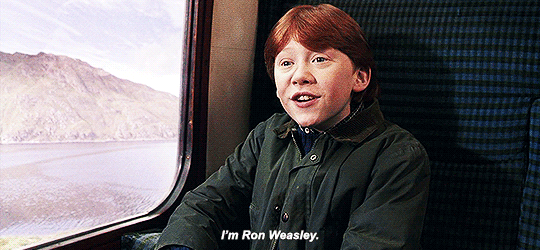本当に惜しい。もし「私、誰の心を覗くか自分で決められないからこそ、心が綺麗で純粋な夢を追っかけてる相手しか選びたくないの」とか、そんな一言が明示的に添えられただけで2016年度Love Storyランキングの上位に食い込めたのに…

Queenie and Jacob by PatPaige - Random Allusions

Percival Graves Trash - Queenie/Jacob || you’re so beautiful [x] Burning...
Kowalski & Queenie by… well, I couldn’t quite... - Random Allusions
何の話? もちろん…
心の読める魔女「わたしたち〜」
パン屋の店長「もしかして〜」
主人公「いれかわってる!!(またカバンが)」
の、「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 (Fantastic Beasts & Where to Find Them)」の話です。
ファンタスティックビースト、実質『君の名は。』というか、マジで『君の名は。』過ぎてちょっと笑ってしまうくらい『君の名は。』です
— ねりま (@AmberFeb201) 2016年11月25日
海外評で吹いたのは「J.K.ローリングは嫉妬いから、メインヒロインを必ず酷い男とくっつける」というもの。読者の納得いかないカップル量産マシンなる悪名は、この作品でも遺憾なく発揮されちゃった?
*キャラの好き嫌いだけでなく恋愛展開の唐突さも含むらしい。
まぁ、これに関しては「どうしてハリー・ポッター×ジニー・ウィーズリーでロン・ウィーズリー×ハーマイオニー・グレンジャー?」「ルーナ・ラブグッドじゃ 駄目だったんですか?」「そもそもジニー・ウィーズリーって誰よ?」といった具合の壮絶なFundom論争があって「分別を弁えなさい!! 私達読者にできる事は現実(本編の展開)を素直に受容して、それについての最良の解釈を引き出すのを楽しむ事だけなの」と主張する良識派が最終的勝利を収めたりとか、いろいろ大変な展開があったんです。
*「いいですか、皆さん。男子がまだこの状態のうちに、将来ああなると見抜くのです」「 先生、ずぇーったい無理です」なんて定番ギャグが成立したのもこの時期。どうして女子の恋愛論は極めれば極めるほど武芸者の武芸論と似てくるのか。
*ちなみに当時私はルーナ・ラブグッド(Luna lovegood)派に属してたのです。比較的男子の比率が高く「これだから男子は…」とか冷たい目で見られ、実際ネット上の同胞が次々と討ち取られていく悪夢を経験。もちろん国際SNS上の関心空間の標準語は英語とスペイン語とポルトガル語で、そうした言語でペラペラ自説を開陳するタイプでない限り「討ち取られる」心配なんぞ不要だったのだが…今から思えば、あの女子ばかりで編成された「反ルーナ騎士団」って一体何だったのだろう?

【意訳】「私はルーナが好きではありませんでしたが(決っして嫌いだったわけじゃありません)ジニーを選んだハリーには純粋に失望を禁じ得ませんでした。初登場以来ずっと一緒にいて、衝動的でともすれば迷走しがちな性格のハリーをずっと支えてきたのに。私の目には二人こそ互いを特別視せず欠陥を補完し合う地上で最も完璧なカップルと映ってたんです。」
*割と「こういう不思議ちゃん好き」レベルの軽薄なタイプが多かった男子ルーナ派。まぁだからこそ「反ルーナ騎士団」の逆鱗に触れ、次々と虫ケラの 様に易々と狩られていった訳だけど(国際SNS上の関心空間には「それがこの地に留まる4chan兼民の役割」なんて恐るべき暗黙の了解が存在する)、女子ルーナ派はガチGothタイプが多く、双方とも(一度戦端が開かれたら殲滅戦になると分かっているので)直接対決は避けつつつ「手前ら、ヴォルデモート卿に魅入られたベラトリックス・レストレンジと何が違うよ?」なんて陰口が流れる形に。しかも、全体像を俯瞰したこういう視点まで存在したからややこしい。
J.K.ローリング当人もこういう流れを相応に気にしていたらしく「ハリー・ポッターと呪いの子(Harry Potter and the Cursed Child、2016年)」で壮絶なまでのフォローを展開。「ハリーは本来こういう存在だから、ジニーくらい受動的なタイプでないと受け止め切れないの。ハーマイオニーも独身だとこういう具合に煮詰まっちゃうタイプだから、ロンくらいチャランポランなタイプでちょうど釣り合うの」といった自説を強烈に開陳。その一方で(ハリーが娘にその名前まで与えた)ルーナ問題への直接言及はなく、ベラトリックス・レストレンジについてはさらにディープな事実が明らかに。まだまだ未回収の伏線(Unfinished Business)も多いですが、それについては多分ルーナ・ラブグッドの義理の祖父ニュート・スキャマンダーを主人公に据えたファンタビ・シリーズで説明される事になるのでしょう。これに以下の過去が絡んでくるのは必定?
心優しい少女だったが、6歳の頃に、魔法を使っているところ(「ダンブルドア校長の弟」アバーフォースが言うにはこの年頃の魔法使い・魔女は魔法の力の制御はできない)を3人のマグルの少年に見られてしまい乱暴される。
それが原因で精神的に不安定となってしまい、自分を抑えきれなくなると、感情が爆発し魔力が暴走する「発作」を起こすようになった。それを隠すため、一家はゴドリックの谷に引っ越し、アリアナは軟禁状態に置かれた。
14歳の頃、アバーフォースが留守の間に「発作」を起こした彼女を静めることができず、母ケンドラが死亡。残されたアルバスとアバーフォースはどちらがアリアナを世話するかで争ったが、結局はアルバスが妹を世話することになった。
しかし数週間後、ゲラート・グリンデルバルドがゴドリックの谷を訪れたことで、アルバスがグリンデルバルドと行動を共にするようになり、その後、グリンデルバルドとアルバス、アバーフォースの間で争いが起こり、この争いが原因でアリアナは「発作」を起こし、誰かが放った呪いがアリアナの命を奪ってしまった。3人が気づいた時には彼女は息絶えていた。
どう考えてもこれ「オブスキュラス」じゃないですか。
- どうやらJ.K.ローリングはある種の憂鬱症の持ち主らしく、その時感じる「すべてを無に帰してしまう絶対的虚無感」から吸魂鬼(Dementor:ディメンター)やヴォルデモート卿やオブスキュラスといった「非実在の闇から飛来する怪物」を着想したらしい。
- だからハリー・ポッター・シリーズの世界は「みんな仲良く」でなく、それが自分の一部と 分かっていながらあえて「(周囲に実害を与え、建設的努力をくじく)非実在の闇から去来する怪物」だけは切り捨てる未来を志向してきた。ファンもそれは熟知しており、それで「ヴォルデモート卿は(選択肢を間違った)私!!」、「( 「シンゴジラ」の)鎌田君は私!!」、「オブスキュラスは私!!」と叫んできたという次第。
- しかしファンタスティック・ビースト・シリーズの世界はこのテーマについて、さらに一歩踏み込もうとしている。「脅威は発生の可能性ごと除去すべし」なる理念を奉じてオブスキュラスは見つけ次第滅ぼそうとする米国魔法省の保守的態度。それと対比的にオブスキュラスを「必ず助ける」と誓う主人公の登場。石田スイ「東京喰種(Tokyo Ghoul、2011年)」や「パラノーマン ブライス・ホローの謎(ParaNorman、2012年)」めいたヘビーな恨解の物語が展開するのは必定?
*ここは最初からのハリーポッターファンとして是非「奴らもう 勝ったつもりでいますぜ」「では教育してやるか」クラスの逆転勝利を期待したいところ。
「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」におけるリーマス・ルーピンの説明
「吸魂鬼は地上を歩く生物の中でももっとも忌まわしい生き物の一つだ。もっとも暗く、もっとも穢れた場所にはびこり、凋落と絶望の中に栄え、平和や希望、幸福を周りの空気から吸い取ってしまう」
しかもこれにスネイプとの絡みで「愛の証として死まで要求する超ハードサディステック・ホモ」の烙印を押されたアルバス(ダンブルドア校長)と「恋人」グリンデルバルドが絡んでくる。もしかしたらミュータントの未来に関するプロフェッサーXとマグニートの価値観の違いを軸に展開する「X-Men」シリーズの超克あたりまで狙ってるのかもしれません。これでワクワクしないほうがおかしいとも?
ところで前回の投稿に関してこんなやりとりがありました。
日本で類例を探すなら、岩明均「七夕の国(1996年〜1999年)」とか貴志祐介「新世界より(2008年、アニメ化2012年〜2013年)」あたりかなぁ…そしてハリーポッター・シリーズと違って「魔法が使える事に付帯する対価が重過ぎて気楽に使えない」のが敗因だったとも。
新世界より、読みましたよ。あれは暗い小説でした。ハリポタのワクワク感が無いわ。悪の教典の作者の新境地ですね。読ませる小説ではあったわ。 / “【ネタバレなし】「ファンタスティックビースト」観てきました。まさか「君の名は」? - …” https://t.co/uvMBALq85m
— 松井 (@wdMiCaPlx0Pffks) 2016年11月26日
これまさに「どうして日本人の想像力はハリー・ポッターを生み出せなかったのか?」なる疑問についての本質を突いてる指摘だと思うんでよね。
- 現代ファンタジーの基礎を築き上げたトールキンやル・グインといった 始祖達は、なまじ古典文学や宗教人類学の世界に精通していたが故に、魔法を気軽に日常的に使えるペナルティなき能力として気軽に扱う事など思いつかなかった。そして「魔法の世界」が古典文学や宗教人類学の世界から独り立ちしていく過程に陰鬱なビジョンしか持ち得なかった。
- その一方でTVゲームなどの世界では気軽に魔法を打ち合う文化が発達したが、こちらはこちらでファンタジー文学の世界の魔法みたいにドラマ性と結びついた重厚な展開と無縁になり過ぎて結局「強ければ強いほど良い」ハイパー・インフレ状態に陥ってしまう。
- J.K.ローリング「ハリー・ポッター・シリーズ(Harry Potter Series、1997年〜2016年)」は、まさにこの分断状態を背景に降誕した訳である。(誰もが「魔法ごっこ」で気軽に使いたくなる様な)一般的な魔法呪文は本当にあっけなく2つ上的に使われる一方、「磔の呪い(Cruciatus Curse)」 「クルーシオ(Crucio、苦痛の呪い)」「インペリオ(Imperio、服従の呪い(Imperius Curse)」「アバダ・ケダブラ(Avada Kedavra、死の呪い(Killing Curse)) 」といった誰でも直感的に「術者が状況を楽しめば楽しむほど威力を増したり、そもそも効力を発揮しない。そして対価として術者を暗黒面に引き込む」と理解可能なおぞましい呪文群を設定。しかも「パクリ」呼ばわりされずにこの独特のバランス感覚を模倣するのが極めて困難で、良い意味でも悪い意味でも劣化コピー版が大量に現れる展開とはならなかった。「スターウォーズ・シリーズ(1977年〜)」がスペース・オペラの世界に与えた影響と 相似関係にあるとも。
まぁ、一言で言うと「ファンが求める気持ち良いアクションの実現こそが最優先。そして、それに従って生じるジレンマはちゃんとドラマに反映する」みたいなエンタメ精神の勝利って事になるんですかね?