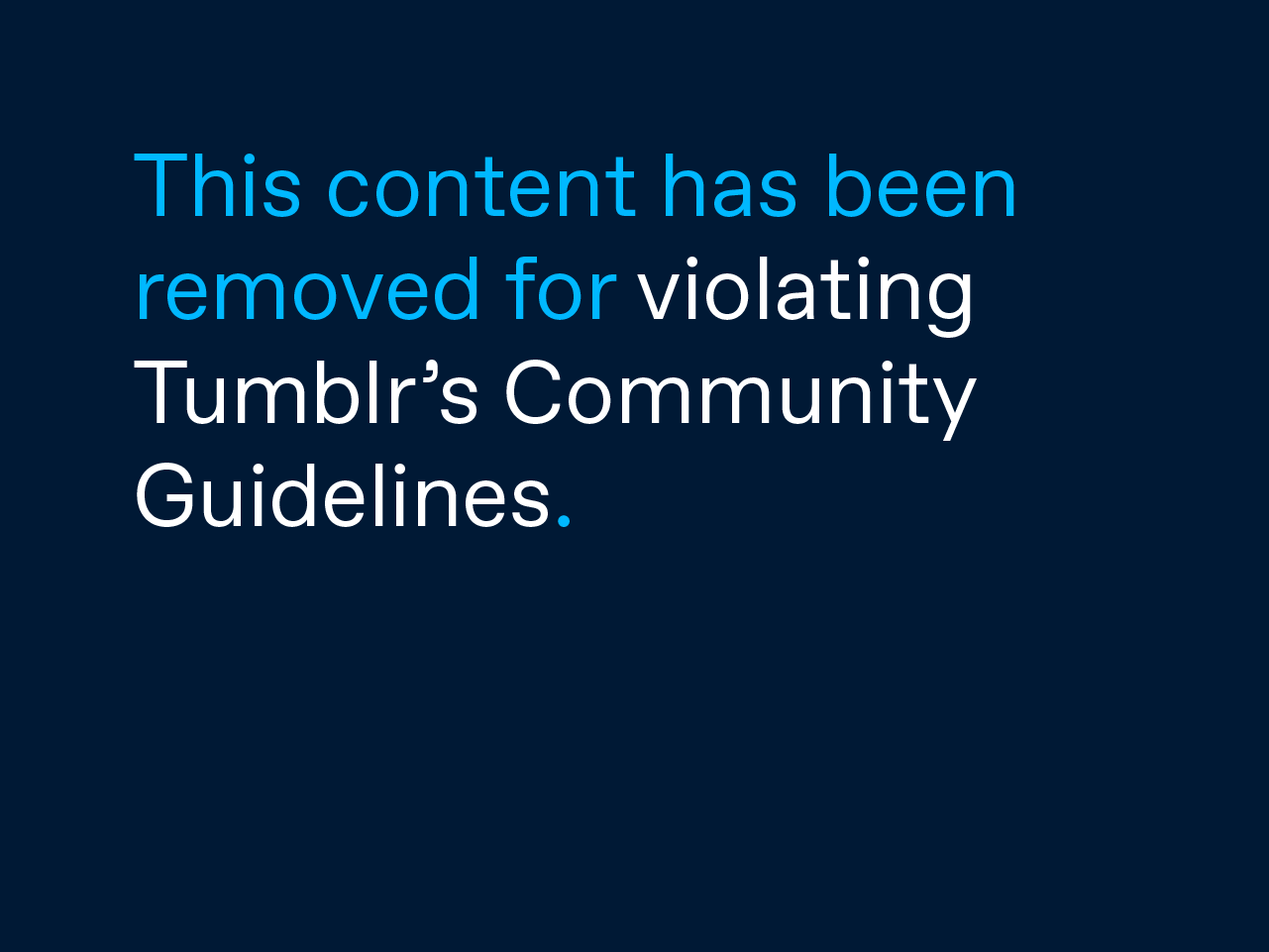明治天皇は現役当時、国際的に「大帝」と呼ばれていました。「大政奉還(1867年)」「王政復古の大号令(1868年)」「版籍奉還(1869年)」「廃藩置県(1871年)」「廃債処分(1872年)」「廃債処分(1872年)」「秩禄処分(1876年)」をスムーズに成し遂げて江戸幕藩体制の完全解体を成し遂げた「手腕」が評価されたのです。

- ただ、西洋文化の機微に通じた森有礼(1847年〜1889年)は「必ずしも褒め言葉ではなかった」という同時代証言を残している。「欧米先進国においては、王侯貴族の財産権(Property)に土足で踏み込ねば必ずしや致命的な内戦勃発を誘発する。そういう展開とならなかった事によって大日本帝国は帝政ロシア並の絶対王政 / 権威主義国家だと証明した様なものだ」。
*実際(福井藩の「お雇い外国人」として廃藩置県を経験した)W.E.グリフィスによれば、この時に明治天皇を「雷帝」と報じた海外メディアすら存在したという。もちろん欧米社会で「雷帝(ро́зный //the Terrible=「ひどく峻厳な / 恐怖を与える / 脅すような」統治者)」といったら「モスクワ大公」イヴァン4世(Иван IV Васильевич / Ivan IV Vasil'evich、在位1533年〜1547年)を指す。ある意味、この感覚を理解していないと「ロシア革命(1917年)が欧米諸国に与えた独特の印象」および「共産主義革命? ロシアだったら起こりかねん。何としても欧州への伝播までは防がねば」という所感が理解出来ないかもしれない。
- 実際の日本史を知る日本人の所感はまた異なる。幕末期へと至る過程で諸般の多くが債務超過の経営破綻状態にあったからこそ、こうした「大博打」はスムーズに通ったのだった。似た様な状況なら、壬申の乱(672年)の結果成立した天武天皇代(673年〜686年)にもあった。「(氏族戦争(Clan War)を激化させるだけの)氏姓(うじかばね)制」が完全破綻し、中華王朝から律令制を導入する試みが始まるまでの過渡期。天武天皇は従来の位階制度の一切を停止し、新位階制度を発足させたのである。
*この意味で日本の天皇には伝統的に「究極のリセットボタン」という機能が与えられてきたと表現される事もある。むしろ重要なのは天皇そのものの意思というより「誰がリセットボタンに手を伸ばしたか」だったりするという次第。
天武天皇 - Wikipedia
案外、日本人が「GHQ占領期(1945年〜1952年)」を黙って受容したのも。そうした伝統ゆえだったのかもしれない。
- こうした「日本のリセット文化」と対比すべきは、おそらく「時代遅れとなった太平洋三角貿易などをオンライン状態のままリアルタイムに精算してきた英米の凄み」なのである。
まさしく議会制民主主義に根差す重厚な保守主義文化の大源流。
どちらがいいかといった比較論ではなく「根底にあるのはこの発想」といった本質論の世界。基本的にどちらも部族連合状態から出発してる筈なのに、どうしてこんな違いが発生してしまったのでしょうか?
JAIRO | 国民国家の始原 : ジョン・フォーテスキューの政治理論についての一考察
ジョン・フォーテスキューの政治理論について,人民を志向する解釈と絶対王政を志向する解釈に分けて論じてきたが,最後にその双方を同じように強調する立場,すなわち「二重大権(double majesty)」論の見地に立った研究を取り上げたい。
マイケル・マンデルは,王的・政治的支配とは王と人民の「2つの回路を流れる権力をもつ君主政」であり,それはヘンリ・ブラクトンに代表されるイングランド中世法学に根差し,17世紀に開花することになる伝統のなかで,2つの時代を架橋する巨大な影響力をもったと論じた。
サンドズもまた,フォーテスキューの王的・政治的支配は,「議会において代表される政治的人民と法によって拘束された王権という二重大権の憲法」を意味するとしたうえで,それは太古からの自由を保護する法を王領の合意を通して確立するとともに,議会と王のバランスを保証して,全共同体の福祉に奉仕する効果的な支配を実現するところの「イングランドの古代憲法の心」そのものであると述べた。
つまり,フォーテスキューの王的・政治的支配は古から続くイングランドの伝統に根差す混合統治を示すというわけである。
もちろんフォーテスキューの時代のイングランドでは,まだ混合統治について論じられてはいない。混合統治に関するイングランドにおける古典的理論は,16世紀のテューダー期にトマス・スターキー,ジョン・エイルマ,ジョン・ポネット,トマス・スミス,トマス・カートライト,ロバート・パーソンズらの議論に垣間見ることができるが,その段階においてすら一貫した明確な政治理論には程遠く,イングランド人が政治的秩序を論じる際の知的道具にはなっていなかった。
ヒントンによれば,その後,エリザベス治世下,ジェームズ1世やチャールズ1世と議会との抗争において繰り返し用いられたが,それが明確な憲法理論となり,革命戦争のなかで流布したきっかけになったのは,1642年に議会側が議会主権を主張する「19カ条提案」をチャールズ1世に提出し,王がそれへの返答のなかで混合君主政を採用したことであった。
チャールズ1世が提示したイングランド統治のあり方は,「絶対王政・貴族政・民主政という3種類の統治が人間にはあり,これらはすべてそれぞれに独自の利益と不利益をもっているので,あなた方の祖先の経験と知恵はこれらの混合からイングランドの統治を作り出し,3つすべてのバランスが3つの身分の間で均等にとられる限り,3つのどれもが不利益を被ることなしに,(人間の深慮が行き届く範囲内において)3つすべての利益がこの王国に与えられるようにしたのです」という言葉に示されている。チャールズ1世の意図は国王の身分的保証であったが,この言葉のなかではっきりと表現された混合君主政の特徴は,3身分のチェック&バランスと機能分化であった。
このようにイングランド政治思想史のなかで,二重大権や混合統治といった独自の伝統を中世から近代へと架橋して発展させた人物としてフォーテスキューを位置づけることは,1930年代のクライムズやマックス・A・シェパードの論述にも垣間見られるので,長い歴史をもつ解釈の仕方と言ってよいだろう。
ドナルド・W・ハンソンの二重大権説
そのなかでも一際優れた研究を行ったのが,二重大権と混合君主政を明確に区別する必要性を唱えたドナルド・W・ハンソンである。
ハンソンによれば,フォーテスキューの理論のなかには,身分を差異化する議論も身分代表の観念もなければ,チェック&バランスと機能分化の論理も含まれていない。というのも,チャールズ1世の時代に混合統治の理論が洗練されるようになったのは,主権論が前提になり,それの行使に関して国王と議会,ないしは国王と貴族と平民の間に対立関係が明確に存在するようになったからであるが,フォーテスキューの時代にはまだ主権論が生まれていないからである。こうした理由により,ハンソンは混合君主政を二重大権から区別し,後者のみをフォーテスキューに帰属させた。
では,二重大権とは何か。
二重大権という独創的な表現そのものは,オットー・ギールケが作りだした言葉であるが,ハンソンはイングランドの法的・政治的文脈のなかでギールケとは異なる意味でそれを用いる。
ハンソンによれば,二重大権の論理の核心は,社会秩序を形成する王と貴族のどちらもが,それぞれの権威を他方に由来させることはなく,それぞれに独立した権威をもつことにある。王が貴族によって選ばれ,貴族の称号が王によって授与されたとしても,それはパートナーシップが統治慣行に反映されたにすぎない,ということである。
ハンソンは二重大権の非王について,貴族以外のさまざまな名で現れ,時には「人民(populus)」と呼ばれたことにも注意深く言及する。確かにイングランドでもソールズベリのジョンの著作に見られるように「人民」に権力の淵源があるという主旨の記述はあった。ハンソンはそれについて,中世の語法で言えば,近代的な意味での人民の大多数は「教育を受けた人,あるいは生まれの良い人の視野や関心には入ってこない」ような「民衆(vulgus)」なので,「人民」が貴族と互換的であったとしても驚くようなことではないとする。マグナ・カルタにしても,サインをしたのはほんの一握りの貴族であった。重要なのは「政治的な命令が2つの本来独立した正統性の源の結合として特徴づけられること」であり,王と貴族ないし「人民」の両者とも,単独ではすべての法的・政治的問題について結論を下す権限があるとは見なされなかったことだ。
「二重大権(double majesty)」ゲルマン社会起源説
ハンソンはこうした二重大権の起源を古代ゲルマン社会に求める。
- ハンソンによれば,そこにおいて戦争集団は首長(princeps)と従者(comes)の人格的絆に基づく互恵的関係によって形成され,首長は従者に武器や戦利品を与え,従者は誓いの言葉をもって長に死を賭する忠誠を尽くした。
- ただし,この関係は血縁や種族からも独立した「偶然的な関係」であり,それゆえに首長の贈与能力と軍事的成功に依存した。中世の継承的王国は,こうしたゲルマン的戦争集団の絆が制度化され,土地に根ざすことによって確立したのである。
- そこにおいて,王と貴族の関係は直接的で人格的な一対一の関係であり,個人的愛着の絆を超える政治的忠誠の感覚はなかった。古代の都市への忠誠も,近代の市民的な意識や官僚的な非人格的愛着もなく,貴族的な地位と権利について共有された観念だけが中世の貴族を束ねていた。このように主君と臣下の個人的関係が中枢にあったがゆえに,二重大権が組織原理として生き残り,王権に対し一定の平衡力を構成する「評議」という慣行を生んだ。
ハンソンは以上のように二重大権を定式化した後「フォーテスキューはイングランド政治が二重大権と呼ばれる正統性の理念に依拠していることを完全に知っていた」のであり,彼の作品において「二重大権は絶頂に達した」として,彼が中世末期イングランドにおける二重大権という「操作的政治思想」の完成者であると述べた。
- なぜフォーテスキューが中世に属すかについて,ハンソンは「フォーテスキューの思想体系のなかで決定的である要素は国王と人民が幸福に結びついているという仮定である」と述べる。この説明は至極明快である。
- ハンソンによれば「人民」は議会によって代表されるとフォーテスキューが考えていたことは確実であるが,しかし当然のことながら,フォーテスキューはまだ近代的な市民権の理念を知らず,17世紀に顕在化する国王と人民の対立も知らない。
- 国王と人民はそれぞれに生得の権威をもつが,慣習と法によって制約されながら一体化した王と人民という図式には,二重大権が孕む対立の可能性,おそらくはその不可避性が組み込まれることはなく,それゆえにイングランドの法と統治を礼賛できた,とハンソンは言う。
これまでのフォーテスキュー研究のなかでハンソンが論じた二重大権論的解釈はもっとも説得力をもった研究の一つだろう。独立した2つの権威の源泉があり,それが対立することなく共存する中世イングランドの政治理論をもっとも明確に定式化したものとして「王的・政治的支配」を論じることは,アーサー・B・ファーガソンが言うように,イングランド統治を礼賛しようとするフォーテスキューの「ユートピア熱狂」の姿勢からしても妥当なものだろう。
この表現だと「二重大権(double majesty)」の大源流の一つとしてハスカール(従士)制を見ることになりそうです。
(古ノルド語:Huskarl)/ハウスカール(英語:Housecarl)
11世紀初頭頃から文献記録に登場するゲルマン民族、特に北欧やイングランドで見受けられた軍制の一種。当時欧州軍事力の主体だった「乗馬突撃能力に長けた100騎〜200騎の重装槍騎兵で構成された騎士団」を編成。
*ウィリアム・マクニール「ヴェネツィア(enice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1978年)」によれば、これこそがまさに欧州の十字軍 / 大開拓時代(11世紀〜13世紀)を牽引した「圧倒的暴力=軍事的優位」だったという。小規模とはいえ幼少の頃から高度な戦闘訓練を受けて首領や王侯貴族に私兵として仕えてきた職業軍人によって編成された常備軍であり、普段は食客として暮らし、有事の際には報酬として主に金銭や略奪品の分け前などを受け取っていた。ただしあくまで自発的な戦闘集団であった為に主君に絶対服従を誓うとは限らず、実際首領や王侯貴族が略奪を禁止したり十分な報酬を支払わない場合、彼らを排除したり見捨てたりする事すらあったのであった。
*幸村誠「ヴィンランド・サガ(VINLAND SAGA、2005年〜)」 では彼らを「客人」と呼び、北欧諸族の伝統的互酬慣習との関係を強調する。イングランドへはスヴェン1世双叉髭王(デンマーク王985年〜1014年、ノルウェー王985年〜995年、1000年〜1014年、イングランド王1013年〜1014年)が持ち込んだとされ、この土地でのハスカールは王宮に住み、1人の伯に対して250~300人が仕えていたという。当時のイングランドとしてはほぼ最強の戦士集団であったが消耗補充能力に乏しく、その事がヘイスティングズの戦い(1066年)で不利に働いたとも。
*またこの戦いではハロルド2世が戦死した後も配下のハスカールが最後の一人に至るまで果敢に戦い、討ち死にしていったとされるが、実にハスカールらしくない展開であった。
ギヨーム公のヘイスティングズの戦いでは、レンヌ伯に敵対的な北東部の領主たちが数多く参戦し、その褒賞としてイングランド各地に領地を与えられた。征服の100年後でも、イングランド王国全体の約5000の騎士領の5%(250の領地)がブルターニュ出身の騎士たちのものだった。ちなみに、ギヨーム一族はブリテン島の半分の領地を、そのほかのノルマン出身貴族が1/4を取得し、以前の支配者であるサクソン人はわずか5%を保持するに過ぎなかったという。
こうした経緯に鑑みても「英国王権意識の大源流はハスカール(従士)制だった」という印象は強化されるばかり。
なるほど、二重大権論を基礎とした混合政体英国がその後、軍事財政国家として新たな貴族階級である勅許会社とともに重商主義政策によって私腹を肥やしたり、国有地をタダ同然で処分するような大阪のアレも、ゲルマン的な戦争略奪-主従対等(二重大権)=幸せな結婚があってこそなのかも。
— 95389592 (@95389592) 2017年3月19日
でも、そんな幸せな結婚状態がながく続くわけがないというあたりが、一般的かつ歴史的な理なのかもしれないわねー。
— 95389592 (@95389592) 2017年3月19日
念のため追記。古代ゲルマンに起源をもつ二重大権論を紹介したのは、英国に起源をもつ議院内閣制って、実は王権に民主的統制を加えることに主眼があるというよりは、サルの政治と同じで合従連衡を通じた群れの支配に主眼があるってことを、民主主義万歳のお子様たちに注意喚起したかったのよねー。
— 95389592 (@95389592) 2017年3月19日
まぁ実際「17世紀英国の商業革命(クロムウェル卿が企図した、英国経済基盤のカリブ海シフト=大西洋三角貿易の成立)」なんて流れも、こうした歴史的展開の一環として位置付ける事が可能だったりします。
この商業革命こそがイングランドを近世欧州大陸で王侯貴族が繰り広げた「華麗なる氏族戦争(Clan War)」から脱却させる原動力となっていきます。やがてポルトガルや北欧諸国もその輪に加わり第一次世界大戦(1914年〜1918年)を迎える展開に。
内村鑑三 デンマルク国の話 信仰と樹木とをもって国を救いし話
日本の場合どうだったのでしょうか。
- 日本で最も中華文明の影響力が色濃く及んでいた九州北部において、まず「最初の部族連合(連合王国)」が成立した(紀元前1世紀〜3世紀)。ただしこの種の組織は(北米のイロコイ連邦の様に)部族解体を恐れるあまり中央集権化を目指さないのが普通である。
イロコイ連邦(Iroquois)/6部族連合(Six Nations) - Wikipedia
*フランク王国(481年〜987年)を建国したフランク族もまた同種の部族連合(連合王国)から出発しており、それゆえに安定した中央集権体制に到達出来なかったと考えられている。そして神聖ローマ帝国は第一次世界大戦(1914年〜1918年)の頃までこの弱点を引きずり続けていく事となる。その一方で帝政ローマ植民地の残党支配地域、およびイングランドから招聘した官僚 / 聖職者やアイルランドからの伝教者からの影響を不可逆的な形で受けた。イロコイ連邦に所属する国家は母系社会であり、クラン・マザー(氏族の母)をはじめとする女性たちが合議し、連邦を運営する首長たちを推挙・解任する。首長は連邦全体で50名で構成され、モホーク族9名、オナイダ族9名、オノンダーガ族14名、カユーガ族10名、セネカ族8名と決まっている。首長にはそれぞれに称号があり、次代の首長へと継承される。その中にはワンパムの保管など特別な役目をもつ称号もある。
*「グランド・ピースメーカー (Grand Peace Maker)」として、モホーク族のハイアワサと並び称される「(5部族の和平を結び連邦の成立を成し遂げた)部族戦争調停者」デガナウィダの出身部族ワイアンドット族 / ヒューロン族(Huron)はこれに加わらずカナダ方面に追い散らされた。その一方で18世紀前半にタスカローラ族が加わって6部族連合となる。首長は年に一度オノンダーガ領内にある「中央の炎」と呼ばれる場所に集まり、連邦全体に関わる問題を討議した。連邦のうち、モホーク・オノンダーガ・セネカは「年上の兄弟」、カユーガ・オナイダは「年下の兄弟」と呼ばれるグループに分かれる。ある議題を論議する場合、まず年下の兄弟のあいだで討議し、その議論を年上の兄弟たちは傍聴する。次に年上の兄弟たちが同じ議題について議論し、年下の兄弟ででた結論と同じ結論になればそれで可決となる。結論が異なった場合、議論は振り出しに戻る。全体が納得するまで議論する仕組みから、結論が出るまでに1年以上かかることも珍しくなかった。
重要な決まりごとはワムパム・ベルトという貝殻ビーズの織物に幾何学模様で記録する。19世紀になると、白人たちがでたらめな模様のワムパム・ベルトを作って売り買いしたため、これを正規物と誤解したインディアン部族間の戦争まで起こった。現在も部族の法を記録したこの織物は大切に保持されている。
*古典的欧州史観は「フランク王国こそ欧州文化の起源」と主張する。しかし実際にはヴァイキング(北欧諸族の略奪遠征)とマジャール人侵攻が生んだ「建築史上の暗黒期(10世紀後半〜11世紀前半)」を生き延びたのはザクセン辺境伯(初代神聖ローマ帝国王統)やパリ辺境伯(フランス王家王統)やウェセックス王国(英国王室源流)くらいで、実際に中世前期のロマネスク文化を牽引したのはノルマン貴族が束ねたアストゥリアス貴族(イスラム教団にイベリア半島を明け渡した西ゴート王国末裔)、ブルグンド貴族(現フランスのブルゴーニュ地方)、ロンゴバルト貴族(現イタリアのロンバルディア地方)などによる「新部族連合」であり、その勢力が勢いを失うと北フランス諸侯や神聖ローマ帝国のゲルマン系諸侯の拡大志向に牽引された十字軍 / 大開拓時代(11世紀〜13世紀)が始まる。
- 「部族崩壊を恐れるあまり中央集権化が進まない」傾向自体は「北九州部族連合」に抗すべく3世紀頃に編成され、これをその世紀のうちにを「併呑」した「纒向豪族連合」においても当初は見て取れた。佐紀盾列古墳群に安定した間隔で大王墓が築造される様になるのは4世紀後半以降。副葬品の傾向から推察するに(華やかな首長威信材や鉄製の農具や歩兵用武器中心)、当時の「ヤマト大王」は「(鉄の供給を外国に頼る)豪族連合の宗教的調停役」といった職能を与えられていた様である。だが(恐らく「高句麗の広開土王の朝鮮半島南部遠征」以降)劇的な変化が訪れる。4世紀末頃より新たに河内に巨大古墳群が築造される様になり(佐紀盾列古墳群への大王墓築造も継続)、副葬品も(高句麗遊牧民文明に対抗意識を燃やしたかの様な)三燕文化の影響色濃い馬具や騎兵武具中心となるのである。同様の傾向は朝鮮半島における加羅諸国や新羅でも見られた。
*こうした展開は欧州史でいうと「ノルマン・コンクエスト(1066年)」がノルマンディー地方のルーアンを事実上の首都とする「アンジュー帝国(英Angevin Empire、仏Empire Plantagenêt)成立(12世紀)」を経て英仏百年戦争(1337年/1339年〜1453年)に至る歴史に該当する。最初期の中央集権国家はむしろ歴史のその時点における文明中心地には現れない。メソポタミア文明に対するアケメネス朝ペルシャ成立、古代ギリシャのポリス(都市国家)群に対するマケドニア王国、エトルリア都市国家群に対する(共和制)ローマ成立、中国戦国時代における「西の最果て」秦国の台頭、朝鮮半島南部における新羅と日本列島におけるヤマト王権の成立全てがその条件を満たしている。
* 稲荷台1号墳出土の王賜銘鉄剣、稲荷山古墳出土の金錯銘鉄剣、江田船山古墳出土の銀錯銘大刀などの銘文から推察するに、5世紀頃の日本ではヤマト大王は全国各地の地方豪族の縁者を集め近習として用いていた。「杖刀人の首(おびと)」といった役職に就いていた事から「人制」と呼ばれるシステム。歴史のこの時点では欧州のハスカール制などとそれほど大差なかった。
鉄剣・鉄刀銘文 - Wikipedia - そして、ここからが「欧州型中央集権国家」と「(中華王朝から律令制を仕入れた)東アジア系中央集権国家」の分岐点となる。
- 現存する様々な記録から想像されるに、雄略天皇の即位に際して「群臣応挙の儀式」が行なわれている。当時はまだま「群臣総意で新王を選んだ建前」が必要だったのである。
*時期的に見ておそらく5世紀頃の状況。河内の大王墓に対抗すべく吉備や日向や「毛の国」などの地方豪族も次々と巨大古墳を築造したが、やがて全国規模で集落放棄が起こって途絶。記紀によれば物部氏や大友氏といった連姓氏族が畿内豪族を圧倒していった時代に該当する。渡来人が集落単位で部民に編成されたり、地方豪族として土着化していった時代でもあった。氏姓(うじかばね)制の原型が出来上がった時期とも推測されている。 - 「大化の改新(645年)」に際して史上初めて「ヤマト大王が、生前のうちに後継者を指名して譲位する」快挙が成し遂げられる。
- やがて「群臣応挙の儀式」は「皇室の正統性を証明する長大な説明文を含む祝詞(中臣氏が読み上げる)」に差し変えられる。
- 誰もいちいち祝詞なんて聞かされなくても天皇の正統性を疑わなくなると「(誰が渡しても効果の代わらない)三種の神器の授与式」が登場する。
「三種の神器の授与式」が定着していく流れについては(余計な干渉者の介入を防ぎたい)武家政権や、それに味方する公卿などの思惑の繁栄もあったかもしれない。
- 現存する様々な記録から想像されるに、雄略天皇の即位に際して「群臣応挙の儀式」が行なわれている。当時はまだま「群臣総意で新王を選んだ建前」が必要だったのである。
日本神話において、天孫降臨の時に、瓊瓊杵尊が天照大神から授けられたという鏡・玉・剣のこと。また、神話に登場した神器と同一とされる、あるいはそれになぞらえられる、日本の歴代天皇が継承してきた三種の宝物(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)のこと。皇族はもとより天皇でさえもその実見はなされておらず、多くの面が謎に包まれている。
- 『古事記』では天照大御神が天孫降臨の際に、瓊瓊杵尊に「八尺の勾璁(やさかのまがたま)、鏡、また草薙(くさなぎの)剣」を神代として授けたと記される。
- 『日本書紀』には三種の神宝(神器)を授けた記事は無く、第一の一書に「天照大神、乃ち天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)に、八尺瓊の曲玉及び八咫鏡・草薙剣、三種(みくさ)の宝物(たから)を賜(たま)ふ」とある。
古代において「鏡」、「玉」、「剣」の三種の組み合わせは皇室特有のものではなく、「支配者」一般の象徴であったと考えられている。
「三種の神器」のようなそれを所有することによって正統な王や君主とみなされる品々を西欧では「レガリア(regalia)」という。品数に関しては二種とするものと三種とするものがある。
- 二種神宝説は「古語拾遺」で、鏡と剣を言うと曰う。「日本書紀」でも、継体天皇元年二月の条、「大伴金村大連、乃ち跪きて天子の鏡(みかがみ)剣(みはかし)の璽符(みしるし)を上りてまつる」とか、宣化天皇前記十二月の条、「群臣、奏して、剣(みはかし)鏡(みかがみ)を武小広国押盾尊に上りて、即天皇之位さしむ」と、あるいは、持統天皇四年(690)正月の条、「忌部宿禰色夫知神璽の剣鏡を皇后に奉上り、皇后天皇の位に即く」とあり、二種神宝説を採るがごとき表記も見られる。
- 三種宝物説は「日本書紀」「古事記」の説で、鏡、剣、玉を言う。中臣氏の説くところだが、宝器は奈良時代には後宮の蔵司が保管した。その後、後宮を制した中臣氏の一族である藤原氏の背後勢力により忌部氏は宮中祭祀において中臣氏に圧倒されてしまった。当然のことながら、神器も三種となったのである。しかし、三種の神器についてはその淵源はもっと古いという説もある。
弥生時代に入って漢(中国)の政変により漢の上層部の人々は中国大陸を追われ朝鮮半島へやって来て、その玉突き現象で朝鮮半島から九州北部地域に渡ってきた人もいたと思われる。その人たちの埋葬の風習として甕棺墓があったらしい。その中で一族の族長的な人の甕棺墓には副葬品として一つのセットとしての型があった。即ち、銅剣、銅矛のような武器類と、鏡類、玉類がワンセットとなって副葬されているのである。この副葬品の風習はその後古墳にも引き継がれたので、これを「三種の神器」の原型と解し、東京大学名誉教授故井上光貞博士は天皇家ないし三種の神器は九州北部に起源があると考えておられるようだ。
そしてこういう状況を背景に「藤原氏」が台頭してくる訳です。
本来は排仏派だった中臣氏であったが、中臣鎌足が中大兄皇子を助けて蘇我氏を倒してから、蘇我氏の代わりに仏教の保護者になっていった。
- 天智天皇は危篤の中臣鎌足を訪れて、長年の功績により鎌足一代に与えられた「藤原」の姓を子孫代々使うことを許す。その後の記録を見ると驚いたことに、中臣姓を用いるときは神祇の仕事に関わり、藤原姓を名乗っているときは一般行政の仕事にたずさわる。つまり二つの姓を使い分けていたのだ。
- やがて、不比等が中心となり大宝律令が制定され(701年)、それに基づいて国家組織として太政官と神祇官を二大頂点とする官僚体制が構築される。そして、太政官の中心に居座ったのが藤原氏であり、神祇官を占めたのが中臣氏であった。不比等は一族を太政官と神祇官に振り分けたのである。
ここから神仏習合の道がはじまったと言えそうである。
- 天武天皇が亡くなった時、皇太子草壁皇子は25歳だったが即位しなかった。当時は30歳にならないと即位できなかったらしい。
- 母親が天皇の代行となったが、3年後に草壁皇子は亡くなってしまう(28歳)。そこで、母は正式に持統天皇として即位する。はじめから天皇にならなかったのは、いったん即位すると亡くなるまで在位し生存中に譲位することができないという当時の原則があったらしい。
- しかし持統天皇といえども、いつまでも元気ではいられない。ついに、持統天皇は孫の軽皇子を一刻も早く即位させようとする。かくして、不比等の協力により15歳の皇子へ生前譲位するという離れ業を行った。
- 持統天皇の思いはとげられたが、この超法規的譲位の慣習化は、年少即位とあわせて、上皇の存在に道をつけ、あるいは摂政関白という実質的な政権ができるようになってしまった。天皇という絶対権力が、権威と権力に分化してしまった。
そしてさらにのちに武家政権と朝廷という、両者が牽制し、補完しあう、日本的な政治の柔構造が生まれる事になる。
*そしてさらにその延長線上に「大日本帝国時代の超然主義」が現れる。https://t.co/l0sqnEAVyF
— Ruby@皇位継承は秋篠宮家に! (@RubyRing0) 2016年8月26日
>「譲位」は権力の二重支配の温床となりやすく、敵対勢力に利用されやすく、もめる原因だった。だから、安定した「天皇大権」を維持するためには、譲位制度などあってはならない。なので明治政府が「譲位」廃止を定めた
ところでこれって「東洋的専制主義」の一種なんでしょうか?
近代ヨーロッパにおいて確立された社会構造及び政治形態の類型の一つ。ヨーロッパが先進的、アジアが後進的であるという世界認識を根底に形成された社会構造で神格化された専制君主による絶対的支配を特徴とする。中国の歴代王朝を始め古代オリエントやインド、日本における律令制に至るまでアジア社会においては広く存在する社会構造であるとされている。
- もともとはアリストテレスが自著『政治学』において王制の一つの例として奴隷制を受容したアジアにおいて行われている法による支配を中心とした世襲制の王制を挙げた事に由来する。ただし歴史のその時点においてはギリシアに始まる古代民主制の対極的な概念として漠然と掲げられていただけであった。
*当時はアケメネス朝ペルシャを指していたっぽいが、マケドニア王国にアレキサンダー大王が登場して以降両者は混じり合い、ヘレニズム時代が到来する。
- 18世紀になるとシャルル・ド・モンテスキューが『法の精神』において政体を民主制、君主制及び専制主義の三つに区分した際にこれについて言及し、専制主義下では国民は政治的にまったく無権利な状態であると指摘した上でこれを政治的奴隷制と呼んだ。
*絶対王政下における政治力学については、当時の啓蒙主義者の分析よりむしろドイツのマルクス主義者カウツキー(1854年~1938年)の階級バランス(均衡)論などの方に分があるとも。
絶対王政/絶対主義- またゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは『歴史哲学』において自由意識を軸とした原理の発展段階を叙述するものが世界史であるとした上で、自由意識が最初に芽生えたのは専制君主が唯一の自由人として現れたアジアでありそこに真の世界史の萌芽を見出せると指摘した。
*昭和軍人皇道派の「日本は天皇陛下一人が市民の共和制」という説明はこれ起源?
更に19世紀に入るとヨーロッパ中心の世界認識に立ったアジア社会への理解の必要性が高まり、重要な意味を持つようになった。
- カール・マルクスは『イギリスのインド支配』においてインドを素材に「アジア的生産様式」と呼ばれる概念を提唱した。
- 『資本主義生産に先行する諸形態』においては、新たにこの東洋的専制主義について農業と手工業が結合して自給自足的である労働主体が非自立的に共同体に埋没しており、土地の所有は世襲的な物で共同体の総括的統一体である専制君主のみが唯一の所有者である社会構造であると定義した。この社会構造では剰余労働は貢納という形式をとり、専制君主の讃仰の為の共同労働として搾取される物であるとされ、マルクス自身はこの様な労働主体と専制君主の関係を総体的奴隷制と呼んだ。専制の形態は一人の首長に代表される場合と家父長間の相互関係として代表される場合があるとされる。
*「(国王や教会の権威などに援用される形で)領主が領民を全人格的に代表する農本主義的伝統」なる(貨幣機材浸透以前の)中世的統治概念とと近い。カール・ポランニーの経済人類学や、ジョルジュ・バタイユの普遍経済学の世界でもある。
G.バタイユによる連続性の概念- その後執筆した『経済学批判』や『資本論』においても同様の意味でこの概念を用いた。特に『資本論』においてはこの様な社会構造では労働主体と専制君主との関係は臣従関係以上に発展する事は無く、租税は地代と等しい事から国家は最高の地主としての機能を持ち、主権は国家的規模で集中された土地の所有であるとも述べている。
*「この状態から一足飛びには資本主義的段階へと移行出来なかったので後進国は共産主義化を余儀なくされた」と考えるのが「共産主義瘡蓋(かさぶた)論」となる。
ドイツで生まれアメリカに帰化したフランクフルト学派の社会学者 / 歴史学者カール・アウグスト・ウィットフォーゲル/ヴィットフォーゲル(Karl August Wittfogel、1896年9月6日 - 1988年5月25日)は、東洋史、とりわけ中国研究においてこの考え方をさらに発展させた。
- 青年期より中国に関心を抱き、中国の社会経済について研究を進め、官僚制の起源とされる四大文明が河川の流域に位置し水利事業と大規模灌漑農業に基づいた共通点から水力社会と名づけた。また、周辺民族が中国に同化されるという従来までの理解を改め、遼・金・元・清を「征服王朝」という概念を通じて考えた。
K・A・ウィットフォーゲルの東洋的社会論 - 柄谷行人- さらには文明を「中心」「周辺」「亜周辺」の三重構造で説明。西洋や日本のような「亜周辺」では資本主義が発達したのに対し、北アジア、中央アジアを抱えるソ連やモンゴル人民共和国の様な「周辺」では社会主義革命が起きたとした。
*この分類だと日本は「アジア的専制政治」の範疇から外れるからややこしい。
*イタリアの共産主義者アントニオ・グラムシは「(社会民主主義が広まった)西欧」と「(共産主義革命が起こってしまった)ロシア」を両極に置き「発展状態が異なれば、それにふさわしい革命形態も異なる」とした。
- さらには「亜周辺」の対極にある中華人民共和国、エジプト、イラク、インド、パキスタンなどは五カ年計画によって計画経済が敷かれ、非同盟を掲げつも中東戦争や印パ戦争ではソ連や中国と軍事協力するなどかなり似た体制をとったとし、これにマルクスの「アジア的生産様式」概念を援用して「アジア的専制政治」と説明した。
ウィットフォーゲルの仮説はその理論通りにスターリンや毛沢東が自然改造計画や大躍進政策と称して運河やダムの建設や灌漑農業の集団化に邁進していた当時では反響が大きく、同じく中国を研究するジョゼフ・ニーダムの反論を招いている。
中国と西欧の科学技術と医学の歴史の対照に関するニーダムの問いはよく知られているが、改めて読み直してみると、やはり面白い。
ジョゼフ・ニーダム - Wikipedia
- 古代と中世の中国の科学技術は西欧よりもはるかに進んでおり、数多くの発見や技術は中国のほうがはるかに早かった。
*たとえば錬金術や鉄の利用に関しては1000年以上も早かった。
- それにもかかわらず、中国はヨーロッパ文明のような「近代」の科学や技術を生み出すことができずに、近現代には西欧の科学技術を受け入れて、西欧の科学技術が世界に共通するoecumenical(世界普遍的) なものになった。
*ただし医学においては、中国やインドは独自の伝統医学の理論と実践を現在でも保っており、これは別の問題であるとする。- 中国の科学技術は経験的なものにとどまり、西欧のような理論的な基盤へと掘り下げなかった。
*中国における科学技術の理論は、その経験の蓄積に基づいた実践面での洗練にもかかわらず、陰陽五行説のような原始的なものを長く保持した。問題となるになるのが、なぜ西欧においては16世紀から科学技術が理論的に進展したのに、中国では古来の理論を使っていたのかという部分についての説明。この部分がニーダムの理論の中核になる。ニーダムはその理由を中国と西欧の地理的な条件と、それと密接に結びついた社会的な違いであるとした。
- 中国は大陸であり「一様な陸塊」であった。それは巨大な灌漑を必要とし、早くに大運河が作られなければならなかった。大運河の建設には何百万人という労働者を集めなければならず、彼らを管理する官吏が必要であり、この官吏たちは皇帝による支配を支えることになる。そこでは皇帝のために社会を掌握するし、それを実務的な改善によってより完成し高めることが、社会の最も重要な力になる。中国は、気候や地理と関連する仕方で、官吏と文官が社会に大きな力を及ぼす構造になっており、その構造が新規の理論への調査研究に向かわなかった。
*ただし古代メソポタミアにおける神殿宗教の様な都市国家の割拠状態もまた「灌漑国家」の一種。巨大な多民族国家はむしろ砂漠に生まれる。- 一方で西欧は半島的な地理であり、それは商業都市国家の形をとった。遠洋航海と商業経済が重要であった。商人がいつも低い地位に置かれていた中国と違い、商人がより高い生産と貿易の新しい形態を発展させるために、調査研究にお金をかけることが重要であった。中国のような保守性をもつ文明の構造とは違い、より大胆に生産と経済を変えることがヨーロッパの中には組み込まれていた。
- もちろんニーダムの議論の雰囲気は通じるし、共感できる部分も多い。しかし、これが中国において科学技術が経験と実務においては進歩し蓄積したが、理論においては保守的だったという事実の説明になるという道筋がよく分からない。
もう一つ、別の論文で、西欧医学が中国医学より先行するようになったのはいつかという興味深い問題に触れている。
- ここでは、医療の臨床的な知識や、外科、解剖学、そして生理学といった領域と、治療の話を分けて考えている。
*ウィリアム・マクニール「ヴェネツィア(enice: the Hinge of Europe, 1081-1797、1978年)」はイタリア・ルネサンス期における人体解剖学の発展と出版文化の結びつきを重視する。
- 解剖、外科、病理解剖については、比較的早い時期から西洋が進んでいたのは確実である。しかし、それ以外のことを考えたときに、1850年から1870年に西欧が中国を抜いたのだろうという。
*統計学や衛生学の発展期に該当。
- とくに、患者の視点からみて、治療について考えたとき、20世紀の初頭においても、中国よりも西欧のほうが進んでいたという判断はできないという。
ホスピタリティとは? ホスピタリティ の極意この問題も、もっときちんと研究している本か論文を読んで、授業に組み込みたいと思っている。
ライシャワー博士が「日本史(Japan The Story of a Nation、 1978)」の中で「藤原氏由来の談合政治」と呼んだ政体、本当に分類が難しい様で。
さて、私達は一体どちらに向けて漂流してるのでしょうか…