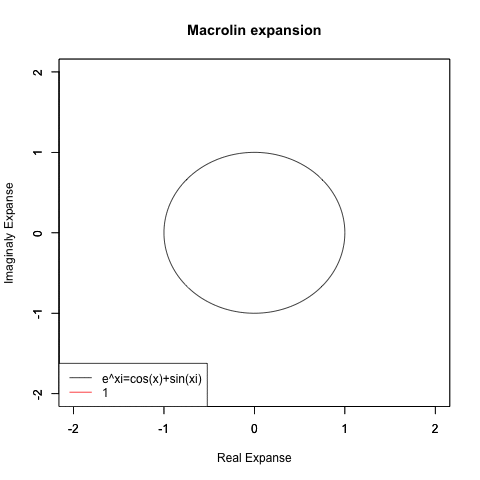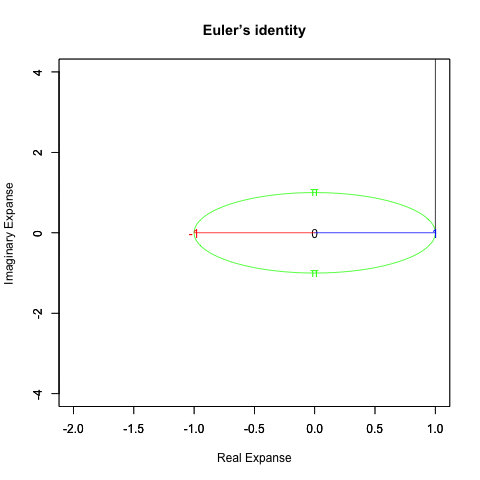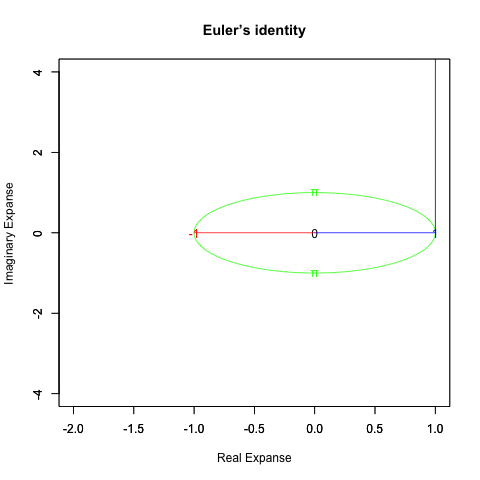誰しも人は、宗教や道徳など、何らかの「信念」を抱いて生きている。異なる「信念」同士が衝突し、それが深刻化すると、凄惨な争乱になることすらある。我が「信念」こそ、絶対に「正しい」と信じて疑わないからだ。そうした対立を超克し、互いの差異を肯定しながら、協働し共生するための哲学とは何か?パース、ジェイムズ、デューイ、クワイン、ローティら、プラグマティズムの重要人物を取り上げ、その思想を概観しつつ、現代社会における連帯と共生の可能性を探る哲学の書である。
そもそも「実用主義」「道具主義」「実際主義」とも訳されるプラグマティズム(pragmatism)の語源はドイツ語のpragmatisch。実はそれは「(人間が認識可能な情報の集大成としての)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に「原則として」人類に不可知な形で拡がる)物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の世界」を峻別したイマヌエル・カント(ImmanuelKant、1724年〜1804年)の超越論上の語彙で、観念論哲学史的には「(南北戦争(American Civil War、1861年〜1865年)に至った米国人間の不和を内省し)神はこの世界を人力だけでは手に負えない(すなわち改めて創造主の再登場とデバッグを必要とする様な)欠陥品としては設計されてない」なる強烈な楽観論に立脚する宗教的信念を導入した点に最大の特徴があるのです。

ある意味、皇帝ナポレオンに対し「科学はその理論展開において神に言及する必要のない体系なのです」と説明したピエール=シモン・ラプラス(Pierre-Simon Laplace, 1749年〜1827年)と同じ立場に属するとも。
そして…
プラグマティズム (pragmatism) は、pragmatisch というドイツ語に由来する実用主義、道具主義、実際主義、行為主義とも訳されることのある考え方。元々は、経験不可能な事柄の真理を考えることはできないという点でイギリス経験論を引き継ぎ、物事の真理を実際の経験の結果により判断し、効果のあるものは真理であるとするもので、神学や哲学上の諸問題を非哲学的な手法で探求する思想。
その創始者であるパースがカントの語彙から採した言葉で、さらなる原意はギリシャ語で行為・実行・実験・活動を表すプラグマ(πράγμα)。思想が行為と密接に関係する意が強調されたといえる。パースの友人は「プラクティカリズム(実際主義)」という語を勧めたが、カント哲学に通じていたパースにとってpraktischという言葉は、「実践理性」の領野、つまり神・道徳・霊魂に関わるので、実験科学者にとってふさわしくないと判断された。こうして名前こそドイツ哲学由来だが、その合作者達はジョン・ロックやジョージ・バークリなどのイギリス哲学に影響されており、さらにさかのぼれば、バールーフ・デ・スピノザ、アリストテレス、プラトンに行き着く。
西部邁ゼミナールにおけるpragmatismへの触れ方。
目標を達成した者ほど自由意志を疑いこれまでの環境に感謝しなければならないし、未だ成しとげていない者ほど自由意志を信じることに意味がある。状況の違うこの2つには、1つの固い定義では当てはまらず、その“状況によって柔軟にスタンスを変える”ことがもとめられているのだと感じます。その振る舞いは“謙虚”な姿として写るんだろうなあと。
三島由紀夫は、「習慣という怪物」で継続を力に変え執筆活動を専念してきたという。コレには自由意志の否定の意味から環境や習慣という自動操縦的なものを応用していてなかなかウマい。また、偶然という余地を知り、自由意志を信じなければ(強靭な力)、環境や習慣という安定した状況をつくるきっかけは生みだせないし目標を達成するフラグにもなり得ない。
おっと、ただでさえ難しい話題なのに、あえて検討範囲を「自由意志問題」にまで飛び火させますか。実はこうした設問の持ち方の歴史は欧州近世思想以前、すなわち地中海沿岸地域の主役がイスラム諸王朝だった時代のアラビア哲学にまで遡流るのです。
イスラム教には「定命(神の定めた道筋)」信仰がある。
- この世界は全て創造主によって決定付けられ、用意されたものだから、あらゆる人間もまた神の定めた運命によって生きている。
ならばそれ以外の道、つまり人が自由意志によって決めることのできる範囲はあるのだろうか。この問題についての2つの答えが用意された。
- 【ジャブル (al-jabr)】人間に行為を選択する自由意志など存在せず、例えどのような振る舞いに及んだとしてもその行為の責任は全て神へと帰される。
*ジャブル (al-jabr)…「(神の意志の)復元」を意味する宗教語で、代数を意味するアルジェブラ(algebra)の語源になった。
- 【イフティヤール(自由)の能力】一見、人生には自由選択の余地が存在し”この自由には、限界はない、時には神の予定を退ける“と見える事もあるとする立場。
*イフティヤール(自由)の能力…「一見そう見える事もある」という言い回しになるのは「それさえもその人に最初から与えられていた定命の一部」と看做すのが公式の立場だから。
この種の議論は特にスーフィズム(イスラム神秘主義)の分野において担われてきが、その最終到達目標は「(一切の自由意志を認識論的に放棄して神に絶対帰依する)忘我=法悦の境地」だったのである。
アラビア哲学者の多くはアリストテレスの様なギリシャ古典の注釈者でもあり、そのラテン語への翻訳を通じて欧州にこうした考え方が伝わります。

- 一般に欧州におけるこの種の議論は12世紀ルネサンス運動(イベリア半島におけるレコンキスタ運動の進行(特にキリスト教国側のトレノ奪還)とパレルノに首都を構えたシチリア王国のイスラム文化吸収を背景とする第一次グレコローマン古典翻訳ブームに由来する)の延長線上に現れたラテン・アヴェロス主義を巡る諸議論を皮切りとする。
- こうした論争はイタリア・ルネサンス期(14世紀〜16世紀)までにパドヴァ大学やボローニャ大学の解剖学部で流行した新アリストテレス主義、すなわち「実践知識の累積は必ずといって良いほど認識領域のパラダイムシフトを引き起こすので、短期的には伝統的認識に立脚する信仰や道徳観と衝突を引き起こす。その一方で実践知識の累積が引き起こす如何なるパラダイムシフトも、長期的には伝統的な信仰や道徳の世界が有する適応能力に吸収されていく」なる楽観的ドグマ(dogma、教義)にまで深められて科学実証主義の起源となった。
-
そして宗教戦争の時代を乗り越えた18世紀欧州においては「神義論(Theodizee)」すなわち「神は無謬のはずなのに、どうしてこの世には悪が存在するのか?」についての議論が盛んに行われた。契機となったのはおそらく(大貴族連合に対する絶対王政の勝利を目の当たりにした事を受けて)オラトリオ会修道士のニコラ・ド・マルブランシュ(Nicolas de Malebranche,1638年~1715年、奇しくもルイ14世と生没年が一緒)の手になる「ガザーリーの流出論」の絶対王政下フランスへの紹介あたり。
神は無謬の存在の筈なのに、どうしてこの世には悪や対立が存在するのか。スンニ派古典主義を完成させたイスラム神秘主義者(Sufi)にして法学者(ulama)のガザーリー(Abū Ḥāmed Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al-Shāfi'ī al-Ghazālī 、1058年〜1111年)はこの問題をネオ・プラトミズムの流出論を援用してこう説明した。
①神の英知そのものは確かに疑うまでもなく無謬である。
②しかしながら神の英知は理念の世界から現実の世界へと全方向に向けて流出していく過程で数多くの誤謬を累積させていく。
③こうした誤謬の累積がやがては矛盾や対立、さらに究極的には悪をもこの地上に誕生させる。
フランスにおいて中世より続いてきた「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制(いわゆる封建体制)」に立脚する大貴族連合が国王を最高峰に頂く中央集権的官僚体制を掣肘するシステムは、(ブルゴーニュ猪突公シャルル(在位1467年〜1477年)の自滅に終わった)公益同盟戦争(1465年〜1477年)と(法服貴族と帯剣貴族の内ゲバに終始した)フロンドの乱(Fronde, 1648年〜1653年)によって自滅した。代わって「(主権国家として)十分なだけの機動力と火力を保有する常備軍を中央集権的官僚制に基づく徴税によって養う」絶対王政の掣肘手段として台頭してきたのが「現体制と理性に基づく理想的支配体制を比較する」啓蒙主義(英Enlightenment, 仏Lumières, 独Aufklärung)である。そうした時代の黎明期にあってシャルル・ペロー(Charles Perrault, 1628年〜1703年)は新旧論争によって「人類の最盛期はグレコローマン時代であり、それ以降世界は衰退を続けている」としてきた欧風末世思想に反駁し、韻文童話集(Histoires ou Contes du temps passe、1697年)や散文童話集(Contes en vers、1694年)において「(法服貴族や帯剣貴族が立脚してきた)伝統的権威との兼ね合いで出身階層によって自動的に個人の人生が定まる中世的身分制」を全面否定したのだった。
一方「(ニュートンと並ぶ)微積分の父の一人」ゴットフリート・ライプニッツは「弁神論(Essai de théodicée sur la bonté de Dieu,la liberté de l'homme et l'origine du mal、神の善性、人間の自由、悪の起源に関する弁神試論、1710年)」において「人間に認識不可能なだけで、おそらく悪にも存在理由がある」という立場を表明している。
我々が現実に生きているこの世界は、その枠内において成立している事態の多くが矛盾しておらず、その範囲内においてなら概ね矛盾なく考えることが「可能」である。もちろんそうした組み合わせは他にも無数に考えられるが(Possible world group=可能世界群)、神が唯一選んだのがこの現実世界である以上、この世界こそが最善であると考えるべきであるとライプニッツは提言したのだった。
しかしながらポルトガルにおけるリスボン大地震(1755年11月1日、推定マグネチュード8.5〜9.0、推定死者数5万5千人〜6万2千人、この数字は津波の犠牲者1万人を含む)がこうした楽観論や(この時代まで相応の評価を得てきた)公正世界仮説(Just-world hypothesis、人間の行いに対して公正な結果が返ってくると考える認知バイアス、もしくは思い込み)を吹き飛ばしてしまい、理神論(Deism、一般に創造者としての神は認めるが、神を人格的存在とは認めず啓示を否定する哲学・神学説)を台頭させる展開を迎える。
それまで主流だった神義論(theodizee)
それまでヨーロッパ思想の世界において主流だったのは「慈悲深い神が監督する我々の「最善の可能世界(le meilleur des mondes possibles)」では「すべての出来事は最善」である(悪は存在するにせよ、他のさまざまな善が存在するために必要なかぎりの悪である)」なる楽観主義に支えられた神義論(theodizee)だった。
当時のフランスを代表する有識者となったヴォルテール(Voltaire=François-Marie Arouet、1694年〜1778年)の反応
当時のフランスを代表する有識者だったヴォルテール(Voltaire=François-Marie Arouet、1694年〜1778年)は翌年3月「リスボンの災害についての詩(Poème sur le désastre de Lisbonne、1756年)」を発表し、その序文で「〈すべては善である〉という語を厳密な意味で、しかも未来の希望なしで把握すると、これはわれわれの人生の苦しみにたいする侮辱にほかならない」と述べ、こうした楽観主義に挑戦した。
「すべては善である」と叫ぶ迷妄の哲学者たちよ、
ここに駆け付け、この恐るべき廃墟をよく眺めるがよい。
この瓦礫を、このずたずたの破片を、この不幸な屍を。
たがいに重なりあったこの女たちを、この子供たちを。
崩れ落ちた大理石の下に散らばっているこれらの手足を。
大地が呑み込んだ数万の不幸な人々を。
さらに「これは天罰だ」という声にも挑戦している。
あなたがたはこの山のような犠牲者をみて、それでも言うのか、
「神が復讐したのだ、彼らの死は犯した罪の報いなのだ」と。
どのような罪を、どのような過誤を犯したと言うのか、
母の乳房の上で、潰され、血まみれになっている
これらの子供たちは。
壊滅してもはや地上にはないリスボンは
それほどの悪徳の町だったのか、
ロンドンよりもパリよりも悦楽にふけっていたと言うのか。
テオドール・アドルノは「リスボン地震はライプニッツの弁神論(慈悲深い神の存在と悪や苦痛の存在は矛盾しない、という議論)からヴォルテールを救いだした」と述べている。当時のスイスを代表する有識者となったジュネーブ出身のルソー(Jean-Jacques Rousseau、1712年〜1778年)の反応
ヴォルテールの下した「地上には悪が実在する」なる結論と対立したのが同年「人間不平等起源論(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes、1755年)」を発表したジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau、1712年〜1778年)の内容だった。
- 人間に悪をもたらしたのは神でなく人間そのものであり、もし人間がもし野生人のように素朴な生活のままだったら、こんな災害に遭う事もなかっただろう。
- 火災や地震などのために、さまざまな都市が崩壊し、あるいは全滅していること、そのために何千もの人々が死亡していることも考えてほしい。
さらには都市の放棄とより自然な人間らしい生活様式への回帰を訴え、ヴォルテールとの関係は完全なる断絶を迎える事になる。こうしたルソーの理想主義は結局、フランス革命期における大量虐殺を伴う産業インフラの徹底破壊という形で実践に移されたが、渾身の努力にも関わらずフランスへの産業革命の波及をわずか半世紀遅らせるのに成功しただけだった。
当時のドイツを代表する有識者となったプロイセン王国出身のイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)の反応
また 当時のドイツを代表する有識者だったプロイセン王国出身のイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)は、同時に(英国から伝わった)人間の力の及ばない自然の巨大さなどへ対する感情たる「崇高」なる概念に強く惹かれ、それを自らの哲学において発展させて中核概念とした事で知られる。若き日の彼はこれを契機に地震に魅せられ、報道から地震被害や前兆現象など可能な限りの情報を集め、それらを使って地震の起こる原因に関する理論を構築し、3冊の薄い書物を出版。そこで「熱いガスに満たされた地底の巨大空洞が震動して地震が起こる」と主張した。これは後に誤りであることが分かったが、とにかく「地震は超自然的な原因ではなく自然の原因から起こる」という仮定に従って地震のメカニズムを説明しようとした近代最も初期の試みだった事実は揺るがない。ヴァルター・ベンヤミンはカントが出版した地震に関する書物について「おそらくドイツにおける科学的地理学の始まりを代表するものであり、そして確実に地震学の始まりである」と述べている。
哲学用語としての「大地=揺るぎなき存在」なる概念の崩壊
ドイツの哲学者ヴェルナー・ハーマッハーによれば、地震の結果は哲学用語にも及び、硬い根拠を大地に例えてgroundと呼ぶ比喩がぐらつき、不安定なものとなったという。「リスボン地震により起こされた印象は、ヨーロッパの最も神経質な時代の精神に触れたため「大地」や「震動」の比喩はその明らかな無垢さを失い、もはや単なる修辞には過ぎなくなってしまった」。ハーマッハーはルネ・デカルトの哲学のうち「確実性」に関する部分がリスボン地震後の時代に揺らぎ始めたとする。
当時のスコットランドを代表する有識者となったエドマンド・バーク(Edmund Burke、1729年〜1797年)の反応
若かりし頃のエドマンド・バーク(Edmund Burke、1729年〜1797年)は「崇高と美の観念の起原(A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful、1757年)」の中でこう述べている。原初のイメージの源泉はスコットランドあたりの峻険な山岳地帯あたり。


- 崇高(Sublime)には美と戦慄が同居する。
実は同時代に併行進化的に成立したピクチャレスク(Picturesque)の概念は、この理念の影響を濃厚に受けつつも、それそのものではなかったりするからややこしい。
当時のドイツを代表する有識者となったプロイセン王国出身のイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)の反応
イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)は 「美と崇高の感情に関する観察(Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen、1764年)」の中でエドマンド・バークの著作について触れている。

- 当時のドイツは、英国と同君統治状態にあったハノーファー王国(1714年〜1837年)」経由で英国思想が際限なく流入してくる状態にあったので、強い違和感を惹起する代物が流れてくるとたちまち激しい論争が巻き起こった。
- エドマンド・バークが「フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France、1790年)」の中で示した「(ある世代が自分たちの知力において改変することが容易には許されない)時効の憲法(prescriptive Constitution)」概念についても激論が交わされており、ヘーゲル哲学流に「それが民族精神(Volksgeist)と合致するなら誰にも変更は許されないが、たまたま時代精神(Zeitgeist)と合致しただけならその変遷に従って変わっていくだろう」と結論付けられている。
- ラッサールが「既得権の体系全2巻(Das System der erworbenen Rechte、1861年)」 の中で示した「正しい私的所有の範囲は時代によって変遷してきた」とする態度や、マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus、1904年~1905年)」の中で示した鋼鉄の檻(Gehäuse)理論にまで影響を与えた可能性が指摘されている。
フェルディナント・ラッサール「既得権の体系全2巻(Das System der erworbenen Rechte、1861年)」によれば、そもそもそも貨幣経済浸透以前の「支配」は「領主が領土と領民を全人格的に代表する農本主義的権威体制(いわゆる封建体制)」として実現されていた。ラッサールはこの著作の中でその状態からの脱却過程を以下の様に説明する。
①初め権力者はこの世の全てが部が自分の物だと思い込んでいたが、次第に漸進的にその限界を受容してきた。
②神仏崇拝の自由化は、神仏の私有財産状態からの解放に他ならない。
*かつて都市国家の神殿宗教は祭政一致体制を敷いて土地と農業ノウハウを独占し、人類そのものを「神に奉仕する目的のみで創造された奴隷」と規定し領民を完全隷属下に置いていたが、この状態では神殿が破壊されると人間集団そもものも霧散してしまう。この欠陥を補う為に啓典宗教が発案され(神殿の付属物に過ぎない)神官に代わって(究極的には民の一員たる)啓典を奉じた教導者の時代が訪れる。②農奴制が隷農制、隷農制が農業労働者へと変遷していく過程は農民の私有財産状態からの解放に他ならない。
*「領主による領土と領民の全人格的支配」からの脱却過程。地主は土地使用料を受け取るだけの存在に、雇主は賃金を支払う対価として労働者から労働力の供給を受けるだけの存在に変貌していく。③ギルドの廃止や自由競争の導入も、独占権が私有財産の一種と見做されなくなった結果に他ならない。
*かつて特権商人や特権組合は「領土と領民を全人格的に支配する領主」の認可を受ける形で特定商品の生産権や取扱権、特定商人と特定集団の取引権、特定領域における通商権を独占し、私有財産の様に継承してきた。これが最終的に全て自由競争に置き換えられていく。そして現在世界は資本家と労働者の富の収益の再分配はどうあるべきかという問題に直面している。
*この問題には今なお答えが見つかっていない。王侯貴族や教会からの特権剥奪によって、生産を支える労働者がそのまま市場を支える消費者と目される様になった。それでは、このシステムを支えるには「資本家と労働者の富の収益の再分配」はどうあるべきなのか? 共産主義が最終的に到達したのは「全てを統制下に置いて完全管理すれば誰もが幸福になれる」というもの。しかし実際には自由主義圏より先に暴走し、あっけなくシステムとして崩壊してしまった。マックス・ウェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus,1904年~1905年)」における「鉄の檻(Gehäuse)」言及箇所の要約
実は今日でこそ我々の間で普通に通用しているが、実はその意味が思う程自明でない「職業義務(Berufspflicht)」という独特の思考様式が存在する。
その具体的活動内容如何に関わらず、またそれに囚われない俯瞰的立場からすれば、労働力や(資本回転を継続する原資としての)物的財産を用いた単なる営利行為の追求に過ぎない筈の事に対し、各人が自らの「職業」活動の内容を義務と意識すべきと考え、実際に意識して振る舞っているのである。
資本主義文化の「社会倫理」はこうした義務の観念によって支えられているが、既に完成した資本主義をのみ土台として発生したとは到底言えない。すなわちさらに過去まで遡って考えなければその起源は分からないし、資本主義社会の企業家や労働者ならそうした倫理的原則を必ず主体的に内在的に獲得しているとは限らない。今日の個々人は「既成の巨大な秩序界(コスモス)」としての資本主義的経済組織の成員としてその枠内に生まれつき、その枠内で生きる事を強いられ、その枠内で死んでいく。(少なくともばらばらな個人の寄せ集めとしての)個々人の眼にはそれは「(改変の余地なき)鋼鉄の檻(Gehäuse)」として映る。誰であれこの秩序界(コスモス)は市場との関連が存在する限り彼の経済的営為に対して一定の規範を押し付けてくるものなのである。製造業者は長期官この規範に反する行動を続ければ必ず経済的淘汰を余儀なくされるし、この規範に適応出来ない、あるいは適応しようとしない労働者もまた、最期には必ず失業者として街頭に投げ出される羽目に陥る。
この様に秩序界(コスモス)そのものが経済的淘汰による教育的再生産を通じて自らが必要とする経済主体(企業と労働者)の生活態度や職業観念を獲得していく反復的営為の起源は、果たして本当に素朴な唯物史観が提唱する様に特定の経済の段階的発展の反映が生み出す上部構造として規定可能なのだろうか?
資本主義の特性に適合した生活態度や職業観念が淘汰によって反復的に強化され続けていく社会が出現する為には、あらかじめそうした生活態度や職業観念が特定の人間集団共通の見解として共有されていなければならない。だからこそ、そうした職業観念の成立史が重要課題となってくる訳だが、これが全てを上部構造の一言で片付け、その超克を目指す素朴な唯物史観からは導出不可能なほど複雑怪奇な茨の道だったりする訳である。
我々が想定する様な資本主義精神は、少なくともすでにベンジャミン・フランクリンの生地たる17世紀マサチューセッチュには存在していた(1632年のニューイングランドにおいて既に「アメリカの他の地方に比べて人々が特に利益計算に長けている悪徳」が弾劾されている)。その一方で隣接する植民地(後の合衆国南部諸州)においては、そこが営利を目的として大資本家によって開拓された地域だったにも関わらず、同様の概念が(当時カリブ海沿岸に多数建存在した砂糖や綿花の奴隷制プランテーションや、同時期に穀物輸出を担った東欧の再版農奴制の様に)恐ろしいまでに未成熟な段階にあった。
そもそも前近代段階における資本主義精神は、当時の一般の人々に喜んで受容された一方で、古代や中世の通念に照会すれば「汚らわしい吝嗇」「およそ低劣な心情の発露」に他ならなかった。それどころか今日なお国際的資本主義社会との関連が極めて薄いか、あるいはそれへの適応を免れている社会集団にあっては今日なおこの理念が生々しい形で通用しているが、それは決して「営利への志向」が未知ないし未発達な「無垢なる幸福状態」にあるからでも、近代浪漫主義者が夢想した様に「呪われた黄金への飢餓(Auri sacra fames)」から免れていたせいでもない。むしろそれは属州におけるコロナートゥス(colonatus)制履行によって私服を肥やした古代ローマ貴族、領民を人間と思わない中華王朝の科挙官僚(マンダリン)の搾取、再版農奴制度に胡座をかいた近代農場主達や奴隷制プランテーションの経営者達に見受けられる際限なき貪欲への当然の反応に過ぎず、同様の金銭欲と厚顔無恥は経験した人なら誰でも知っている様にナポリの馬車屋や船乗り、及び同様の仕事に就いている南欧やアジア諸国の職人達の間に遙かに徹底した形でより深く根付いている。
実際には如何なる内面的規範にも服しようとしない、訓練なき「自由意思(liberrm arbitrium)」は、それが実業家の物であれ、労働者の物であれ、必ず健全な資本主義社会発展の妨げとなってきた。当然その出発点は「金儲けの為には地獄にへも船を乗り入れて帆が焼け焦げても構わない」冒険商人達による向こう見ずな営利活動でも、戦争や海賊や山賊を正当化してきた「共同体内部(unter Brudern)では禁じられた規範からの逸脱も、対外道徳(Aussenmmoral)では許される」伝統でも有り得ない。むしろそれらに寛容(Clemenza)過ぎた伝統が、合理的経営による資本増殖と合理的労働組織によって克服された事こそが、市民的資本主義経済成立の前提となった事は疑う余地もないといえよう。

要するに彼は、こうした当時の最新概念を認識可能な「物(独Ding、英Thing)の世界」の外側に茫漠と広がる認識不可能な「物自体(独Ding an sich、英Thing-in-itself)の世界」を峻別する試みの最初の踏み台として利用したのである。
20世紀前半のパルプマガジン文化を代表する一人たる恐怖小説作家H.P.ラヴクラフト(Howard Phillips Lovecraft、1890年〜1937年)の反応
H.P.ラヴクラフト(Howard Phillips Lovecraft、1890年〜1937年)は、自らの開拓した「宇宙的恐怖(Cosmic Horror)」の極意について「ピクチャレスク(Picturesque)だ。普段は視野外だが、意識し出すと途端に決っして目が離せなくなる様な何か」と端的に述べている。この時点で初めて現代的な形で「崇高(Sublime)=戦慄(Shudder)=ピクチャレスク(Picturesque)」の等式が成立したといえよう。

- E.T.A.ホフマン経由で江戸川乱歩が日本へも広めた恐怖概念。
- フロイトが解明した世紀末オーストリア人の神経症的病理そのものとも。
こちらは「(百鬼夜行型怪異の目撃譚を誘発する)暗闇とそれに対する恐怖」「古塚や丘に何か棲んでそうな感じ」「家に何か憑いてる感じ」「人里離れた森や湖に何か集まってる感じ」「場違いの場所にある祭祀施設の違和感」「不気味の谷の境界線上を彷徨う人形達が引き起こす不安」といった異化作用をトリガーに発動する。
ここで「イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)の反応」が2系列存在する点が重要。彼の存在は近代哲学史上において「先験=アプリオリ(a priori)」論の提唱者でもあ ったという点において直交座標系(Rectangular coordinate system/Orthogonal coordinate system)を提唱して機械的宇宙論(Mechanistic Universe)を展開しつつ、心身二元論(ただしここでいう「魂」は脳の最奥部に位置する松果腺や動物精気、血液などを介して身体と相互作用を行う物理的実体に過ぎないかもしれない)を説いたルネ・デカルト(René Descartes、1596〜1650年)の後継者であり、かつ数学者コンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743年〜1794年)の学問体系論を継承しつつ「全てを統括するのは数理でなく実証主義哲学(Philosophie Positive)を習得した科学者でなければならない」としたオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)の先駆者にも位置付けられているのであった。
こうした経緯を経て「(人間が認識可能な情報の集大成としての)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に「原則として」人類に不可知な形で拡がる)物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の世界」を峻別したイマヌエル・カント(ImmanuelKant、1724年〜1804年)の超越論が一旦はメインストリームに躍り出した訳ですが、実は同時代の数学はこれに呼応する形で想像を絶するパラダイム・シフトを経験していたのです。
スイスのバーゼル出身の数学者ヤコブ・ベルヌーイ(Jakob Bernoulli、1654年〜1705年)とその弟子レオンハルト・オイラー(Leonhard Euler, 1707年〜1783年)の出発点は、あくまで「大数の弱法則 (WLLN: Weak Law of Large Numbers)」であったと想定される。
- 大数の弱法則 (WLLN: Weak Law of Large Numbers) …独立同分布/独立同一分布に従う可積分な確率変数の無限列X1, X2,…Xnとその平均μが与えられた時、標本平均(Sample mean)(X1, X2,…Xn)/n(ただしn>=1) のとる値が平均μの近傍から外れる確率は、十分大きなnを取れば、いくらでも小さくできるとする考え方。
- 確率変数(random variable, aleatory variable, stochastic variable)…ある確率のセットが変数として存在し、しかも概ねそうした確率の合計が1となる様に正規化(normalization)された状態モデルを指す。例えばコインの出目は{表,裏}のいずれかで、それぞれの目が出る確率は1/2(P(X)=1/2(x=0,1))。6面体サイコロを投げて出る目は{1, 2, 3, 4, 5, 6}のいずれかで、それぞれの目が出る確率は1/6(P(X)=1/6(x=1,2,3,4,5,6))。3の目が出る確率は1/6(P(X=3)=1/6,P(3)=1/6)。
- 独立同分布/独立同一分布(independent and identically distributed; IID, i.i.d., iid)…確率論と統計学において、確率変数の列やその他の系が、それぞれの確率変数が他の確率変数と同じ確率分布を持ち、かつ、それぞれ互いに独立している場合をいう。例えば6面体サイコロで各出目の確率は毎回1/6であり、その前後の出目の影響を受けない(メモリレス性)。「独立同分布/独立同一分布」なる確率分布自体が存在する訳ではない点に注意。
- 可積分(integrable)…ニュートンが17世紀にケプラー問題を解いて微分積分学や古典力学が発祥して以降追求されてきた「求積法で完全に解ける」範囲。
①彼らはまず「各出目の出現確率が均等に1/6の六面体サイコロを6回降って特定の目が1回も出ない確率」なる概念を数式的に抽象化した(1-1/N)^Nの式を通じてネイピア数1/e=0.3678794を極限値として観測した。
②次いで「一年で元金が倍になる夢の金融商品において、複利計算でさらに利益を上げられる上限」なる思考実験を数式的に抽象化した(1+1/N)^Nの式を通じ極限値としてネイピア数e=2.718282に到達。
③両者が逆数の関係にあった事から自然に自然指数関数e^xと自然対数関数log(x)が導出される。ちなみに対数概念そのものはスコットランドの男爵ジョン・ネイピア(John Napier, 1550年〜1617年)が発見済みだった。
④そして同時代には並列的にテイラー級数(Taylor series)やマクローリン級数 (Maclaurin series) 、さらには(奇関数の値を実数域、偶関数の値を虚数域に割り振る)虚数指数(Imaginary Index)の概念の研究が進んでいたのである。
⑤かくして1748年にはオイラーの公式(Euler's formula)e^θi=cos(θ)+sin(θi)(理論値)=(1±θi/N)^N(大数の弱法則に従い、観測結果の集計が理論値に決して到達しない事の証明)が公式に発表される。
⑥並列して物理学の世界でも「等速円運動(Constant velocity circular motion)のX軸に対する写像は単振動Cos(t)、Y軸に対する写像は単振動Sin(t)。これを再構成すれば円が描かれる」なるコンセンサスが成立。そもそも「複素数の実数部をX軸、虚数部をY軸に割り振ると円が描かれる」と公式に発表されたのは数学者にして天文学者にして物理学者でも会ったガウス(独Johann Carl Friedrich Gauß De-carlfriedrichgauss.ogg listen、羅Carolus Fridericus Gauss、1777年〜1855年)の時代に入ってからであり、実際の前後関係は不明点が多い。
ここに見受けられる「(神の計画通りの)理論値」と「(人類は決っしてそれに到達し得ない)計測値の総計」の鮮やかな対比こそ当時の時代精神(Zeitgeist)の賜物であり、「(人間が認識可能な情報の集大成としての)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に「原則として」人類に不可知な形で拡がる)物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の世界」を峻別したイマヌエル・カント(ImmanuelKant、1724年〜1804年)の超越論ばかりか「ラプラスの悪魔(Laplace's demon)」と「ベイズ推定(Bayesian inference)」を同時提唱したピエール=シモン・ラプラス(Pierre-Simon Laplace, 1749年〜1827年)の数学上の立場とも重なってくる。
それでは、かかる数学史上のパラダイムシフトが当時の社会学や哲学の発展にどう寄与したかというと…これがまた何とも難しい問題だったりするのです。
第一の点は、〈数学の概念は、まったく予想外のさまざまな文脈のなかに登場してくる〉ということ。
The first point is that mathematical concepts turn up in entirely unexpected connections.しかも、予想もしなかった文脈に、予想もしなかったほどぴったりと当てはまって、正確に現象を記述してくれることが多いのだ。
Moreover, they often permit an unexpectedly close and accurate description of the phenomena in these connections.第二の点は、予想外の文脈に現れるということと、そしてまた、数学がこれほど役立つ理由を私たちが理解していないことのせいで、〈数学の概念を駆使して、なにか一つの理論が定式化できたとしても、それが唯一の適切な理論なのかどうかがわからない〉ということ。
Secondly, just because of this circumstance, and because we do not understand the reasons of their usefulness, we cannot know whether a theory formulated in terms of mathematical concepts is uniquely appropriate.〔この二つの論点をさらに言い直すと〕第一の点は〈数学は自然科学のなかで、ほとんど神秘的なまでに、途方もなく役立っているのに、そのことには何の合理的説明もない〉ということ。
The first point is that the enormous usefulness of mathematics in the natural sciences is something bordering on the mysterious and that there is no rational explanation for it.第二の点は〈数学の概念の、まさにこの奇怪な有用性のせいで、物理学の理論の一意性が疑わしく思えてしまう〉ということ。
Second, it is just this uncanny usefulness of mathematical concepts that raises the question of the uniqueness of our physical theories.
実際、王政復古期(1814年〜1848年)には、思いっ切り当時の政治的状況に忖度した「現在こそが最善の可能世界(le meilleur des mondes possibles)」としたヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年〜1831年)の哲学が最終勝利を収めます。
そうした状況が本格的に引っ繰り返されるのは1850年代も末頃になってから。
大恐慌を背景に1850年代末には欧州近代思想の大源流が一気に出揃った。
①「文明が発展するためには個性と多様性、そして天才が保障されなければならないが、他人に実害を与える場合には国家権力が諸個人の自由を妨げる権利が生じる」としたジョン・スチュアート・ミル「自由論(On Liberty、1859年)」の古典的自由主義。
②「我々が自由意思や個性と信じ込んでいるものは、実際には社会の同調圧力に型抜きされた既製品に過ぎない(本物の自由意思や個性が獲得したければ認識範囲内の全てに抗え)」とする「上部構造理論の提唱者」カール・マルクス「経済学批判(Kritik der Politischen Ökonomie、1859年)」の社会自由主義。
③「進化は系統的に展開する」としたチャールズ・ダーウィン「種の起源(On the Origin of Species、初版1859年)」の科学主義(Sientism)的アプローチ。
科学主義(Sientism)の台頭
実は19世紀前半に猛威を振るった「俗流唯物論(vulgar materialism、今後は自然科学的な知のみを体系化すべきであり、それによって哲学は不要になるとする立場)」に対し、ウェーバーやフェヒナーらの精神物理学、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツらの感覚生理学といった研究の積み重ねが「(人間が認識可能な情報の集大成としての)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に「原則として」人類に不可知な形で拡がる)物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の世界」を峻別するイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)の超越論をリヴァイヴァルさせ「自然科学のようないわゆる経験科学の発展によって物自体が認識可能となる」とする独断論の克服に役立てられていく流れでもあった。
そしてここに、アンリ=ルイ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson 1859年〜1941年)の「生命の跳躍(elan vital)」論が登場してくる訳です。
感覚は純粋に質的なものであり、それを量的に扱うことはできない。
フェヒナーの精神物理学では、感覚の差異は「最小の差異」(minima)として表され、差異の質は捨象される。これによって差異の同一性が確保され、それにもとづいて、感覚Sが、その感覚に到達するまでに通過した最小差異ΔSの総和として規定される。
- しかしここには問題がある。つまり「S=ΔSの総和」は成立しないのだ。
- 精神物理学はΔSを実在するものの量とみなしている。しかしそもそもそれは実在しない。なぜなら、前提として、実在するもの同士の間にはそれらを分割する間隔が存在するが、感覚Sと新たな感覚S'の間には、そうした間隔は存在しないからだ。
- 精神物理学は、量や刺激を測るように質や感覚を計測しようとする。ΔSを導入するにいたったのも、まさにそうした見方のゆえだ。しかしここにはひとつの錯覚、つまり、ある感覚が別の感覚の原因として働くという錯覚がある。
- 物理学というものは私たちの内的状態の外的原因を計算にかけることをまさにその役割とするもので、これらの内的状態そのものにできるかぎり関わるまいとする。絶えず、かつ断固として、物理学はそれらをそれらの原因と混同する。だから、物理学はこの点に関しては常識の錯覚を奨励し、誇張しさえするのだ。こうした質と量、感覚と刺激との混同に慣れ切ってしまい、いつかは科学が後者を計測する通りに前者を計測しようとするようになる時が来るのは避けがたい運命だったが、そうしたことこそ精神物理学の目標だったのである。
この点に関してはベルクソンはいいポイントを突いている。私たちの感覚が刺激の積み重ねによって成立しているわけではないことは、普段の経験を内省すれば簡単に見て取れる。特にこのことは人間的な感情(快不快)について当てはまる。フランス料理も毎日食べれば飽きるだろうし、美人も100回見れば凡人と映るだろう。逆に一目ぼれの場合もある。快不快が質的なものであり、刺激量の多さに比例するわけではないことを教えてくれる。
*逆を言えばベルグソンはここで「計数的に扱える感覚以外を考察の対象とする」と宣言している。
そして私たちの意識もまた質的なものである。
次にベルクソンは、感覚だけでなく私たちの意識も質的なものだと主張する。
- 意識は感覚と異なり、純粋持続として存在している。
- しかし反省的に捉えられるとき、意識は記号によって等質的に表現され、真の持続=真の意識からは程遠くなってしまっている。真の意識は、記号に定着させるような思考ではなく、「自己自身に立ち返って精神集中するような思考」において初めて捉えられるのだ。
ベルクソンによれば、私たちが純粋持続を分断し記号に固着させようとするのには理由がある。それは、日常の私たちの生がそうすることを好むからだ。
ベルクソンによれば、持続のうちで私たちはそもそも自由だ。自由についての問題が現れてくるのは、持続を記号化するからにすぎない。したがって記号化を止め、相互に浸透しあう意識状態に同化すればよい。そうすれば私たちは自由になる。そうベルクソンは言う。
しかしベルクソンによれば、私たちが自由な行為を行うことはとても難しい。普段私たちは日常性のうちに没入しており、そこから脱却することは難しいからだ。
*ここでいう「記号化」はおそらく「ルーティンワークの自動化による意識からの抹消」と言い換えられる。
悟りと決意の哲学
ヘーゲルは『法の哲学』で次のように論じていた。
- 私たちが欲求を満たして自由を実現するためには「所有」が必要であり、所有は、他者がそれを私のものとして承認してくれることを条件とする。その意味で、所有が帰属する人格を相互に承認しあうことが、自由の本質的な条件である。
ここから取り出せるポイントは、少なくとも2つある。
- 自由は、欲求との関係で立ち現れる
- 自由は、他者からの承認を必要とする
詳しく言うと以下の通りだ。
- 私たちは、無意識にもしくは強制的にする(させられる)行為について自由を感じることはなく、したい行為を行うときに自由を感じる。たとえば、オリから脱出したときに自由を感じるのは、腱や筋肉が物理的に動くようになったからではなく、そこから脱出したいという欲求があったからだ。もしそうした欲求がなければ自由は感じない。仮にオリの外にライオンがいるとして、オリから無理矢理出されたとしたら、確かに物理的には動くようになるが、それは強制だと感じるはずだ。この意味で、自由は私の欲求に相関して確信されるものだといえる。
- 行為によって欲求を満たすとき私は自由を感じる。欲求を満たすためには、その欲求が向かう対象が必要となる。私はその対象を手に入れる。しかしただ持っているだけでは誰かに奪われかねない。その対象が稀少であればなおさらだ。このことは各人に対して当てはまる。そこで、各人が自由を享受できるようになるためには、各人が互いに所有をなす人格であることを承認しあわなければならず(人格の相互承認)、一切の社会制度は、この原理に基づいて打ち立てられなければならない。
これと比較すると、ベルクソンは、自由を個人の意識における事象としてのみ捉え、私たちの関係性のうちに位置づけていない。
- 世俗にまみれた自我は“頽落”していて、真の自我に目覚めていない。そこから脱却するためには心の内奥を直視して、ただひたすら純粋持続を見て取ることが必要だ。そうすれば真の自由まではあと一歩、持続のうちから行為すればいい。そのとき真のあり方に目覚めた自我はすでに自由を体現してしまっているのだ。
ベルクソンは、後の著作である『創造的進化』にて、第一の活動性である「生命のはずみ」(エラン・ヴィタル)が、生命の進化全体のプロセスを本質的な仕方で規定しており、自由は新たな形態を創造するような進化のうちで発現するのだ、というように論じている。ヘーゲルのように自由を人間的欲望との相関性のうちで現れる“感度”として捉えるのではなく、獲得されるべき生の本来的なあり方として位置づける点に、ベルクソンのいう自由のポイントがある。
全体像を俯瞰してみると以下に連なる系譜の思考様式と言えそうです。
- 直交座標系(Rectangular coordinate system/Orthogonal coordinate system)によって幾何学と代数を統合した機械的宇宙論(Mechanistic Universe)を展開しつつ、心身二元論(ただしここでいう「魂」は脳の最奥部に位置する松果腺や動物精気、血液などを介して身体と相互作用を行う物理的実体に過ぎないかもしれない)を説いたルネ・デカルト(René Descartes、1596〜1650年)。後世には機械的宇宙論(Mechanistic Universe)の部分だけが継承された。
- 「(人間が認識可能な情報の集大成としての)物(独Ding、英Thing)の世界」と「(その外側に「原則として」人類に不可知な形で拡がる)物自体(独Ding an sich、英thing-in-itself)の世界」を峻別する超越論を展開しながら、(非数学的な)先験=アプリオリ(a priori)能力にその抜け穴を求めたイマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年〜1804年)。ちなみに米国のプラグマティズム(pragmatism)は「神はこの世界を人力だけでは手に負えない(すなわち改めて創造主の再登場とデバッグを必要とする様な)欠陥品としては設計されてない」なる宗教的信念の導入によって物自体への言及を回避。これはピエール=シモン・ラプラス(Pierre-Simon Laplace, 1749年〜1827年)も用いたレトリックであった。
- 数学者コンドルセ(Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet, 1743年〜1794年)の学問体系論を継承しつつ「全てを統括するのは数理でなく実証主義哲学(Philosophie Positive)を習得した科学者でなければならない」としたオーギュスト・コント(Isidore Auguste Marie François Xavier Comte、1798年〜1857年)。結局、後継者が現れず事実上途絶。
このサイトはあくまで人類が生得的に備える数学的把握能力の大源流をカンブリア爆発時代(Cambrian Explosion、5億4200万年前〜5億3000万年前)に全身を統括する中枢神経を備えないが故に動作が鈍重な放射相称動物(Radiata、ウニやクラゲやイソギンチャクの類)から明瞭な形で分化して「視覚とそれを処理する脊髄」を急速に進化させ始めた左右相称動物(Bilateria、カニやエビの様な節足動物の先祖筋)の中から生物史上初の「百獣の王(食物連鎖の頂点)」アノマロカリス(Anomalocaris、約5億2,500万- 約5億0,500万年)が突如現れ、やがて一切の末裔を残す事なく滅んでいった先例に求める立場なので、彼らが執拗に追い求めた「人類の非数学的先験性」なる概念はどうしても視野外となってしまいます。
一方、ベルクソンの述べた様な意識の進化過程論は以下の様な形で完成に向かったと考えます。そう解釈すると(引用文で指摘されている様な)ヘーゲルの自由論との相違点も自然解消するからです。
Q:「Turn on Tune in Drop out」とはどういう意味ですか?
A:ティモシー・リアリー博士当人はこう説明しています。
- "'Turn on' meant go within to activate your neural and genetic equipment. Become sensitive to the many and various levels of consciousness and the specific triggers that engage them. Drugs were one way to accomplish this end.
「Turn on」というスローガンで主張したいのは(「RAVEせよ(自分に嘘をついてでも盛り上げよ)」という話ではなく)「(自らを包囲する外界に対するさならるJust Fitな適応を意識して)自らの神経を研ぎ澄まし、生来の素質を磨け」という事である。あらゆる状況に自らを曝せ。そして自分の意識がどう動くか細部まで徹底して観察し抜け。何が自分をそうさせるのか掌握せよ。ドラッグの試用はその手段の一つに過ぎない。
*「ドラッグの試用はその手段の一つに過ぎない」…実際、当人も後に「コンピューターによる自らの脳の再プログラミング」の方が有効という結論に至っている。その意味では「汚れた街やサイバースペース(cyber space)への没入(Jack In)」も「デスゲーム(Death Game)に巻き込まれる事」も「異世界に転生する事」も手段としては完全に等価。- 'Tune in' meant interact harmoniously with the world around you - externalize, materialize, express your new internal perspectives. Drop out suggested an elective, selective, graceful process of detachment from involuntary or unconscious commitments.
「Tune in」というスローガンで主張したいのは(「内面世界(Inner Space)の完成を目指せ」という話ではなく)「新たに掴んだ自らの内面性を表現(Expression)せよ」という事である。自己感情を外在化し、具体化し、それでもなお自らを包囲し拘束する現実と「調和」せよ。
*「Tune in」は「Turn in」とほぼ同義。ここで興味深いのはどちらにも「警察に届ける(問題解決を公権力あるいは専門家に委ね、後はその指示に従順に従う事)」というニュアンスが存在するという点。そして直感的には「in」の対語は「out」となるが「Turn out」とは「自らを包囲し拘束する現実」を「全面否定して引っ繰り返す」あるいは「諦念を伴って全面受容する」事。「Tune out」とは「黙殺を決め込む」事。だがあえてティモシー・リアリー博士はこうした選択オプションを嫌い「自らを包囲し拘束する現実」を突き抜けた向こうに「外側(Outside)」は存在しない(あるいはどれだけ無謀な進撃を続けても「現実」はどこまでも付いてくる)とする。無論(自らも専門家の一人でありながら)「問題解決を公権力あるいは専門家に委ね、後はその指示に従順に従う」という選択オプションも許容しない。マルコムX流に言うなら「「誰も人に自由、平等、正義を分け与える事は出来ない。それは自ら掴み取る形でしか得られないものなのだ(Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it. )」、日本流に言うなら「誰にも人は救えない。それぞれが勝手に助かるだけだ」といった感じ?- 'Drop Out' meant self-reliance, a discovery of one's singularity, a commitment to mobility, choice, and change.
「Drop Out」というスローガンで主張したいのは「(本当の自分自身であり続けるために)現実社会から離脱せよ」という話ではなく「自立せよ」という事である。再発見された自らの個性に従った動性、選択、変化に専心せよ。
*「Drop Out」は「Get off」とほぼ同義。ここで言いたいのはおそらく「解脱(Turn out)せよ」という事で、まさに「縁(自らを包囲し拘束する現実)からの解放」を主題とした原始仏教における「解脱」の原義はティモシー・リアリー博士の説明とぴったり重なる。ちなみに「Drop in」は「突然ぶらりと立ち寄る事」で、「オトラント城奇譚」作者として知られるホレス・ウォルポールが1754年に生み出した造語「セレンディピティ(serendipity、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること)との関連が認められる。「Get on」は「大き力に便乗する事(そしてそれによって成功を収める事)」。Unhappily my explanations of this sequence of personal development were often misinterpreted to mean 'Get stoned and abandon all constructive activity.'"
残念ながら、こうした私の自己発達に関する言及は「ドラッグでラリって建設的なすべての行動から遠ざかる」というように誤解されている。
すると後には何が残されたでしょうか?
- 要するにベルクソンは、左右相称動物の時代から継承されてきた「視覚とそれを処理する脊髄が処理する世界と時間の認識手段」の背後にこれと直結した「ルーティンワーク化され、それぞれの単位にカプセル化され、普段は思い返す事さえされない日常」を見て取り、むしろティモシー・リアリー博士(Timothy Francis Leary, 1920年〜1996年)いうところの「状況対応の為の再プログラミングを担う割り込みタスク」こそが真の意識であると考え様としたのではあるまいか。発想的にはシステムとしての個体や社会を「脱皮が成長に間に合わなくなったら死ぬ外骨格生物」に見立てたマックス・ウェーバーの「鉄の檻(Gehäuse)」理論に近い。
- ところでコンピューターを情報処理手段として獲得して以降の人類は、これまで触れてきた自由論を総括する形でこう述べる事も出来る。「神は定命を文学や映画の様にただ単にシーケンシャルに再生される物語としてではなく、多くのフラグ分岐を含むアドベンチャー・ゲームの様な形で書き下ろされたのかもしれない」と。さらにフィクションの世界では自動的にネットワークに接続してリサーチし、最新の流行に従ってシナリオをアップデートし続けるシステムまで想定されている。ここまでくるとベルグソンが日常的ルーティンワークの外側で機能すると想定した「生命の飛躍」は自然とさらなる外側、すなわち「人類に認識可能な範囲外を跋扈する絶対他者」により近い領域へと押し出されてしまう。
これでやっと冒頭の記述に戻った訳ですが、実はこれには以下の様な続きが…
「こんな「リベラル」が日本にいてくれたらいいのに」大賀祐樹
— SYNODOS / シノドス (@synodos) September 3, 2019
現代の日本に影響力を備えたリベラルは存在していない。日本の歴史、文化、文脈を踏まえた、まったく新しいリベラルを創造しなければならない。https://t.co/IsnHtWX0nR
本文は買わないと読めないので論評できないが、「日本の歴史や文化を踏まえたリベラル」というと、具体的にどういうイメージだろうか。中江兆民とか田中正造みたいなのだろうか。あるいは尾崎行雄か。それとも時代をうんと遡って道元とか親鸞みたいなのを意識するのか。 https://t.co/aUQbinggkM
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
西尾幹二氏が『国民の歴史』を書けたのは、日本史の研究者ではないからだろうし、小堀桂一郞先生が皇室弥栄を唱えるのも、やはり本職が日本史の研究者ではないからこそだろう。
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
→ついでにいうと西部邁先生がチェスタトンを学生に勧めたのも、英国思想や文学が専門ではなかったからだろう。その当時、西部先生は「"保守"になるには、何をすれば良いのか」を考え悩んでいる、保守事始めの段階だったのである。
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
西尾幹二(1935年〜) - Wikipedia
小堀桂一郎(1933年〜) - Wikipedia
西部邁(1939年〜2018年) - Wikipedia
古典的教養を踏まえた保守派インテリとして例に挙がるのは、だいたいが田中美知太郎とか福田恒存とか、一世代前どころか数十年以上前の世代の人である。今も活動中なのは小堀桂一郎先生とか西尾幹二氏等、ごく少数で、もはやほとんど存在しないが、こうなった理由は色々考えつく。一つは人文社会の→
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
→学問分野そのものが時代に応じて大きく変貌し細分化していることがあるだろう。「古典」「伝統」などの概念が動かしがたい重みを持っていた時代ははるか遠くに過ぎ去っている。今活動している小堀桂一郎先生は、日本史や日本文化が専門ではない。これらを専攻していたなら、多分違った感じの論者に→
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
→なったのではないか。そして、現在「保守」「右派」と俗に呼ばれているような、もっと下の現役世代の論者たちは、大体が人文社会の学問研究の積み重ねには無知・無関心なのである。
— Shin Hori (@ShinHori1) September 5, 2019
田中美知太郎(1902年〜1985年) - Wikipedia
みんなそう言うけれど、一番は思想にダンディズムを求めなくなったからじゃないですかね。福田恆存がなぜ未だに読まれるか、それは素朴にダンディで格好いいからです。これは受け手以上にこれまでの歴史の中に自分を位置付けようとするとそう考えざるを得なくなる。 https://t.co/udoknSlfdq
— ミスター (@hahaha8201) September 5, 2019
花田清輝が喝破していたことですが、保守反動が思想として保守反動かといえば全くそうではない。福田恆存のような批評家は端的に自分をダンディに位置付けようとした時に保守として名乗りを上げたわけです。小林秀雄もそう。そしてこれは彼らの通俗に対する拒否反応と密接に関わっている。
— ミスター (@hahaha8201) September 5, 2019
1958年(昭和33年)には、小林当人が悪影響を懸念して死後公開を禁じ、第五次全集で故人の遺志を裏切る形で公開された未完のベルクソン論『感想』の連載を開始している。
この連載の契機となったのは何よりこの時期の小林のギリシャ哲学への傾斜であろうが、当時内外論壇を賑わしたコリン・ウィルソン『アウトサイダー』の神秘主義的進化論の影響も考えられる。この時期、小林の盟友河上徹太郎は『日本のアウトサイダー』という評論を著し、これを小林は出版事情については言葉を濁しながら『考えるヒント』で紹介している。
『感想』で考察されたベルクソン哲学の時代背景
1859年にダーウィンが『種の起源』を公表した当時、イギリス(大英帝国)ではダーウィンに先んじジャーナリストのロバート・チェンバースが匿名で出版した、万物進化論を主張する『創造の自然史の痕跡』が話題となっていた。これについてダーウィンは「下等」、「高等」という概念を人間の主観的価値観の産物であって科学的な概念とは言えないとして、その科学的価値には否定的な評価を下している。一方で、その影響が自らの学説の普及するために一役買ったことについては一定の評価を下している。このような、「下等」な生物が「高等」な生物に変化するという形式の「進化論」は、ダーウィンの指摘するとおり近代科学の水準に至っていない疑似科学であるが故に、ダーウィン以前から存在していたが充分な影響力を持つには至らなかった。ダーウィン自身、当初は自らの自然選択説を疑似科学の代名詞たる「進化論」の範疇に入れることを拒否していた。疑似科学としての「進化論」の本質はその説が生命の謎、或いはその究極的な目的を説明することであり、これは本質的に科学的な証明の不可能な形而上学である。一方、ダーウィンの学説はそれが近代科学の枠組みにある限り「生命とは何か」という哲学的な問いには無関心であり「種の起源」という名の通りに生命の多様な「種」がいかにして発生したかについての理論であり「生命はいかにして誕生したか」という問いには無力である。それが社会のダーウィン学説に対するイメージからいかに隔たっていようとも、これは動かしがたい真理である。
ダーウィンの有力な協力者であり、現代では疑似科学的な進化論者の見本と見られているトマス・ヘンリー・ハクスリーは、自然選択説を教えられた当時の感想を「何でこんな簡単なことに気づかなかったんだ」というものだったと言っている。これは、ハクスリーの思索態度が哲学的であって、科学的でなかったことによるものであろう。「ラマルク主義」で有名な、19世紀初頭のジャン=バティスト・ラマルクによる『動物哲学』以来、近代科学の水準を満たさない進化論学説のバリエーションは豊富であり、それぞれの理論の特徴についての議論はあるが、その内にはダーウィンの祖父エラズマスや、ハクスリーと共にダーウィンの有力な協力者であったハーバート・スペンサー、また小林が論じたフランスの哲学者ベルクソンも入れられるであろう。ベルクソンは著作中、スペンサーへの敬意を隠していない。
伝統的キリスト教会の神学では、世界は神が七日で創り、人間の祖先は塵から創られたアダムと、アダムの肋骨から創られたエバであるとして来た。このような世界観を無批判に受け入れる限り、人間の存在する意味を我々が改めて問う必要はない。一方、ダーウィンの学説が主張するのは「人間の先祖がサルである」という事実だけであり、しかもこの事実だけで伝統的なキリスト教神学の権威を無効化するには充分である。しかしダーウィンの学説は神学ではなく、仮にキリスト教の神学を抛棄するならば、人間の存在する意味を改めて規定する新しい神学が必要になる。それが、疑似科学的進化論の意義であったと言える。ダーウィン学説についての科学的厳格さを伴った論争では、ハクスリーやスペンサーのような疑似科学的進化論からのダーウィン学説の擁護者は間もなく排除されることになった。しかし、教会の権威に代わる新たな神学を必要とする世俗社会では、ハクスリーやスペンサーの権威が不要になることはなかった。かくて現代に至るまで、科学としてのダーウィン学説と疑似科学としての進化論の、社会における混同は多かれ少なかれ続いており、小林もまたこの混同から完全に逃れきっているとは言えない。
19世紀半ば以後、ダーウィン学説と共に西欧を中心とした自由主義的な世俗社会は、原罪論も最後の審判もない楽観主義の哲学を受け入れた。この楽観主義はしかし、20世紀初頭の第一次世界大戦の惨禍によって打ち砕かれた。第一次世界大戦後の西欧社会の知的潮流は、この言わば新しい神学の崩壊、乃至は解体から始まる。西洋哲学史におけるこの時代のランドマークとなる、ドイツの哲学者ハイデッガーの『存在と時間』、オーストリア出身の哲学者ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』は、いずれも楽観主義の哲学における形而上学の解体を主眼として展開されている。また、大戦以前から進化論哲学を主導して来たベルクソンのような哲学者自身、自ら路線変更を強いられた時代でもあった。
ベルクソンの四冊の主著で、最後に発表された『道徳と宗教の二つの源泉』(1932年)を除いた他の三著は、第一次世界大戦(1914-18)以前の1889年から1907年にかけ公刊された。最終の「二源泉」刊行までの間が開いているのは、戦後のベルクソンが賢人会議に参加するなど、思索よりも大戦後の平和活動に熱心だったせいである。また三著がそれぞれ意識現象、生理現象、生物現象を扱った進化論哲学であるのに対し、最終の「二源泉」は、どちらかと言えば社会学的考察である。進化論哲学者としてのベルクソン哲学の要となる部分は、小林が文筆活動を始めた第一次世界大戦前に刊行されていたのである。
『感想』で考察されたベルクソン哲学の特徴
ダーウィン学説の普及と共に盛んになった進化論哲学は、科学の発展を大前提とするが故に人間の理性を絶対視する「自然の光」、或いは主知主義の哲学であり、ベルクソンの哲学も例外ではない。ベルクソンをアリストテレスに象徴されるような伝統的な理性の哲学と区別するのは、その直観主義であると言われる。しかしベルクソンは、第一次世界大戦前の1903年に発表した『形而上学入門』で「知的直観」“intuition intellectuelle”と書いた箇所を、大戦後 ―― つまり思想背景としての進化論を抛棄した後と思われる時期に発表した論文集に転載するにあたり「心的直観」“intuition spirituelle”と書き直している。この戦前のベルクソンの直観主義は、我々日本人が禅仏教で歴史的に親しんでいるような宗教的直観主義とは異なるベルクソン哲学の特徴的なものであろう。
またこの知的直観主義と対をなしてベルクソン思想を特徴付けるものにイマージュ論がある。ベルクソンにとって、「イマージュ」とは単なる心的表象とは異なる、一種の観念実在論である。このベルクソンのイマージュ論の影響は、小林においてはそのドストエフスキー伝の序文をなす「歴史について」で見られるような、(ややグロテスクな)実在論的な歴史哲学となる。ベルクソンのイマージュ論は、彼が一時期会長を務めた英国心霊現象研究協会が研究対象にしたエクトプラズムを連想させるものがある。また、ベルクソンの宗教観もこれに倣ったものであり、後年、英国国教会が心霊主義を内偵して秘密提出し、暴露されたと言われる報告書における心霊主義の宗教観についての批判は、ベルクソンの宗教思想を非常に連想させる。
- 「英国国教会“スピリチュアリズム調査委員会”多数意見報告書」
愛の崇高さについても、新約聖書の「神は愛なり」という主張に匹敵するものが見られることは事実だが、キリストの持つ贖罪性についての叙述などは、人間の罪の重荷を背負ってくれるという根本的な(キリスト者の)受容の信仰ならびに十字架上での勝利ではなく、どうやら(復活における)物質化現象という奇跡を生じさせるある種のエネルギーのことであるらしく、キリスト教的福音の教えには遠く及ばないことがしばしばである。ベルクソンは、いずれ科学の発展が死後生の謎をも解き明かすことを期待する。これは現代ではいささか牧歌的に過ぎる態度と言わざるを得ないが、ともかくも小林の『感想』冒頭における小林自身の超自然的体験談は、このようなベルクソンの俗流神秘主義の影響を受けていると言えるであろう。小林のこのような形での超心理学的問題についての関心は、最晩年の未完となった『正宗白鳥の作について』(1981年(昭和56年)-1983年(昭和58年))までに至る。ここで小林は、論旨が脱線しユング論が展開され、「心の現実に常にまつわる説明しがたい要素は謎や神秘のままにとどめ置くのが賢明・・・」という引用文で、我に返ったように絶筆となった。
戦前のカントを論じた小林の初期文章では、カントの人倫重視の形而上学を「窮余の一策」と評したものがある。この小林の形而上学観はベルクソンを論じるにあたって自らの姿勢を暗に表明しているものと思われる。しかし、概してベルクソンの進化論哲学の体系は、小林がそれと信じた(信じたがった)程には精神的でも芸術的でもなく、小林の文筆活動において我々が論じる価値のあると見る分野に比較してあまりに素朴であり、楽天的に過ぎるのであって、そこから小林が期待するものを汲み上げるのは困難であったと言えるであろう。ベルクソンは生命活動を砲弾の飛び交う戦争のようなイマージュによって提示する。事実、歴史はそのようになったのであって、戦後のベルクソンの平和活動にも関わらず、生物学的民族主義と進化論哲学を奉じるナチス・ドイツがユダヤ人哲学者ベルクソンの住むパリを占拠することになったのである。ベルクソンは遺稿の公開を禁じてナチス占領下のパリでひっそりと最期を迎え、ベルクソンの膨大な遺稿を期待しながら戦後を迎えた小林はそれを知り「恥ずかしかった」と告白している。
1963年(昭和38年)に、小林はソ連作家同盟の招きで訪ソしたのを期に、5年の歳月をかけたベルクソン論を中断した。後に小林は数学者岡潔との対談で、中断の理由として「無学を乗り越えられなかった」と述べている。
小林が封印したベルクソン論『感想』は本人の意志とは無関係に、生誕百年を記念した小林秀雄全集(第五次)・別巻として公刊された。
そう、アンリ=ルイ・ベルクソン(Henri-Louis Bergson 1859年〜1941年)の「生命の跳躍(elan vital)」論には、ソレル「暴力論(Réflexions sur la violence、1908年初版)」を介してファシズムやナチズムのイデオロギー形成に役立ったという暗黒面も存在したのですね。要するに彼の「他者との関係性の一切を視野外に置いた内省的進化論」は「究極の自由は専制の徹底によってのみ達成される」ジレンマの究極形態ともいえる最終戦争論と極めて相性が良かったのです。
西部邁がきわめて特殊だったのは高度消費社会の情報環境の中では、大衆社会を侮蔑し精神の高貴さを擁護する知識人を「演じている」自分がドン・キホーテ的な道化に過ぎないというサンチョ・パンサの目を持っていたことです。いわばそれまでの態度としての保守がダンディズムを成立させるために
— ミスター (@hahaha8201) September 5, 2019
拒否してきた保守反動にとっては拒否するべき対象である「通俗」の渦中に身を置いていた。通俗的な場では西部邁のような知識人も消費させるキャラクターに過ぎず、彼のニヒリズムはある意味で徹底的に伝わない。であるが故に西部邁のドン・キホーテ的なダンディズムは成立していたのです。
— ミスター (@hahaha8201) September 5, 2019
「誰も思想に通俗性を否定するダンディズムを求めなくなった」というのはそうでしょう。その一方で「保守反動=反通俗」なる認識、そもそも英国や日本の様に保守政党が「地主の利権団体」の枠組みを超えて大衆を味方に付け、与党として成功した国で果たしてそのまま通用するのかとも思います。